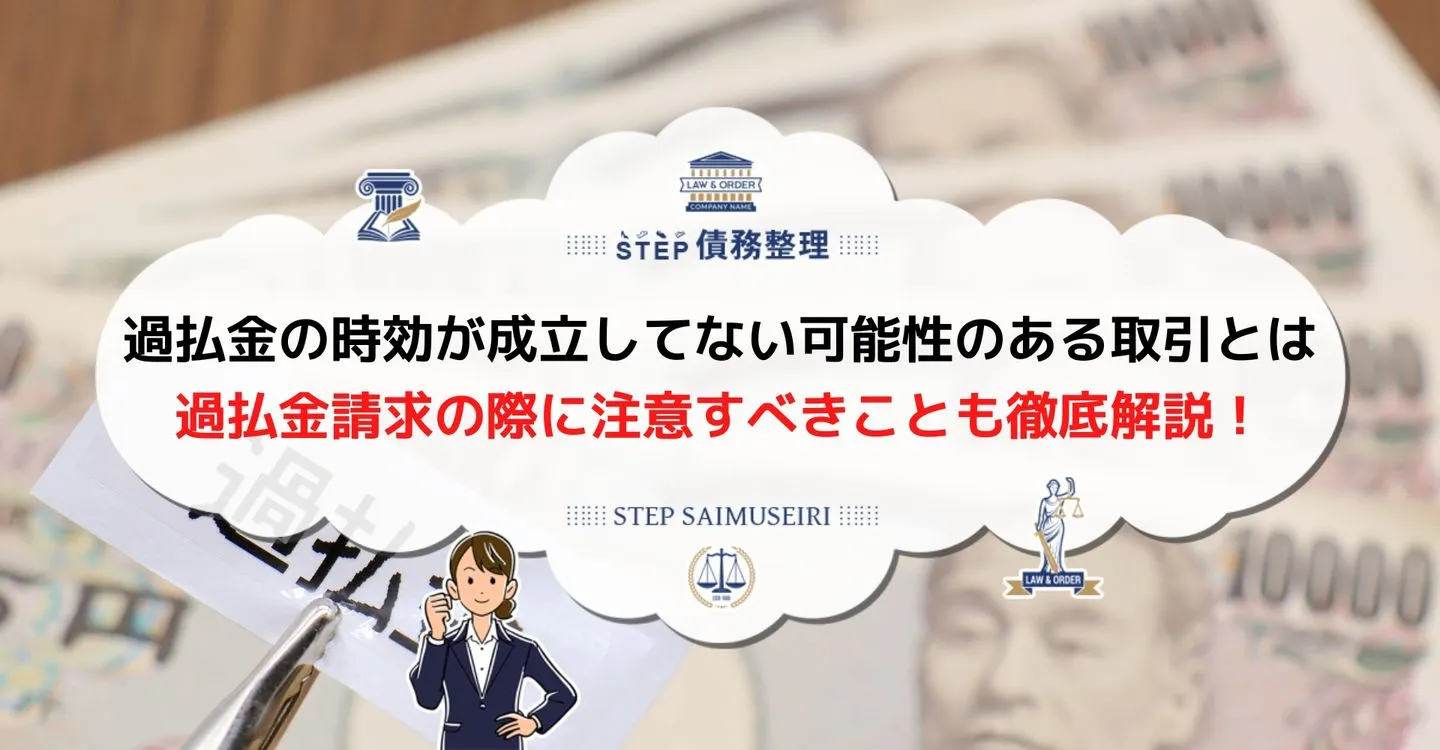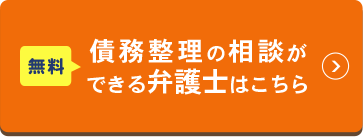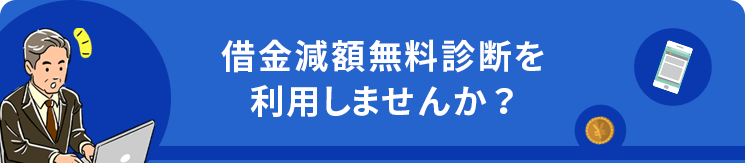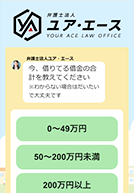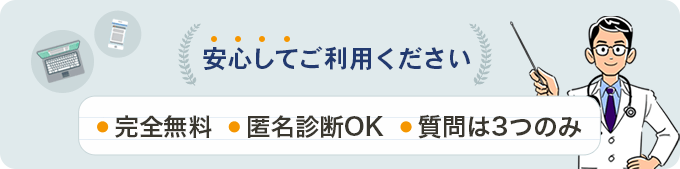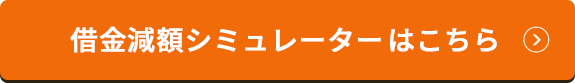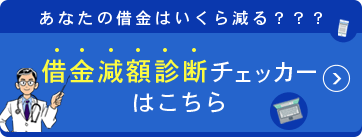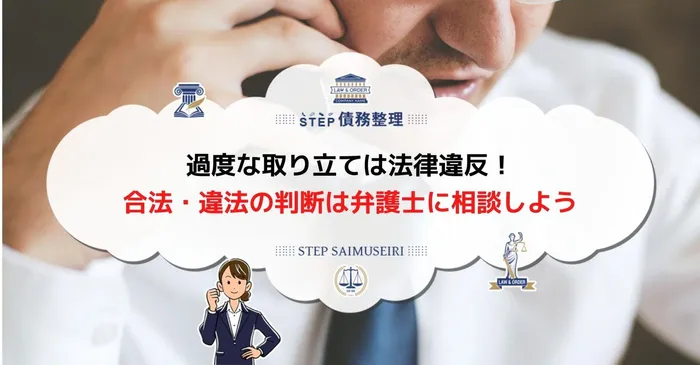以前取引をしていた貸金業者に、過払金が発生しているかもしれません。でも、もうずいぶん前のことだから、時効になってしまったでしょうか?


過払金の時効は、2020年4月以前に完済しているなら、完済日から10年です。多くの貸金業者が2007年ごろに利息を下げたので、2007年以前に取引を開始し、完済からまだ10年経過していなければ、過払金が発生している可能性が高いでしょう。
過払金が発生しているとしても、時効が迫っていそうですね。すぐに請求するにはどうしたらいいでしょうか?


貸金業者に過払金を請求するためには、まずは相手から当時の取引履歴を全て取り寄せる必要があります。
ただし、時効が迫っていると、引き延ばしにあう可能性もあるでしょう。スムーズに返還請求をするためには、取引履歴の開示時点から、弁護士に依頼することを検討しましょう。
過払金請求権は、過去に違法な高金利で取引をおこなっていた貸金業者から、払いすぎた利息を取り戻す権利です。
しかし、利息制限法が改正されたのは2010年。2023年の現在では、過払金請求権の多くは時効消滅が迫っているでしょう。
過払金の時効は、基本的には最終取引日(完済)から10年です。しかし、完済から10年経過していても場合によっては取り戻せる可能性もあります。
この記事では、過払金の時効について具体的な日にちを挙げて解説しますので、自分の過払金が時効消滅していないかを確認することができます。
時効が迫った過払金を取り戻すには、時効を成立させようとする貸金業者と交渉するためにも、弁護士に依頼することをおすすめします。
この記事で自分も過払い金が発生しているかもしれないと思ったら、一度相談だけでもしてみることをおすすめします。
- 過払金の時効は最終取引日から10年
- 2020年の民法改正により、過払金発生を知ってから5年経過でも時効消滅することになった
- 過払金が発生している可能性がある取引は、2007年より以前からの取引で、完済から10年が経過していないもの
- 時効が迫っている場合はまず内容証明郵便で過払金を請求して時効の進行を止め、その後半年以内に裁判手続きで請求する
- 過払金を請求する際は取引履歴開示から弁護士に依頼することをおすすめ
過払金の時効が成立する条件の主な2つ
利息制限法の上限を超える金利での取引がある場合、払いすぎた利息を過払い金として返還できます。しかし、過払金請求権には時効があり、それを過ぎると請求権が消滅してしまいます。
以下で、過払金請求権の時効が成立する2つの条件について解説します。
最終取引から基本10年で時効成立
過払金請求権は、最終取引日から10年経過すると、時効によって消滅します。
過払金の請求権は、法律上は「不当利得返還請求権」に該当します。これは、相手が不当な理由で取得した利益を返還するよう請求する権利です。
不当利得返還請求権の時効は、民法166条1項により以下のように定められています。
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。引用元:民法第166条1項
条文上の「権利を行使することができる時」とは、最終取引日です。
つまり、最終取引日から10年間不当利得返還請求権を行使して過払金返還請求をしなければ、過払金を知らなったとしても、時効によって権利が消滅してしまうということです。
10年経たなくても過払金と知ってから5年で時効成立
2020年の民法改正により、10年経過しなくても、過払金があると知ってから5年経過することで時効成立することが定められました。
法改正は2020年4月1日に施行されたため、その日の前後で時効の扱いが違うことに注意が必要です。
改正民法の附則10条1項、4項によると、施行前(2020年3月31日以前)に「債権が生じた場合」と「その発生原因である法律行為がされた場合」は、旧民法が適用されると規定されています。
つまり、2020年3月31日以前に完済した借金については、この条件は当てはまらず「最後の取引から10年後」という条件のみです。
- 2020年3月31日以前:最終取引日から10年で時効
- 2020年4月1日以降:最終取引日から10年or10年以内でも知ってから5年で時効
過払金の発生が疑われる取引
過払金が発生するのは、利息制限法の法改正がおこなわれる以前から続いていた取引です。
特に2007年以前から貸金業者と20%以上の利率で取引を続けており、完済から10年経過していない取引は過払金が発生している可能性が高いといえるでしょう。
2010年に法律が改正される以前から、既に各貸金業者は上限利率を徐々に下げていました。
- ~2006年まで
利息を取り締まる2つの法律があった。
利息制限法の上限利率15%~20%、出資法上の上限利率29.2%
多くの貸金業者で、刑事罰が設けられている出資法上の上限利率29.2%を基準に取引
20%以上29.2%未満の金利は、「グレーゾーン金利」と呼ばれた - 2006年1月13日:最高裁判所でグレーゾーン金利を違法とし、返還義務を認める判決
- 2006年~2010年:各金融機関で利率の上限変更
- 2010年6月18日:改正利息制限法完全施行
各消費者金融の上限金利変更時期は、以下のとおりです。
- アコム:2007年6月18日
- アイフル:2007年8月1日
- プロミス:2007年12月19日
- レイク:2007年12月2日
なお、プロミスは現在SMBCコンシューマーファイナンス株式会社、レイクはレイクALSAと名称が変わっています。
つまり、だいたい2007年より前に開始した取引で、完済後10年経過していなければ過払い金が発生している可能性があります。
過払金の時効が実は成立していない可能性のある取引
既に完済から10年経過していても、実は時効が成立していない可能性がある取引もあります。
以下のようなケースは、10年経過していても例外的に時効が成立していないかもしれません。
同じ貸金業者から再度借り入れをしていた場合
同じ貸金業者から何度も借り入れを繰り返していた場合には、時効が成立していない可能性があります。
たとえば、以下のように①と②の取引があった場合について説明します。
- 2006年にA社から借り入れをおこない、5年後の2011年に完済
- その後同じ年にA社から再度借り入れをおこない、さらに5年後の2016年に完済
この場合、通常であれば①の取引は2011年から10年後の2021年に時効消滅してしまいます。そして、②は利息制限法改正後、2011年以降の取引なので、基本的には過払金は発生しません。
つまり、通常であれば①の取引でも②の取引でも過払金は請求できないことになります。
しかし、①と②が同一の取引と認められる場合には、②の最終取引日である2016年が時効の起算点となるため、過払金を請求できる可能性があるのです。
・①の最終取引日と②の取引開始日の時間的間隔がおよそ6ヵ月以内
・①と②が同一の契約書によって同じ条件で取引されている
貸金業者による不法行為があった場合
貸金業者に、違法な手段による取り立てなどの不法行為があった場合は、時効が過ぎていても請求できる可能性があります。
貸金業法では、貸金業者の取り立て方法について厳しいルールを定めています。以下のような方法は、違法な取り立てにあたり、処罰の対象となります(貸金業法21条1項)。
- 脅迫や暴力などを行使して返済を迫った
- 早朝・深夜の取り立て、執拗な電話などの非常識な取り立て
- 法的根拠がない金利であることをわかってした請求
- 保証人でもない第三者に代わりに請求した
貸金業者にこのような行為があった場合、「不法行為による損害賠償請求」として過払金を請求できる可能性があります。
過払金の請求方法
過払金が発生している可能性がある場合は、以下のような流れで貸金業者に対して請求をしていきます。
- 貸金業者に対し、取引履歴開示請求をする
- 正しい利息で再度計算し、過払金の発生を確認する
- 貸金業者に過払金請求の内容証明郵便を送る
- 任意で支払ってもらえなければ裁判所に訴訟などを申し立てる
以下で、詳しく説明します。
①貸金業者に対し、過去の取引履歴の開示を要求する
まずは取引をしていた貸金業者に対し、過去の取引を全て開示するよう請求します。取引履歴を開示しなければ、過払金が発生しているか確認することはできないからです。
貸金業者には、取引履歴の保存義務があり、顧客には自分の取引履歴を開示するよう請求する権利があります(貸金業法第19条)。
貸金業者が取引履歴の開示を拒めば、不法行為として慰謝料請求が認められることもあります。
貸金業者に取引履歴の開示請求をする際には、当時の氏名、住所、生年月日を伝えましょう。
②正しい利率に直して計算する(引き直し計算)
貸金業者から取引履歴が開示されたら、過払金が発生しているか確認するために、一連の取引を利息制限法内の利率に直して再計算をします。これを「引き直し計算」といいます。
取引を再計算するには、インターネット上にある無料ソフトなどを利用できます。自分で再計算するのが難しければ、弁護士に依頼しましょう。
③時効が近いときは取りあえず内容証明郵便で請求
計算上過払金が発生していたら、時効の進行を止める必要があります。期限が迫っているなら、取りあえず過払金の請求をする意思表示をしなければなりません。
内容証明郵便にて「過払金請求書」を債権者に送ることで、時効の進行を6ヵ月止めることができます。内容証明郵便とは、郵便局が送付した内容や日付を証明してくれる郵便物で、法律上「催告」の効果があります。
「催告」をすると、時効の完成が6ヵ月間猶予されます。その6ヵ月以内に準備をし、訴訟などの裁判手続きを行うことで、時効の進行が止まります。
④裁判所に訴訟または支払督促の申し立てをおこなう
最終的に時効の進行を止めるには、裁判手続きをおこなう必要があります。裁判所を経由した請求をおこなうことで、時効を完全にリセットすることが可能です。
裁判所を介した請求には、「訴訟」や「支払督促」があります。支払督促は、通常訴訟に比べて費用が半額で済み、申し立ても簡単にできるので使いやすいでしょう。
ただし、過払金を計算し、訴訟提起することは、なかなか自力でできることではありません。難しければ、弁護士に依頼することをおすすめします。
特に時効が迫ってきている際には、弁護士でなければ相手が履歴の開示を引き延ばすなどの手段に出る可能性もあります。
過払金請求の際に注意すべきこと
過払金請求を自分でおこなう際には、いくつか注意すべきことがあります。
- 相手の会社が破産している可能性がある
- 請求した相手とは今後取引ができない
- 自力で交渉すると不利になる可能性がある
利息制限法が改正されたのは10年以上前なので、過払金が発生していたとしても、時効が迫っている可能性があります。
急ぐ場合は取引開示から弁護士に依頼しましょう。
相手の会社が破産している場合は請求できない
過払金が発生していたとしても、相手の会社が既に破産していたら請求はできません。
2010年の貸金業法改正当時、多くの貸金業者では利息制限法以上の利率で取引をしていたため、多額の過払い金返済義務が発生しました。
過払金返還のために経営難に陥り、貸金業者の破産や合併などが相次いだため、既に存在しない貸金業者もあるでしょう。
貸金業法改正によって破産や合併をおこなった貸金業者の一例として、以下のような会社があります。
- 丸和商事(ニコニコクレジット)→2011年4月、民事再生
- 武富士→2010年9月、会社更生法適用し、倒産
- アエル→2008年3月、民事再生申立て、倒産
- 三和ファイナンス→2011年8月、自己破産
- クラヴィス→2012年7月、自己破産
過払金を請求した相手の会社とは今後取引できなくなる
相手の会社が破産しておらず、過払金請求ができたとしても、今後その会社とは取引ができなくなります。
過払金を請求しても、信用情報機関には金融事故の記録は残りません。しかし、その貸金業者の「社内ブラック」になってしまいます。
消費者金融はともかく、クレジットカード会社に過払金請求する際には、今後取引できないことを念頭にいれておくべきでしょう。
弁護士でなければ応じてくれない可能性も
自分で貸金業者と交渉すると、過払金をかなり少なく提案されたり、全部の履歴を一度に出してもらえなかったりする可能性もあります。
時効が迫っていることは貸金業者にもわかるため、履歴開示の引き延ばしをされる可能性もあるでしょう。また、不利な条件で和解を迫られ、一度和解を締結してしまえば、それを覆すのが難しくなります。
過払金が発生する可能性がある場合は、できれば履歴開示前から弁護士に依頼することをおすすめします。
早期に履歴開示を進められ、訴訟になっても代理人として対応してくれるなどのメリットがあります。
まとめ
過払金は、最終取引日から10年が経過すると、時効によって請求権が消滅してしまいます。また、2020年の民法改正により、10年経過していなくても、過払金が発生していることを知ってから5年請求しないことでも時効消滅します。
多くの貸金業者が、2007年ごろまでには利率を利息制限法の上限まで下げているので、それ以降の取引では基本的に過払金は発生していません。また、法改正より10年が経過しており、過払金があったとしても時効が迫っていることが考えられるでしょう。
時効が迫った過払金を自力で請求しようとしても、相手に引き延ばしを受けたり、低い金額で和解を迫られたりするかもしれません。
過払金が発生している可能性がある場合は、取引履歴の開示を請求する前に、弁護士に依頼することをおすすめします。
過払金の時効についてのQ&A
過払金の時効について教えてください
さらに、民法改正により、権利があることを知った時から5年で消滅するという項目がくわわりました。この規定は改正後の2020年4月1日以降に適用されます。
そのため、最終取引日から10年経過した場合に加え、2020年4月1日以降に完済した場合は、10年経過していなくても、過払金発生を知ってから5年経過すれば、時効により消滅することになります。
過払金が発生する条件を教えてください。
2010年の改正で、利息制限法の上限以上の取引は正式に無効になりましたが、2006年1月の最高裁判例で過払金返還義務が認められたことにがきっかけとなり、2010年の法改正で、利息制限法の上限利率を超える取引が無効とされました。
ほどんどの貸金業者は、改正貸金業法が施行される前、2007年ごろには利息を改定していたため、過払金が発生する上限は、2007年以前の取引であること、完済から10年が経過していないことです。
過払金が発生しているか確認し、請求するにはどうしたらいいでしょうか。
過払金があったら、時効が迫っている場合は貸金業者へ内容証明郵便で過払金請求書を送りり、6ヵ月以内に訴訟提起もしくは支払督促を裁判所に申し立てることで時効は止まります。
ただし、時効が迫っていることは相手の貸金業者にもわかっています。最初の履歴開示の段階から弁護士に依頼すると、スムーズに進められるでしょう。