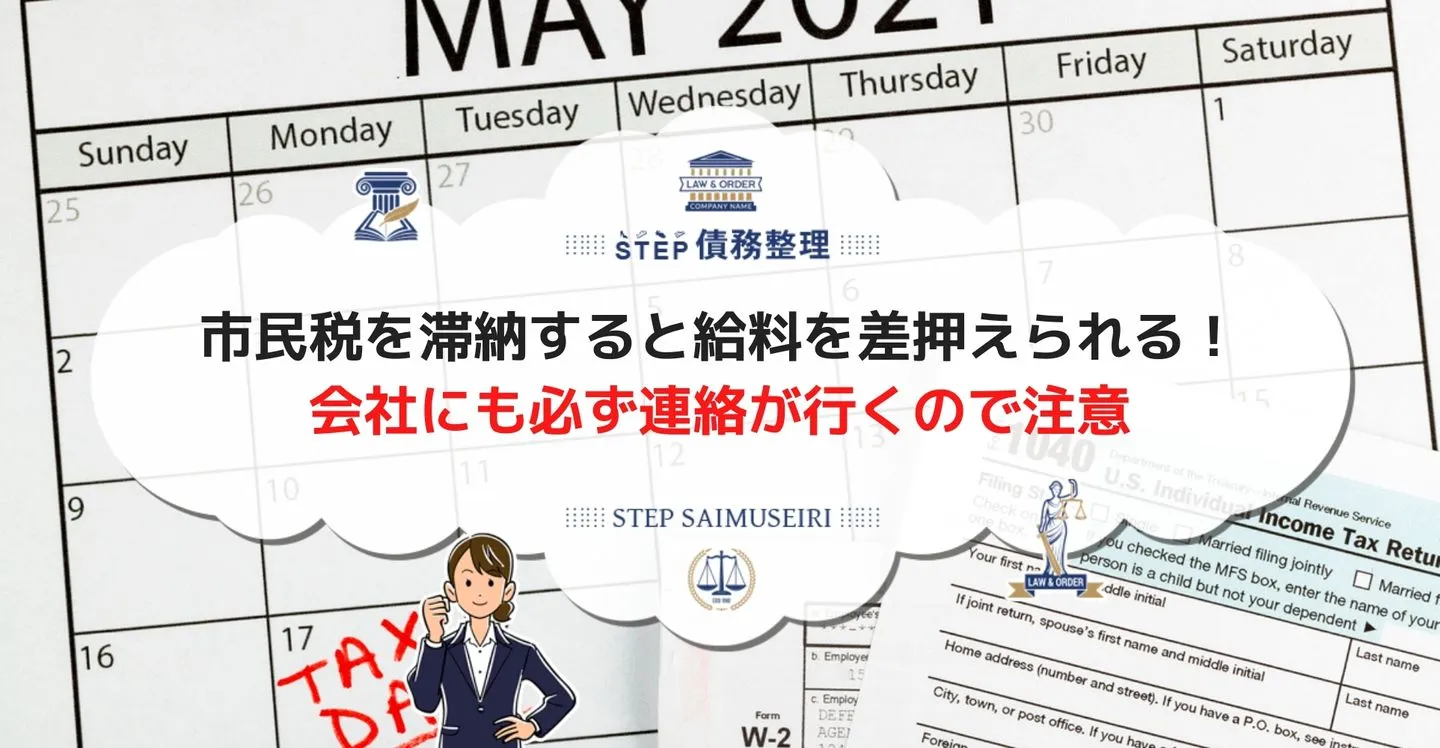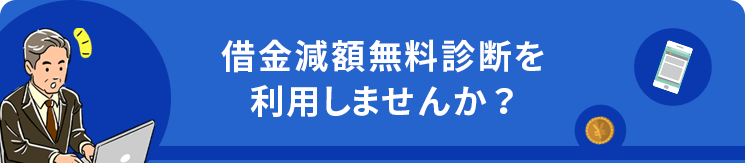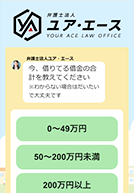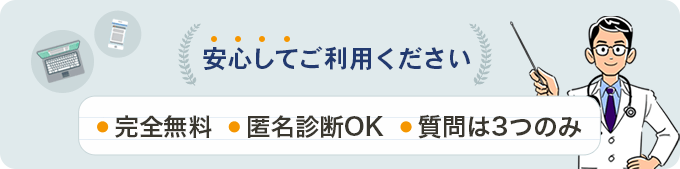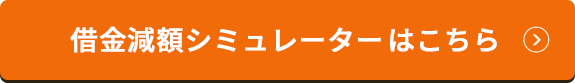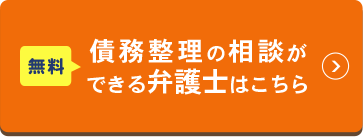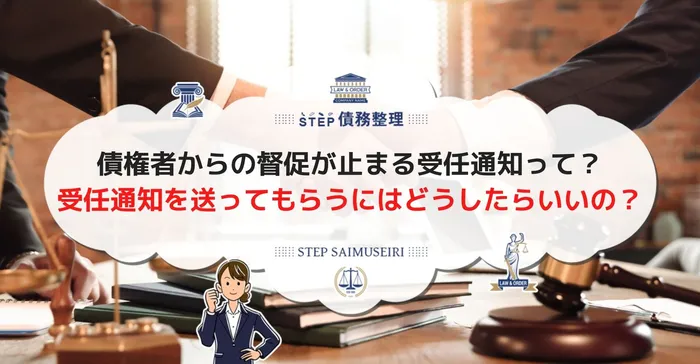普通徴収で市民税を払っているのですが、収入の落ち込みが原因で今年の支払いが難しいです。特別徴収ではなくても滞納が続くと会社に連絡されますか?


市民税の滞納が続くと、最終的には差し押さえによって未払い分の回収が行われます。給与が差し押さえ対象になるとかならず会社に連絡されるので、会社に滞納の事実が知られることになります。
会社にバレるのは困るのですが、どうしても普通徴収を一括で支払えません。何か対処法はありますか?


市民税を滞納しているのなら、市役所に分割交渉に行きましょう。真摯に対応すれば、状況に応じた分割払いを認めてくれるでしょう。また、借金が原因で市民税を払えないのならすみやかに弁護士までご相談を。債務整理で借金問題をまとめて解決できます。滞納する前に、弁護士へ相談するとよいでしょう。
市民税を滞納し続けると、給料が差押えられることがあります。
その場合、会社から給料を振り込まれるときに差押え額が引き落とされるようになるため、会社へ連絡が行くことは避けられません。
また、給料を満額受け取れなくなるので、生活も苦しくなってしまうでしょう。
市民税を支払えない理由が借金の返済である人は多く、それなら弁護士へ相談して借金を解消することをおすすめします。
当サイトでは、借金問題の解決に力を入れる弁護士を紹介しています。無料相談可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
>>【給料差押えの前に!】弁護士へ無料相談して借金問題を解決する
- 市民税の滞納が続くと未納者の給与が差し押さえられる可能性がある。給与が差し押さえられると会社に連絡されるので、滞納の事実がバレる。
- 給与が差し押さえられると未納分が回収されるまで満額を受け取れなくなる。
- 給与の差し押さえを回避するには、市役所で分割払いの交渉をするのがおすすめ。また、状況次第では市民税が減免される可能性もある。
市民税(住民税)の滞納で給与が差し押さえられたときのペナルティ3つ
市民税を払えないままだと、最終的には未納者の給与などが差し押さえられます。
もちろん、他の財産などが滞納処分の対象になることもありますが、給与債権は調査・特定が容易なので、差し押さえの優先順位は高いのが実情です。
給与が差し押さえられると、次の3つのペナルティが発生します。
- 会社に連絡される
- 給与を満額受け取れなくなる
- 延滞金の負担が発生する
それでは、それぞれのペナルティについて見ていきましょう。
市民税(住民税)を滞納すると債権差押通知書が届いて会社にバレる
滞納処分によって給与が差し押さえられると、会社に"債権差押通知書"が届きます。
なぜなら、給与が差し押さえられる際には、従業員の給与が会社から債権者(行政)に直接支払われるという流れが取られるからです。
つまり、従業員が市民税を滞納すると、会社に滞納の事実がバレるだけではなく、「会社が第三債務者として債権者(行政)への支払い義務を負担する」という形で迷惑がかかります。
給与に対する滞納処分は市民税の未納額を全額回収するまで続くもの。長期的に会社に迷惑がかかる可能性があるので注意が必要です。
市民税の滞納で差し押さえられても会社は解雇されない
市民税の滞納処分によって給与が差し押さえられたとしても、当該従業員をクビにすることは法律上禁止されています。
なぜなら、税金の滞納という個人的な事情は、会社の業務についての評価には一切関係がないからです。
とはいえ、市民税の滞納処分によって従業員の信用が失墜するのは事実。すると、法律に詳しくない会社が給与の差し押さえを理由として解雇処分などを言い渡す可能性があります。
この場合には、次のプロセスにしたがって、解雇処分の無効を争う必要があります。
- ①解雇理由証明書を請求する
- ②解雇処分の撤回を要求する
- ③和解交渉を行う
- ④労働審判・訴訟によって解決を目指す
ただ、会社との間で解雇処分の無効を争ったり示談金を求めたりするとしても、従業員が会社と直接交渉するのは立場的にも難しいという問題が残ります。
したがって、会社から不当解雇を受けた場合には、かならず弁護士に相談をして適切な形で交渉を進めてもらいましょう。
市民税(住民税)を滞納すると給与を満額受け取れない
市民税の滞納処分によって給与が差し押さえられると、滞納分全額が回収されるまでは給与を満額受け取れません。
ただ、給与が全額差し押さえられるとすると、未納者が日常生活を送れなくなります。
そこで、市民税を滞納した場合には、「次の①~⑥の合計額」は差し押さえ禁止と扱われ、未納者の手元に残すことができます(国税徴収法第76条1項)。
- ①給与に課せられる所得税
- ②給与に課せられる住民税
- ③各種社会保険料
- ④給与手取り額の20%相当額
- ⑤月額100,000円
- ⑥同一生計で暮らす配偶者等1人あたり45,000円
つまり、市民税の滞納処分を受けたとしても、①~⑥の合計額については毎月会社から給与として受け取れる一方で、①~⑥の合計額を超える部分は会社から行政に振り込まれるので未納者の手元には届きません。
ここで注意しなければいけないのが、貸金業者などからの借金を滞納した場合の差し押さえとは給与の処分範囲が異なるという点です。
貸金業者などからの借金を滞納した場合の強制執行では、給与手取り額の3/4は手元に残せるという運用がとられています(手取り額が44万円を超える場合には33万円以上が処分対象)。
しかし、市民税の滞納の場面では「1/4ルール」が採用されていないので、未納者の給与額次第では、貸金業者からの借金を滞納するときよりも差し押さえ範囲が広がる可能性があるという点に注意しておきましょう。
市民税(住民税)を滞納すると延滞金の負担が加算される
市民税を滞納すると、未払いの税金以外にペナルティとして延滞金の負担が加算されます。そして、給与の差し押さえでは、延滞金の回収まで行われます。
延滞金は、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、毎年所定の年利率を前提に算出されるもの。延滞金の算出根拠は「延滞金特例基準割合」をベースに導かれるので、次のように滞納時期によって負担が異なります。
| 対象期間 | 納付期限の翌日~1ヶ月まで | 納付期限の1ヶ月後以降 |
|---|---|---|
| 令和3年1月1日以降 | 2.5% | 8.8% |
| 平成30年1月1日~令和2年12月31日まで | 2.6% | 8.9% |
| 平成29年1月1日~平成29年12月31日まで | 2.7% | 9.0% |
| 平成27年1月1日~平成28年12月31日まで | 2.8% | 9.1% |
| 平成26年1月1日~平成26年12月31日まで | 2.9% | 9.2% |
| 平成22年1月1日~平成25年12月31日まで | 4.3% | 14.6% |
たとえば、令和3年の市民税20万円を50日滞納している場合には、次の延滞金が発生することになります。
- 延滞金 = (20万円 × 2.5% ÷ 365日 × 30日) + (20万円 × 8.8% ÷ 365日 × 20日) = 1,375円
このように、毎日延滞金が発生する以上、市民税の未納者にとって大切なのは、できるだけ早期に延滞を解消することです。
延滞金の発生を防ぐため、そして、給与の差し押さえを防ぐために、できるだけ早期に市役所まで分割払いなどの交渉に行きましょう。
市民税(住民税)を滞納すると給与差し押さえ以外にもデメリットが生まれる
市民税を滞納すると最終的には給与が差し押さえられるリスクが生じますが、それ以外にもペナルティが発生することになるので注意しなければいけません。
具体的なペナルティとして考えられるのは、次の2点です。
- 給与以外の財産が差し押さえられる
- 滞納中は督促が繰り返される
それでは、それぞれのペナルティについて見ていきましょう。
給与以外の財産も差し押さえられる可能性が高い
滞納処分で差し押さえの対象になるのは給与だけではありません。具体的には、次のものが差し押さえの対象になりうるものです。
- 滞納者に帰属する金銭的価値のある財産(土地・建物を含む)
- 滞納者名義の株式・預金口座
- 夫婦の共有財産
土地・建物
土地・建物が滞納処分によって差し押さえられると、将来的には換価処分によって売却され、売却代金が市民税の滞納額に充てられます。
差し押さえられるとすぐに今の住まいを追い出されるというわけではありませんが、未納分を支払わなければ、生活拠点を失われることにもなりかねません。
滞納者名義の株式・預金口座
滞納者名義の株式・預金口座も差し押さえの対象です。
特に、預金口座が差し押さえられると、口座が凍結されるリスクがあるという点を押さえておきましょう。
たとえば、差し押さえの対象になった口座を開設している銀行との間で、住宅ローンなどの契約を締結していると、第三者による差し押さえはローン契約の「期限の利益喪失条項」に抵触します。
つまり、行政側から預金口座を差し押さえられた段階で、住宅ローンなどの残債を一括請求されるということです。
この場合、預金残高がローン残債総額に満たなければ、銀行口座が凍結されてしまいます。
すると、お金の引き出しはもちろんのこと、各種引き落としなども不可能に。たとえば、公共料金などの支払いもできないということです。
このように、市民税の滞納及び差し押さえをきっかけとして、未納者の生活に波及的なデメリットが生じることになるので、何としても差し押さえは回避すべきだと考えられます。
夫婦の共有財産など
市民税を滞納している人の配偶者や同居家族の財産であったとしても、滞納処分の対象になる可能性があります。
なぜなら、同一生計で暮らしている以上は、財産などの名義がはっきりしないとしても、実質的に滞納者の財産であると評価できる場合が少なくないからです。
たとえば、パートナーの名義の自動車があるとしても、自動車の購入代金を用意したのが滞納者だと判明する場合には、自動車は差し押さえの対象になります。
その一方で、滞納者の住居にある財産であったとしても、次の項目に該当するものについては「滞納者の財産ではないこと」が明確だと考えられるので、差し押さえの対象外と扱われます。
- 配偶者が婚姻前から所有する財産
- 配偶者が婚姻中に自分の支出において獲得した財産
- 配偶者が登記された夫婦財産契約に基づいて所有する財産
- 配偶者・同居親族だけが使用する財産
- 共有財産についての配偶者の持ち分
同居家族の財産は一定範囲で差し押さえの対象外になるものの、差し押さえられるリスクと常に隣り合わせであることには変わりません。
つまり、滞納処分による差し押さえは未納者だけではなく家族にも迷惑がかかる可能性があるので、かならず差し押さえが実行される前に対処法を実践するようにしましょう。
市民税の滞納中は督促が繰り返される
市民税を滞納すると、行政側から督促が繰り返されます。好んで滞納しているわけではないのに、何度も督促状が送付されるのは気持ち良いものではありません。
ただ、貸金業者などからの督促状送付とは異なり、市民税の未納が原因で行われる督促には注意が必要です。
なぜなら、督促状の送付から10日以内に完納しなければ、いつ給与・財産などが差し押さえられてもおかしくない状況に追いこまれるからです。
市民税を滞納した場合、差し押さえまでは次の流れをたどることになります。
- ①市民税の支払い期限
- ②納付期限から20日以内に督促状の送付地方税法第371条
- ③督促状の送付から10日を経過すると差し押さえ可能
通常、貸金業者などからの借金を滞納した場合には、強制執行で財産などを差し押さえる前に裁判所で必要な手続きをとる必要があります。
しかし、市民税の滞納の場合には、①~③のように、裁判所における支払い督促などの手続きは求められません。
したがって、延滞状況におちいり、督促状送付から10日を経過しても完納しない場合には、行政側が未納者の財産調査を行い、必要な財産などを差し押さえることになります。
もちろん、支払い期限を経過してすぐに滞納処分が行われる可能性は低いものの、延滞が長期化するほど不安定な状況に追いこまれることに間違いはありません。できるだけすみやかに対策をとりましょう。
市民税(住民税)の滞納を理由に差し押さえられるときの対処法を5つ紹介
市民税を払えない人にとって大切なことは、給与などが差し押さえられる前に滞納ペナルティを軽減・回避するための対処法に踏みきることです。
もちろん、すでに行政側が差し押さえ手続きに着手した場合でも、未納者側の対応次第では滞納処分を回避できることもできます。
具体的な対処法としては、次の5つが考えられます。
- 滞納を解消して差し押さえを解除する
- 市役所で分割払いを交渉する
- 納付期限の延長・猶予を交渉する
- 減額・免除申請をする
- 借金が理由で住民税を払えないなら弁護士に債務整理を依頼する
それでは、それぞれの対処法について見ていきましょう。
市民税の滞納を解消して差し押さえを解除する
滞納処分によって差し押さえが行われる前であれば、未払い分を完納すればその時点で延滞は解消されるので、それ以上ペナルティが科されることはありません。
また、実際に差し押さえが行われる前なら、分割交渉をする余地も残されています。
その一方で、すでに滞納処分によって差し押さえが実行された場合には、原則として滞納分の市民税を完納しなければ差し押さえを解除することはできません。
つまり、裏から表現すれば、仮に差し押さえが実行されたとしても、未払い分を完納したり、適当な財産が提供されたりした場合には、現在の差し押さえを解除することができるということです。
特に、滞納処分では、どの財産・給与などが差し押さえ対象になるか、未納者側で指定することができません。
滞納処分によって日常生活に大きなデメリットが生じる場合にはすみやかに対応する必要があるので、弁護士などに相談をしてデメリットを軽減するための方法を相談しましょう。
市民税の分割払いを交渉する
市民税は最初から四期分割払いが可能です。
一括で納付書が届くので一括払いだと勘違いしている人は少なくありませんが、自治体ごとに四期ごとの納付期限が定められているので、一括払いが難しい人は分割払いをご検討ください。
また、すでに支払い期限を過ぎてしまった場合でも、市役所で分割払いを交渉することができます。
ただし、どのような分割方法も認められるわけではありません。担当者の判断によりケースバイケースですが、次のような分割方法が提案されるのが一般的です。
- 最大分割回数12回
- 毎月の支払い最低額1万円
- 1年以内に完済できる返済計画
ただ、現在の滞納状況が悪質だったり、支払いの意思がないと判断されたりすると、そもそも分割交渉が認められない可能性もあります。
したがって、支払い意思を示しながら、真摯に交渉に向き合うようにしてください。
市民税の納付期限の延長・猶予を交渉する
市民税の納付期限の延長・猶予を交渉することも可能です。
たとえば、納付期限の翌月にまとまったお金が入ってくる予定が明確なら、その旨を行政側に伝えれば支払い期限を延長してくれます。
また、新型コロナウイルスの影響で収入が大幅に減少したというケースでは、分割払いでも支払いが難しいという場合もあるはずです。
この場合も、市役所の担当者に一定期間納付の猶予を求めれば、延滞金の負担なしで支払いを待ってくれる可能性もあります。
ただ、納付期限の延長・猶予を申請するためには、当初の市民税の支払い期限までに交渉に行くのが原則です。
滞納状態におちいってから延長・猶予を求めると交渉に応じてくれない可能性が高くなるので、できるだけ早いタイミングで窓口まで足を運びましょう。
市民税の納付期限までに減額・免除申請をする
一定の事情が認められる場合には、市民税の減額・免除が認められるケースがあります。
ただし、市民税の減免申請は納付期限までに行わなければいけないのが通常です。
次の事情に該当する方は、期限までに自治体の担当局までお問い合わせください。
| 減免事由 | 注意事項など |
|---|---|
| 生活保護等の公的扶助を受給中 | 全額免除 |
| 失業 | 所得や減少割合によって減額割合が異なる |
| 所得が前年の6割以下に減少 | 退職理由・保有資産次第では減免の対象外 |
| 障がい者・未成年・寡婦・ひとり親 | 所得に応じて減額割合が異なる |
| 被災したケース | 被害の具合で減免割合が異なる |
なお、減額条件や申請方法はお住まいの自治体によって条件が異なります。詳しくは、担当部局までお問い合わせください。
借金が理由で住民税を払えないなら弁護士に相談しよう
借金が理由で住民税を払えないなら、弁護士に債務整理を依頼するのがおすすめです。
債務整理とは、国が認めた合法の借金減免制度のこと。住民税の支払い義務自体は債務整理で減免できませんが、債務者が抱えている借金問題を債務整理で改善すれば、住民税を支払える家計環境を生み出すことができます。
市民税を支払える家計環境を整えるために弁護士に債務整理を依頼するメリットは次の通りです。
- 債権者からの返済督促をとめられる
- 債務整理の依頼によって返済自体がストップする
- 債務者にとって適切な生活再建を目指せる
- 市民税滞納についてのアドバイスをもらえる
それでは、それぞれのメリットについて詳しく見ていきましょう。
債権者からの返済督促をとめられる
弁護士に債務整理を依頼すれば、その時点から貸金業者などの取り立てが止まります。
なぜなら、弁護士が債権者に送付する受任通知には、返済督促を停止させる効力があるからです。
ただし、未払い市民税の督促状の送付はとめることができません。
借金の取り立てから解放されてストレスがない状態で、市民税の支払いについて検討しましょう。
債務整理の依頼によって返済自体がストップする
弁護士に債務整理を依頼すれば、その時点から借金の返済をする必要がなくなります。
なぜなら、債務整理の準備に入ったにもかかわらず返済が続くとなると、借金減額制度の公平な運用の妨げになるからです。
したがって、借金問題を解決するために債務整理を依頼した段階から毎月支払っていた借金の返済額分だけ家計に余裕が生まれることになるので、住民税を支払いやすい環境が整うと考えられます。
債務者にとって適切な生活再建を目指せる
債務整理には、自己破産・個人再生・任意整理の3つの手続きが用意されているので、実績豊富な弁護士に適切な手続きを選択してもらいましょう。
ただ、どの債務整理を選んでも問題なく生活再建を目指せるというわけではありません。
自己破産・個人再生・任意整理はそれぞれ効果も異なりますし、メリット・デメリットにも違いがあります。
- 自己破産:借金の返済義務が免責されるものの、財産処分などのデメリットが大きい。
- 個人再生:借金元本額を大幅に減額できる可能性があるものの、裁判所の手続きが複雑。
- 任意整理:他の債務整理に比べると減額効果は弱いが、スムーズに利息の支払いをカットできる。
たとえば、「マイホームを手放したくない」という債務者には、財産処分が必須の自己破産は不適切です。
なぜなら、どれだけ借金返済義務が免除されるとはいっても、自己破産を利用すると自宅を手放さざるをえないからです。
この場合には、持ち家にそのまま住みながら大幅な減額効果を狙える個人再生や、債権者と直接交渉して今後の返済計画を作り直せる任意整理がおすすめでしょう。
このように、債務整理の手続き選択の際には、債務者の希望だけではなく、手続き自体の特徴や債務者の借金状況などを客観的に分析する必要があります。
債務整理に強い弁護士に相談をすれば、今後の生活を送りやすいように借金問題を改善してくれるので、かならず事前にご相談ください。
市民税滞納についてのアドバイスをもらえる
債務整理に強い弁護士は、債務者が抱えているお金に関する問題すべての相談に乗ってくれます。
したがって、借金問題を解決するために債務整理を依頼するとしても、市民税の滞納に対しても適切なアドバイスが期待できるでしょう。
さらにいえば、市民税の分割払いの交渉の際には、「弁護士からのアドバイスを受けている」旨を行政担当者に伝えれば、比較的交渉が進みやすいというメリットもあります。
まとめ
市民税の滞納が続くと滞納者の給与などが差し押さえられる可能性が高いです。
給与が滞納処分の対象になると、会社に市民税滞納の事実がバレますし、社会的な信用も失われます。
もちろん、市民税の滞納を理由とする解雇処分は無効なものですが、万が一会社側から処分を言い渡された場合には、労働紛争などによって争う負担も強いられます。
したがって、市民税を払えない状況にあるのなら、できるだけ早いタイミングで市役所の担当部局まで足を運び、分割払いや支払い期限の猶予などの交渉を行ってください。支払いを無視しても延滞金の負担が加算されるだけです。
また、市民税以外にも借金を抱えていて家計がひっ迫しているのなら、素直に弁護士の力を借りましょう。
なぜなら、弁護士に相談すれば、借金問題を解決するために適切な債務整理手続きを選択してくれますし、これによって市民税を支払いやすい家計環境が整うからです。
借金問題に強い弁護士なら、債務者にとって必要な対処法を教えてくれるので、これ以上ペナルティが重くなる前にご相談ください。
差押えに関するよくある質問
市民税を滞納すると給与が差し押さえられますか?
滞納が続くと給与などが差し押さえられて未納代金を回収されます。
市民税滞納が原因で給与を差し押さえられると会社に連絡されますか?
なぜなら、給与債権の差し押さえによって、会社が行政に直接お金を支払うことになるからです。
給与を差し押さえられることで会社をクビになりますか?
ただし、法律に詳しくない中小企業などの場合には解雇処分などを下されるリスクがあるので、当該処分の無効などを法的に争う必要が生じます。
早期の対策が鍵になるので、すみやかに弁護士に相談しましょう。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
給与の差し押さえを回避する方法はありますか?
また、納付期限前であれば、期限の猶予や延長、要件を満たせば市民税の減免も可能です。
市民税を滞納すると、給与の差し押さえ以外にペナルティは発生しますか?
同居家族がいる場合には、処分対象になる財産の範囲がさらに拡大するリスクもあるので、家族にも迷惑がかかるでしょう。
滞納処分が下される前に行政や弁護士などの専門家にご相談ください。