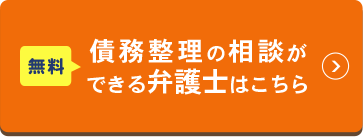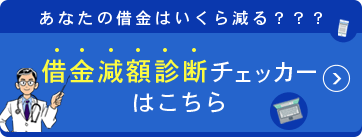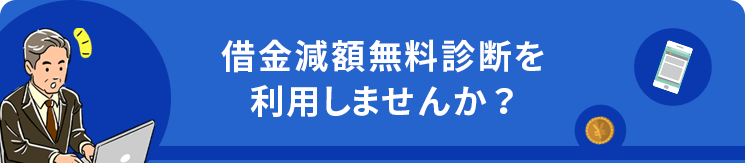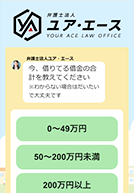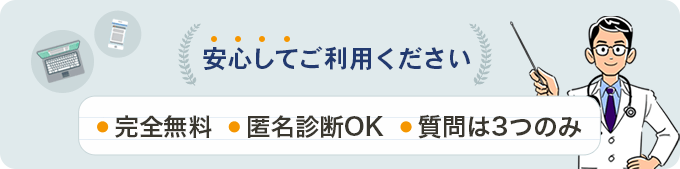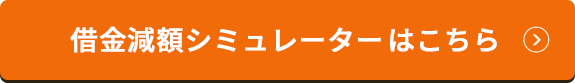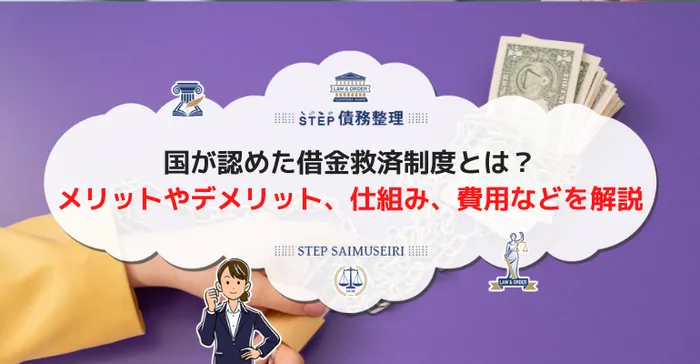夫が自営業をしているのですが、事業がうまくいかず多額の借金を抱えています。私が借金の解決や、自営業を諦めるようにいっても聞く耳をもちません。離婚したいのですが、どうすればよいでしょうか?


配偶者が自営業者でも、離婚の手続きは変わりありません。すでに離婚の意思が固まっているのならば、なるべく早く行動を起こしたほうが配偶者の破綻に巻き込まれずに済むでしょう。
借金がある場合、財産分与はどうなるのでしょうか?


借金に関しては、財産分与の対象になりません。ただし、事業用の借入を肩代わりしている場合や連帯保証人になっている場合は、離婚後も返済を請求されるリスクがあります。離婚前の協議において、公正証書を作るなど対策が必要です。
もし、離婚はせずに借金問題を解決するなら、どんな方法があるでしょうか?


債務整理でいまある借金を清算するのがよいと思います。配偶者としっかり話し合って、弁護士に相談しましょう。
配偶者が自営業者であり事業資金などで借金を繰り返している状況では、生活は非常に苦しくなり離婚を考えている人も多くいると思います。
しかし、配偶者が自営業者の場合、借金が「事業資金」なのか「生活資金」なのかが離婚時の財産分与に影響するなど、離婚すれば金銭的負担が軽くなるとは限らないケースもあります。
そのため、借金問題や離婚問題はまとめて弁護士に相談して、適切なアドバイスをもらうのがおすすめです。
また、弁護士に相談すれば、離婚ではなく配偶者と一緒に借金問題を解決するための方法や心構えも教えてもらえます。
自営業者で借金のある配偶者と離婚する場合、時間が経つほど借金が悪化する恐れがあるため、ぜひ早めに相談してくださいね。
- 自営業者で借金のある配偶者と離婚する場合、決心が固いなら早めに行動を起こしたほうがよい。
- 配偶者が自営業者でも離婚の基本的な流れは変わらず「協議離婚」「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」と進んでいく。
- 配偶者が自営業者の場合、借金が「事業資金」なのか「生活資金」なのかが財産分与に影響する。
- 配偶者の借金問題を解決するには、弁護士に相談して債務整理をするのがよい。
自営業者で借金のある配偶者と離婚するなら早めに行動を起こしたほうがよい
離婚を検討するときは、さまざまな不安があると思います。
離婚後の生活や仕事、子供のメンタルケアなどが気になって、なかなか離婚に踏み切れないという人もいるでしょう。なかには、心のどこかでまだ配偶者を信じたい気持ちがあって、無意識に離婚を避けようとする人もいます。
しかし、離婚の原因が借金である場合、問題解決を先延ばしにするほど事態は悪化していきます。
とくに、自営業者で多額の借金を抱える人は、さらなる借金を重ねやすいので注意が必要です。
離婚は普通、夫婦の信頼関係が失われた場合にするものです。
しかし、借金問題が絡むときは、生活の破綻に巻き込まれないよう自分の身を守る手段にもなります。
「離婚はしたいがどのタイミングで切り出そうか迷っている」というときは、なるべく早く行動に起こしたほうがよいでしょう。
自営業者の借金は時間が経つほど悪化しがち
借金は、金額が大きくなるほど金銭感覚も麻痺していきます。
自営業者の場合、1人で多額のお金を取り扱います。事業の規模にもよりますが、数百万円、数千万円のお金のやり取りも普通です。
事業が順調で、きちんと収益が出ているのなら問題はありませんが、事業が苦しく借金を抱えている状態だと危険な状態に陥りやすくなります。
「いま100万円借りても、事業が波に乗ればすぐに借金を返せる」というような、ギャンブルに近い思考となってしまう場合があるのです。
借金が悪化すれば生活費も勝手に使われる恐れがある
事業がうまくいかず借金を抱えていても、最低限の生活費を稼げるなら良いほうです。
しかし、最低限の生活費を入れるどころか、生活に必要なお金を勝手に使ってしまうケースもあります。
食費や光熱費、子供の教育費など、家にあるお金を勝手に持ち出すような場合もあるかもしれません。
生活費にまで手をつけるような状態であれば、事業は危機的な状況であるといえます。
借金問題や離婚問題は弁護士に相談して適切なアドバイスをもらおう
離婚するにしろ、夫婦で協力して生活を立て直すにしろ、1人で悩んでいても解決は困難です。
「なんとかしなければ」と思ってはいても具体的な対策は思い浮かばず、夫婦の話し合いも喧嘩ばかりでままならないという人も多いのではないでしょうか。
「借金をどうやって解消するか」「離婚すべきか、するならどんな準備や手続きが必要か」は、すべて弁護士に相談できます。
ただ悩むだけでは、事態はよくなりません。無料相談を利用して、弁護士から見た問題解決のアドバイスをもらいましょう。
配偶者が自営業者でも離婚の基本的な流れは変わらない
離婚する場合、具体的にどんな方法があるかきちんと把握している方はそれほど多くないでしょう。
配偶者が自営業者であっても、離婚における基本的な方法は変わりません。
ただし、離婚の方法によっては原因が「借金」のみだと、離婚は認められない可能性があります。
離婚手続きの方法や、借金による離婚の注意点などを詳しく見ていきましょう。
離婚手続きには4種類ある
離婚手続きには4つの種類があり、双方が離婚に合意しているかどうかで手続きも変わります。
4つの離婚手続きは次のとおりで、段階を踏んで進めていく必要があります。
- 協議離婚
- 調停離婚
- 審判離婚
- 裁判離婚
協議離婚が成立しなければ調停離婚、調停離婚が成立しなければ審判離婚、という順番です。
各手続きを詳しく解説していきます。
協議離婚
離婚をする場合、まずは夫婦で離婚に向けて話し合います。当事者間の話し合いで離婚に合意できれば、協議離婚となります。
協議離婚は夫婦の合意がすべてです。財産分与や養育費、子供との面会頻度など、離婚条件を夫婦ですり合わせます。
すべての条件で双方が合意できたら、離婚届を提出して離婚成立です。取り決めた離婚条件は離婚協議書で書面化しておきましょう。
さらに、離婚協議書をもとに公正証書を作成しておけば、取り決めの強制力が高まります。
調停離婚
夫婦の話し合いで離婚の合意が得られなかった場合、家庭裁判所に申し立てて調停を起こせます。調停で離婚を成立させるのが調停離婚です。
調停は裁判所の調停員が間に入り、中立的な立場から離婚に向けた話し合いを進めます。
ただし、調停員はあくまで調整役であり、離婚する・しないを直接決めるわけではありません。
調停員は法律的、客観的な意見の調整をおこないますが、調停が成立するには当人である夫婦の合意が必要です。
審判離婚
調停において離婚自体は夫婦で合意しているものの、細かい条件で折り合いがつかないというような場合、審判離婚に移行します。
夫婦で揉めている部分の条件について、家庭裁判所で裁定します。
ただし、審判の結果は夫婦のどちらかが簡単に異議を申し立てられます。異議を申し立てられると裁判離婚に移行するため、最初から審判離婚を省略するケースも多くあります。
家事事件手続法284条1項
家庭裁判所は、調停が成立しない場合において相当と認めるときは、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情を考慮して、職権で、事件の解決のため必要な審判(以下「調停に代わる審判」という。)をすることができる。
裁判離婚
調停離婚の不成立、もしくは審判離婚での異議申し立てがあった場合、裁判離婚の手続きに移行します。
裁判離婚は、法律上の離婚原因(法定離婚事由)があると裁判官が認めれば成立します。
つまり、協議離婚や調停離婚のように夫婦の同意は必要なく、判決によって強制的に離婚が成立するのです。
法定離婚事由は、民法770条1項で次のように決められています。
民法770条1項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
裁判離婚は原因が借金だけでは成立させるのがむずかしい
裁判離婚の場合、離婚の成立には法定離婚事由を満たしているかが重要になります。
そして、法定離婚事由に借金に関する項目はありません。
つまり、裁判離婚に発展すると、ただ「相手が借金している」というだけでは離婚が成立せず、訴えを棄却される可能性があるのです。
裁判離婚で離婚を成立させるためには、借金のほかに、法定離婚事由に結びつく事実が必要になります。
借金を原因として裁判離婚が成立する事例
借金が原因の離婚でも、下記のような状況であれば裁判離婚が成立します。
- 高額な借金の事実を知らされずに結婚した
- 生活費を入れない
- ギャンブルで浪費している
- 不倫相手に借金のお金をつぎ込んでいる
- DV
細かい状況や経緯によって判断も異なるので、裁判離婚が成立するかは弁護士に相談して聞いてみましょう。
配偶者が自営業者の場合における財産分与と借金の関係性
離婚する際、夫婦の共有財産を財産分与によって分割します。
財産分与の基本は「夫婦で折半」です。夫婦で収入に差がある場合や、専業主婦で収入がまったくない場合でも、夫婦双方に1/2ずつの取り分があります。
しかし、配偶者が自営業者で借金もある場合、財産分与への影響はあるのでしょうか?
配偶者が自営業者である場合、借金が私的なものなのか、事業用のものなのかが重要になります。
事業資金としての借金は財産分与に含まれない
事業資金として借りたお金は、財産分与の対象にはなりません。配偶者名義で借りているのであれば、配偶者に返済義務があります。
反対に、自分が事業資金の借入を肩代わりしていた場合、返済義務も自分にあります。融資した金融機関にとって離婚は関係ないことで、借入の名義人に返済を求めるだけです。
また、自営業者の場合は事業資金と生活資金があいまいになっているケースも多々見られます。借入の名目が事業資金であっても、それを生活費にあてていると客観的に判断されれば、財産分与の対象となります。
離婚しても連帯保証人としての立場は解除できないので注意
自分が直接お金を借りていなくても、配偶者の連帯保証人になっている自営業夫婦は少なくありません。
連帯保証人も、離婚したからといって変更はできません。離婚した後も、債務者である配偶者が返済を滞らせれば、請求が自分にくるリスクは残ります。
債権者である金融機関と交渉して連帯保証人を別の人に差し替える方法もありますが、承諾を得られるケースはあまり多くありません。
名義人である配偶者に借り換えをしてもらうことで、連帯保証人から外れるという方法もありますが、配偶者が借り換えの審査を通過できるのか、という問題があります。
ただし、連帯保証人が連帯保証契約によって代わりに返済をした場合、連帯保証人は債務者に対して求償権を行使できます。
どうしても連帯保証人を解除できない場合、裁判を経ずに求償権を行使して相手の財産を差し押さえられるよう、公正証書を作成しておくとよいでしょう。
生活資金としての借金や住宅ローンは財産分与に含まれる
事業資金が財産分与に含まれないのに対して、生活資金としての借入や住宅ローンは財産分与に含まれます。
財産と借金を合算して、余った分を折半するのが一般的です。
ただし、すでに解説したとおり、財産分与の内容は夫婦の合意次第で自由に決められます。借金は計算に入れず財産分与をするのも可能です。
トータルでマイナスになる場合は財産分与をおこなわないのが一般的
財産と借金を合算して余らない場合や、マイナスになる場合は財産分与そのものをしません。
このような場合、預貯金の100万円を分割しない代わりに、借金500万円も分割しません。
財産の名義や種類(現金か不動産か)によって考えかたは細かく変わるので、離婚時には夫婦がそれぞれもつ財産と借金をしっかり確認し、弁護士などと相談しながら財産分与を決めていくとよいでしょう。
養育費は相手に借金があってももらえる
子供を引き取る場合、養育費をしっかりもらえるかも重要です。
養育費に関しては、配偶者に借金があっても請求できます。仮に配偶者が自己破産しても、相手の「養育費を支払う義務」はなくなりません。
養育費の算定については、家庭裁判所が定める「養育費・婚姻費用算定表」を参考にして決められます。
養育費が減額になる事例
借金があっても養育費の支払い義務はなくなりませんが、いくつかのケースでは減額になる場合もあります。
- 支払う側が再婚して扶養家族が増えた
- 受け取る側が再婚した
- 支払う側の収入が本人の意志によらず減った
- 受け取る側の収入が増えた
上記のケースでは、養育費を減額される可能性があります。
ただし、ある日突然、減額が認められるわけではありません。支払う側から減額の請求があって、受け取る側が合意した場合に減額されます。
また、減額請求が話し合いで解決できなかった場合は、裁判所の調停や審判に発展することもあります。
借金が理由の離婚は慰謝料をもらえない可能性もある
慰謝料は、夫婦関係の破綻に至るような重大な落ち度や責任が認められる場合に請求できます。
そして、裁判離婚の項目でも解説した「法定離婚事由」に借金の項目はありません。
つまり、ただ借金をしたというだけでは、慰謝料は請求できません。借金と同時に、DVなどの事実がある場合に限り請求できます。
また、慰謝料は自己破産で免責(=責任の免除)をできるため、配偶者が自己破産をした場合、請求自体ができなくなってしまいます。
そのため、相手が自己破産をする前に、まとめてすぐに慰謝料を支払ってもらう必要があるでしょう。
配偶者の借金問題は債務整理で清算できる
ここまでは「借金が原因で離婚すること」を前提に解説しましたが、なかには「本音では離婚したくない」と思っている人もいるでしょう。
「借金問題さえ解決してくれれば丸く収まるのに」と考える人もいるのではないでしょうか。
そのような場合は、配偶者に債務整理を提案してみましょう。債務整理をすれば借金を清算できるうえ、新たな借入もできないため、借金が癖になっている場合にも効果的です。
債務整理には次の3種類があります。
| 任意整理 | ・債権者と交渉して利息を減額してもらう ・元本は減らない |
|---|---|
| 自己破産 | ・元本と利息の全額が免責される ・手持ちの財産はほとんど処分する必要がある |
| 個人再生 | ・1/5~1/10まで借金を減らせる ・財産の処分は必要だが、住宅など一部残せる財産がある |
自営業による借金の場合、自己破産を選択するのが一般的です。
ただし、自営業者が自己破産する場合、事業用の資産(機材や売掛金など)も処分する必要があります。
自己破産=廃業ではありませんが、事業用資産を処分した後に事業を継続できない場合、結果的に廃業が必要になるので注意しましょう。
配偶者と一緒に借金問題を解決したいなら相手を否定せずに対話しよう
配偶者と離婚せず、一緒に借金問題を解決したい場合は、夫婦でしっかりと対話を交わすことが大切です。
借金が発覚したときなどは感情的になって、夫婦で言い争いになるケースは多いでしょう
しかし、夫婦で喧嘩をしても借金問題は解決しません。借金をしている自営業者は、後ろめたさや責任感、プライドなどさまざまな理由で「借金を隠したい」「自分でなんとかするから口出しされたくない」と考えます。
自分の言い分もあるとは思いますが、まずはぐっとこらえて、否定せずに相手の話を聞く態度を取りましょう。
相手が頑なに対話を拒むなら弁護士を挟んで話し合おう
とはいえ、自分がいかに対話を試みても、相手に対話を拒まれては話もできません。
そんなときは、弁護士に相談してみましょう。当人同士では冷静に話し合いができなくても、弁護士の客観的な意見を挟むことで、借金問題を解決する糸口が見えてきます。
配偶者の借金で悩んでいる人も、借金をしている配偶者本人も、当人同士で冷静に話し合うのはむずかしいものです。第三者の手を借りて、建設的な解決策を考えましょう。
まとめ
配偶者が自営業で借金を作っていても、離婚の手続き自体は通常の離婚と変わりません。
すでに「絶対に離婚する」と考えている場合は、なるべく早く行動に起こしたほうがよいでしょう。時間が経つほど借金が膨らみ、生活費の使い込みや財産分与の目減りなど、状況が悪化していくかもしれません。
反対に、少しでも「一緒に借金問題を解決したい」と思っている場合は、夫婦でしっかりと対話し、債務整理など具体的な解決方法を提案してみましょう。
そして、離婚をする場合も、債務整理をする場合も、まずは弁護士に相談していみるのをおすすめします。弁護士なら2つの問題に関して、法律家としての観点から最適なアドバイスが可能です。