相続財産に不動産が含まれる場合、基本的には査定が必要です。なります。なぜなら、不動産は相続財産の中でも金額が大きく、現金のように単純に分割できない資産だからです。そのため、遺産分割や売却の判断を進めるうえで、トラブルを避けるためにも「この不動産がいくらの価値を持つのか」を正しく把握しておく必要があります。
査定が必要となる典型的なケースは次の通りです。
- 売却するか所有を続けるかを検討するとき
相続した不動産を売却して現金化するのか、それとも相続人の誰かが利用するのかを判断するには、まず市場でどの程度の価格になるのかを知る必要があります。査定額を基準にすることで、損をしない選択が可能になります。 - 遺産分割の基準を決めるとき
相続人が複数いる場合、不動産はしばしば遺産分割協議の中心になりやすいです。例えば、長男が家を引き継ぐ代わりに他の相続人に代償金を支払う場合、その金額が妥当かどうかの判断基準が必要になります。 - 相続税を計算するとき
不動産の評価額は相続税額に影響するため、納税額の目安を知る上でも重要です。
弊社でも実際に「事前に査定をしておかなかったために揉めている」というご相談を多くいただきます。例えば、相続人同士でおおよその価値を話し合いだけで決めてしまい、後から実際の相場と数百~千万円の差があることが判明したケースがありました。このような場合、一度合意した分割内容をやり直すのは難しく、家族関係に深刻な影響を及ぼすこともあります。
ちなみに、相続不動産の査定方法は大きく3つに分けられます。弊社でご相談を受ける際にも、状況に応じていずれかを検討いただくケースが多いです。
| 相続不動産の査定方法 | 概要 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 不動産会社に査定を依頼する | 地域の取引事例や需要を踏まえて、売却を前提とした価格を提示してもらう方法。 | 実際に売却を検討している場合や、複数社の査定を比較してとりあえず相場観を知りたい場合 |
| 不動産の鑑定評価を依頼する | 不動産鑑定士が法律に基づき客観的に評価額を算出する方法。裁判でも有効な資料になる。 | 複数の相続人同士で不動産を公平に分割したい場合。訴訟で有効な資料を提出したい場合。 |
| 公的な資料をもとに自分で調べる | 国税庁の路線価、固定資産税評価額、公示地価などを利用して自分で査定する方法。 | 手間をかけてでも自分でやりたい場合。大まかな価値を把握できればよい場合。 |
このように、それぞれの方法には特徴があります。例えば「すぐに売却したい」方は不動産会社への依頼が現実的ですし、「相続人間で揉めている」場合は不動産鑑定士による評価が役立ちます。一方で「人に頼むまでもないが、おおよその価値を知りたい」だけであれば、公的資料で概算を確認するだけでも十分でしょう。
本記事では、相続不動産の査定が必要となる具体的なケースや査定方法、必要書類など、相続不動産の査定について詳しく解説します。
相続不動産に関する判断は、将来の資産形成だけでなく、家族関係にも長く影響を及ぼします。不安のある方は参考にしてみてください。
相続不動産の査定が必要になるケース
相続した不動産をどのように扱うかを判断する際には、その資産価値を正しく把握することが欠かせません。不動産は現金のように簡単に分けられる資産ではなく、相続人全員が納得できる判断を下すには客観的な基準が必要になります。弊社でも、査定を行わず遺産分割を進めた結果、相続人間で意見が食い違い、再度話し合いが必要になったケースの相談を受けたことがあります。ここでは、相続不動産の査定が求められる具体的なケースについて解説します。
売却するか所有し続けるかなどの判断材料にしたいとき
不動産の査定は、売却するか所有し続けるかを判断において非常に重要です。市場価値を把握することで、売却すればどの程度の金額で現金化できるか、所有を続ければ資産価値や維持管理の負担がどれほどかを具体的に検討できます。
売却を選択する場合は、査定額をもとに適正な売却価格を設定でき、売却活動をスムーズに進めやすいです。所有を続ける場合は、資産管理や将来の活用計画の判断材料として活用でき、例えば賃貸に出すことで収益化するか、将来売却するまで維持するかといった具体的な方針を決めることができます。
公平な遺産分割のために不動産の資産価値を知る必要があるとき
次に、公平な遺産分割のために不動産の価値を知る必要がある場合です。相続人が複数いる場合、不動産は遺産分割協議の中心になることが多くあります。例えば、長男が実家の建物を引き継ぐ代わりに、他の相続人に代償金を支払うケースがあります。このとき、代償金の額を決めるためには、不動産の市場価値や資産評価を正確に把握しておくことが不可欠です。
弊社でも、査定を行わずに金額を決めたことで、後に相続人間で意見が食い違い、追加の協議や調整が必要になった事例を数多く見てきました。正確な評価があることで、代償金の額や持分の調整が合理的に決まり、相続人全員が納得しやすくなります。
相続税の計算をするとき
相続税の計算にも査定額は重要です。不動産の評価額は相続税の算定に直接関わるため、納税額の目安を知るうえで欠かせません。申告期限に間に合わせるためにも、早めに査定を行い、資金計画や売却・継続所有の判断に活用することが必要です。
相続不動産における3つの査定方法
相続不動産の査定方法は一つではありません。将来の売却や遺産分割、相続税の申告に備えるためにも、状況に応じて適切な手段を選ぶことが大切です。ここでは、それぞれの方法と必要書類について具体的に解説します。
| 相続不動産の査定方法 | 概要 | 向いているケース |
|---|---|---|
| 不動産会社に査定を依頼する | 地域の取引事例や需要を踏まえて、売却を前提とした価格を提示してもらう方法。 | 実際に売却を検討している場合や、複数社の査定を比較してとりあえず相場観を知りたい場合 |
| 不動産の鑑定評価を依頼する | 不動産鑑定士が法律に基づき客観的に評価額を算出する方法。裁判でも有効な資料になる。 | 複数の相続人同士で不動産を公平に分割したい場合。訴訟で有効な資料を提出したい場合。 |
| 公的な資料をもとに自分で調べる | 国税庁の路線価、固定資産税評価額、公示地価などを利用して自分で査定する方法。 | 手間をかけてでも自分でやりたい場合。大まかな価値を把握できればよい場合。 |
不動産会社に査定を依頼する
相続した不動産の資産価値を知るには、不動産会社による査定が有力な手段です。査定には「机上査定(簡易査定)」と「訪問査定」の2種類があります。机上査定は所在地や広さ、築年数などの基本情報をもとに速やかに市場価格の目安が得られるのが特徴です。
一方で、物件の具体的な状態や周辺環境などは反映されないため、より正確な見積もりが必要な場合には訪問査定が適しています。訪問査定では担当者が実際に現地を確認し、建物や権利関係、インフラや法的規制なども踏まえた精度の高い価格評価が可能です。
| 査定方法 | 概要 | 必要な書類例 |
|---|---|---|
| 机上査定 | 不動産会社が物件資料や公的データ(登記情報、路線価、過去の取引事例など)をもとに、現地に行かずに算出する査定。おおよその売却価格を短時間で把握できる。 | 登記事項証明書(登記簿謄本) 土地公図公図・測量図・建物図面(所在地・面積・築年等が確認できる資料) |
| 訪問査定 | 不動産会社が実際に物件を訪問し、建物の状態や周辺環境、日当たり、設備状況などを確認した上で査定を行う方法。より精度の高い査定が可能。 | 上記に加え、 権利証/登記識別情報 身分証明書(運転免許証等) 固定資産税関連書類(納税通知書や評価証明) 売買契約書・重要事項説明書 リフォーム契約書 マンションなら管理規約・修繕計画書など |
不動産の鑑定評価を依頼する
不動産鑑定評価は、国家資格である不動産鑑定士のみが行える評価手法であり、「経済価値を判定し、価額として表示する」専門業務です。相続や税務、紛争などの重要な場面において、法的・客観的に価値を証明する際に不可欠です。
依頼時には、以下のような書類の提出が求められます。
| 書類 | 内容 |
| 納税通知書(固定資産税・都市計画税) | 地番・家屋番号を含めた不動産特定に役立つ資料 |
| 全部事項証明書(登記簿謄本) | 所有者や権利関係、土地・建物の面積等が確認できる基本資料 |
| 住宅地図、公図、地積測量図、建物図面 | 位置・形状や建物の構造・延床面積を把握するための図面類 |
| その他必要資料 | 固定資産税評価証明書、建築確認通知書・検査済証、賃貸契約書など、物件の特性に応じて追加資料が求められる場合もあります。 |
公的な資料をもとに自分で調べる
相続した不動産の資産価値を自己確認する際、手間や費用を抑えてある程度の目安を把握するには、公的データの活用が非常に有効です。まずは、固定資産税の課税明細書や評価証明書、名寄帳(固定資産課税台帳)によって、土地や建物の評価額や所在地、面積などの基本情報を取得できます 。
さらに、路線価図や評価倍率表(国税庁)をもとに相続税評価額を自分で概算したり、地価公示価格や都道府県地価調査、さらに国土交通省の「不動産情報ライブラリ」や「全国地価マップ」などで周辺の取引価格や公示地価を参照し、相場を確認する方法もあります 。
これらを組み合わせることで、相続不動産が資産としてどの程度の価値を持つのか、初期の判断材料として十分に役立ちます。
相続不動産を査定する際の注意点
相続した不動産を円滑に活用・処分するためには、査定を依頼する際の注意点を理解しておくことが欠かせません。ここでは、査定を依頼する前に確認しておくべき重要なポイントを整理し、実務上の注意点を解説します。
相続が発生したら早めに査定を依頼する
相続が発生した場合、不動産の査定はできるだけ早く依頼することが重要です。相続税の申告期限は原則として相続開始から10か月以内と定められており、不動産の正確な評価額を把握しなければ、納税資金の準備や遺産分割協議を進めることができません。
特に不動産は現金のように分けにくく、相続人間での取り扱いを巡って対立が生じやすいため、客観的な査定額を早期に確認しておくことが円滑な話し合いに直結します。さらに、相場は景気や地域の開発状況によって変動するため、適切なタイミングでの査定が将来的な売却や資産管理の判断にも役立ちます。
ローンが残っている場合は査定額から残債が差し引かれる
相続した不動産に住宅ローンが残っている場合、その残債は査定額から差し引いて考える必要があります。たとえば査定額が3,000万円でも、ローン残高が2,500万円あれば、実質的な資産価値は500万円にとどまります。もし残債が査定額を上回る「オーバーローン」の状態であれば、不動産を売却しても借金が残るため、自己資金で補填するか、相続放棄や任意売却を検討しなければなりません。
ただし、被相続人が団体信用生命保険に加入していた場合は、死亡時にローンが完済されるケースもあり、その場合には純粋な資産として相続可能です。
相続登記が完了していないと相続不動産を売却できない
相続した不動産を売却するには、まず相続登記の完了が前提となります。登記名義が被相続人のままでは、亡くなった人が売主と認められず、売買契約自体が法的に成立しません。さらに、相続登記は2024年から義務化され、期限を越えて未実施の場合、過料(10万円以下)が科される可能性があります。
登記手続きには戸籍の収集や遺産分割協議書の作成が必要で、複雑なケースでは時間を要することもあるため、早めの対応が重要です。
不動産を遺産分割する4つの方法
不動産は現金のように容易に分けられないため、相続人が複数いる場合には、どのように分割するかを事前に合意することが欠かせません。遺産分割の方法には大きく分けて下記の4つの選択肢があり、それぞれに利点と注意点があります。
- 現物分割
- 代償分割
- 換価分割
- 共有分割
現物分割
現物分割とは、相続財産をそのままの形で相続人同士で分ける方法を指します。不動産の場合は、建物は物理的に分けられないので、土地を物理的に分筆して各相続人が所有する形をとるのが一般的です。たとえば広い宅地を相続人ごとに区画を分けて登記するなどが該当します。
ただし、土地の形状や立地によっては分割が難しく、分割後の利用価値が低下したり、不公平感が生じる恐れもあります。建物についても同様で、複数人で1つの建物を現物分割するのは現実的に困難です。そのため、現物分割を行う際には、測量や登記など専門的な手続きが必要となり、費用負担も発生します。公平性や利用価値を確保するには、他の分割方法と比較検討したうえで選択することが望ましいといえます。
代償分割
代償分割とは、不動産を特定の相続人が単独で取得し、その代わりに他の相続人へ金銭などで補償を行う方法です。たとえば自宅を同居していた相続人が引き継ぎ、他の相続人には相応の金銭を支払うといった形が典型です。不動産は分けにくい資産であるため、代償分割を利用することで現物をそのまま維持しつつ、相続人間の公平性を保つことができます。
ただし、代償金を支払う側にはまとまった資金が必要であり、資金調達が難しい場合は実行が困難となる点が課題です。また、公平な補償額を決めるためには不動産の正確な査定が不可欠です。適切な評価をもとに合意を形成することで、相続人間の紛争を避け、円滑な遺産分割を実現することが可能となります。
換価分割
換価分割とは、不動産を売却し、その売却代金を相続人同士で分配する方法です。不動産は現金のように分けられないため、公平性を確保する手段として選ばれるケースが多く、特に相続人が複数いて利用目的が異なる場合に有効です。売却によって現金化されることで、相続税の納税資金を確保しやすい点も大きな利点です。
ただし、売却には一定の時間がかかり、市場の状況によっては希望額で売却できないリスクもあります。また、売却方法や分配割合を事前に合意しておかないと、相続人間で対立が生じる可能性もあるため注意が必要です。円滑な実行のためには、不動産の正確な査定を行い、分配基準を明確に定めたうえで手続きを進めることが望ましいでしょう。
共有分割
共有分割とは、不動産を複数の相続人が持分割合に応じて共有する方法です。現物を分割せずにそのまま維持できるため、売却したくない場合や特定の相続人が単独で取得できない場合の選択肢となります。しかし、共有状態では売却や大規模な修繕、建替えといった重要な判断には共有者全員の同意が必要となり、意思決定が難航するリスクがあります。また、使用方法や管理方針をめぐり相続人同士でトラブルが生じやすい点も注意が必要です。
将来的に売却や処分を検討する場合には、事前に利用方法や維持費の負担割合について取り決めをしておくことが望ましいでしょう。共有分割は一時的な解決策として有効ですが、長期的には管理上の課題を抱える可能性が高いため、他の方法と比較しながら慎重に検討する必要があります。
まとめ
相続不動産は分割が難しい資産であり、感情的な対立を招きやすい点が特徴です。まずは早い段階で査定を行い、客観的な価値を把握することが出発点となります。
そのうえで、相続人同士の話し合いは「公平性」と「将来の管理負担」を軸に進めることが肝要です。とくに売却や分割の方法を巡る協議では、専門家を交えて透明性を確保することで、無用な紛争を避けられます。
FAQ
不動産の相続が発生してから相続税の申告・納税までの流れを教えてください
相続開始後は、まず遺言書の有無を確認し、相続人と相続財産を確定します。その後、不動産会社や不動産鑑定士に依頼して資産価値を把握し、査定結果をもとに相続人全員で遺産分割協議を行います。分割方法が決まったら法務局で相続登記を行い、最終的に相続税の申告・納税を進めるのが一般的な流れです。相続税の申告期限は相続開始から10か月以内と定められているため、早めに手続きを進めることが重要です。
不動産を相続する際に課される税金を教えてください
相続不動産には、状況に応じて次の税金が発生します。まず、相続財産全体に対して相続税が課されます。相続登記を行う際には登録免許税が必要です。取得後は毎年の維持費として固定資産税(および都市計画税)が発生します。さらに、不動産を売却した場合には、その譲渡益に対して譲渡所得税が課されます。どの税金が該当するかは、相続後の利用や売却の有無によって異なるため、早めに確認しておくことが大切です。
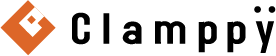


コメント