共有名義不動産における固定資産税は、共有者全員に連帯で支払い義務がありますが、実際に納税の手続きを行うのは代表者1人だけです。
つまり、代表者は他の共有者からその分の支払いを集めて、まとめて納付をすることになります。
そのため、代表者を誰にするのかを決める必要がありますが、その基準は購入時と相続時とで異なります。
たとえば、不動産を共有名義で購入した場合は、自治体の基準に沿って選出されます。
代表者の決定基準は自治体によって異なりますが、基本的には次のような要素を考慮して決定されることが多いです。
- 持分割合が多い
- その不動産に実際に住んでいる
- 登記簿の記載順位が早い
- その自治体に住民登録している
つまり、自治体から見て「固定資産税を確実に回収できる人物」が代表者として選ばれる傾向にあります。
一方で、不動産を共有名義で相続した場合は、相続人同士の話し合いによって代表者を決めるのが基本です。たとえば、親の土地を兄弟3人で相続したケースが典型です。
この場合、代表者の決め方に法的なルールはありませんが、共有持分割合や実際にその土地に住んでいるかどうかを考慮するのが公平でしょう。
ちなみに、もし固定資産税を支払わない共有者がいたとしても、滞納すると下記のようなリスクがあるため、代わりに立て替えてでも期限内に支払わなければなりません。
- 延滞税や督促状が発生する恐れがある
- 共有者全員の財産が差し押さえの対象になる
そして、立て替えた分については、支払わなかった共有者に後から請求することができます。この権利を「求償権」と呼び、口頭での請求に応じなければ法的措置をとることも可能です。どうしても回収できない場合には、その共有者の持分を強制的に買い取る方法もありますが、いずれも経済的な負担を伴います。
固定資産税自体が負担になっている場合や、共有名義の不動産を手放したい場合は売却する選択肢もあります。しかし、共有名義の不動産は権利が複雑に絡んでおり、購入しても自由に使えないことから、一般の人が買主になることはまずありません。
そのため、専門の買取業者に依頼するのがおすすめです。専門の買取業者であれば、訳あり物件でも収益化できるノウハウがあるため、買主が見つからなかったり他の共有者との関係が良くなかったりする場合でも積極的に買取相談に応じています。
手放したいものの、売却先が見つからない場合は、専門の買取業者への売却も検討してみてください。
共有名義不動産の固定資産税における基本ルール
共有名義の不動産の固定資産税の支払を考える時に、押えておくべき基本的なルールは次の2つです。
- 固定資産税の支払い義務は共有者全員にある
- 負担割合は原則「持分割合」に応じて決まる
知らなかったとはいえ、納税を怠ると罰則が課される恐れもあるため、まずは共有名義の不動産における基本的な固定資産税の支払方法を理解しておきましょう。
固定資産税の支払い義務は共有者全員にある
共有名義の不動産において、固定資産税の支払義務は共有者全員に生じますが、納付書は代表者宛てで届くのが一般的です。納税者の名前は1人しか記載されていなくとも、実際には共有者全員で支払わなければなりません。
これは、地方税法第10条の2第1項に基づいており、共有名義の不動産の固定資産税は、共有者全員が連帯して支払う旨が定められています。
共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。
引用:e-Gov 法令検索
連帯とは、全員が協力して全額を納めるということです。つまり、共有者のうちの誰かが固定資産税を支払わなかった場合は、他の誰かがその不足分を肩代わりすることになります。これが元で、トラブルが発生するケースは非常に多いです。
実際に、「固定資産税を支払わない共有者が原因で負担が大きくなったため不動産を手放したい」という相談を受けた事例もございます。
負担割合は原則「持分割合」に応じて決まる
共有名義の不動産の固定資産税は、「持分割合」に応じて支払う金額が決まるのが原則です。このルールの根拠は、民法第253条第1項に記されています。
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
引用:e-Gov 法令検索
つまり、固定資産税は共有者全員が同じ金額ずつ支払うとは限らず、多めに納税する人もいれば、納税額が小さい人もいます。
例えば、固定資産税12万円の不動産をA・B・Cの3人で、次のような持分割合で共有していると仮定しましょう。
| 【固定資産税12万円】 | 持分割合 | 納税額 |
|---|---|---|
| A | 3/6 | 6万円 |
| B | 2/6 | 4万円 |
| C | 1/6 | 2万円 |
Aの持分割合が最も大きいため納税額も一番大きく、持分割合の小さいCは納税額も小さくなります。しかし、前述したように誰かが納税を怠った場合、他の共有者がその不足分を負担しなければなりません。
例えば、Aが支払わなかった場合、持分が少ないBとCがその分を負担することになります。このように、本来の価値よりも多くの金額を払わざるを得ないケースもあるのです。
共有名義不動産の固定資産税は代表者が全員分を納める
前述のとおり、共有名義不動産の固定資産税は全員で支払いますが、実際に自治体に納めるのは代表者1人です。そのため、代表者は他の共有者からお金を回収し、まとめて納税しなければなりません。
基本的には固定資産税納付書に記されている人物が代表者にあたります。なお、代表者の決め方は購入時と相続時で異なるため注意しておきましょう。
代表者の決め方は「購入時」と「相続時」で異なる
代表者の決め方は、タイミングによって次のように決定の仕方が異なります。
- 購入時:自治体の基準に則り決められる
- 相続時:相続人で話し合って決める
それぞれの内容をみていきましょう。
購入時:自治体の基準に則り決められる
共有名義の不動産を新しく購入した場合は、原則として自治体の基準で代表者が決定されます。例えば、兄弟3人でお金を出し合って1つの土地を購入した場合が該当します。
代表者の決定基準は自治体によって異なるものの、次のような要素を考慮して決定されることが多いです。
- 持分割合が多い
- その不動産に実際に住んでいる
- 登記簿の記載順位が早い
- その自治体に住民登録している
基本的には、自治体から見て、最も固定資産税を回収できる可能性が高い人物が代表者に決定されます。なお、自治体が決定した代表者は課税台帳に記載されているため、確認したい場合は役所などで開示を請求しましょう。
相続時:相続人で話し合って決める
不動産を共有名義で相続した場合は、相続人で話し合って代表者を決めるのが一般的です。例えば、親の土地を兄弟3人で相続した場合が当てはまります。
代表者の決め方にルールはありませんが、共有持分割合や居住の有無を考慮するのが公平でしょう。相続によって代表者を決めた場合は、原則として自治体に「相続人代表者指定届」を提出しなければなりません。
相続人代表者指定届とは、その共有名義不動産の代表者が誰であるかを自治体に登録するための書類です。不動産を共有名義で相続した場合は、市区町村から法定相続人に送付されます。
相続人代表者指定届を提出すると、それ以降は固定資産税納付書がその代表者宛に届くようになり、納付も代表者が行います。なお、相続人代表者指定届の提出義務はありませんが、提出しない場合は自治体が独自の基準で法定相続人の中から代表者を選別・決定します。
このとき、相続放棄をした人も代表者の選択肢に入ります。ここで相続放棄した人が選ばれると、相続分がないにもかかわらず、毎年固定資産税の納付手続きを求められるリスクがあるのです。
こういったトラブルを無くすためにも、共有名義の不動産を相続した場合は、相続人代表者指定届を提出して代表者を明確にしておく必要があります。
代表者が変わる場合は自治体への届出が必要
自治体に届け出をすれば、代表者を途中で変更することも可能です。
届け出書類の名前は「共有資産代表者変更届」「共有名義の固定資産にかかる納税義務代表者(設定・変更)申請書」など自治体によって異なります。まずは役所に相談してみましょう。
共有名義不動産の固定資産税の計算方法
不動産の固定資産税は、数十万円に上ることもあります。なお、納付時期は自治体によって異なりますが、一般的には5月・7月・12月・翌年2月の年4期に分けて納税します。
特に、代表者以外には納付書が届かないため、いつまでにどれくらいのお金が必要なのかを知りたいと思う人も多いでしょう。固定資産税は、次の3ステップで計算できます。
- 土地の固定資産税額を計算する
- 建物の固定資産税額を計算する
- 土地と建物の固定資産税額を持分割合で按分する
ステップごとの計算方法をみていきましょう。
Step1.土地の固定資産税額を計算する
固定資産税は、土地と建物に分けて計算します。まずは土地の固定資産税額を計算しましょう。土地に課される固定資産税は、次の計算式で求められます。
土地に課される固定資産税=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)
固定資産税評価額=固定資産税路線価×土地面積×評点
「固定資産税評価額」とは、固定資産税や都市計画税といった課税の基準となる数字で、毎年5月に送られてくる固定資産税納付書に記載されています。固定資産税納付書が手元にない場合は、国土交通省が発表している路線価を調べれば算出可能です。
路線価とは道路に面している宅地の1㎡あたりの価額のことで、「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」を見ると、土地ごとの固定資産税路線価が分かります。そのうえで土地面積と評点をかけて、固定資産税評価額を算出しましょう。
なお、住宅が建っている土地は、以下の特例が適用される場合があります。
| 住宅用地の面積 | 軽減率 | 固定資産税額の算出式 |
|---|---|---|
| 200㎡までの部分(小規模住宅用地) | 1/6 | 固定資産税評価額×1/6×1.4% |
| 200㎡超の部分(一般住宅用地) | 1/3 | 固定資産税評価額×1/3×1.4% |
それでは、下記条件の固定資産税を求めてみましょう。
- 土地面積100㎡
- 路線価1㎡あたり40万円
- 小規模住宅用地
固定資産税評価額=路線価1㎡あたり40万円×土地面積100㎡×評点1=4,000万円
土地に課される固定資産税=固定資産税評価額4,000万円×1.4%=56万円
小規模住宅用地の特例の適用=56万円×1/6=9.3万円
このように、土地分の固定資産税額は9.3万円となります。
Step2.建物の固定資産税額を計算する
建物の固定資産税額は、土地と同様に「固定資産税評価額×1.4%」で求められます。しかし、固定資産税評価額は「再建築費評点数」や「経年減点補正率」などを用いる必要があるため、土地よりも複雑な計算が必要です。
再建築費評点数とは、その家屋と同じ建物を現在新築した場合にかかる建築費を点数で表したものです。ここから、建物の経年劣化分の減価(経年減点補正率)を考慮し、固定資産税評価額を求めていきます。計算方法は下記の通りです。
建物の固定資産税評価額=評点数×評点1点あたりの価額
評価点数と評点1点あたりの価額は下記の計算方法で求めます。
| 評点数 | 再建築費評点数×損耗状況による減点補正率 |
|---|---|
| 評点1点あたりの価額 | 1円×物価水準による補正率×設計管理費等による補正率 |
なお、減点補正率などは自治体や建物の状況によって異なるため、不動産の知識がない人が建物の固定資産税額を計算するのは現実的ではありません。代わりに、以下のような簡易の計算式で固定資産税額の概算を求められます。
建物の固定資産税評価額の概算=購入したときの50~70%
例えば、「3,000万円で購入した家屋」の固定資産税額を求めてみましょう。
建物の固定資産税評価額の概算=3,000万円×50~70%=1,500~2,100万円
建物の固定資産税額=固定資産税評価額1,500~2,100万円×1.4%=21~29.4万円
このように、建物分の固定資産税額は21~29.4万円となります。
Step3.土地と建物の固定資産税額を持分割合で按分する
最後に、土地分と建物分の固定資産税額を合算して、共有者それぞれの持分割合で按分します。前述の例を取り、Aが3/6・Bが2/6・Cが1/6ずつの持分割合と仮定しましょう。
- 土地と建物の固定資産税額=9.3万円+21~29.4万円=30.3~38.7万円
- Aの負担額=15.15~19.35万円
- Bの負担額=10.1~12.9万円
- Cの負担額=5.05~6.45万円
それぞれの納税額は上記のようになります。
共有名義不動産の固定資産税の負担を減らす方法
不動産の固定資産税は、共有者全員で按分したとしても、1人当たりの金銭的負担が想定外に大きくなるケースも珍しくありません。少しでも固定資産税の負担を減らしたい場合は、次のような特例や非課税措置・減額措置が適用できないかチェックしてみましょう。
- 住宅用地の特例を利用する
- 「公共の用に供する道路」の非課税措置を利用する
- 新築住宅に係る固定資産税の減額措置
それぞれの内容をみていきましょう。
住宅用地の特例を利用する
固定資産税額の軽減に役立つのが、先にも述べた「住宅用地の特例」です。これは、居住を目的として所有している土地の税額を軽減することを目的にした特例措置です。
住宅用地の特例では、住宅用地の面積が200㎡を超える部分・超えない部分で軽減措置が異なります。なお、固定資産税額だけでなく、都市計画税額も減税されるため、あわせてチェックしてみてください。
| 住宅用地の面積 | 固定資産税額 | 都市計画税額 |
|---|---|---|
| 200㎡までの部分(小規模住宅用地) | 固定資産税評価額×1/6×1.4% | 固定資産税評価額×1/3×0.3% |
| 200㎡超の部分(一般住宅用地) | 固定資産税評価額×1/3×1.4% | 固定資産税評価額×2/3×0.3% |
「公共の用に供する道路」の非課税措置を利用する
「公共の用に供する道路」の非課税措置とは、敷地内にある私道が公共に役立つと判断される場合に、非課税となる措置です。
例えば、国道・県道・市町村道といった、いわゆる「公道」は、「人的非課税」といって固定資産税は課税されません。これに対して、私道は敷地内にある私的な道路であるため、固定資産税の対象です。
しかし、一個人の敷地内にある私道であっても公共性が高いと判断されると、公道に似た扱いとなり、固定資産税が優遇されることがあります。地方税法第348条2項5号が根拠です。
地方税法第348条2項
固定資産税は、次に掲げる固定資産に対しては課することができない。ただし、固定資産を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる固定資産として使用する場合には、当該固定資産の所有者に課することができる5号
公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地
引用:e-Gov 法令検索
対象となるのは、簡単にいえば不特定多数の人が簡単に利用できる私道です。例えば、次のような私道が適用の対象とされています。
| 不特定多数が自由に利用できること | ‐ |
|---|---|
| 通り抜け私道 | 私道の起点・終点が公道に接している 幅員1.8m以上 |
| 行止り私道 | 2以上の家屋で利用できる 幅員4m以上 |
| コの字型私道 | 2以上の家屋の用に利用できる 幅員4m以上 |
| セットバック部分(セットバック:敷地を後退させて道路幅4m以上を確保すること) | 建築基準法道路の拡幅(私道)部分 |
なお、「公共の用に供する道路」の非課税措置を利用する場合は、市区町村に申告する必要があり、上記に加えて次のような条件を満たす必要があります。
- 登記上分筆され位置が特定されている
- 客観的に道路として認定できる
- アパート・マンション・貸家・駐車場等における敷地内の道路ではない
- 建築敷地として含まれていない
- 賃料、通行料を徴収していない
新築住宅に係る固定資産税の減額措置
新築住宅の場合は、「新築住宅に係る固定資産税の減額措置」を適用して、建物分の固定資産税を減額できる可能性があります。
新築住宅の固定資産税の減額措置は、本来、令和6年3月31日までが適用期間でしたが、令和6年度の税制改正に伴って、適用期間が令和8年3月31日まで延長されています。つまり、令和8年3月31日までに新築された建物であれば、この減額措置を利用できる可能性があるのです。
新築住宅に係る固定資産税の減額措置は、不動産の種類・状態によって内容が変わり、1戸あたり120㎡相当分までが限度とされています。
| 種類 | 種別 | 条件 | 建物の固定資産税 の減額割合 | 減額期間 |
|---|---|---|---|---|
| 一般住宅 | 新築一戸建て 新築マンション | 床面積が50㎡以上280㎡以下(一戸建て以外の賃賃貸住宅は40㎡以上) 併用住宅の場合、居住部分の床面積が2分の1以上 | 1/2 | 3年間 |
| 3階建以上の耐火・準耐火建築物 | 3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間 | |||
| 長期優良住宅 | 新築一戸建て | 5年間 | ||
| 新築マンション | 7年間 |
国土交通省は、長期優良住宅について、「長期にわたり良好な状態で使用するための措置講じられた優良な住宅」と定義づけています。
不動産が長期優良住宅であるかを確認するには、「長期優良住宅建築等計画認定通知書」または「住宅性能評価書」をチェックしてみましょう。
参考:長期優良住宅|国土交通省
不動産の評価額が本当に正しいかもチェック!
固定資産税の計算は「固定資産の評価額×標準税率1.4%」で行われますが、土地の評価額が間違っていることもあります。特に、先祖代々引き継いできた土地などでは、実際の面積と登記簿の面積が異なり、過剰に課税されている場合もあります。
正確な測量を行うことで、税額が減少する可能性がありますが、逆に増えることもあるので注意が必要です。
共有名義不動産の固定資産税を払わない共有者がいる場合の対処法
共有名義不動産の固定資産税は、共有者全員に支払義務がありますが、なかには支払を拒否したり、忘れたりする共有者もいるでしょう。固定資産税を滞納すると後述のリスクを負うことから、次のような方法を取ることが一般的です。
- 一旦立て替えたあとに本人に直接請求する
- それでも拒否される場合は「強制的な持分買取」も検討する
納税が遅れて滞納となるとさまざまなリスクがあるため、基本的には、納税を優先することが重要です。滞納した場合のリスクについてはこちらで解説しています。
一旦立て替えたあとに本人に直接請求する
固定資産税の滞納にはペナルティが課されるため、共有者から回収できない場合は、まずは他の共有者が立て替え、自治体への納税を優先させるのがベストです。立て替えの割合などについては、他の共有者が話し合って決めてかまいません。
その後、固定資産税を支払わなかった共有者に対し、持分割合に応じた請求を行いましょう。請求方法も任意ですが、基本的には口頭で請求するのが一般的です。これを拒否された場合は、法的手続きによって「求償権」を行使する方法があります。
求償権とは、他者の債務を立て替えた際にその立替分の返還を求める権利です。なお、口頭での請求も求償権の行使にあたります。それでも拒否された場合は、次のような段階を踏みながら圧力を強めていきましょう。
- 内容証明で請求
- 支払督促
- 訴訟
- 強制執行
支払督促以降のステップは、裁判所への申し立てが必要です。細かな法的ルールがあるため、まずは弁護士に相談してみると良いでしょう。
なお、求償権には5年の時効があります。原則として、固定資産税を立て替えたときから5年を経過すると、返済を請求できなくなるため、共有者の固定資産税を立て替えたときは早めに請求を行いましょう。
それでも拒否される場合は「強制的な持分買取」も検討する
それでも立替分の返済を拒否される場合は、裁判所に申し立てて強制的な持分買取りを検討するのも選択肢の1つです。固定資産税を支払わない共有者の持分を他の共有者が購入することで、共有関係を解消します。
強制的な持分買取りは、民法第253条2項によって認められています。
民法第253条
各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う
2項
共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる
引用:e-Gov 法令検索
例えば、その人の経済力が低く、立替分の返済を見込めそうにない場合などに有効な方法です。買取にあたるので、当然ながらその共有者には買取代金を支払う必要があります。
また、持分の買取は手続きが複雑なため、弁護士に依頼するのが一般的です。その分の報酬も発生する点に留意しましょう。
ややコストはかかりますが、固定資産税は毎年納税するため、翌年以降のトラブルを減らせるという点でメリットのある方法です。
共有名義不動産の固定資産税を滞納するリスク
共有名溥儀不動産の固定資産税を滞納すると、次のようなペナルティの恐れがあります。
- 延滞税や督促状が発生する恐れがある
- 共有者全員の財産が差し押さえの対象になる
このようなリスクを回避するためにも、共有者全員から回収できない場合は誰かが一旦立て替えて納税することが望ましいです。各ペナルティの内容をみていきましょう。
延滞税や督促状が発生する恐れがある
固定資産税を滞納した場合は、延滞税を課されたり、督促状が届いたりする恐れがあります。固定資産税の延滞税は、滞納期間によって変動します。
| 延滞日数 | 延滞金の税率 |
|---|---|
| 納付期限の翌日から1か月以内 | 年率2.4% |
| 1か月以上 | 年率8.7% |
例えば、令和6年5月31日期限の固定資産税5万円を同年10月31日に納付した場合は、次のような延滞税がかかります。
【令和6年5月31日期限の固定資産税5万円を延滞】
令和6年6月1日~30日までの延滞税:5万円×2.4%×30日÷365日=98.6円
令和6年7月1日~10月31日までの延滞税:5万円×8.7%×123日÷365日=1,465.8円
合計の延滞税:98.6円+1,465.8円=1,564.4円
合計の延滞税は1,564.4円となります。固定資産税の本体額に比べると少額のため、気にしない人もいるかもしれません。しかし、地方税法第329条を根拠として、不動産の固定資産税を滞納した場合は、原則として納付期限後20日以内に自治体が督促状を送付します。
加えて地方税法第331条1項では、督促状を送付した日から10日を経過しても完納されなかった場合に、滞納者の財産を差し押さえる旨を定めています。
| 地方税法第329条 | 納税者(特別徴収の方法によつて市町村民税を徴収される納税者を除く。以下本款において同様とする。)又は特別徴収義務者が納期限(第三百二十一条の十一又は第三百二十八条の九の規定による更正又は決定があつた場合においては、不足税額又は不足金額の納期限をいい、納期限の延長があつたときは、その延長された納期限とする。以下市町村民税について同様とする。)までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては、市町村の徴税吏員は、納期限後二十日以内に、督促状を発しなければならない。但し、繰上徴収をする場合においては、この限りでない。 |
|---|---|
| 地方税法第331条 | 市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない |
| 1項 | 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき |
つまり、共有者の代表者が督促状を受け取ってから10日以内に固定資産税を支払わない場合は、財産が差し押さえられる可能性があるのです。
共有者全員の財産が差し押さえの対象になる
前述のとおり、自治体が督促状を送付してから10日内に固定資産税が完納されない場合は、差し押さえされるリスクがありますが、このときは共有者全員が差し押さえの対象になります。
固定資産税の滞納による差し押さえでは、土地や家屋が差し押さえられることが多いです。つまり、居住目的で使っていた共有者がいる場合、その人は自宅に住み続けられなくなります。あるいは、預貯金や給与といった金銭が差し押さえられることもあります。
いずれにしろ、代表者・共有者本人だけでなく、その家族の日常生活にも支障をきたす恐れが高いです。このような事態を避けるためにも、固定資産税は期限までに納付しましょう。
なお、差し押さえが執行されるまでには、財務調査のほか、電話・文書・訪問などによる納税の催告が複数回行われるのが一般的です。つまり、実際に財産を差し押さえられるまでに10日以上かかることもあります。
とはいえ、督促状の送付から10日を経過すると、自治体はいつでも差し押さえできる状態になるのは事実です。したがって、代表者は督促状を受け取ったらその時点で完納することが望ましいといえます。
共有者から持分の固定資産税が支払われない場合は、他の共有者と相談したうえで一旦立て替えてから、後ほど本人に求償権を行使しましょう。
共有名義不動産の固定資産税を払いたくない場合は「共有持分の売却」も検討する
不動産の共有関係を解消すれば、毎年の固定資産税の支払いに煩わされることがなくなります。そのため、共有名義不動産の固定資産税を支払いたくない場合は、自身の共有持分を手放すのも選択肢の1つです。
なお、前提として、共有名義の不動産を売却するには次のようなルールがあります。
| 共有名義不動産 | 条件 |
|---|---|
| 不動産を丸ごと売却 | 共有者全員の同意が必要 |
| 自身の持分のみを売却 | 自身の意志のみで可能 |
つまり、自身の持分のみであれば、他の共有者の同意は不要で、いつでも自由に売却可能です。ただし、持分のみの不動産を一般個人に売るのは難しいため、実質的に売却先は次の2つに絞られます。
- 他の共有者に売却する
- 買取業者などの第三者に売却する
それぞれの内容をみていきましょう。
他の共有者に売却する
共有名義の不動産は、共有者の許可がないと自由に活用したり、売却したりできません。多くの制約があることから、第三者が共有持分を購入することはほとんどない不動産です。
実際、仲介の立場で「一般の買主を探したい」という依頼を受けて販売活動を行ったものの、数か月経っても購入希望者が現れず、最終的には他の共有者への売却でまとまった事例もあります。
しかし、他の共有者が持分を買い取れば、自身の持分を増やせるため、より多くの権利を持つことになります。特に、過半数の持分を占める所有者となれば、賃貸に出すなどの管理行為も単独で行えるようになり、活用しやすくなります。
このように、他の共有者への売却はメリットが多く交渉がスムーズに成立しやすいため、共有持分を売る場合は他の共有者への相談から始めるのが基本です。
ただし、これは経済力があり、関係性も良好な場合に限られます。また、家族や親族であってもトラブルを避けるために、売買契約を結ぶ際には不動産会社や弁護士に間に入ってもらい、きちんと売買契約書を作成することを強くおすすめします。
買取業者などの第三者に売却する
他の共有者から買取を断られた場合は、不動産会社に買取を依頼する方法もあります。しかし、前述のように持分のみの不動産は活用がしにくいため、一般的な不動産会社は買取を敬遠する傾向があります。
一方、訳あり物件の買取に特化した専門業者であれば、共有名義の不動産も積極的な買取に応じています。実際に、他社で買い取りを断られたり、仲介で数か月活動しても買主が見つからなかったりしてご相談いただいたケースでも、数日で現金買取を実現した例があります。
他の共有者との調停や交渉まで代行しているケースも多いため、トラブルのリスクを軽減できるでしょう。
共有名義の不動産は活用がしにくいにも関わらず、固定資産税は毎年発生するため、所有し続けることがデメリットにしかならないという場合もあるでしょう。このような場合は、訳あり物件専門の買取業者への相談がおすすめです。
まとめ
共有名義の不動産の固定資産税は、共有者全員がそれぞれの持分割合に応じて納税しなければなりません。滞納した場合は、延滞税や差し押さえのリスクがあるため、もし共有者の1人が納税を拒否した場合は、他の共有者が一旦立て替えたうえで、拒否した人に立替分を直接請求しましょう。
なお、共有名義の不動産はたとえ所有者であっても活用がしにくく、一方で固定資産税は毎年発生します。税制上のデメリットが大きいと感じる場合は、訳あり物件の買取に特化した専門業者への売却がおすすめです。
よくある質問
- 固定資産税の代表者が死亡した場合はどうすればよいですか?
-
固定資産税の代表者が死亡した場合は、固定資産税の支払い義務は、相続人または継承者に引き継がれます。相続人が複数いる場合は、全員で納税義務を負わなけれなばなりません。
なお、相続人がいない場合は、民法255条を根拠にその持分は他の共有者に帰属します。つまり、他の共有者が継承者となって代わりに固定資産税を支払う必要があります。
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
引用:e-Gov 法令検索 - 固定資産税の代表者が行方不明になった場合はどうすればよいですか?
-
固定資産税の代表者が行方不明になった場合は、自治体に「共有資産代表者変更届」を届け出て、他の共有者が代表者になる方法があります。あるいは、管轄の家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てるのも選択肢の1つです。
固定資産税における不在者財産管理人とは、不在である代表者の財産から固定資産税を支払えるようにする措置です。なお、不在者の財産で納税できない場合は、申立人が不足分を肩代わりする必要があります。
- 共有持分を年途中で手放した場合は日割りで払いますか?
-
共有名義不動産を年途中で手放した場合、固定資産税は日割りで支払うのが一般的です。固定資産税は毎年1月1日時点の所有者に課される税金であるため、仮に年途中で持分を手放したとしても、1月1日からその日までの納税義務は残ります。
- 売却以外に共有持分を手放す方法はありますか?
-
売却以外に共有持分を手放す方法はあります。具体的には、「相続放棄」「共有持分の贈与・放棄」「土地の分筆」「共有物分割請求」などが一般的です。
- 共有持分を手放す方法は売却以外にもありますか?
-
共有持分を手放す方法は売却以外にも下記の方法はあります。
- 相続放棄
- 共有持分の贈与・放棄
- 土地の分筆
- 共有物分割請求
最も簡単な方法は相続放棄です。しかし、相続放棄を選ぶとすべての財産を放棄することになるほか、一度放棄の手続きをすると取り消しができません。そのため、よく考えて決めるのがおすすめです。
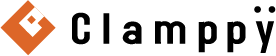



コメント