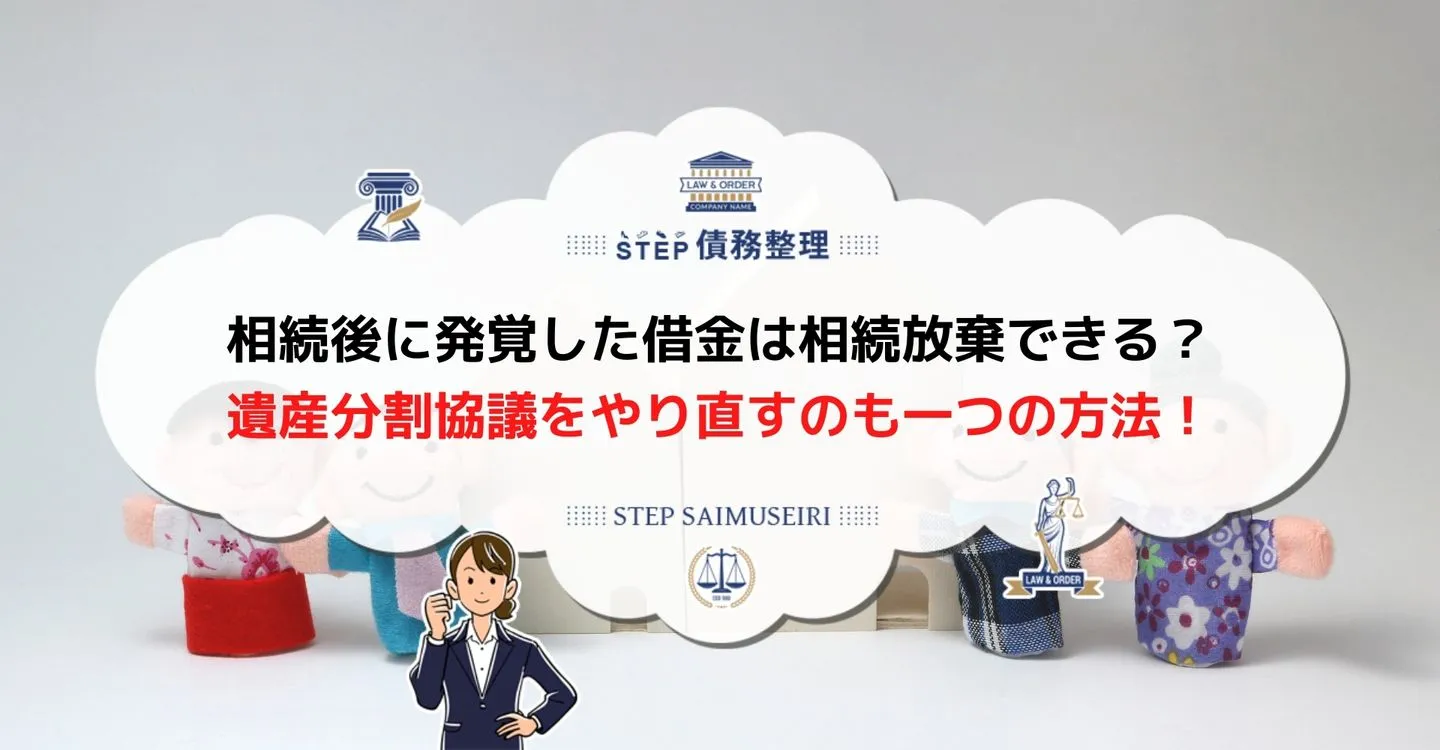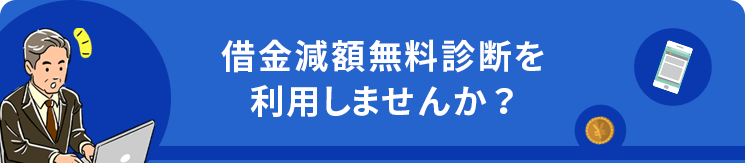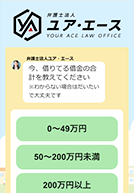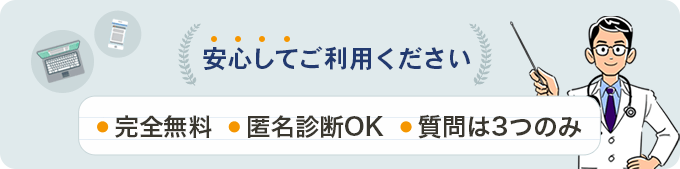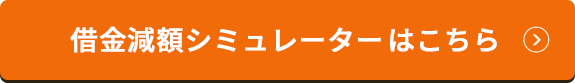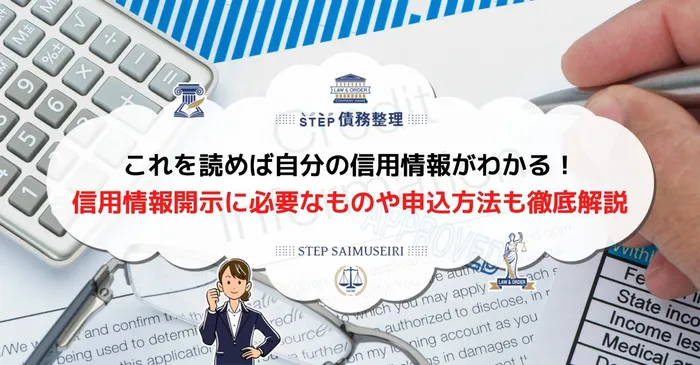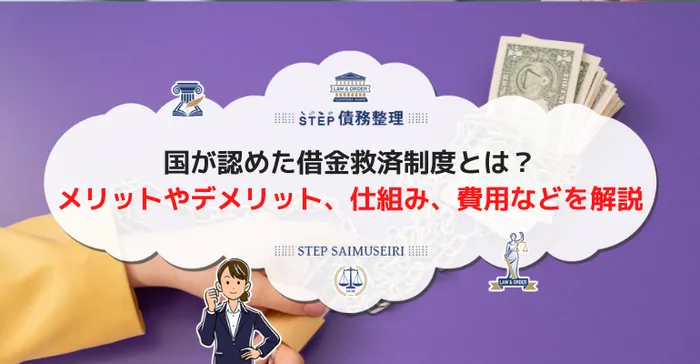相続した後で被相続人に借金があることがわかりました。すでに遺産分割協議は終わっているのですが、この借金はどうすればよいでしょうか?


遺産分割協議後に発覚した場合でも、借金の返済義務は相続人が引き継がなければいけません。相続人全員で遺産分割協議をやり直すか、相続放棄をする必要があるでしょう。
相続放棄って、相続した後でもできるんですか?


相続放棄の期限は「相続発生を知ってから3ヶ月以内」ですが、相続時に借金の存在を知らなければ、例外的に期限以降でも認められます。ただしケースによって判断が異なるので、弁護士に相談したほうがよいでしょう。
もし借金も払えないのに、相続放棄が認められない場合はどうすればよいですか?


まずは借金の時効が成立していないか確認して、成立していない場合は債務整理による借金の減額・帳消しをおすすめします。ただし、時効も債務整理も手続きには法的な知識が必須なので、やはり弁護士に相談するのがよいでしょう。
相続がようやく終わったと思ったら、後から被相続人に借金があったと発覚するケースは珍しくありません。
その場合、後から発覚した借金も相続人に引き継がれます。
例外的に相続後でも相続放棄できる可能性もありますが、遺産分割時に借金の存在を知らなかった事実を証明しなければならず、すべてのケースで相続放棄が認められるとは限りません。
これらの事実を自力で証明することはむずかしいため、相続後に相続放棄をしたい場合、基本的に弁護士へ相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
また、弁護士に相談すれば、相続放棄ができず借金の返済もむずかしい場合に「債務整理」という手続きで借金の減額・帳消しが可能です。
当サイトでは、全国対応&24時間無料相談できる法律事務所を紹介しているので、ぜひ気軽に相談してください。
- 被相続人の借金は後から発覚しても相続人が引き継ぐ
- 借金の相続は法定相続分にしたがって分割するか、遺産分割協議で配分を決める
- 相続時に借金の存在を知らなかった場合は、遺産分割協議のやり直しや相続放棄ができる
相続後に発覚した借金はどのように扱われる?
後から「被相続人の借金」が発覚した場合の対処方法を解説する前に、相続財産に借金が含まれている場合の取り扱いについて、基礎知識をおさらいしておきましょう。
基礎知識を把握しておかないと、後から「被相続人の借金」が発覚した場合に、どんな事柄が問題になるのか理解できません。
問題点が理解できなければ、適切な対処方法もわからず、具体的な行動を起こせないでしょう。
これから相続する人はもちろん、相続終了後に借金が発覚して困っている人にとっても重要なことなので、ぜひ参考にしてください。
後から発覚した借金も相続人に引き継がれる
被相続人に借金がある場合、借金の返済義務は相続人に引き継がれます。
相続前に借金の存在がわかっている場合はもちろん、相続後に借金が発覚した場合も同じです。
相続人が1人ならばその人が単独で、相続人が複数いれば共同で借金の返済義務を引き継ぎます。
「借金は相続放棄をしてプラスの財産のみ相続する」ということはできません。
それぞれの相続人の借金返済額は法定相続分で決まる
相続人が複数いる場合、財産の取り分と同様に借金の返済額も法定相続分にしたがって分けるのが基本です。
法定相続分とは、民法で定められた遺産分割の目安で、遺言によって取り分指定されていない場合、プラスの財産もマイナスの財産も法定相続分に沿って分配されることが多いです。
・配偶者:1/2
・子供A:1/4
・子供B:1/4
相続財産のなかに借金が500万円あるときは、配偶者が250万円、子供がそれぞれ125万円ずつ返済しなければいけません。
「遺産分割協議」で法定相続分とは違う相続配分にもできる
遺言による相続配分の指定がない場合、遺産分割協議によって法定相続分とは違う相続配分を取り決めることもできます。
つまり、被相続人の借金について、相続者間で話し合い「誰がいくら返済するか?」を決められます。
ただし、遺産分割協議を成立させるには、取り決めの内容に全員が合意しなければなりません。
とはいえ、相続人全員が顔を合わせて協議する必要はなく、書面による意思表示でも問題はありません。
債権者からの督促は法定相続分どおり請求されるため注意
遺産分割協議で法定相続分とは違う配分で相続しても、債権者との契約に反映されるわけではありません。
つまり、債権者は法定相続分に沿って各相続人に対して借金返済を請求できます。
わかりやすいように具体例で説明します。
債権者はA以外の相続人に対しても、法定相続分にもとづいた返済請求をできます。
返済請求をされた人はこれを拒否できません。
「それでは遺産分割協議で借金の配分を決める意味はないのか?」というと、そんなことはありません。
遺産分割協議で誰かが借金を引き受けると決めたのに他の人が借金を肩代わりした場合、その金額を借金を引き受けると決めた人へ請求できます。
この場合、Bは債権者の返済請求を断れません。
しかし、Aが借金をすべて引き受けると取り決めているので、Bは自分が債権者に支払った分を、Aに対して請求できます。
相続発生から3ヶ月以内なら借金ごと「相続放棄」できる
相続放棄とは、文字どおり自分の相続分をすべて放棄することです。
相続放棄には期限があり、相続の開始があったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所へ申告する必要があります。
民法915条1項
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
相続放棄の期限における「相続の開始があったことを知ったとき」とは、被相続人が亡くなったタイミングではありません。
例えば、被相続人が死亡してすぐにその事実を知らされず、数ヶ月後に相続権あったと知った場合は、相続があったと知った時点から3ヶ月以内が相続放棄の期限となります。
また条文にあるとおり、家庭裁判所への申し立てれば、相続放棄の期限を伸ばすこともできます。
ちなみに、相続放棄は「相続する権利そのもの」を放棄する手続きのため、一部の財産や借金だけを選択して放棄はできません。
「限定承認」で借金の相続額を減らすことが可能
限定承認とは、負債がプラスの財産を上回らないように相続する手続きで、相続できる借金が財産より多い場合に有効な方法です。
後から借金が発覚した場合も、相続で得られた財産で相殺できるため、結果的に損するのを防げますが、手続きには3ヶ月の期限があるため注意しましょう。
普通に相続すれば相続財産は400万円のマイナスですが、限定承認をすれば引き継ぐ借金の上限額がプラスの財産額と同じになるので、相続財産は差し引き0円となります。
「単純承認」が成立すると相続放棄も限定承認もできなくなる
相続放棄も限定承認もしない場合、借金もプラスの財産もまるごと相続する「単純承認」が成立します。
単純承認には特別な手続きや意思表示は不要であり、相続開始を知ってから3ヶ月が経過すると自動的に成立します。
単純承認が一度成立してしまうと、後から相続放棄や限定承認へ変更できないため注意しましょう。
また3ヶ月以内でも、次のような行為があると単純承認をしたとみなされます。
- 財産の処分(譲渡や抵当権設定、廃棄など)
- 民法第602条の期間を超える賃貸借契約
- 相続放棄や限定承認にあたって、わざと相続財産を隠したとき
- 相続放棄や限定承認にあたって、秘密裏に消費したとき
- 相続放棄や限定承認にあたって、意図的に財産を目録へ記載しなかったとき
相続した後で借金の存在を知ったときの対処法
先に解説したとおり、相続によって借金を背負う事態を防ぐには、相続発生を知ってから3ヶ月以内に「相続放棄」または「限定承認」をしなければなりません。
しかし、相続が終えてから被相続人に借金があったと発覚するケースも多く、すでに相続放棄や限定承認の期限が過ぎてしまっています。
こうした場合、借金を背負わないためには次のような対処法があります。
- 借金の存在を知らなかった場合は遺産分割協議をやり直す
- 相続から3ヶ月以上経っていても相続放棄できる可能性がある
- 借金の時効が成立していないか確認する
- 借金が正当なものか確認する
- 返済がむずかしいときは債務整理で「借金の減額や帳消し」を検討する
1つずつ具体的な方法や、注意点を見ていきましょう。
借金の存在を知らなかった場合は遺産分割協議をやり直す
遺産分割協議は相続人全員の同意があればやり直し可能で、新たに発覚した財産や借金の分け方のみを話し合うか、すべての遺産分割を白紙撤回にして最初から協議します。
ただし、相続人が遠方に住んでいる場合や相続人同士の仲が悪い場合、改めて遺産分割協議をすることがむずかしいケースも少なくありません。
そのため、最初の遺産分割協議の段階で「新しく財産や借金が発覚した場合どうするのか?」を取り決めておくのが一般的です。
そのような取り決めがない場合のみ、他共有者へ連絡して遺産分割協議のやり直しをおこないましょう。
贈与税や所得税が発生するケースもあるので注意
遺産分割協議のやり直し自体は相続人全員の同意があればできますが、税制上の取扱いではやり直しがききません。
遺産分割協議をやり直した場合、相続人間における財産の移動は、税制上では贈与や売却があったものとして取り扱われます。
相続税は最初の遺産分割時に納税していますが、これが返還されることもありません。
結果として、遺産分割協議をやり直すことで二重課税となってしまいます。
すでに売却or贈与した財産は戻せないので代償金が必要になる
例えば、最初の遺産分割協議で不動産を取得後、第三者へ譲渡した後に遺産分割のやり直しが発生したとします。
この場合、遺産分割協議のやり直しが発生したとしても、第三者との譲渡契約は取り消せません。
遺産分割協議をやり直しても分割する財産自体がありませんので、財産を譲渡した相続人は代わりに金銭で清算する必要があります。
例外的に相続後でも相続放棄できる可能性もある
後から被相続人の借金が発覚した場合「借金の存在を知っていれば相続放棄したのに・・・」と思う人もいるでしょう。
すでに解説したとおり、相続放棄は相続発生を知ってから3ヶ月以内に手続きしなければなりません。
しかし、相続時に借金の存在を知らなかった場合、例外として期限が過ぎていても相続放棄が認められるケースがあります。
ただし、遺産分割時に借金の存在を知らなかった事実を証明しなければならず、すべてのケースで相続放棄が認められるとは限りません。
これらの事実を自力で証明することはむずかしいため、相続後に相続放棄をしたい場合、基本的に弁護士へ相談してアドバイスを受けることをおすすめします。
借金の時効が成立していないか確認する
借金には時効が存在しており、一定条件を満たせば返済義務がなくなります。
相続した借金が5年もしくは10年以上前のものであれば、そもそも返済する必要がないかもしれません。
ただし、債権者と直接連絡を取ることで借金の時効が無効になってしまうケースもあります。
時効の成立している借金であっても、急いで自分から債権者へ連絡するのではなく、いったん弁護士に相談して、対応方法のアドバイスを受けるとよいでしょう。
時効が成立している借金の返済義務をなくす方法については、こちらの記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
本当に被相続人の借金であるか確認する
後から借金が発覚するということは「被相続人と債権者間でどんなやり取りがあったか?」といった借金の経緯が不明瞭なケースも多いでしょう。
そうした場合、債権者が嘘をついてお金をだまし取ろうとしている可能性も考えられます。
借用書の有無をはじめ、借用書の筆跡・印鑑などから「本当に被相続人の借金であるか?」をきちんと確認したほうがよいでしょう。
「被相続人の借金」の有無を調べる方法
被相続人に借金があったかどうか調べるには、どのような方法があるでしょうか?
銀行や貸金業者など企業からの借金であれば、信用情報機関に情報開示を請求すると借金の履歴がわかります。
相続人であれば、被相続人の信用情報も問い合わせできるので、こちらの記事を参考にして確認してみるとよいでしょう。
信用情報機関は3つあり、借入先の銀行や貸金業者によって加盟が違うため借金の有無を確実に調べたい場合は、すべての信用情報機関に問い合わせたほうがよいでしょう。
一方、個人間での貸し借りだと証拠としては借用書くらいしかありません。
とはいえ、すでに完済しているケースもあるので、銀行の口座履歴や領収書など、被相続人の書類関係を確認するとよいでしょう。
返済がむずかしいときは債務整理で借金の減額や帳消しを検討する
遺産分割協議のやり直しや相続放棄ができず、借金の返済もむずかしい場合は「債務整理」という手続きで借金の減額・帳消しを検討してみましょう。
債務整理には3つの方法があり、それぞれで減額できる借金の金額や条件が異なります。
| 任意整理 | 債権者と交渉して利息を減額してもらう | 元本は減らない |
|---|---|---|
| 自己破産 | 元本と利息の全額が免責される | 手持ちの財産はほとんど処分する必要がある |
| 個人再生 | 約50%〜90%も借金を減らせる | 財産の処分は必要だが、住宅など一部残せる財産がある |
それぞれの債務整理の仕組みや条件について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
「どの債務整理が自分には適しているか?」や「そもそも債務整理が必要なのか?」は自分で判断するのはむずかしいでしょう。
そうした場合、弁護士の無料相談を受ければ、あなたの事情に合わせたベストな方法をアドバイスしてもらえるので、一度相談してみるとよいでしょう。
まとめ
後から被相続人の借金が発覚した人へ向けて、相続に関する借金の基礎知識や対処法を解説しました。
被相続人に借金があった場合、相続放棄や限定承認をしなければ、相続人が借金を相続して返済しなければなりません。
後から被相続人の借金が発覚した場合、まずは遺産分割協議のやり直しをしましょう。
相続人同士で話し合って、新たに発覚した借金の分け方を決めたり、最初の遺産分割協議を白紙に戻すことも可能です。
もし相続した借金が払えない場合は「相続放棄や債務整理ができないか?」を弁護士に相談しましょう。
あなたの状況をヒアリングして、ベストな対処方法をアドバイスしてくれるはずです。