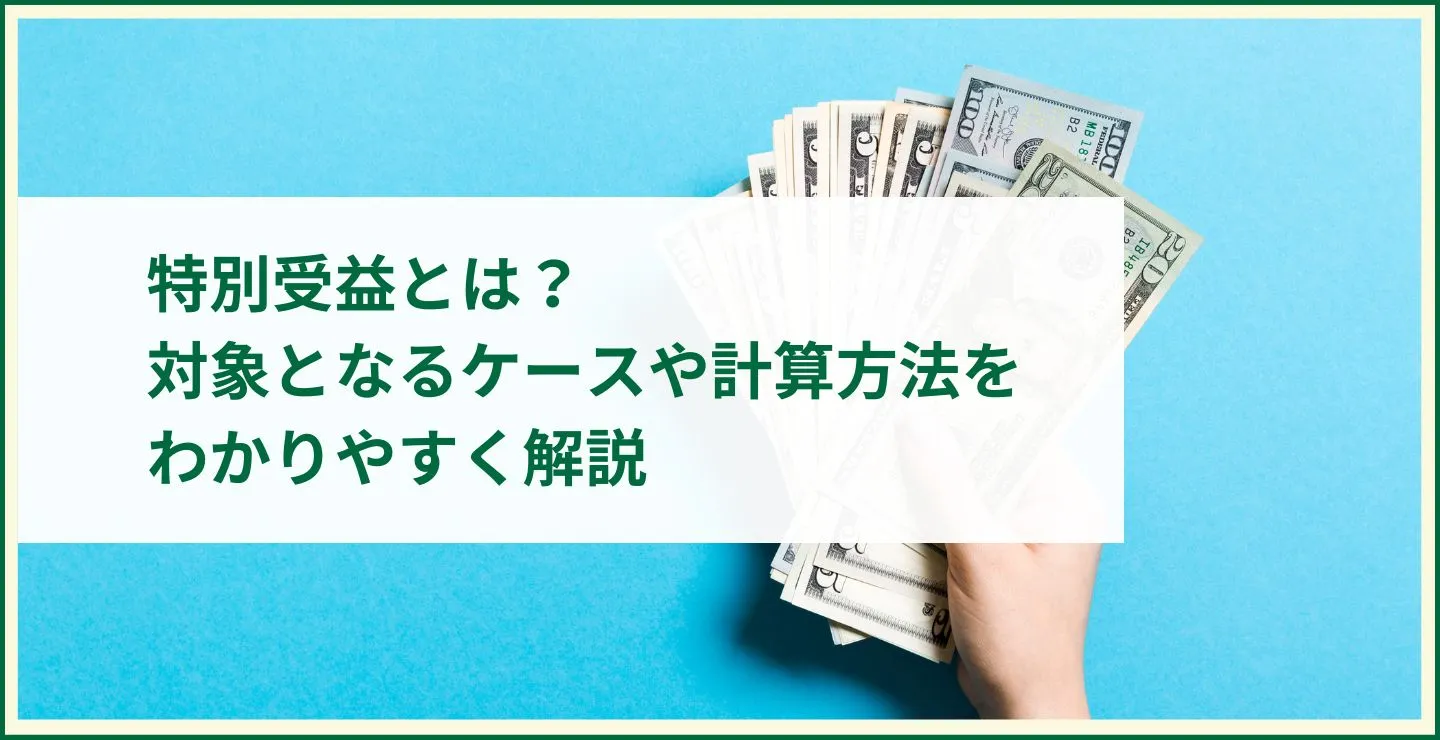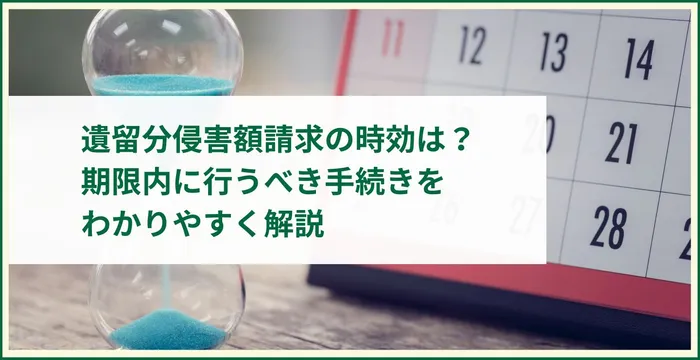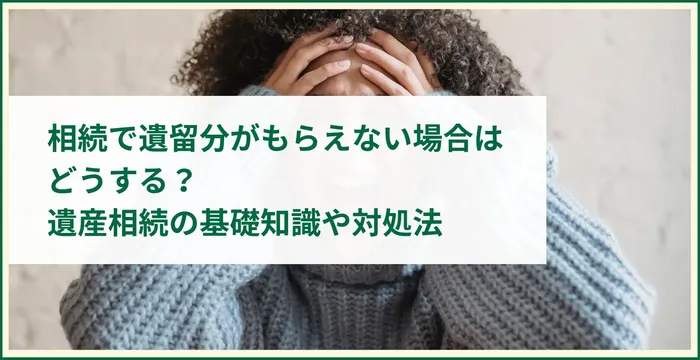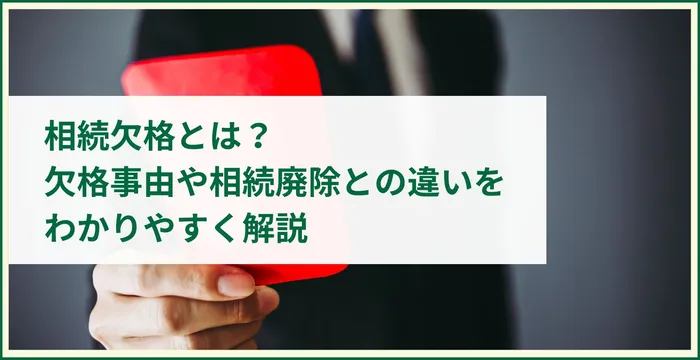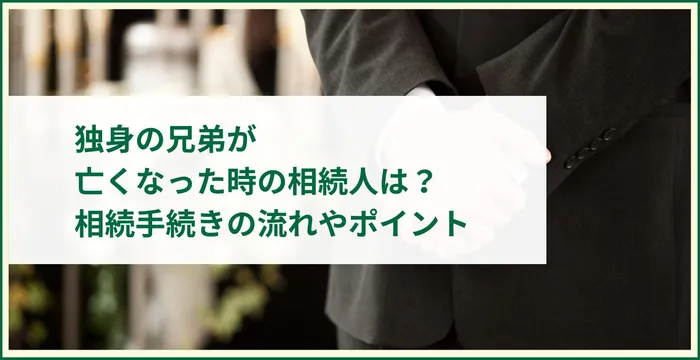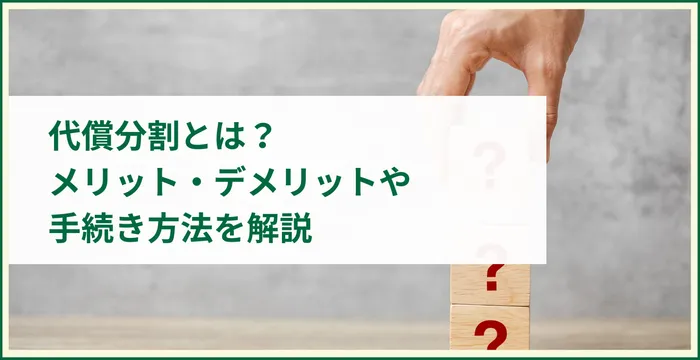特別受益とは被相続人の遺産を公平に分けるための制度
特別受益は、一部の相続人が被相続人から受けた利益のことを指します。対象となるのは、贈与・遺贈・死因贈与の3つです。
複数いる相続人のうち、誰か1人だけ生前に財産をもらっていた場合、それを考慮せずに遺産分割を行うと、他の相続人は「不公平だ!」と感じるでしょう。そこで、生前受け取っていた財産を特別受益として計算すると、相続人同士の不公平はなくなり、公平に遺産分割が行えます。
特別受益が認められれば持ち戻しが行われる
特別受益が認められれば、特別受益分は相続財産に合算されます。その後、すべての相続人同士で遺産分割を行い、特別受益分のあった相続人はその金額分を差し引いた額を受け取るのが一般的です。この方法を「持ち戻し」と呼びます。
持ち戻しの際には、原則として相続開始時の評価額が用いられます。
特別受益の対象となるのは原則として相続人のみ
特別受益の対象は、原則として相続人のみです。相続人以外の相手に対して生前贈与が行われていても、特別受益は認められません。
ただし、相続財産の多くの割合を占めるほど多額の贈与があった場合は、遺留分侵害額請求を行える可能性があります。また孫への援助・贈与なども特別受益として認められません。しかし孫の親である「子への特別受益」だとされるケースもあります。
さらに、推定相続人や相続人の配偶者も特別受益の対象とされる場合があります。
特別受益に該当するのは生前贈与・遺贈・死因贈与
特別受益に該当するのは、以下の3つです。
3つの特別受益を詳しく見ていきましょう。
- 生前贈与
被相続人が生前に行った贈与です。婚姻・養子縁組・生計の資本として受けた贈与のみを対象とします。
- 遺贈
遺言書で財産の贈与が指定されている相続のことです。原則として、すべてが特別受益の対象と認められます。
- 死因贈与
被相続人が生前に亡くなってから贈与することを約束していた贈与を指します。死因贈与の場合、原則としてすべてが特別受益の対象です。
特別受益の対象となるケース
特別受益の対象となるケースは、以下の6つです。
- 婚姻や養子縁組で発生した金銭
- 不動産や車の贈与、購入のための資金援助
- 被相続人が所有する土地・建物の無償利用
- 開業資金・運営資金の援助、事業資産の継承
- 学費の援助
- 扶養の範囲を超えた援助
1つずつ詳しく見ていきましょう。
婚姻や養子縁組の際に金銭を渡した
婚姻や養子縁組の際の金銭贈与は、特別受益とみなされます。
婚姻費用や養子縁組(持参金・結納金・支度金・挙式の費用など)に関しては、少額なら扶養義務範囲内とされています。多額な金銭のみを特別受益と認めるケースが多いです。
具体的な金額は定められていません。資産額や家庭の収入状況、他の相続人の関係などを含め、特別受益に該当するかどうかが判断されます。
不動産や車を贈与、購入するための資金を援助した
生計を共にしない子に対し、不動産の購入資金や不動産そのもの、車や車の購入資金を贈与・援助した場合です。その他、借地権の継承や借地権名義の変更も、特別受益とみなされます。
被相続人が所有する土地や建物を無償で利用させた
被相続人所有の土地や建物も、相続財産の一部です。被相続人の所有している家に、相続人を無償で住まわせている場合、相続人が無償で利用している場合は、特別受益とみなされます。
ただし、被相続人と相続人が同居している場合は、特別受益に該当しません。
事業の開業・運営資金を援助、事業資産を継承した
相続人が新たに事業を開業する際、開業や運営資金を援助した場合、特別受益に該当します。
被相続人の行っていた事業を、子に継承した際も特別受益とみなされます。
大学や大学院の学費を援助した
扶養範囲外の学費援助は、特別受益に該当します。どこまでが扶養範囲内か、判断する基準は家庭の収入や家柄、さらに社会環境によって左右されるため、判断が難しいところです。
近年は大学進学が一般的になっており、大学進学までの学費援助は特別受益の対象外とみなされるケースが増えています。
それ以上の大学院への進学や、海外留学にかかる費用など高いレベルの学費援助に関しては、特別受益に該当する可能性が高いです。
扶養の範囲を超える金銭を援助した
子や親に対して、扶養範囲内の援助であれば特別受益とは認められません。
ただし、不要範囲を大きく超える生活費援助は、生前贈与とみなされて特別受益とされる可能性があります。
金銭援助のみならず、相続人の借金の肩代わり、有価証券や金銭債権なども該当します。
また相続税対策として行われる「年間110万以下の贈与」も特別受益です。
特別受益の対象外となるケース
特別受益の対象となるケースを理解したうえで、次は特別受益の対象外となるケースを見ていきましょう。
- 扶養範囲を超える生活費の負担
- 相続人以外への贈与や遺贈
- 生命保険や死亡退職金の受け取り
- 被相続人からのおしどり贈与
- 遺言による持ち戻し免除の意思表示
以上の5つについて、詳しく見ていきます。
扶養範囲内の生活費を負担した
生活費の援助が扶養範囲内であれば、特別受益には該当しません。ただし、どこまでが扶養範囲内なのか、どこからが扶養範囲外となるのか、実際に判断するのは難しいところです。
相続人以外の人物に贈与や遺贈をした
相続人以外への贈与や遺贈は、原則として特別受益の対象外です。友人の事業への資金援助、使用人への金銭贈与などは、特別受益と認められません。
ただし相続財産のうち、贈与や遺贈をした金額が一定割合以上であると認められれば「遺留分侵害額請求」が可能です。
また相続人ではない孫への贈与や遺贈も、特別受益には該当しません。間接的に子への贈与であるとみなされ、特別受益に該当する可能性があります。
生命保険や死亡退職金を受け取った
相続人が受取人となっている生命保険や死亡退職金は、受取人の財産です。特別受益には該当しません。
ただし、他の相続人が受け取る相続財産の金額とあまりに差が大きいと、特別受益とみなされて持ち戻しが行われる可能性もあります。
被相続人からおしどり贈与された
おしどり贈与とは、婚姻期間20年以上の配偶者に対し、居住用の不動産もしくは不動産取得用の金銭を贈与した場合、持ち戻し免除となる贈与のことです。
以上の条件を満たす場合、特別受益には該当しません。
遺言で持ち戻し免除の意思表示がされている
特別受益とみなされる贈与・遺贈が発生していても、被相続人の遺言で「持ち戻し免除の意思表示」があれば、持ち戻しは行えません。
これは民法第903条3項に定められています。
特別受益の計算方法
特別受益に該当する遺産があった場合は、持ち戻しをして遺産分割を行います。特別受益を受けていない人、特別受益を受けた人によって計算方法が異なるため、正しい計算方法を理解しておきましょう。
特別受益を踏まえた遺産分割の計算例
・特別受益を受けた人の計算方法
(相続財産+特別受益額)×法定相続分割合-特別受益を受けた金額
・特別受益を受けていない人の計算方法
(相続財産+特別受益額)×法定相続分割合
以下の場合で計算例を見ていきましょう。
・相続財産:1億円
・相続人:配偶者・子2人(長男・長女)
・特別受益:長男に1,000万円
・分割割合:配偶者1/2、子1人あたり¼
この場合の相続分は、以下のとおりです。
・配偶者:(1億円+1,000万円)×2分の1=5,500万円
・長男:(1億円+1,000万円)×4分の1-1,000万円=1,750万円
・長女:(1億円+1,000万円)×4分の1=2,750万円
長男の特別受益分を差し引いて計算することで、特別受益を受けていない人は多く相続できます。
特別受益を踏まえた遺留分侵害額の計算例
相続人には、それぞれ「遺留分」が認められています。遺留分は、相続人が直系尊属のみである場合を除き、法定相続分の1/2が基本です。特別受益が多額であり、相続財産を超えた金額であった場合は、特別受益による遺留分の侵害が発生します。
以下の場合で計算例を見ていきましょう。
・相続財産:2,000万円
・相続人:子3人(長男・長女・次男)
・特別受益:長男に1億円
・分割割合:子1人あたり1/3ずつ、遺留分割合は1/6
この場合の相続分は以下の通りです。
長男:(2,000万円+1億円)×1/3-1億円=0円
長女:(2,000万円+1億円)×1/3=4,000万円
次女:(2,000万円+1億円)×1/3=4,000万円
特別受益を合算して1/3ずつ受け取る場合の金額は、相続財産を超えています。また遺留分である1/6で計算すると、長女と次女には2,000万円ずつの遺留分があるはずです。しかし、実際の相続財産は2,000万円しかないため、1,000万円ずつの遺留分が発生します。
1億円の特別受益を受けた長男に対し、1,000万円ずつの遺留分侵害額請求が行えます。
特別受益を主張する流れ
特別受益は、主張する・しないは自由です。主張しなければ、なかったこととして遺産分割は進められます。また特別受益があったら必ず主張しなければならない、というわけでもありません。
以下が特別受益を主張する際の流れです。
- 特別受益を主張する
- 証拠を集める
- 話し合いでまとまらなければ調停や裁判を行う
1. 遺産分割協議で特別受益を主張する
まずは、特別受益を主張しなければ始まりません。相続人が集まって遺産分割を話し合う「遺産分割協議」を実施して、特別受益を主張します。相手が特別受益があったと認めて、遺産分割で合意が得られれば、その旨を記載した遺産分割協議書を作成します。
2. 特別受益を受けていた証拠を集める
特別受益を主張しても、相手が認める証拠がなければうやむやになってしまいます。客観的判断が可能な証拠を用意しましょう。銀行預金通帳・残高証明・登記簿・査定書などが有効です。
自力での証拠集めは手間も時間もかかるため、難しい場合は弁護士に相談する方法もあります。
3. 相手が特別受益を認めなければ調停や裁判を行う
証拠を集め、遺産分割協議で特別受益があったと主張しても、相手が認めないケースもあります。また、特別受益があったことは認めても、評価額で争いになるケースも多いです。
遺産分割協議では話がまとまらない、決着がつかないときは、家庭裁判所で調停を申し立てます。調停では、調停委員が相続人の間に入り、話し合いを進めて解決を試みます。そこで合意できれば、調停成立です。
それでも合意できない場合は、調停不成立として裁判へと移行します。裁判では、裁判官が特別受益があったか、金額がいくらであったかを踏まえ、最終的な判断を下します。
特別受益を主張する際の注意点
特別受益の有無や金額に関しては、相続人同士で揉めやすい問題です。主張する際は以下の点に気を付けておきましょう。
特別受益は主張しない限り有効にはならない
特別受益があっても、主張しない限り有効にはなりません。特別受益のあった相続人が自ら申告することは少ないです。他の相続人が主張しなければ、考慮されないまま遺産分割が進められます。
また特別受益があったことを客観的に証明する証拠が必要です。
相続開始から10年経過すると特別受益を主張できなくなる
令和5年の法改正により、遺留分の計算をする際に基本とする特別受益の範囲は「被相続人が亡くなってから10年が経過するまで」と定められ、それ以前の特別受益は主張できません。
ただし、2018年3月31日以前に亡くなった被相続人の相続は、2028年3月31日までの申し立てで特別受益の主張が可能です。
また令和元年に行われた法改正では、特別受益の持ち戻し対象は「相続開始前10年間」と限定されています。20年前や40年前などの昔の贈与は、特別受益として主張ができません。
特別受益が認められるかどうかはわからない
特別受益が認められるかどうかは、さまざまな要因で決まります。
被相続人の経済状況や社会情勢、その他の相続人との金額の差などによっては、特別受益があったとしても認められません。
例えば、被相続人に億単位の資産があった場合、そのうち500万円程度の贈与であれば、あくまで扶養の範囲内での贈与と考えられる可能性が高いです。
また、以前までは特別受益に当てはまるとされていた大学への進学費用も、社会情勢が変わったことで扶養の範囲内とみなされるケースが増えています。
特別受益には贈与税と相続税が課税される
特別受益は、贈与税と相続税の課税対象です。生前贈与は贈与税の課税対象に、遺贈や死因贈与は相続税の課税対象にあてはまります。
では、実際にどのように課税されるのかを見ていきましょう。
生前贈与は贈与税の課税対象
贈与税は、暦年課税が基本です。
暦年課税では、1年間の贈与額が110万円を超えた場合、超過部分に対して10〜55%までの税率が課せられます。
贈与税は、納付していないと追徴課税を受ける可能性があるため、贈与する側も受ける側も、注意しなくてはなりません。
遺贈や死因贈与は相続税の課税対象
相続税は、遺贈・死因贈与を含め、相続開始前3年以内の生前贈与や、相続時精算課税制度の生前贈与が対象です。
相続時精算課税制度とは、贈与税を納めずに2,500万円まで贈与ができる制度です。被相続人がなくなった際、贈与した財産の価額と相続財産の価額を合計し、相続税を計算します。ただし、令和6年1月より年間110万円の基礎控除が設けられ、相続発生時も相続財産に加算されません。
相続税を申告する際は、遺贈や死因贈与も含めたうえで申告する必要があります。
特別受益のトラブルを避けるためにやるべきこと
特別受益は、相続人同士のトラブルに発展しやすいです。いかにトラブルにならないように、スムーズに解決できるかが重要になるでしょう。
トラブルを避けるためのポイントは、以下の3つです。
- 事前に贈与の話し合いをしておく
- 遺言書を作成しておく
- 生命保険を利用する
事前に贈与について相続人と話し合いをしておく
複数の相続人のうち、特定の相続人に対して資産を贈与したい場合、あらかじめ話し合いを行っておくべきです。どうして贈与をするのか、理由や思いを伝えて、特別受益を受けない相続人に納得してもらいましょう。
話し合いをして被相続人の思いを伝えておくと、亡くなった後に問題が発生した場合でも、大事にならずスムーズに解決しやすいです。
遺言書に「持ち戻し免除」と記載しておく
遺言書を作成する際「特別受益による持ち戻しを免除すること」と記載します。記載しておくと、遺言の効力により持ち戻しは行えません。
口約束で持ち戻しの免除を成立させるケースもありますが、口約束はトラブルに発展しやすいです。「言った・言わない」で訴訟に至るケースも多々あります。
遺言書であれば、確実に持ち戻しの免除が可能です。ただし、遺留分の請求は遺言書があっても侵害できません。
また、特別受益を受けていない相続人にも配慮した配分を決め、相続人同士がいがみ合わないように注意してください。
正式な形で書かれていない遺言書は「無効」となるため、作成時には十分留意しましょう。
資産を相続させたい人を生命保険の受取人にする
生命保険の保険金は、原則として特別受益の対象外です。
資産を多く受け取ってもらいたい相続人を受取人としておくと、特別受益の主張をされずに贈与ができます。
ただし保険金が多額だと、特別受益の対象とみなされるケースもあります。
まとめ
遺産分割協議を行う際、トラブルになりやすい「特別受益」は、明確なルールや金額が定められていません。主張する・しないも自由で、なかったことにして遺産分割も行うことができます。
特別受益は、主張しても認められるかどうかはわかりません。実際に特別受益を受け取っていた相続人が素直に認めるケースは少ないため、証拠集めや交渉の方法が重要です。
まずは特別受益に関して正しい知識を習得して、スムーズに遺産分割協議が行えるように準備しておきましょう。