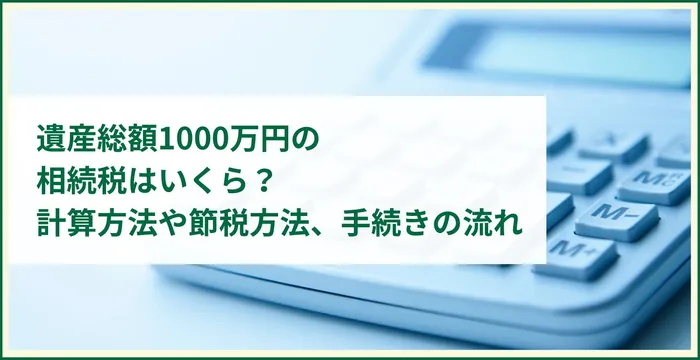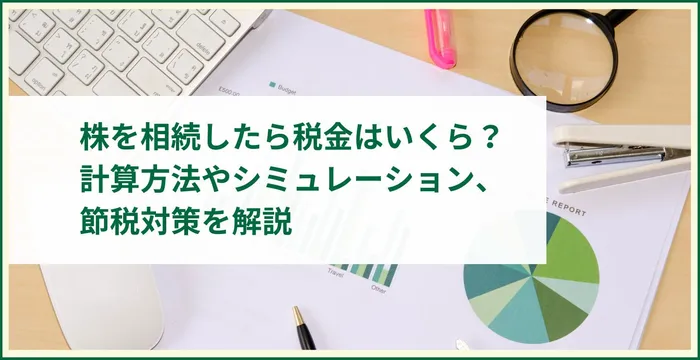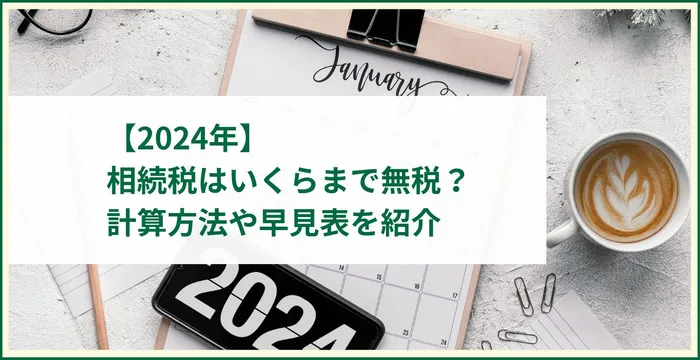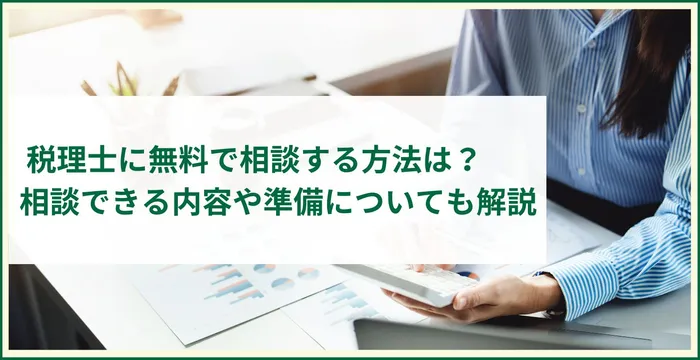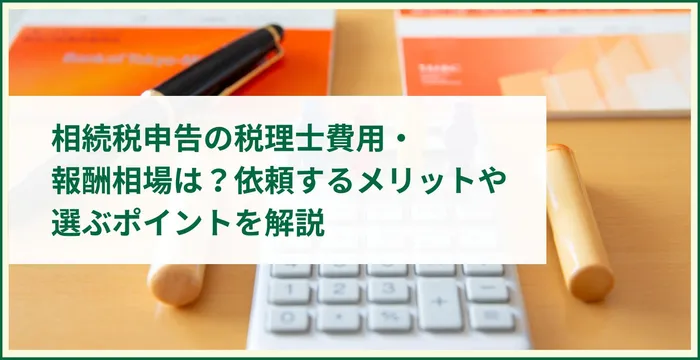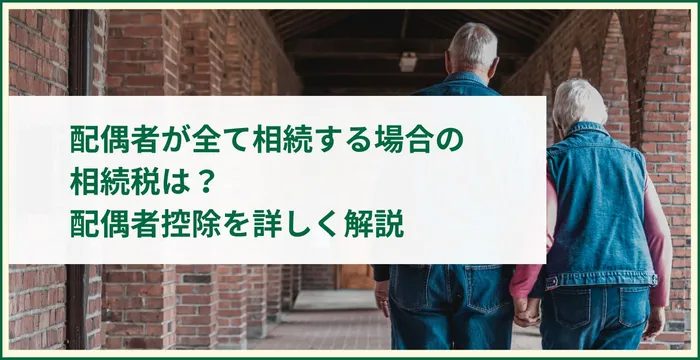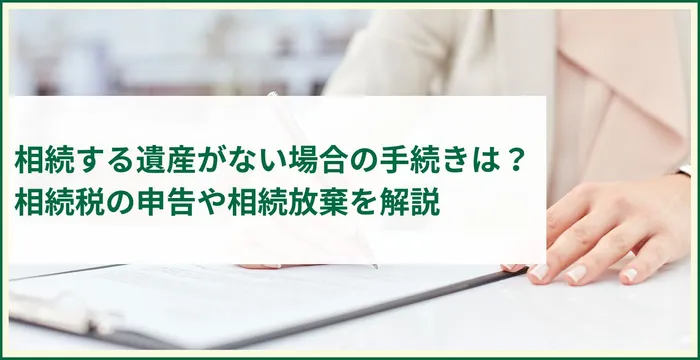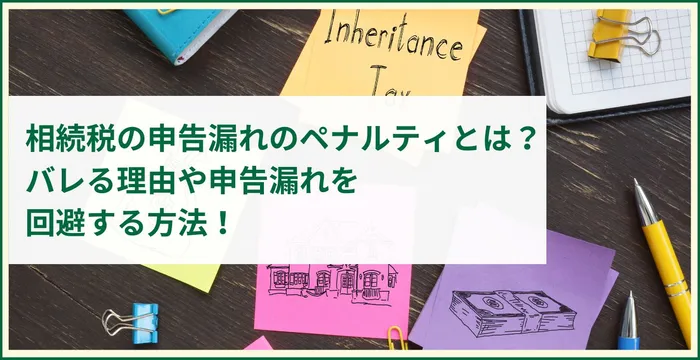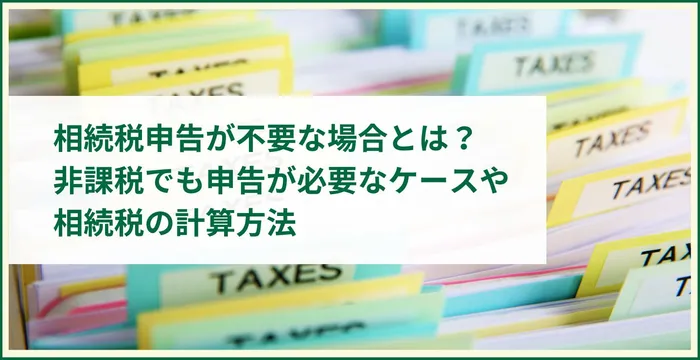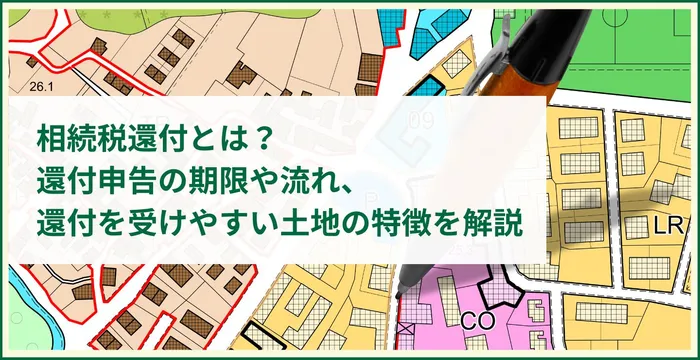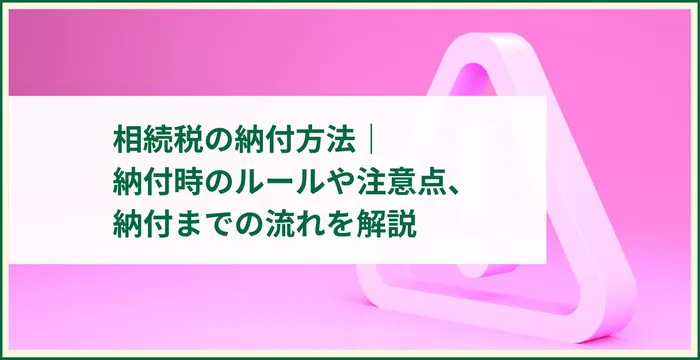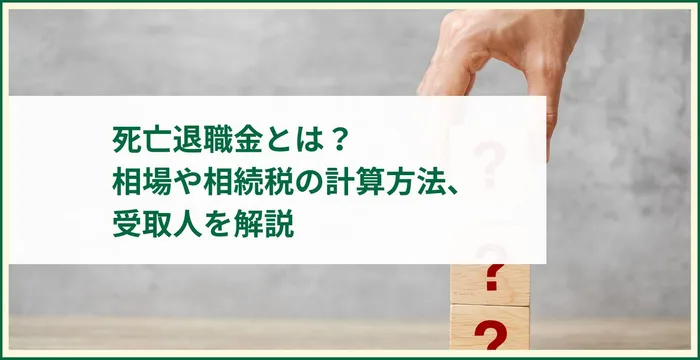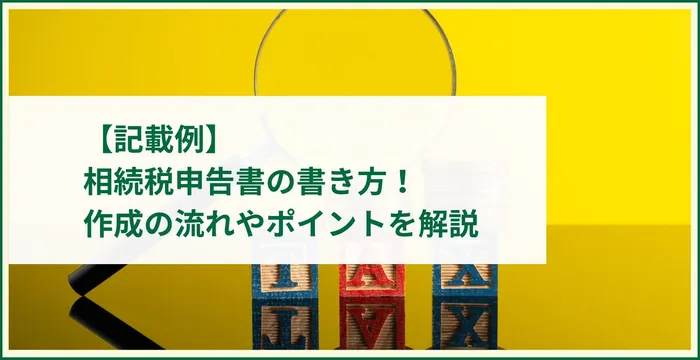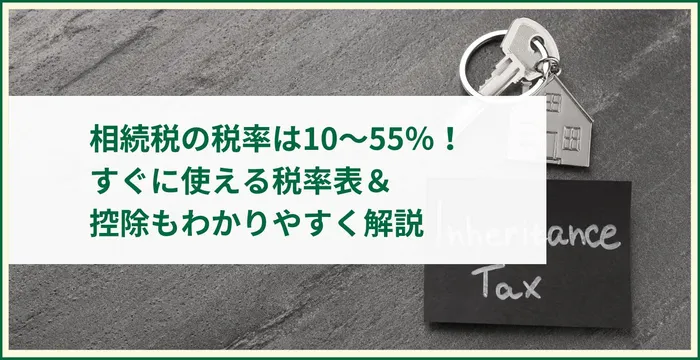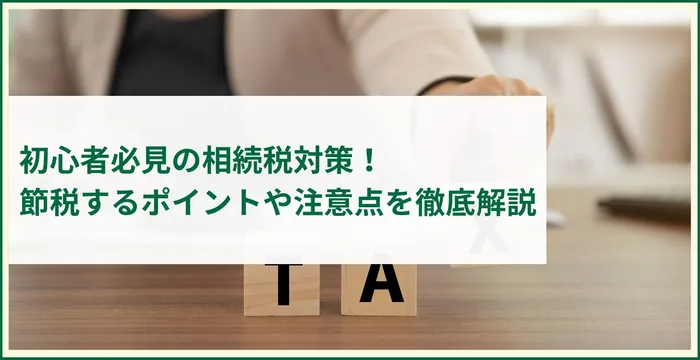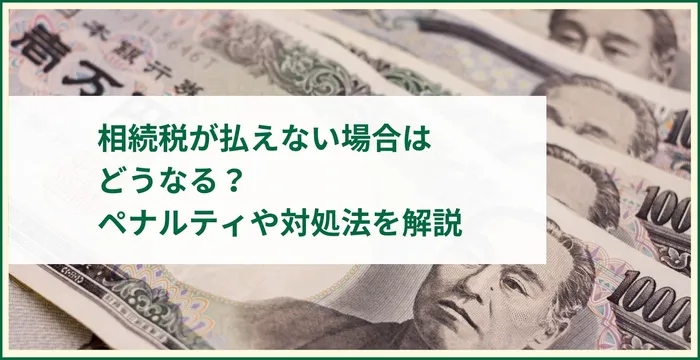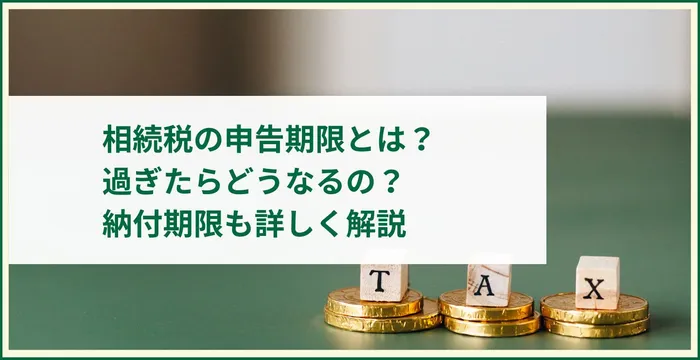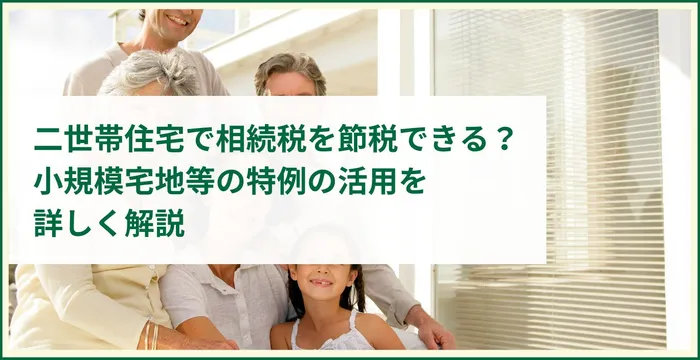遺産総額が1000万円の場合の相続税額について解説します。相続税の計算方法を知らない人が多いため、どれくらいの税金を支払うのかピンとこない方も多いでしょう。相続税の計算方法や節税方法も解説するので最後までチェックしてください。
相続税・相続税申告一覧
カテゴリーから相続コラムを探す
株を相続した場合には基本的に相続税がかかりますが、生前贈与や特例の利用などにより節税が可能です。計算方法や手続きが複雑なため専門家への相談も検討しましょう。本記事では、株を相続する場合の計算方法や節税対策について解説しています。
相続税は、相続した財産から控除や特例分を差し引き、算出された金額に対して課せられる税金です。正しい計算方法を知り、正確な相続税額を納付しましょう。本記事では、相続税が無税になる目安や計算の早見表、控除や特例の種類、計算方法を紹介しています。
税理士の無料相談では、確定申告の方法や給付金の申請方法、相続に関する相談が可能です。時間や回数は限られているものの、無料で専門家のアドバイスを受けられます。今回は税理士に無料相談する方法や相談できる内容、事前準備について解説します。
相続税申告に伴う税理士費用や報酬相場は、一般的に遺産総額の0.5%〜1.0%程度です。本記事では、相続税申告にかかる税理士費用や報酬相場、税理士に依頼するメリットなどを解説します。
配偶者が全て相続する場合の相続税は、配偶者控除などで軽減できます。しかし、二次相続の際に多額の相続税がかかるおそれがあるため要注意です。この記事では配偶者が全て相続する場合の相続税について解説します。
相続する遺産がないなら遺産相続は必要なく、手続きをすることもありません。しかし、実際は何らかの遺産があり、本当は手続きが必要であるケースも考えられます。本記事では、相続する遺産がないときに覚えておきたいポイントを紹介します。
相続税の申告漏れは追徴課税を課される可能性があります。ペナルティを課されないためには、正しい申告を行いましょう。本記事では、申告漏れのペナルティやバレる理由、申告漏れを回避する方法を解説します。
相続税の申告が不要になるケースについて解説します。相続が発生した場合でも、状況によって相続税の申告が不要になることがあります。逆に、非課税になる場合でも申告しなければならないケースもあるので、本記事をチェックして理解しておきましょう。
本来よりも多くの相続税を納税してしまった場合、税務署に申告をすれば納税しすぎた分を返還してもらえる「相続税還付」を受けられます。本記事では、相続税還付の概要や手続きの流れ、還付を受けやすい土地の特徴について解説していきます。
相続税の納付方法を解説します。相続税は金融機関やクレジットカード、税務署窓口、コンビニエンスストアでの納付が可能です。納付時のルールや注意点、納付の流れも紹介するので最後までチェックしてください。
死亡退職金の相場から受取人、相続税の計算方法まで、会社や相続人間でトラブルとならないために、遺族が知っておいた方がよいことについて解説します。
相続税申告書の書き方は、第9表から作成するのがおすすめです。 本記事を読むと、相続税申告書の書き方や作成の流れ、ポイントがわかります。 相続税申告書の作成・提出が必要なケースや作成が難しいときの対処法も解説します。
相続税の税率や課税額の計算方法を具体的なシミュレーション付きで解説します。基礎控除額や相続税の課税対象になる財産についても説明しますので、相続税の計算に不安を感じている方は参考にしてください。
相続税の申告を自分でできるかどうかの判断基準と、手続きの流れを解説します。相続税は自分で申告できるものの、内容が複雑であり申告までに時間がかかるため、自分でできるか判断することが大切です。自己申告を考えている人はぜひチェックしてください。
相続税は、ご本人が生きているうちに対策を行えば、大きく節税することが可能です。この記事では、生前贈与や控除などを活用した相続税対策の方法を解説していきます。
相続税が払えない場合、無申告加算税や延滞税、差し押さえなどのペナルティを受ける可能性があります。この記事では相続税が払えない場合の対処法について解説します。相続税が払えなくて困っている人はぜひ参考にしてください。
相続税の申告期限について詳しく解説します。被相続人が遺した財産を相続する場合、相続税の納付義務が生じます。いつまでに申告し、期限を過ぎたらどうなるのか、期限は延長できるのか、すべて理解できるので、ぜひチェックしてください。
相続税の納付を延滞したり、無申告や過少申告をした際に課せられるのが追徴課税です。追徴課税が発生しやすいパターンや、税務調査対象にならないための対策、課税の負担を軽減するための対策を解説します。
二世帯住宅で相続税を節税するには「小規模宅地等の特例」の活用がおすすめです。要件にあてはまれば、土地の評価額が80%減額できます。この記事では、二世帯住宅の節税方法について「小規模宅地等の特例」を中心に解説します。ぜひ最後までご覧ください。