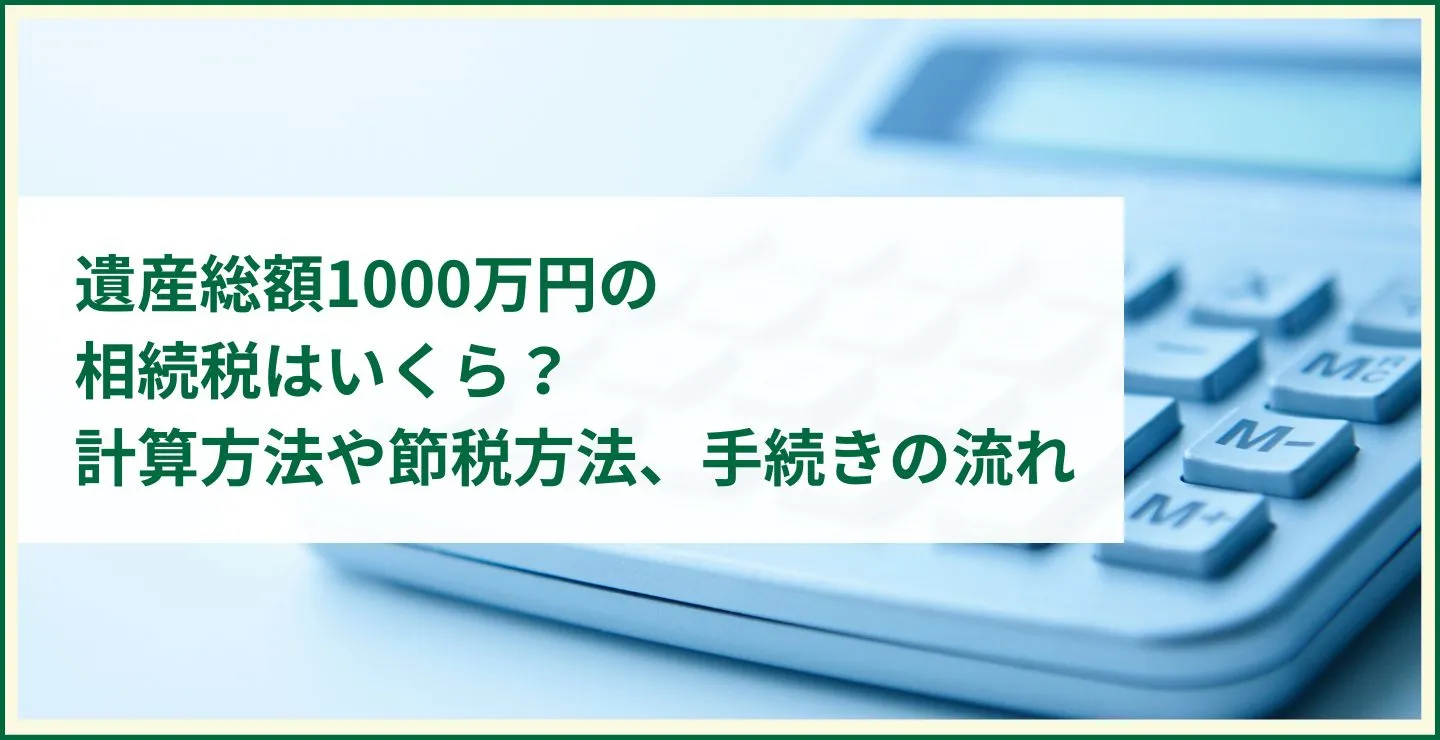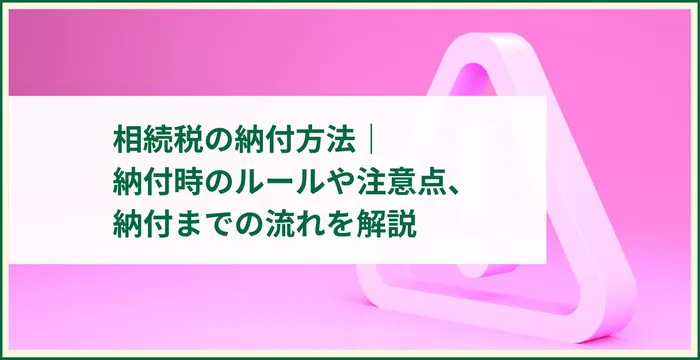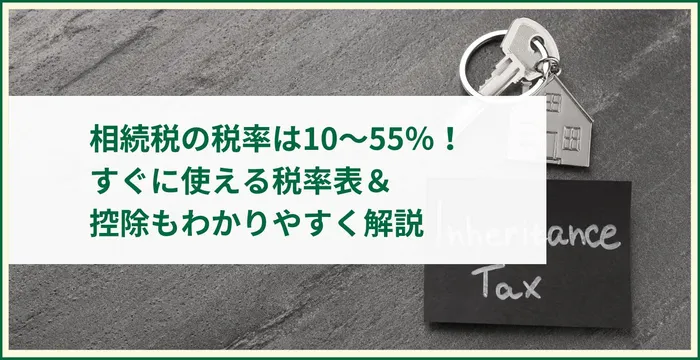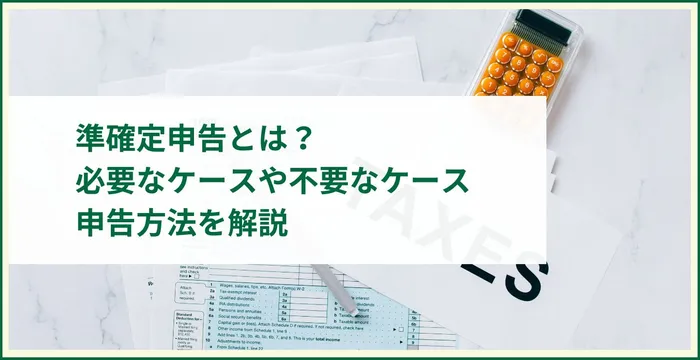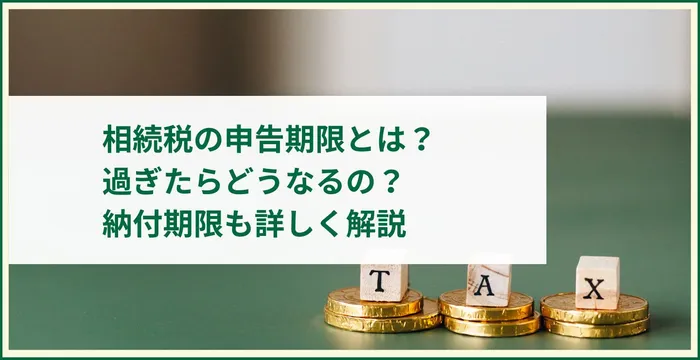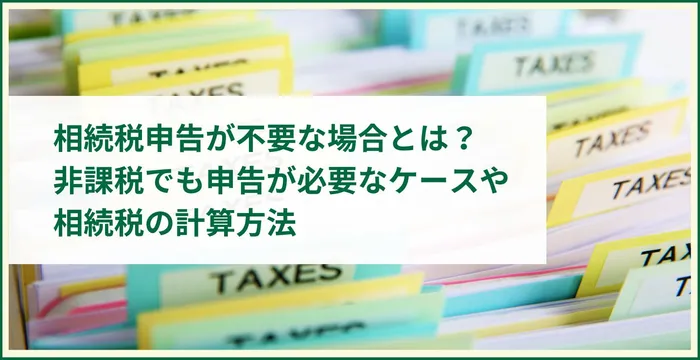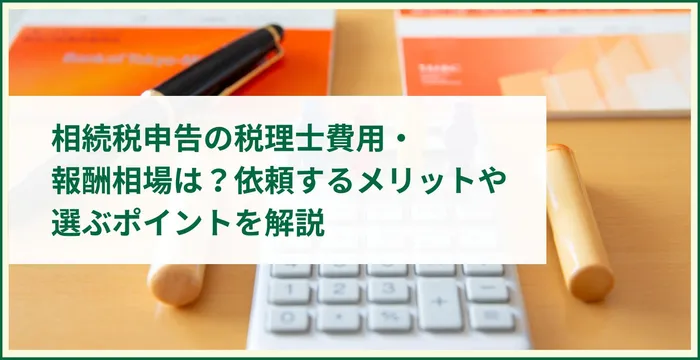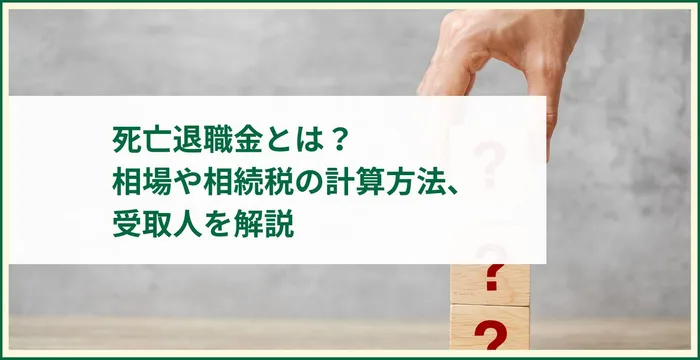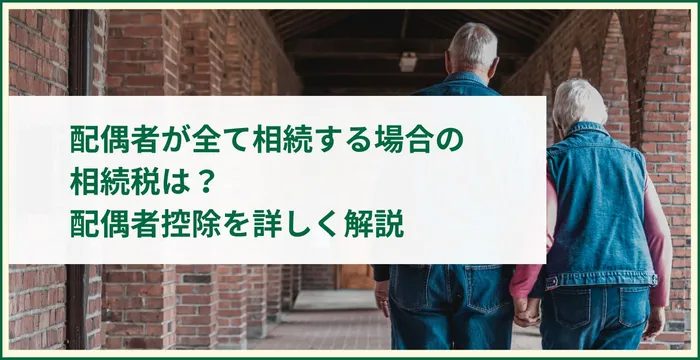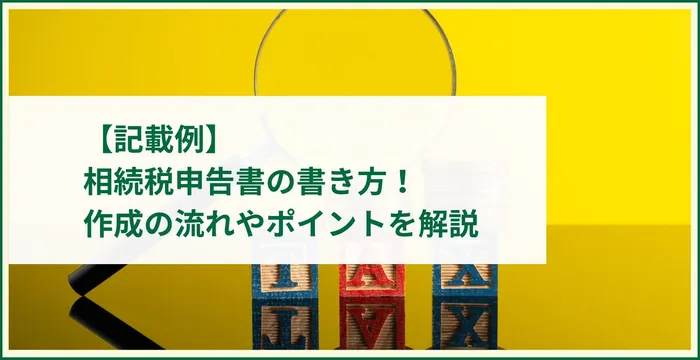1000万円の遺産の場合、相続税はかからない
被相続人が遺した遺産の相続が1000万円だった場合、基本的には相続税がかかりません。
相続税には基礎控除額が設定されているためです。
相続税の基礎控除額は以下の通りです。
相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
仮に法定相続人が1人だった場合でも、3600万円の基礎控除が適用されるため、遺産が1000万円の場合に相続税がかからないのです。
なお、法定相続人とは民法によって相続人と認められた人のことで、被相続人の子どもや孫、両親、祖父母、兄弟姉妹やその子どもなどが該当します。
ただし、相続税がかからないのは、遺産が本当に1000万円だった場合です。例えば、被相続人の預貯金が1000万円だからといって、遺産総額が1000万円とは限りません。
相続税の課税対象となる財産のなかには価値が高いものがあるため、遺産総額が1000万円以上になることもあります。
そのため、相続時には被相続人の財産を徹底的に調べる必要があります。
また、生前贈与があった場合、贈与された財産の一部は相続税の対象となるため、こちらも確認が必要です。
相続税の課税対象になる代表的な財産
国税庁のWebサイトには、相続税の課税対象となる財産が紹介されています。
相続税の課税対象となる財産は、大きく分類して以下の2種類です。
- 相続や遺贈によって取得した財産
- そのほか相続税がかかる財産
相続税とは死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得する場合に課税されるのが原則です。
この場合の財産(本来の相続財産)に該当するのは以下の通りです。
- 現金、預貯金
- 有価証券
- 宝石
- 土地
- 家屋
- 貸付金
- 特許権
- 著作権 など
このように、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものには、相続税が課せられます。
また、相続税法によって定められている、そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産ほか)には以下のようなものがあります。
- 死亡退職金や、被相続人が保険料を支払っていた生命保険契約の死亡保険金
- 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例適用を受けた農地、非上場会社の株式、事業用資産など
- 教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(一部条件あり)
- 結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
- 相続や遺贈で財産を取得した人や、加算対象期間内に被相続人から暦年課税にかかる贈与で取得した財産
- 被相続人から生前に相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産
- 相続人がいない場合に民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
- 特別寄与者が支払いを受けるべき特別寄与料の額で確定したもの
被相続人が死亡して相続が発生する場合は、被相続人が所有もしくは関係するこれらの財産の有無をすべて調査し、相続税が発生するかどうかを確認する必要があります。
これらの財産のうち、代表的な財産について紹介します。
参考:相続税がかかる財産|国税庁
預貯金
預金は故人(被相続人)の財産であるため、相続した場合は相続税が発生します。ただし、相続する財産の総額が基礎控除額以下の場合は、相続税はかかりません。
預貯金は銀行口座を開設して管理されている場合が多いですが、家族に内緒で別の口座を開設してお金を貯めているケースや、自宅でタンス預金を行っているケースもあります。
いずれの預貯金も相続税の課税対象となるため、預貯金の有無は確実に調査する必要があるでしょう。
また、名義預金も相続税の課税対象です。
名義預金とは、口座の名義人と、実際にお金を出している人が異なる預金のことをいいます。
例えば、被相続人が孫のために、孫の名義で開設した口座に入金していた場合や、口座名義人は妻であるものの、実際には被相続人がお金をねん出していた場合、名義預金に該当します。
これらの財産は、口座名義人ではなく、被相続人の相続財産となるため、相続税の申告が必要になります。
税務調査によって名義預金と見なされた場合は、過少申告加算税や延滞税、重加算税などが課せられる場合があります。
それぞれの税額は以下の通りです。
| ペナルティの種類 |
税率 |
| 過少申告加算税 |
・新たに納めることになった税金の10%相当額。
※ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%相当額となる。
|
| 重加算税 |
・期限内に申告した税額が少なかった場合は税率35%。
|
| 延滞税 |
・法定納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは、年7.3%もしくは延滞税特例基準割合2.5%に1%を加えたもののうち、いずれか低い割合の税率が適用。
・納期限の翌日から2ヶ月を経過した日以降は、年14.6%もしくは延滞税特例基準割合8.7%に7.3%を加えたもののうち、いずれか低い割合の税率が適用。
※いずれの延滞税特例基準割合も令和6年時点の割合
|
参考:延滞税の割合|国税庁
参考:申告納税制度|国税庁
参考:加算税の概要|財務省
自宅(不動産)
被相続人が生前住んでいた自宅や、所有していた不動産も、相続税の課税対象です。
例えば、死亡した親と同居していた家があった場合、その家の相続にも相続税が発生します。築年数が経過していて価値がないと思っていても、意外と評価額が高いケースもあり、その場合は相続税も高くなります。
また、自宅の土地や建物だけではなく、外構の塀や門扉にも相続税がかかります。
他にも、被相続人が自宅以外に不動産を所有していた場合や、土地を借りて使用している場合の借地権も、相続財産に含まれるため課税の対象です。
家電などの家庭用財産
家庭用財産(家財道具)とは、自宅にある一般動産の総称です。
家具や家電、衣類、靴、楽器、スポーツ用品、貴金属、宝石、自動車、骨董品、電話加入権などが家庭用財産にあたります。
特に気を付けたいのが、親の相続が発生して、別世帯で暮らしている子どもなどが相続人となる場合です。
相続人となる子どもは、死亡した親の家にある家庭用財産の多くを相続することになるからです。
また、税務署は相続税の申告があった場合、家財道具の申告の有無を必ず確認しています。家庭用財産の申告を怠った場合、税務署から相続財産を隠したと見なされる場合もあります。
そのため、面倒であっても家庭用財産についても申告するようにしましょう。
原則的にすべて個別に評価を行いますが、1個当たりの価格が5万円以下になる場合は一括評価となります。
例えば、自家用車や宝石、掛け軸などの骨董品といった査定額が5万円を超えるような財産は、相続発生所の時価によって個別に評価して相続税に計上します。
一方、1個当たりの価格が5万円となる家庭用財産は、まとめて評価して相続税に計上します。
見落としがちな課税対象になる財産
相続税の課税対象となる財産には、預貯金や土地・建物といった不動産など、分かりやすいものがありますが、一方で見落としがちな財産も存在します。
ここでは、相続税の課税対象となる見落としがちな財産を紹介します。代表的なものは次のとおりです。
- デジタル遺産
- 保険金・死亡退職金・年金の受給権など
- 死亡日前の7年間に贈与された財産
- 相続時精算課税制度によって贈与された財産
それぞれ詳しく解説します。
デジタル遺産
デジタル遺産とは、死亡した人がデジタル形式で保管していた財産のことです。
被相続人が死亡した場合に所有していた財産は、原則的にすべて相続対象となるため、現物の財産に加えて、デジタル遺産も相続の対象となります。
デジタル遺産の一例は以下の通りです。
- 暗号資産(仮想通貨)
- 電子マネー
- デジタルの著作物
- NFTアート
- クレジットカードのポイント、マイレージ
- ネット銀行の口座の残高
- ネット証券会社の口座の残高 など
デジタル遺産は他の現物の財産と比較して、相続人が把握しにくく、財産調査の際に見つけるのは簡単ではありません。
ただし、デジタル遺産であっても、申告漏れがあった場合は過少申告加算税の対象となる恐れがあります。
そのため、被相続人の生前にリストアップしておくことをおすすめします。
保険金・死亡退職金・年金の受給権など
保険金や死亡退職金、年金の受給権などには、相続税が課税されます。
例えば、非相続人が保険料を負担していた生命保険から支給される死亡保険金には、相続税がかかります。
死亡退職金とは、労働者の死亡に伴う退職や、退職後の死亡によって発生する退職金のことです。
一般的には、死亡した人もしくは退職した人の代わりに、遺族に支給されます。
死亡退職金は、被相続人の死亡から3年以内に支給額が確定したものに関しては、みなし相続財産となるため、相続税がかかります。
なお、みなし相続財産とは、被相続人が所有していた財産ではないものの、経済的な実態としては本来の相続財産と同じになるため、相続税の課税対象となるものをいいます。
また、企業年金や個人年金に加入していた場合、本来被相続人が持つ年金の受給権を相続人が相続することになり、相続税がかかります。
一方、厚生年金や国民年金といった公的年金には相続税はかかりません。
なお、保険金や死亡退職金、年金の受給権に関しては、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が設定されており、相続税の軽減が可能です。
死亡日前の7年間に贈与された財産
被相続人の死亡日前の7年間に贈与(生前贈与)された財産にも、相続税が課せられます。
生前贈与とは、被相続人が存命中に財産を他者に贈与することを指します。
2023年の税制改正により、これまでは相続財産に加える財産の対象は、死亡日前の3年以内に贈与された財産でしたが、7年以内に贈与された財産に変更されることになりました。
段階的な期間延長が実施され、2031年1月以降は完全に7年となります。
被相続人が亡くなる直前にもらった財産に関しては、相続税が発生すると理解しておきましょう。
相続時精算課税制度によって贈与された財産
相続時精算課税制度によって贈与された財産にも、相続税が発生します。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子ども・孫に財産を贈与する際に選択できる制度です。
同制度を選択した場合、最大2500万円の特別控除を適用でき、2500万円を超えた贈与財産については増税の税率が一律で20%になります。
ただし、贈与した財産は贈与者が死亡して相続が発生した際に、相続財産に加えて相続税額を計算する必要があります。また、相続人以外が贈与を受けても、課税対象となります。
例えば、1億円の財産を持つ父親が相続時精算課税制度を利用して、自分の長男に2500万円の生前贈与を行ったとします。
このケースでは、贈与された財産が特別控除額の2500万円を超えないため、長男は贈与税を支払う必要がありません。
しかし、父親が死亡した際には、父親が遺した残りの財産の7500万円に加えて、制度を利用して贈与した2500万円を加えた1億円に対して相続税がかかり、納税しなければなりません。
なお、2024年1月以降は、年間110万円の基礎控除が設けられ、毎年1月1日から12月31日までの贈与額が110万円を超えた場合には贈与税の申告が必要です。
相続税の課税対象にならない財産
被相続人が遺した財産のうち、相続税の課税対象とはならない財産があります。これを、非課税財産といいます。
国税庁の公式Webサイトに記載されている、非課税財産の一例は以下の通りです。
- 墓地や墓石、仏壇、仏具、紙を祭る道具など、日常礼拝をしているもの
- 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とした事業を行う一定の個人などが、相続や遺贈によって取得した財産で、公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
- 地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のなる人またはその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
- 相続によって取得したと見なされる生命保険金などのうち、500万円に法定そう祖K人の数をかけた金額までの部分
- 相続によって取得したと見なされる退職手当金などのうち、500万円に想定相続人の数をかけた金額までの部分
- 個人製経営している幼稚園の事業に使われていた財産で、一定の要件を満たすもの
- 相続や遺贈によって取得した財産で、相続税の申告期限までに国または地方教協団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄付したもの。または、相続や遺贈によって取得した金銭のうち、相続税の申告期限までに公益信託の信託財産とするために支出したもの
上記のほかにも、厚生年金や国民年金の受給権は非課税となり、公的年金の未支給部分や国家資格は相続税の課税対象外となります。
これを見ればすぐにわかる!相続税の早見表
被相続人から財産を相続した場合、どれだけ税金がかかるのか気になる方も多いでしょう。そのような場合は、相続税の早見表(速算表)を利用するのが便利です。
相続税額の算出方法は、各相続人が実際に取得した財産に税率をかけ合わせて算出するものではありません。
実際には、正味の違算金額から基礎控除額を差し引き、残りの金額(課税遺産総額)を民法によって定められた相続分により、按分した金額に税率をかけ合わせて計算します。
この場合に利用するのが、早見表(速算表)です。法定相続分に応じた取得金額を算定して早見表に当てはめれば、相続税の総額のもとになる税額を算出できます。
また、早見表で計算したそれぞれの法定相続人の相続税額を合計したものが、相続税の総額となります。
相続税の早見表(速算表)は以下の通りです。
| 法定相続分に応じた取得金額 |
税率 |
控除額 |
| 1000万円以下 |
10% |
― |
| 1000万円超から3000万円以下 |
15% |
50万円 |
| 3000万円超から5000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 5000万円超から1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 1億円超から2億円以下 |
40% |
1700万円 |
| 2億円超から3億円以下 |
45% |
2700万円 |
| 3億円超から6億円以下 |
50% |
4200万円 |
| 6億円超 |
55% |
7200万円 |
例えば、法定相続人が配偶者である妻と子ども2人の場合、法定相続分は妻が2分の1、子どもは4分の1ずつとなります。
課税遺産総額が1億4000万円だった場合、妻が7000万円、子どもがそれぞれ3500万円の遺産を取得することになります。
この金額を早見表に当てはめて計算すると、以下のようになります。
| 項目 |
金額 |
| 妻の相続税額 |
7000万円×30%-700万円=1400万円 |
| 子どもの相続税額 |
3500万円×20%-200万円=500万円 |
| 相続税の総額 |
1400万円+500万円=1900万円 |
参考:相続税の税率|国税庁
相続税の計算方法
次に、相続税の計算方法を紹介します。
相続税額を正確に計算するためには、以下の手順を踏む必要があります。
- 1. 相続する財産をすべて調査して遺産総額を合計する
- 2. 遺産総額から基礎控除額分を差し引く
- 3. 相続税がいくらになるか計算する
- 4. 相続人一人ひとりの相続税額を計算する
それぞれ詳しく解説します。
1. 相続する財産をすべて調査して遺産総額を合計する
相続税を計算するには、相続する財産をすべて洗い出して、遺産総額の合計を算出します。
前述の通り、遺産には相続税がかかるものとかからないものがあります。
また、財産には土地や建物、預貯金などのプラスの財産に加えて、借金や未払い金、葬儀費用などのマイナスの財産(債務)があります。プラスの財産からマイナスの財産を差し引いた金額が正味の遺産額です。
例えば、現金や預金、株式、不動産、生命保険金などのプラスの財産が1億5000万円、借金や葬儀費用などのマイナスの財産が1000万円だった場合、正味の遺産額は1億4000万円となります。
なお、被相続人が死亡する7年以内に生前贈与された財産は相続財産に含まれるので、忘れずに計算しましょう。
2. 遺産総額から基礎控除額分を差し引く
遺産総額が算出できたら、相続税の基礎控除額を差し引きます。
相続税の基礎控除額は以下のように計算します。
相続税の基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が被相続人の妻と子ども2人の合計3人だった場合、相続税の基礎控除額は4800万円となります。
3. 相続税がいくらになるか計算する
遺産の合計額から基礎控除額を差し引いた金額がわかれば、次に合計の相続額を算出します。
相続税額は、課税遺産総額を各相続人が法定相続分を取得したと仮定して算出します。
例えば、法定相続人が被相続人の妻と子ども2人で、課税遺産総額が9200万円だった場合、各相続人の相続額は以下のようになります。
- 妻:9200万円×1/2=4600万円
- 子ども1:9200万円×1/4=2300万円
- 子ども2:9200万円×1/4=2300万円
算出された相続額に対して、相続税額を算出します。既出の早見表(速算表)に当てはめて計算した場合、各相続人の相続税額と合計相続税額は以下のようになります。
- 妻:4600万円×20%-200万円=720万円
- 子ども1:2300万円×15%-50万円=295万円
- 子ども2:2300万円×15%-50万円=295万円
- 合計相続税額:720万円+295万円+295万円=1310万円
4. 相続人一人ひとりの相続税額を計算する
相続税の総額が算出できたら、最後に相続人ごとの相続税額を算出します。
法定相続分は民法によって決まっていますが、遺産分割協議や遺言書の内容によっては、法定相続分通りの配分にはならないケースも多々あります。
そこで、仮の相続税額の合計を算出し、それから実際の相続分で按分して本来の相続税額を計算するのです。
各相続人の税額を算出して税額控除を適用すれば、実際の納税額が把握できます。
相続税を節税するコツ
他の税金と同じように、相続税も節税できるケースがあります。
具体的な節税方法は以下の通りです。
- 生命保険に加入する
- 生前贈与を行う
- 一括贈与による特例を活用する
- 小規模宅地等の特例で評価額を下げる
- 非課税財産を現金一括で購入する
それぞれ詳しく解説します。
生命保険に加入する
相続税の節税方法の1つが、生命保険への加入です。
生命保険金に設定されている非課税枠を利用すれば、相続税の節税が可能です。
被相続人が自分で掛け金を支払っていた生命保険の死亡保険金が給付される場合、500万円×法定相続人の数で算出された金額が非課税となります。
例えば、法定相続人が4人存在する場合、500万円×4人で非課税枠は2000万円となり、その金額までの保険金であれば非課税で受け取れます。
預貯金で2000万円の財産がある場合、その2000万円すべてが相続税の課税対象となるものの、受取保険金であれば同じ金額でも相続税がかからないため、相続税を節税できます。
生前贈与を行う
生前贈与も相続税の節税に活用できます。
贈与税には、年間110万円の基礎控除が設けられており、その範囲内であれば贈与が行われても、贈与税が発生しません。
つまり、暦年贈与をうまく活用すれば、相続前に贈与税を負担させることなく、子どもなどに財産を渡せるのです。
ただし、毎年一定の期間に一定額の贈与を継続していると、定期金給付契約と見なされて贈与税の課税対象となる場合があります。そのため、同じ時期や同じ金額での贈与は避けた方がいいでしょう。
また、被相続人が死亡した日から7年以内に暦年贈与を行った場合は、基礎控除額の範囲内でも、相続時に贈与分の金額を含めて相続税を支払う必要があります。
一括贈与による特例を活用する
一括贈与による特例を活用すれば、相続税を節税できます。
一度にまとまった財産を贈与する場合、非課税特例の適用が受けられるためです。
具体的な特例は以下の通りです。
| 特例の種類 |
内容 |
| 住宅取得等資金の非課税 |
・最大1000万円までの贈与が非課税
|
| 教育資金の一括贈与の非課税 |
・最大1500万円までの贈与が非課税
|
| 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税 |
・最大1000万円までの贈与が非課税
|
このように、住宅取得等の資金や教育資金、結婚・子育て資金を一括で贈与する場合は、一定額まで非課税となります。
ただし、それぞれの特例を利用する場合は、各特例制度の条件を満たす必要があるほか、書類の提出や贈与税の申告、金融機関との資金管理契約が必要になります。
加えて、上記の非課税特例には適用期限が設けられており、それぞれ以下の期限までしか利用できません。
- 住宅取得等資金の非課税:2026年(令和8年)12月31日まで
- 教育資金の一括贈与の非課税:2026年(令和8年)3月31日まで
- 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税:2025年(令和7年)3月31日まで
※2024年5月時点での適用期限
※将来的に変更になる可能性あり
小規模宅地等の特例で評価額を下げる
小規模宅地等の特例を活用すれば、相続税を節税できます。
小規模宅地等の特例とは、一定の要件を満たす宅地等について、最大80%評価額を下げて相続税の負担を軽減できる制度です。
被相続人の自宅や事業に使用していた宅地などは、遺族にとっては大切な財産ですが、通常の取引価額をもとに算出した評価額を相続税の算出に適用した場合、相続税が高額になります。
そこで、配偶者などの遺族がその家に住み続けられるようにすることを目的に、この特例制度が設けられました。
居住用と事業用の宅地について4つの特例が設けられており、評価額を50%~80%減額できるため、相続税額が軽減できます。
例えば、死亡した人が自宅として使用していた宅地等に対しては「特定居住用宅地等」の特例を適用できます。適用条件は以下の通りです。
- 限度面積は330㎡
- 被相続人の配偶者もしくは同居している親族に相続される
- 相続税の申告期限まで居住している
なお、死亡した人の配偶者は、無条件で特例を受けられます。
例えば、死亡した人の自宅の土地が150㎡、評価額が3000万円とします。この場合、控除可能な評価額は以下のように算出します。
3000万円×150㎡/150㎡×80%=2400万円
3000万円から2400万円を控除できるため、残りの600万円に相続税がかかります。
また、相続人が配偶者と子ども1人だった場合、相続税の基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)は4200万円となります。
自宅以外の財産が2000万円と仮定すると、特例を受けた自宅の評価額600万円に自宅以外の財産額2000万円を加えて2600万円となり、基礎控除額を下回るため、相続税は発生しません。
ただし、小規模宅地等の特例を適用して基礎控除額を下回った場合でも、特例適用のためには相続税の申告が必要になることを覚えておきましょう。
非課税財産を現金一括で購入する
非課税財産を現金一括で購入するのも、相続税の節税に有効です。
前述した通り、被相続人が遺した財産は、相続財産となる財産と、相続財産にならない財産があります。
仏壇や墓石、祭祀財産などは非課税財産となるため、生前に購入すれば相続税の節税対策となります。
この手段を選択する場合のポイントは、現金一括で購入することです。一括支払いで決済を済ませれば、被相続人の財産の圧縮効果が期待できます。
一方、ローンを利用したり、分割払いを利用したりして購入した場合、被相続人が死亡したタイミングで支払いが終わっていなければ、債務控除として認められなくなるため、節税効果が薄れてしまいます。
節税効果を期待したい場合は、生前に非課税財産に変換することを検討しましょう。
相続税の節税に「控除」も活用しよう
相続税の節税は、前項で紹介した方法以外にも、控除(税額控除)を利用すれば実現可能です。ここでは、相続税を節税できる控除について解説します。
利用可能な控除には以下のようなものがあります。
- 配偶者控除
- 未成年者控除
- 贈与税額控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
それぞれ詳しく解説します。
配偶者控除
税額控除の1つが、配偶者控除です。
配偶者控除とは、配偶者が取得した正味の遺産の金額が、配偶者の法定相続分相当額もしくは1億6000万円のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないという控除制度です。
つまり、取得した課税対象となる財産が1億6000万円までなら相続税は課税されないほか、1億6000万円を超えた場合でも配偶者の法定相続分の範囲内であれば非課税となります。
控除の対象となるのは、被相続人の戸籍情報配偶者のみです。なお、内縁の夫や妻は対象外となります。
なお、配偶者控除は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産価額をもとに計算する必要があります。相続税の申告期限までに遺産が分割されていない場合や相続税の申告書を税務署に提出していない場合は、原則として税額軽減の対象とはなりません。
未成年者控除
未成年控除も、相続税の税額控除の1つです。
未成年控除とは、相続人が未成年の場合に、相続税額から一定金額が差し引かれる控除制度です。
控除額は、その未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき、10万円となります。例えば、財産を取得した時点で15歳4ヶ月だった場合、4ヶ月を切り捨てて15歳で計算し、3年に10万円をかけた30万円が税額から控除されます。
未成年控除が適用されるのは、相続時に未成年で日本国内に居住していることが条件となります。ただし、日本国籍の有無を問わずいくつかの条件を満たせば適用される可能性があるため、適用条件の確認をおすすめします。
贈与税額控除
贈与税額控除を利用しても、相続税を節税できます。
贈与税額控除とは、自分が支払う相続税の金額から、すでに支払った増税税の金額を、ルールの範囲で差し引ける制度です。
なお、前述の通り、生前贈与には2つの課税方法があり、どちらを選択しているかによって、贈与税額控除が適用される条件が異なります。
暦年贈与の場合、3年以内の生前贈与発生時に納めた贈与税額を、自分の相続税額から差し引けます。
一方、相続時精算課税の場合、制度選択後に納付した贈与税額を差し引けるため、3年以内といった期限はありません。5年前でも10年以上前でも、納付済の贈与税額を差し引けます。
ただし、控除できるのはあくまでも本税のみで、加算税や延滞税などは贈与税額控除の対象外となります。
また、相続人が相続放棄を選択した場合でも、みなし相続財産を取得している場合は、雑徭税額控除の適用が受けられます。
なお、贈与税額控除額は以下の計算式で算出できます。
贈与税額控除額=贈与を受けたその年分の贈与税額×(相続税の計算時に足した贈与財産の価格÷贈与を受けた年分の贈与財産の合計額)
障害者控除
障害者控除が適用される場合も、相続税を節税可能です。
障害者控除とは、相続人に障害者が含まれる場合、その障害者の相続税額から一定金額を控除できる制度です。
障害者控除の適用条件は以下の通りです。
- 85歳未満の障害者
- 日本国内に住所がある
- 法定相続人である
- 相続財産を取得する
なお、ここでいう障害者とは、一般障害者もしくは特別障害者を指します。それぞれの障害者の要件については、国税庁のWebサイトで確認してください。
障害者控除の控除額の計算方法は以下の通りです。
障害者控除額=(85歳―相続開始日の障害者の年齢)×10万円
※特別障害者は20万円、端数は切り上げ
ただし、被相続人が死亡した時点で障害者とは認められていない場合、障害者控除は受けられません。
参考:第19条の4《障害者控除》関係
相次相続控除
相次相続控除も、相続税の税額控除制度の1つです。
相次相続控除とは、10年以内に2回以上相続が発生して相続税が課せられた場合に、税負担を軽減できる制度です。
例えば、祖父が死亡して父への一次相続が発生し、そこから10年が経過しないうちに父が死亡してその子どもに二次相続が発生する場合、一次相続で父に課せられた相続税額の一部が控除されます。
なお、一次相続と二次相続の期間が短いほど、また、一次相続で課せられた相続税が多いほど、控除額は大きくなります。
相次相続控除の適用条件は以下の通りです。
- 法定相続人である
- 今回の相続の開始前10年以内に前回の相続が発生している
- 今回死亡した被相続人が前回相続で相続税を課されている
相次相続控除の金額を計算する方法は非常に複雑となっているため、国税庁のWebサイトを確認するか、税理士に相談することをおすすめします。
参考:相次相続控除|国税庁
外国税額控除
外国税額控除を利用しても、相続税を節税可能です。
外国税額控除とは、相続税をすでに海外で支払っている場合に、日本で納付する相続税から外国の財産部分の割合を控除できる制度です。
日本と外国での二重課税を排除することを目的にした制度で、以下のいずれか金額が少ない方が控除されます。
- 外国で支払った相続税や相続税に似た税金
- 相続税額×海外にある財産額÷相続人の相続財産額
なお、外国税額控除の適用を受けられるのは、以下の条件を満たす人です。
- 相続や遺贈によって国外の財産を相続した人
- 国外の財産に関して、その国で相続税相当を課税された人
相続税を申告・手続きする際の流れ
ここでは、相続税の申告や手続きの流れを紹介します。
具体的な流れは以下の通りです。
- 1. 遺言書・相続財産・負債がないか調査
- 2. 法定相続人を調査・確定させる
- 3. 相続方法を選ぶ
- 4. 被相続人の準確定申告を行う
- 5. 相続財産・負債を確定させ、遺産分割協議を行う
- 6. 相続税の計算・申告・納付を行う
それぞれ詳しく解説します。
1. 遺言書・相続財産・負債がないか調査
まずは、遺言書の有無や相続財産の有無を調査します。
被相続人が作成した遺言書があれば、その内容に沿って財産を分ける必要があります。自宅に遺言書が保管されていた場合は、開封前に家庭裁判所の検認を行いますので、勝手に開封しないようにしましょう。
また、被相続人が所有していた相続財産についても調査します。この際、プラスの財産だけではなく、借金や未払い金、連帯保証人になっているなど、負債についても調査が必要です。
すべての財産を洗い出した結果、プラスの財産よりもマイナスの財産が多かった場合、そのまま相続すると相続人が負債を抱えることになるためです。
負債の多さによっては、相続放棄を選択した方がいいケースもあるため、プラス・マイナスのすべての財産を調べ上げましょう。
特に、被相続人が会社を経営していた場合や、賃貸用の不動産を所有していた場合などは、徹底的に負債の調査を行ってください。
2. 法定相続人を調査・確定させる
次に、法定相続人が誰になるのかを調査・確定させます。
死亡した人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を取得して、法定相続人を調べます。
被相続人の出生まで遡る場合、本籍がどこかの自治体になるケースもあり、郵送での取得が必要な場合は時間がかかる場合もあるため、できるだけ早く法定相続人の調査を行う必要があります。
3. 相続方法を選ぶ
次に、相続方法を選択します。
相続方法は、以下の3つから選択します。
| 相続方法 |
内容 |
| 単純承認 |
・全面的に被相続人の権利義務を承継する方法
・プラスの財産がほとんどの場合に有効
|
| 限定承認 |
・プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法
・プラスの財産が多い場合、手放したくない住居が含まれている場合に有効
|
| 相続放棄 |
・プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない方法
・マイナスの財産が相当多い場合に有効
|
このうち、限定承認や相続放棄を選択する場合は、被相続人が死亡してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。申し立てをしない場合は、単純承認に同意したと見なされます。
4. 被相続人の準確定申告を行う
次に、被相続人の準確定申告を行います。
準確定申告とは、被相続人が年の途中で死亡した場合、相続人がその年の1月1日から死亡した日までの確定した所得金額や税額を計算して申告・納税することです。
申告・納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。
申告書の提出には、相続人全員が連署した死亡者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表を添付する必要があります。
なお、確定申告が不要だった場合、準確定申告を行う必要はありません。
5. 相続財産・負債を確定させ、遺産分割協議を行う
次に、相続財産や負債を確定し、遺言書がない場合は遺産分割協議を行います。
プラスの財産とマイナスの財産(葬儀費用を含む)をすべて調査し、相続財産を確定させたら、財産目録を作成します。
財産目録には正式な書式がないため、手書きで作成しても、Excelなどを利用しても構いません。洗い出したすべての財産を記載することが大切です。
作成した財産目録をもとに、相続人が集まって遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、相続人同士が相続財産の権利配分を明確にするための話し合いのことです。
遺産分割協議が完了して遺産の分割割合が決まったら、その結果を遺産分割協議書にまとめます。作成した協議書の内容に相続人全員が同意・署名・実印の押印を行い、相続人全員の印鑑証明書を添付することで、遺産分割協議書は法的効力を持つことになります。
相続人全員が同じ協議書を保管する場合、人数分の書面・印鑑証明が必要です。
なお、被相続人が遺言書を作成している場合、その内容が優先されるため、遺産分割協議書の作成は必要ありません。
6. 相続税の計算・申告・納付を行う
次に、相続税を計算して申告・納付を行います。
相続財産から課税対象額を算出すると同時に、相続税の基礎控除額を計算します。課税対象額が基礎控除額よりも多い場合に、相続税の申告と納付が必要になります。
相続税額を計算し、申告書を作成したら、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告・納付を行います。
また、申告後に納付書が送付されることはありません。納付書は最寄りの税務署で入手しましょう。管轄の税務署であれば、税務署名・税務署番号が記載された納付書を入手可能です。
さらに、相続税の申告にはさまざまな書類が必要になり、相続の状況によって書類の種類が異なりますので、必ず事前に確認しておきましょう。
なお、相続税の納付は、各相続人が行います。代表者が一括で納付した場合、贈与と見なされる可能性があるため、必ず相続人それぞれが納付するようにしましょう。
相続税の申告・納付をする際に注意したいこと
相続税を申告・納付する場合、いくつかの注意点があるので紹介します。具体的には、以下のポイントに注意しましょう。
- 相続税は0円でも申告が必要となる
- 10ヵ月の申告・納付期限に遅れない
- 財産の調査漏れがないかしっかりと確認する
- 「連帯納付義務」の適用に気を付ける
- 納税資金が不足する場合は延納・物納申請も検討する
それぞれ詳しく解説します。
相続税は0円でも申告が必要となる
計算の結果、相続税額が0円の場合、納付は不要でも申告は必要です。
例えば、小規模宅地等の特例によって相続税額が0円になるようなケースでは、期限内に申告することで特例が適用されます。他にも、配偶者の税額軽減も、申告なしでは軽減措置は適用になりません。
相続税の申告が不要になるのは、小規模宅地等の特例や配偶者の軽減措置を適用しなくても、課税価額が基礎控除以下になる場合です。
また、以下の制度のように、非課税措置や控除に申告要件が含まれない場合も、申告は不要です。
- 死亡保険金の非課税額
- 退職手当金の非課税額
- 贈与税額控除
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
10ヵ月の申告・納付期限に遅れない
相続税は、相続の開始があったことを知った翌日から10ヵ月以内に申告・納付を完了させなければなりません。
相続税の申告期限・納付期限を過ぎた場合、以下のペナルティが課せられます。
無申告加算税とは、申告期限までに相続税の申告を行わなかった場合のペナルティです。
相続税の申告期限を過ぎてからの申告(期限後申告)を行った場合、申告時期や税額によって無申告加算税の税率が決められます。
具体的な税率は以下の通りです。
| 期限後申告のタイミング |
相続税額50万円以下の部分 |
相続税額50万円を越えた部分 |
相続税額300万円を越えた部分 |
| 自主的な期限後申告 |
5% |
5% |
5% |
| 実地調査の事前通知から実地調査までに行った期限後申告 |
10% |
15% |
25% |
| 実地調査後の期限後申告 |
15% |
20% |
30% |
このように、場合によっては30%もの無申告加算税が課されるケースもあるため、できるだけ自分から期限後申告を行いましょう。
重加算税とは、税務調査によって仮想や隠ぺいが認められた場合のペナルティです。
重加算税は、相続税の納税額を下げる目的で、申告をしなかったり、相続財産を隠したりした場合に課せられます。
本来の納税額に税率を掛ける形で重加算税額が計算されますが、期限内申告では35%、期限後申告では40%もの税金が発生します。
延滞税とは、期限までに相続税を納付しなかった場合のペナルティです。
申告期限の翌日から納付が完了するまでの日数に応じて計算され、納期限から2ヵ月以内に納付が完了した場合は原則年7.3%、2ヵ月を過ぎた場合は原則年14.6%の延滞税が掛かります。
ただし、現在は延滞税特例基準割合が設定されており、2ヵ月までなら年2.4%、2カ月を過ぎた場合は年8.7%の延滞税が発生します。
相続税の申告期限や納付期限を過ぎた場合、ペナルティが課せられる恐れがありますが、一方で申告期限にどうしても間に合わないケースもあります。
そのようなケースでは、以下のように対処しましょう。
- 財産評価が間に合わない場合は概算の評価額で期限内に申告する
- 遺産分割の方法が決まらない場合は未分割申告をする
相続する財産の評価が間に合わず、明確な相続税額がわからないために申告期限に間に合わないケースでは、概算の評価額を期限内に申告しましょう。
この際、概算評価額を大きめに申告しておけば、期限後に申告しても延滞税や過少申告加算税は課税されず、更正の請求により払いすぎた相続税の還付が受けられます。
また、申告期限までに遺産分割の方法が決まらない場合は、未分割申告を行いましょう。
未分割申告とは、仮の相続税申告を行う事です。
法定相続分で遺産分割を行ったものとして申告書を一旦作成し、申告期限後3年以内の分割見込書を添付して申告します。
仮の申告を行うことで、申告期限から3年以内に遺産分割の方法が決まった場合、その金額に応じてすでに支払った相続税の過不足を精算できます。
未分割申告を行えば、加算税や延滞税などのペナルティが発生しないほか、遺産分割方法が決まった後に小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用が受けられます。
なお、相続税の申告と納付は同時に行う必要はなく、申告をして後日納付をしても問題はありません。
申告期限・納付期限を過ぎてペナルティを受けないよう注意しましょう。
財産の調査漏れがないかしっかりと確認する
相続税の申告・納付の際には、財産の調査漏れに注意が必要です。
調査漏れがあった場合、税務調査が入って、追徴課税を課せられる可能性があるためです。
申告後の税務調査で追徴課税が発生するのは、財産の調査漏れのケースが多い傾向にあります。
そのため、見落としがちな財産についてもきっちり調べなければなりません。例えば、残高が少ない銀行口座や証券口座、暗号通貨などのデジタル資産、海外の所有している資産などは注意深く探しましょう。
なお、個人が被相続人の財産をすべて調査するのはかなり大変です。万が一、財産漏れが発覚した場合、遺産分割協議もやり直さなければなりません。
また、税務署は税理士による申告よりも、個人の申告の場合に財産漏れを厳しくチェックする傾向にあります。
手間や時間をかけたくない場合は、税理士に調査や申告を依頼するのがおすすめです。
「連帯納付義務」の適用に気を付ける
相続税の納付には、連帯納付義務が適用されます。
連帯納付義務とは、相続税を各相続人が連携して納付しなければならない、というルールのことです。
例えば、相続人の誰かが納付を怠った場合は他の相続人に通知され、相続税の納付義務を負うことになります。
連帯納付義務は、相続人本人が納税した場合や納税猶予・延納手続きを行った場合、納期限から5年経過して時効になった場合を除いて、必ず適用されるルールです。
このルールを逃れるのは難しく、督促を受けた場合は時効が中断されます。納税義務がある場合は、速やかに相続税を納付しましょう。
納税資金が不足する場合は延納・物納申請も検討する
納税資金が足りない場合は、延納や物納の申請を検討しましょう。
延納とは、金銭での相続税納付が困難な場合に、担保の提供によって分割納付する手段です。
物納とは、延納を利用しても金銭での納付が困難な場合に、相続財産を相続税の支払いに充てる手段です。
ただし、これらの手段は誰でも気軽に利用できるものではありません。延納の場合は相応の担保の提供が求められ、国債や不動産、社債、株式などの財産が必要になります。
また、物納を利用する場合にも、相応の財産が必要です。
これらの手段を利用したい場合も、税理士に相談して利用の可否を確認したり、調査・手続きを依頼したりした方がいいでしょう。
まとめ
遺産総額が1000万円の場合、基礎控除の範囲内となるため、相続税はかかりません。ただし、非課税枠や控除制度を利用する場合、税額が0円でも申告が必要になるケースがあります。
また、相続税はさまざまな方法で節税できますが、内容や手続きが複雑な場合が多いといえます。また、相続税の計算や申告も手間や時間がかかりやすいため、税理士に対応を依頼することをおすすめします。