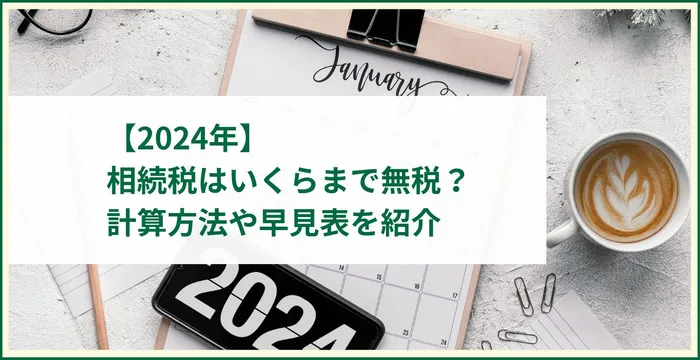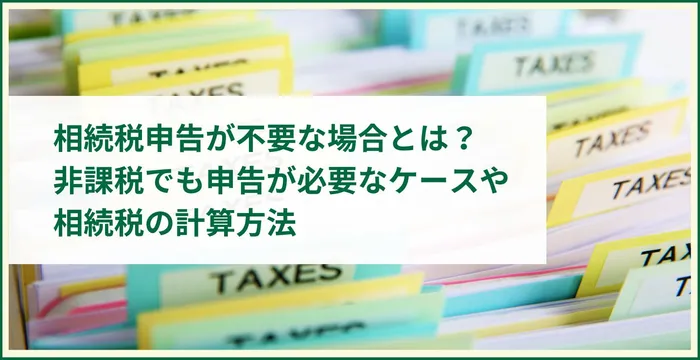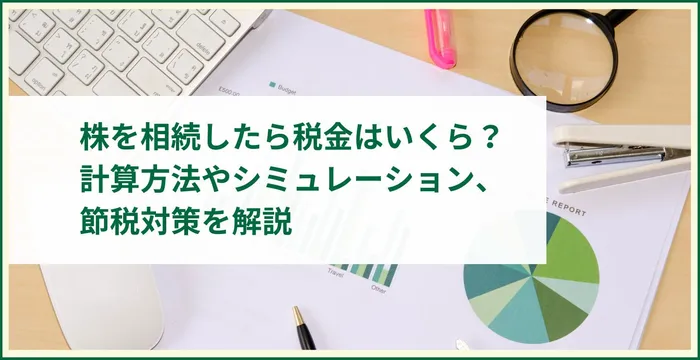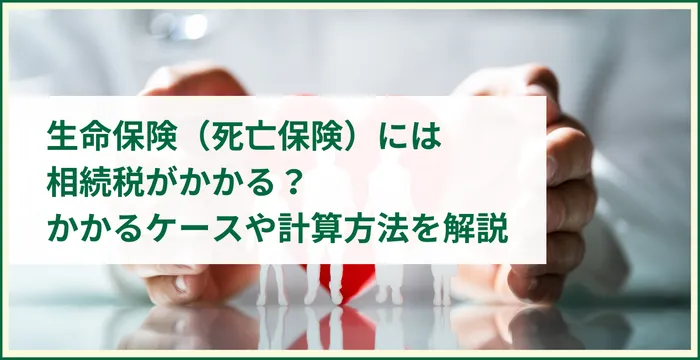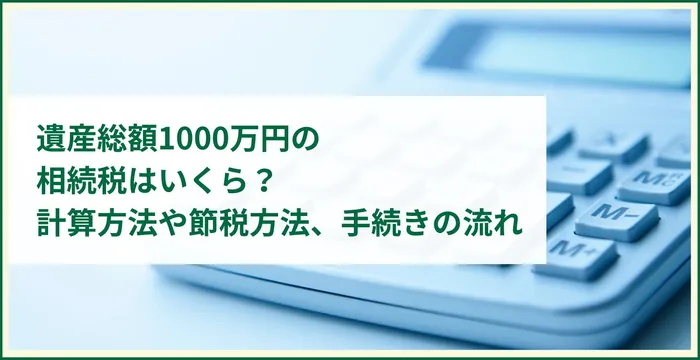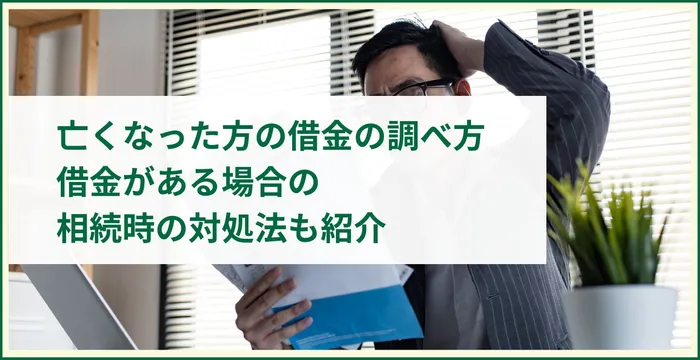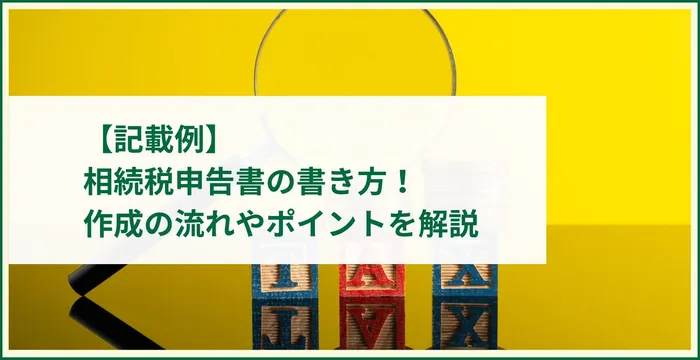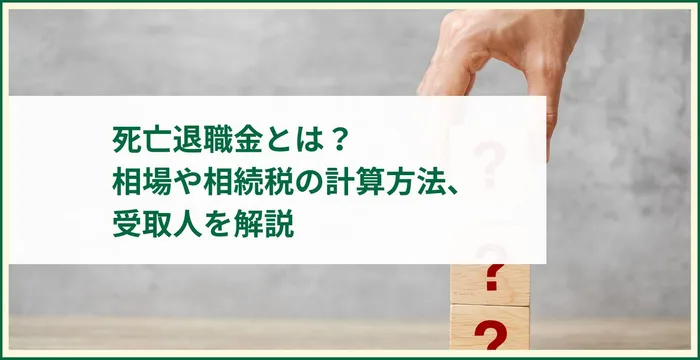相続財産額が控除額以下であれば相続税申告は不要
相続が発生した場合、必ず相続税がかかるわけではありません。
特に、相続財産が少ない場合は、相続税の課税対象となる課税遺産総額が相続税の基礎控除額より少なければ申告は必要ありません。
・課税遺産総額が基礎控除額より多い場合:相続税の申告が必要
・課税遺産総額が基礎控除額より少ない場合:相続税の申告が原則不要
ただし、基礎控除額は法定相続人の数によって変わり、また、相続税の課税対象となる相続遺産の計算においては、生前贈与が加算される場合もあるため慎重に計算しなければなりません。
基礎控除額の計算方法
相続税の計算について、相続した遺産総額がそのまま相続税の対象となるわけではありません。相続税の対象となる課税遺産総額を計算しなければなりません。ここでは、課税遺産総額の計算方法について解説します。
- 遺産総額から債務・葬儀費用を引く
- 生前贈与がある場合はその分を足す
- 法定相続人の数をもとに課税対象額を算定する
- 基礎控除額を上回っているかを確認する
遺産総額から債務・葬儀費用を引く
相続税の対象となる課税遺産総額を計算するにあたり、相続財産から借入金などの債務や葬儀費用を差し引くことができます。
ここで控除対象となる債務とは、相続開始時点で現に存在する借入金や未払金と認められるものです。亡くなった日時点の借入金の残高および未払利息を相続財産から控除することができます。
また、亡くなった人(以下「被相続人」)が納付義務を負う税金について、亡くなった時点の未納分のほか、納税義務が発生しているものも含まれます。
例えば、被相続人が死亡した年度の住民税や固定資産税は、相続人が納税義務を引き継ぐとともに、納期が到来する前のものでも控除の対象です。
また、葬式費用のうち控除できる費用は、原則として亡くなってから葬儀、納骨までの費用で次のようなものです。
- お通夜・告別式の費用
- 火葬料・埋葬料・納骨料
- お布施
- 遺体の運搬費用 など
一方で、位牌や仏壇、墓石の購入費用や法事に関する費用は、控除対象となりません。
生前贈与がある場合はその分を足す
相続開始前の一定期間内の生前贈与がある場合、相続遺産に加算しなければなりません。
これを「生前贈与加算」といいますが、被相続人の死亡間近に駆け込みで贈与することで、相続税の負担を回避することを防止するための制度です。
加算対象となる生前贈与については、令和5年度の税制改正により取扱いが変わりました。
令和6年1月1日以前に行われた贈与は、相続発生前3年以内の贈与が対象でしたが、令和6年1月1日以降に行われる贈与から順次7年以内に延長されています。
なお、贈与税には暦年課税制度があり、110万円の基礎控除額があります。つまり、年間110万円以下の贈与は、贈与税の申告・納付義務はありません。ただし、生前贈与加算の計算においては、贈与額が基礎控除以下の場合でも加算対象となる点には注意が必要です。
また、110万円を超える贈与を受けて贈与税を支払った場合、贈与税と相続税の二重課税を回避するために、相続税に贈与税額控除が認められています。
法定相続人の数をもとに課税対象額を算定する
法定相続人の数をもとに基礎控除額を計算し、相続税の課税対象となる課税遺産総額を算出します。
基礎控除額の計算方法は次のとおりです。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人は、民法が定める被相続人の財産を承継する権利のある人です。配偶者は常に相続人となり、配偶者と同時に相続人になるのは次の順位のとおりです。
| 順位 |
法定相続人 |
| 第1順位 |
被相続人の子や孫(直系卑属) |
| 第2順位 |
被相続人の父母や祖父母(直系尊属) |
| 第3順位 |
被相続人の兄弟姉妹 |
第1順位の相続人がいなければ第2順位が相続人となり、第1、第2順位がいなければ第3順位が相続人となります。なお、被相続人の子や孫もしくは兄弟姉妹が相続発生時点ですでに亡くなっていた場合、その子どもが代わりに相続人(代襲相続)となります。
例えば、法定相続人が配偶者と2人の子どもの場合、基礎控除額は次のようになります。
基礎控除額=3,000万円+600万円×3名(法定相続人)=4,800万円
課税遺産総額が基礎控除額を上回っていれば、超えた部分に対して相続税がかかりますが、基礎控除額より少ない場合、相続税は発生しません。
相続税申告をしなくても適用される控除・特例
相続税には、相続人や相続時の状況に応じて、さまざまな控除が設けられています。そのため、基礎控除額を超える相続財産がある場合でも控除制度を活用することで相続税がかからない場合もあります。
ここでは、相続税の申告をしなくても適用される控除制度について解説します。
障害者控除
障害者控除は、85歳未満の障害者が相続財産を承継した場合に、所定の要件を満たすことで相続税の税額から一定の金額を控除できる制度です(税額控除)。
控除額の計算方法は、次のとおり一般障害者と特別障害者で異なります。
・一般障害者:(85歳-相続発生時の年齢)×10万円
・特別障碍者:(85歳-相続発生時の年齢)×20万円
※障害の程度が一般障害者より重い特別障害者の控除額が高く設定されています
年数の計算にあたり1年未満の期間が生じるときは、切り上げて1年として計算します。
例えば、相続発生時に60歳6ヶ月の一般障害者であれば、85歳-60歳6ヶ月=24年6ヶ月となりますが、これを切り上げて25年として計算するため、控除額は、25年×10万円=250万円となります。
控除後の税額が0円となった場合、相続税の申告は不要です。
また、対象となる障害者の相続税額から控除しきれない金額が生じた場合、障害者の扶養義務者(配偶者や子や父母など)の相続税額から控除することが可能です。
未成年控除
相続人が未成年者である場合に、一定の要件を満たすことで、相続税額から控除できる制度です。
未成年者控除の控除額の計算方法は次のとおりです。
・未成年者控除額=(18歳-相続発生時の年齢)×10万円
※相続発生が2022年3月31日以前の場合は、(20歳-相続発生時の年齢)
年数の計算にあたり1年未満の期間が生じるときは、切り上げて1年とします。
例えば、相続人が14歳6ヶ月の場合、18歳-14歳6ヶ月=3年6ヶ月となり、切り上げると4年となります。そのため控除額は、4年×10万円=40万円となります。控除後の税額が0円となった場合、相続税の申告は不要です。
なお、未成年者控除についても、相続税額から控除しきれない金額が生じた場合、未成年者の扶養義務者の相続税から控除することが可能です。
相次相続控除
相似相続控除とは、前回の相続から10年以内に相次いで相続が発生した場合に、今回の相続税から一定割合の相続税を控除できる制度です。
これは、短期間の間に続けて相続が発生した場合に、相続人の税負担が過大になりすぎないように設けられているものです。
控除できる金額は、前回の相続時に課税された相続税額のうち、1年を経過するごとに10%を逓減したあとの金額を、今回の相続税から控除することができます。
相続税申告をしないと適用されない控除・特例
前章では、相続税の申告をしなくても適用される相続税の控除制度を紹介しましたが、ここでは、相続税の申告が適用要件となっている控除あるいは特例について解説します。
また、これらの控除や特例を利用した結果、相続財産がそれぞれの控除額を下回る場合でも相続税の申告は必要となるため注意が必要です。
- 配偶者控除
- 小規模宅地等の特例
- 農地の納税猶予の特例
- 相続税の寄付金控除
- 特定計画山林の特例
配偶者控除
配偶者控除(配偶者の税額の軽減)は、配偶者が取得した相続財産のうち、相続税の課税対象が1億6,000万円まで(もしくは法定相続分まで)は、相続税が課税されない制度です。
控除額が大きいため、ほとんどのケースでは相続税の対象となりませんが、特例を適用するには、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。
小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例は、被相続人や生計を一にする親族の居住用あるいは事業用としていた宅地などをについて、一定の要件を満たすことで、相続税の対象となる宅地の評価額を最大80%まで減額できる制度です。
被相続人が自宅や事業として活用していた宅地は、残された家族にとっても生活や収入の基盤となる重要な遺産です。
その財産について、通常の土地評価額に基づいた相続税が課されるとなると、相続税の支払いが困難となり宅地を売却しなければならない状況に陥る可能性があります。
そこで、一定の要件を満たす宅地については、課税対象となる評価額を下げ、相続税の負担を軽減する制度として「小規模宅地等の特例」が設けられました。
農地の納税猶予の特例
農地の納税猶予の特例は、相続や贈与によって農地を取得した人が、一定の要件を満たすことで、農地にかかる税金の納税が猶予される制度です。
これは、農地を相続した人に多額の税金が課されると、税金の支払いのために農地を売却せざるを得なくなり、農業を継続することが難しくなることを防止するためです。
農地の納税猶予の特例を適用させるには、納税猶予額や利子税の額に見合う担保を準備したうえで相続税の申告が必要になります。
相続税の寄付金控除
相続税の寄付金控除とは、相続した財産から寄付した分について相続税の課税対象としない特例です。
特例の対象となるためには、相続財産をそのままの形で寄付することが必要であり、例えば、相続した不動産を売却した収入(現金)を寄付した場合には適用されません。
また、寄付の対象となるのは、国や地方公共団体、公益社団法人、独立行政法人などで、対象とならない法人に寄付しても適用されません。
特例を適用するには、相続税の申告時に対象になる財産の明細を記載し、寄付先からの受領書、証明書類などを添付する必要があります。
特定計画山林の特例
特定計画山林の特例とは、特定計画山林を特定計画山林相続人などに相続した場合に、山林の相続税評価額を軽減できる特例です。
特定計画山林とは、「特定森林経営計画対象山林」または「特定受贈森林経営計画対象山林」を指し、森林法において、市区町村長の認定を受けた森林経営計画が定められている区域内にある立木もしくは土地をいいます。
適用要件として、相続開始から相続税の申告期限まで、森林経営計画に基づいて事業を行っていること、また、保有し続けていることなどが必要です。
相続財産が少ない場合の注意点
ここでは、相続財産が少なく相続税が課税されない場合でも、注意しなければならない点、ならびに、相続人がしなければならない手続きについて解説します。
- 故人に債務が残されていた場合は相続放棄の検討が必要
- 相続税がゼロでも遺産分割協議や不動産の相続登記は必要
- 生前贈与時に相続時精算課税制度を利用していたか確認する
故人に債務が残されていた場合は相続放棄の検討が必要
相続財産は、被相続人のプラス財産だけでなく、借入金などのマイナス財産も含めたすべて財産です。そのため、相続財産が少なくて、被相続人に借入金などの債務が残されているとき相続放棄を検討したほうがよい場合もあります。
相続放棄は、被相続人の遺産のすべてについて相続を拒否することです。相続放棄すると、プラス財産も含めてすべての財産を承継することはできません。
プラスの財産より借入金などが多い場合や遺産相続のトラブルに巻き込まれたくない場合などに有効な手段です。
相続放棄は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内にしなければならず、相続放棄に必要となる書類と費用は次のとおりです。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍の附票
- 申述人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 収入印紙(800円)
- 郵便切手
相続放棄申述書は、相続放棄を申し立てるときに家庭裁判所に提出する書類で、裁判所のホームページから入手することが可能です。
これらの書類以外にも、相続放棄する人によって必要となる書類があるため、家庭裁判所のホームページなどで確認しながら進めましょう。
相続放棄を申立てしてから10日程度で、家庭裁判所から「照会書」が送付されます。照会書は、相続放棄する相続人の意思や理由を確認するための質問書で、回答後、家庭裁判所に返送します。
照会書を返送後、1週間から10日程度で「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続きは終了です。
相続放棄は、3ヶ月内という限られた期間内にしなければならないため、専門家である弁護士などに相談することも検討しましょう。
参照:裁判所「相続の放棄の申述」
相続税がゼロでも遺産分割協議や不動産の相続登記は必要
相続税がかからない場合でも遺産分割協議や不動産の相続登記は必要です。
たとえ相続財産が少なくても、相続人で遺産分割協議を行い相続財産の分割方法を決めなければなりません。
金融機関で被相続人の口座の相続手続きを行うときや不動産の名義変更をする際に、相続人全員の合意のもと作成する遺産分割協議書が必要となる場合があります。
また、相続財産に不動産がある場合、被相続人から相続人に名義人を変更する所有権移転登記(相続登記)をしなければなりません。
以前は、相続登記は任意でしたが、2024年4月1日から義務化されました。不動産を承継する相続人は、相続の開始ならびに不動産の取得を知ってから3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
なお、相続登記の義務化は、2024年4月1日以前に発生した相続についても適用されます。正当な理由なく期限内に申請しなかった場合10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
また、相続登記しなければ、相続不動産を売却したり、土地上に建物を新築したりすることが難しくなるため、不動産の処分、活用に支障がでる可能性があります。
生前贈与時に相続時精算課税制度を利用していたか確認する
生前に贈与を受けて相続時精算課税制度を利用していたかを確認しましょう。
相続時精算課税制度とは、被相続人の子や孫が生前に贈与を受けた場合に、贈与額の累計2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。
つまり、相続時精算課税制度を利用した相続人は、相続財産に生前受けた贈与額を加えたものが相続税の対象となるため、相続財産が少ない場合でも相続税が発生する可能性があります。
相続時精算課税制度を選択している場合、最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日(贈与税の申告期限)までに、受贈者が相続時精算課税選択届出書などを贈与税の申告書に添付して管轄する税務署へ提出しているはずです。
相続手続きで不明な点があるときは弁護士などの専門家に相談しよう
相続手続きに不安があるときは、弁護士などの専門家に相談することも方法の1つです。
相続では、さまざまな手続きが関係するため、それぞれの専門家が対応できる内容を把握しておくことが大切です。
| 相談先 |
相談できる内容 |
| 税理士 |
相続税対策・相続税申告 |
| 司法書士 |
不動産の登記申請に関する手続き |
| 弁護士 |
相続トラブル、相続放棄など相続全般 |
| 金融機関 |
預金口座の解約手続き、相続財産の管理・運用 |
| 行政書士 |
戸籍の収集や書類作成、自動車の名義変更など |
| 市役所 |
国民年金や国民健康保険、介護保険などの手続き |
相続税がかかるか知りたい、もしくは相続税の申告や財産評価など税金に関する相談は、税理士に相談しましょう。
また、登記のプロである司法書士は、不動産の相続登記だけでなく、預貯金や有価証券などの遺産整理を取り扱っていることもあります。
何から始めてよいか分からない場合は、行政の相談窓口や初回無料相談を実施している弁護士を活用してもよいでしょう。
まとめ
相続財産が少ない場合でも、相続税の申告の要否は、基礎控除額を超える相続財産があるかどうかで決まります。
相続税の課税対象となる相続財産を算出するには、被相続人の債務や葬儀費用、生前贈与などをもとに計算することが必要です。
また、基礎控除額を超える相続財産がある場合でも、配偶者控除や相似相続控除、小規模宅地等の特例など、相続人や相続財産によってさまざまな特例が使える可能性があります。
ただし、これらの特例には、相続税が発生しなくても、申告手続きをしなければ適用されないものもあるため注意が必要です。
また、相続財産が少なく借入金がある場合、負債も承継することになるため、相続放棄を検討することも必要です。さらに、相続財産に不動産が含まれている場合、不動産を承継した相続人は相続登記をしなければなりません。
このように、相続財産や相続人、適用する特例などによって、相続税の申告だけでなく、必要な手続きは変わります。相続手続きに不安がある方は、早めに、弁護士や税理士などの専門家に相談するとよいでしょう。