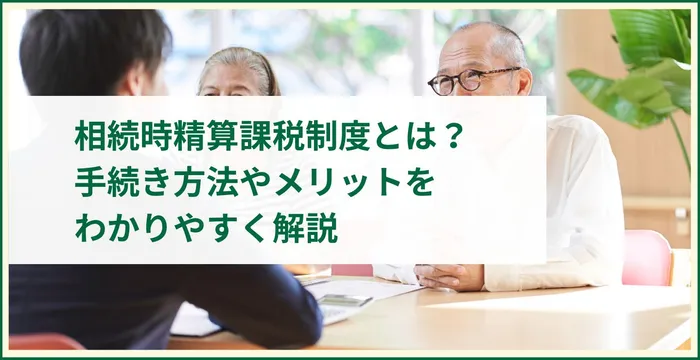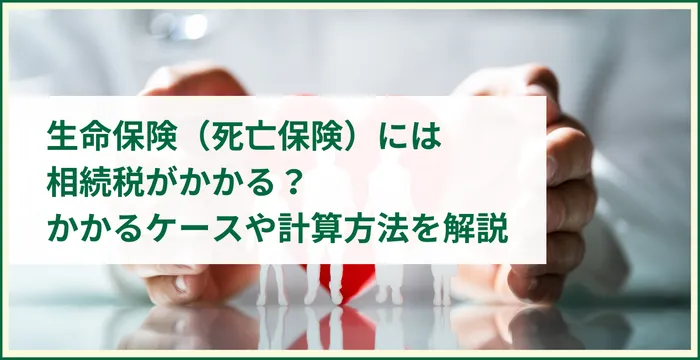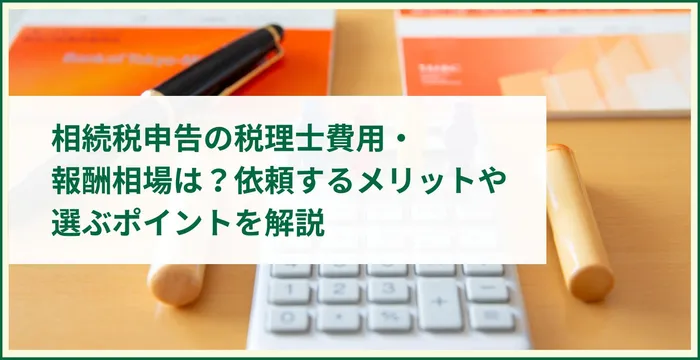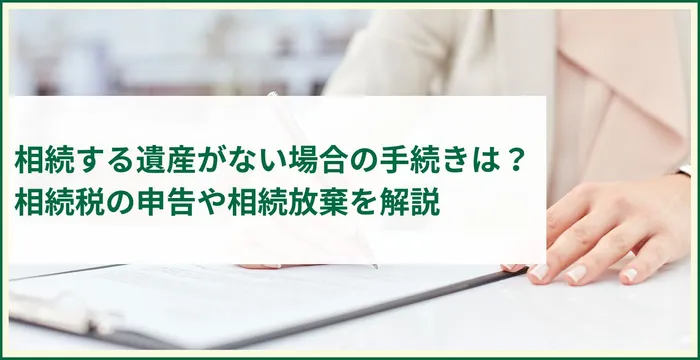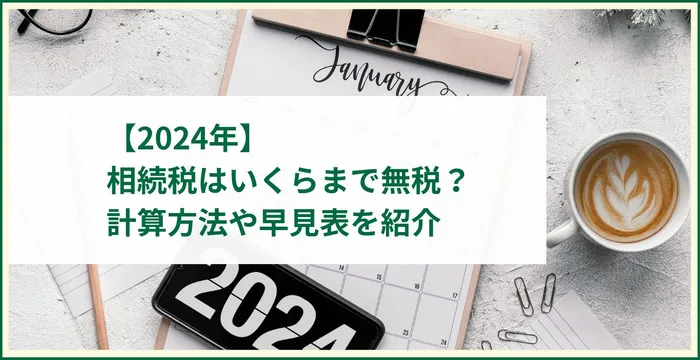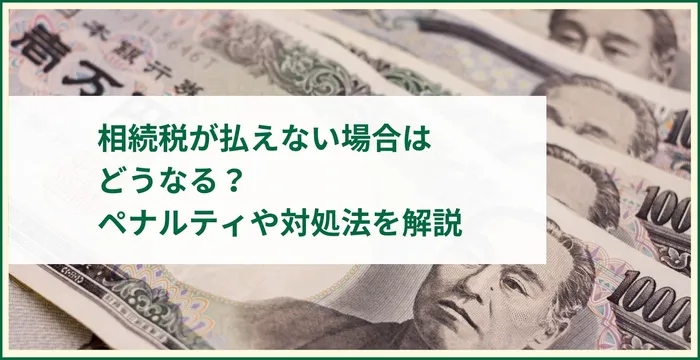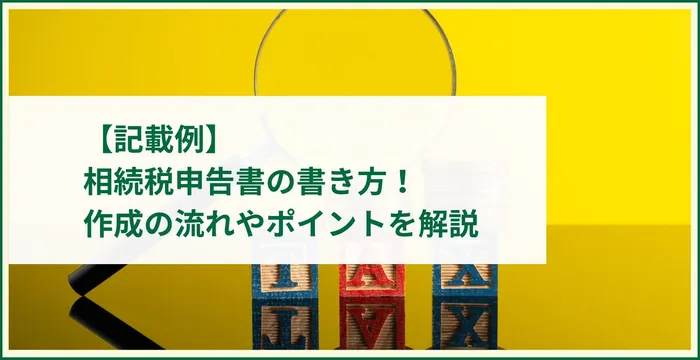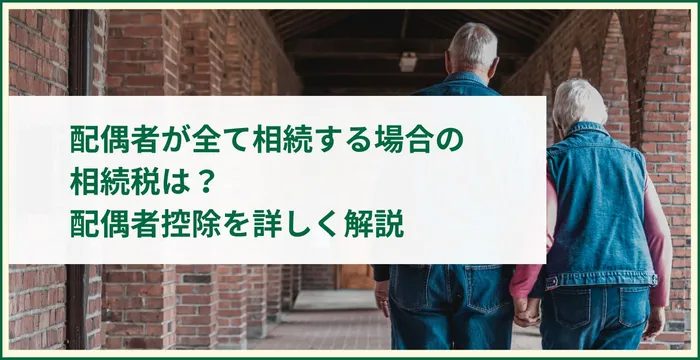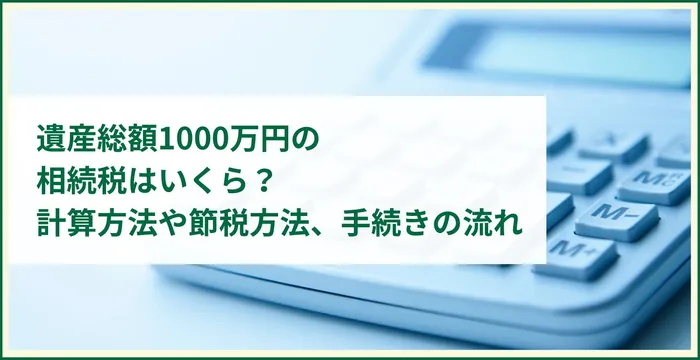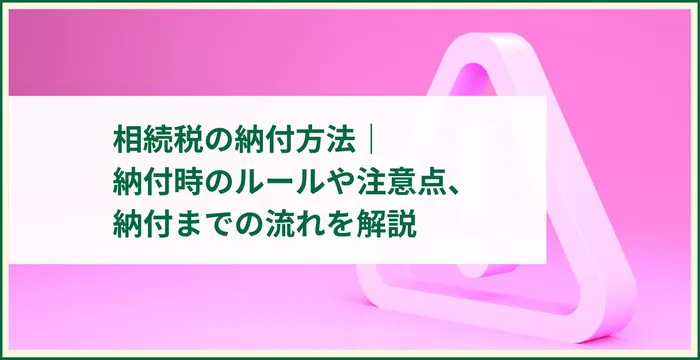知っておきたい相続税対策
相続税対策の基本的な考え方は、2つのステップで把握できます。
- 税法上決まっているシステムを理解する(控除・非課税枠など)
- 亡くなった際に受け取る相続財産自体を減らす方法を知る(生前贈与・生命保険など)
1は節税全体に関する考え方です。
国が定めた法律上、相続税が軽減される措置は豊富に用意されているので、それを最大限活用するだけでも、大きな節税効果が期待できます。
2は自分たちで準備することで行える節税方法です。
同じ価額の財産であっても、亡くなったときに全額を受け取るより、生きている間に分散させておいたほうが、支払う税金の総額が大幅に節約できるという前提で読み進めると、理解しやすいと思います。
ここからは、相続税対策に有効な方法を13こお伝えしていきます。
誰でもできる基本的な節税対策から裏技的な方法まで、取り組みやすい順番にご紹介していきます。
本記事でご説明すること
- 基本的な節税対策:暦年贈与・相続時精算課税
- 税法上の控除:住宅や配偶者などの特例
- 生命保険の活用
- 裏技的な方法:アパート経営・養子縁組 など
それでは、ひとつずつ解説していきます。
毎年110万円の基礎控除額がある「暦年贈与」を活用する
まず、相続税対策の中で最も簡単に取り組みやすいのが、暦年贈与(れきねんぞうよ)の活用です。
暦年贈与とは、「1年間に行う贈与が基礎控除の110万円以下におさまる場合、贈与税がかからないという税法上のシステムを利用した贈与方法です。
毎年1月1日〜12日31日までに他者から譲り受けた財産が110万円以下であれば、贈与税を納める必要がありません。
したがって、生きている間に毎年110万円ずつ振り込んでいれば、税金は0円になります。
(例)贈与者の親から、受贈者の子供へ1,000万円の財産を譲り渡す場合
| 死亡時に1,000万円まとめて相続する |
相続税が発生する |
| 生前に10年間かけて、毎年110万円以内におさまる金額を贈与しておく |
贈与税・相続税ともにかからない |
贈与税は1年間の合計金額で計算するので、回数に制限はなく「全部で110万円以内」であれば、基礎控除内におさまります。
ただし、暦年贈与には3つの注意点があります。
1つ目は、金額のカウントは贈与者ごとではなく、受贈者ごとに行われることです。
たとえば父母からそれぞれ100万円ずつ受け取った場合は、1年間の受け取り合計金額が200万円になるので、基礎控除を上回った90万円分に贈与税がかかってしまいます。
2つ目は、毎年決まった時期に決まった金額で送り続けていると定期贈与とみなされて、贈与税が発生する可能性があることです。
定期贈与に判定されないよう、以下の点を意識して贈与を行いましょう。
- 毎年振り込む時期をずらす
- 金額を変える
- 贈与をするたびに贈与契約書を作成する
3つ目は、相続発生から3年以内の贈与が相続財産とみなされる生前贈与加算というシステムです。
相続税のルール上、贈与者が亡くなった際、その年から遡って3年間の贈与が相続財産扱いになります。
これを回避するためにも、暦年贈与は贈与者がなるべく元気なうちに始めましょう。
当然、人が亡くなるタイミングは誰にもわからないものですが、高齢になってから・病気になってから慌てて始めると、早く亡くなってしまった場合、結果的に生前贈与加算の対象になってしまいます。
また、暦年贈与はわかりやすい控除である一方、多額の贈与をしたい場合には適していないのと、贈与契約書を都度作成する必要があり、手間がかかるという点には注意しましょう。
相続時精算課税制度を活用する
次に、相続時精算課税制度についてご説明します。
これも生前贈与に関係する制度で、自分で申請することで利用できます。
相続時精算課税の特徴は、以下の2点です。
- 生前贈与のうち、2,500万円までは贈与税を支払わずに受け取れる
- 贈与者が亡くなった時点で、生前贈与額と相続で得た資産を合算し、一括で相続税として支払うことができる
相続時精算課税制度は、贈与者が生きている間にまとまった金額を受け取りたい場合に有効です。
暦年贈与では毎年110万円までしか控除がないため、たとえば2,500万円を一括で贈与すると、課税対象額は2,390万円になり、1年間で810万円もの贈与税を納めなければなりません。
(※直系尊属で20歳以上の特例税率を適用した場合の計算)
まとまったお金が必要でもらったはずなのに、すぐに多額の税金を支払わなければならないとなると、納税の負担で生活が苦しくなってしまうかもしれません。
しかし、相続時精算課税制度を利用すると、もらった段階では税金は発生せず、その後贈与者が亡くなった際にまとめて税金を納めることになるため、納税の負担感が減ります。
相続時精算課税制度の計算式
(「1年間の贈与額-年間110万円の基礎控除」の累計額-2,500万円の特別控除)×20%
こちらの制度でも、暦年贈与と同じように、毎年110万円の基礎控除があります。
また、贈与者が亡くなり相続財産と合わせて計算した結果、相続税が発生しなかった場合は、遡って贈与税が発生するということもありません。
なお、この制度が適用されるのは、ひとりの贈与者が亡くなるまでに受け取った合計金額が2,500万円に達するまでなので、2,500万円以内であれば、生前に何度受け取っても贈与税はかかりません。
また、暦年贈与にするか相続時精算課税制度にするかは、贈与者ごとに選択できますので、「父からの贈与は相続時に精算・母からの贈与は暦年贈与で毎年控除を受ける」といったことも可能です。
その他、大きな節税効果が期待される場面としては、「所有している財産の評価額が将来上がる見込みである」というケースが挙げられます。
相続時精算課税を利用した場合、生前贈与された財産の評価は、贈与時の評価額で計算されます。
たとえば、現在の評価額が5,000万円の土地を子供に相続したいと考えていて、その土地の評価額が将来7,000万円くらいまで上がりそうだという場合を考えてみましょう。
その土地が実際に7,000万円まで上がったあと相続するのでは、当然、その全額に相続税が課されます。
しかし5,000万円の時点で、相続時精算課税を選択したうえで生前贈与を受けていれば、相続時に7,000万円に上がっていたとしても、相続税は贈与当時の5,000万円で計算されます。
このように、大きな財産を引き継ぐ際には大変魅力的な制度ですが、注意しなければならない点もあります。
- 一度選択すると、暦年贈与には戻せない
- 2,500万円を超過した分には20%の贈与税がかかる
- 土地の贈与を受ける場合、特例が受けられない+取得にコストがかかる など
土地の相続に関しては「小規模宅地等の特例」という控除もあります。
しかし相続時精算課税制度を利用すると、この特例は受けられなくなります。
また、不動産の生前贈与は、不動産取得税や登録免許税にコストがかかり、毎年の固定資産税も発生しますので、相続時精算課税制度と小規模宅地等の特例のどちらが得になるか、よく考えたうえで選択しましょう。
参照:相続時精算課税の選択|国税庁
小規模宅地等の特例制度を活用する
ここからは、特定の人や用途に限定して適用される贈与税の特例についてご説明していきます。
まずは前項で出てきた小規模宅地等の特例です。
これは、亡くなった方の家族がその土地に住み続けたり、事業を続けたりできるよう、土地の相続税評価額を最大80%減額する制度です。
小規模宅地等の特例は、大きく分けて3つに分類されており、特定の要件を満たすと適用されます。
土地の用途によって平米数や減額率が異なるので、確認しておきましょう。
| 土地の種類 |
限度面積 |
減額率 |
適用要件 |
特定居住用宅地等
(住宅として使われていた土地) |
330㎡ |
80% |
・故人や生計一親族が住んでいた土地を配偶者が相続する
・同居の親族が相続した土地に住み続ける
・生計一親族が相続した土地に住み続ける |
| 特定事業用宅地等(事業で使われていた土地) |
400㎡ |
80% |
・相続開始3年前よりも以前からその土地で事業を営んでいる
・相続人が相続税の申告期限まで事業を継続している |
| 貸付事業用宅地等(不動産貸付業に使われていた土地) |
200㎡ |
50% |
・相続開始前からその土地で不動産貸付業を営んでいる
・相続人が相続税の申告期限まで不動産貸付業を継続している |
この特例が適用されると、土地に対する相続税の評価額そのものが下がり、相続税の計算に関わる税率が下がったり、場合によっては相続税が0円になることもあります。
(例)法定相続人が3人 居住用の5,000万円の土地が80%減額された場合
→評価額は1,000万円
相続税には基礎控除「3,000万円+(600万円×法定相続人の人数)」があり、法定相続人が3人の場合は、4,800万円までであれば、相続税はかかりません。
土地が1,000万円まで下がれば、他の財産を足しても基礎控除以内におさまる可能性も高く、そうなれば相続税は0円になります。
もし控除内におさまらなかった場合でも、課税対象額が少なければ、他の相続人の税金も含めて税率が下がりますので、いずれにせよ大きな節税効果が期待できます。
この特例は、二世帯住宅に一緒に住んでいて、家計や住民票を分離していた場合でも適用になります。
なぜならば、同じ家屋に住んでいる親族という要件に当てはまるからです。
ただし、以下のようなケースでは、二世帯住宅であっても特例が適用にならないので注意しましょう。
- 居住部分を親子で別々に区分登記している
- 建物の構造上「1棟」とは言えないもの
たとえば、2つの建物を渡り廊下でつなげているだけで、実質2棟であるといった場合は、同居の要件に当てはまらない可能性があります。
小規模宅地等の特例制度が使えるかは、税法や建築基準法などの専門知識が必要になるため、税理士に相談することも検討してみてください。
国税庁のホームページには、ご紹介した3種類に加えて、さらに細かい利用区分や要件による限度面積と減額率が記載されています。
参照:相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁
贈与税の配偶者控除を利用する
贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)です。
これは、配偶者に居住用の不動産(またはその購入資金)を贈与する際、2,000万円まで非課税になるという制度です。
以下の要件を満たすと控除が適用されます。
- 婚姻関係が20年以上ある
- 贈与のあった年の翌年3月15日までに居住用不動産に住み、その後も住み続ける
つまり、マイホームとして購入していた家に、自分が亡くなったあとも配偶者が住み続けられるよう、2,000万円までは相続税が課されないようになっているということです。
暦年贈与と併用すれば、非課税枠が最大2,110万円まで拡大します。
ただし、相続時精算課税制度と同様に、住居取得にかかるコストが高くなることに注意しましょう。
結婚子育て資金の一括贈与特例を活用する
結婚子育て資金の一括贈与特例を利用すると、親や祖父母から結婚や子育てのための資金を一括で贈与された場合、1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。
利用には、受贈者が18歳以上、50歳未満であるという要件があります。
この制度のメリットは、1,000万円(結婚費用は300万円)までの財産を一括で非課税で贈与できるという点です。
子供の医療費や保育費用はもちろん、不妊治療や不妊治療や妊婦検診に要する費用も対象です。
| 1,000万円枠の対象 |
不妊治療・妊婦検診に要する費用・分娩費・産後ケアに要する費用・子の医療費・幼稚園や保育所等の保育料(ベビーシッター代含む) など |
| 300万円枠の対象 |
挙式や衣装代等の婚礼費用(婚姻の日の1年前の日以後に支払われるもの)・家賃・敷金等の新居費用、転居費用(一定の期間内に支払われるもの) など
|
両方合わせて合計1,000万円までが非課税です。
(1,000万+300万円ではないので注意しましょう)
制度を利用するには、銀行などの金融機関受け取り専用の口座を準備し、贈与された金額を金融機関に預けておく必要があります。
引き出しの際には、結婚または子育て資金に使ったことが証明できる領収書を提出しなければなりません。
領収書がないと非課税が適用されませんので、紛失しないように気をつけましょう。
その他注意事項として、結婚子育て資金として認められない場合は贈与税が課税されることと、50歳に達した段階で口座に残高がある場合、贈与税が課されるが課せられるという点に注意しましょう。
制度の詳細は、国税庁ホームページのパンフレットをご覧ください。
父母などから結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁
教育資金の一括贈与制度を活用する
生前に大きな贈与を受ける際には、子供の教育資金の一括贈与制度も有効です。
これは、父母や祖父母が30歳未満の子・孫に教育資金を贈与する場合に、最大1,500万円まで贈与税がかかりません。
| 1,500万円枠の対象 |
入学金・授業料・入園料・保育料・施設設備費・入学(園)試験料・学用品費・修学旅行費・学校給食費 など
|
| 500万円枠の対象 |
学習塾や習い事などの授業料・習い事に使用する物品の購入に要する費用・学校教育等に必要な費用で、学校等が必要と認めたもの(例:オンライン授業用のパソコン購入費)・通学定期券代・留学渡航費・転入学に伴って転居した際の交通費 など
|
こちらも両方合わせて最大1,500万円で、結婚・子育ての特例同様、専用の口座を開設して利用します。
受贈者が30歳になったところで契約は終了し、残高が残っていれば、その分には贈与税がかかります。
以上見てきたとおり、用途や対象者を限定した特例では、暦年贈与を上回る大きな金額が非課税になります。
また、暦年贈与の場合は、渡したお金の使い道が決められませんが、特例を適用する場合は用途以外の無駄遣いの心配も少なくなります。
お墓や仏具などを生前に購入する
お墓や仏具などの祭祀財産は、非課税財産に該当するため、相続税がかかりません。
(相続税法第12条で「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は課税価格に算入しない」と定められています)
したがって、お墓や仏具などを生前に購入しておくことも、相続税対策のひとつになります。
条件としては、相続発生前(亡くなる前)に購入し、支払いまで済ませておく必要があります。
相続発生後(亡くなったあと)に購入すると非課税財産扱いにはならないので、注意しましょう。
その他、注意点としては2つ挙げられます。
まず、お墓や仏具をローンで購入した場合、債務控除の対象にならないという点です。
債務控除とは、相続財産の価額から、亡くなった方が残した借金などの債務や、お葬式にかかった費用を差し引いて相続税を計算することができる控除のことを言います。
しかし、お墓などは非課税扱いですので、債務控除の計算には入りません。
また、骨董価値があるものは、仏具だったとしても課税対象になってしまいます。
たとえば、純金の仏像を生前に購入し、相続後に売却するなどのケースでは、非課税扱いになりません。
のちに発覚すると追加の税金を支払わなければならない可能性もありますので、投資目的で過度に高額なものを購入するといったことはやめましょう。
生命保険などの非課税枠を活用する
続いては、生命保険などの非課税枠を活用する方法です。
生命保険金には相続税の非課税枠があり、生命保険金の金額から「500万円×法定相続人の数」を差し引いた金額には、相続税がかかりません。
(例)法定相続人が3人の場合
非課税枠:500万円×3人=1,500万円
現金で1,500万円を受け取ると相続税が発生しますが、1,500万円の生命保険金であれば、相続税はかかりません。
また、生命保険金は受取人の指定ができますので「家族の中で特定の誰かに1,500万円相続させたい」ということが決まっている場合は、生命保険に加入するのは大きなメリットになります。
また、生命保険金は亡くなった段階で支払われるものですので、遺産分割協議前でも受け取ることができますし、相続放棄の手続きを行って相続人から外れたとしても、生命保険金はそのまま受け取れます。
※相続放棄とは:亡くなった方の財産(債務含む)を一切相続しないこと
生命保険を利用した相続税対策は節税額が大きい一方、デメリットも存在します。
- 非課税枠は相続人しか使えない
- 遺産分割トラブルが発生するリスクがある
まず、非課税枠は法定相続人にしか適用されないため、たとえば家族以外の方を受取人にした場合は、この控除が使えず、受け取った生命保険金に対して相続税がかかります。
また「特定の人に決まった金額を渡す」という性質上、家族間で不公平が生まれ、相続トラブルに発展するリスクもあります。
生命保険の非課税枠を使って相続対策を行う場合は、受取人に指定する予定の方以外の法定相続人ともよく話し合い、全員が納得したうえで受取人を指定することをおすすめします。
生命保険金の受け取り方を一時所得にする
上記の非課税枠を使い切った場合でも、まだ生命保険を利用して節税できる方法があります。
それが、生命保険を一時所得として受け取れるように契約することです。
生命保険の契約には、契約者・被保険者・受取人という3つの立場があります。
- 契約者:保険料を支払う人
- 被保険者:支払いの対象となる人
- 受取人:被保険者が亡くなったときに保険金を受け取る人
契約者と受取人が同一の場合、一時所得(臨時収入)扱いとなるため、相続税ではなく所得税が課税されます。
(例)妻が亡くなったときに備えて、夫が契約し、夫自身を受取人とする
一時所得に課せられる税金は、いままで支払った保険料と、特別控除の50万円を差し引いた金額を半分に割るという計算式で算出されるため、普通に相続で受け取るよりも節税に繋がります。
(計算式)
課税所得金額=(受け取った死亡保険金額-支払った保険料-特別控除額 50万円)×1/2
たとえば、保険金3,000万円・保険料の総支払額が400万円の生命保険を契約していた場合、上記の計算式に当てはめると、課税対象額は1,275万円で済みますので、大きな節税効果が期待できます。
ただし、生命保険を一時所得として受け取る場合、金額によって、所得税の確定申告が必要になる場合があります。
これを忘れてしまうと、罰則として追加の税金を支払わなければならなくなるため、必ず申告しましょう。
詳細は国税庁のホームページをご覧ください。
参照:所得税の申告|国税庁
祖父母と子・孫の間で生命保険を活用する
生命保険を子や孫にかけるのも、相続税対策になります。
方法は以下の2つがあります。
- 保険料相当額を生前に贈与しておき、子や孫が支払う
- 子や孫に生命保険をかける
ひとつずつ見ていきましょう。
保険料相当額を生前に贈与しておき、子や孫が支払う
まずは、保険料相当額を生前に贈与しておき、亡くなったあとに子や孫が支払うという方法をご説明します。
この方法を取ると、生きている間にもらう金額に贈与税がかかりますが、亡くなった際には相続税がかかりません。
さらに、1年間の贈与金額を暦年課税の基礎控除110万円以内におさめてこまめに贈与をしていけば、贈与税も掛からなくなります。
前述したとおり、契約者と受取人が同一の場合、一時所得として所得税が発生する場合がありますが、普通に現金で1,000万円を相続するよりは支払う税金の総額は格段に抑えられます。
この方法が使いやすいケース:被相続人の生前から準備をしておけるとき
子や孫に生命保険をかける
まずは、親が父母が契約者となって、子や孫に対して終身の生命保険をかけるという方法です。
この方法では、解約返戻金を利用することで節税します。
保険契約は、契約者が亡くなると、その契約は相続財産として法定相続人に受け継がれます。
支払い者が亡くなった時点で払込年数が少ない段階で亡くなった場合は、そのときの返戻金が相続評価額になります。
具体例を挙げて、シミュレーションしてみましょう。
(例)
保険契約:年100万円の支払い・9年目までは返戻金が0円・10年目になると1,000万円になる終身保険
相続発生時:契約者(親や祖父母)が契約から8年目に亡くなった
9年目までは返戻金が0円という契約ですので、8年目時点で子供や孫に相続された場合、生命保険の評価額は0円なので、相続税がかかりません。
では、このようにして契約者が子や孫になったあと、返戻金がもらえるまでの2年間、200万円分の保険料を子供や孫自身が保険料を支払い、10年目で解約した場合どうなるでしょうか?
10年目の解約時に受け取れる金額
解約返戻金1,000万円ー子供が支払った保険料200万円=800万円
この800万円は契約者である子や孫の所有財産ですので、当然相続税がかかりません。
この方法が使いやすいケース:贈与者の余命がわずかで、返戻金が0円のうちに亡くなりそうだというとき
家族信託を活用する
ここからは、相続税・所得税の控除や非課税枠以外で、相続税対策を行う方法をお伝えしていきます。
まずは、家族信託を活用する方法です。
家族信託とは、財産の運用や管理・処分などを家族に任せることができる制度です。
主な目的は「認知症などになって判断能力が低下してしまった際に、預貯金が引き出せないといった事態を防ぐため」の制度ですので、直接的な節税効果あるわけではないのですが、うまく利用すれば相続税対策に繋がる場合があります。
通常、財産の運用・売却・譲渡などは本人しか行えませんが、生前にあらかじめ家族信託の契約をしておくと、本人に代わって家族が資産全般の管理が行えるようになります。
ここまでお伝えしてきたとおり、相続税対策のメインは、生前に本人の意志があるうちに贈与等を行い、亡くなった際に発生する相続財産自体を減らしておくことです。
しかしこの方法は、万が一本人が相続税対策を行う前に認知症などになってしまった場合、一切できなくなってしまいます。
それを防ぐため、家族信託を契約しておけば、本人の判断能力がなくなってしまったあとも、代理人となった家族が相続税対策を行うことができるということです。
また、家族信託を利用すれば、二次相続の対策もできます。
二次相続とは、たとえば父親が亡くなり妻と子が財産を相続したあと、妻が亡くなることで子に発生する、二度目の相続のことを指します。
通常の遺言書では二次相続までは指定できませんが、家族信託契約の際に受益者(財産収入を得る人)を指定しておけば、二次相続対策も可能です。
一点注意したいのは、家族信託で財産管理ができるのは受託者(本人に代わって財産管理できる人)に指定された人しかできないということです。
法定相続人が複数いる場合、一部の受託者だけが財産管理の権限を持っている=不公平感からトラブルに発展する可能性があります。
また、受託者が財産を使い込んでしまう可能性もあるため、家族信託を契約する際には、他の相続人とよく話し合い、全員が納得できる形で利用できるようにしましょう。
アパートなど不動産経営を始める
土地を持っている場合、アパートやマンションなどの賃貸物件の不動産経営を始めると、節税できる可能性があります。
まず、アパートなどの経営を始めると、借地権割合・借家権割合等で不動産評価額が下がります。
加えて小規模宅地特例を適用すると「貸付事業用土地」になり、最大50%減額されます。
また、アパートなどを建てる際にローンを組むと、さらに節税効果が期待されます。
通常の借入では単純に現金が増えるだけですので、相続時にはその金額に相続税が課されます。
しかし、借り入れた資金でアパートやマンションなどを建設すると、相続税の計算は建てた物件の固定資産評価額を基準に行われます。
固定資産評価額は現金より低い評価額になるため、同じ金額でも、現金で相続するより建物として相続したほうが税金が安くなります。
養子縁組をして法定相続人の数を増やす
最後に、養子縁組をして法定相続人を増やす方法をお伝えします。
養子縁組とは、手続きによって法律上親子関係になれる制度です。
法定相続人が増えると、相続税の基礎控除をはじめ、相続人の人数が関係する控除や非課税額の上限を引き上げることができます。
法定相続人の人数で決まる控除と非課税枠
- 相続税の基礎控除:3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
- 生命保険金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税枠:500万円×法定相続人の数
相続税対策として養子縁組を行う場合、孫を養子にするケースが多いです。
孫を養子縁組するケースの例
- 被相続人(本人)・相続人(子)ともに高齢:現役世代の孫を子供することで相続の心配が減る
- 子が多くの財産を持っている:孫が将来相続する資産と相続税が莫大になるのを防ぐ
相続税対策で養子縁組をする場合、以下の3点に注意が必要です。
- 法定相続人の増加人数には制限がある
- 相続税対策のための養子縁組は否認される場合もある
- 遺産分割協議で揉めてしまう可能性がある
養子縁組には人数制限があり、実子がいる場合は1人、いない場合は2人までです。
また、明らかに相続対策のためのみに組まれた養子縁組であると判定された場合、法定相続人含めることが認めれない場合もあります。
そして、これは心情的な問題ですが、税金対策のためだけに子や孫の人生を左右する決断をしていいのかは、本人の気持ちも含めて十分に検討する必要があります。
急に法定相続人が増えたことにより、本来の相続人の間で不満が出て、結果、遺産相続分割が揉めてしまうことも考えられます。
養子縁組を検討する際は、親族全体の問題としてよく話し合い、全員納得したうえで行いましょう。
トラブル防止にも!相続税を節税する際のポイント
相続税対策をする際にの考え方として、以下のポイントを踏まえると、トラブルに繋がりにくくなります。
- 老後資金を考慮する
- 相続税対策に強い税理士に依頼する
ひとつずつ見ていきましょう。
老後資金を考慮する
ここまで見てきたように、相続税対策の主な方法は、生前贈与や生命保険などを駆使して「相続時の財産を減らしておくこと」です。
しかしこれをやりすぎると、本人が生きている間に必要な老後資金が減り、生活に支障が出る可能性もあります。
死後のお金を蓄えるために、生きている間に必要なお金を削って生活しなければならないとしたら、それは本末転倒です。
相続税対策を行う場合は、老後の生活に必要な金額を算出し、余剰部分で節税できないかを考えるという順番で検討しましょう。
相続税対策に強い税理士に依頼する
相続税の計算は、いくつもの控除や非課税枠があるため、複雑化しやすいです。
節税するためには、相続の実績が豊富な税理士に依頼しましょう。
「専門家に頼むと費用がかさむのでは?」と身構えてしまう方もいるかもしれませんが、控除や非課税枠が適用されれば、納めるべき税金の額が減りますし、基礎控除内におさまって相続税が0円になることも十分に考えられます。
無理に自力で計算して余計な税金を払うことになるよりは、税理士に依頼したほうが結果的に安く済むことが多いので、税理士に依頼するのはおすすめです。
なお、同じ税理士であっても、必ずしも相続対策に詳しいとは限りません。
たとえば、誤って会社経営が専門の税理士に頼んでしまうと、十分な節税効果が得られない可能性もあります。
ホームページや口コミを調べ、相続実績がある税理士に依頼するようにしましょう。
家族間の相続争いの対策も重要
最後に、家族間の相続争いを回避する方法について解説していきます。
相続人同士で揉めないように、以下の4点を意識して相続の準備をしましょう。
- 生前に意思を伝えておく
- 遺言書を残す
- 相続財産の一覧を作成しておく
生前に意思を伝えておく
相続に関しては、本人ひとりで決めるのではなく、日常的に家族間で話し合えるよう、コミュニケーションを取っておくことが大切です。
本人側からの「この自宅は誰に相続させたい」という希望や、相続人側からの「車は生活に必要なので相続させてほしい」といった希望を伝えておくなど、ミスマッチが起きないようにしましょう。
将来的に相続対象となる財産については、内容や現在の管理方法についても普段から共有し合い、不公平感に繋がらないように対策をしておくのも大切です。
遺言書を残す
誰にどの財産を渡すのか、あらかじめ遺言書を作成しておけば、トラブルを防げます。
遺言書の残し方は、3つの方法があります。
- 自宅で保管
- 公正証書にして公証人役場で預かってもらう
- 法務局の遺言書保管制度を利用する
相続人の中でも、同居の有無や介護への貢献度など、本人との関わり方には差があることが多いです。
兄弟姉妹のうち、特に世話になった子供に多めに渡したいなど、希望がある場合はその旨を書いておきましょう。
ただし、不公平な内容だとトラブルになるため、分割の仕方の理由や根拠について、付言事項に詳しく書いておくことをおすすめします。
相続財産の一覧を作成しておく
家族間でのトラブルを防ぐためには、相続財産の一覧を残しておくことも重要です。
相続手続きには時間を要するものが多くあり、中には期限が決まっているものもあるため、相続が発生したらすぐに動き出す必要があります。
しかし、どんな財産があるのかが把握できていない場合、財産調査から始めることになり、日記・郵便物・書類など、様々なものを探して洗い出す必要が出てきます。
また財産に含まれるものは預貯金だけではなく、有価証券・不動産・骨董品や宝飾品など、査定に出さなければ価額がわからないものもあります。
一番厄介なのは、遺産分割協議が終わったあとに、新たな財産や債務が見つかるケースです。
こうなると、所得税の申告と遺産分割協議を、全てやり直さなければならなくなってしまいますので、トラブル防止のため、生前に相続財産の一覧を作成しておくようにしましょう。
この一覧表があれば、節税対策も適切に行えます。
まとめ
以上が、初心者にもわかりやすい相続税対策の方法でした。
改めて相続税対策のポイントをおさらいしてみましょう。
相続税対策の主な方法は以下の4つです。
- 「暦年贈与」や「相続時精算課税制度」など、生前贈与の控除を利用する
- 相続時に適用される「特例」の非課税枠や控除を活用する
- 生命保険に加入し、非課税枠などで節税する
- 家族信託やアパート経営などを行う
相続について話すことは、決して不謹慎なことではなく、家族の未来のために必要なことです。
生前の元気なうちからよく話し合い、将来に備えましょう。