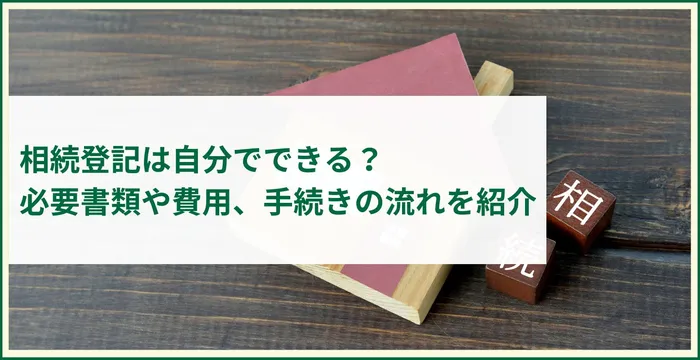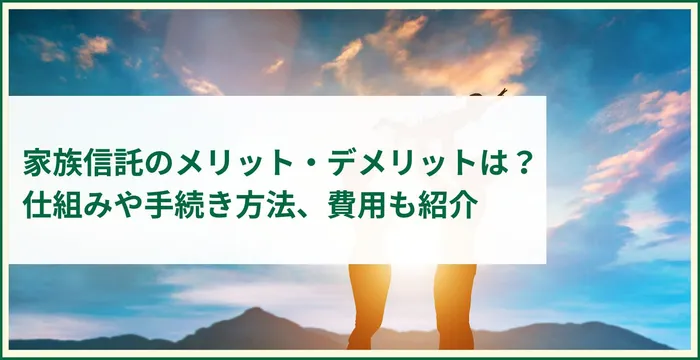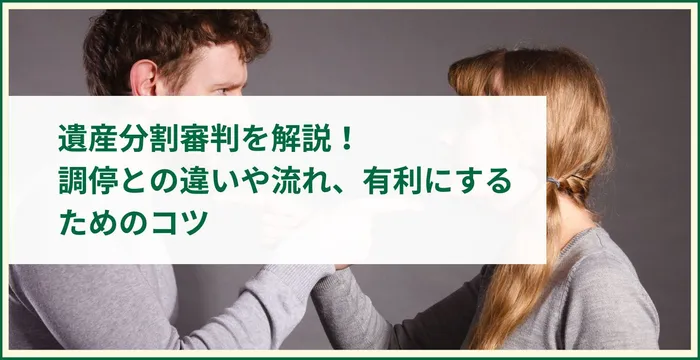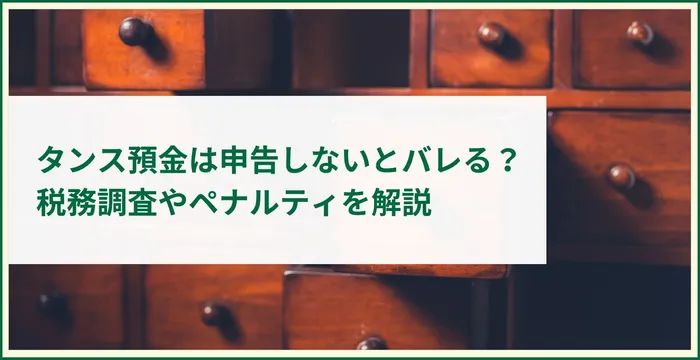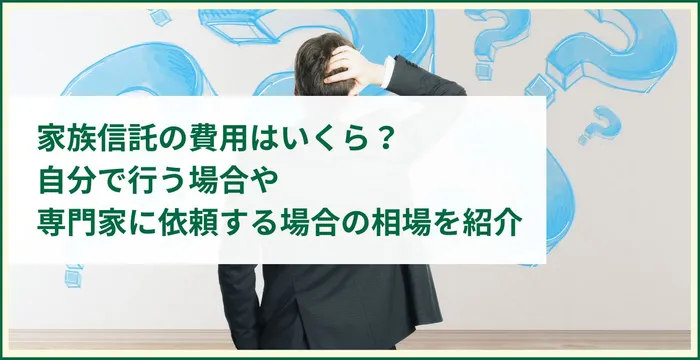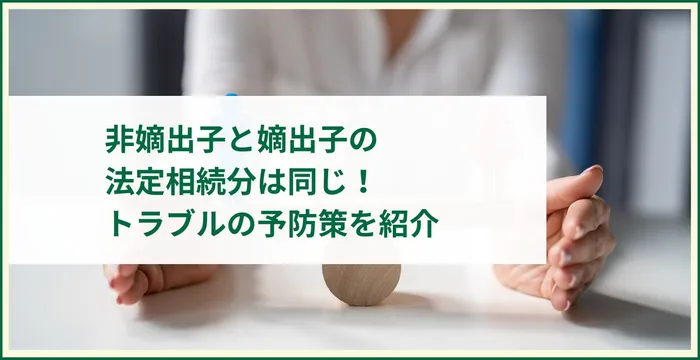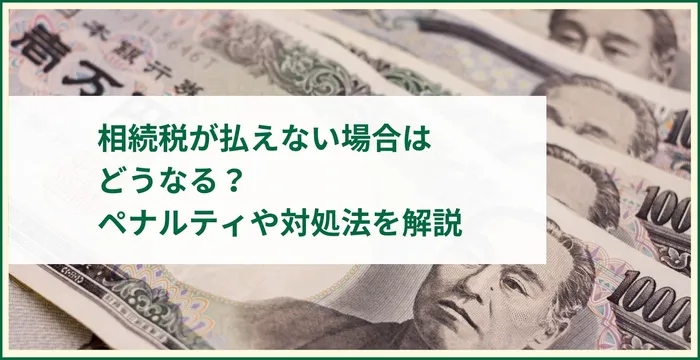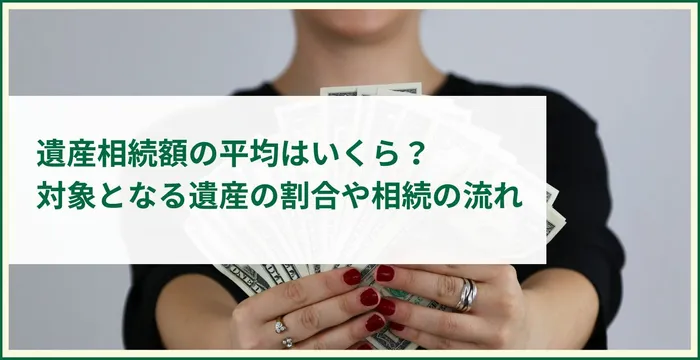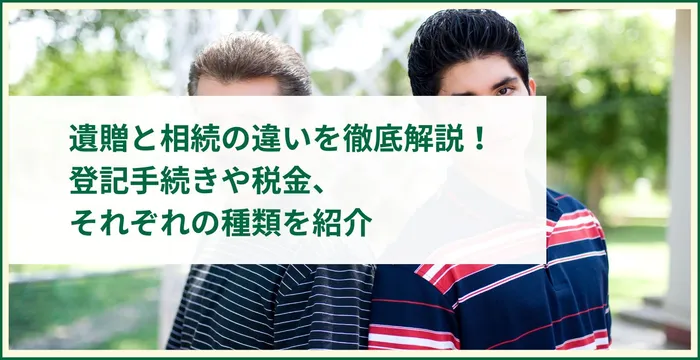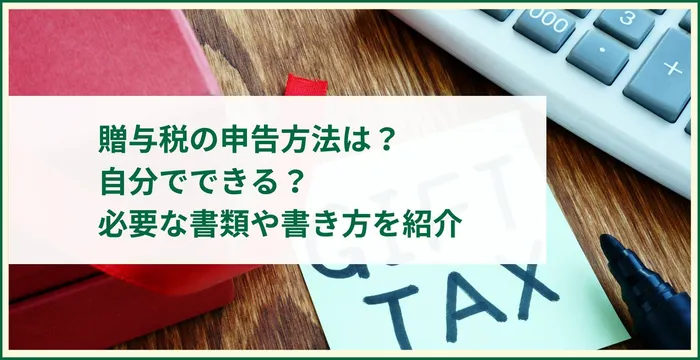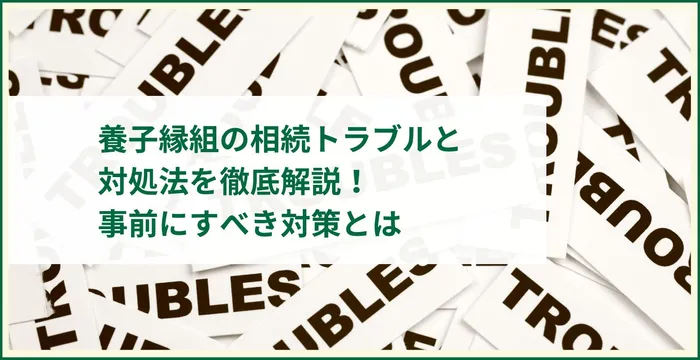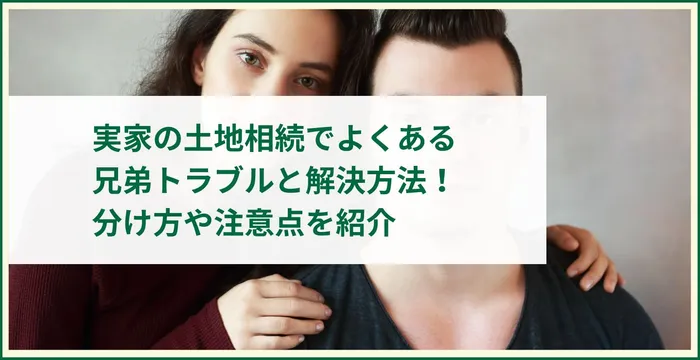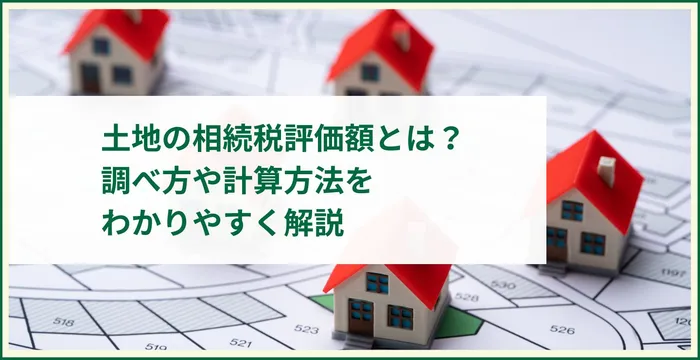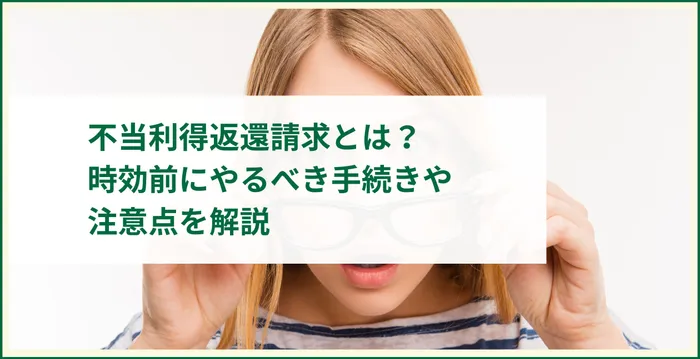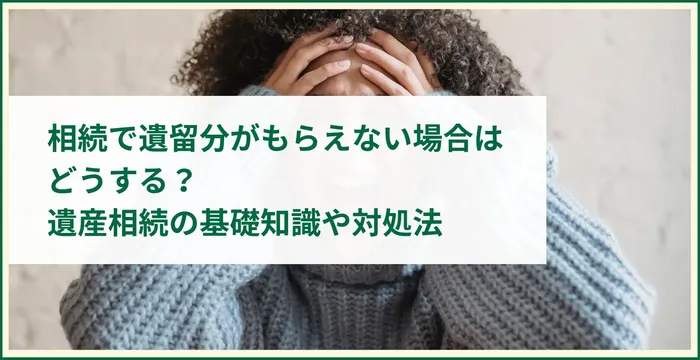相続登記とは亡くなった被相続人から相続した不動産を相続人名義に変更することで、専門家に依頼せず自分で行えばコストを軽減できます。本記事では、相続登記を自分で行う場合の手続きの流れや必要書類、費用などについて解説しています。
相続コラム一覧
カテゴリーから相続コラムを探す
家族信託は、認知症になったとしても資産が凍結されることがなく、成年後見人制度と比べて柔軟に財産管理が行えることから近年認知症対策として注目を集めています。本記事では家族信託のメリット・デメリット、仕組みや手続き方法、費用について解説します。
遺産分割審判と遺産分割調停は異なる手続きです。相続財産にも影響する遺産分割審判の流れや有利にすすめるコツについて解説します。
兄弟一人だけで相続放棄をする場合、他の兄弟の許可を得ずに手続きを進められますが、トラブルに発展する可能性があります。本記事では、相続放棄の手続きの進め方や、兄弟一人だけが相続放棄する際の注意点などについて解説します。
タンス預金は、税務調査でバレてしまいます。発覚すると追加で税金を支払うだけでなく、刑事罰が科されることも。記事では、タンス預金が隠せない理由や税務調査の内容、申告漏れへのペナルティを解説します。
家族信託の費用は、専門家に頼むと30〜60万円程度、自分で手続きするなら信託財産の金額などにもよりますが20万円程度に抑えられます。この記事では、家族信託の費用について解説します。ぜひ参考にしてください。
非嫡出子にも相続権が与えられます。相続割合も、嫡出子と同じです。非嫡出子を含む相続は、トラブルに発展する可能性が高いのが特徴です。この記事では、非嫡出子の相続における問題点や、トラブルに対する解決策を紹介しています。
相続税が払えない場合、無申告加算税や延滞税、差し押さえなどのペナルティを受ける可能性があります。この記事では相続税が払えない場合の対処法について解説します。相続税が払えなくて困っている人はぜひ参考にしてください。
相続放棄は、相続人が権利を放棄する手続きです。主な必要書類は住民票除票と戸籍謄本などであり、相続人によって追加の書類が必要となります。本記事では相続放棄にまつわる必要書類について解説します。
親の遺産額をある程度把握していれば早めに相続の準備や節税対策が行えますが、親に遺産額を直接聞くのは少々気が引けるでしょう。 そこで本記事では、遺産相続の平均額や平均年齢、遺産の内訳や相続の流れについて解説していきます。
他の相続人が何も言ってこずに遺産相続の手続きが勝手に行われていた場合、手続きは無効です。遺産分割協議をやり直しましょう。本記事は相続が発生しているかの確認方法や相続が遅れた場合のリスクを解説しています。
遺贈と相続には違いがあります。 遺贈は第三者や団体・法人などにも継承できますが、相続は相続人に限られます。 本記事を読むと、遺贈の種類や相続・贈与との違いがわかります。 遺言書の種類や記載する内容、遺贈を行う際の注意点も解説します。
贈与税の申告方法や書類の書き方の解説。税金がいくらかかるかや、節税に繋がる特例や控除についても解説します。
亡くなった人が連帯保証人だった場合に、連帯保証債務を相続する可能性があるのは法定相続人です。連帯保証債務の確認方法から相続放棄の可否、知らずに相続した場合の対策まで解説します。
養子縁組が関係する場合、法定相続人が増え、他の相続遺産に影響を与えることからトラブルが起きやすくなります。養子縁組の相続トラブル事例から解決方法、事前にできる遺言書などの対策について解説します。
兄弟間で実家の土地相続トラブルが起こったとき、揉めている原因によって解決方法が異なります。本記事では、実家の土地相続でよくある兄弟トラブルを原因別に紹介した上で、解決方法について詳しく解説します。
相続税評価額とは、財産ごとに決められた計算式に基づいて算出する財産の価額のことです。本記事では、土地の相続税評価額の計算方法や土地の相続税について詳しく紹介します。
相続財産がすでに何者かによって使い込まれていた場合は、不当利得返還請求で取り戻せる可能性があります。不当利得の返還を求める場合にはどんな点に注意すればいいのか、またやるべき手続きや弁護士に依頼する際の費用相場について解説します。
遺言書の内容や生前贈与の有無などによっては、取得できるはずの遺留分がもらえないケースがあります。本記事では、相続で遺留分がもらえなかったときの対処法や、遺産相続の基礎知識などについて詳しく解説します。
家族信託契約書の書き方には、いくつか注意点があります。内容に不備があると、契約書が無効になってしまうためです。この記事では、信託契約書の書き方や自分で作成する際の注意点を解説します。