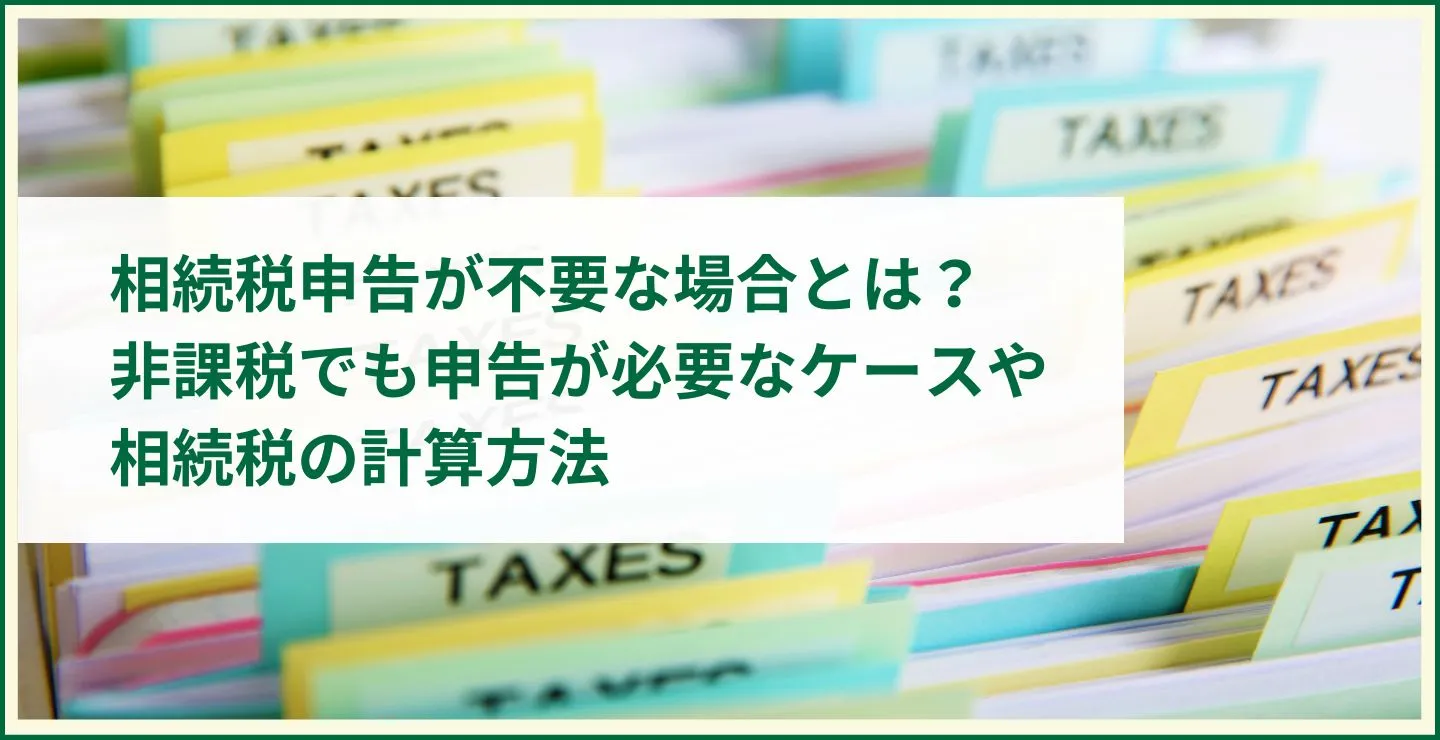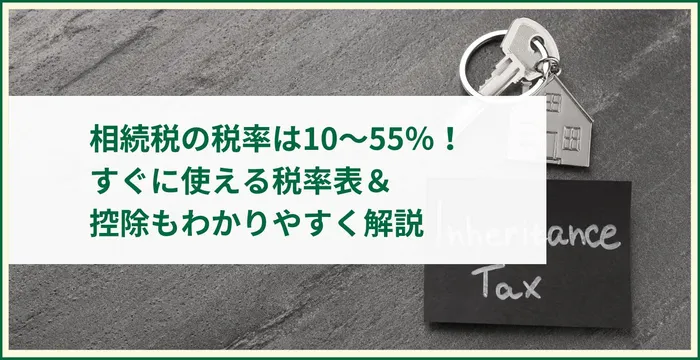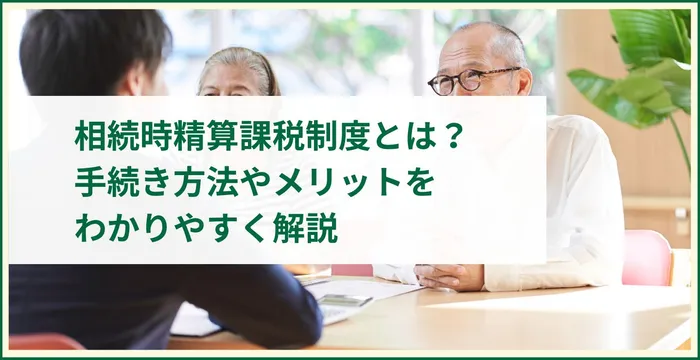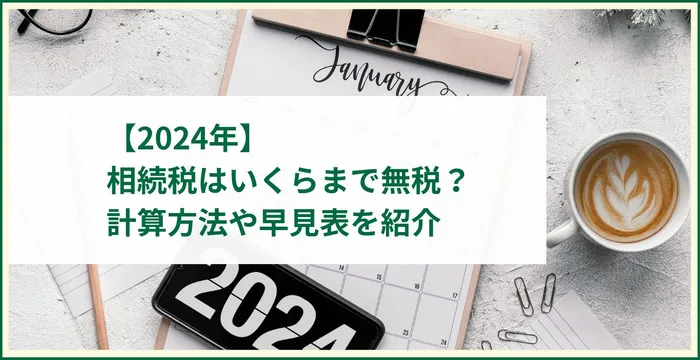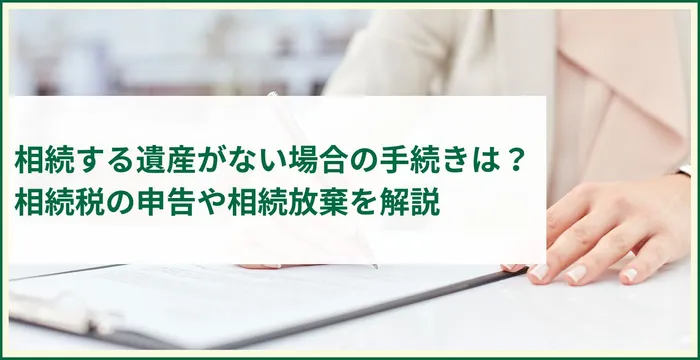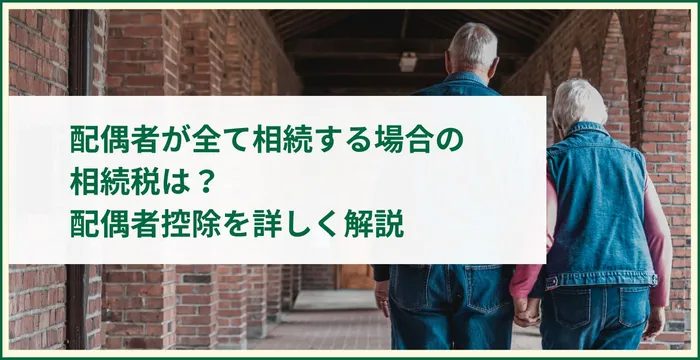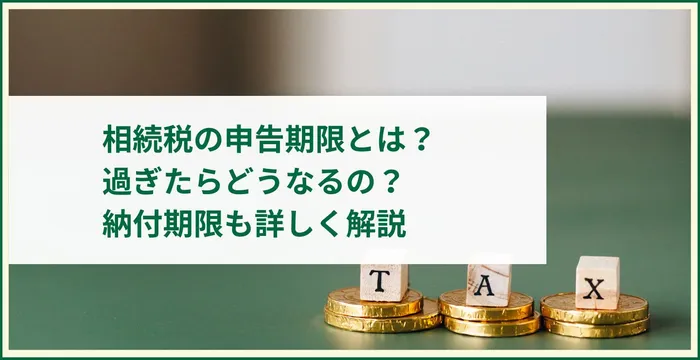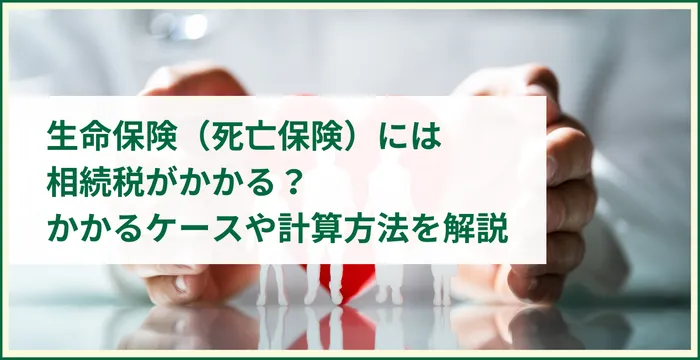相続税申告が不要になる2つのケース
被相続人が亡くなって相続が発生した場合、法定相続人には相続税の申告義務が発生します。
ただし、以下に該当する場合は相続税の申告が不要になることがあります。
- 1.遺産総額が基礎控除額以下の場合
- 2.各種控除が適用され非課税となる場合
それぞれ詳しく解説します。
1.遺産総額が基礎控除額以下の場合
遺産総額が基礎控除額を下回る場合、相続税申告は不要です。
基礎控除とは、相続税が課税される前に適用される控除のことです。基礎控除によって一定額までの遺産が相続税の対象外となります。
なお、相続税における基礎控除の金額は、以下の通りです。
相続税の基礎控除の金額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
つまり、法定相続人の人数が多いほど、相続税の基礎控除の金額は増加することになります。
被相続人が遺した遺産の総額が、基礎控除額を下回っている場合、相続税の申告手続きは不要です。
例えば、法定相続人が3人の場合の基礎控除額は4,800万円に、法定相続人が5人の場合の基礎控除額は6,000万円になります。
被相続人が遺した遺産の総額が4,000万円だった場合、いずれのケースでも基礎控除の金額を下回るため、相続税の申告は不要です。
一方、遺産総額が基礎控除の金額を超える場合は、相続税の申告が必要です。
上記の例でいえば、被相続人が遺した遺産の総額が1億円だった場合、法定相続人が3人いれば基礎向上額の4,800万円を差し引いた5,200万円が相続税の対象となります。
ただし、相続財産の金額が相続税の基礎控除額を超えた場合でも、必ず相続税が発生するとは限りません。相続税には基礎控除以外にも、控除や特例が定められているからです。
詳しくは次の章で解説します。
2.各種控除が適用され非課税となる場合
相続税にて設定されている各種控除や特例によって非課税となり、相続税の申告が不要になるケースもあります。
相続税には、基礎控除以外にもいくつかの控除や税額が軽減される特例が設けられています。
主な控除や特例としては、以下のものが挙げられます。
| 相続税の控除の名称 |
内容 |
| 贈与税控除 |
被相続者が死亡する前3年間の贈与について、贈与税を納めた場合にその前払いした贈与税を相続税から控除できる |
| 配偶者の税額軽減 |
配偶者の想定相続分と1億6,000万円のいずれか多い金額までにかかる相続税を控除できる |
| 未成年者控除 |
法定相続人の中に未成年者がいる場合に、その未成年者の相続税額から一定金額を控除できる |
| 障害者控除 |
法定相続人の中に障害者がいる場合に、その障碍者の相続税額から一定金額を控除できる |
| 相次相続控除 |
今回の相続の前10年間で、今回死亡した人が相続税を支払っていた場合に、一定金額の税額を控除できる |
| 外国税額控除 |
死亡した人の財産が外国にあり、その財産に関して外国で相続税がかかった場合に、相続税から一定金額を控除できる |
| 小規模宅地の特例 |
一定の要件に該当する土地を相続する場合、一定面積まで相続税を計算する際の評価額を50%または80%減額できる特例制度 |
各種控除や特例の詳細は後述しますが、これらが適用された結果、相続税額が0円以下になる場合、納税する必要はありません。
ただし、相続税の控除や特例の中には、非課税となっても申告が必要になるものがある点には注意が必要です。
相続税の控除や特例は以下の2種類に分類できます。
- 非課税となるならば相続税の申告が不要な控除・特例
- 非課税となる場合でも相続税の申告が必要な控除・特例
そのため、納税額が0円以下(非課税)でも、申告が必要になるケースがあります。
また、各種控除や特例の適用を受けるためには、要件を満たすことを証明する書類の提出が求められます。
相続税の計算と申告の流れ
ここでは、相続税の計算方法を解説します。計算の手順は以下の通りです。
- 課税対象となる遺産総額を計算する
- 基礎控除額を計算する
- 各種控除や特例を計算する
- 相続税を算出・申告する
課税対象となる遺産総額を計算する
相続税を計算するには、まずは相続税の課税対象となる遺産の総額を算出します。被相続人が遺した遺産には、以下の2種類があります。
| 遺産の種類 |
内容 |
| 相続財産(プラスの財産) |
被相続人が持っていた財産のことで、現金や預貯金、不動産、株式などの有価証券、車や貴金属、骨董品、ゴルフ会員権など |
| 債務・借金(マイナスの財産) |
借入金や住宅ローンなど、被相続人が亡くなる時点で未払いだった負債 |
相続財産や債務、借金をすべて合算した金額が遺産総額となります。
なお、債務や借金が多く、遺産総額がマイナスとなった場合、相続放棄や限定承認を選択できます。
相続放棄とは、一切の相続権を放棄する手段です。プラスの財産も含めて相続できなくなりますが、債務や借金を相続して返済義務を負うのを避けられます。
また、相続人が所有する財産を保護できるメリットがあります。相続財産のうち、借金が透過状況にあることが明らかな場合に有効な手段です。
限定承認とは、プラスの財産を上限にマイナスの財産も相続する相続方法です。プラスの財産でマイナスの財産を精算し、財産が余った場合はそれを相続できます。
相続財産のうち、プラスの財産が多い場合や、手放したくない財産が含まれる場合に有効な手段です。
基礎控除額を計算する
遺産総額が算出できたら、法定相続人の人数を調べて相続税の基礎控除額を確認します。既出の通り、基礎控除額は3,000万円に加えて、法定相続人1人に付き600万円を加算した金額です。
なお、法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、被相続人の配偶者と子ども、父母、祖父母、兄弟、姉妹が該当します。
法定相続人の範囲は、亡くなった被相続人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本を取得して確認します。
具体的には、被相続人が死亡した時点の本籍地から戸籍謄本を取り寄せ、記載されている以前の本籍地からさらにさかのぼって戸籍謄本を取り寄せます。
そのまま、被相続人が生まれた時点の本籍地までさかのぼって戸籍謄本を取得すれば、法定相続人の範囲をもれなく把握できます。
何通もの戸籍謄本を取り寄せる必要があり、すべてが揃うまでに数週間から1ヶ月程度要すると考えておきましょう。
正確な法定相続人の人数を把握できれば、課税される遺産総額から基礎控除額を差し引きましょう。この値が0円もしくはマイナスになる場合は、相続税は非課税となり申告不要です。
各種控除や特例を計算する
相続財産から基礎控除額を差し引いた値がプラスとなる場合は、該当する控除や特例などを差し引きます。
前述したように、相続税の計算時には以下の控除や特例があります。
- 贈与税控除
- 配偶者の税額軽減
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
- 小規模宅地の特例
控除や特例の適用条件は後述します。控除や特例を考慮して計算した結果、プラスの値となれば、その金額が相続税の対象となります。
相続税を算出・申告する
最後に、相続税を算出し申告書や必要書類を準備して、税務署に相続税を申告します。
相続税の税率は、相続する財産の金額が多いほど税率が高くなる超過累進課税で、10%から55%の税率で課税されます。相続金額区分における相続税額は以下の通りです。
- 1,000万円まで:10%
- 3,000万円まで:15%
- 5,000万円まで:20%
- 1億円まで:40%
- 3億円まで:45%
- 6億円まで:50%
- 6億円超:55%
なお、相続税を計算する場合は、下記の速算表を利用して計算すると便利です。
| 相続分に応じた取得金額 |
税率 |
控除額 |
| 1,000万円以下 |
10% |
ー |
| 3,000万円以下 |
50万円 |
| 5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
| 1億円以下 |
30% |
700万円 |
| 2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
| 3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
| 6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
| 6億円超 |
55% |
7,200万円 |
例えば、相続分に応じた取得金額(相続人が相続する金額)が7,000万円の場合、以下のように計算します。
7,000万円×30%-700万円=1,400万円
相続税額が計算できれば、相続税の申告書と必要書類を準備します。
相続税の申告時に必要な書類は以下のように分類できます。
- 相続税の申告書(第1表~第15表)
- 相続税の申告を行うすべての相続人が提出するべき書類
- 財産ごとに必要となる添付書類
すべての相続人が提出するべき書類としては、以下のような書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本と改製原戸籍
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員のマイナンバー確認書類
- 相続人全員の印鑑登録証明書の原本(遺産分割協議を行った場合)
- 法定相続情報一覧登録図
なお、法定相続情報一覧登録図を提出できる場合は、上記の1~4の種類は不要です。
また、財産ごとに必要となる添付書類とは、申告書等に記載した数字を裏付けるために必要な書類です。土地や建物、現金、預貯金、有価証券、保険、退職金、債務、贈与など、遺された財産に関わる書類を提出しましょう。
相続税申告の提出方法は、以下の3つです。
- 被相続人が亡くなった住所地を管轄する税務署に直接持参する
- 郵送する
- e-taxを利用する(電子申告)
非課税であれば相続税申告が不要である控除一覧
相続税には、非課税になる場合には相続税を申告しなくても適用される控除があります。具体的には、以下に挙げる控除です。
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
- 未成年者控除
それぞれ詳しく解説します。
障害者控除
障害者控除は、85歳未満の障害者が財産を相続した場合に適用される制度で、要件を満たすと相続税額から一定金額を控除できます。
障害者控除の額は一般障害者と特別障害者で控除額が異なります。
具体的な計算方法は以下の通りです。
| 障害者控除の違い |
障害者の概要 |
計算方法 |
| 一般障害者 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを所持している人 |
控除額は(85歳-相続発生時の年齢)×10万円で計算 |
| 特別障害者 |
身体障害者手帳1級または2級、療育手帳AまたはB、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを所持している人 |
控除額は(85歳-相続発生時の年齢)×20万円で計算 |
また、障害者控除の要件は以下の通りです。
- 85歳未満の障害者であること
- 日本国内に住所があること
- 法定相続人であること
- 相続財産を取得すること
相次相続控除
相次相続控除とは、前回の相続が発生してから10年以内に再度相続が発生した場合に税負担を軽減するために適用される制度です。
この制度は、短期間に相続が連続して生じると、相続税の負担が過度に重くなることから、税負担の公平性を保つために設けられています。
相次相続控除の申告要件は以下の通りです。
- 申告者が法定相続人であること
- 今回の相続が始まる10年以内に、前回の相続が発生していること
- 今回死亡した被相続人が前回の相続時に相続税を課されて納めていること
相次相続控除では、前回の相続から1年経過ごとに控除金額が10%ずつ減少する仕組みとなっています。
例えば、前回の相続から1年後に再度相続が発生した場合、相続金額の90%の金額が控除対象となります。さらに、2年後なら80%、3年後なら70%と、経過年数に応じて控除率が下がります。
前回の相続と今回の相続の期間が短いほど、相似相続控除額は大きくなるほか、前回納税した相続税額が大きい場合も控除額は大きくなります。
外国税額控除
外国税額控除とは、日本国内に居住地を置く人が外国の所得税に相当する税金(以下、外国所得税)を納付した場合に適用される控除制度です。
相続財産には、外国にある財産が含まれる場合があります。このように、国境を越えて財産を取得する場合には、以下の2つの課税方式が取られます。
居住地国課税とは、納税義務者が居住もしくは在籍する国内で発生した所得だけではなく、国外で発生した所得を含めて課税する方式です。全世界所得課税とも呼ばれます。
一方、源泉地国課税とは、所得が発生した国で課税する方式を指します。
上記2つの課税方式は、ほとんどの国で採用されているため、国外の所得に関しては二重に課税されることになります。これを二重課税といいます。
被相続人から相続した財産に外国の財産が含まれている場合、日本では「居住地国課税」によって課税されるため、国内で相続税を納める必要があるほか、財産がある国で源泉地国課税が採用されていれば、その国でも相続税相当の税金が課せられる可能性があります。
このような二重課税による税負担の増大を防ぐために設けられた控除制度が外国税額控除です。具体的には、外国で課税・納税した相続税に相当する金額を相続税から控除できます。
なお、外国税額控除を受けるための要件は以下の通りです。
- 相続または遺贈により財産を取得していること
- 取得した財産が法施行地外にあること
- 取得した財産に現地の法令によって相続税に相当する税金が課されていること
未成年者控除
未成年者控除とは、相続人の中に未成年者がいる場合、未成年者が本来納めるべき相続税額から一定額を控除できる制度です。
未成年者の相続人が成人するまでに多額の教育費や養育費がかかることを考慮し、相続税負担の軽減によって未成年者の生活をサポートするために設けられています。
未成年控除を受けられるのは、以下の要件をすべて満たす場合です。
- 財産取得時に日本国内に住所があること
- 財産取得時に18歳未満であること
- 財産を取得した人が法定相続人であること
また、未成年者控除の金額の計算方法は次の通りです。
未成年者控除額=(18歳-相続時の年齢)×10万円
※相続開始時の年齢は満年齢でカウント
例えば、相続時に6歳の相続人が含まれている場合、120万円の未成年者控除を受けられることになります。
なお、控除額が相続税額よりも大きい場合、引ききれない控除額は成年者の扶養義務者で他の相続人の税額から差し引けます。
非課税でも相続税申告が必要である控除一覧
相続税が非課税になる場合でも、相続税を申告しなければ適用されない控除があります。具体的には、以下の控除や特例です。
- 配偶者の税額軽減
- 小規模宅地の特例
- 寄付金控除
- 農地の納税猶予の特例
それぞれ詳しく解説します。
配偶者の税額軽減
配偶者の税額軽減(相続税の配偶者控除)とは、被相続人の配偶者が相続・遺贈により取得した遺産額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは、配偶者に相続税がかからないという特例のことをいいます。
つまり、配偶者が相続した財産が1億6,000万円以内であれば相続税が発生しないほか、1億6,000万円以上でも法定相続分までは相続税が課税されません。
例えば、遺産総額が3億円で相続人が配偶者と子どもだった場合、配偶者の法定相続分は1億5,000万円となります。配偶者の税額軽減の要件である1億6,000万円よりも放置相続分が小さいため、配偶者には相続税がかかりません。
また、遺産総額が6億円の場合で相続人が同じく配偶者と子どもだった場合、配偶者の法定相続分は3億円となります。法定相続分が1億6,000万円よりも大きくなるため、配偶者は3億円まで非課税となります。
配偶者の税額軽減を受けるための要件は以下の通りです。
- 戸籍上での配偶者であること(内縁や事実婚の関係では適用されない)
- 相続税の申告期限までに遺産分割の方法が決定していること
- 税務署に相続税の申告をしていること
要件の1つにあるように、配偶者の税額軽減を適用してその配偶者や相続人全体の相続税額が0円(非課税)になったとしても、相続税の申告が必要になります。
相続税が非課税であっても、相続の事実を税務署に報告する義務があるからです。
また、配偶者の税額軽減は大きな節税効果が期待できますが、二次相続が発生した際の相続税が高額になる点には注意が必要です。
二次相続とは、最初の相続(一次相続)によって配偶者とその子どもが相続した後に、配偶者が死亡することで起こる2度目の相続を指します。
相続財産が1億6,000万円以内なら、財産のすべてを配偶者に分割すれば、子どもを含めた相続税を0円にできますが、その配偶者が亡くなった場合、配偶者が遺した財産に対して相続税が発生します。
つまり、子どもには父の場合と母の場合、2回の相続税が発生することになります。
一次相続の際に配偶者の税額控除を最大限に活用するために、母に多くの財産を分割した場合、その母が死亡したときには相続した財産に加えて、母が元から所有していた財産が追加されることになります。
財産が多いほど相続税は高くなるため、二次相続時に子どもの税負担が大きくなるのです。
子どもの相続には配偶者のような特例はないほか、子どもが相続する際には法定相続人の人数が減っている場合もあり、基礎控除額が小さくなる恐れもあります。
そのため配偶者の税額軽減制度を利用する場合は、二次相続のことも考えて遺産分割をする必要があります。
小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは、被相続人や同一生計の親族が居住用や事業用として使用する宅地等(土地や敷地権)について、要件を満たせばその宅地等の評価額を50~80%減額できる制度のことです。
小規模宅地の特例は、課税価格に算入する土地の評価額の計算時に適用されます。
小規模宅地の特例の要件は以下の通りです。
| 小規模宅地等の適用要件 |
内容 |
| 配偶者 |
被相続人の配偶者は無条件で特例適用 |
| 同族親族 |
相続が発生したときに、被相続人と同居していた親族に特例適用
※同居とは生活拠点が同じことを指す。住民票が同じでも同居実態がなければ特例は不適用
※相続税の申告期限まで継続してその宅地等を所有し、建物に住み続ける必要がある |
| 別居親族(同居親族以外) |
別居親族の特例適用には、以下の要件を満たす必要がある
・被相続人に配偶者、同居相続人が存在しない
・宅地等を相続した親族が、相続が開始する前3年以内に、親族や親族の配偶者、3親等内の親族、同族会社等が所有する家屋に住んだ実績がない
・相続時にその親族が住む家屋を過去に所有していない
・申告期限まで継続してその宅地等を所有している
|
なお、特例対象の宅地等には、次の4種類があります。
| 小規模宅地等の特例の種類 |
内容 |
| 特定居住用宅地等 |
・死亡した被相続人の自宅をして使用していた宅地等への特例
・限度面積330㎡、減額割合80% |
| 特定事業用宅地等 |
・死亡した人の個人事業として使用していた宅地等への特例(※貸付用を除く)
・限度面積400㎡、減額割合80% |
| 貸付事業用宅地等 |
・死亡した人が貸地または貸家など貸付用として使用していた宅地等への特例
・限度面積200㎡、減額割合50% |
| 特定同族会社事業用宅地等 |
・死亡した人の会社(同族会社)として使用していた宅地等への特例
・限度面積400㎡、減額割合80% |
例えば、死亡した人の自宅の土地が200㎡の評価額が4,000万円だった場合、この土地の相続に上記の特例を適用すると、土地すべての評価額の80%を控除できるため、控除できる評価額は3,200万円、相続税評価額は800万円となります。
小規模宅地等の特例を受けるためには、相続税の申告が必要です。なお、相続税の基礎控除によって相続税が非課税となる場合は、特例を受ける必要がないため、申告も不要となります。
寄付金控除
寄付金控除とは、相続した財産を国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合、その財産は相続税の課税対象にならないという控除制度です。
寄付金控除を受けるための要件は以下の通りです。
- 相続税の申告期限までに寄付手続きが完了していること
- 相続財産をそのまま寄付すること
- 寄付先として認められている団体や組織に寄付していること
寄付金控除では、相続財産をそのままの形で寄付する必要があります。例えば、不動産を寄付する場合、不動産のまま相続すれば寄付金控除の要件を満たしますが、現金化してから寄付した場合は寄付金控除の対象外となります。
また、寄付先として認められているのは以下の団体や組織です。
- 国や地方自治体
- 教育や科学の進行などに貢献することが著しいと認められている特定の公益法人など
なお、寄付金控除を受けるためには、相続税の申告書に特例の対象になる財産の明細を記載したうえで、寄付先の受領書や証明書類などを添付する必要があります。
農地の納税猶予の特例
農地の納税猶予の特例とは、相続や贈与などで農地を取得した人が所定の要件を満たしている場合、農地にかかる税金の納税が猶予される制度のことです。
農地を相続した人に多額の相続税が課せられた場合、税金を納めるために農地の売却が必要になるケースがあり、農業を継続できなくなる恐れがあるのを防ぐための制度となっています。
納税猶予の対象となる農地は、以下の3つに分類されます。
| 納税猶予の対象となる農地 |
詳細 |
| 被相続人が農業の用に供していた農地等 |
被相続人が農業を営むために使用していた農地のうち、以下に該当する場合は納税猶予の対象
1.被相続人から相続によって取得した農地等で、すでに遺産分割されているもの
2.贈与税納税猶予の対象となっていたもの
3.相続の年に被相続人から生前一括贈与を受けたもの
|
| 被相続人が特定貸付を行っていた農地等 |
被相続人が特定貸付を行っていた農地等で、上記の1~3のいずれかに該当する場合は納税猶予の対象となる。
※特定貸付とは、市街化区域外の農地を対象として、農業経営基盤強化促進法に基づく農地中間管理事業や利用権設定等促進事業のこと
|
| 被相続人が認定年農地貸付または農園用地貸付を行っていた農地等 |
被相続人が認定年農地貸付または農園用地貸付を行っていた農地等で、上記の1~3のいずれかに該当する場合、納税猶予の対象となる。
|
また、農地が納税猶予の対象となるケースでの、被相続人や相続人の要件はそれぞれ以下の通りです。
| 要件 |
詳細 |
| 被相続人の要件 |
以下のいずれかに該当すること
・亡くなった日まで農業を営んでいた人
・生前に一括贈与をした人
・亡くなった日まで特定貸付、認定年農地貸付または農園用地貸付を行っていた人
|
| 相続人の要件 |
被相続人の相続人であり、以下のいずれかの要件に該当すること
・相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後に継続して農業経営を行う人
・生前一括贈与を受けた受贈者
・相続税の申告期限までに特定貸付または認定年農地貸付等を行った人
|
なお、相続税の納税猶予を受けるには、以下の手続きが必要です。
- 相続税の申告書に所定の事項を記載のうえ期限内に提出する
- 農地等納税猶予税額および利子税の額に相当する担保の提供
- 相続税の申告書に相続税の納税猶予に関する適格者証明書や担保関係書類などを添付する
相続税の計算時における注意点
相続税を計算する場合、いくつかの注意点があります。具体的には、以下のポイントに注意しましょう。
- 相続時精算課税制度を利用している場合は財産に加算される
- 相続発生から3年以内に贈与を受けている場合は財産に加算される
- 被相続人の名義預金は財産とみなされる
- みなし相続財産の非課税枠は差し引く必要がある
それぞれ詳しく解説します。
相続時精算課税制度を利用している場合は財産に加算される
相続時精算課税制度を利用している場合、生前贈与を受けた財産が相続税に加算される点には注意が必要です。
相続時精算課税制度とは、被相続人から生前に受けた贈与に対する贈与税を、相続が発生したときにかかる相続税とともに精算する制度です。
この制度を利用している場合、贈与を受けた財産が相続財産に加算されます。
相続時精算課税制度を利用して、贈与を受けた財産を相続財産に加算するのを忘れた場合、正しい相続税の計算ができなくなります。
相続税の計算は、相続人が全員で納める相続税の総額を求め、実際に相続した割合で割り振った金額が、各相続人が納める税額となるため、同制度を利用している場合、贈与部員の財産は必ず加算しましょう。
相続発生から3年以内に贈与を受けている場合は財産に加算される
相続開始前3年以内に贈与が行われている場合、贈与された財産は相続財産に加算される相続税の対象となる点にも注意が必要です。
これを暦年課税制度の生前贈与加算といいます。
贈与を受けた日から3年以内に贈与者が死亡した場合、行われた生前贈与はなかったものとみなされます。そのため、贈与を受けた財産は相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。
例えば、贈与者が2021年9月30日に亡くなった場合、その前3年以内となる2018年9月30日から死亡日までの間に実施された贈与が、生前贈与加算の対象となります。
ただし、暦年贈与制度によって生前贈与が実施された場合でも、その年の1月1日から12月31日までの1年間で贈与された財産総額が110万円以下(贈与税の基礎控除額)の場合は、贈与税は非課税となります。
また、この制度によって相続財産に加算される金額は、相続が発生した際の時価ではなく、贈与時の時価として計算しなければなりません。
さらに、生前贈与の際に、すでに贈与税を納めている場合、その贈与税額を相続税から控除できます。
なお、税制改正により令和6年以降に贈与される財産については、相続税の対象となるのが、相続開始前7年以内の贈与に変更されます。
ただし、新しい制度には経過措置が講じられており、令和12年末までに相続が始まる場合、令和6年1月1日以降の贈与が相続税の対象と定められています。
変更された通りに相続開始前7年以内の贈与が相続税の対象となるのは、令和13年1月1日以降に相続が始まる場合となります。
被相続人の名義預金は財産とみなされる
相続税を計算する場合の注意点として、被相続人の名義預金は相続財産とみなされる点が挙げられます。
名義預金とは、被相続人が配偶者や子ども、孫などの名義で開設した口座のことです。
例えば、祖父母や孫名義の口座を開設して預金したり、専業主婦が自身の名義で配偶者の収入を預金したりするケースがあります。
名義が被相続人ではなくても通帳や印鑑を被相続人が管理していたり、名義人自身が自由に預金を出し入れできなかったりする場合、実質的に被相続人の財産であるとみなされるため、相続財産に含まれます。
相続発生時に名義預金は被相続人の財産に含まなければ、相続税が正しく計算されず、誤った申告・納税につながり、税務調査や延滞税などのペナルティを受ける恐れがあります。
相続税の計算時には、被相続人の名義預金が相続財産に含まれることを忘れないようにしましょう。
みなし相続財産の非課税枠は差し引く必要がある
相続税の計算時には、みなし相続財産の非課税枠を差し引く必要がある点に注意しましょう。
みなし相続財産とは、生命保険金や死亡退職金など、相続の開始によって相続人が取得するお金のことです。
これらは、相続税の計算においては相続財産として扱われ、その額は相続財産に加算されます。
ただし、生命保険金や死亡退職金には非課税枠が設定されており、非課税枠を差し引いた残額をプラスの遺産へ加えて相続税額を計算しなければなりません。
なお、生命保険金(死亡保険金)や死亡退職金の非課税枠は、それぞれ以下の通りです。
| みなし相続財産の代表的な例 |
非課税枠の計算方法 |
| 生命保険金(死亡保険金) |
500万円×法定相続人の人数 |
| 死亡退職金 |
500万円×法定相続人の人数 |
例えば、被相続人が死亡して、相続人である母と子どもの合計2人が1,000万円の生命保険金(死亡保険金)を受け取るとします。
この場合、生命保険金の非課税枠は500万円×2人の合計1,000万円となるため、相続税は課税されません。
また、被相続人が死亡して、生命保険金と死亡退職金がそれぞれ1,500万円発生し、相続人である母と子どもの合計2人がそれぞれ受け取る場合も考えてみましょう。
生命保険金の非課税枠が1,000万円、死亡退職金の非課税枠も1,000万円となるため、相続税の非課税枠からそれぞれ500万円が残ります。この残額500万円が相続税の課税対象となります。
このように、相続税の計算ではみなし相続財産とその非課税枠を考慮しなければなりません。
まとめ
遺産総額が基礎控除額以下となる場合や、各種控除の適用によって納税額が0円以下になる場合は、相続税の申告が不要になるケースがあります。
ただし、相続税が非課税の場合でも、相続税の申告が必要になることもあるため、本記事を参考に確認してください。
また、相続時精算課税制度を利用している場合や、相続発生前3年間に贈与を受けている場合は相続財産に加算する必要があるほか、被相続人に名義預金は財産と見なされるため、相続税の計算時には注意しましょう。
【Q&A】相続税の申告要否に関するよくある質問
「相続税についてのお尋ね」が送られてきた場合は申告義務はある?
税務署から「相続税についてのお尋ね」が送付されてきた場合でも、申告が不要な場合は対応する必要はありません。
「相続税についてのお尋ね」とは、相続開始から6~8ヶ月が経過した頃に税務署から相続人へ送付される文書です。
この文書は、相続税の申告が必要な場合に対応するものです。
例えば、税理士に相談して相続税の申告の準備をしている場合や、相続税を計算して相続税がかからないとわかった場合は、対応しなくてもいいでしょう。
ただし、税務署は被相続人(死亡者)の財産情報を精査し、相続税が発生することを見込んで文書を送付しているため、相続税の申告が必要かどうか確認することをおすすめします。
なお、文書に対して虚偽の回答をした場合でも、それだけで罰せられることはありません。ただし、意図的に財産を隠した場合は、相続税に40%の重加算税などのペナルティが課せられることがあるため、注意しましょう。
相続税の申告要否を簡単に判定するには?
相続税の申告が必要かどうかを確認したい場合は、国税庁の
「相続税の申告要否判定コーナー」を利用しましょう。
このサイトでは、相続税の申告が必要かどうかを簡単に確認できるほか、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)及び配偶者の税額軽減(配偶者控除)を適用した場合の税額計算のシミュレーションも可能です。
また、自分で確認するのが難しい場合や、相続税申告の要否や計算のための時間が取れない場合は、税理士に相談することをおすすめします。
相続に強い税理士に相談すれば、費用こそ発生するものの、相続税の申告の要否が確認でき、申告が必要な場合でも財産の計算や申告書の作成を正確に行ってくれます。