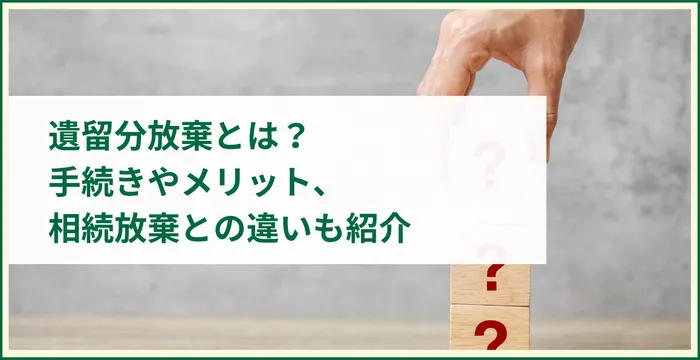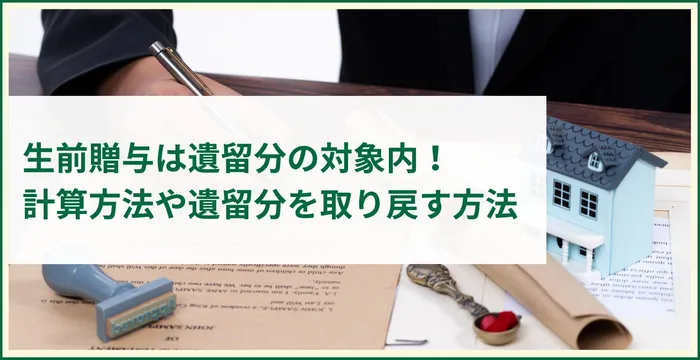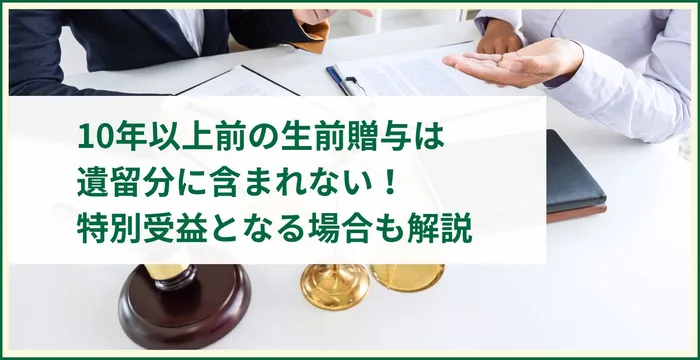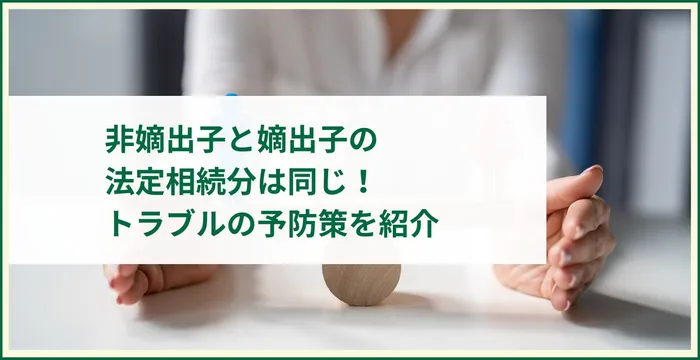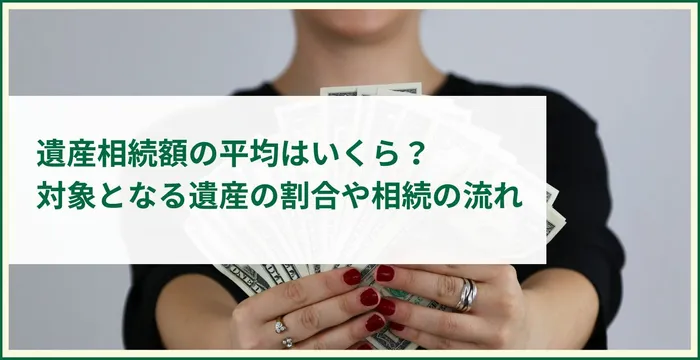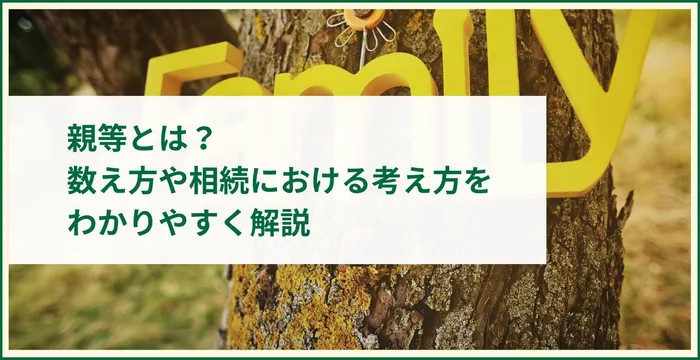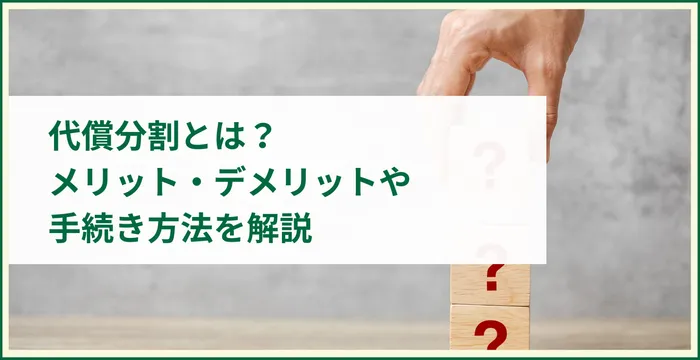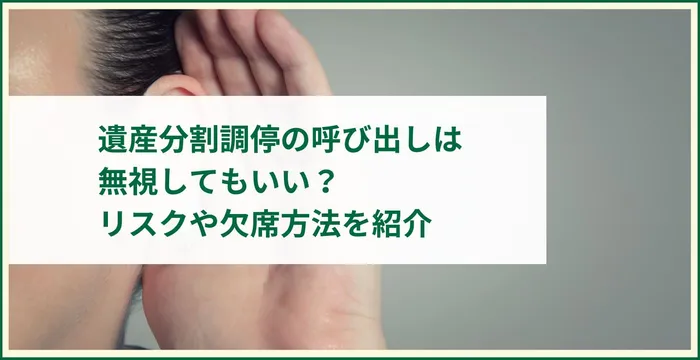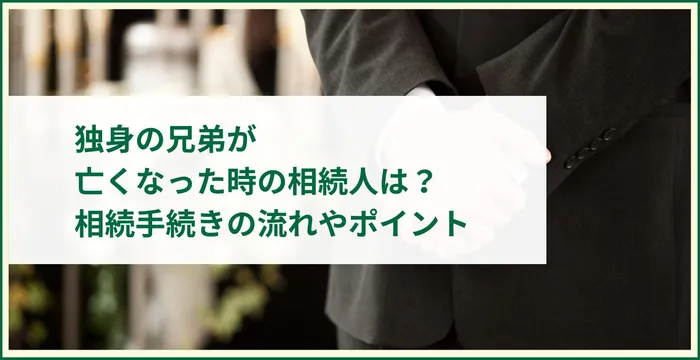遺留分を渡さなくていい5つの方法
遺留分は相続人に保障された最低限の遺産分配ですが、特定の状況下ではこれを渡さなくても済む方法があります。
- 遺留分放棄をお願いする
- 相続放棄をお願いする
- 相続廃除の手続きを行う
- 相続欠格の手続きを行う
- 遺言書の付言事項を記載する
以下では、遺留分を渡さなくていい5つの方法を具体的に紹介します。
1. 遺留分放棄をお願いする
遺留分を放棄することに同意した相続人には、その遺留分を渡す必要がなくなります。遺留分放棄は被相続人(亡くなった方)がまだ生きているうちにすることも、亡くなった後にすることもできます。
生前に遺留分の放棄をする場合は家庭裁判所の許可が必要であり、生前の遺留分放棄が認められるための条件は次の通りです。
- 遺留分放棄が相続人自身の自由意思であること
- 遺留分放棄を行う合理性と必要性があること
- 遺留分放棄に見合うだけの見返りがあること
放棄の意志は相続人自身の自由意志に基づくものであり、被相続人からの要請は可能ですが、強要は許されません。これは、相続人が遺産分配における平等性や生活保障の観点から、特定の財産に執着しない意思を示すものです。
また、この「遺留分放棄」は「相続放棄」とは異なり、相続権そのものを放棄するわけでありません。遺留分の放棄は遺産が遺留分に満たない際、不足分に関する請求をしないという選択を意味し、遺産を全く受け取らない状況を指すものではありません。
遺留分放棄には、遺留分侵害額請求権の消滅時効(1年)や遺留分侵害額請求権の除斥期間(10年)の経過後にも同様の効果があります。「遺留分侵害額請求権」とは、遺産相続において法律で定められた最低限度の相続分(遺留分)を受け取れなかった相続人が、遺留分を侵害されたとして、遺留分を確保するために遺産の一部を請求できる権利です。これらの期間が過ぎれば、相続人は遺留分を請求できなくなります。
2. 相続放棄をお願いする
相続権の放棄は、相続が発生した後に相続人が相続を一切受け入れないと決める手続きです。この放棄は、家庭裁判所に申し立てを行い、相続財産に対する一切の権利を放棄するものです。
相続権の放棄を行うには、相続人が家庭裁判所へ放棄の意志を明確に示す必要があります。これは、相続財産だけでなく、遺留分に対する権利も含めて一切の相続権を放棄することを意味します。相続権の放棄が正式に受理されれば、その相続人は法律上、相続財産から除外されます。
ただし、相続を放棄するという行為は、相続権が完全に失われることを意味します。そのため、一般的には遺留分を放棄する場合と比較して、他の相続人の了承を得る難易度は、一層高くなると考えられます。
3. 相続廃除の手続きを行う
家庭裁判所に相続廃除の申し立てを行うことで、推定相続人(遺留分を渡す予定のある法定相続人)を相続権から除外できます。この手続きは、推定相続人が遺留分を受け取る資格を失うため、相続廃除が認められると、該当する相続人は遺留分を含む一切の相続権を失います。
相続廃除の申し立てができるのは、生前の被相続人自身または遺言によって指名された遺言執行者のみです。遺言執行者が相続廃除を申し立てる場合、その旨が遺言書に明記されている必要があります。これにより、遺言執行者の行動が被相続人の意思に沿ったものであることが保証されます。
ただし、家庭裁判所による相続廃除が承認されるのは、以下の三つの状況下でのみです(民法892条による)。
- 推定相続人による被相続人への虐待があった場合
- 推定相続人による被相続人への深刻な侮辱があった場合
- 推定相続人による被相続人への重大な不正行為を行った場合
上記のような、被相続人に対する長期間の虐待や重大な侮辱が発覚した場合、その相続人を相続から除外することができます。
4. 相続欠格の手続きを行う
相続欠格は、民法の第891条に規定された、特定の相続人から遺産相続の資格を剥奪する制度です。相続欠格は、相続人が被相続人に対して重大な違法行為を行った場合に適用されます。これに該当する相続人は、法律により自動的に相続権を失い、遺留分も含め、遺産を一切受け継ぐことができません。
相続欠格の条件は以下のいずれかに該当する場合です。
- 故意に被相続人や他の相続人を死亡させた場合
- 被相続人が殺害されたことを知りながら、告発または告訴をしなかった場合
- 詐欺や強迫により遺言の作成、撤回、または変更を妨害した場合
- 詐欺や強迫により被相続人に遺言書を作らせたり、または遺言書の撤回、取り消し、変更させた場合
- 被相続人の遺言書を偽造、変造、隠匿、または破棄した場合
ただし、相続欠格を受けた人が子どもを持っている場合、その子どもは親が失った相続の機会を引き継ぎ、遺産を相続することが可能です。
5. 遺言書の付言事項を記載する
遺言書における付言事項は、遺言作成者が相続人に伝えたいメッセージや願望を記載しておくものです。
付言事項には直接的な法的効力はありません。つまり、遺留分の請求権が発生した場合、この付言事項だけでは遺留分の支払いを回避することはできません。しかし、遺言書全体の理解を深めるためや、相続人間のトラブルを未然に防ぐための補足的な情報として、有効な手段となり得ます。
実際に、ある特定の人に遺留分を渡したくない場合は、遺言書に以下のような項目を含めるようにしましょう。
- 特定の相続人への遺産の集中配分についての希望とその根拠
- 遺留分の請求を控えてほしいという希望とその理由
遺言の具体例の一例を紹介します。
具体例
次女であるA子は、これまで長い間私たち夫婦と一緒に住んでくれ、日々の食事の用意や妻の介護に至るまで、大変尽くしてくれました。
彼女のおかげで、私達夫婦は心穏やかな晩年を送ることができました。
その感謝の気持ちとして、妻とA子へは、他よりも多くの遺産を遺すことを決めました。長女B子と長男C男には相対的に少なめの遺産となりますが、彼らも現在の家庭環境を十分に理解してくれていると信じています。どうか遺留分に関する請求を控えてくれることを望みます。これからも家族全員が支え合い、和気あいあいと過ごしてくれることを願っています。
遺留分は相続人が受け取る権利のあるお金
遺留分は、相続人が法的に保障された遺産の一部を受け取る権利です。では具体的に遺留分を分配する相続人の範囲や遺留分として貰える割合はどのくらいなのでしょうか。ここでは、遺留分が認められる相続人の範囲や相続における遺留分の割合、遺産分割方法について紹介します。
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分の権利は、法廷相続人のうち、被相続人の配偶者、子ども、父母や祖父母などの直系尊属に認められています。一方で、被相続人の兄弟姉妹や甥姪などは、遺留分の権利を有していません。
もし被相続人が亡くなる前にその子供が先に死去した場合は、代襲相続が認められ、その故人の子供(被相続人にとっての孫)が相続権を持つことになります。
この代襲相続を受けた孫がもし亡くなっていた場合は、その孫の子供(被相続人のひ孫)がさらに相続の権利を継承し、代襲相続(再代襲)が繰り返されます(民法第887条の第2項及び第3項に規定)。
相続における遺留分の割合は2分の1または3分の1
遺留分の具体的な割合は、相続人の関係によって異なりますが、原則として遺産全体の1/2が遺留分とされます。ただし、相続人が直系尊属のみの場合は、遺留分が遺産の1/3となります。
遺留分の割合をまとめると下記となります。
| 配偶者のみが相続人の場合 |
2分の1 |
| 子のみが相続人の場合 |
2分の1 |
| 直系尊属のみが相続人の場合 |
3分の1 |
| 兄弟姉妹のみが相続人の場合 |
遺留分なし |
| 配偶者と子が相続人の場合 |
配偶者が4分の1、子が4分の1 |
| 配偶者と父母が相続人の場合 |
配偶者が3分の1、父母が6分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 |
配偶者が2分の1、兄弟姉妹は遺留分なし |
遺留分は遺産分割協議で決める
遺留分を正式に受け取るためには、相続財産の全体像が明らかになった後、全相続人が参加する遺産分割協議を経る必要があります。この遺産分割協議を通じて、各相続人の取り分が決定され、遺留分に関する合意が成立します。
遺産分割協議が完了すると、次は名義変更や換金などの手続きを経て、遺留分が実際に受け取られます。この段階では、相続財産が具体的な形で相続人に渡ることになります。
もし、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合は、内容証明郵便を用いて遺留分侵害額請求を行うことができます。これにより、協議結果に対する正式な異議申し立てが行われます。遺留分侵害額請求に対し、関係者間で合意に至らない、または協議が不可能な状況にある場合は家庭裁判所による調停手続を利用することができます。
【生前対策】遺留分を減らす方法
遺留分を渡したくない場合、適切な生前対策により、遺留分の金額を最小限に抑えることが可能です。以下では、遺留分を減らすための方法を4つ紹介します。
- 遺言執行者を決めておく
- 生前贈与する
- 生命保険を活用する
- 養子縁組で相続人を増やす
遺言執行者を決めておく
遺言執行者は、遺言に記された指示に従って相続手続きを進める重要な役割を果たします。遺言執行者は、被相続人が遺言書で指定できます。
遺言では、遺言執行者として法律専門家や信頼できる個人を事前に指定しておくことが推奨され、これにより遺言者の意思が反映された相続が実現しやすくなります。
特に弁護士などの法律専門家を遺言執行者として指名しておけば、相続に関するトラブルを未然に防ぎ、公正かつ平等な遺産の分配が実現できる可能性が高まります。
生前贈与する
生前贈与は、被相続人が生前に相続人へ財産を移転することにより、相続発生時の財産総額を減らし、結果的に遺留分の金額を軽減する有効な手段です。ただし、贈与時期によっては、贈与された財産が遺留分計算の基礎となる場合があるため、早期に生前贈与をする必要があります。
相続人への生前贈与については10年、相続人以外への生前贈与に関しては1年が経過した場合、遺留分を計算する基礎財産に含まれなくなります。できるだけ早い段階で計画的に行うことで、相続時の遺留分に関する請求を最小限に抑えることができます。
ただし、贈与により受け取った資金を預金口座にそのまま保管しておくと、口座の名義人と実際の資産所有者が一致しない「名義預金」と見なされ、遺留分計算の対象財産として扱われる恐れがあることも念頭に置くべきです。
さらに、生前贈与を行う際は、「生前贈与加算(持ち戻し)」に留意する必要があります。これは、相続税を逃れるために被相続人の死亡間際に贈与が行われることを防ぐための法律上の決まりです。贈与者が贈与を行った日から3年以内に死亡した場合は、生前に行われた贈与は無かったものとされ、相続税の算出時に相続財産に加算して(持ち戻して)計算されます。
以前は、故人が亡くなる3年以内に行われた贈与が持ち戻し期間の対象となっていましたが、2023年度の税制改正でこの期間が7年以内へと拡大され、2024年1月以降の贈与から適用されています。
生命保険を活用する
遺留分の問題を効果的に回避する手段の一つとして、生命保険の活用があります。指定された受取人に支払われる生命保険金は、相続財産には該当せず、受取人に特有の権利とみなされます。遺産分割の際、生命保険金は通常の相続財産とは別に扱われるため、この金額は遺留分の計算に含まれません。
生命保険金を遺留分対策として利用する場合は、受取人を明確に指定することで、被相続人の意向に沿った資産の分配が可能になります。
ただし、保険金額が大きすぎると、例外的に遺留分の請求対象となる可能性があるため、遺産全体のバランスを考慮する必要があります。
養子縁組で相続人を増やす
養子縁組は、相続人を法的に増やす手段の一つです。相続人が増えることで、個々の相続人が受け取る遺留分の割合が自然と減少します。その結果、遺留分が分散されるため、特定の相続人が大幅な遺留分を請求することが難しくなります。
養子縁組を遺留分を減らす目的のみで行う場合、その意図が明らかになった時には養子縁組そのものが無効になる可能性があります。したがって、養子縁組の動機や条件には注意が必要です。
養子縁組を生前対策として考える際には、法的な側面だけでなく、倫理的な考慮も重要です。相続人との関係や相続財産に関する公平な扱いを確保するために、専門家の意見を参考にしながら慎重に計画を進めることが推奨されます。
【相続開始後】遺留分を減らす方法
相続が開始された後でも、遺留分の影響を最小限に留める方法があります。ここでは、下記の2つについて、遺留分を減らす方法を詳しく紹介します。
- 遺留分を受け取る権利があるかどうか調査する
- 不動産の評価方法を検討して評価額の低い方法を選ぶ
遺留分を受け取る権利があるかどうか調査する
遺留分の問題が発生した際は、まずは遺留分を受け取る権利があるかどうか調査しましょう。権利があるかどうか調査すべき点は以下の3つです。
- 法定相続人かどうか
- 時効ではないか
- 権利の濫用ではないか
法定相続人かどうかを調査する
相続が開始された後に遺留分の問題に直面した場合、対処法の一つとして、遺留分請求権が実際に存在するかの詳細な調査を行うことが重要です。
遺留分請求が提起された際、まずは請求者が遺留分を受け取る権利を有する相続人であるかどうかを確認します。遺留分の権利を持つのは、被相続人の配偶者、子、親などの直系親族だけです。
次の個人は遺留分の権利を持つ相続人ではないとされています。
- 被相続人の兄弟姉妹
- 相続権が剥奪された人
- 生前に多額の贈与を受けた人
被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利がなく、相続権が剥奪された人や、生前に大きな贈与を受けた人も遺留分を請求することはできません。
時効ではないかを調査する
遺留分侵害額請求権には「1年」と「10年」という時効および除斥期間が設定されており、これらの期間が経過した後には請求ができなくなります。その結果、請求時にこれらの期間が過ぎている場合、時効を理由に遺留分を支払わなくても済むのです。
遺留分侵害額請求権の消滅時効は、「相続が開始されたこと」と「遺留分が侵害されたこと」を認識してから1年間です。遺留分侵害額請求権の除斥期間は、相続が開始されて(被相続人が亡くなってから)10年間です。
例えば、被相続人の死後1年を過ぎてから遺留分侵害額が請求された場合、時効の可能性が高いです。この消滅時効を適切に主張して、請求を退けるべきです。時効1年または除斥期間10年を超えて請求があった場合、遺留分を支払う義務は生じません。
権利の濫用ではないかを調査する
また、家庭裁判所では、遺留分請求が権利の濫用にあたると判断されるケースもあります。これは、法定相続人が遺留分の請求を行う際、法の趣旨に反して不当にその権利を行使することを指します。
権利の濫用に該当する事例としては、以下のような状況が挙げられます。
- 相続人が既に十分な経済的利益を受けているにも関わらず、遺留分の請求を行うケース
- 相続人が、相続開始の長期間後や、被相続人との関係が希薄であるにもかかわらず、遺留分の請求を行うケース
- 相続人が、相続財産に対して実質的な関心を持っていないが、他の相続人に対して圧力をかける目的で遺留分請求を行うケース
遺留分請求権の濫用は、被相続人の意志に反する結果を招く可能性があるため、遺留分請求権の行使にあたっては、遺留分の制度の趣旨と公平さを考慮することが重要です。
濫用が疑われる場合、裁判所は具体的な事情を考慮して、請求が権利の濫用にあたるかどうかを判断します。請求者の行動が相続の公平性や道徳に反する場合、請求権が認められないこともあります。
不動産の評価方法を検討して評価額の低い方法を選ぶ
不動産を所有している場合に遺留分の負担を減らすためには、不動産の評価額の低い方法を選択することが有効です。
不動産の評価方法には、路線価(相続税路線価)、固定資産税評価額、公示価格(公示地価・基準地価)、時価(実勢価格)、不動産鑑定評価額など、複数の選択肢があります。
しかし、これらの方法によって算出される不動産の価値は不動産の所在地の条件や状況により大きく異なるため、最適な評価方法を一律に推奨することは難しいと言えます。
素人が不動産の評価を行うことは難しいため、不動産鑑定士に評価を依頼するケースもあるでしょう。不動産鑑定士による評価は、正確な市場価値を把握する上では、最も信頼性が高いとされています。しかし、高額な鑑定料が発生する可能性がある点は知っておきましょう。
相続人間で意見が分かれた場合、評価額に関しては中間値での合意形成を目指すことも一つの解決策です。これにより、遺留分に関する紛争を避けることができます。
遺留分に関する対策の注意点
遺留分を渡したくない、もしくは減らしたい場合に、遺留分に関する対策を行う際には、留意すべきポイントがあります。ここでは、遺留分に関する対策の注意点を2つ紹介します。
- 遺言では遺留分をゼロにできない
- 相続廃除や欠格でも遺留分を支払うケースがある
遺言では遺留分をゼロにできない
遺留分は法律によって保護された相続人の最低限受け取るべき財産です。したがって、遺留分は遺言によって完全に排除することはできません。被相続人が、遺言で「遺留分を放棄する」と記述しても、相続人がその遺留分を請求する権利は残ります。
遺留分の制度は、特定の相続人が不当に遺産から除外されることを防ぐために設けられています。そのため、被相続人が遺言で遺留分に触れ、相続人に遺留分を放棄させようとしても、相続人はいつでもその権利を行使することが可能です。
「遺留分は受け取らない」との合意があっても、相続が開始された後に相続人が遺留分請求を行うと、遺言の意向に反しても、法定遺留分の支払いを求めることができます。このため、遺言で遺留分の放棄を記載しても、それが絶対的な効力を持つわけではありません。
遺留分について適切な対応を取るためには、法的枠組みと相続人の権利を正しく理解し、それをどのように扱うかについて正確な情報を得ることが重要です。裁判所が提供するガイドラインや、専門家からのアドバイスが有効です。
相続計画を立てる際は、遺留分に関する法的要件を遵守し、可能な限り紛争を避けるための方法を模索しましょう。
相続廃除や欠格でも遺留分を支払うケースがある
相続廃除や欠格は、特定の相続人が相続権を失う重大な措置です。相続廃除や欠格措置を取った場合でも、相続人に子供(被相続人にとっての孫)がいる場合は、その子供は代襲相続により相続権を有することになり、遺留分の権利も引き継がれます。
代襲相続においても、相続割合や遺留分の割合に変更はありません。したがって、相続廃除や欠格措置を施した場合でも、その影響を受ける相続人の子供がいれば、遺留分の問題は完全には解消されません。
相続廃除や欠格措置を行う場合は、法的要件やその後の代襲相続人への影響を十分に検討し、専門家のアドバイスを求めることが望ましいです。
遺留分を渡す方がトラブルのリスクは少なくなる
相続は、遺産を巡る感情の高まりからしばしば複雑なトラブルに発展します。遺留分は相続人が受け取るべき最低限の財産の保障であり、遺言に優先して権利が認められています。そのため、遺言の内容のみで相続を進めるなど遺留分を無視すると、相続人から遺留分請求権が行使され、結果として予期せぬ法的紛争に発展する可能性があります。遺留分の適正な請求に対しては支払うことで、より大きな紛争を避けることが可能です。
また、訴訟に至ると、弁護士費用や裁判費用など、金銭的な負担が大きくなります。さらに、相続に関する訴訟は、精神的なストレスや時間的な負担が伴います。遺留分の支払いにより、これらの負担から解放されます。
また、相続発生後に遺留分請求が予見される場合は、事前に相続人との間で話し合い、合意に至ることが望ましいです。必要に応じて、弁護士や相続専門家のアドバイスを受け、紛争の可能性を最小限に抑えましょう。
遺留分を渡したくないなら専門家に相談を
遺留分は特定の相続人に対して認められた権利であるため、単に「遺留分を支払いたくない」「渡したくない」という理由でこれを回避したり、放棄させたりすることは難しいです。生命保険の利用や生前贈与を通じて相続財産を減少させることが、遺留分問題を緩和する現実的なアプローチであると言えます。
遺留分に関連する問題は、相続人同士の話し合いだけでは解決が困難なことが多く、時には感情的な対立を引き起こし、事態をより複雑にする可能性があります。これを解決するためには、法的な知識と経験を持つ専門家への相談が非常に有効です。特に、遺留分をできるだけ渡したくない場合や対応策を検討したい場合には、相続に関する複雑な法律や判例を理解し、遺留分に特化した経験が豊富な弁護士に相談することが推奨されます。
弁護士の支援を得ることで、遺留分の支払いを回避するための遺言の作成方法や、生前にとるべき措置、または相続が開始された後で遺留分の請求を最小限に留めたい場合の対応策について、正当な理由と交渉戦略が求められます。
遺留分を最小限に抑える方法について詳しく知りたい、あるいは既に相続が始まっており遺留分の請求に直面している場合は、弁護士へ相談してみましょう。
まとめ
遺留分は、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障された、遺産の一部を受け取る権利です。特定の相続人に遺留分を渡したくない場合に有効な対策は、遺留分放棄や相続放棄の合意の取得、相続人の排除手続き、相続欠格の主張、遺言書の付言事項の記載などです。
これらの手段を適切に実行するためには、相続法の専門家である弁護士による支援が不可欠です。弁護士は、法的な知識と経験を駆使して、最も適切な対策を提案し、相続人間の紛争を未然に防ぐことが可能です。
初回相談無料のサービスを提供している法律事務所もあるため、遺留分に関する疑問や相続の悩みがある場合は、気軽に相談してみましょう。