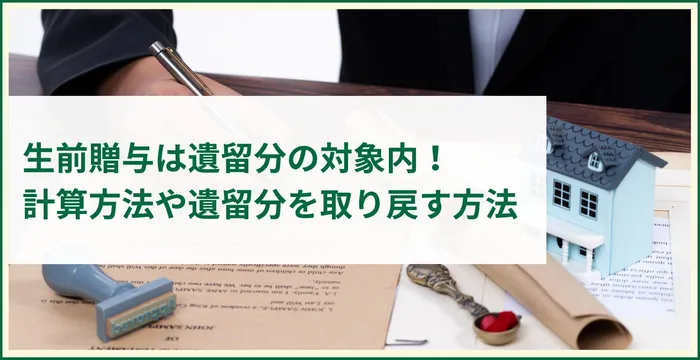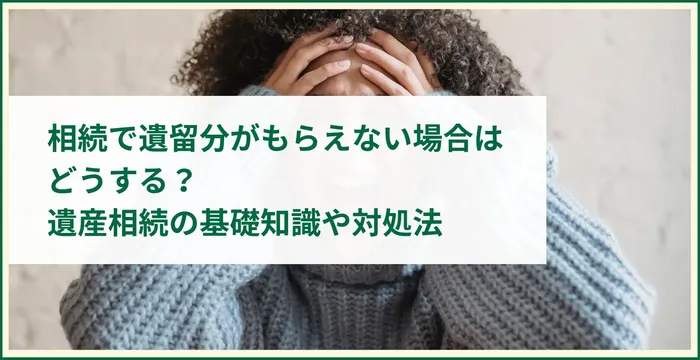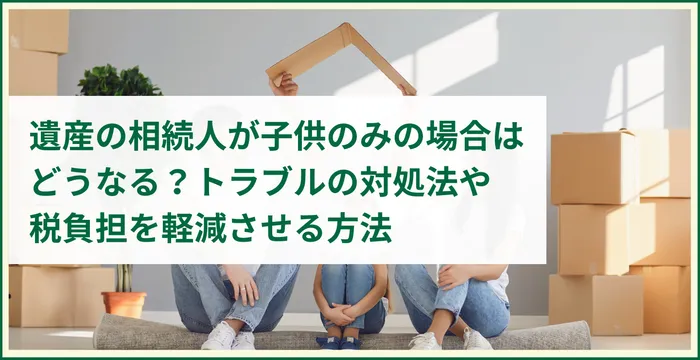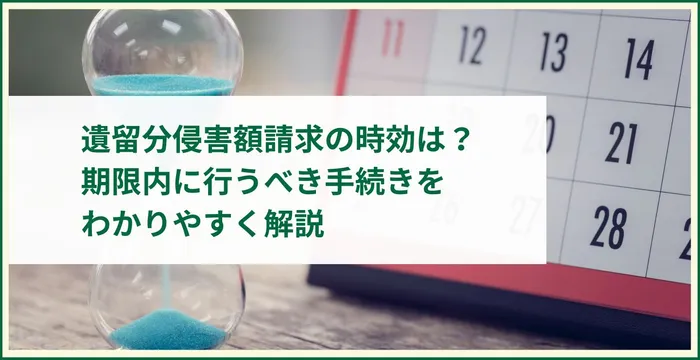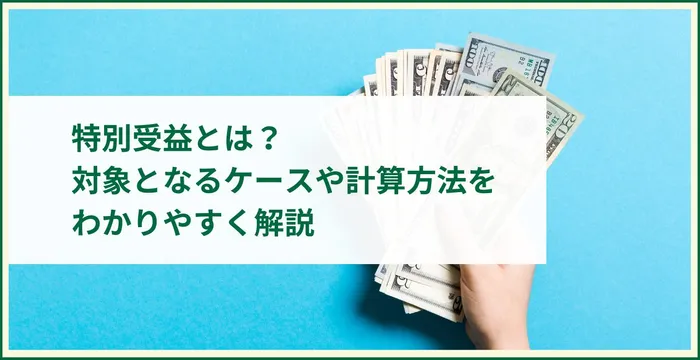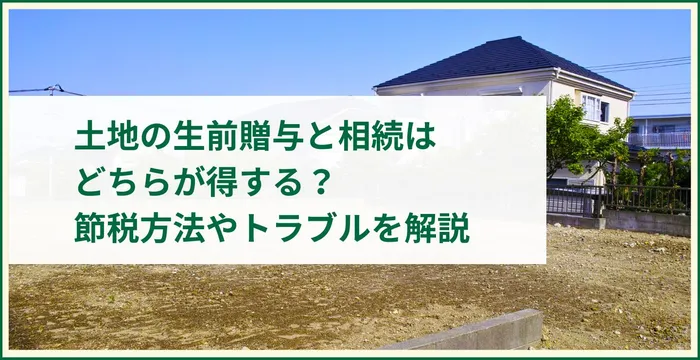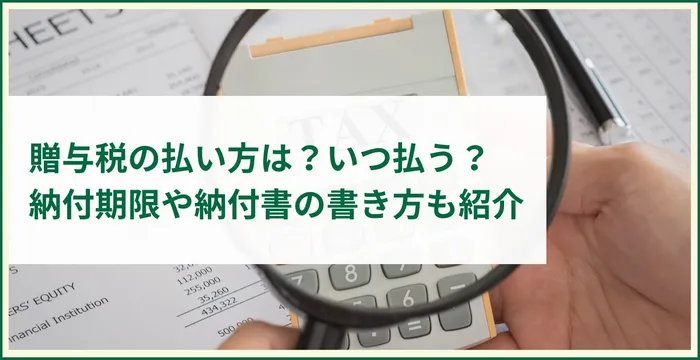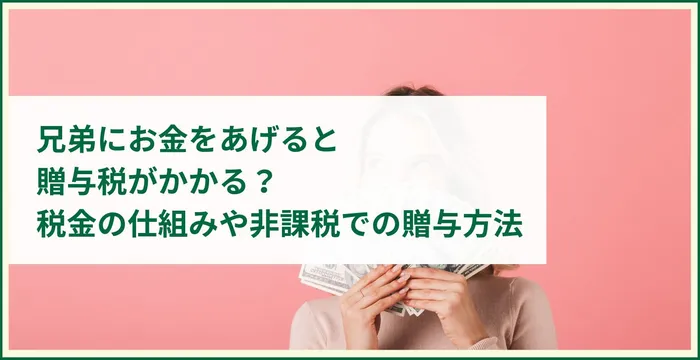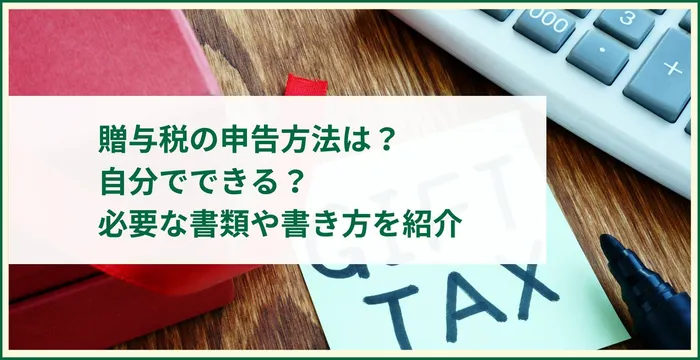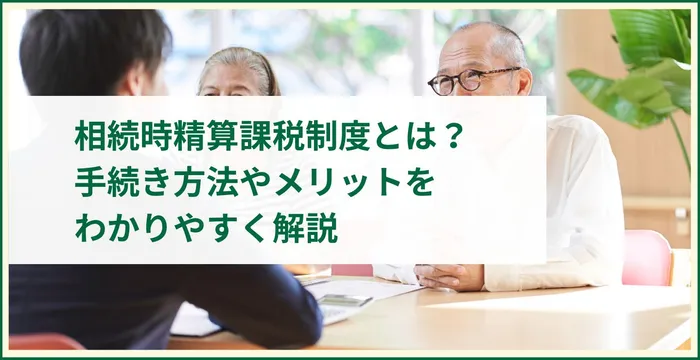生前贈与と相続における遺留分の関係
まず、生前贈与と相続における遺留分との関係について解説します。
生前贈与は他の相続人が受け取るべき遺留分を侵害するケースや、同じ生前贈与でも中には遺留分を侵害しないケースもあります。
この生前贈与と相続における遺留分の関係について以下で見てみましょう。
生前贈与は他の相続人の遺留分を侵害することがある
生前贈与は他の相続人の遺留分を侵害することがあります。
生前贈与とは、被相続人が生きている間に、子や孫、あるいは第三者などに無償で財産を譲ることです。
一方、遺留分とは、法定相続人が、遺産のうち、最低限受け取れると保証されている割り当て分のことです。被相続人の配偶者や子などの法定相続人は、被相続人の意思や遺言に関係なく、一定割合の遺産、遺留分を受け取ることができるとされています。
遺留分は、相続財産に基づいて計算されますが、生前贈与が行われていると、その計算のもととなる相続財産が減ることとなります。相続財産が減ると、受け取れる遺留分も減る(遺留分が侵害される)計算です。
なお、相続税の計算ルールとして、相続開始前の3年以内(※)の生前贈与については、相続財産に加算する(持ち戻す)こととなっています。この持ち戻し後に遺産分割を行うとしても、3年を超える生前贈与が相続財産に加算されないと、他の法定相続人の遺留分を侵害する可能性は残ります。
※2023年度税制改正により、相続開始前の3年以内から7年以内に段階的に変更されることとなりました。
10年以上前に受けた生前贈与は遺留分の計算に含まれない
生前贈与で他の相続人の遺留分を侵害している場合には、それらの法定相続人から「遺留分侵害額の請求」が行われることがあります。
遺留分侵害額の請求とは、被相続人が生前贈与を行ったために、相応の遺留分を受け取れなくなった遺留分の権利者が、生前贈与を受けた者に対し、侵害された金額を請求することです。
遺留分の権利者が遺留分を請求できる対象は以下の3つとされています。
- 相続開始前1年以内の相続人以外への生前贈与
- 相続開始前10年以内の相続人への生前贈与
- 贈与者と受贈者の双方が遺留分権利者に損害を与えると分かっていながら行った生前贈与
孫や愛人など相続人以外への生前贈与は相続開始前1年以内のものについて遺留分の計算に含まれます。
配偶者や子などの相続人への生前贈与については10年以内のものが対象です。言い方を変えると10年以上前に受けた生前贈与は遺留分の計算に含まれないといえます。
なお、遺留分権利者に損害を与えると知りながら行われた生前贈与は、期間を問わず全て遺留分計算の対象となります。
なお、これらの遺留分の侵害は金銭での請求・返還が原則のため、請求されると、金銭で侵害分を支払うこととなります。
10年以内の生前贈与に対する遺留分侵害額の計算方法
遺留分の侵害額がどのように計算されるかについて詳しく見てみましょう。
遺留分侵害額とは自分の遺留分がどれだけ侵害されているかを示すものです。遺留分侵害額の計算式は、以下の通りです。
【遺留分侵害額の計算式】
遺留分侵害額 = 遺留分額 -(遺贈または特別受益の価額)-(遺留分権利者が相続によって得た財産額)+(引き継ぐ借金の額)
【計算項目の内容】
|
項目
|
内容
|
|
遺留分侵害額
|
当該相続人が本来受け取るべき遺留分額から減額された(侵害された)金額。
|
|
遺留分額
|
当該相続人が本来受け取るべき遺留分の金額。
「相続財産(遺留分算定基礎額という)× 法定の遺留分割合」で計算される。
|
|
遺贈または特別受益の価額
|
当該相続人が遺贈・特別受益を受けていればその金額のこと。相続開始以来10年以内に限らず、過去全ての期間における遺贈・特別受益が含まれる。
|
|
遺留分権利者が相続によって得た財産額
|
遺留分の権利がある当該相続人が相続で受け取った財産の金額
|
|
引き継ぐ借金額
|
被相続人が残した借金のうち当該相続人が引き継ぐ借金の金額。
|
遺留分侵害額は、本来受け取るべき「遺留分額」から、これまでに受けた遺贈や生前贈与、相続額を差し引き、相続した借金額を加算して算出します。
具体例で見ていきましょう。
【例】
◆被相続人Aが下記遺産を残して亡くなったとする。
・預貯金3,000万円
・借金1,000万円
◆法定相続人は、Aの長男Bと長女Cの2名のみとする。
◆長男は、相続開始の5年前に4,000万円、相続開始15年前に1,000万円の生前贈与を受けていた。
◆相続人が子2人のみであるため、長男B、長女Cのそれぞれの相続割合は2分の1となる。
◆子の遺留分は全体で2分の1のため、長男B、長女Cのそれぞれの遺留分割合はその2分の1を平等に分けた4分の1となる。
以下では、遺留分の侵害請求をするのは長女Cとして、長女Cの遺留分侵害額を計算していきます。
遺留分額の算定
まず長女Cの「遺留分額」を算定します。
遺留分額は、遺留分算定基礎額となる相続財産に長女Cの遺留分割合(4分の1)をかけて計算します。遺留分算定基礎額となる相続財産は、相続開始10年以内の生前贈与を加算するので下記のように計算されます。
・遺留分算定基礎額=預貯金3,000万円 - 借金1,000万円 + 長男への生前贈与4,000万円 = 6,000万円
これに長女Cの遺留分割合4分の1をかけて遺留分額が求められます。
・長女Cの遺留分額=6,000万円 × 4分の1 = 1,500万円
遺贈または特別受益の価額
長女Cの「遺贈または特別受益の価額」を把握します。
これは長女Cが、遺贈や生前贈与で特別な利益を得た場合の価額のことです。遺留分算定基礎額の算出には、相続開始よりも10年以上前の生前贈与は考慮しないことになっていましたが、ここで差し引く「遺贈または特別受益の価額」には、10年以上前の生前贈与も加味します。
長女Cは過去にまったく遺贈・生前贈与を受けていないため、下記の通りとなります。
・長女Cの「遺贈または特別受益の価額」= 0 円
遺留分権利者が相続によって得た財産額
長女Cの「遺留分権利者が相続によって得た財産額」を算出します。
・長女Cの相続額=預貯金3,000万円 × 2分の1 = 1,500万円
です。
相続で引き継ぐ借金額は
・長女Cの引き継ぐ借金額=借金1000万円 × 2分の1 = 500万円
です。
遺留分侵害額
ここまでの計算から、長女Cの遺留分侵害額を求めると下記の通りとなります。
長女Cの遺留分=遺留分額1,500万円 -(遺贈又は特別受益の価額)0円-(遺留分権利者が相続によって得た財産額)1,500万円+(引き継ぐ借金の額)500万円= 500万円
長女Cの遺留分500万円について侵害されたとして長男Bに請求可能となります。
遺留分侵害額請求の方法
実際に遺留分侵害額を請求する場合の請求方法について解説します。
遺留分侵害額請求ができる人
まず、遺留分侵害額の請求ができる人について確認してみましょう。
遺留分侵害額の請求ができる人というのは、もともと遺留分を有するとされている人といえます。具体的には下記の相続人です。
【遺留分侵害額の請求ができる人】
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子ども(子どもが亡くなっている場合は代襲相続人となる孫)
- 被相続人の直系尊属(父母や祖父母。ただし子どもと子どもの代襲相続人がいない場合に限る)
被相続人の兄弟姉妹は、法定相続人となる場合でも遺留分はないとされているため、請求できません。
遺留分侵害額請求にかかる費用
遺留分侵害額の請求について、生前贈与を受けた受贈者と相続人との話し合いだけでスムーズに進めば、特に遺留分侵害額の請求にかかる費用は発生しません。
遺留分侵害請求の話し合いがまとまらずに調停などに持ち込む場合は、受贈者に内容証明を出し、調停申し立てを行うといった手続きが必要となります。調停を行う場合には下記のような費用が発生します。
【遺留分侵害額請求にかかる費用】
|
費用項目
|
内容・金額
|
|
内容証明郵便(配達証明付き)を送る費用
|
・遺留分侵害額の請求を行うことを生前贈与を受けた受贈者に知らせるための費用。
・通常の郵便料金 + 内容証明送付文書1枚当たり440円(追加1枚ごとに260円加算)
+配達証明350円
|
|
調停申立費用
|
・調停で遺留分侵害額の請求を行う場合に必要となる費用。
・1,200円分の収入印紙(※1)+ 数千円の郵便切手(※2)
※1 調停を起こす場合の申し立て費用のことで、収入印紙で支払う。
※2 裁判所から通知書などで連絡をもらう際の送料
|
|
戸籍謄本
|
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を取り寄せるための費用
・1通450円(除籍や改正原戸籍は1通750円)×必要人数分
|
遺留分侵害請求について調停などを行う場合には、まず「遺留分侵害の請求の意思表示」として、内容証明郵便(配達証明付き)を受贈者に送るため、内容証明送付と配達証明の費用が必要となります。
内容証明郵便とは、どのような内容の文書が誰から誰あてに差し出されたか、郵便局が証明するものです。さらに配達証明付きで送ることで、相手にいつ配達したのかも証明可能となりできます。
その後、調停を起こす場合には、調停申し立て費用として1,200円が必要です。これは裁判所に収入印紙で納めます。別途裁判所との連絡費用として数千円分の郵便切手が必要となります。切手代は裁判所によって異なるため確認が必要です。
また、調停を申し立てる際には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本と相続人全員の戸籍謄本が必要となるため、戸籍謄本を取り寄せる費用も必要となります。
また、弁護士に相談や交渉の依頼をする場合には、弁護士費用が必要です。弁護士報酬は自由化されているため、実際の弁護士費用は弁護士によって異なりますが、目安は下記の通りです。
【遺留分侵害額請求についての弁護士費用】
|
弁護士費用の内訳
|
費用の目安
|
|
相談料
|
0~1万円
|
|
着手金
|
10万~30万円
|
|
弁護士への成功報酬
|
遺留分侵害額請求によって得た利益の4%~16%など
(参考)【日弁連の旧報酬基準】
・回収額が300万円以下:回収額の16%
・回収額が300万円超3,000万円以下:回収額の10%+18万円
・回収額が3,000万円超3億円以下:回収額の6%+138万円
・回収額が3億円超:回収額の4%+738万円
|
最初に相談したときに相談料が発生します。最初の相談は無料で相談できるケースも少なくありません。正式に依頼することになると、着手金が発生します。着手金は、結果が不成功に終わっても支払うお金です。
また、弁護士の交渉が成功裏に終わると、別途成功報酬が発生します。その場合、依頼人が遺留分侵害額請求によって得た利益の4%~16%などの費用が支払われます。その他、弁護士事務所以外で弁護士が作業した場合には日当がかかったり、交通費や郵送費などの実費がかかったりします。
これらの費用が遺留分侵害請求の手続きで必要となります。
遺留分侵害額請求に必要な書類
遺留分侵害請求に必要な書類としては、下記のものがあります。
【調停や裁判を起こす場合に必要な書類】
1)調停申立書
2)被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
3)相続人全員の戸籍謄本
4)被相続人の子で死亡した者がいる場合、その子の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
5)遺言書写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
6)遺産に関する証明書(不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写しまたは残高証明書、有価証券写し、債務の額に関する資料など)
7)訴状
参考:裁判所「遺留分侵害額の請求調停」
調停を行う際には1)から6)までの書類が必要となります。1)の調停申立書とは、遺留分侵害請求の調停を申し立てる手続きのための書類です。調停申立書のテンプレートは下記の裁判所のホームページで確認できます。
・裁判所「遺留分侵害額の請求調停の申立書」
なお、7)の訴状は、裁判を起こす場合のみに必要となるものです。訴状のテンプレートは下記の裁判所のホームページで確認できます。
・裁判所「金銭支払(一般)請求」
裁判に際しても、調停と同じく2)から6)までの書類が必要となります。
遺留分侵害額請求の流れ
遺留分侵害額請求の流れは下記の通りです。
1. 当事者同士での話し合い
まずは、遺留分を侵害している相続人と侵害されている相続人との直接の話し合いでの解決を図ります。この話し合いで遺留分の返還に合意できれば、「遺留分侵害額に関する合意書」に合意した内容や返還日についてまとめておきましょう。その後、合意書に従って返還してもらうようにします。
2. 内容証明の送付
当事者同士の話し合いができない場合や、当事者同士の話し合いがまとまらない場合は、調停、訴訟へと続く可能性があります。調停や訴訟に備え、請求の意思表示の内容証明を、遺留分を侵害している相続人に送付します。
3. 調停による話し合い
当事者同士の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停申し立ての手続きを行い、裁判官および調停委員立ち合いのもと話し合いを進めます。
遺留分の返還について合意ができれば、裁判所で遺産分割調停調書が作成され、それに従って遺産分割がなされます。調停でも合意ができなければ、裁判へと続きます。
4. 裁判で決着する
調停でも話し合いが決裂して、なお遺留分侵害の請求をする場合には、請求側が原告となって訴訟を起こすことになります。
訴訟の提起先は、遺留分侵害額請求の金額が140万円以内であれば簡易裁判所、140万円以上の場合には地方裁判所です。
裁判では、双方の主張を踏まえて裁判官が判決を下します。勝訴となった場合には、遺留分を侵害している被告側が侵害分の返還をしない場合でも、強制執行ができるため、侵害分を取り戻せます。
生前贈与は「特別受益」として扱われる場合がある
特別受益とは、特定の相続人が、被相続人から遺贈や生前贈与などによって、特別に受けた財産上の利益のことです。
相続において、特別受益を相続財産に加えなければ不公平になるため、原則として、特別受益と見なされた場合は、相続財産に加算(持ち戻し)することとなっています。
遺留分侵害請求の場合には、相続開始から10年以内の生前贈与が対象という制限があったものの、相続においては、加算すべき特別受益の期間に制限はありません。過去の全ての特別受益が相続財産への加算対象となります。
なお、民法903条では、次の3つが特別受益となる生前贈与として挙げられています。
- 婚姻のための生前贈与
- 生計の資本としての生前贈与
- 養子縁組のための生前贈与
ただし、生前贈与が上記3つのいずれかに当てはまるからといって、必ずしも特別受益と見なされるわけではありません。遺産の前渡しと判断されるかどうかや、他の相続人が受けている生前贈与とのバランスを考慮して特別受益と判断されます。特別受益に該当するかどうかの判断は簡単ではなく、専門家の意見を仰ぐ必要があるといえるでしょう。
それぞれの詳しい内容は次の通りです。
婚姻のための生前贈与(持参金・嫁入り道具など)
婚姻のための生前贈与の例としては、下記の例が考えられます。
しかし、これらの全てが特別受益となるわけではありません。極めて高価であったり、必ずしも必要とされないものは特別受益と見なされる傾向です。扶養義務の範囲内、安価だと判断される場合は、特別受益とは見なされないことが多いといえます。
例えば、持参金・支度金および嫁入り道具は、必ずしも必要なものではないため特別受益と見なされやすいといえます。ただし、扶養義務の範囲内とされる価格である場合には、特別受益と見なされないことも少なくありません。
一方、挙式代は挙式を行えば消滅し、結納金も嫁ぎ先に贈った後は贈与を受けた子の手元には残らないため、特別受益とは見なされないケースがほとんどです。
なお、いくら以下であれば扶養義務の範囲内で特別受益でないと見なされるかという判断は難しく、専門家の意見を仰ぐ必要があります。
生計の資本になる生前贈与(車の購入費・子供の留学費など)
生計の資本、いわば、生計を立てる上での基礎として役立つ生前贈与の例には次のようなものがあります。
- 車の購入費
- マイホーム購入資金
- 開業資金
- 子どもの留学費
車の購入費やマイホーム購入資金、開業資金などは、金額も大きく、特別受益に当たるケースがほとんどといえます。
一方、子どもの学費については、通常は特別受益とは見なされないものの、留学資金や医学部への進学費用など高額な学費の贈与の場合は、特別受益と見なされる傾向です。
実際に特別受益と見なされるかどうかは、他の相続人が同様の生前贈与を受けていないかどうかも勘案して判断されるため、専門家に確認することがおすすめです。
養子縁組のための生前贈与(支度金・住居の準備費用など)
婚姻以外の養子縁組のための生前贈与の例としては、養子となる子供に、実の親が支度金や住宅の準備費用などを贈与するといったことが挙げられます。
養子縁組のための支度金や住宅の準備費用は、養子縁組をするために必ずしも必要な費用ではありません。そのため、贈与額が高額な場合は、特別受益とみなされる可能性が高いといえます。
生前贈与のうち特別受益とならないもの
生前贈与のうち特別受益とならないものもあります。代表的な例としては次の4つが挙げられます。
- 被相続人が「特別受益とはしない」と意思表示した生前贈与
- 夫婦間での不動産の生前贈与
- 死亡によって発生する生前贈与
- 介護や看護をしてくれた者への生前贈与
それぞれの内容について以下で詳しく解説します。
被相続人が「特別受益とはしない」と意思表示した生前贈与
被相続人が「特別受益とはしない」と遺言などで意思表示をした生前贈与については、特別受益とは見なされないこととなっています。
特別受益を相続財産に加算(持ち戻し)をするという制度は、相続人の間で大きな不平等が生じないように配慮された制度です。しかし、一方で、被相続人の「特定の人に多く遺産を残したい」という意思を尊重する意味で、生前贈与した分について特別受益とはしない制度も設けられています。
この制度を、「特別受益の持ち戻し免除」といいます。
特別受益の持ち出し免除を実現するためには、あらかじめ被相続人がその意思表示をしておく必要があります。
例えば、遺言書や贈与契約書などの書面で、特定の生前贈与財産について持ち戻し免除をすることを記載しておくなどすることで、その生前贈与は特別受益とは見なされなくなります。
ただし、遺留分侵害額の請求においては、この特別受益の持ち戻し免除は行われません。この特別受益の持ち出し免除は、通常の遺産分割の時に有効となるものです。
夫婦間での不動産の生前贈与(婚姻期間20年以上の住まい)
婚姻期間が20年以上の夫婦間における不動産の生前贈与については、原則として特別受益として扱わなくてよいこととなっています。
これは、2019年7月1日施行の民法改正で、婚姻期間20年以上の夫婦間における居住用不動産の遺贈・贈与があった場合には、「特別受益の持ち戻し免除」の意思表示があったと推定することとなったためです。
あくまで推定のため、確実に認められるわけではありませんが、多くの場合、特別受益ではないと判断されます。
また、特別受益の持ち出し免除は、前項でも述べた通り、遺留分侵害額請求をされる場合には、免除とはなりません。遺留分の算定基礎額である相続財産に加算されることとなります。
死亡によって発生する生前贈与(生命保険・死亡退職金)
生命保険や死亡退職金といった死亡によって発生する生前贈与は、原則として特別受益とはみなされないことになっています。原則として遺留分の算定基礎額の加算対象にもなりません
なぜなら、そもそも生命保険金などの保険金請求権は、保険金の受取人と保険会社との債権関係に基づくものであり、民法903条1項の遺贈や生前贈与に該当しないとされているからです。
ただし、過去には生命保険が特別受益に準ずるものとして扱われた判例もあります。(参考:最高裁平成16年10月29日第二小法廷の判例)これは、支払われた生命保険金の額が大きく、他の相続人の相続額との間に大きな不平等が生じたためです。
このように生命保険金の金額が、相続額と比べて極めて大きい場合には、特別受益と見なされることがあります。
介護や看護をしてくれた者への生前贈与(負担付贈与)
介護や看護をした人などへの生前贈与など、負担付贈与については、負担部分の評価額についてのみ特別受益とは見なされません。
負担付贈与とは、何らかの負担を負わせる代わりに贈与するというものです。例えば、介護や看護をお願いする代わりに、住宅資金の一部を支払ってもらうなどといったケースです。
この場合、介護や看護といった負担の部分の評価額を算出し、その分については特別受益に含めないとされています。
なお、遺留分の算定においても、負担付贈与については負担の評価額は特別受益とせず、生前贈与から負担部分の評価額を控除した額を遺留分の計算に加えることとなっています。
生前贈与に特別受益があった場合の持ち戻し計算
生前贈与に特別受益があった場合の持ち戻しの計算方法について紹介します。
下記2パターンについて、シミュレーションで解説します。
- 生前贈与を特別受益として持ち戻しをする場合
- 持ち戻しをしない場合
詳しくは次の通りです。
特別受益の持ち戻しをしない場合の遺産分割シミュレーション
特別受益の持ち戻しをしない場合の遺産分割のシミュレーションについて解説します。
特別受益の持ち戻しをしない場合は、相続財産に特別受益分を加算しないで、財産を法定相続割合に応じて分け合うこととなります。下記ケース例で実際にシミュレーションで見てみましょう。
【特別受益の持ち戻し計算用ケースⅠ】
◆被相続人Aの財産
4,000万円
◆法定相続人
妻B(配偶者)、長男C、長女D
◆特別受益となる生前贈与
長男Cが1,000万円、長女Dが600万円
上記ケースⅠに従うと、特別受益の持ち戻しをしない場合、相続財産は被相続人Aの財産4,000万円です。この相続財産4,000万円を法定相続割合に基づいて分割します。法定相続割合は、配偶者が2分の1で、子ども全員で残りの2分の1を均等に4分の1ずつ分けるため、それぞれの相続額は下記の通りとなります。
妻B:4,000万円 × 2分の1 = 2,000万円
長男C:4,000万円 × 4分の1 = 1,000万円
長女D:4,000万円 × 4分の1 = 1,000万円
特別受益の持ち戻しをする場合の遺産分割シミュレーション
次に、特別受益の持ち戻しをする場合の遺産分割のシミュレーションを見てみましょう。
特別受益の持ち戻しをする場合、相続財産に特別受益の金額を加算します。先述と同じケースでシミュレーションをしてみましょう。
【特別受益の持ち戻し計算用ケースⅠ】
◆被相続人Aの財産
4,000万円
◆法定相続人
妻B(配偶者)、長男C、長女D
◆特別受益となる生前贈与
長男Cが1,000万円、長女Dが600万円
まず、相続財産については下記の通りとなります。
被相続人Aの財産4,000万円 + 長男Cの特別受益1,000万円 + 長女Dの特別受益600万円 = 5,600万円
この相続財産5,600万円を法定相続割合で分割します。法定相続割合は、配偶者が2分の1で、長男Cと長女Dとで残りの2分の1を均等に分けた4分の1ずつです。これらの相続割合からそれぞれの相続額を計算し、長男C、長女Dの相続額からすでに受け取った特別受益分を差し引きます。
結果としてそれぞれの相続額は、下記の通りとなります。
妻B:5,600万円 × 2分の1 = 2,800万円
長男C:5,600万円 × 4分の1 - 1,000万円 = 400万円
長女D:5,600万円 × 4分の1 - 600万円 = 800万円
特別受益や遺留分の計算が難しい場合は弁護士への相談がおすすめ
上記で解説した通り、生前贈与のうち特別受益として扱われるか否かの判断は難しく、遺留分の計算も簡単ではありません。そもそも生前贈与がいつどのように行われたかどうかの立証も簡単ではなく、行われていたことが把握できたとしても不動産や非上場株式など評価額の算定が難しいケースが多いといえます。
また生前贈与の節税方法も比較的複雑です。贈与が年間110万円以下であれば非課税といった制度のほか、年間110万円の基礎控除を除く贈与財産が累計2500万円まで非課税となる「相続時精算課税制度」を活用する方法もあります。
生前贈与の相続における取り扱いは、素人にとっては難しいため、専門家である弁護士に相談することがおすすめです。
専門家の助言を受けることで、遺留分の請求にどう備えるか、また相続税の節税にどう対処すればよいかなど、適切な行動を取ることができるでしょう。
まとめ
10年以上前などの生前贈与については、遺留分侵害額請求の計算には含まれません。遺留分侵害額請求の計算上、相続財産に加算すべき生前贈与は、相続開始前10年以内のものとされています。
しかし、この遺留分の考え方とは別に、「特別受益」と見なされれば、贈与された時期に関係なく、遺産を分配する際の相続財産に持ち戻す必要があります。
特別受益と見なされるか否かの判断は簡単ではありません。また、遺留分の計算も煩雑です。生前贈与の相続への影響を正確に知りたい場合には、弁護士などの専門家に相談することがよいといえます。
相続をスムーズに進めるためにも、専門家の助言を受けて、適切に対応することがおすすめです。