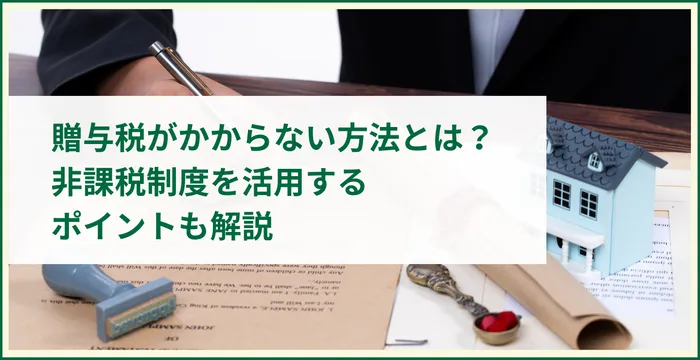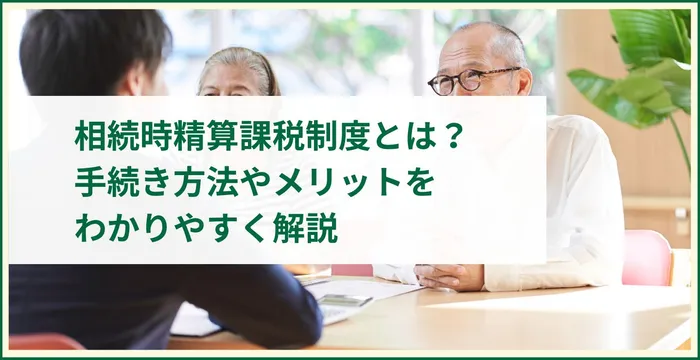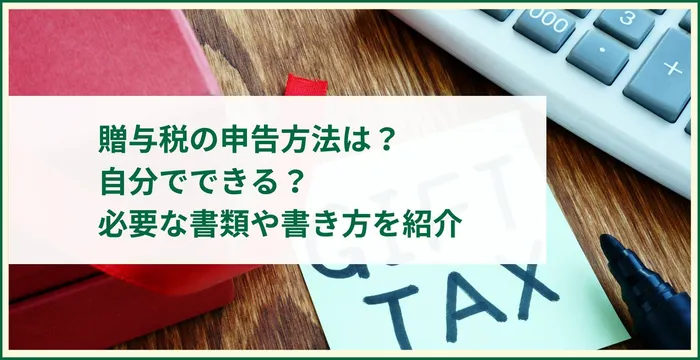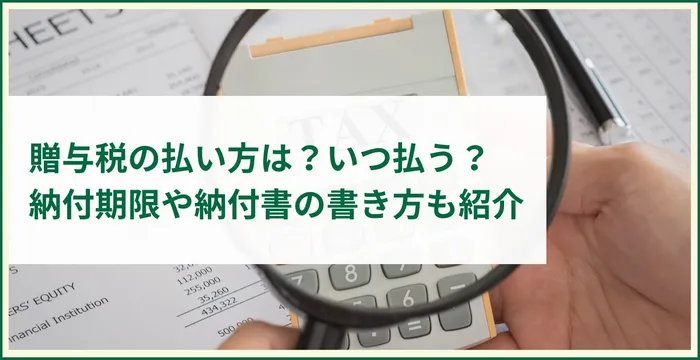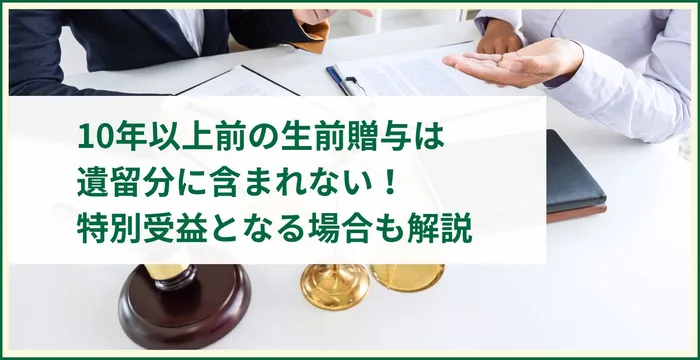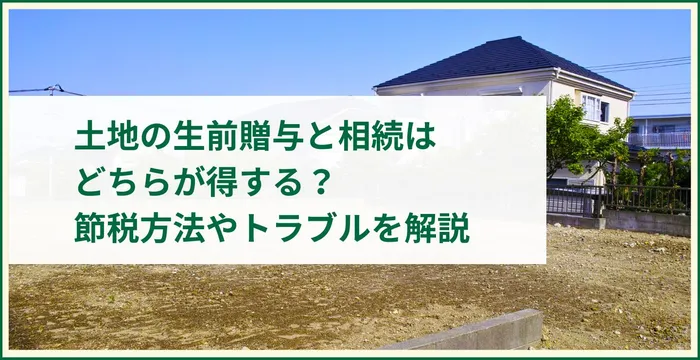親子間では生活費用や結婚費用、住宅購入費用など、多額の金銭のやりとりが生じることがあります。他者に金銭や不動産などの資産を贈ることは、法律的には「贈与」といい、親子間の贈与でも場合によっては税金がかかるので注意が必要です。本記事では、親子間での贈与ではいくらから税金が課されるのかをはじめ、課税されるケースと非課税になるケースそれぞれを解説します。贈与税の具体的な計算方法や注意すべきポイントなども紹介するので、ぜひご参考にしてください。
贈与税は親子でもかかる!課税・非課税のケースや注意点などを紹介

親子でも状況によっては贈与税が必要
親子間の贈与においても、一定の条件を満たした場合には贈与税がかかるので注意が必要です。以下では、贈与税がいくらからかかるのか、贈与税の基本的な課税条件と計算方法を解説します。
親から100万円もらうと贈与税は必要?
まず、親から100万円をもらう場合を考えましょう。贈与税は「年間110万円以上」の贈与があった場合に課されます。つまり、年間の贈与額が100万円であれば非課税枠内(基礎控除内)に収まるため、贈与税はかかりません。年間110万円以内なら非課税で済むことは、贈与税の節税において非常に重要なポイントです。
両親からそれぞれ100万円もらうと贈与税は必要?
次に、両親からそれぞれ100万円をもらう場合を考えてみます。ここで重要なのは、贈与税が「贈与を受けた人(受贈者)」に対して課税されるという点です。たとえ贈与する側が複数人であっても、非課税枠が増えるわけではありません。
したがって、両親から100万円ずつ、合計200万円の贈与を受けると、非課税枠の110万円を超えてしまうため、「200万円-110万円」で90万円分に贈与税が課されることになります。このように親子間、あるいは複数人からの贈与であっても、贈与の総額が非課税枠を超えた場合には税金が発生することを理解しておかなければなりません。
贈与税を計算する方法
贈与税には、「暦年課税」と「相続時精算課税」という2つの計算方法があります。ただし、相続時精算課税を選択する場合、それ以降は暦年課税の選択ができません。以下では、それぞれの計算方法を解説します。
暦年課税の計算方法
「暦年課税」は、1年間(1月1日~12月31日)に受けた贈与額から基礎控除額(110万円)を差し引いた金額に対して、税率を適用する方法です。受贈者は、贈与を受けた翌年の確定申告で贈与額を申告し、贈与税を納付します。ここでのポイントは、用いられる税率が「超過累進課税」であることです。つまり、基礎控除額を超過した贈与額が増えるにつれて、以下のように税率も上昇します。
| 基礎控除額を超過した贈与額 | 税率 |
|---|---|
| 200万円以下 | 10% |
| 300万円以下 | 15%(控除額10万円) |
| 400万円以下 | 20%(控除額25万円) |
| 600万円以下 | 30%(控除額65万円) |
| 1,000万円以下 | 40%(控除額125万円) |
| 1,500万円以下 | 45%(控除額175万円) |
| 3,000万円以下 | 50%(控除額250万円) |
| 3,000万円超 | 55%(控除額400万円) |
上記の一般贈与(一般税率)とは、親から未成年の子への贈与、夫婦間での贈与、兄弟間での贈与などで該当する仕組みです。親または祖父母などの直系尊属から成人の子や孫へ贈与する場合は、以下の特例贈与(特例税率)が適用されます。
| 基礎控除額を超過した贈与額 | 税率 |
|---|---|
| 200万円以下 | 10% |
| 400万円以下 | 15%(控除額10万円) |
| 600万円以下 | 20%(控除額30万円) |
| 1000万円以下 | 30%(控除額90万円) |
| 1,500万円以下 | 40%(控除額190万円) |
| 3,000万円以下 | 45%(控除額265万円) |
| 4,500万円以下 | 50%(控除額415万円) |
| 4,500万円超 | 55%(控除額640万円) |
納付すべき贈与税の額は、これらの税率や控除額を基に、以下の計算式で算出します。
贈与税=(贈与額-基礎控除額)×税率-控除額
一例を出すと、親から成人の子への贈与額が500万円の場合は、以下のような手順で計算します。
贈与額500万円-基礎控除額110万円=基礎控除後の課税額390万円
(課税額390万円×特例税率15%)-控除額10万円=贈与税48万5,000円
国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
相続時精算課税の計算方法
「相続時精算課税」とは、贈与者が亡くなった後で、贈与税と相続税を一括で納付する方法です。この制度は、贈与者が60歳以上の直系尊属(親や祖父母)で、受贈者が推定相続人、つまり子や孫である場合に選択できます。
この方法では、贈与に対する非課税枠が2,500万円となり、この枠を超えた額に対して一律20%の税率が適用されます。この制度の利点は、暦年課税に比べて大きな非課税枠を利用できること、そして贈与税の納付を相続時まで延期できることです。相続時精算課税を選ぶ場合は、以下の計算式で算出します。
贈与税=(贈与額-2,500万円)×20%
一例として、贈与額が3,000万円の場合を考えてみましょう。この場合、2,500万円分は非課税となるので、課税対象額は500万円になります。したがって、納付すべき贈与税は「500万円×20% =100万円」です。もし贈与者の死後に相続された財産があれば、ここに相続税も加算して納付します。
親子間で贈与税が非課税のケース
先述の通り、年間110万円以下の贈与であれば一般的に贈与税はかかりません。これに加えて、親子間の贈与ではそれ以外にも非課税になるケースが存在します。ここでは、そのような特別なケースをいくつか紹介します。
用途が教育費や生活費である
第一の例は、贈与の用途が教育費や生活費である場合です。扶養義務者(たとえば親)が被扶養者(子)に対してその都度支出する生活費や教育費、医療費などは贈与税の課税対象になりません。これは留学費用などについても、通常必要であると認められる限りにおいて同様です。
また、子から親に対する生活費の仕送りなども贈与税の対象にはなりません。この場合は、子のほうが扶養義務者で、親が被扶養者ということになります。
用途が結婚費用や出産費用である
親子間の贈与では、結婚や出産に関連する費用も、社会通念上相当とみなされる支出については贈与税の課税対象外です。たとえば、子の結婚式や結婚披露宴の費用、新居の入居費用や家具の購入費用などを親が立て替えたとしても贈与税はかかりません。
妊娠出産に伴う検診費用・入院費用、ベビー用品の購入費用なども同様です。ただし、妊娠出産に関しては、医療保険や出産育児一時金が支給される分を差し引いて考えなければいけません。
どのくらいの額であれば「社会通念上相当な範囲」を超えてしまうのかは、その人の立場や状況、地域性などに応じて変わります。もし不安であれば税務署や税理士などに相談しましょう。
親子間で贈与税が課税となる事例
生活費や結婚費用などの名目でお金をもらう場合も、場合によっては贈与税の課税対象になってしまうので注意が必要です。以下では親子間の贈与で課税が生じてしまう事例を紹介します。
教育費や生活費を貯蓄に回した
親から受け取った教育費や生活費は、原則として贈与税の課税対象外です。しかし、このような資金を預貯金に回したり、有価証券の購入などに使ったりした場合、本来の目的にそぐわない使用をしていると判断され、課税対象になる恐れがあります。たとえば、数年分の生活費・教育費をまとめて親からもらった場合などはこのリスクを特に警戒すべきです。
親が保険料を支払ってきた生命保険金を受け取った
親が保険料を支払ってきた生命保険金を子が受け取った場合も、贈与税の課税対象となるケースがあります。具体的には、親が保険料を負担してきた生命保険が親の存命中に満期になったり、保険を解約して保険金が支払われたりした場合です。こうした状況では、保険料の支払いは実質的に親から子への贈与とみなされる可能性があります。ただし、ケガや病気によって保険金を受け取った場合は贈与税の対象外です。
借金を肩代わりした
親が子の借金を肩代わりしたケースでも贈与と判断されます。ここには、クレジットカードの支払いやキャッシングローンなどの民間の債務だけでなく、滞納していた税金の納付なども含まれます。「子に直接お金を渡すわけではないから贈与ではない」と誤解しないように注意しましょう。
さらに、親から借りたお金の返済やその利子を免除してもらった場合も、その放棄された債権の価値が贈与として扱われることもあるので注意が必要です。なお、借金そのものは原則的に贈与にはあたりません。これは、返すつもりで借りるのであれば消費貸借契約に該当するからです。
親から住宅や車をもらった
贈与税が課されるのは現金だけではありません。不動産や自動車などの物理的な財産も贈与税の対象になりえます。土地や家などの不動産、あるいは自動車などの高額な動産が贈与された場合は、これらの財産の市場価値が贈与税の計算基準になります。
たとえば市場価値300万円の自動車を親から贈与された場合、300万円から贈与税の基礎控除額である110万円を差し引いた額(190万円)が課税対象になります。このように、現金以外の財産の贈与も贈与税の対象となるため、親子間で高額の財産を移転する際には、贈与税の発生を考慮しましょう。
親子間で贈与をするときの注意点
親子間での贈与にあたっては、感情面でも税制面でもトラブルが生じることがあります。こうしたトラブルを避けるためには、以下の点に注意することが重要です。
契約書を作成しておく
贈与を行う際には、その内容を明確にするために贈与契約書を作成しましょう。法律上、贈与は口約束でも有効です。しかし、書面に残しておかないと、税務調査が入った際に贈与について客観的に証明することが困難になってしまいます。
契約書には贈与の正確な額や対象物、贈与に双方が合意したことなどを明記しておくことが大切です。これは、税務調査への備えだけでなく、贈与に関して後に親子間でトラブルになることを避ける上でも役立ちます。
贈与税の節税をするには、基礎控除額の範囲内で毎年贈与を行うのが有効です。ただ、その場合も契約書はその都度作成することが推奨されます。たとえば、「毎年100万円、10年間贈与する」という契約内容にすると、実質的にその時点で1,000万円分の贈与が成立したと判断され、課税対象になりかねません。贈与の額・時期などにもバラつきがあったほうが、課税のリスクは低くなります。
贈与税の無申告はばれるので申告する
「親子間での贈与なら、無申告でいてもばれないだろう」と軽視されがちです。しかし、税務署の調査能力は優秀で、発覚するリスクが高いことを理解しなければいけません。相続の発生時や不動産の売買時、税務署はこれまでの資産の流れを調査することがよくあります。多額の贈与が行われた場合、この調査の過程で発覚する可能性は非常に高く、これはたとえ贈与の方法が現金の手渡しであっても例外ではありません。
もし贈与税が無申告であった場合、発覚した際には本来納付すべきだった税額に加え、申告期限を過ぎた分の延滞税や無申告加算税が発生します。延滞税は、無申告期間が長ければ長いほど高額になるので、結果として正直に申告した場合よりも大きな税負担が生じます。
このように、贈与税の無申告や隠蔽工作は税務当局に「ばれる」可能性と、追加のペナルティが発生するリスクがともに高いため、贈与が発生した際には適切な申告が非常に重要です。税法の遵守は、結果として将来的なトラブルや不要なコストを避けることにつながります。
贈与税がかからないように親の財産を受け取る方法
では、合法的に認められる範囲内で贈与税の節税を図るにはどうしたらいいのでしょうか。以下では、贈与税がかからないように親から財産を受け取る際に利用できる制度を紹介します。
相続時精算課税制度を利用する
贈与税を軽減する第一の方法としては、すでに紹介した「相続時精算課税制度」があります。この制度では、2,500万円までの贈与が非課税になるので、基礎控除の110万円を大きく超えて一度に贈与したい場合に有効です。もし非課税枠を超過した場合でも、税率は一律20%で済みます。暦年贈与の税率は最大55%なので、場合によっては暦年贈与よりも遥かに大きな節税が可能です。
ただし、この制度を選択すると、後で暦年課税に変更することはできません。また、贈与税がかからないとしても、相続が発生した場合は相続税を別途納付する必要がある点にも注意が必要です。
住宅資金贈与の特例を利用する
住宅資金贈与の特例を利用することでも大きな節税効果が期待できます。これは子や孫が自分の居住用に家を新築・増改築などをする際の資金援助を、直系尊属(親や祖父母)がする場合に利用可能な制度です。最大1,000万円までの贈与が非課税になります。相続時精算課税制度との併用も可能なので、その場合は合計3,500万円もの贈与を非課税にすることが可能です。
ただし、この特例を利用するには、受贈者の年齢・収入状況や、住宅の面積や仕様などに関する要件を満たす必要があります。たとえば、最大1,000万円の非課税枠を利用するには、対象の住宅が省エネ住宅などであることが求められます。それ以外の住宅の場合は500万円が非課税となる限度額です。
なお、この特例を利用する場合、贈与額が非課税枠内であれば納税は不要ですが、申告自体は必要になります。住宅資金贈与の特例は、他の制度との兼ね合いもあって税法の複雑な理解が必要なので、利用にあたっては税理士などの専門家に相談するのがおすすめです。
国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」
教育資金の一括贈与の特例を利用する
教育資金の一括贈与に関する特例は、子や孫の教育費用をサポートしつつ贈与税を節税するために有効な方法です。この特例を利用すると、直系尊属からの教育資金の一括贈与が、最大1,500万円まで非課税で行えます。
ただし、この特例を活用する上では、受贈者が「30歳未満である」「前年の合計所得金額が1,000万円以下である」という制限があります。また、贈与契約書を作成し、金融機関に教育資金専用口座を開設して、教育資金非課税申告書を提出することが必要です。
国税庁「No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
結婚・子育て資金の一括贈与にかかる特例を利用する
子の結婚や出産といったライフイベントは、節税しつつ多額の贈与をする絶好の機会でもあります。結婚・子育て資金の一括贈与にかかる特例を利用すれば、最大1,000万円までの贈与を非課税にすることが可能です。
ただし、この特例を利用するには、受贈者が「18歳以上50歳未満」という年齢制限や、「前年の合計所得金額が1,000万円以下」という収入制限があります。さらに、1,000万円のうち結婚資金に使えるのは300万円までなのでご注意ください。
国税庁「No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税」
贈与税の申告方法
贈与税の申告は、受贈者が行います。申告の基本的な流れは以下の通りです。
申告書の準備
まずは、贈与税の申告書やその他の必要書類を準備します。贈与税の申告書は税務署や、国税庁のホームページから取得可能です。贈与の形式(暦年贈与/相続時精算課税)や特例の利用の有無などに応じて、提出書類は変わるのでご注意ください。また、贈与税額を正確に計算するために、贈与をした際の明細なども用意しておきましょう。
税額の計算
贈与された資産の評価額から基礎控除などを差し引き、税額を計算して申告書に記載します。これが贈与税の額に反映されるので、正確な計算を心がけることが重要です。
税務署への提出
準備した申告書と必要書類を税務署に提出します。これは郵送や直接持参にて、またはe-tax(電子申告)を利用して行うことが可能です。
贈与税の支払い
申告が完了したら、計算された税額を納付しましょう。納付は、現金、e-tax、クレジットカード、コンビニなど、さまざまな方法で行うことが可能です。現金で納付する場合は、税務署や金融機関で納付書を取得して一緒に提出します。贈与税の申告と納税は、原則として贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに行わなければいけません。
まとめ
親子間といえども、一定以上の財産の贈与が行われた場合には贈与税の申告及び納付が必要になるので注意が必要です。親から年間100万円もらう程度なら非課税枠内に収まりますが、その場合でも贈与契約書などを作成して記録に残しておくと、後で税務調査が入った場合でも説明が容易になるので安心できます。また、子の進学や結婚・出産、住宅の取得などの大きなライフイベントは、非課税枠の大きい特例を利用できる絶好の機会です。贈与税を抑えたい方は、こうした機会を適宜利用して、計画的に贈与を行うことをおすすめします。