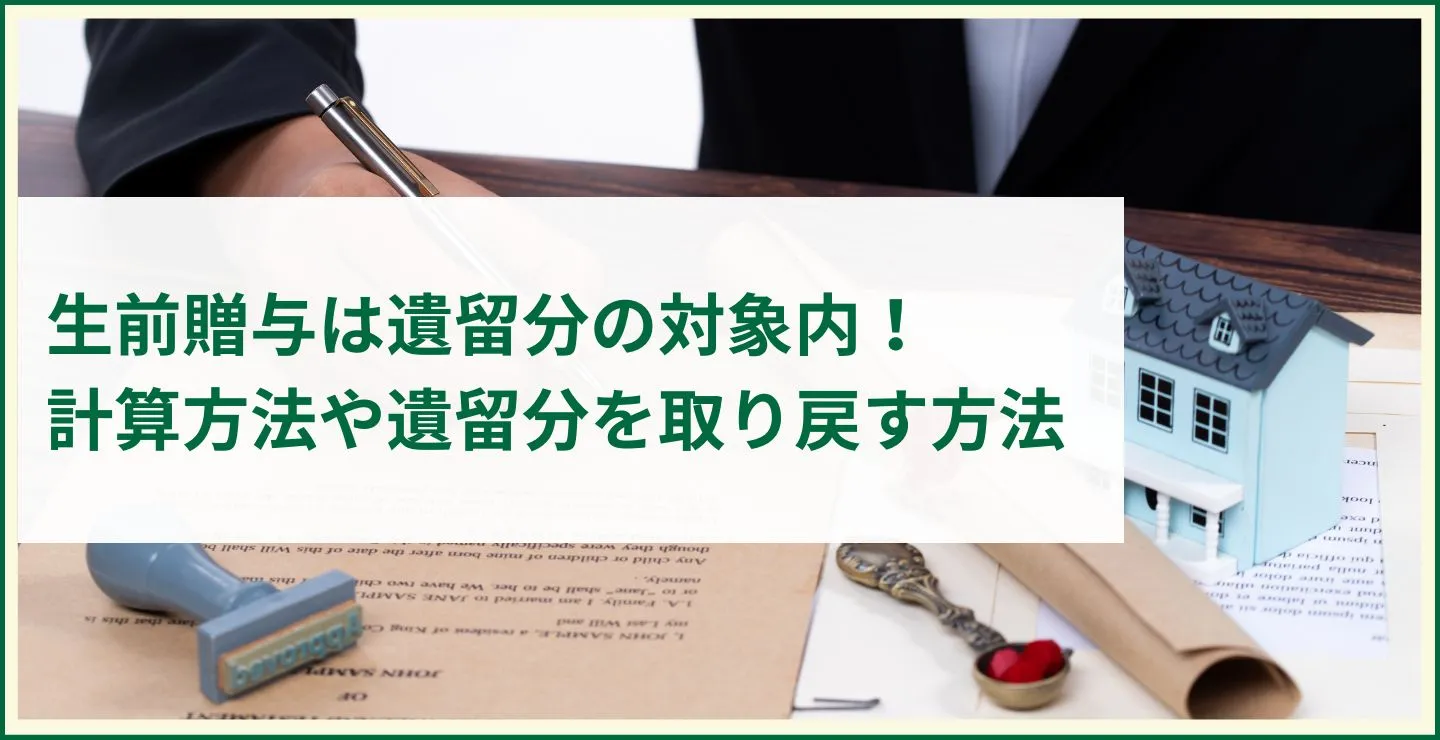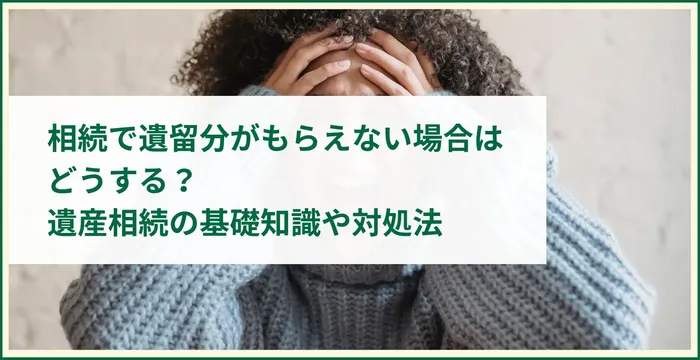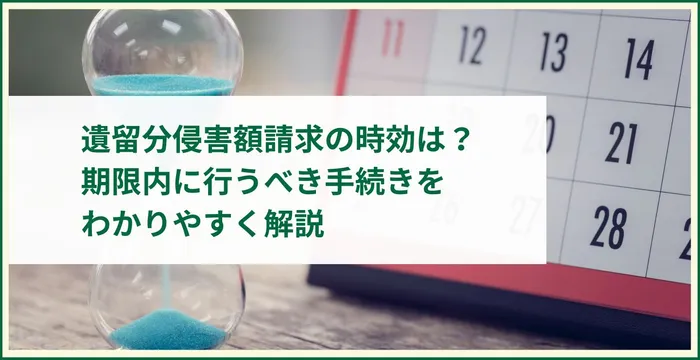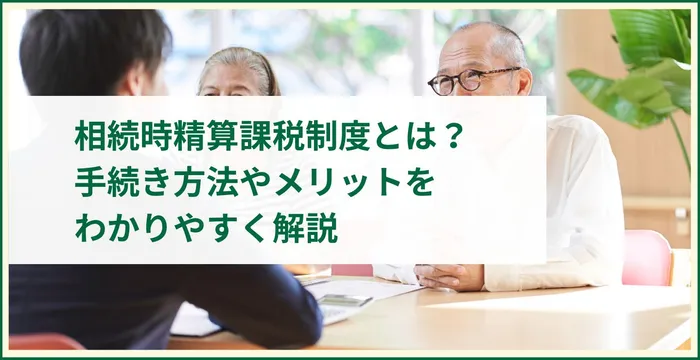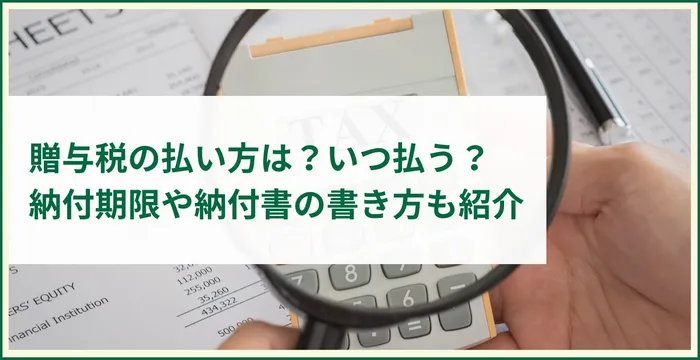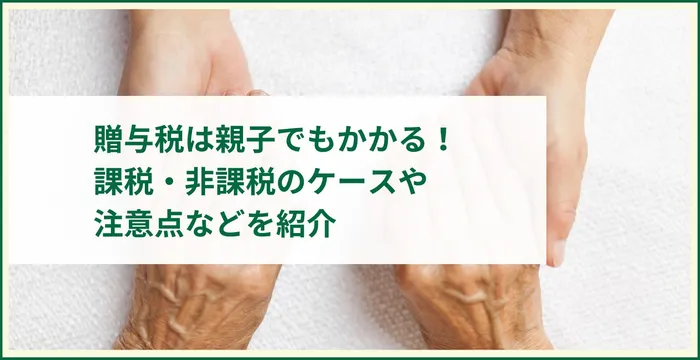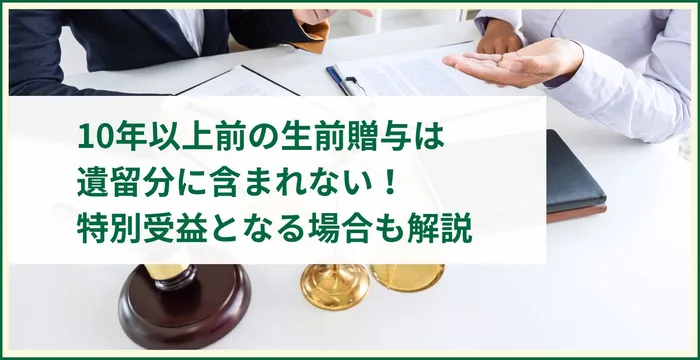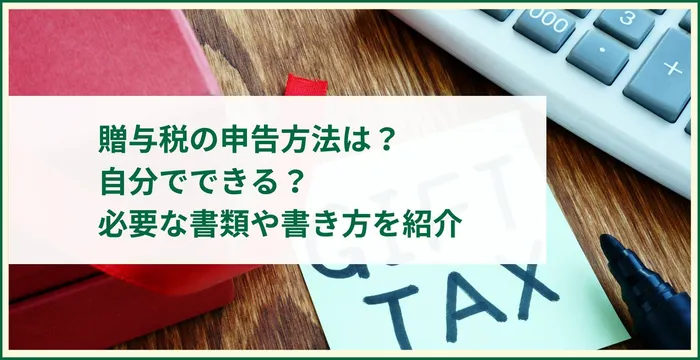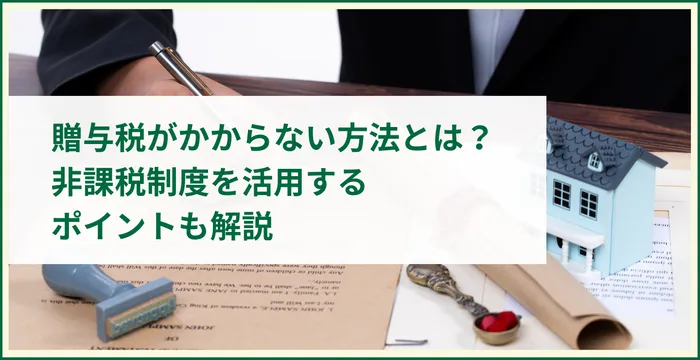生前贈与と遺留分の関係
まず「遺留分」とは、相続人に最低限保障されている遺産取得割合です。相続では遺言や遺言分散協議の結果に沿って遺産が分配されますが、遺言では特に気に入っていた人物だけ、遺産が分配されるよう記載されているケースもあるでしょう。
しかし、配偶者、子供・孫、親・祖父母に当たる相続人には、遺言に記載されていても奪うことのできない留保分が設けられています。それが遺留分です。
そして、遺留分は生前贈与とも密接に関係がある制度となっています。生前贈与と遺留分の関係について、特筆すべき点は主に以下の2つです。
- 生前贈与は遺留分の対象に含まれる
- 特別受益の持ち戻し免除は適用されない
それぞれ詳しく解説していきます。
生前贈与は遺留分の対象に含まれる
遺産に遺留分が適用されるなら、生前贈与にも遺留分は設けられているのか?と気になる方もいるでしょう。結論からいえば、生前贈与も遺留分の対象となります。なぜなら、生前贈与が遺留分の対象とならなければ、被相続人の遺族が相続できる財産が少なくなる可能性があるからです。
仮に生前贈与によって相続遺産がほとんど失われてしまうと、被相続人死亡時に残された家族が、経済的に困窮するかもしれません。特に、高齢となった配偶者は、被相続人の財産なしでは生活をするのが難しいでしょう。そのため、生前贈与が被相続人の遺族の生活を侵害しないよう、遺留分の対象となっているのです。
こうした遺留分を計算する際に、対象となる財産を「遺留分の基礎となる財産」と呼びます。遺留分の基礎となる財産として計算されるのは、主に以下の4つです。
- 被相続人が死亡1年前に贈与した財産
- 被相続人の死亡前10年以内に相続人が受けた特別受益
- 被相続人が相続開始時に持っていた財産
- 不相当な対価をもって行った有償行為
上記の財産を足して、債務を引いた合計額が「遺留分を算定する際の基礎となる財産」に当たります。仮に受け取った財産の金額が、基礎財産に遺留分の割合をかけた額(法定相続割合の2分の1または3分の1)に満たなかった場合は、その不足分を他の相続人や受贈者に対して請求することが可能です。
特別受益の持ち戻し免除は適用されない
生前贈与の遺留分に関しては、特別受益の持ち戻し免除は適用外となります。
まず、「特別受益の持ち戻し」とは、特別受益を相続遺産に加算して遺産分割を行う方法です。例えば、兄弟の中で長男だけ特別受益として住宅の購入費用を受け取りながら、遺産も分配された場合、家庭内で不満が発生するかもしれません。その際に、持ち戻しを行えば、特別受益も相続財産に含まれ、相続人間の公平性を保つことが可能です。
ただ、被相続人が遺産分割時に「特別受益を考慮せず分割してほしい」と意志を示せば、特別受益は相続遺産に加算できません。なぜなら、特別受益に該当する資産でも、被相続人の財産となった以上、持ち戻しを行うかどうかの意思は被相続人にあるからです。これを「特別受益の持ち戻し免除」といいます。
しかし、「特別受益の持ち戻し免除」は、遺産分割時に適用されるだけで、遺留分の計算には含まれません。そもそも、遺留分は相続の際に、兄弟姉妹以外の相続人へ最低限の取り分を保障する制度です。そのため、遺留分を侵害するような特別受益の持ち戻しは、認められないということです。
事実、平成24年1月26日の最高裁による判決では、特別受益の持ち戻しを希望しても、遺留分の基礎財産に含まれると判断されました。
参考: 遺産分割審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件
生前贈与が遺留分の対象になるケース
遺留分の対象となる生前贈与は、主に以下の3パターンです。
- 相続開始の1年以内に行われた相続人以外への贈与
- 相続開始10年以内に行われた相続人への特別受益に該当する贈与
- 遺留分の侵害に当たると知りながら行われた贈与
それぞれ順を追って解説していきます。
死亡前1年以内に行われた生前贈与
被相続人が死亡する1年以内に行われた生前贈与は全て遺留分の対象となります。
これは相続人だけでなく、相続人ではない親族への生前贈与も対象です。他にも、友人や愛人、団体など親族に該当しない他人への贈与も遺留分として加算できます。
逆に言えば、相続人に行われた1年以内の生前贈与や、1年以上前に行われた生前贈与に関しては、後述する条件に該当しない限り遺留分に加算できません。
遺留分を侵害すると理解したうえで実施した生前贈与
他にも、遺留分の侵害に当たると行われた生前贈与は、相続開始時期や特別受益かどうかに関わらず遺留分として見做されます。
例えば、資産が増える見込みのない被相続人が、資産の半分以上を1人の人物に贈与したとしましょう。すると、被相続人が亡くなった際に、他の相続人が獲得できる資産は遺留分より少なくなる可能性があります。これが「遺留分の侵害」です。そして、生前贈与が遺留分の侵害になると被相続人と受贈者(財産を受け取った人物)が知っていた場合、贈与財産は遺留分に含まれます。
ただし、「遺留分の侵害に当たるかどうか」は、贈与に関わった双方が認知していたかが重要です。そのため、双方から「侵害に当たると知らなかった」と言われてしまえば、遺留分の侵害を立証するのは難しくなります。
そのため、当事者間同士での解決が難しい場合は、弁護士に相談してみるのもいいでしょう。弁護士に依頼すれば、贈与の時期や贈与者の健康状態、財産の状況などから「遺留分を侵害すると知り得たか?」を立証してくれる可能性があります。
死亡前10年以内の相続人への特別受益にあたる生前贈与
10年以内に相続人へ行われた特別受益も、遺留分の対象となります。
特別受益とは主に結婚や住宅購入の際に、相続人へ特別に資産が送られることです。簡単に言えば、特定の相続人だけが得をするような贈与が特別受益に当たります。例えば、長男だけが住宅購入をする際に生前贈与を受けていた場合は、特別受益と見做されるでしょう。
特別受益として見做される生前贈与は、主に以下のケースです。
- 生活費・学費
- 事業を始めるための援助
- 結婚費用
- 居住用の不動産を購入するための資金
- 借金の肩代わり
一方で、相続人以外への贈与や、贈与した資産が扶養の範囲内に当たる場合は特別受益には該当しません。また、生命保険や死亡退職金なども、特別受益の対象外となります。
なお、特別受益に当たるかどうかは、財産の金額や被相続人の経済状況によって変化するので、個人で判断するのは非常に困難です。そのため、特定の相続人へ行われた生前贈与が特別受益に該当するか迷ってる方は、1度弁護士へ相談するのが得策でしょう。
遺留分の計算方法
遺留分の計算は、主に以下の流れに沿って行われます。
- 1.遺留分の基礎となる財産を計算する
- 2.個別の遺留分割合を出す
- 3.遺留分割合に基づいて遺留分を計算する
それぞれ順を追って解説していきます。
1.遺留分の基礎となる財産を計算する
まず、遺留分の基礎となる財産を計算します。
計算方法は以下の通りです。
相続開始時の全財産+被相続人死亡1年前の生前贈与+死亡10年前に相続人へ行われた特別受益ー債務=遺留分の基礎となる財産
これを算出するためには、すべての財産の価値と、生前贈与、債務の額を割り出す必要があります。しかし、事前に額を知らされていない限り、正確な額を割り出すのは困難です。
特に、生前贈与が誰に、いくら行われたか分からない場合も多いでしょう。その際は、贈与契約書を確認するか、税務署へ開示請求手続きを行ってください。
生前贈与は相続税を計算する際に、相続人がその有無を調査できるよう、相続税法49条1項に基づいて所轄税務署長に開示の請求が可能になっています。
開示請求手続きに必要な書類は以下の通りです。
- 全部分割の場合:遺産分割協議書の写し
- 遺言書がある場合:開示請求者及び開示対象者に関する遺言書の写し
- 上記以外の場合:開示請求者及び開示対象者に係る戸籍の謄(抄)本
これらの書類を提出すれば、相続開始3年以内の贈与について割り出すことが可能です。
また、家の中に督促状が残っていない場合は、債務を調べるのが難しいかもしれません。
被相続人の債務がどれほどあるか分からない場合は、以下の3つの方法で調査することができます。
- 借金がある場合:全国銀行協会、CIC、JICCに問い合わせる
- 税金の滞納がある場合:市税事務所などの問い合わせる
- 不動産が差し押さえされている場合:不動産の登記簿謄本を取得
なお、財産や生前贈与に現金以外の財産が含まれていた場合は、相続開始時の評価額で計算してください。現金と違って、不動産や動産(車や骨董品)は時期によって価格が変動します。そのため、相続開始時の評価額を、遺留分の基礎となる財産として計算するのです。
ただ、車や骨董品は買取先によっても、価格が大きく変動する場合もあるでしょう。その際は、相続人同士で話し合って決定するか、相場の平均を評価額として設定するのがおすすめです。
2.個別の遺留分割合を出す
遺留分の基礎となる財産の総額を割り出したら、個別の遺留分の割合を確認しましょう。
基本的に遺留分の割合は、法律で決められた相続割合(法定相続分)の2分の1です。ただし、相続人が被相続人の直系尊属(父母・祖父母)に当たる場合は、相続割合は3分の1と定められています。つまり、法定相続割合×2分の1または3分の1が、遺留分の割合ということです。
相続人ごとの詳しい遺留分の割合は以下の表の通りとなります。
|
相続人の内訳
|
法定相続割合
|
遺留分の割合
|
|
配偶者のみ
|
全額
|
2分の1
|
|
子・孫のみ
|
全額
|
2分の1
|
|
父母・祖父母のみ
|
全額
|
3分の1
|
|
兄弟姉妹または甥・姪のみ
|
全額
|
遺留分なし
|
|
配偶者と子または孫
|
配偶者2分の1
子供2分の1
|
配偶者4分の1
子供4分の1
|
|
配偶者と父母または祖父母
|
配偶者3分の2
父母または祖父母3分の1
|
配偶者3分の1
父母6分の1
|
|
配偶者と兄弟姉妹または甥・姪
|
配偶者4分の3
兄弟姉妹4分の1
|
配偶者2分の1
兄弟姉妹なし
|
なお、被相続人の兄弟姉妹には遺留分は認められないので、「なし」と表記しています。
3.遺留分割合に基づいて遺留分を計算する
上述した遺留分割合が判明したら、遺留分の基礎となる財産の額と掛け合わせて計算します。
例えば、1億の資産を配偶者と子供1人で分ける場合は、1億円×4分の1で2,500万円が2人の遺留分です。仮に子供が複数人いた場合は配偶者が2,500万円で、子供の遺留分は2,500万円÷子供の人数で計算します。割り出された遺留分より相続財産が少なかった場合は、「遺留分が侵害されている」状況ということです。
自身の相続財産を確認して、遺留分に満たなかった場合は遺留分侵害額請求するのがいいでしょう。
遺留分を取り戻す際の流れ
上述した手段で計算した遺留分に、相続した財産が満たなかった場合は、遺留分を取り戻すために動くのがおすすめです。
遺留分を取り戻す際の流れとしては、主に以下のようになっています。
- まずは当事者の協議において解決を目指す
- 内容証明郵便を送付する
- 遺留分侵害額請求調停を申し立てる
- 遺留分侵害額請求訴訟で決める
それぞれ詳しく解説していきます。
まずは当事者の協議において解決を目指す
遺留分侵害額請求の方法として、裁判・調停といった手段も挙げられます。しかし、裁判や調停はあくまで最終手段で、まずは当事者間で話し合うのがおすすめです。例えば、相続時の遺留分に関して、相手方が把握していない可能性もあります。
もし、相手方が話し合いに応じてくれるなら、遺留分割合など具体的な数字を出しながら交渉してください。遺留分は法律で割合が明記されているので、相手方も納得せざるを得ないはずです。具体的な数字を出すのが難しいようであれば、弁護士に依頼して話し合いに参加してもらうのもいいでしょう。仮に話し合いで決着するならば、調停や裁判に発展してから弁護士へ依頼するよりも費用が安く済む可能性があります。
話し合いがまとまったら、話し合いに参加した全員の署名・押印がある和解書か合意書を作成しましょう。話し合いの内容を証拠として残しておかなければ、後に「言った言ってない」の水掛け論に発展する恐れがあります。
和解書や合意書の効力に不安があるのなら、公正証書として作成するのもいいでしょう。公正証書は公証人(法律のプロ)立ち合いの元作成される文書で、公的に高い証明力を有しています。また、作成後は元本が公証役場に保存されるので、文書の改竄や、紛失を心配する方にはおすすめです。
内容証明郵便を送付する
当事者間の話し合いで決着がつかなかった場合は、内容証明郵便を利用して遺留分侵害額請求を行いましょう。
内容証明郵便を簡単に説明すると、郵便局が郵便物の内容を証明してくれる制度です。そのため、内容証明郵便を利用すれば、相手方に法的通知をしたと郵便局が証明してくれます。正式な文書を送ることで、受け取る側にも重圧を与えられるため、遺留分の支払いに繋がる可能性もあるでしょう。
また、内容証明郵便の送付は、民法上では債権者が債務者へ債務履行を要求する催告に当たります。そして、催告を行った場合には、時効期間の6ヶ月延長が可能です。そのため、内容証明郵便を送付すれば、遺留分侵害学請求の時効の完成を6ヶ月停止させられます。
参考:法テラス
遺留分侵害額請求の時効は、「侵害を知った時」から1年と短いため、速やかに内容証明郵便を送るのがおすすめです。
遺留分侵害額請求調停を申し立てる
内容証明郵便を送っても、相手方が支払いに応じなければ、家庭裁判所で遺留分侵害額請求調停を申し立てましょう。
調停とは、裁判官や民間人から選ばれた調停委員の立ち合いの元、話し合いで問題の解決または和解を目指す手続きです。調停委員が間に入って、問題解決へ向けたアドバイスをしてくれるので、当事者間だけで行うよりもスムーズに話し合いを進められます。また、裁判のように法律に則った勝ち負けではなく、話し合いによる解決を目指すので、双方が納得できる結果を得られるかもしれません。
そして、話し合いが解決したら、裁判所側が話し合いの結論を調停証書として作成してくれます。調停証書には確定判決と同じ効果があるため、支払いが行われなかった場合は、複雑な手続きなしで差し押さえを行うことが可能です。そのため、当事者間の話し合いよりも、法的に強い強制力を相手方に与えられます。
ただし、調停はあくまで話し合いの場を設ける制度なので、第三者が判決を下してくれるわけではありません。そのため、委員から「話し合いでは解決しない」と見做された場合は、調停が打ち切られる可能性があるので注意してください。
また、調停に出頭しなかった場合のペナルティはないため、相手方が調停に現れない可能性もあります。相手方が出頭しなければ「話し合いは成立しない」と判断され、調停は打ち切られると覚えておきましょう。
調停申し立てに必要な書類は以下の通りです。
- 被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子が死亡している場合、その子の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本
- 遺言書の写しまたは遺言書の検認調書謄本の写し
- 預金通帳など遺産を証明する資料
参考:遺留分侵害額の請求調停
他にも、申し立ての費用として収入印紙代1,200円と、連絡用の郵便切手が必要となります。切手代は家庭裁判所によって異なるので、申し立てる裁判所のウェブサイトを確認してください。例えば、東京家庭裁判所では切手代として1,022円ほどかかります。
参考:裁判所 予納郵便切手一覧
遺留分侵害額請求訴訟で決める
調停でも決着がつかなかった場合は、遺留分侵害額請求訴訟訴訟を提起しましょう。
訴訟は他の手段に比べて、法的強制力が非常に強い点が特徴です。例えば、訴訟は調停とは違い、被告が出頭しなければ訴訟した側の主張が全て認められます。そのため、相手方を半強制的に出頭させることが可能です。
ただし、訴訟による解決は、時間がかかりすぎるというデメリットがあります。基本的に半年から1年ほどかかるため、すぐに遺留分の財産を獲得できるわけではないのです。そのため、十分な財産が獲得できず生活が困窮する可能性があります。
また、裁判では法的観点に基づいて争うため、「遺留分が侵害されている」ことを立証できる客観的証拠が必要です。具体的には、遺言書や贈与契約書など、「遺留分が侵害されるほどの財産が贈与された」と証明できる文書が有効となります。
しかし、これらの証拠を十分に集め、遺留分が侵害されていると正確に計算するのは一般人には困難でしょう。そのため、遺留分侵害額請求を行う場合は、裁判の手続きや証拠集めを含め、弁護士に依頼するのが得策です。弁護士ならば弁護士法に基づいて、生前贈与に関して詳しく調査する権利を持っています。そして、相手方が得ている利益を正確に計算して、遺留分の侵害を証明してくれるでしょう。
また、裁判のためには証拠集め以外にも、慰謝料請求の作成など準備が必要な書類がいくつもあります。更に、裁判となれば、相手方も弁護士を立ててくるかもしれません。法律のプロ相手に、一般人が法的根拠を持って主張するのは難しいでしょう。これらの負担がなくなると考えれば、弁護士に依頼するメリットは非常に大きいといえます。
遺留分侵害額請求に関する注意点
遺留分侵害額請求は自身の相続分を最低限確保できる手段ですが、一方で請求する上での注意点もあります
遺留分侵害額請求を行う上で、注意すべきポイントは以下の6点です。
- 請求の権利は最短1年で時効となり消滅する
- 相手が返還に応じない場合がある
- 相手が使い込んだ場合、回収が難しくなるケースがある
- 不動産に対する遺留分侵害額請求は行えない
- 遺留分侵害額請求者は請求する相手を選べない
- 生前贈与を受けた人が相続放棄すると遺留分侵害額請求ができない可能性がある
それぞれ詳しく解説していきます。
請求の権利は最短1年で時効となり消滅する
上述した通り、遺留分侵害額請求の権利は最短1年で時効となり消滅するので注意してください。
一応、「被相続人の死亡時から10年間」が、長期消滅時効として定められています。しかし、相続人が「遺留分の侵害」を知った場合は、知った日から1年が消滅時効の期間となってしまうのです。つまり、「遺留分の侵害」を知らない場合の猶予期間が10年、知ってからの猶予は1年と覚えておきましょう。
遺留分侵害額請求の時効消滅は非常に早いので、遺留分の侵害を知った場合は、すぐに相手方へ内容証明郵便を送るのが得策です。内容証明郵便を送れば、「請求した」という事実が郵便局によって証明され、時効完成を6ヶ月停止させることもできます。
相手が返還に応じない場合がある
遺留分侵害額請求をしても、相手が返還に応じてくれない場合もあるでしょう。
例えば、相手方と自分の仲が悪いと、返還に非協力的である可能性もあります。また、仲の悪い相手との話し合いは、精神的にも非常に負担がかかります。特に財産というデリケートな話題を扱うため、つい感情的になってしまい話し合いがスムーズに進まないかもしれません。
相手との話し合いが上手くいかない場合は、弁護士に依頼して代理人として相手方と話し合いを行なってもらいましょう。弁護士であれば、法的観点に基づいて正確に遺留分を割り出し、冷静で的確な主張を行なってくれます。弁護士相手であれば、相手方も重圧を感じて素直に返還に応じてくるかもしれません。
また、相手方がどうしても返還に応じず、調停や裁判に発展した場合でも、弁護士に依頼すればスムーズに手続きを行なってくれます。特に裁判に発展した際に、「遺留分を侵害された」客観的な証拠を、個人で集めるのは非常に困難です。そのため、相手が素直に返還に応じない場合は、弁護士に依頼するのがおすすめとなっています。
相手が使い込んだ場合、回収が難しくなるケースがある
相手が相続した財産を使い込んでいた場合、遺留分の回収が難しくなるケースがあります。
本来、遺留分は法的に認められた権利なので、客観的な証拠に基づく正当な遺留分侵害額請求であれば、最低限の取り分を取り戻すことが可能です。しかし、相手が既に相続した財産を使い切ってしまい、資産がなくなっていると回収が困難になります。当然ですが、無くなってしまった財産を、相手から取り戻すことはできないからです。
そのため、相手方が財産を使い込む前に、仮差し押さえを行なって相続財産の保全措置を行いましょう。仮差し押さえは、遺留分侵害額請求前に、請求額に相当する範囲で相手方の財産の処分を禁止する手続きです。例えば、相手が車や骨董品を相続していた場合は、自由に売買したり譲渡できなくなります。
ただ、仮差し押さえをするには、相手が相続した財産を正確に把握しておかなければいけません。相続財産を正確に計算するのは一般人には難しいので、ここも弁護士に依頼するのが得策です。
不動産に対する遺留分侵害額請求は行えない
不動産に対しては、遺留分侵害額請求は行えない点も注意してください。なぜなら、遺留分侵害額請求は受贈者に対して、遺留分の侵害額を金銭で要求する制度だからです。かつては現物返還も可能でしたが、2019年7月1日の民法改正によって、遺留分に相当する額を金銭で請求する決まりに変更されました。
そのため、相手方が不動産を相続していた場合、不動産の返還を要求することはできません。不動産が相続財産だった場合は、相続した際の不動産の評価額を割り出し、その金額を元に遺留分額請求を行います。
ただし、不動産は高額な財産であるため、金銭での支払いができない受贈者もいるでしょう。例えば、5,000万円近い不動産を相続しながら、現金の資産は100万しかなかった場合、支払いは困難になるでしょう。そのため、双方が合意すれば金銭の代わりに、不動産を請求者に譲渡可能となっています。ただし、不動産の譲渡は「譲渡取得」と見做され、譲渡取得税がかかってしまうと覚えておきましょう。
どうしても金銭で返還できない場合は、不動産を共有財産とするのもひとつの手段です。
遺留分侵害額請求者は請求する相手を選べない
遺留分侵害額請求者は、請求する相手が選べない点も注意してください。
勘違いされがちですが、遺留分侵害額請求を負担する順序は民法1047条第1項で定められています。そのため、請求者が特定の人物を選んで、遺留分侵害額請求を行うことはできません。
民法で定められた遺留分侵害額を請求できる順番は、主に以下の通りです。
- 生前贈与より相続で受け取った人が先に負担
- 相続した人物が複数いる場合、遺産の価額に応じて負担
- 同時に生前贈与されたものがいる場合、財産の価額に応じて負担
- 生前贈与されたものが複数人いる場合、贈与を受けた時期が近い順から負担
参考:法令検索
まず、生前贈与で財産を受け取った方よりも、相続で受け取った人へ先に侵害額請求を行ってください。
また、相続した人が複数人いた場合は、相続された財産の価額によって負担額が決定されます。例えば遺留分が1,000万円で、受遺者Aが3,000万円、受遺者Bが1,000万円を相続していたとしましょう。この場合、AとBの負担割合は3:1となり、Aは750万円Bは250万円を請求します。同時に生前贈与された者がいる場合も同様です。
ただし、生前贈与されたものが複数人いる場合は、贈与を受けた時期が新しい順で負担していくことになります。
生前贈与を受けた人が相続放棄すると遺留分侵害額請求ができない可能性がある
生前贈与を受けた人が相続放棄をすると、遺留分侵害額請求ができなくなる可能性があります。
なぜなら、相続放棄を行なった相続人は、「最初から相続人ではなかった」と見做され、特別受益の対象とはならないからです。そのため、相続開始から10年以内に行われた特別受益にあたる生前贈与としての、遺留分侵害額請求ができなくなります。
特別受益として見做されない場合は相続開始の1年前、もしくは遺留分権利者へ損害を与えると知りながら行われた生前贈与に対してのみ遺留分侵害額請求が可能です。しかし、生前贈与が相続開始1年以上前に行われるケースも多いため、遺留分の対象にならない可能性が高くなります。また、「遺留分権利者へ損害を与える」と、贈与者と受贈者が知っていたかを証明するのは非常に難しいでしょう。
一応、相続放棄に関しては、以下に該当する場合は相続放棄の無効を主張できます。
- 相続人が相続財産を全部または一部を処分した場合
- 相続放棄をした後に相続財産を秘匿し、私的に消費していた場合
- 相続人に知らせずに他の人が相続財産を放棄した場合
ただし、上記のケースを理由にしても、遺留分侵害額請求を目的とした無効化は認められないかもしれません。なぜなら、利益を得るために行う相続放棄の無効は、信義則違反や権利濫用と見做される可能性があるからです。
そのため、相続放棄をされると、遺留分侵害額請求を行える可能性はかなり低くなると言っていいでしょう。
生前贈与を含めた遺留分を請求する際は弁護士への相談がおすすめ
生前贈与を含めた遺留分を請求するには、弁護士へ相談するのがおすすめです。
先述した通り、遺留分の請求は相手方が支払いに応じなかった場合は、回収が難しくなる可能性があります。しかし、弁護士に依頼すれば、相手方へ強い圧力をかけることが可能です。法的措置に出ることを恐れ、支払いへ素直に応じてくれるかもしれません。
また、遺留分侵害額を正確に割り出すのは、馴染みのない一般人には非常に難しいでしょう。債務や生前贈与、財産の価値を割り出すだけでかなりの労力を要します。しかし、弁護士がいれば、遺留分侵害額の計算に必要な財産調査まで全て任せることが可能です。
相手がどうしても支払いに応じず、訴訟や調停に発展した際の手続きも、全て弁護士が行ってくれます。弁護士を代理人として裁判へ出頭させることもできるので、時間的にも精神的にも余裕が生まれるでしょう。
そのため、確実に遺留分を取り戻したい方は、弁護士へ相談するのがおすすめです。
まとめ
生前贈与は「遺留分の基礎となる財産」に含まれます。ただし、死亡1年以内に行われた贈与、死亡10年前に行われた特別受益にあたる贈与、遺留分の侵害にあたると知りながらの贈与にのみ限られると覚えておきましょう。
なお、遺留分の計算には、個別の遺留分割合や、遺留分の基礎となる財産の計算が必要になります。他にも、請求した際に相手が返還に応じないケースなど、トラブルが発生する可能性もあるでしょう。遺留分侵害額請求は一般人には判断が難しい場面が多くあるので、なるべく弁護士に依頼するのがおすすめです。