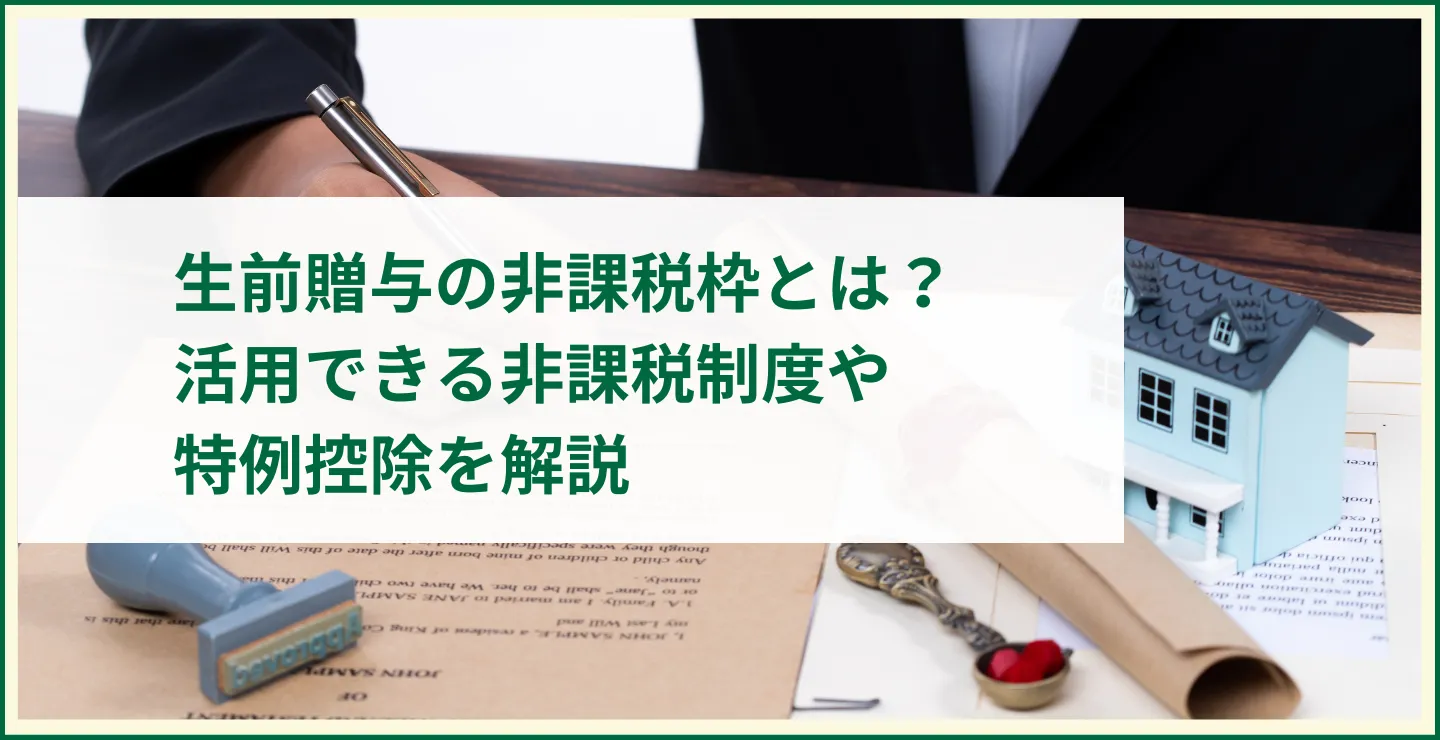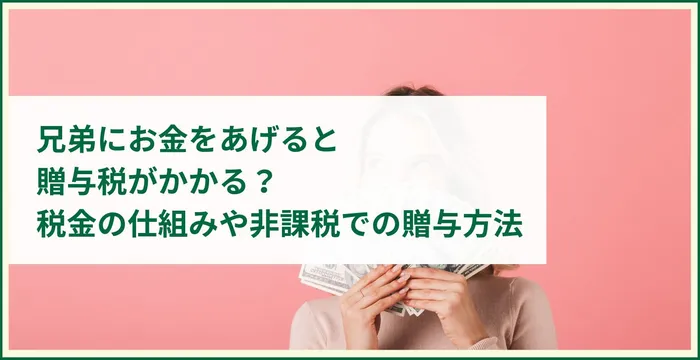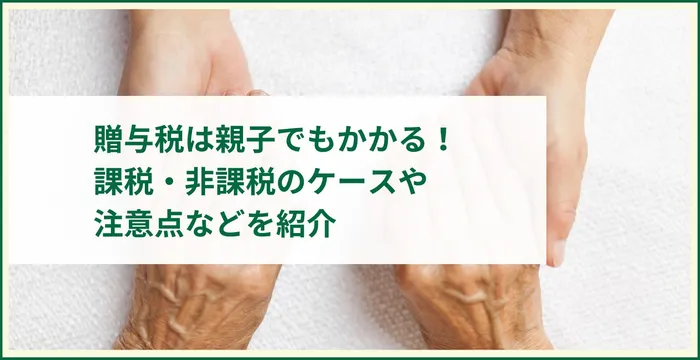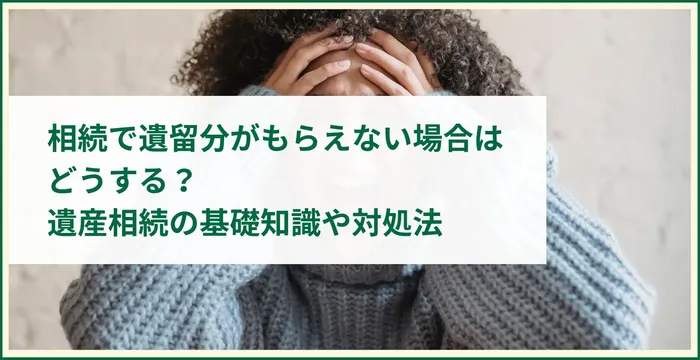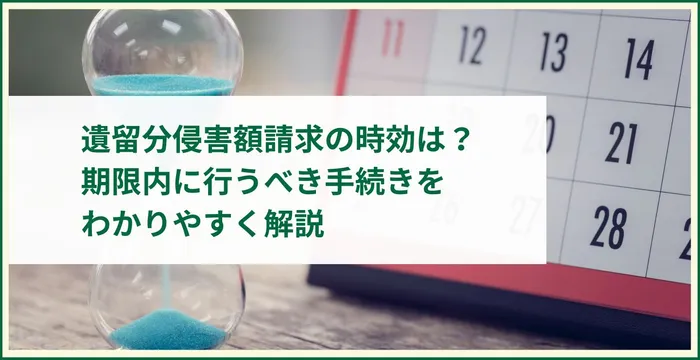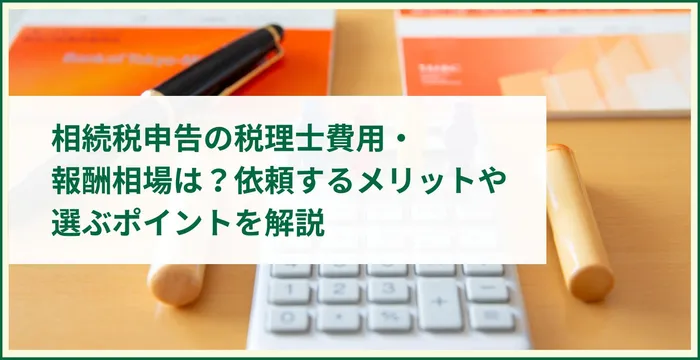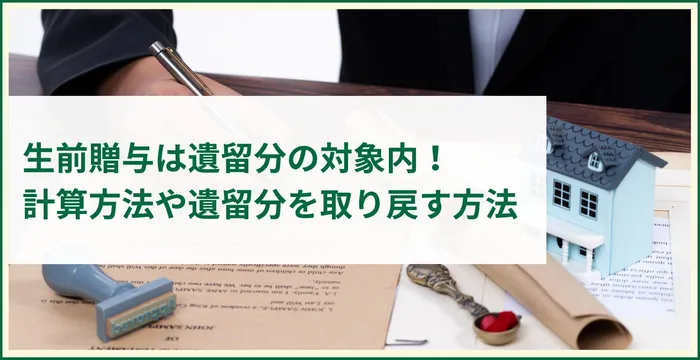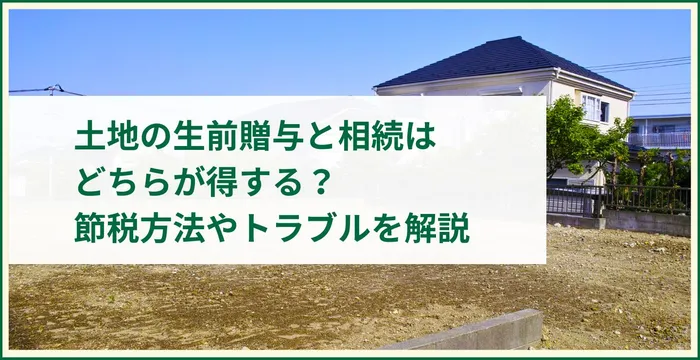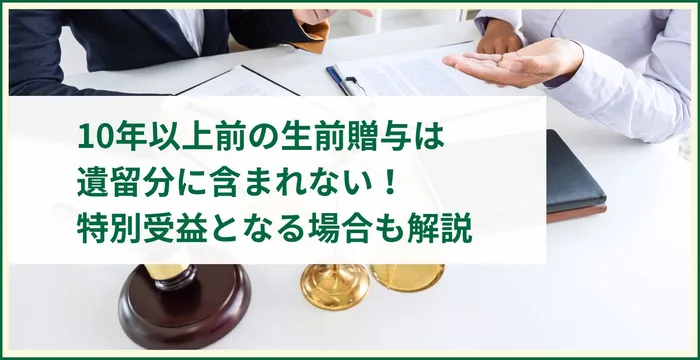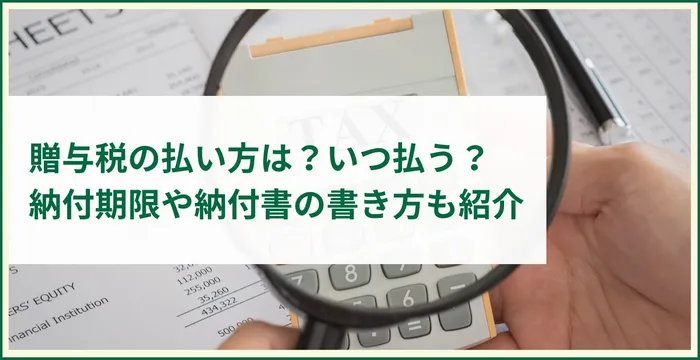生前贈与に活用できる非課税制度
生前贈与における贈与税の課税制度として「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。ここでは、それぞれの制度について、贈与税が非課税になる場合や贈与税がかかる場合の税率などについて解説します。
- 「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」のどちらを選ぶべき?
- 年間の受取額が110万円以下で非課税になる「暦年課税制度」
- 2500万円まで贈与税が非課税になる「相続時精算課税制度」
「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」のどちらを選ぶべき?
暦年課税と相続時精算課税制度それぞれの向いているケースについてまとめると次のようになります。
| 課税制度 |
選ぶべきケース |
| 暦年課税 |
長期間かけてコツコツと財産を移転させたい |
| 相続時精算課税制度 |
・短期間で子や孫に資金を移転させたい
・将来値上がりする財産(不動産)を贈与したい
・今、値下がりしている財産を贈与したい
・収益不動産を贈与したい
|
暦年課税は、長期間かけて財産を移転させたい人に向いています。
また、相続時精算課税制度には、贈与者(60歳以上の父母もしくは祖父母)や受贈者(18歳以上の子や孫)に要件があるため、配偶者に贈与する場合などは使えません。
一方、相続時精算課税制度が向いているのは次のようなケースです。
- 短期間で子や孫に資金を移動させたい
- 将来値上がりする財産(不動産など)がある
- 値下がりしている財産がある人
- 収益不動産
1度に大きな資金を移動させたい場合は、相続時精算課税制度の特別控除額(2,500万円)、適用税率(20%)を活用することで、税負担を抑えやすくなります。
また、贈与財産が将来値上がりが見込まれる不動産などの場合、あるいは保有する株価が値下がりしているときも相続時精算課税制度が活用しやすいでしょう。
なぜなら、相続時に相続財産に加算される贈与財産は、贈与時点の価格で評価されるため、相続時点より贈与時点の評価が低くなれば、支払う相続税額が少なく済むためです。
さらに、贈与する財産が収益不動産の場合、そこから発生する家賃収入は、受贈者(子や孫など)の収入になります。
収益不動産を生前贈与せず相続した場合、不動産だけでなく毎月の収入が相続財産の対象となるため、相続税の負担が大きくなります。
年間の受取額が110万円以下で非課税になる「暦年課税制度」
暦年課税制度は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産に対して贈与税が課される制度です。
暦年課税制度には110万円の基礎控除額があるため、1年間の贈与額が110万円を超えなければ贈与税はかかりません。
ただし、注意したいのは、110万円の基礎控除額は贈与を受けた人(受贈者)ごとに認められる控除額です。
そのため、1人からは110万円に満たなくても、複数人から受けた贈与額の合計が110万円を超えると贈与税がかかります。
また、暦年課税において、基礎控除額の適用回数に制限はありません。そのため、毎年110万円を超えない範囲で複数回の贈与をすることで、贈与税の負担なく多額の贈与をすることも可能です。
例えば、毎年100万円を10年間贈与すると、1,000万円を贈与することができます。非課税枠の範囲内であるため贈与税はかかりません。一括で1,000万円の贈与を受けると発生する贈与税の負担がなくなります。
ただし、このとき定期贈与をみなされないように注意することが必要です。定期贈与とは、毎年一定の金額を贈与することが決まっている贈与です。
例えば、100万円を10年に分けて100万円ずつ贈与する約束のもとに行った場合、定期贈与とみなされ1,000万円に対して贈与税が課税されます。
定期贈与とみなされないためには、贈与のたびに贈与契約書を作成することです。また、毎年同じ金額や時期ではなく、異なる金額や時期に贈与する形にするのがよいでしょう。
また、暦年課税には、「特例贈与」と「一般贈与」があります。
・特例贈与:親や祖父母などの直系尊属から18歳以上の子や孫に対してされた贈与
・一般贈与:特例贈与以外の贈与
特例贈与は、一般贈与と比べ税率が低いため、贈与税の負担が軽くなります。
暦年課税の税率
暦年課税制度では、年間110万円を超える贈与額には贈与税がかかります。その際に適用される税率や控除額は、特例贈与と一般贈与で異なり、それぞれ次のとおりです。
●特例贈与の場合
| 基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
- |
| 400万円以下 |
15% |
10万円 |
| 600万円以下 |
20% |
30万円 |
| 1,000万円以下 |
30% |
90万円 |
| 1,500万円以下 |
40% |
190万円 |
| 3,000万円以下 |
45% |
265万円 |
| 4,500万円以下 |
50% |
415万円 |
| 4,500万円超え |
55% |
640万円 |
●一般贈与の場合
| 基礎控除後の課税価格 |
税率 |
控除額 |
| 200万円以下 |
10% |
- |
| 300万円以下 |
15% |
10万円 |
| 400万円以下 |
20% |
25万円 |
| 600万円以下 |
30% |
65万円 |
| 1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
| 1,500万円以下 |
45% |
175万円 |
| 3,000万円以下 |
50% |
250万円 |
| 3,000万円超え |
55% |
400万円 |
出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
暦年課税の計算方法
暦年課税における贈与税の計算方法は次のとおりです。
贈与税額=(贈与を受けた財産の合計額-基礎控除額(110万円))×税率-控除額
実際に贈与を受けた金額から基礎控除額を差し引いたものが、贈与税の課税対象(課税価格)となります。課税価格に税率を乗じたものから控除額を差し引いて、贈与税を計算します。
例えば、親から子どもへ800万円の贈与がされた場合、課税価格は690万円(800万円-110万円)となります。この場合の贈与税額は、特定贈与財産にあたるため、税率30%、控除額90万円となり次のとおりです。
・贈与税額=690万円×30%(税率)-90万円(控除額)=117万円
2500万円まで贈与税が非課税になる「相続時精算課税制度」
贈与税を非課税とするもう1つの方法は、「相続時精算課税制度」です。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母もしくは祖父母から18歳以上の子、孫に生前贈与するときに活用できる制度です。
同一の父母または祖父母からの贈与について、累計額が2,500万円の特別控除枠を超えるまで贈与税がかかりません。
さらに、2024年1月以降の贈与については、相続時精算課税制度の特別控除額以外に年110万円の基礎控除が適用できることになりました。
累計2,500万円を超える贈与には贈与税がかかりますが、相続時に贈与額(基礎控除を除く)を相続財産に加えて相続税を計算し、支払った贈与税がある場合は精算します。
相続時精算課税制度の税率
相続時精算課税制度では、特別控除額2,500万円を超える贈与に対して20%の税率で贈与税が課されます。
なお、相続時精算課税制度を利用するためには、最初に贈与を受けた年の翌年3月15日までに相続時精算課税選択届出書と必要書類を贈与税の申告書に添付して税務署に提出することが必要です。
相続時精算課税制度の計算方法
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税は次のように計算します。
(「1年間の贈与額-110万円(年間ごとの基礎控除額)」-2,500万円)×20%
贈与税の計算方法を事例で紹介します。
例えば、相続時精算課税制度のもと親から子へ次の贈与したとします。
・1回目:1,500万円
・2回目:1,500万円
1回目の1,500万円の贈与については、特別控除額(2,500万円)の範囲内のため贈与税はかかりません。
相続時精算課税制度においても基礎控除額(110万円)を適用できるため、1回目の贈与額は、1,500万円-110(基礎控除額)=1,390万円となります。
そのため、2回目以降の贈与で特別控除額として適用できる額は、2,500万円-1,390万円=1,110万円となります。
2回目の1,500万円の贈与についても、基礎控除額(110万円)が使えるため、贈与額は1,390万円です。
2回目の贈与額(1,390万円)が相続時精算課税制度の残りの控除枠(1,110万円)を超えるため、超えた分については贈与税がかかります。
この場合の贈与税額は、(1,390万円-1,110万円)×20%(税率)=56万円となります。
生前贈与で非課税として活用できる特例控除
ここでは生前贈与に活用できる控除制度について解説します。
- 結婚・子育て資金としての贈与(1,000万円)
- 教育資金としての贈与税(1,500万円)
- 住宅取得の資金としての贈与 (500〜1,000万円)
- 婚姻期間20年以上の夫婦間の住宅贈与(2,000万円)
- 特定障害者等に対する贈与(3,000万~6,000万円)
結婚・子育て資金としての贈与(1,000万円)
父母や祖父母から子や孫(18歳以上50歳未満)に、結婚・子育て資金を贈与した場合に適用できる非課税制度です。
贈与を受けた者が50歳に達するまでに結婚もしくは子育て資金として支払ったものは、1,000万円まで贈与税がかかりません。
結婚資金の活用用途としては、挙式費用や衣装代など婚礼費用、子育て資金については、不妊治療や分べん費用、子の医療費、保育料などです。
2023年税制改正で、2025年3月末まで適用期限が延長されています。
教育資金としての贈与税(1,500万円)
父母や祖父母から教育資金の贈与を受けた場合に適用できる非課税制度です。
原則、贈与を受けた子や孫が30歳に達するまでに教育資金として支払った金額について、1,500万円を限度として贈与税がかかりません。
資金の用途としては、入学金や授業料、入園料、保育料、学用品の購入費用などです。2023年の税制改正により、2026年3月末まで適用期限が延長されています。
住宅取得の資金としての贈与 (500〜1000万円)
親や祖父母から住宅取得のための資金の贈与を受けた場合に活用できる非課税制度です。
非課税となる額は、取得する住宅の省エネ性能によって異なり、一定の省エネ基準を満たす省エネ住宅は1,000万円、それ以外の住宅は500万円となっています。
●省エネ住宅の基準
- 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級4以上である
- 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物である
- 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上である
受贈者は、贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上で、合計所得金額が2,000万円以下(新築住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)であることが必要です。
婚姻期間20年以上の夫婦間の住宅贈与(2,000万円)
婚姻期間が20年以上の夫婦について、配偶者に対して「居住用の不動産」または「居住用不動産の購入資金」を贈与した場合に、2,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。内縁関係は対象となりません。
おしどり贈与とも言われる制度ですが、配偶者が亡くなった場合にも、相続財産に贈与額を加算する必要はありません。
ただし、対象は「居住用財産」であり、収益不動産や別荘、セカンドハウスを贈与する場合は対象となりません。
特定障害者等に対する贈与(3,000万~6,000万円)
特定障害者の方の生活費などに充てるために、信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときに活用できる制度が、「特定障害者に対する贈与税の非課税」です。
信託契約とは、財産を持つ人が所有する財産の管理や処分、運用を信頼できる相手に託し、相手が目的に従って管理、運用を行う契約。信託した財産から収益を得る権利を信託受益権といいます
信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の方については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の方については3,000万円まで贈与税がかかりません。
特定障害者とは次の方をいいます。
・特別障害者
・特別障害者以外の障害者のうち精神に障害がある方
生前贈与をする際に注意すべきこと
相続税対策として行われる生前贈与ですが注意すべき点もあります。
- 名義預金は意味がない
- 毎年の贈与の度に贈与契約書を作成する
- 現金の手渡しは避ける
- 遺留分に注意する
- 老後資金を十分に確保しておく
- 亡くなる直前の贈与は相続税の対象になる
- 相続時精算課税から暦年課税に切り替えられない
名義預金は意味がない
生前贈与として認められるためには、贈与の証拠を残しておくことが必要です。現金を手渡ししても証拠が残らないため、銀行口座を利用するようにしましょう。
このとき注意しなければならないのが「名義預金」です。
名義預金とは、預金口座の名義人と実際に口座を運用・管理している人が異なり、名義人として名前を借りただけの預金をいいます。
例えば、親が子の口座に贈与したお金を振り込んでも、その口座の管理を親が行っており、子が自由に活用できなければ「名義預金」とみなされます。名義預金とみなされると、生前贈与とは認められないため、相続財産として相続税が課される可能性があります。
名義預金とみなされないためには、口座の通帳や印鑑の管理を贈与された人が自ら行うことが必要です。
なお、贈与は、贈与する側とされる側の合意に基づいて成立します。子どものために、こっそりとお金を貯めていたという場合、生前贈与と認められません。
毎年の贈与の度に贈与契約書を作成する
生前贈与の証拠を残すために、贈与のたびに贈与契約書を作成するようにしましょう。
また、毎年贈与する場合は、定期贈与とみなされないように贈与契約書を作成することが必要になります。
定期贈与とは、毎年一定の決まった金額を贈与することをいい、国税庁のホームページでは以下のように記載されています。
毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受けることが、贈与者との間で契約(約束)されている場合には、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかります。
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
つまり、定期贈与とみなされると、最初から1,000万円の贈与が約束されていたとして、贈与税が課税されます。
贈与契約書に決まった書式等はありませんが、記載しておいたほうがよい事項は以下のとおりです。
- 贈与者と受贈者の住所・氏名
- 贈与年月日(契約締結日・贈与履行日)
- 贈与財産に関する情報/li>
- 贈与の条件
- 贈与の方法
- 贈与者・受贈者の押印
贈与される人が未成年者の場合、親権者の署名・押印が必要です。手書きでもパソコンでも大丈夫ですが、2通作成し双方が保管しておくようにしましょう。
なお、現金や株式の場合不要ですが、不動産を贈与する場合の契約書には200円の収入印紙が必要です。
現金の手渡しは避ける
生前贈与の方法として、現金による手渡し自体は法的に問題はありません。
ただし、銀行口座の入出金履歴など明確な証拠がなければ、贈与の事実を証明できず生前贈与として認められない可能性があります。
生前贈与する際に、現金での手渡しは避けるべきでしょう。
遺留分に注意する
生前贈与するにあたり、相続人が有する遺留分に注意する必要があります。
遺留分とは、法律上、法定相続人に最低限認められた相続分です(民法第1042条)。
遺留分を請求する権利があるのは、次の相続人です。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子(子がすでに亡くなっている場合は、孫)
- 被相続人の父母
また、遺留分を計算する際に対象となる生前贈与は次の3つです。
- 相続開始前1年以内に行われた相続人以外への生前贈与
- 相続開始前10年以内に行われた相続人への特別受益にあたる生前贈与
- 遺留分を侵害していると知りながら行われた生前贈与
生前贈与する財産が多額である場合に法定相続人の遺留分を侵害すると、遺留分侵害請求権の対象となる可能性があるため注意が必要です。
老後資金を十分に確保しておく
相続税対策を優先し生前贈与し過ぎると、自らの生活費など必要資金が不足する可能性もあります。
老後に必要な資金をしっかりと確認しながら行うことが大切です。
亡くなる直前の贈与は相続税の対象になる
亡くなる直前の「駆け込み贈与」による相続税逃れを防ぐため、亡くなる直前の一定期間内に贈与された財産は、相続財産に加算して相続税を計算します。
これば、基礎控除額(110万円)の範囲内の贈与であっても加算の対象となります。
亡くなる何年前までの贈与が加算対象となるかは、被相続人が亡くなった日によって変わります(下図参照)。
| 相続開始日 |
加算対象期間 |
| ~令和8年12月31日 |
相続開始前3年以内 |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 |
令和6年1月1日から死亡の日まで |
| 令和13年1月1日~ |
相続開始前7年以内 |
出典:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
相続時精算課税から暦年課税に切り替えられない
贈与税は、暦年課税と相続時精算課税制度の2つの方法があり、生前贈与を受けた受贈者が選択することができます。何もしなければ、暦年課税制度に基づき申告・納付することになります。
一方、相続時精算課税制度を選択した場合、同じ贈与者について暦年課税に戻ることはできません。
相続時精算課税制度は、贈与を受けた財産を相続財産に加算して精算する制度であり、特別控除の限度額内であれば贈与税の負担はありませんが、以後暦年課税にできない点には注意しましょう。
まとめ
贈与税の課税方法については、暦年課税制度と相続時精算課税制度どちらかを選択することができます。
暦年課税制度は、一定の時間をかけてコツコツを資産を移転していく場合に活用しやすい制度です。
一方、まとまった額の財産を移転したい、収益不動産を贈与したい場合など、相続時精算課税制度を活用したほうがよい場合があります。
どちらを選択すべきかは、贈与にかけられる期間や贈与額、贈与する財産によって変わるため、税理士に相談したほうがよいでしょう。
また、暦年課税の基礎控除額や相続時精算課税制度の特別控除額以外にも、贈与税を非課税とできる制度があります。
- 結婚・子育て資金の贈与税の非課税制度
- 教育資金の贈与税の非課税制度
- 住宅取得等資金の贈与税の非課税制度
- 婚姻期間20年以上の夫婦間の住宅贈与
- 特定障害者に対する贈与
これらの制度を状況に応じてしっかり活用することが大切です。
また、生前贈与するとしても注意しなければ、生前贈与と認められない、あるいは老後資金が少なくなったり、法定相続人の遺留分を侵害する可能性もあります。
こういった点も含めて相続に強い税理士に相談することがおすすめします。