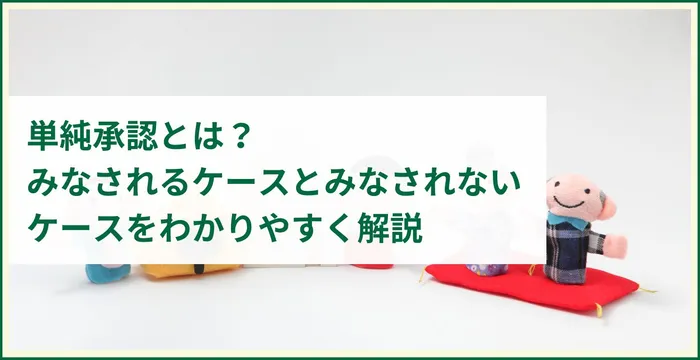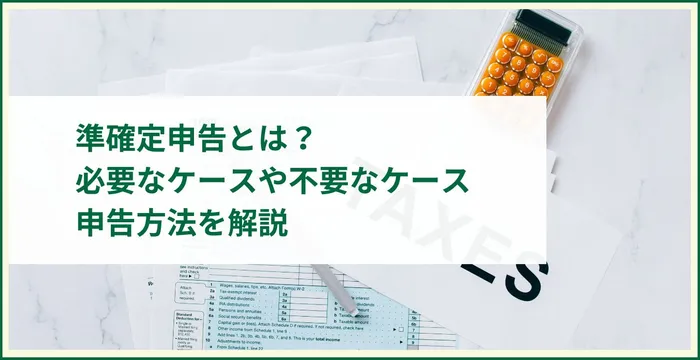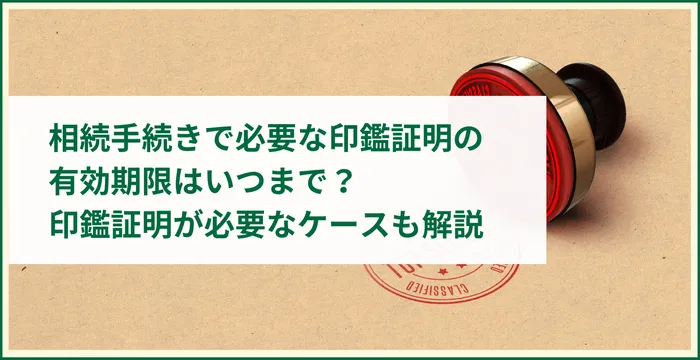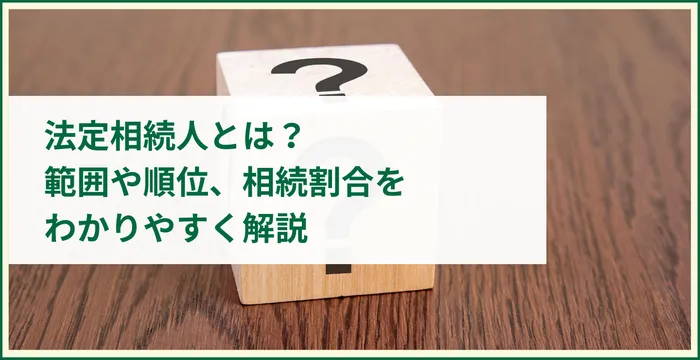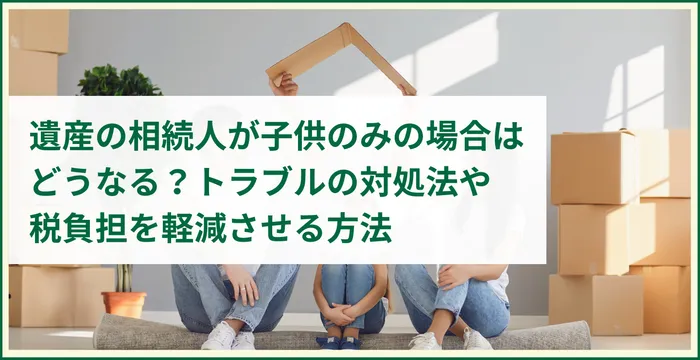遺贈とは遺言によって相手に財産を譲ること
遺贈とは、遺言によって特定の相手に財産の一部、または全部を譲ることです(民法964条)
遺言書によって財産を分与する人を「遺贈者」といい、遺言により財産を受け取る人を「受遺者」とよびます。
受遺者は法定相続人だけではなく、それ以外の個人や団体、法人も指定可能です。
また、遺贈にともなう手続きを行う人を「遺贈義務者」といいます。
遺贈義務者になる人は、以下のとおりです。
遺言執行者が定められている場合、遺言執行者が遺贈義務者の代理人となるため、相続人が遺贈の手続きをする必要はありません。
遺贈は「包括遺贈」「特定遺贈」に分けられる
遺贈は「包括遺贈」と「特定遺贈」に分けられます。
包括遺贈と特定遺贈は故人の財産の中に負債があった場合、取り扱いが異なります。
それぞれの遺贈を表にまとめたため、それぞれ確認しておきましょう。
|
包括遺贈 |
特定遺贈 |
| 遺贈財産 |
譲る財産は決めず割合のみを指定 |
譲る財産と割合を具体的に指定 |
| 遺産分割協議の参加 |
必要 |
不要 |
| 相続債務 |
プラスの財産以外のマイナスの財産についても割合分は負担が必要 |
遺言書で指定されない限り、債務の負担はなし |
| 放棄 |
相続開始があったと知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に放棄の申し立てが必要 |
ほかの相続人・遺言執行者に放棄の意思を示す(期限なし) |
| 不動産取得税 |
非課税 |
相続人は非課税、相続人以外は課税 |
順に解説します。
具体的に指定しない包括遺贈
包括遺贈とは、譲る財産を決めず割合だけ指定する方法です(民法964条)
遺産全体の割合を指定する方法のため、預貯金や不動産などのプラスの財産以外にも借金や保証債務などマイナスの財産も遺贈されます。
したがって、負債がある場合は、指定した割合の分だけ引き継がなければなりません。
たとえば遺言者が第三者の借金の連帯保証人になっており、遺言執行者がそのことを把握していない場合、相続人や受遺者が負債を抱えるリスクがあります。
また包括遺贈の場合、具体的な遺産総額が不明なため、相続人と受遺者で遺産分割協議が必要です。
なお受遺者は、負債を相続したり売却するのが難しい土地を遺贈されたりした場合などは、遺贈の放棄が可能です。
包括遺贈を放棄する際は、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に遺贈放棄の申述書を提出する必要があります(民法915条、938条)
具体的に指定する特定遺贈
特定遺贈とは、譲る財産と割合を具体的に指定する方法です(民法964条)
具体的に財産を指定するため、受遺者はマイナスの財産を引き継ぐリスクがありません。
遺言書に書かれた財産を引き継ぐため、遺産分割協議への参加も不要です。
受遺者が財産を受け取る意思がないときは、放棄できます。
なお、特定遺贈は、遺言者の死後いつでも死亡時までさかのぼって放棄が可能です(民法986条)
ほかの相続人や遺言執行者に意思表示をすれば放棄できるため、受遺者に負担がかかりにくい方法といえるでしょう。
ただし受遺者が遺贈を承認するか放棄するかの意思を示さない場合、遺贈義務者や利害関係者は、期間を定めて遺贈をどうするか決めるよう催告できます(民法987条)
決められた期間内に回答しなかった場合は、遺贈を承認したとみなされます(民法987条)
遺贈に対して承認するか放棄するか意思を示したあとは、撤回できないため注意が必要です(民法989条)
相続は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」に分けられる
相続は次の3種類に分けられます。
それぞれの違いは、以下の表のとおりです。
|
単純承認 |
限定承認 |
相続放棄 |
| 内容 |
相続財産を全部承継する |
プラス財産の範囲内でマイナス財産を弁済する |
相続財産をすべて承継しない |
| 相続手続き |
不要 |
相続人全員での手続きが必要 |
相続人単独で可能 |
| 申し出期間 |
相続人であると知ったときから3ヵ月以内に、限定承認も相続放棄もしなければ単純承認とみなされる |
相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し出が必要 |
相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申し出が必要 |
それぞれについて、解説します。
相続財産を全部承継する単純承認
単純承認とは、故人の相続財産すべてを承継することです(民法920条)
被相続人のすべての権利義務について承継するため、プラスの財産のみでなく、マイナスの財産も承継します。
そのため、被相続人が連帯保証人になっていたり借金があったりした場合は、注意が必要です。
なお、次の場合は単純承認したものとみなされます。
- 相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき(民法921条)
- 相続人が熟慮期間(被相続人の死亡または自分が相続人であると知ったときから3ヵ月以内)に限定承認も相続放棄もしなかったとき(民法921条2項)
- 限定承認や相続放棄をした後に、相続財産の全部または一部を隠匿したり消費したり、わざと財産目録に記載しなかったとき(民法921条3項)
単純承認したとみなされると、それ以降は限定承認や相続放棄はできません。
また、債務割合は相続人のあいだで自由に決められますが、第三者である債権者にその割合を主張できないため注意が必要です。
相続財産を限定して承継する限定承認
限定承認とは、相続で得たプラスの財産を限度として、マイナスの財産も引き継ぐことです(民法922条)
被相続人のプラス財産の範囲内でマイナス財産を承継するため、債務があっても相続人が自分の財産から返済する必要がありません。
一方、マイナスの財産よりプラスの財産が多かった場合は、相続人が承継できます。
そのため、相続財産にプラスの財産とマイナスの財産があり、どちらが多いか不明な場合に有効です。
ただし、限定承認は、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります(民法924条)
また複数の相続人がいる場合、全員で手続きを行う必要があり、1人だけが限定承認を選ぶことはできません(民法923条)
限定承認の手続き前に相続放棄をした人がいたときは、残った相続人の合意があれば限定承認は可能です。
なお、受け継いだプラスの財産は、被相続人からの譲渡とみなされ課税対象となるため注意が必要です。
相続財産をすべて承継しない相続放棄
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべて受け継がないことです(民法939条)
プラスの財産とマイナスの財産を比較したとき、マイナスの財産がプラスの財産を大幅に上回っている場合に有効です。
相続放棄した場合、その人は初めから相続人でなかったことになり、代襲相続も認められません(民法887条2項)
また、相続放棄したい場合は、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所に申し出る必要があります(民法915条)
なお、相続放棄は相続人1人でも行えます。
遺贈と相続の具体的な違い
故人の財産を承継する面では遺贈も相続も同じといえます。
しかし、遺贈と相続では財産を受け継ぐ人や登録手続きなどに違いが生じます。
遺贈と相続の違いを表にまとめました。
|
遺贈 |
相続 |
| 内容 |
遺言によって特定の相手に財産の一部、または全部を譲ること |
財産を相続人に引き継ぐこと |
| 財産を受け継ぐ人 |
第三者や団体、法人など誰でも可能 |
法定相続人 |
| 登記手続き |
相続人全員と受遺者で登記手続きが必要
※相続人に対する遺贈は、受遺者が単独で申請可能 |
相続人が単独で相続登記できる |
| 登録免許税 |
固定資産税評価額×2% |
固定資産税評価額×0.4% |
| 不動産取得税 |
固定資産税評価額×3%
※非住宅の場合は4% |
不要 |
| 相続税 |
配偶者及び一等親以外は2割加算
※法人の場合は、相続税はかからない |
どの法定相続人も加算なし |
それぞれについて、詳しく解説します。
財産を受け継ぐ立場が異なる
1つ目の違いは、財産を受け継ぐ立場が異なる点です。
遺贈は、相続人ではない第三者や団体、法人でも受遺者に選任できます。
一方、相続は受け継ぐ人が法定相続人に限られており、配偶者や子どもなど一定範囲の血族だけが財産を承継できます。
法定相続人とは、民法によって被相続人の財産を受け継ぐ権利がある人のことです。
なお、法定相続人になる人は以下のとおりです。
法定相続人に対しては「遺贈する」「相続させる」のどちらも使用可能ですが、第三者には「遺贈する」しか使えません。
一般的には遺贈よりも相続のほうがメリットがあるため、法定相続人に引き継ぎたい場合は相続、第三者や団体などに譲りたい場合は遺贈を選択するとよいでしょう。
登記手続きが異なる
2つ目の違いは、登記手続きが異なる点です。
不動産の相続では、受け継いだ相続人が単独で不動産の名義変更(相続登記)ができます。
しかし遺贈の場合は、相続人全員と受遺者が共同で登記手続きをしなければなりません。
相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明なども必要となるため、多くの時間や手間がかかります。
ただし、遺言で遺言執行者を指名している場合、受遺者との共同申請により所有権移転登記が可能です(民法1012条2項)
なお、不動産の所有者が変わった場合は登録免許税が発生しますが、相続よりも遺贈のほうが高くなります。
登録免許税の計算方法は次のとおりです。
・相続する場合:固定資産税評価額×0.4%
・遺贈する場合:固定資産税評価額×2%
※参照URL:登録免許税の税額表|国税局
さらに、特定遺贈された不動産には、不動産取得税がかかります。
不動産取得税の計算方法は、次のとおりです。
固定資産税評価額×3%(非住宅の場合は4%)
※参照URL:不動産取得税|東京都主税局
包括遺贈の場合は相続人と受遺者が同じ立場のため、不動産取得税の課税についても相続と同じく非課税です。
相続税が異なる
3つ目は、相続税が異なる点です。
遺贈と相続は、双方とも相続税の課税対象です。
ただし、遺贈された人が配偶者や子どもなどの一等親以外の人だった場合、相続税が2割増しで加算されます(相続税法18条)
第三者や法人、団体以外でも、次の人は相続税が2割加算されるため注意が必要です。
- 兄弟姉妹
- 甥・姪・いとこなどの親族
- 孫(代襲相続人でない場合)
- 祖父母
- 結婚したことにより出来た親戚
- 内縁の妻や夫(血族関係以外)
なお、相続税の2割加算の計算方法は、次のとおりです。
加算される金額=各相続人などの相続税額×20%
また、相続税が課税されるのは、基礎控除を超える場合です。
遺産総額が基礎控除額より少なければ、相続税は課税されません。
基礎控除額は以下の式で計算されます。
3,000万円+600万円×法定相続人の数(相続税法15条)
しかし、遺贈により財産を承継する場合、受遺者は法定相続人の数に含められないため注意しましょう。
遺贈と贈与の違いは「合意の有無」「税金」「放棄」
遺贈と贈与の違いは以下の表のとおりです。
|
遺贈 |
贈与 |
| 内容 |
遺言によって特定の相手に財産の一部、または全部を譲ること |
・生前贈与:生前に財産を無償で譲ること
・死因贈与:贈与者が亡くなると効力が発生する贈与 |
| 財産を受け取る人 |
人物・団体・法人など誰でも可能 |
人物・団体・法人など誰でも可能 |
| 贈与の相手の合意 |
合意は不要 |
合意が必要 |
| 課税対象の税金 |
相続税
※法人は相続税がかからない |
・死因贈与:相続税
・生前贈与:贈与税
※法人は法人税 |
| 放棄 |
放棄可能 |
死因贈与は贈与者の死後は放棄できない |
それぞれについて解説します。
遺贈は合意不要だが贈与は必要
1つ目の違いは、お互いの合意があるかないかです。
遺贈は、遺言者の意思で財産を残すもののため、受け取る側の合意は不要です。
そのため、遺贈者(財産をあげる人)が亡くなったときに初めて、受遺者(財産をもらう人)が財産をもらえることを知る場合もあります。
一方、贈与は贈与者(財産をあげる側)と受贈者(財産をもらう側)で契約を締結しなければならず、お互いの合意が必要です(民法549条)
遺贈・死因贈与は相続税、生前贈与は贈与税の課税対象
2つ目は税金の違いです。
遺贈によって財産を譲り受けた場合、受遺者は相続税が課税されます。
法人への遺贈の場合、相続税は課税されません。
しかし、株式会社や有限会社などへの遺贈は、法人税がかかる可能性があります。
一方、生前贈与で譲り受けた場合は贈与税の課税対象です。
ただし、死因贈与で財産を受け取った場合は、贈与税ではなく相続税がかかります。
法人の場合、贈与は法人税の課税対象ですが「政令で定める34事業」(収益事業)に該当しない事業を行っている法人は、法人税も非課税です。
相続税と贈与税は、控除額や計算方法が異なります。
一般的に贈与税の方が相続税よりも税額が高くなる場合が多いため注意しましょう。
遺贈は放棄可能だが死因贈与は放棄できない
3つ目は、放棄の違いです。
遺贈で財産を譲るときは、受遺者は放棄できます(民法986条)
なぜなら、遺贈は遺贈者の単独行為なので、受遺者が財産を譲り受けたくないと思う可能性があるためです。
また、遺贈は遺言書によって意思を示すため、遺言書を別の内容で作成し直したり撤回したりもできます。
一方、死因贈与の場合は生前に契約を締結しているため、贈与者の死後は放棄できません。
なお、贈与者と受贈者の双方が生前に合意できれば撤回が可能です。
ただし負担付き贈与の場合、受遺者がすでに負担の内容の一部、または全部を実施していたときは原則として撤回できません(民法550条)
遺贈に必要な遺言書の種類や書く内容
遺言書には受贈者の情報や遺贈内容などを明確に記載しなければいけません。
ここでは、遺贈に必要な遺言書の種類や書く内容について解説します。
遺言は3種類存在する
遺言には「自筆証書遺言」「構成証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
それぞれに違いがあるため、内容を確認していきましょう。
1. 遺言者本人が作成する自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文を手書きによって作成する遺言書です。
遺言書の本文は、パソコンや代筆では作成できません。
自筆証書遺言を有効にするための要件は、民法968条に定められています。
要件は以下のとおりです。
- 遺言者本人が全文を自書すること
- 遺言者本人が正しい日付を自書すること
- 遺言者本人が氏名を自書すること
- 遺言者本人が自筆証書遺言に押印すること
- 加筆修正等の変更(訂正)をする場合、民法968条3項の定めるルールにしたがっていること
なお、遺産目録は、パソコンを利用したり資料を添付したりする方法で作成可能ですが、すべてのページに署名と押印が必要です。
自筆証書遺言は、簡単かつ無料で作成できますが、不明確な内容の遺言になっていたり、不備で無効になったりするリスクがあります。
ほかにも被相続人の死後、相続人が遺言書の存在を知りながら隠したり、無視したりする危険性もあるでしょう。
さらに、開封の際には家庭裁判所で検認が必要なため、内容がわかるまでに時間がかかります。
ただし、法務局に自筆証書遺言を預けた場合には検認が不要です。
2. 公証人が作成する公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者の代わりに公証人が作成してくれる遺言書です(民法969条)
次に基本情報を整理します。
- 公証人役場:法務省が管轄している機関で、全国に約300ヵ所ある
- 公証人:判事・検事などを長く務めた法律実務の経験豊富な人の中から法務大臣が任命した法律の専門家
公正証書遺言を作る場合、遺言者は公証人に証人2人の前で遺言の内容を伝えます。
公証人は、遺言が判断能力を有する遺言者の本心であることを確認したうえで、遺言書を作成します。
その後、遺言者と証人2人に読み聞かせ、遺言の内容に誤りがないことを確認してもらい、公正証書遺言に署名・押印して完成です。
なお、耳やことばの不自由な人の場合は、通訳を通じて遺言の作成が可能です。
公正証書遺言は、公証人役場で作成するのが一般的ですが、身体が不自由だったり病院に入院したりしている場合は、公証人に出張してもらえます。
また、公正証書遺言の原本は公証人役場に20年間保管されており、オンライン検索もできます。
紛失や改ざんされるリスクも低いため、家庭裁判所での検認も不要です。
ただし、公正証書遺言には、以下のデメリットがあります。
- 証人を2人用意しなければならない
- 公証人や証人に手数料を支払わなければならない
証人になるための資格は不要ですが、次の人は証人になれません。
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者やその配偶者、または受遺者の直系血族
- 公証人の配偶者や四親等内の親族、書記や使用人
もしも証人になってくれる人がいない場合は、公証役場に相談すれば紹介してもらえます。
公正証書遺言作成の手数料は、財産価格に応じて加算されます。
3. 遺言内容を秘密にできる秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言内容を秘密にした状態で公証人役場にて認証してもらえる遺言書です(民法970条)
氏名以外は代筆やパソコンの使用も可能です。
秘密証書遺言は、自分で記入した遺言に封をして公証役場に持参し、公証人と証人2人の前で自分が書いた遺言書だと証明してもらいます。
封がしてあるため、遺言の内容を知られることはありません。
遺言者自身が封をし、公証人が封紙に署名するため、改ざんされるリスクは軽減されます。
手数料は一律11,000円です。
ただし、秘密証書遺言は公証人が内容をチェックしていないため、不備が生じ法的に有効でない遺言になっている可能性があります。
また、開封の際は自筆証書遺言と同じく、家庭裁判所の検認が必要です。
なお、秘密証書遺言は自分で管理しなければならないため、遺言書を紛失してしまったり誰かに隠されたりするリスクもあるでしょう。
遺言書には受贈者の情報や遺贈内容等を明確に記載する
財産を遺贈する場合は、遺言書に以下の内容を必ず記載しましょう。
- 受遺者の氏名、または法人名
- 受遺者の生年月日
- 住民票に登録されている住所
- 遺贈する財産の割合(包括遺贈の場合)
- 遺贈する財産名と、どの財産か特定できる情報(特定遺贈の場合)
遺言書には書いた日付と遺贈者の氏名、捺印も必要です。
印鑑はとくに決まりがないので認印でもよいですが、遺言書の信頼性を上げるため、実印にするとよいでしょう。
遺言書は形式に準じて書かない場合、無効になってしまう可能性があるため注意が必要です。
自筆証書遺言が無効にならないためのポイントは以下のとおりです。
- 遺贈者本人が万年筆やボールペンなどの消せないペンで自書する
- 日付は「〇月吉日」や「〇月末」などではなく、年月日まで記入する
- 署名・捺印する
- あいまいな表現は避ける
なお、遺言書を書く用紙に指定はありませんが、法務局に預ける場合はA4サイズのみとなります。
また、改ざんを防ぐため、遺言書は封筒に入れ糊付けしておきましょう。
印鑑証明書を同封するのも有効です。
自筆証書遺言は無効になるリスクがあるため、無効になりにくい公正証書遺言を選択するとよいでしょう。
遺贈を行う際の注意点
遺贈を行う際の注意点は、以下のとおりです。
- 相続トラブルを回避した遺言を心がける
- 相続人の遺留分に気を付けて遺贈する
- 法定相続人に対する遺言は基本的に「相続させる」
- 農地や借地権・借家権の遺贈には許可や承諾が必要
-
それぞれについて解説します。
相続トラブルを回避した遺言を心がける
1つ目の注意点は、相続トラブルを回避した遺言を心がける点です。
相続人は自分たちが相続するのは当然だと思っている可能性が高いため、遺言書で第三者に遺贈すると知れば納得できない相続人も多いです。
そのような場合は、包括遺贈を検討するのもよいでしょう。
包括遺贈はマイナスの財産も遺贈するリスクがありますが、財産の内容が変わっても割合によって指定するため、相続人も納得のいく分配が実現できます。
また、遺言書を作成するときは、付言事項で遺贈を行う理由をしっかり明記すると、相続人も納得してくれる可能性があります。
付言事項とは、遺言に追加できる記載事項のことです。
法律上の効力はありませんが、お世話になった人への感謝や、家族や自分が大切にしてきたものへの気持ち・願いなどを自由に記載できます。
トラブルになるのを防ぐためにも、財産の分割配分を決定した理由を付言事項に書いておくとよいでしょう。
付言事項に記載する内容は次のとおりです。
- 感謝を伝える言葉
- 財産の分割配分を決定した理由
- 遺留分について
なお、付言事項には、受遺者が先に亡くなった場合の内容も明記しておくとよいでしょう。
相続人の遺留分に気を付けて遺贈する
2つ目の注意点は、相続人の遺留分に気を付けて遺贈する点です。
兄弟姉妹を除く相続人には、遺留分(遺産を最低限相続できる割合)が存在します。
遺留分の割合は以下のとおりです。
・被相続人の配偶者や子どもの場合:法定相続分の1/2
・被相続人の父母の場合:法定相続分の1/3
遺贈によって遺留分が侵害されると、遺留分損害額請求が行われるリスクがあります。
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された法定相続人が侵害した人へ遺留分の取り戻しを請求できる権利です。
たとえば「姪に財産のすべてを遺贈する」という遺言が残されていても、被相続人の子は遺留分侵害額請求権を行えば、最低限の遺留分を取り戻せます。
トラブルを避けるためには、遺留分を侵害しないよう気を付けて遺言書を作成することが大切です。
また、受遺者に生命保険金を受け取らせるのも有効です。
生命保険金は、受取人の固有の財産となるため、遺産分割の対象になりません。
遺留分侵害額請求が行われても生命保険から支払いができるため、トラブルになるリスクを軽減できるでしょう。
法定相続人に対する遺言は基本的に「相続させる」
3つ目の注意点は、法定相続人に対する遺言は基本的に「相続させる」にする点です。
相続人にも「遺贈する」が使えますが、基本的には「相続させる」を使用したほうがよいといえます。
なぜなら「遺贈する」と「相続させる」では効力が異なり、遺贈にすると相続手続きの際に手間がかかるためです。
「相続させる」と記載したほうがよい理由を以下の表にまとめました。
|
相続させる |
遺贈する |
| 不動産の所有者移転登記 |
相続人単独で登記が可能 |
ほかの相続人と共同で登記申請が必要
※遺言執行者が指定されている場合は、受遺者と共同申請で登記可能 |
| 農地を承継する場合の農業委員会や知事の許可 |
不要 |
必要 |
| 借地権や借家権を承継する場合の賃貸人の承諾 |
不要 |
必要 |
| 所有者の主張 |
法定相続分までについては、相続登記していない場合でも対抗できる |
相続登記をしていない場合は対抗できない |
相続人に財産を継承する場合「遺贈する」より「相続させる」のほうがメリットが多いため、遺言書には「相続させる」と記載しましょう。
農地や借地権・借家権の遺贈には許可や承諾が必要
4つ目の注意点は、農地や借地権・借家権の遺贈には許可や承諾が必要な点です。
農地や借地権・借家権についても、相続と遺贈では内容が異なります。
それぞれについて、詳しく解説します。
農地を遺贈する場合
第三者が特定遺贈で農地を取得する場合、農地法3条の許可が必要です(農地法3条)
農地を特定遺贈で遺贈する際は、農業委員会や知事の許可がないと登記できません。
ただし、特定遺贈の受遺者が相続人であれば、農地を譲り受けるのに3条許可は不要です(農地法施行規則15条5号)
特定遺贈で第三者が農地を譲り受ける際、受遺者が農業に従事していない場合は、農業委員会の許可がおりない可能性が高いです。
そのため、相続人以外の人に農地を相続したい場合は、包括遺贈を検討するとよいでしょう。
包括遺贈で農地を取得する場合は、受遺者が相続人以外であっても農地法3条の許可はいりません。
全部包括遺贈であれば、第三者も無条件で農地を譲り受けられます。
また、一部包括遺贈の場合は遺産分割協議により農地を受け継げますが、協議の結果によっては農地を譲り受けられないこともあります。
なお、相続の場合は、農業委員会や知事の許可は不要のため登記も簡単に行えます(農地法3条1項12号)
相続や包括遺贈で農地を譲り受ける場合、許可は不要ですが届け出は必要なため忘れずに行いましょう。(農地法3条の3、3条1項12号)
借地権や借家権を遺贈する場合
借地権や借家権を遺贈する場合は、賃貸人の承諾が必要です。
遺言書を作成する前に賃貸人に承諾してもらい、書面として残しておく必要があります。
遺贈者が他界後、承諾がもらえないと、家庭裁判所に許可の申し立てをする必要があるため注意が必要です(借地借家法19条1項類推適用)
また、遺贈で不動産を譲り受けた場合、賃貸人へ譲渡承諾料を支払わなければならない可能性もあります。
譲渡承諾料の相場は、借地権価格の10%ほどです。
なお、相続の場合は賃貸借契約は相続人に引き継がれるため、賃貸人の承諾は不要です(民法612条)
ただし、名義変更の原因が相続だったとしても、賃貸借契約の当事者が変更することには違いないため、借地権を誰が相続したか連絡しておきましょう。
まとめ
本記事では、遺贈と相続の違いについて解説しました。
遺贈は第三者や団体・法人などにも継承できますが、相続は相続人に限られます。
また、遺贈は遺言書が必要ですが、相続は必須ではありません。
遺贈と相続には、財産を受け継ぐ人や登記手続き、税金などに違いがあります。
第三者に遺贈する際はトラブルに発展しやすいため、付言事項で遺贈を行う理由を明記したり相続人の遺留分に気を付けて遺贈したりするとよいでしょう。
それぞれの違いを理解し、遺贈と相続のどちらを選択するか検討してください。