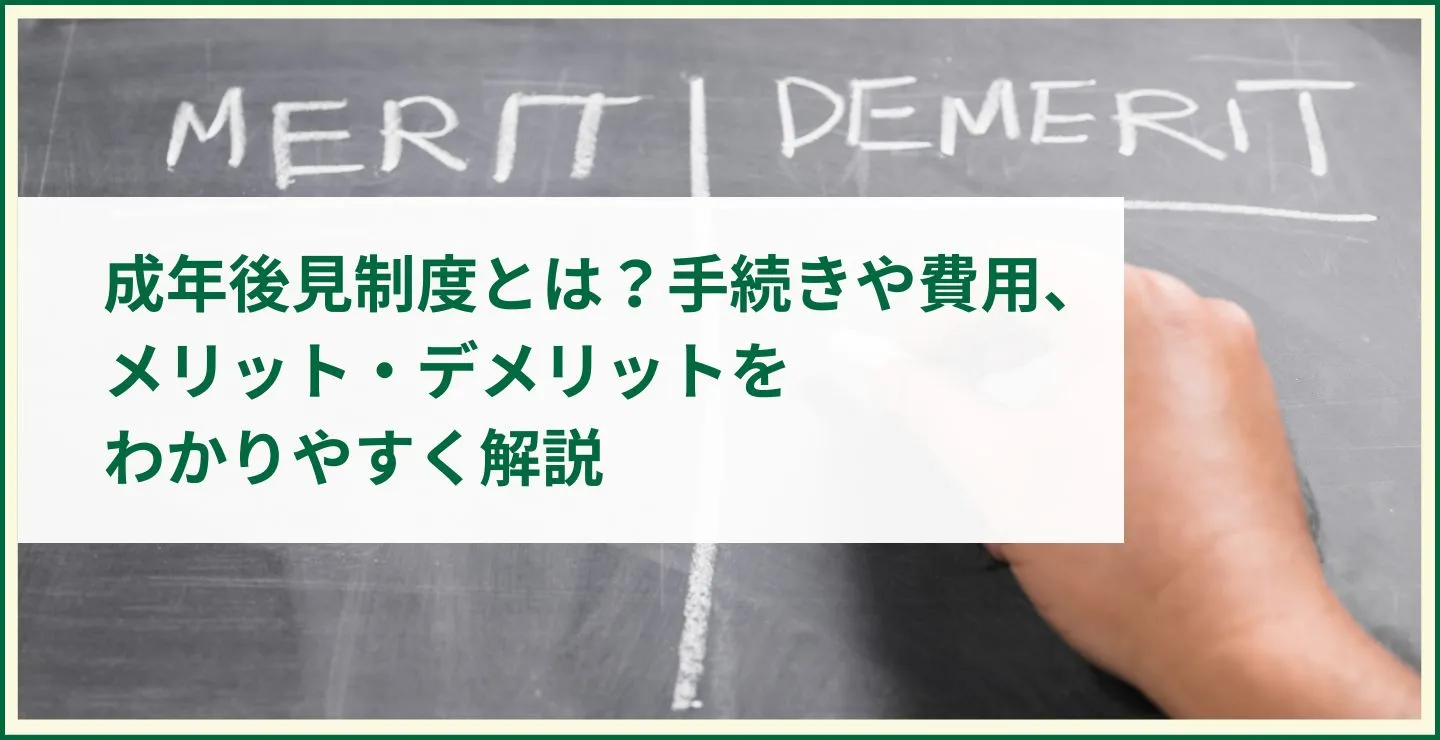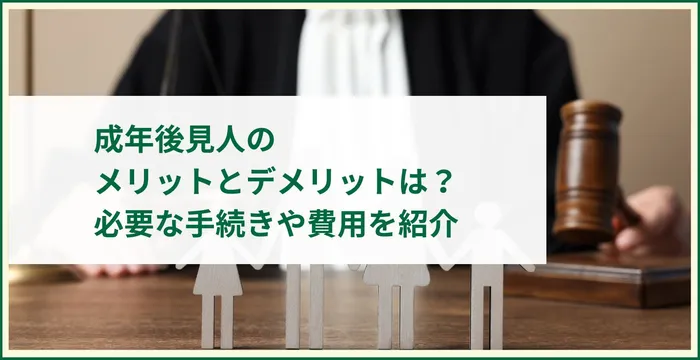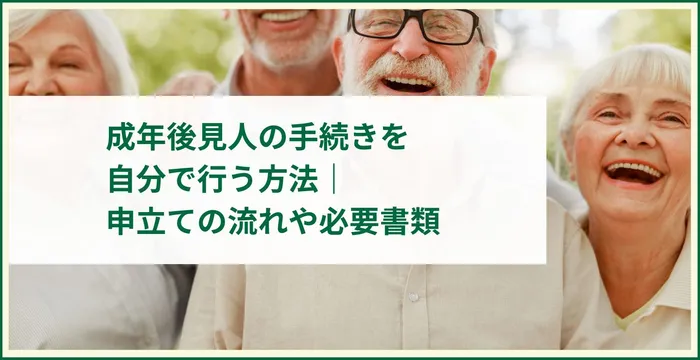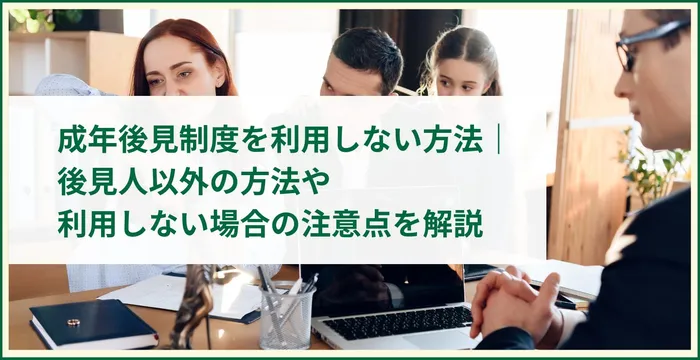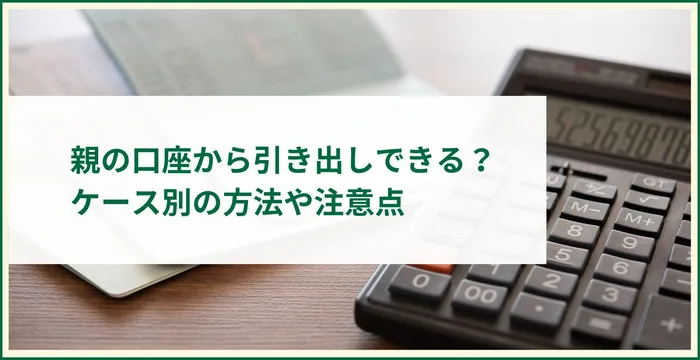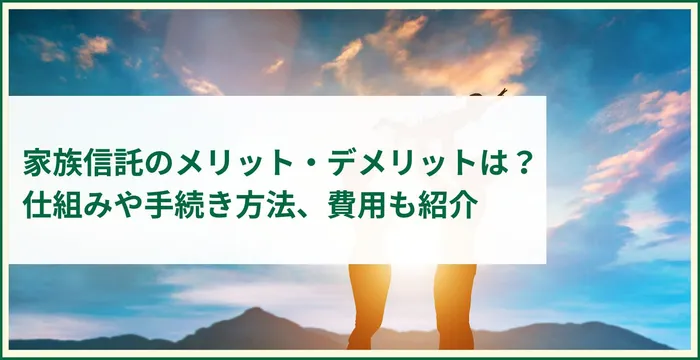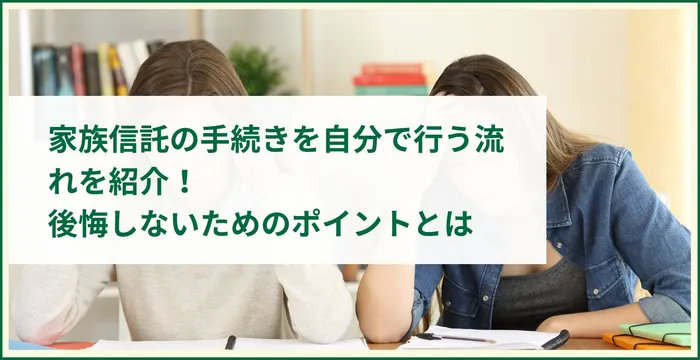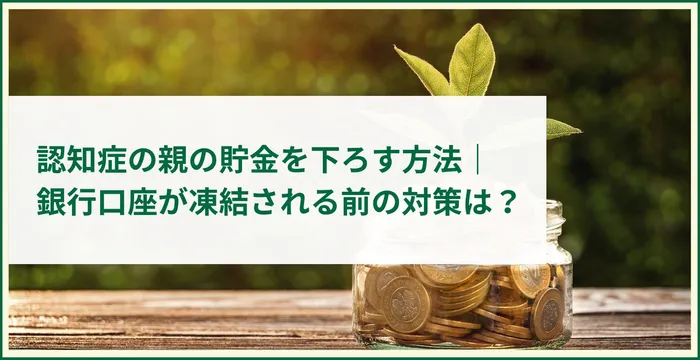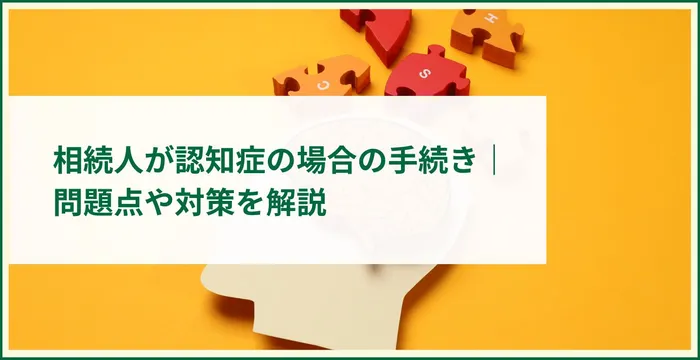成年後見制度とは?わかりやすく解説
成年後見制度とは、認知症などによって判断力の低下した人が、生活上不利益を被らないようにする支援制度のことです。判断能力の低下した本人に代わり「成年後見人」が、財産の管理と契約行為の支援を行います。本章では、成年後見制度が誕生した経緯や背景、制度の目的・現状について解説します。
制度ができた経緯と背景
成年後見制度の根幹には、自己決定の尊重という考え方にあります。成年後見制度は、2000年(平成12年)にスタートしました。成年後見制度は、判断能力の低下している認知症患者や知的障がい者に代わって、財産管理や契約行為を支援する制度です。判断能力が低下した人であっても、特別な扱いをせず、従来の生活を送れるようにというノーマライゼーションの考え方をベースに誕生しました。
【制度の目的】高齢者などの保護
成年後見制度は、判断能力の低下した高齢者や知的障がい者などを、詐欺やトラブルから保護することを目的とした制度です。後段で解説する後見人が、高齢者などに代わって財産の管理や契約行為を進めます。成年後見制度を利用することで、判断能力が低下した方であっても、上記のような被害に遭うリスクを抑えられます。
【制度の現状】利用者数は25万人
現状、成年後見制度の利用者は、まだまだ少ないとされています。2023年(令和5年)時点で、成年後見制度の利用者は約25万人です。これは後ほど解説する、法定後見制度・任意後見制度の合算値です。
しかし、判断能力を失っていると想定される人口は、約1000万人に及びます。25万人の利用者は、制度が必要と想定される人口のうち、わずか2%にとどまります。具体的な数字は、以下のページよりご覧ください。なお成年後見制度の利用者が増えない理由は、後述するデメリットが大きいことが挙げられます。
参照:厚生労働省|成年後見制度の現状 (令和5年5月)
成年後見制度の利用者25万人は、法定後見制度・任意後見制度の合算値と説明しました。2つの分類が、それぞれどのような制度であるのか次章で解説します。
成年後見制度の2つの分類
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。さらに法定後見制度は、後見・保佐・補助といった3種類にわかれます。本章では、それぞれの制度について解説します。
1. 判断能力を既に失っている場合に利用する「法定後見制度」
対象となる人物の判断能力が、既に失われていると判断される場合は、法定後見人制度を利用します。家庭裁判所にて選任してもらうことで、後見人と認められます。「親に認知能力がない」と判断した子どもが、裁判所に申し立てるケースが多く見られます。
法定後見は、対象となる人物の症状の重さによって、3種類にわかれます。症状が重篤である順に、後見>補佐>補助となっています。区分や詳細は、法務省のサイトを参照してください。
参照:法務省|Q3~Q15 「法定後見制度について」
以下では、3種類の後見人について簡単に解説します。
法定後見の種類その1. 後見
「後見」が必要とされる対象者は、常に判断能力が失われている人です。日常生活面も困難を伴い、援助が必要なケースは、後見に分類されます。例としては、病気や事故などにより寝たきりとなった場合や、重度の認知症・知的障がいが認められた場合です。代理権や同意が必要な行為、後見人が取り消せる行為については、以下のとおりです。
- 代理権の範囲:財産に関するすべての法律行為
- 同意が必要な行為:すべての法的行為・契約
- 取り消せる行為:すべての法的行為・契約
ただし、日常生活に関する行為は除外されます。なお申立てが行えるのは、3種類すべてに共通して、以下の条件に該当する人です。
法定後見の種類その2. 保佐
「保佐」は、判断能力が著しく低下している人が対象です。日常的な生活はある程度行えるものの、契約行為は困難と判断される場合、保佐に分類されます。中程度の認知症・知的障がいをもつ人が対象です。保佐の代理権や同意が必要な行為、後見人が取り消せる行為については、以下のとおりです。
- 代理権の範囲:申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める行為
- 同意が必要な行為:民法13条1項で定められた行為
- 取り消せる行為:民法13条1項で定められた行為
民法13条1項で定められた行為には、借金や相続の承認などが該当します。
法定後見の種類その3. 補助
「補助」の対象者は、判断能力が低下している(鈍っている)人です。日常生活や契約行為も可能だが、援助があった方がよいと思われる場合は、補助が付きます。具体的には、軽度の認知症・知的障がいなどをもつ人が該当します。補助の代理権や同意が必要な行為、後見人が取り消せる行為については、以下のとおりです。
- 代理権の範囲:申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める行為
- 同意が必要な行為:同上
- 取り消せる行為:同上
2. 判断能力が失われる前の段階で利用する「任意後見制度」
成年後見制度には「任意後見制度」もあります。対象となる人物の判断能力はあるが、将来が不安などの理由から、後見人を立てる場合は、任意後見制度を利用します。名前のとおり、任意で指名した人を成年後見人として契約する制度です。
対象人物の判断能力に問題ないうちは、任意後見は発動しません。判断能力が低下したと判断されたのちに「任意後見監督人」を家庭裁判所に選任してもらいます。申立てを行い任意後見監督人が選任されてから、任意後見で選ばれた人物がサポートを開始します。
成年後見制度の利用を検討すべき5つのケース
どのようなケースに陥った場合、成年後見制度を利用すべきか、最初の判断は難しいでしょう。本章では、成年後見制度の利用を検討すべきケースとして、以下5つについて解説します。
- 銀行での手続きを行いたい場合
- 介護保険・介護施設を契約させたい場合
- 遺産分割協議を行いたい場合
- 不動産を売却したい場合
- その他、身上監護が必要な場合
1. 銀行での手続きを行いたい場合
銀行の預貯金を下ろす、口座を解約するという行為は原則として本人にしかできません。親や親戚などの判断能力が低下し、上記の行為を適切に行えない場合は、成年後見制度を検討しましょう。成年後見人であれば、代理人として上記の手続きが行えます。
2. 介護保険・介護施設を契約させたい場合
介護保険契約や介護施設への入居手続きも、成年後見人で行えます。本人に適切な契約を進めることは難しい、尚且つ上記の手続きが必要である場合は、制度の利用を考えましょう。介護保険に関連した契約・手続きのなかで、成年後見人が行えるものは、以下のとおりです。
- 生活費の送金
- 要介護認定の申請などの手続き
- 施設入所手続き、介護費用の支払い
- 入院手続き
- 医療費の支払い
- 介護サービスの契約手続き
3. 遺産分割協議を行いたい場合
高齢の両親のどちらか一方が死亡した場合、生存している配偶者と子どもで遺産分割を行わなければなりません。しかし、配偶者が認知能力に問題がある場合、遺産の分割が滞る可能性があります。円滑な手続きのためには、法定後見人制度が必要になるかもしれません。
4. 不動産を売却したい場合
親や親戚などが認知症などによって入院した際も、成年後見制度を検討するタイミングです。本人が住んでいた家や土地が不要なため、売却を検討している場合は、成年後見制度を適用するとよいでしょう。不動産売却をはじめ、家族が代理人として契約・解約できない行為は、成年後見人が進めるとスムーズです。
5. その他、身上監護が必要な場合
その他、さまざま身上監護の必要性が生じた場合も、制度検討のタイミングです。本人が生活するうえで必要となる法的手続き全般は、成年後見人が行えます。病院への入院手続きや要介護認定など、日常におけるさまざまな契約を成年後見人が代行できます。
成年後見制度を利用するメリット
成年後見制度を利用するには、複数のメリットがあります。具体的には、以下の効果がメリットとして挙げられます。
- 不利益な契約・詐欺を防止できる
- 必要な手続き・契約を行える
- 不要な契約の取り消しを行える
- 財産の使い込みを防げる
- 相続発生時に正確な財産状況を把握できる
本章では、上記のメリットについて、それぞれ解説します。
不利益な契約・詐欺を防止できる
本人にとって、不利益な契約や詐欺を防げる点は、成年後見制度の代表的なメリットです。成年後見制度は、判断能力の低下した人を詐欺被害から守る目的で誕生した制度です。正常な判断能力が備わっている人が、同意権や取消権をもつことで、不利益な契約を結ぶリスクを回避できます。
必要な手続き・契約を行える
本人の判断能力がない状態でも、必要な契約や手続きを行えることもメリットです。介護施設への入居や住宅の売買などは、認知機能が低下している人にとって、非常に困難なものです。後見人が手続きを代行することで、本人も安心できます。
不要な契約の取り消しを行える
判断能力の低下によって結ばれた不要な契約を、法定後見の成年後見人であれば、本人の代理で取り消しを行えます(代理権の行使)。例えば新聞契約をはじめとした、契約事項も取り消せます。ただし、任意後見人制度における成年後見人の場合、取り消しの権限をもっていないため、注意してください。
財産の使い込みを防げる
認知症などにより判断能力が低下している場合、親族が預金通帳を管理するケースがあります。このような状況では、通帳を管理している親族が不正利用している可能性もあるでしょう。成年後見人を指定することで、財産管理権が後見人に移ります。その結果、親族は被後見人の財産を自由に使用できなくなります。
成年後見人を選任することで、親族による不正利用を防げます。また成年後見人は中立的な第三者であり、裁判所によって選出されます。彼らが財産を管理し、財産状況を家庭裁判所に報告するため、親族間の感情的な衝突を防ぐ利点もあります。もちろん本人が知らずに使い込んでしまうケースも防げるでしょう。
相続発生時に正確な財産状況を把握できる
相続発生時に、正確な財産状況を把握できることもメリットです。成年後見制度では、後見人が財産の管理を行っているため、本人が死亡した際も、財産状況の確認を素早く行えます。遺産分割協議を行う場合も、スムーズに話し合いが進むでしょう。
成年後見制度を利用するデメリット
前半で、成年後見制度の利用者が少ないと解説しました。繰り返しになりますが、成年後見制度は必要と想定される人口のうち、約2%にしか利用されていません。その原因は、制度の利用において、いくつかのデメリットがあるためです。制度利用におけるデメリットは、以下の通りです。
- 本人死亡まで制度を利用しなくてはならない
- 利用開始まで手間と時間がかかる
- 成年後見に対して報酬を払い続けなくてはならない
- 財産運用の柔軟性が失われる
- 家族が選任されるとは限らない
- 一度選任された後見人を途中で解任することはできない
各デメリットについて、本章で解説します。
本人死亡まで制度を利用しなくてはならない
成年後見制度における最大のデメリットは、一度申し立てると取り下げが不可である点です。例えば、認知症の親の口座を解約したいといった、特定の目的があり、制度を利用した場合です。口座の解約を果たしたあとも、制度を利用し続けなくてはなりません。柔軟性が乏しい点は大きなデメリットです。
利用開始まで手間と時間がかかる
必要な場合に、すぐ利用できない点もデメリットです。成年後見制度は、申立てを行ってから、成年後見人が選出されるまでに時間がかかります。手続きや必要書類も煩雑であり、非常に手間がかかってしまいます。忙しい人が、なかなか手続きを進められないことは、大きなデメリットです。
成年後見に対して報酬を払い続けなくてはならない
一度制度を利用すると、継続しなければならないとは、つまり後見人への報酬も継続します。本人が死亡するまで、成年後見人に対して報酬を払い続ける必要があります。費用の相場は後述していますが、弁護士などの専門家が選任された場合は月額2~6万円の報酬が発生します。
財産運用の柔軟性が失われる
成年後見制度を利用すると、財産運用の柔軟性が失われてしまいます。生前贈与をはじめとした選択肢が失われるため、積極的な節税対策を行えません。財産運用の選択肢を狭めることになってしまいます。
家族が選任されるとは限らない
法定後見人の場合、家族が成年後見人になれるとは限りません。希望は出せるものの、最終的には家庭裁判所が選任します。また次で解説するように、選任された後見人の変更は原則できません。財産に関する契約に家族以外が関与する状況も生じるため、抵抗を感じる人は、制度の利用を躊躇ってしまうでしょう。
一度選任された後見人を途中で解任することはできない
原則として、一度選任された後見人を途中で解任することはできません。後見人を解任する場合は、財産の横領や不貞行為など、解任が相当と判断できる事由が必要です。ただし、被後見人の健康状態・認知能力が回復し、医師の診断によって「後見人が不要」と診断された場合は、相当な事由がなくとも解任できます。
成年後見制度を利用した具体事例
実際に成年後見制度を利用した人は、どのようなケースであったのでしょうか。本章では、制度を利用した具体事例を、2つ紹介します。
軽度認知症の自覚があり成年後見制度を利用したケース
80代女性の事例について、解説します。女性は健康上の問題はないものの、時折物忘れを起こしていました。結婚して子どもが二人いるものの、別居していたため、夫には頼れない状況でした。
老人ホームへの入居が決まり、一時金の支払いのために銀行の定期預金を解約しようとしました。しかし、認知機能に問題があり、窓口での本人確認にしっかりと返答できませんでした。その後、軽度の認知症を自認し、成年後見制度の利用に至りました。なお、この段階では、任意後見契約が適用されます。
遺産分割協議の対応ができないほど認知症が進んだ相続人のケース
60代男性の事例を紹介します。男性は、アルツハイマーによる認知症であり、日々症状が悪化していました。妻による介護を受けているなかで、男性の父親が死亡します。遺産分割協議が必要となったが、男性自らの対応は困難であったため、成年後見制度を利用しました。
男性は、認知症が進んでいたため、法定後見制度が適用されました。身上監護は妻となり、遺産分割協議をはじめとした財産管理は、専門家が担当することとなりました。
成年後見人になるための必要資格はない!ただし注意すべき欠格事由がある
後見人になるために必要な資格はありません。基本的に誰でも後見人になれますが、以下の条件(欠格事由1~5)に該当する場合は不可とされます。
欠格事由(民法第八百四十七条)
- 未成年者
- 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
- 行方の知れない者
参照:e-GOV|民法 第五章 後見
後見人を選ぶのは家庭裁判所であり、特に注意したいポイントとしては、以下2点が挙げられます。
- 希望した人が選任されるとは限らない
- 希望した人が選ばれなかったという理由での取り下げは不可
成年後見制度を利用する場合の手続き
成年後見制度を利用する際は、手続きが必要です。利用開始までの手続きは「法定後見人を選任する場合」と「任意後見人を選任する場合」では異なります。それぞれについて解説します。
法定後見人を選任する場合、まずは家庭裁判所へ申立てる
まずは被後見人(本人)の住所地にある「家庭裁判所」に申し立てを行います。申し立てを行えるのは、本人もしくは四親等以内の親族(配偶者、子、孫、両親、兄弟姉妹、従妹など)に限ります。
家庭裁判所の調査官が本人と面談し、判断能力を確認します。ここで「後見」「保佐」「補助」のいずれに該当するのか決定します。手続きに必要な書類や流れは、以下の記事で確認してください。
任意後見人を選任する場合、まずはサポートしてくれる人を探す
任意後見人を選任する場合は、被後見人(本人)の判断で、将来必要なサポート内容やサポートしてくれる人(=後見人)を決めます。「公証役場」にて、任意後見契約書の作成・契約締結を行います。成年後見制度促進を目的に、厚生労働省が作成したポータルサイトがあります。手続きの流れや必要書類について記載されているため、参考にしてください。
参照:厚生労働省|成年後見はやわかり
成年後見制度を利用する場合の費用
成年後見制度を利用するにあたって、相応の費用が発生します。本章では、成年後見制度の開始から終了までにかかる費用の相場を解説します。なお費用は、法定後見制度か任意後見制度かによっても異なるため、それぞれの相場価格も参考にしてください。
成年後見制度の開始から終了までの費用:100万円~700万円
成年後見制度の利用を開始し、被後見人が死亡するまでを10年間とした場合、約100~700万円の資金が必要となります。これは任意後見の最低価格である月額1万と、法定後見の最高月額6万をもとに計算した価格です。
法定後見制度の利用にかかる費用:月額2~6万円が相場
法定後見人を選任する場合、申し立てにかかる費用相場は、以下のとおりです。
- 申立て手数料:600円
- 後見登記費用:2,600円
- 郵便切手代:3,000~5,000円(家庭裁判所によって異なる)
上記の手続きを、司法書士をはじめとした専門家に依頼した場合は、別途10~20万円の費用がかかります。
そして成年後見人への報酬も必要です。選任される後見人が、誰になるのかによって相場が異なります。
- 親族など:0円/月
- 弁護士などの専門家が選任された場合:2~6万円/月
上記は、本人が死亡するまで毎月かかる費用です。日常業務以外の特別な業務が発生した場合は、必要に応じて付加報酬も支払います。
任意後見制度の利用にかかる費用:月額1~3万円が相場
任意後見人を選任する場合、必要な費用は月額1〜3万円です。利用にあたって公証役場を利用する場合は、初期に以下の費用も発生します。
- 公正証書作成手数料:11,000円
- 公正証書代:10,000円
- 任意後見契約の登記嘱託手数料:1,400円
- 登記に納付する印紙代:2,600円
こちらも手続きを、司法書士や弁護士などの専門家に依頼した場合、別途10~15万円の費用が発生します。任意後見人への報酬相場は、以下のとおりです。
- 親族など:0円~5万円/月
- 弁護士などの専門家に依頼する場合:3~6万円/月
- 任意後見監督人への報酬:1~3万円/月
任意後見監督人は、家庭裁判所が選任し、報酬も裁判所が決定します。
まとめ
成年後見制度は、認知症や障がいによって判断能力の低下した人が、不利益を被らないようにする支援制度です。判断能力に問題のない後見人が、多くの契約・手続きを代行することで、被後見人を詐欺やトラブルから守ります。
しかし成年後見制度には、メリットとデメリットがあります。高額な費用もかかるため「できれば、他の方法を採用したい」と考える人もいらっしゃるでしょう。成年後見制度を利用したくない人は、以下の記事もご覧ください。