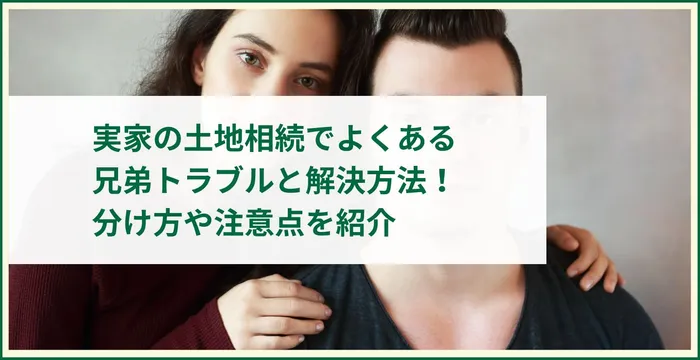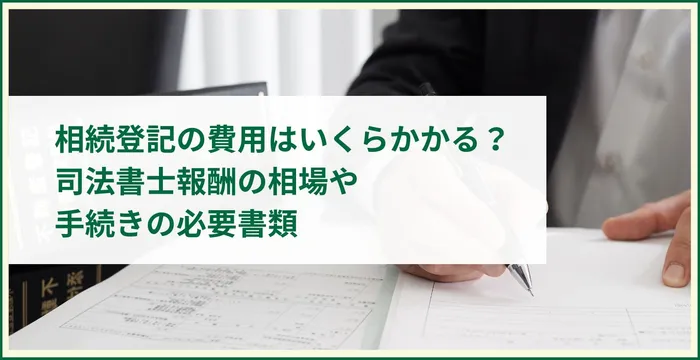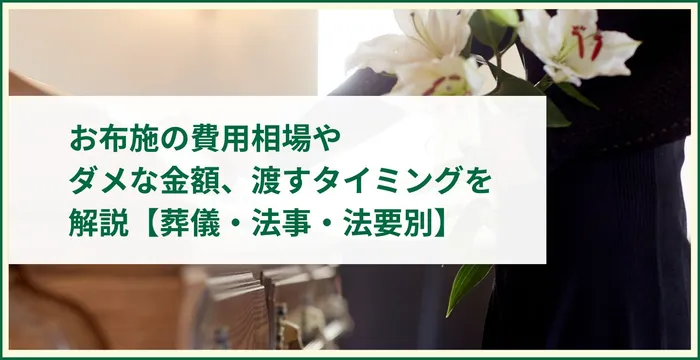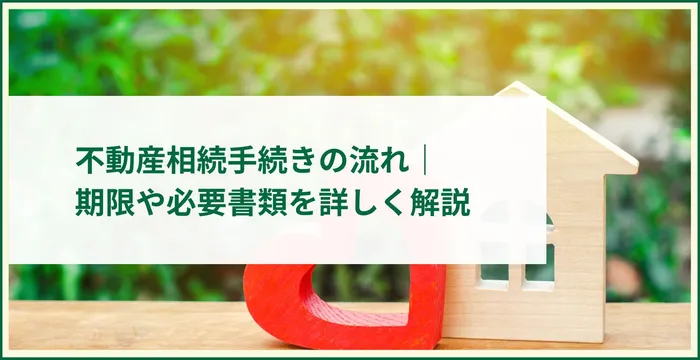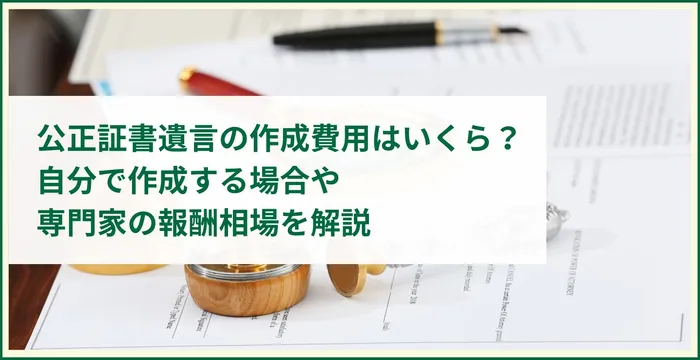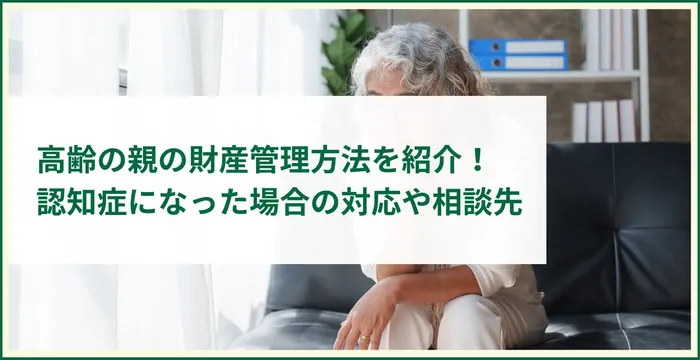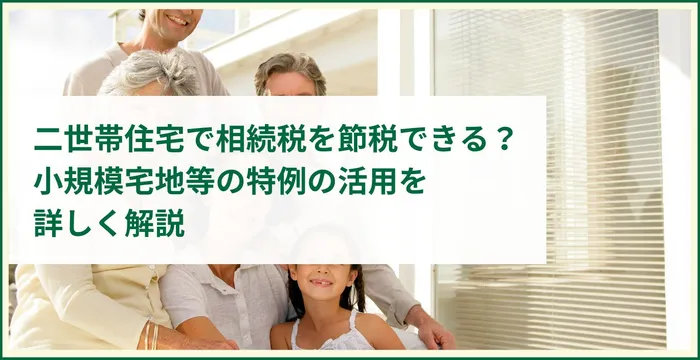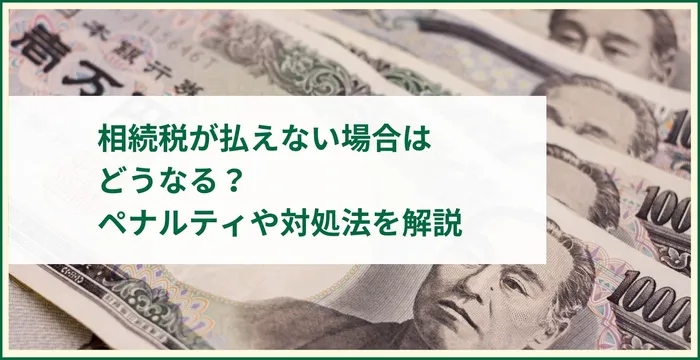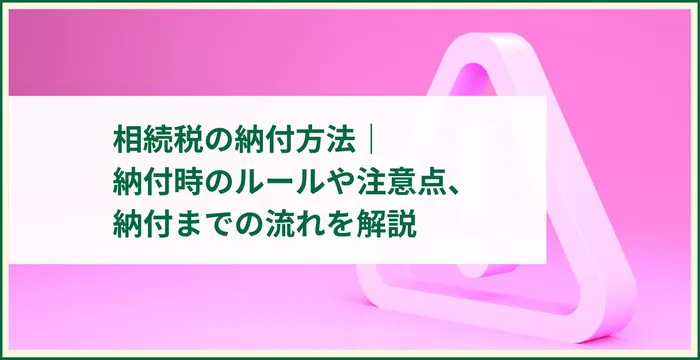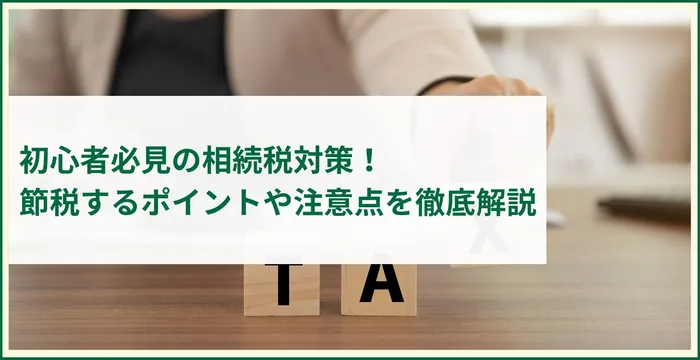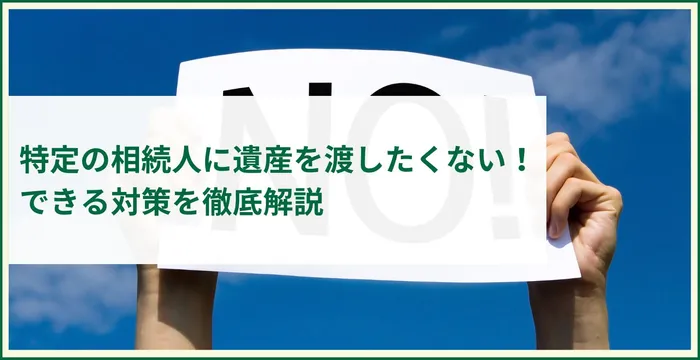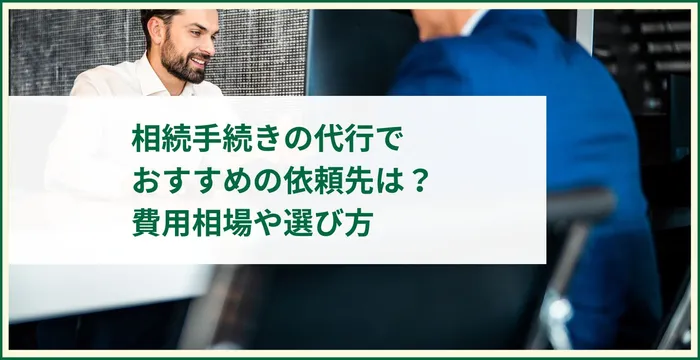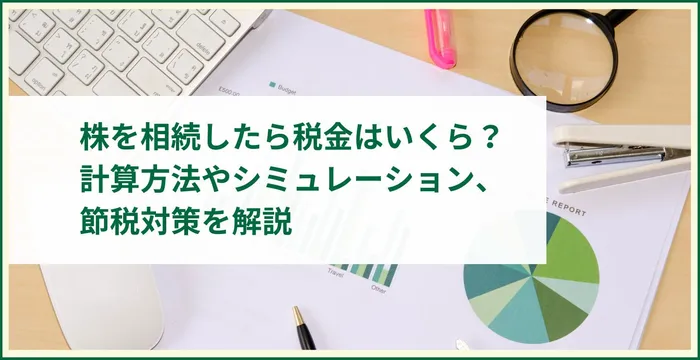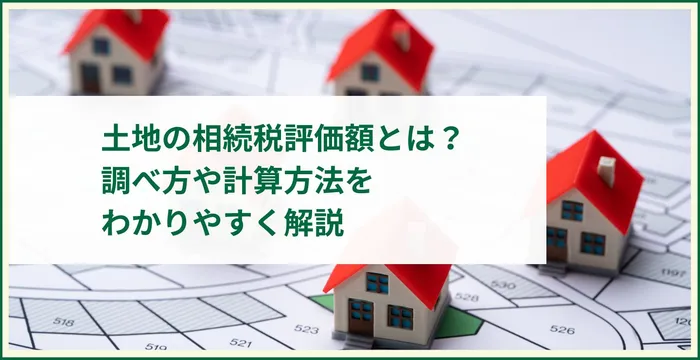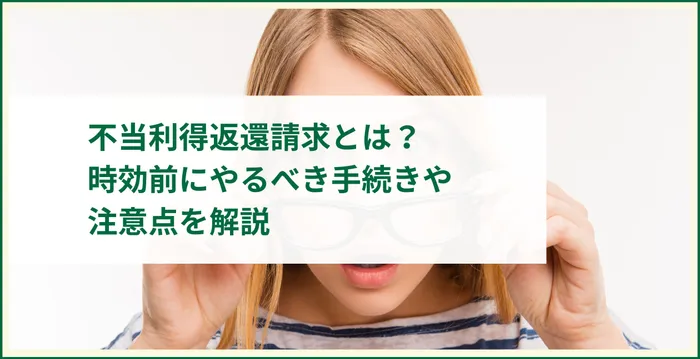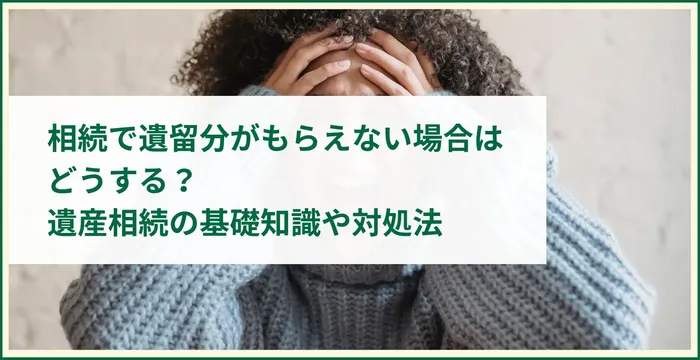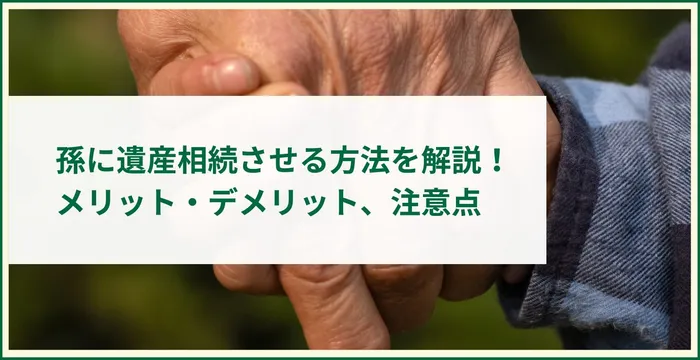兄弟間で実家の土地相続トラブルが起こったとき、揉めている原因によって解決方法が異なります。本記事では、実家の土地相続でよくある兄弟トラブルを原因別に紹介した上で、解決方法について詳しく解説します。
『ツナグ相続編集部』執筆のコラム一覧
相続登記にかかる司法書士報酬の相場や必要書類の取得費用、登録免許税について紹介します。費用は誰が支払うのか、自分でできるのか、司法書士に依頼するメリットとデメリットについても解説します。
お通夜や葬儀、初七日や四十九日などのお布施の相場について、シーンごとにわかりやすくまとめています。お布施の渡し方や渡すタイミングなども解説しており、お布施を渡すときの疑問解消に役立つ記事です。
不動産相続手続き(相続登記)の流れや費用、必要書類、手続き期限などの知識を解説する記事です。相続登記を自分でやったほうがよいのか、司法書士に依頼したほうがよいのかも含め、不動産相続手続きに際してよくある質問に対してお答えします。
認知症の人は判断能力が低下している状態であるため、相続放棄をするためには成年後見人を選任し、代理で手続きをしてもらう必要があります。本記事では、認知症の相続人が相続放棄をする方法や、成年後見制度について解説します。
公正証書遺言か自筆証書遺言のどちらを作成するか検討するにあたり、公正証書遺言の作成にかかる費用や手続きを知ることは重要です。本記事は必要書類や踏むべき手順を詳しく説明しています。遺言作成に関心のある方はご覧ください。
高齢の親が認知症になる前・なった後にできる財産管理の方法を解説します。財産管理の相談先も紹介しますので、良い方法がないか悩んでいる人は必見です。
二世帯住宅で相続税を節税するには「小規模宅地等の特例」の活用がおすすめです。要件にあてはまれば、土地の評価額が80%減額できます。この記事では、二世帯住宅の節税方法について「小規模宅地等の特例」を中心に解説します。ぜひ最後までご覧ください。
相続税が払えない場合、無申告加算税や延滞税、差し押さえなどのペナルティを受ける可能性があります。この記事では相続税が払えない場合の対処法について解説します。相続税が払えなくて困っている人はぜひ参考にしてください。
相続税の納付方法を解説します。相続税は金融機関やクレジットカード、税務署窓口、コンビニエンスストアでの納付が可能です。納付時のルールや注意点、納付の流れも紹介するので最後までチェックしてください。
相続税は、ご本人が生きているうちに対策を行えば、大きく節税することが可能です。この記事では、生前贈与や控除などを活用した相続税対策の方法を解説していきます。
特定の相続人に遺産を渡したくない場合の対処法や注意点を詳しく解説しています。遺留分に関するトラブルを避けるポイントも紹介しますので、参考にしてください。
相続手続きは、弁護士・司法書士・税理士などに代行を依頼することができます。おすすめの依頼先の選び方や、費用の相場など、わかりやすく解説していきます。
株を相続した場合には基本的に相続税がかかりますが、生前贈与や特例の利用などにより節税が可能です。計算方法や手続きが複雑なため専門家への相談も検討しましょう。本記事では、株を相続する場合の計算方法や節税対策について解説しています。
相続税評価額とは、財産ごとに決められた計算式に基づいて算出する財産の価額のことです。本記事では、土地の相続税評価額の計算方法や土地の相続税について詳しく紹介します。
相続財産がすでに何者かによって使い込まれていた場合は、不当利得返還請求で取り戻せる可能性があります。不当利得の返還を求める場合にはどんな点に注意すればいいのか、またやるべき手続きや弁護士に依頼する際の費用相場について解説します。
遺言書の内容や生前贈与の有無などによっては、取得できるはずの遺留分がもらえないケースがあります。本記事では、相続で遺留分がもらえなかったときの対処法や、遺産相続の基礎知識などについて詳しく解説します。
家族信託契約書の書き方には、いくつか注意点があります。内容に不備があると、契約書が無効になってしまうためです。この記事では、信託契約書の書き方や自分で作成する際の注意点を解説します。
通常孫は法定相続人になれないため、生前に何らかの相続対策をしておかないと孫に遺産を相続させられません。そこで本記事では、孫に遺産相続させる方法やメリット・デメリット・注意点について解説していきます。
遺産分割協議書に印鑑を押してくれないときは、相続人が納得いくよう協議するか、弁護士や家庭裁判所を介して交渉を進めます。記事では調停や審判、実印がないときの対処法の詳細を解説しています。