配偶者が死亡したときにやること、必要な手続きは少なくありません。
死亡日から数日以内に行わなければならない、短い期限が設定されている手続きも多いため、次に何をしたらよいのかわからず困ってしまう場合もあるのではないでしょうか。
この記事では、死亡届といった役所関係の手続きをはじめ、年金関係、保険関係、相続関係の手続きなど、夫や妻が死亡したときに行わなければならないさまざまな手続きに関して、期限の短いものから時系列で解説していきます。
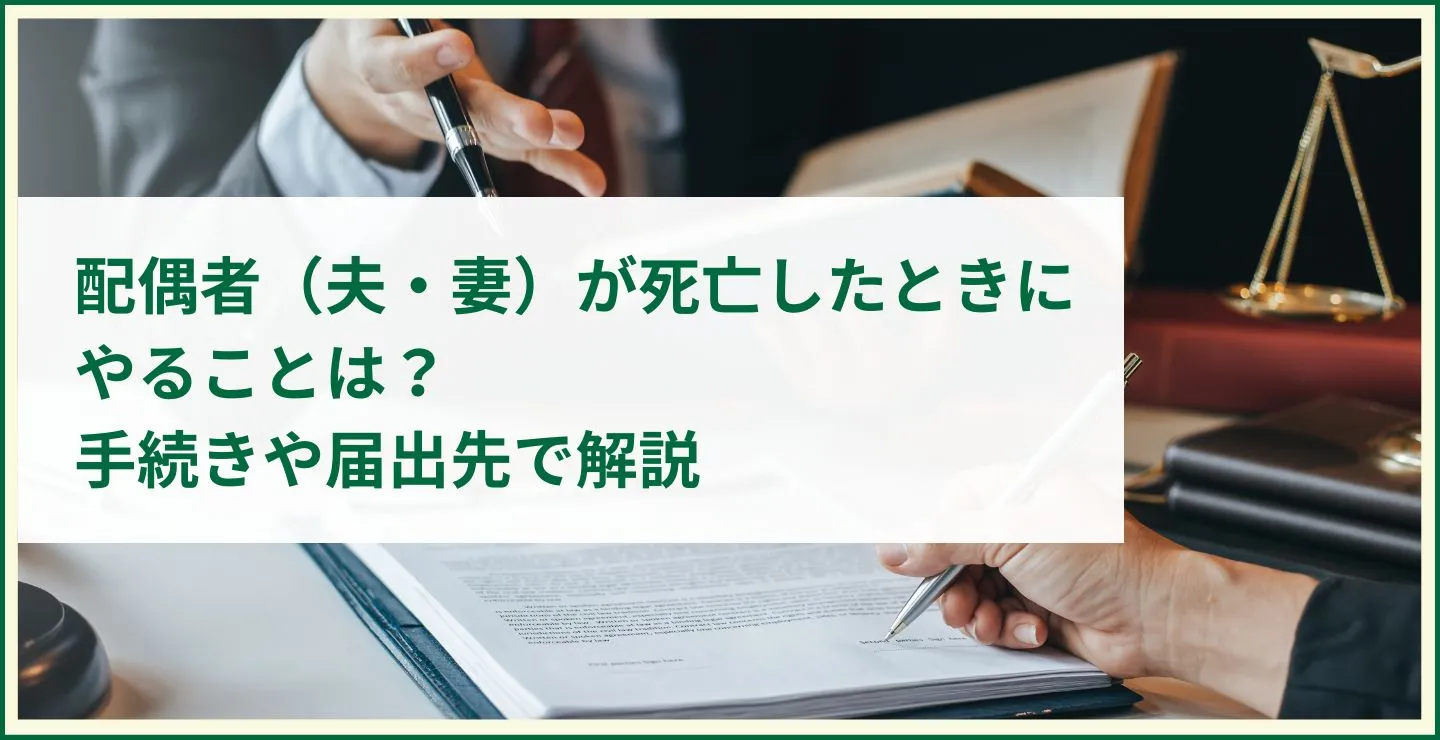
配偶者が死亡したときにやること、必要な手続きは少なくありません。
死亡日から数日以内に行わなければならない、短い期限が設定されている手続きも多いため、次に何をしたらよいのかわからず困ってしまう場合もあるのではないでしょうか。
この記事では、死亡届といった役所関係の手続きをはじめ、年金関係、保険関係、相続関係の手続きなど、夫や妻が死亡したときに行わなければならないさまざまな手続きに関して、期限の短いものから時系列で解説していきます。
夫・妻が死亡した際には、やらなければならないさまざまな手続きがあります。はじめに、すぐにやることとして、最短で7日以内、最長で30日以内に行わなければならない手続きを解説します。
| 死亡から手続きまでの日数 | やるべきこと一覧 |
|---|---|
| 死亡後すぐ | 死亡診断書を受け取る |
| 5日以内 | 社会保険の健康保険資格喪失手続き(勤務先が行う) |
| 7日以内 |
・死亡届の申請 ・埋火葬許可証の申請 |
| 10日以内 | 厚生年金の受給停止手続き |
| 14日以内 |
・国民健康保険の資格喪失手続き ・介護保険の資格喪失手続き ・世帯主変更手続き ・国民年金の受給停止手続き |
| 30日以内 | 雇用保険受給資格者証の返還 |
妻や夫が死亡したときの手続きとして最初にやるべきことは、死亡診断書の受け取りです。死亡診断書は、医師が死亡を確認した時点で作成するもので、死亡した日時や場所、死亡原因などが記載されています。
入院中や通院中に病気などが原因で死亡した人の場合には、病院から死亡診断書が発行されます。ただし、急死や自殺など、原因がはっきりしない場合には、警察で検死が行われ、警察から死体検案書が発行されます。
死亡診断書の発行費用は病院ごとに異なり、3,000円~1万円ほどです。死体検案書の発行には、検案や遺体の搬送などの費用もかかります。検査内容や搬送距離などで費用が異なるため、発行費用は3万~10万円ほどになります。
死亡保険金の請求で死亡診断書を利用する場合など、手続きの際に必要になるケースは少なくないため、多めにコピーを取っておくことをおすすめします。
死亡届は、死亡診断書と同時に渡される書類です。
死亡診断書用紙の左半分が死亡届になっているため、死亡した夫・妻の氏名や住所、本籍などの必要事項を記入してから両方の書類を一緒に市区町村役場に提出します。死亡届を提出して役所で処理されると、戸籍には「死亡」と記載されます。
提出先は、死亡者の本籍地もしくは死亡した住所地、届出人の住所地の市区町村役場です。死亡届を提出できる届出人は、同居の親族、同居者、家主などに限定されます。
届出人は死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出しなければなりません。
夜間や休日でも提出は可能で、死亡届と同時に「火葬許可申請書」も提出して受理されると、火葬許可証が発行されます。なお、死亡届や火葬許可申請書の提出は、葬儀社が代行してくれる場合もあります。
健康保険の手続きは、加入先によって必要な手続きと期限が異なります。健康保険の加入先は、会社員の場合が社会保険(健康保険組合もしくは協会けんぽ)、自営業や主婦が国民健康保険、公務員が共済組合です。
会社員と公務員の場合には、勤務先に配偶者の死亡を伝えると健康保険資格喪失手続きをしてくれます。ただし会社の手続きには死亡日から5日以内の期限があるため、早めに連絡しなければなりません。連絡後は、厚生年金保険の被保険者資格喪失手続きも同時に勤務先が行ってくれます。
死亡者が国民健康保険に加入していた場合は、14日以内に市区町村役場の窓口で資格喪失の手続きをしなければなりません。
窓口には、国民健康保険資格喪失届、保険証、死亡診断書のコピーなどを提出します。死亡者の扶養に入っていた人は、死亡日の翌日から14日以内に自身が国民健康保険に新しく加入しなければなりません。
| 社保 | 国保 | |
|---|---|---|
| 期限 | 5日以内 | 14日以内 |
| 手続き場所 | 勤務先 | 市区町村役場 |
| 必要書類 | 特になし |
国民健康保険資格喪失届 被保険者証(世帯主死亡の場合には世帯全員分) 死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーなど) 世帯主認印 届出をする人の本人確認書類 |
死亡者が65歳以上の第1号被保険者の場合や、40歳以上65歳未満の第2号被保険者で要支援・要介護認定を受けていた場合には、介護保険の資格喪失手続きも必要です。
資格喪失手続きの期限は14日以内で、死亡者の住民票がある市区町村の窓口で行います。
介護保険料は、死亡した時点の月割りで再計算されるため、保険料に変更が生じた場合には「介護保険料変更決定通知書」が届きます。再計算後、保険料を納めすぎていた場合には手続きによって還付が受けられ、不足している場合には相続人が不足分を納付しなければなりません。
世帯主が死亡した場合には、世帯主を変更するため14日以内に市区町村の窓口へ「世帯主変更届」の提出が必要です。
ただし、世帯が夫婦2人だけで形成されていた場合など、世帯主になる人が明らかな際には届出が不要なこともあります。なお、15歳未満の子どもは世帯主になれないため、夫婦と15歳未満の子どもだけの世帯も同様に届出は不要です。
死亡者が年金を受給していた場合には、国民年金、厚生年金の受給停止手続きを行います。
年金の受給停止手続き期限は、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。提出に必要な書類は、年金受給権者死亡届(報告書)と死亡者の年金証書、死亡診断書など死亡を証明する書類です。
年金受給の停止手続きは、市区町村役場ではなく、年金事務所もしくは年金事務センターで行います。
年金は偶数月の15日が支給日で2カ月分がまとめて支給されるため、「未支給年金請求手続き」が受理されると死亡月までの年金を遺族が受け取れます。ただし、未支給分の年金は、死亡者と生計を同じくしていた親族だけしか受給できません。
なお、生前にマイナンバーを年金事務所に登録していた場合には、死亡届を提出した市区町村のデータが年金事務所にも伝わるため、年金受給権者死亡届(報告書)を提出する必要はありません。
雇用保険の受給者が死亡した場合には、「雇用保険受給資格者証」の返還手続きが必要です。死亡1カ月以内に、雇用保険を受給していたハローワークに雇用保険受給資格者証と死亡を証明する書類を提出、返還します。
(参考:配偶者(夫・妻)が死亡した時にすべき手続きは?時系列ごとに解説|みんなが選んだ終活)
いままで解説した手続きは、配偶者の死亡後1カ月以内にすべきものです。これらの手続きを終えたあとには、期限まで少しゆとりのあるものを順に行っていきます。代表的なものとしては、死亡者の所得税や相続税の申告、死亡後に受け取れる死亡一時金申請手続きなどがあります。
| 4カ月以内 | 死亡した配偶者の所得税準確定申告 |
|---|---|
| 10カ月以内 | 相続する遺産の相続税申告 |
| 遺留分侵害の事実を知ったときから1年または相続開始から10年以内 | 遺留分侵害請求 |
| 死亡日の翌日~2年以内 |
国民年金の死亡一時金請求 社会保険の埋葬料 高額療養費の支給申請 |
死亡した配偶者が自営業をしていたり、動産所得があったりなど、生前の所得の確定申告をしなければならない場合には、死亡を知った日の翌日から4カ月以内に本人の代わりに相続人が確定申告を行わなければなりません。
相続人が代わりに行う確定申告は「準確定申告」と呼ばれます。準確定申告後には、所得税の還付金が受け取れる場合があります。準確定申告が期限に間に合わないと延滞税や加算税などが発生する恐れがあるため、期限内に手続きを行うことが大切です。
死亡者の遺産総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、相続税を申告する必要もあります。
法定相続人が2人のケースでは「3,000万円+(2人✕600万円)=4,200万円」が基礎控除額になるため、相続税額が4,200万円を超えた場合、期限までに税務署で申告・納税をしなければなりません。
相続税は、相続開始を知った翌日から10カ月以内が申告期限です。提出に必要な書類は、相続財産の種類や受ける控除・特例などによって異なります。
相続関係でやるべきことは、後述する「配偶者(夫・妻)が死亡したときに相続関係でやること」でまとめています。
遺留分とは、相続人に保障されている一定の相続分です。
遺留分は、法定相続人のなかでも、死亡者の兄弟姉妹にはなく、死亡者の配偶者、子(孫)、父母(祖父母)だけが認められている権利です。
死亡者の遺言や遺贈を執行すると遺産の相続額が少なくなる場合に、遺留分侵害請求の手続きで一定分の遺産を取り戻せます。
遺留分は、配偶者だけが相続人の場合には2分の1、配偶者と子が相続人の場合には配偶者が4分の1・子が4分の1などと定められています。
遺留分侵害請求は、受遺者や相続人に遺留分侵害額の支払いを求めて起こす調停・訴訟手続きです。期限は遺留分侵害の事実を知ったときから1年以内、もしくは相続開始から10年以内です。金額が140万円以下では簡易裁判所、それ以上の金額の場合には地方裁判所に申請を行います。
相続関係でやるべきことは、後述の「配偶者(夫・妻)が死亡したときに相続関係でやること」でまとめています。
亡くなった配偶者が国民年金の加入者だった場合には、生計を同じくしていた親族が死亡一時金を受け取れる可能性があります。
死亡一時金は、国民年金に第1号被保険者として3年間以上加入し、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しなかった場合に支給されます。支給される額は12万円~32万円です。加入期間によって支給額が決まります。
死亡者が社会保険に加入していた場合には、必要書類を提出して手続きを行うと、5万円の埋葬料が支給されます。埋葬料の申請は、死亡者によって生計を維持されていた配偶者などが行えます。
死亡者に生計を維持されていた人がいない場合には、実際に埋葬を行った人・喪主などが申請可能です。手続きの期限は死亡後2年以内、健康保険組合、協会けんぽのうち、加入していた社会保険に連絡して行います。
高額療養費は、1カ月分の医療費が一定額を超えた場合に、超えた金額が戻ってくる制度です。本人が死亡したあとでも、相続人が申請すると支給を受けられます。
医療費の自己負担限度額は、保険加入者の所得や年齢によって異なり、健康保険組合の加入者には付加給付分がつく場合があるため、ほかの健康保険加入者よりも還付額が多くなる場合があります。
還付される金額は保険適用になる医療費だけです。保険適用外の先進医療費や住居費、食事代などは還付額には含まれません。
申請の期限は、死亡者が診療を受けた月の翌月1日から2年以内です。未申請で時効になっていないものがあれば、その分も請求が可能です。「高額療養費支給申請書」に必要な書類を添付して、申請窓口や郵送で申請を行います。
妻や夫が死亡した際、やらなければならないことが多いのが相続関係です。相続税の申告・納付期限までに、遺産の確認や遺産分割協議などをスムーズに行わなければなりません。
遺言書は、相続の際に重要な役割をもつ書類です。配偶者が死亡した場合には、相続手続きを開始する前に遺言書が遺されていないかを確認しましょう。遺言書には、「公正証書遺言」「秘密証書遺言」「自筆証書遺言」の3種類があります。
公正証書遺言と秘密証言遺言は、公証役場に問い合わせると遺言書の有無が確認可能です。自筆証書遺言は、自身で保管している遺言書で、自宅の金庫や机、棚、仏壇などを確認すると見つかる場合があります。また、弁護士や行政書士などに預けてあるケース、銀行の貸金庫内に保管してあるケースもあるため、予想できる範囲を確認しましょう。
遺言書が見つかった場合、遺言書の内容を検認してから相続を進めていきます。検認とは、裁判所で遺言書の内容を確認することです。相続人全員に遺言の内容を知らせて偽造や破棄などを防止する目的で行われます。
検認は、死亡者の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てします。申立てには、死亡者の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言書の提出、収入印紙800円と切手代が必要です。
なお、公証役場で作成・保管されている公正証書遺言の場合は検認が不要で、そのまま執行できます。
ただし、自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、原則として家庭裁判所で検認を受けなければなりません。検認をせずに開封してしまうと、5万円以下の過料が科される場合があるため、検認まで開封せずに保管します。
なお、2020年7月10日からは、法務局が遺言書を保管する「遺言書保管制度」が始まったため、この制度を利用している場合には検認の必要がありません。
相続時には、遺産分割などの手続きを進める前に誰が相続人になるのか把握することが必要です。相続人を把握するためには、死亡者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、戸籍に記載されているすべての相続人を調べます。
戸籍謄本は、死亡者の本籍地がある市区町村役場で取得が可能です。死亡者の戸籍謄本の取得に必要なものは、戸籍交付申請書、印鑑、申請者の本人確認書類などです。
相続放棄や限定承認を行う場合には、申請期限の3カ月が過ぎる前に相続人の把握を終わらせなければなりません。相続を放棄する人がいた場合、「相続放棄申述受理証明書」のコピーを受け取って相続人を確定させます。
遺産分割前には、不動産や預貯金、証券など、相続財産がいくらあるのかを調査して確定する必要もあります。
不動産を調べる場合には、毎年家に届く「固定資産税課税明細書」や、市区町村役場で取得できる「名寄帳」などを確認します。法務局では、不動産の「全部事項証明書」の取得も可能です。
預貯金などを調べるには、通帳やキャッシュカード、郵便、貸金庫などの確認が有効です。各銀行の預金残高は、銀行で「預金残高証明書」を取得すると明確になります。証券がある場合には、証券会社への確認も行います。
請求書、借用書などからマイナス財産の債務まですべて確認することが大切です。相続財産が確定したら、期限内に相続放棄や限定承認を行うかどうかを検討します。
遺産分割は、相続人が複数いる場合に、死亡した配偶者の遺産を相続人全員で分けることです。
そして、相続人と相続財産が確定してから、相続人全員で遺産の分け方を決めるために話し合いをするのが遺産分割協議です。
遺産分割協議が終了したあとには、「遺産分割協議書」の作成を行います。相続税の申告や納付期限は相続開始から10カ月以内のため、期限までに協議を終わらせることが大切です。
相続人同士の話し合いで解決できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停を行い、調停委員が間に入って解決に向けた話し合いを進めます。
調停でも話がまとまらなかった場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。
相続財産確定後に負債額が高額になっているとわかった場合、相続放棄や限定承認も可能です。
どちらも配偶者の死亡から3カ月以内に手続きを行う必要があるため、早めに決定する必要があります。
相続放棄は、プラスとマイナスの財産すべてを放棄する手続きです。死亡者の住所地を管轄する家庭裁判所で、相続人全員ではなく1人で手続きを行えます。手続きには「相続放棄申述書」に、死亡者の除籍謄本・住民票除票、申述人の戸籍謄本などの添付書類が必要です。
一方、限定承認は、負債よりも資産の方が多い場合に、マイナス資産を差し引いて残ったプラスの資産だけを承継するための手続きです。限定承認の場合は、相続人全員で手続きをしなければなりません。
手続きは相続放棄と同様に死亡者の住所地を管轄する家庭裁判所で行えます。「限定承認の申述書」に、財産目録、死亡者の戸籍・住民票除票(戸籍の附票)、相続人全員分の戸籍謄本、収入印紙(800円)、切手などを添付して申述します。
遺産の相続後には、不動産や自動車、銀行口座、株式などの名義変更を行います。不動産の名義変更は、所在地を管轄する法務局に、死亡者の除籍謄本、死亡者の住民票除票、相続人の住民票、相続人の戸籍謄本、遺産分割協議書(遺言書)、固定資産評価証明書、相続関係説明図などの必要書類を提出して実施します。
自動車を相続した場合は、運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に、死亡者の除籍謄本、遺産分割協議書(遺言書)、相続人の印鑑登録証明書、車検証、自動車税申告書、車庫証明書などを持参すると名義変更が可能です。
預貯金を相続する場合、凍結された口座を名義変更によって解除する必要があります。名義変更をする際は、金融機関所定の名義変更申請書、死亡者の戸籍謄本、預金通帳、キャッシュカード、銀行印、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、遺産分割協議書(遺言書)などを窓口に持参します。
株式の名義変更は、証券会社に必要書類を持参して行います。必要書類は、死亡者の戸籍謄本、証券会社への届出印、口座がわかる書類、相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書、遺産分割協議書(遺言書)などです。会社によって必要な書類が異なるケースもあるため、確認してから書類をそろえるのがおすすめです。
夫・妻が死亡した場合、役所関係や相続関係といった期限が定められている手続きのほかにも、公共料金の名義変更や、運転免許証の返納など、さまざまな手続きをしなければなりません。
死亡した配偶者が生命保険・医療保険に加入していた場合、受取人になっている人は死亡保険金を受け取れます。生命保険は遺産ではないため、遺産分割協議への影響はありません。ただし、受け取る保険金には相続税がかかります。
法定相続人が受取人になる場合には1人500万円の非課税枠が利用可能で、法定相続人が2人いる場合には保険金の1,000万円までが相続税非課税です。それ以上の金額には相続税がかかります。また、法定相続人でも配偶者、子、親以外が受取人の場合では、かかる相続税が2割加算になります。
保険金請求手続きは、死亡後3年以内です。保険会社に連絡して、保険証書や死亡者の除籍謄本、受取人の身分証明書、印鑑などをそろえて手続きを行います。
電気、水道、ガスなどの公共料金を配偶者名義で契約している場合には、名義変更、口座変更も必要です。契約先の電力会社、ガス会社、市区町村の水道料金窓口に連絡をすると、変更が行えます。
故人名義の携帯電話やスマートフォンの契約は、放置するといつまでも基本料金がかかるため、早めに解約するのがおすすめです。
請求書などで契約先を確認し、その携帯電話会社に連絡して解約しましょう。電話番号を残したい場合には、「承継」によって相続人に名義変更ができるかどうかを各携帯電話会社に確認し、可能な場合には名義変更の手続きを行います。
死亡した配偶者が免許を持っていた場合には、警察署や自動車安全運転センターで免許証を返納します。返納手続きには、免許証、死亡診断書のコピー、死亡者の除籍謄本、手続きをする人の身分証明書と印鑑が必要です。
配偶者が持っていたパスポートは、早めに失効手続きを行いましょう。パスポート、死亡診断書のコピー(もしくは死亡者の住民票除票)、申請者の身分証明書を準備してパスポートセンターに行くと、手続きが可能です。
配偶者が死亡したときには、数日の短い期限内に行う手続きから、数カ月、数年の間に行う手続きまで、さまざまな手続きが発生します。死亡後すぐにやらなければならないことも多いため、やるべきことを整理して、スムーズに手続きを行うことが大切です。