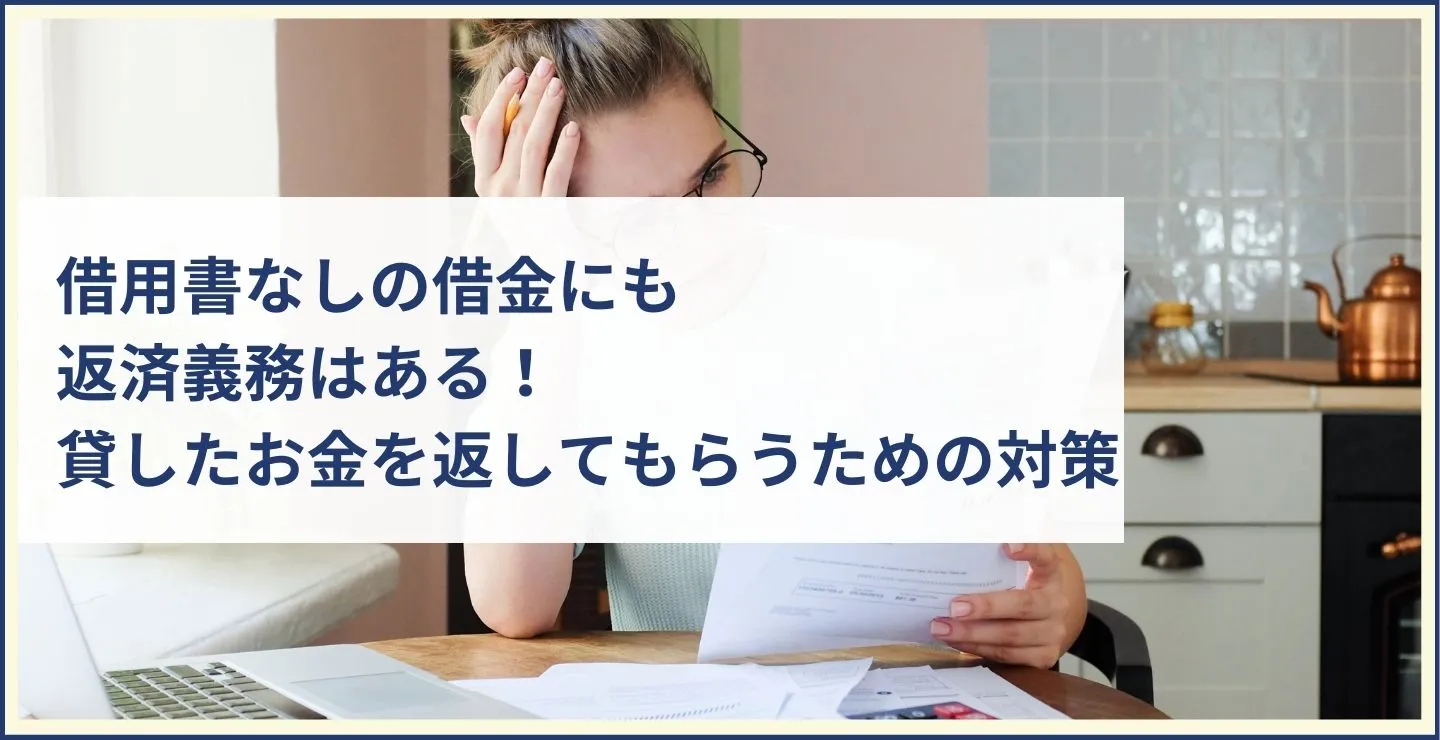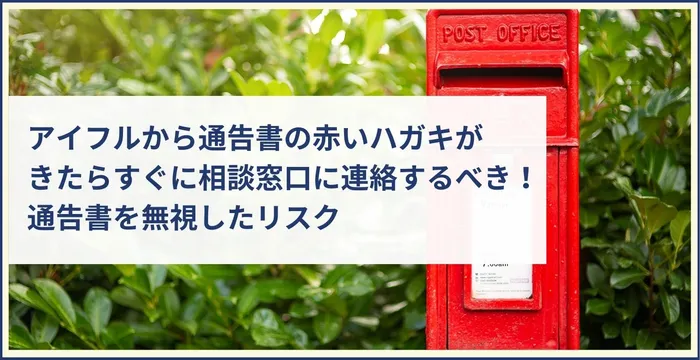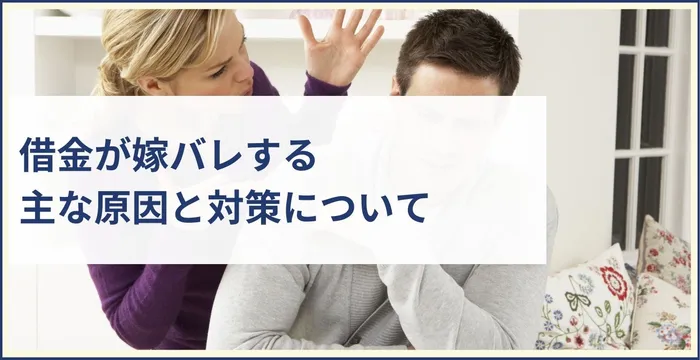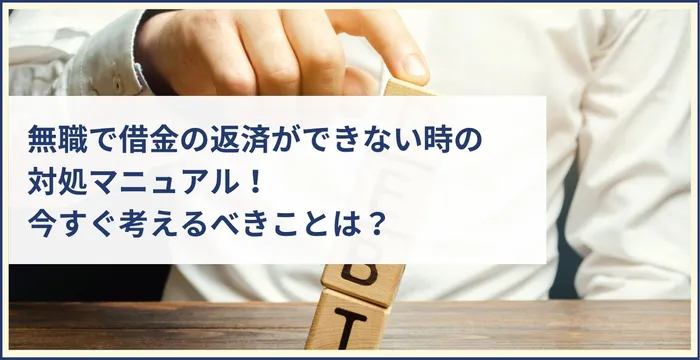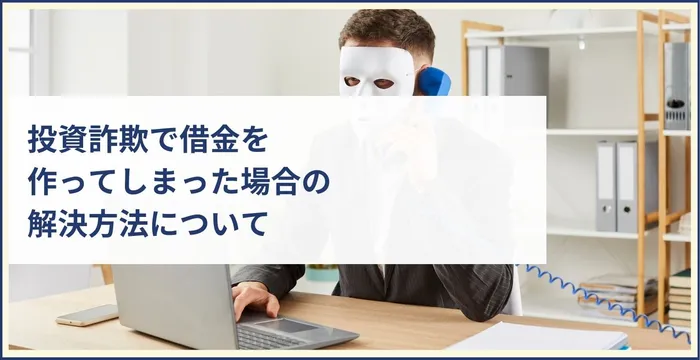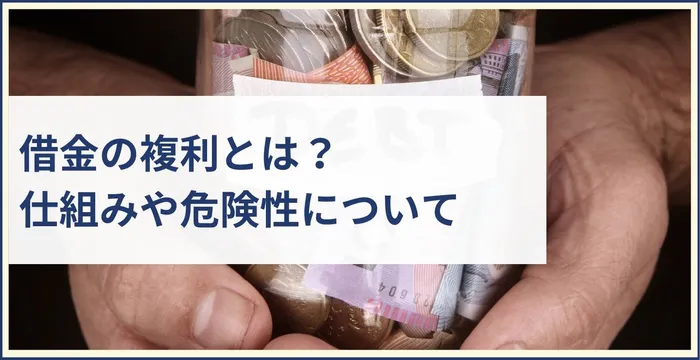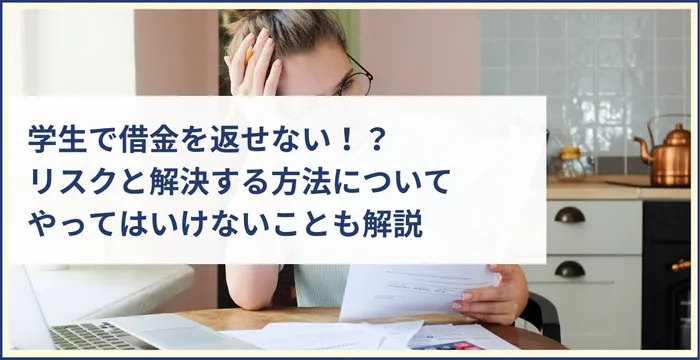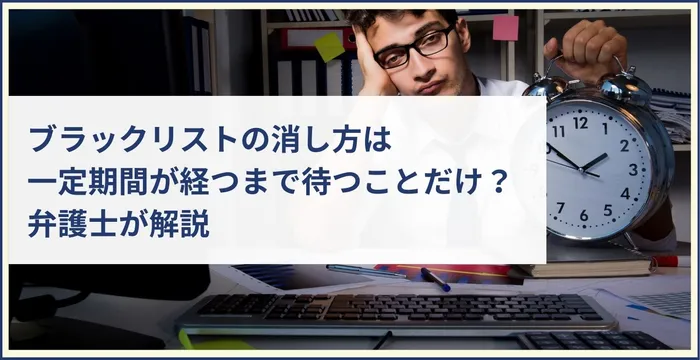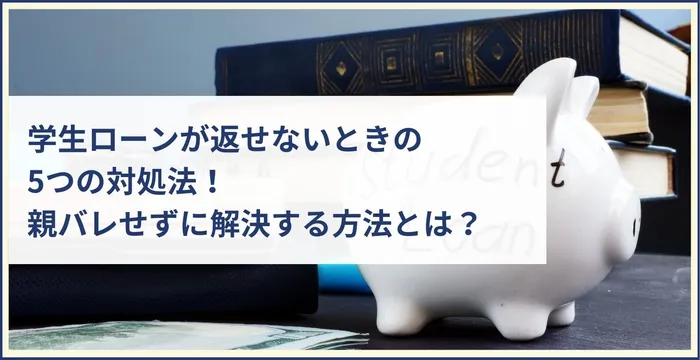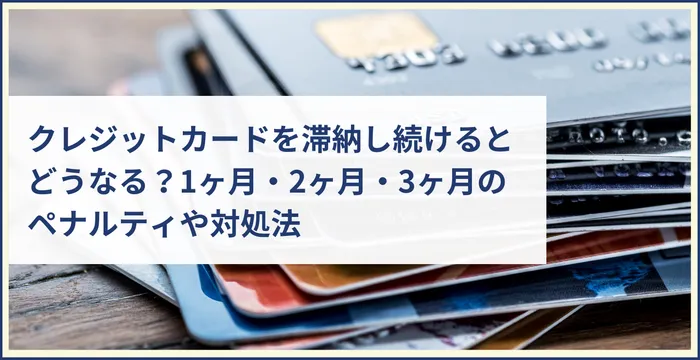借用書なしでも借金の契約は成立するため借用書が絶対に必要というわけではない
結論からいえば、借用書を作成しておらず、口約束でお金の貸し借りをした場合であっても借金の契約は成立し、この契約のことを「金銭消費貸借契約」といいます。
金銭消費貸借契約とは、借り手がお金を借りた場合、その金額を貸し手に返済する契約のことです。簡単にいえば、「借りたお金は将来的に返済します」という契約となります。
金銭消費貸借契約は、お互いの合意のうえ金銭の貸し借りが実際に行われることで成立します。そのため、借用書がなかったとしても、借り手には返済義務が生じ、貸し手は借り手に対して貸した金額の返済を請求できるのです。
とはいえ、借り手がお金を借りた事実を認めない場合、金銭消費貸借契約が成立しているかが曖昧になるため、貸したお金を取り戻すのが難航すると予測されます。
借用書はあくまで金銭消費貸借契約を証明するための書類
「借用書を作成しなかったら貸し借りがあったこと自体なかったことになるのでは?」と考える人もいるかもしれません。
前述したように、お互いの合意があったうえで金銭の貸し借りが実際に行われていれば、金銭消費貸借契約は成立します。そのため、個人でお金の貸し借りをする際には、必ず借用書を作成しなければならないというわけではありません。
個人でお金の貸し借りをする際、口約束では貸し借りの内容を証明するのが難しくなります。貸したお金や返済期日などを書面に残し、その条件にお互いが同意をしたうえで貸し借りがあったことを証明できるように借用書は作成されます。
お金の貸し借りがあった事実を証明する際には、どのような証拠であっても問題ありません。つまり、あくまで借用書は「作成しておけばお金の貸し借りがあった事実を証明しやすくなる」という立ち位置の書類です。
借用書がなくてもほかに証拠があれば、お金を貸したという事実を証明できます。
借用書なしの借金を取り戻すには貸し借りを裏付ける証拠が必要
前述したように、借用書がなくてもほかに証拠があれば、お金を貸したという事実を証明できます。そのため、「お金は借りていない」「返済期日は決めていない」などと借り手が主張している場合、ほかの証拠を集めることでお金の貸し借りがあった事実を証明できます。
お金の貸し借りがあった事実を証明するには、「借り手が実際にお金を受け取ったこと」「返済する約束があったこと」を裏付ける証拠が必要です。
借用書であればこれらすべてが書面に残っているため基本的には1つで事足りますが、借用書がない場合には複数の証拠を集めておくのが得策です。そのため、借用書なしの借金を取り戻したい場合、下記のような証拠を可能な限り集めておくとよいでしょう。
- メールやLINEのメッセージ
- 振込明細書や通帳の入金記録
- 会話の録音
- 友人など第三者による証言
メールやLINEのメッセージ
お金を貸した人とのメールやLINEも貸し借りを裏付ける証拠になります。
たとえば、「お金を貸してほしい」「今お金がないから返済できない」などのメッセージが残っていれば、当事者間にお金の貸し借りがあったことを推測できます。
過去のメールやLINEの内容を見返して、このようなメッセージのやり取りをしていないか確認してみましょう。
もし、このようなメッセージが残っていれば、きちんと保存して残しておくことをおすすめします。
また、該当するメッセージだけでなく前後のやり取りも必要になることがあるので、併せて残しておくとよいでしょう。
振込明細書や通帳の入金記録
お金を手渡しではなく振込みで渡した場合、ATMから発行される振込明細書や通帳の入金記録などが残っていれば、借金があることの証拠になる可能性があります。
ただし、振込明細書や通帳の入金記録はお金の受け渡しをしたという証拠にはなりますが、これだけでは贈与か貸付かの区別がつきません。
そこで、前述したメールやLINEなどのやり取りと併せることで、お金の貸し借りがあったことを証明できるのです。
会話の録音
お金の貸し借りをする時の会話を録音していれば、借金の証拠になります。
相手を信頼していると、なかなか会話を録音しておこうという気にならないかもしれませんが、借用書を要求できないのなら、少しでも証拠になるものを残しておくべきです。
こちらもメッセージの場合と同様、前後の会話も必要になることがあるので、すべての会話を録音しておくのがおすすめです。
また、録音データに手を加えてしまうと無効になるおそれもあるので、録音した音声は編集せずそのまま保存しておきましょう。
友人など第三者による証言
貸し借りを裏付ける証拠は物証だけではありません。お金の貸し借りについて知っている友人なども証人となる可能性があり、その人からの証言も証拠になり得ます。
具体的には「お金の受け渡しに立ち会った」「お金の貸し借りがあったことを聞いた」といった友人がいる場合、その人も証人になり得ます。
ただし、あくまで補完的な証拠であるため、第三者による証言だけでは貸し借りを裏付ける証拠にならない可能性があります。お金を貸した証拠を集める際には、第三者の証言以外にも証拠を集めておくとよいでしょう。
返済してくれない相手から借用書なしの借金を回収するための対策
お金を貸した相手が、返済期日が近くなるとあれこれ理由をつけて、結局返済してくれないケースは珍しくありません。返済してくれない相手からお金を回収する場合、下記の手順をとってみてください。
- メールやLINEなどで督促をする
- 弁護士や司法書士に依頼する
- 督促状を内容証明郵便で送る
- 裁判で争い相手の財産を差押える
最終的には裁判での争いが必要になりますが、多くの場合には弁護士に依頼するのは抵抗があることでしょう。そのため、お金を貸した人に対して自身で督促を行い、貸したお金を回収するのが無難です。
メールやLINEなどで督促をする
借用書を作成していなくても、お金を貸した人には返済の意思があることも考えられます。そのため、まずはメールやLINEなどで督促を行ってみてください。
なお、相手からの返信を証拠として残せるため、督促は基本的にメールなどの文面を残せる方法が無難です。仮に対面や電話で督促をする場合、心苦しいかもしれませんが録音しておくことをおすすめします。
督促方法に注意しないと自分が不利になる可能性がある
場合によっては、お金を貸した人に対して強く返済を求めたくなるかもしれません。その場合、督促方法に注意しないと自分が不利になる可能性があることを覚えておいてください。
たとえば、相手がなかなか返済してくれないからといって、脅すように取り立てたり、暴力を振るってしまったりすると、恐喝罪や暴行罪などの罪に問われる可能性があります。
そのため、自身で督促をする際には、メールやLINEで様子を見ながら相手に返済の意思があるかを確認するのがよいでしょう。万が一、相手から返済の意思が見えない場合、無理な督促は行わず、弁護士に相談するのが賢明です。
弁護士に依頼する
相手が督促に応じない場合、弁護士に依頼することも検討してみてください。
親しい人に対して督促をすることは精神的にも負担がかかる行為です。弁護士は依頼者の代理人として相手と交渉をしてくれるため、精神的な負担を減らせます。
また、弁護士に依頼することで、お金の貸し借りがあったことを証明する証拠を集めつつ、訴訟に向けた準備をしてくれます。
相手が督促に応じない場合、貸したお金を回収するには裁判での争いが必要になりますが、借用書がなくとも有力な証拠を用意できることに期待できるのも弁護士に依頼するメリットです。
督促状を内容証明郵便で送る
弁護士に交渉をしてもらっても返済の意思が見えない場合、督促状を内容証明郵便で送ることも検討してみてください。
内容証明郵便とは、その内容と郵便の受領を証明できる郵便のことです。返済を強制できる効力はありませんが、相手に対して「返済をしなければならない」と心理的な圧力を与えることもできます。
また、督促状に裁判への発展を検討していることを記しておくことも有効な手段です。
裁判で争い相手の財産を差押える
電話や書面、直接訪問などの方法で交渉しても、相手がお金の貸し借りを否定する場合は、裁判で争うことも検討するとよいでしょう。裁判で争い勝訴すれば、以降は相手が約束どおり返済しない場合、相手の財産を差押える権利を得られます。
裁判を起こすためには、訴える相手の名前・住所・連絡先(電話番号)が必ず必要です。これらの情報が分からないと、そもそも裁判所に申立てができません。
お金を貸した相手と連絡が取れなくなり居所が分からない場合は、興信所などを利用して住所などを特定するところから始める必要があります。
そのため、貸した金額が少額の場合には費用の方がかさんでしまう場合もあるので、注意してください。
なお、裁判で争い勝訴すれば、相手の財産を差押える権利を得られますが、差押える財産について裁判所が調査することはありません。そのため、相手に差押える財産があるかどうかは、自力で調査して裁判所に申告する必要があります。
たとえば、給料を差押えたい場合は、勤務先の会社名や住所が必要ですし、銀行口座を差押えたい場合は、銀行名と支店名が必要です。
もし調べても差押えできそうな財産が見つからなかった場合、裁判を起こしてもお金を回収できる見込みが薄いため、その場合には弁護士に相談してみるとよいでしょう。
借用書なしの借金にも時効がある
借用書がなくても借金の証拠を積み重ねることで、お金の貸し借りがあった事実を証明できるため、借用書がないからといって借金の返還請求を諦める必要はありません。
ただし、気をつけてほしいのが、借金には時効があるということです。時効が成立した借金はそもそも借りていた事実がなかったことになり返済義務もなくなります。
借用書のない個人間での借金にも時効は存在するので、返済を求めるなら早めの方がよいことを覚えておいてください。
個人間の借金の時効については、返済期日またはお金を貸した日によって下記のように異なります。
- 令和2年3月31日まで:10年
- 令和2年4月1日以降:5年
たとえば、返済期日を令和2年の1月と定めていた場合、借金の時効は10年となるため、令和12年(2030年)の1月を過ぎると返済義務がなくなってしまい、貸したお金を回収できなくなります。
なお、時効は「内容証明郵便などによる督促」「相手方からの借金の一部返済」といった方法で中断となります。中断された場合には、その時点から再スタートとなるため、貸したお金が時効を迎えないための対策として有効です。
時効による回収不可を危惧する場合には、「一部だけ返済してもらうように頼む」「内容証明郵便で督促をする」といった対策を講じることも検討してみてください。
家族や未成年者への借金も返済義務は生じる?
借用書のない借金のように返済義務があるのか悩むケースとして、家族間の借金や未成年者への借金などがあります。
家族間の借金なら、子供の学費や住宅ローンの頭金を両親に立て替えてもらう人も多いでしょう。また、未成年者への借金なら、出会い系サイトなどで知り合った人とお金の貸し借りをするケースもあります。
家族や未成年者への借金も、法律上の返済義務は生じるのでしょうか。次の項目から、それぞれ詳しくお伝えします。
家族間の借金でも返済義務は生じる
家族間の借金の場合、わざわざ一筆書かせるようなことはせず、口約束で済ませている人も多いのではないでしょうか。
しかし、たとえ家族間であっても、法律上は借金の返済義務が生じます。
そのため、裁判を起こして勝訴すれば、相手の財産を差押えることも可能です。
とはいえ、一度は信用してお金を貸した相手と裁判で争うのは、気持ちがいいものではないでしょう。それが家族同士であれば、なおさらです。
もしもの時のために借用書など証拠を残しておくことも大切ですが、少額ずつでもきちんと請求して(借りた側であれば返済して)いれば、そもそもトラブルは起きません。
家族だからこそ、お金の問題はきちんとしておきたいものです。
借用書なしの借金は贈与税が発生することもある
家族間でお金を貸し借りする場合、もう一つ注意したいのが贈与税の問題です。
借用書がない借金は贈与とみなされ、贈与税が課せられる場合があります。
贈与税は、1年間に110万円以上の贈与をおこなった場合、110万円を超えた分に対してかかります。
つまり1年間に贈与する額が、110万円以下であれば、贈与税はかからないことになります。
そのため、相手が家族など、借用書がなくてもきちんと返済してくれる相手だったとしても、年間110万円以上の金額を貸し借りする際は、借用書を作成するのがおすすめです。
未成年者への借金は親の承諾がないと無効
未成年者は親の承諾なしに一人で借金をすることはできません。もしも、親の承諾なしに借金した場合、親が後から取消せます。
親が借金を取消した場合、契約は最初からなかったことになり、本来であればお互いに原状回復の義務を負います。
つまり、借金の場合は借りた金額と同額を返金しなければなりませんが、未成年者がした借金を取消した場合、借りたお金は残っている金額のみ返還すればよいとされているのです。
また「未成年者が支払いをしない場合、親に支払義務が及ぶのか?」も気になるところでしょう。
基本的に、お金の貸し借りは個人と個人の契約なので、たとえ親であっても子供がした借金の返済義務を負うことはありません。
親が承諾していた借金であっても、それは未成年者が支払う前提での承諾であり、親自身が肩代わりするという意味にはならないのです。
しかし、親が子供の借金の連帯保証人(保証人)になっている場合は、子供が支払いをしない場合、代わりに返済するよう求められるので注意してください。
未成年者でも借金の返済義務が生じるケース
未成年者の場合、基本的に親が契約を取消せば借金返済義務は生じません。
しかし、例外的に未成年者で親の承諾がなくても借金返済義務を負う場合があります。
例えば、未成年者が結婚した場合には成人と同様の扱いになり、単独で借金した場合でも返済義務が生じます。
また、契約の際に未成年者がいかにも自分が成人であるかのように見せかけて、契約の相手を騙して借金した場合や、親の承諾を得ていると嘘をついて借金した場合も、返済義務が生じます。
まとめ
借用書がない借金であっても、法律上の返済義務は生じます。そのため、貸し借りを証明できる証拠を集めたうえで裁判を起こして勝訴すれば、相手の給料や銀行口座、不動産などの財産を差押えることも可能です。
とはいえ、裁判を起こすには借金の証拠をそろえたり、相手の財産について調べる必要があるため、簡単ではありません。
親しき中にも礼儀ありという言葉があるように、お金の貸し借りができるような親しい間柄だからこそ、後でトラブルにならないよう、きちんと書面で残しておくべきです。
事前に借用書を作成することで、貸した相手も「ちゃんと返済しなければいけない」という気持ちになるでしょう。
自力で相手と交渉して解決が難しい状況であれば、専門家である法律事務所に相談するのも一つの方法です。
悩んでいる人は、まずは当サイトで紹介しているような、無料相談を受け付けている事務所に相談することをおすすめします。
個人間の借金に関してよくある質問
知人にお金を貸していたのですが、借用書がないから無効だと言われました。泣き寝入りするしかないのでしょうか?
借用書がない借金でも、証拠を提示できれば借金は無効になりません。メールやLINEのメッセージ、電話の録音などを証拠として残しておきましょう。
親から借りたお金なのですが、利息をつけて返すように言われています。家族間でも利息が有効なのでしょうか?
家族間でも、利息制限法の範囲内なら利息をつけることは可能です。
親戚からお金を借りているのですが、個人間の借金でも時効は適用させられますか?
はい、個人間の借金にも時効は適用できます。時効を主張する場合は、弁護士へ時効の援用手続きを依頼するとよいでしょう。
個人間の借金でも債務整理できますか?
はい、できます。債務整理に力を入れる弁護士へ相談することをおすすめします。
STEP債務整理「債務整理に力を入れるおすすめの弁護士を紹介」
自己破産した場合、親から借りているお金も対象になりますか?
はい、なります。自己破産は個人間も含め、すべての借金が対象です。
最短即日取立STOP!
一人で悩まずに士業にご相談を
- 北海道・東北
-
- 関東
-
- 東海
-
- 関西
-
- 北陸・甲信越
-
- 中国・四国
-
- 九州・沖縄
-