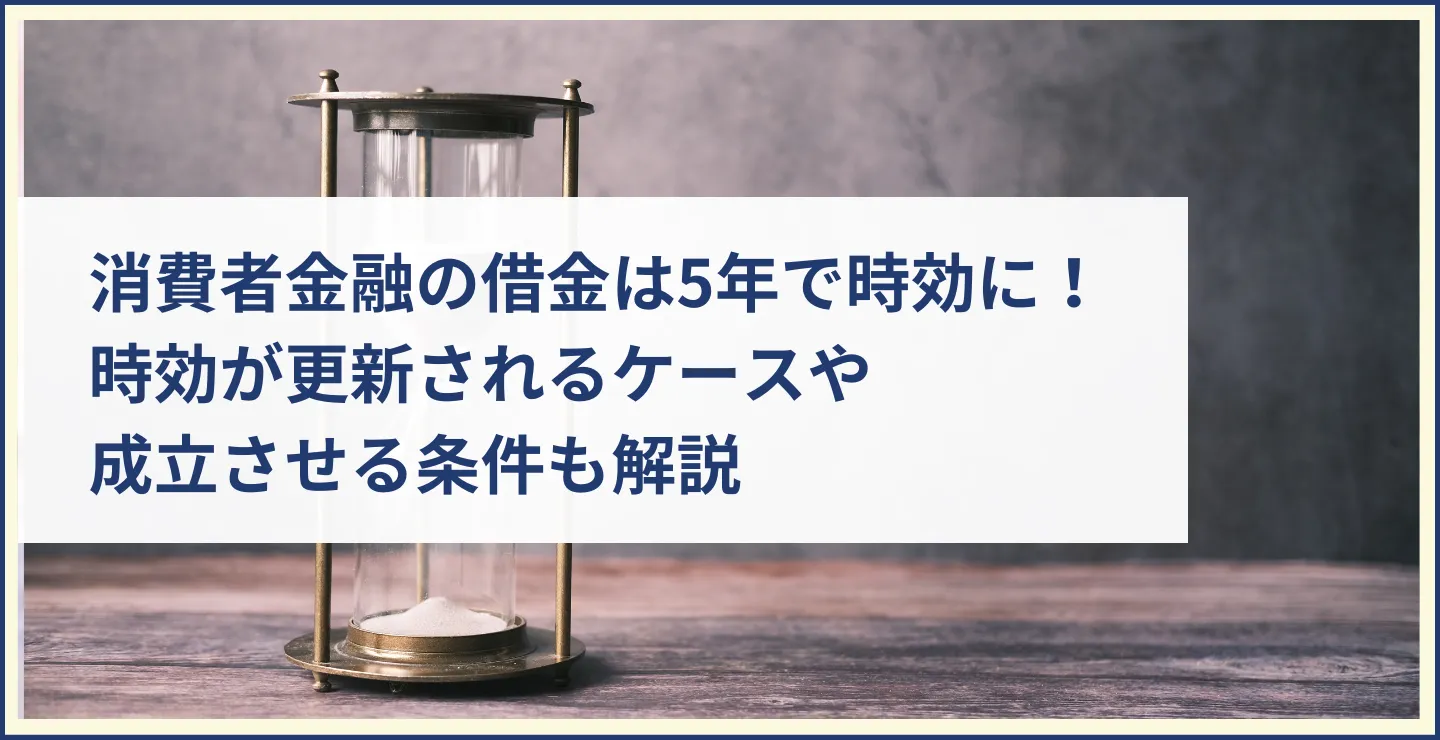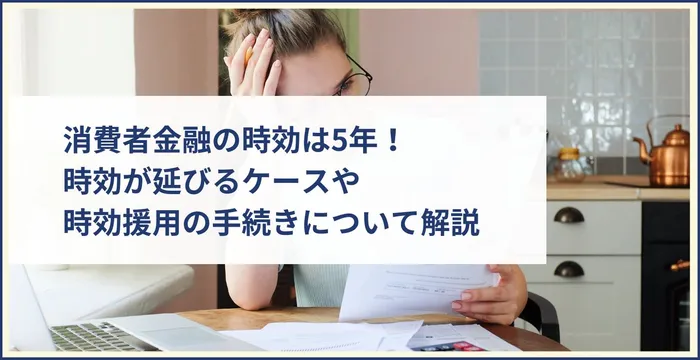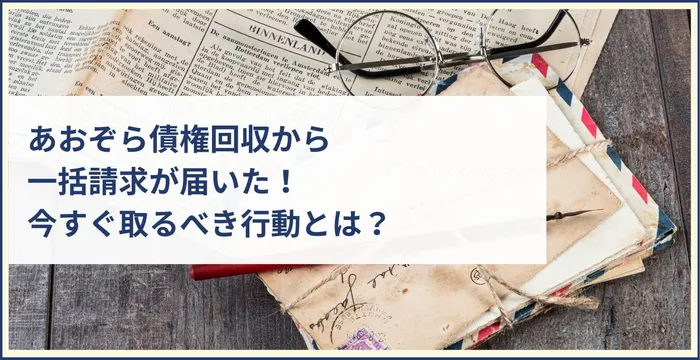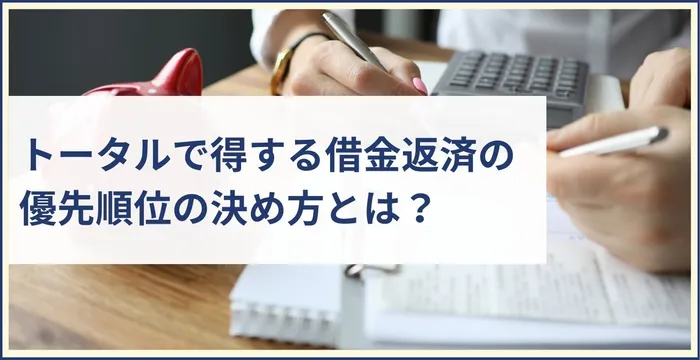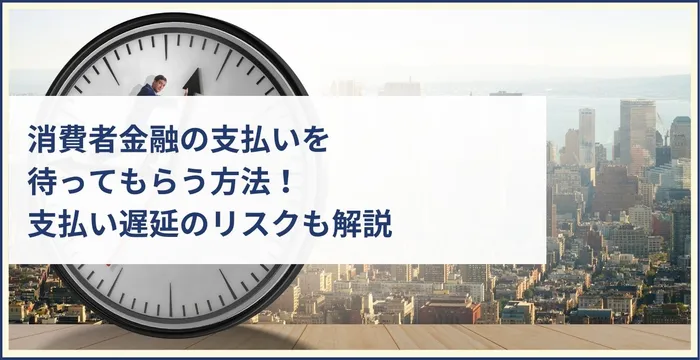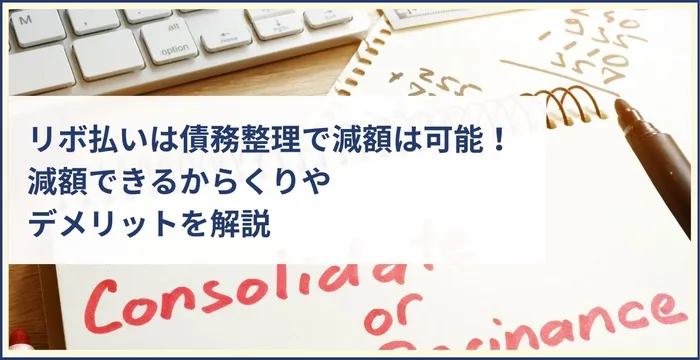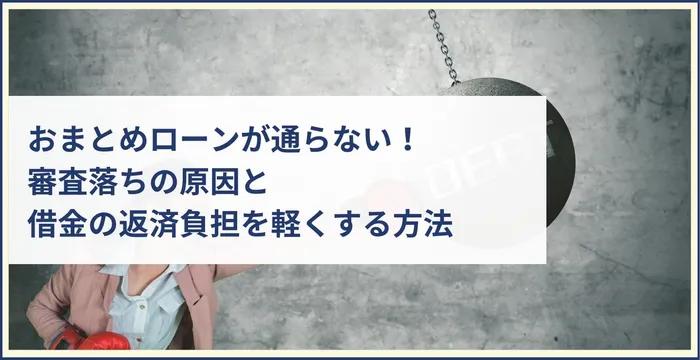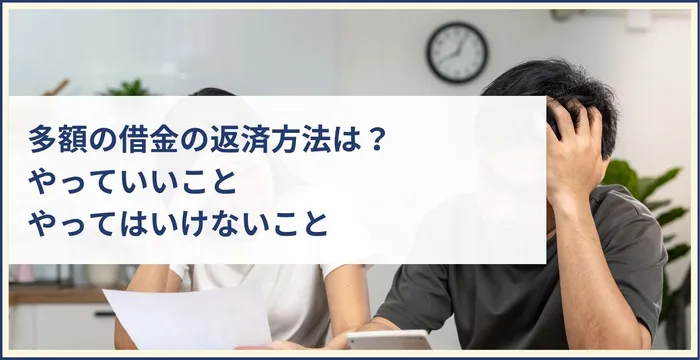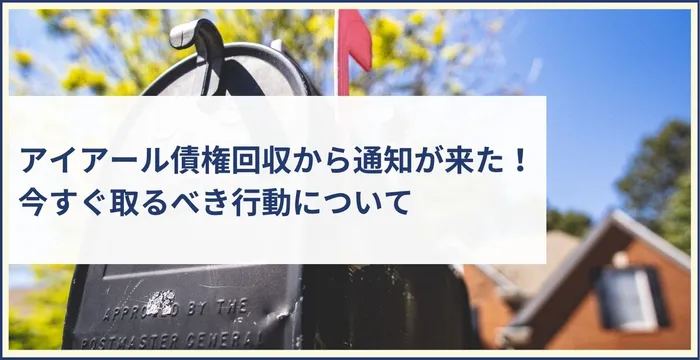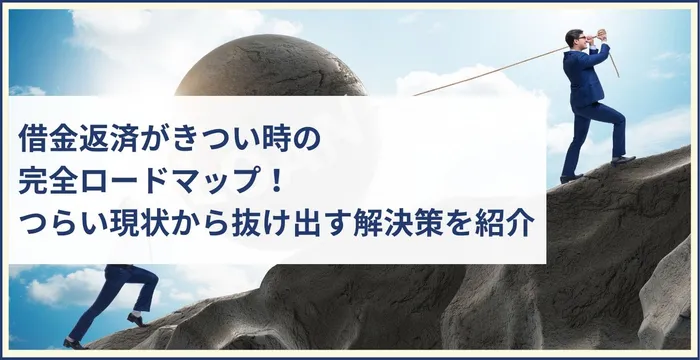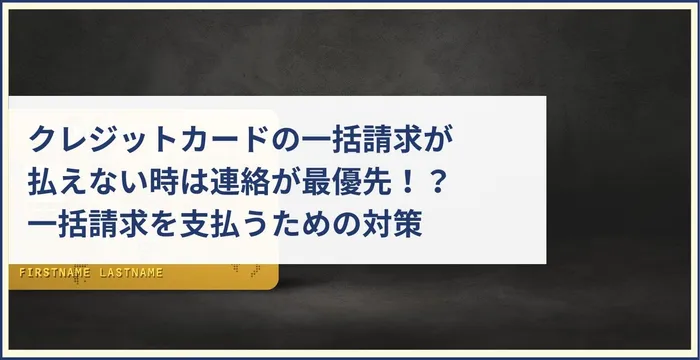消費者金融からの借金の時効(消滅時効)は基本的に5年
消費者金融からの借金は、法律上、原則として5年が経過すると、時効(消滅時効)が成立します。
消滅時効とは、一定期間が経過すると借金などの債務が法的に消滅し、返済の義務がなくなる制度です。
この制度は、債権者(お金を貸した側)が、請求できるにもかかわらず長期間放置してきた場合、その権利を保護する必要はなく、債務者(お金を借りた側)の生活の安定を守るべきという考えに基づいています。
しかし、実際には時効を成立させることは簡単ではありません。
多くの場合、債権者(借金を請求する権利がある人)が、時効の成立を阻止します。
消費者金融業者は、時効が成立する前に、督促や催告(借金の存在を通知し、支払いを求めること)を行ったり、裁判を起こしたりすることで、時効の進行を止め・リセットすることが可能です。
そのため、実際に時効を成立させるには慎重な対応が求められます。
参照:法務省|消滅時効に関する見直し
時効の起算日は借金をしたタイミングで異なる
消滅時効の起算点(時効期間の開始日)は、基本的に返済期日の翌日です。
民法第166条1項では、消滅時効について次のように規定しています。
・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき(主観的起算点)
・権利を行使することができる時から10年間行使しないとき(客観的起算点)
引用元 e-GOV法令検索|民法第166条1項
つまり、借金の請求ができることを知ってから5年間、あるいは借金の返済日から10年間いずれか早い期間が経過すれば消滅時効が完成します。
とはいえ、通常、消費者金融業者が借金の回収ができることを知らないことはないため、基本的には、返済期日の翌日から5年間で消滅時効が完成すると考えられます。
2020年3月31日以前の契約には改正前の民法を適用
なお、2020年4月1日に民法が改正され、2020年3月31日以前と2020年4月1日以降の取引では、消滅時効の起算日や時効完成までの期間が異なります。
次の表は、民法の改正前後で消滅時効制度の違いを比較したものです。
民法改正前後の消滅時効の違い
| 借金の種類 |
民法改正前
(2020年3月31日以前の取引) |
民法改正後
(2020年4月1日以降の取引) |
・消費者金融
・金融機関 |
権利を行使できる時から5年 |
権利を行使できると知った時から5年
または権利を行使できる時から10年 |
・信用金庫
・住宅金融支援機構の住宅ローン
・親族や友人からの借金
・奨学金 など |
権利を行使できる時から10年 |
権利を行使できると知った時から5年
または権利を行使できる時から10年 |
改正前は「権利を行使できる日」という客観的起算点のみが基準でしたが、改正によって「権利を行使できることを知った日」という主観的起算点が導入されました。
また、改正前は、借金の種類によって消滅時効が完成するまでの期間に違いが設けられていましたが、改正後は、借金の種類に関係なく統一されました。
消費者金融の時効が成立する条件は主に2つ
消費者金融の借金を時効で消滅させるためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 1.時効が完成する年数が経過していること
- 2.時効援用の手続きを行っていること
1.時効が完成する年数が経過していること
消費者金融で最後に取引をした日から5年経過していなければなりません。
ただし、単に5年間経過すれば自動的に時効が成立するわけではありません。その間に、時効を更新(リセット)する理由がないことも必要です。
時効の更新
時効の進行がリセットされて、新たにカウントが始まる制度
たとえば、時効期間が進行する途中で、たとえ1円でも返済した場合、「今後も支払います」という意思表示とみなされます。
その結果、その日が最後に取引した日(最終返済日)として、改めてその時点から5年をカウントすることになります。
また、債権者が支払督促や裁判上の請求を申し立て、支払督促や判決が確定した場合も時効期間がリセットされます。
2.時効援用の手続きを行っていること
時効が成立し、借金の返済義務をなくすためには、期間の経過だけでなく時効援用の手続きを行う必要があります。
時効援用とは、「この借金は時効が成立しているため支払いません」と正式に主張する手続きです。
具体的には、消費者金融に、内容証明郵便で「時効が成立したため返済義務がない」ことを通知します。
時効の援用手続きを行わなければ、たとえ時効期間が経過していても、借金の支払い義務はなくなりません。
確実に返済義務をなくすために、弁護士や司法書士など専門家に相談することをおすすめします。
消費者金融の借金について時効のカウントがリセット・中断される4つのケース
消費者金融の借金は、原則として5年を経過すると時効を迎える可能性があります。
しかし、途中で特定の行動によって時効の進行がリセット(中断) されることがあります。
ここでは、時効のカウントがリセット・中断される4つのケースを解説します。
- 消費者金融から支払督促が届いた|時効期間の進行が6か月間止まる
- 借金を少しでも返済した|時効のカウントがリセットされる
- 返済する意思を少しでも示した|時効のカウントがリセットされる
- 裁判を起こされた|時効のカウントがリセットされる
消費者金融から支払督促が届いた|時効期間の進行が6か月間止まる
消費者金融業者から裁判所を通じて「支払督促」が届いた場合、時効期間の進行が 6か月間停止します。
これを「時効の完成猶予」といい、当事者間で協議を行う旨の合意をした場合は最大1年間停止します(民法第151条)。
「支払督促」は、申立人(債権者)の申立てのみに基づいて、簡易裁判所の書記官が相手方に金銭の支払いを命じる制度です。調停や訴訟と異なり、書類審査のみで迅速に行えます。
債務者が内容証明郵便で支払督促を受け取ることで、「消費者金融から支払いの督促を受けた」と判断され時効期間の進行が停止します。
内容証明郵便
一般書留郵便物の内容を郵便局が郵便物の内容、受付日を証明するサービス。
差出人や宛先の記録だけでなく、法律上の意思表示を証拠として残すことができます
参照:e-GOV法令検索|民法第151条
借金を少しでも返済した|時効のカウントがリセットされる
借金の一部を返済すると、債務(借金)の承認とみなされ、それまでの時効のカウントがリセットされます(民法第152条)。これにより、新たに5年間の時効期間がスタート します。
たとえば、消費者金融業者から「少しでも返済すれば、借金の支払い意思があると認める」と言われ、数千円でも振り込んでしまう場合などです。
たとえ1円でも借金を返済すると、「借金の存在を認めた」と判断され、時効はリセットされます。
参照:e-GOV法令検索|民法第152条
返済する意思を少しでも示した|時効のカウントがリセットされる
債務の一部を返済した場合だけでなく、返済する意思を示した場合も「債務の承認」とみなされ、時効のカウントがリセットされる可能性があります。
債務の承認とみなされる意思表示の例として次のものがあります。
- 今は支払えないので数日待ってください
- 来月には一部返済できます
- 残高確認書や返済計画書に署名した
- メールやLINEで「少し待ってください」と伝えた など
これらの行為は、すべて債務の存在を前提とする行為であり、債務の承認とみなされる可能性があります。
家への訪問や電話で返済の督促を受けた場合、その場を切り抜けようと、とっさに「少し待ってほしい」など、支払いする意思を示してしまうこともあります。
このような状況でも債務を承認したことになり、意図せず消滅時効がリセットされてしまう点に注意が必要です。
裁判を起こされた|時効のカウントがリセットされる
消費者金融が裁判を通じて返済を求めてきた場合、時効のカウントはリセットされ、振り出しに戻る可能性があります。
具体的には、債権者が裁判を起こすと、訴訟を提起した時点で時効の完成は猶予されます(民法第147条)。
さらに、裁判で返済義務を認める判決が確定した時点で、新たに時効期間はリセットされます。
また、裁判だけでなく支払督促の申立ての手続きでも、時効がリセットされる可能性があります。
●支払督促に異議申し立てをしなかった場合の流れ
- 支払督促を受け取る(時効期間の進行が6か月間停止)
- 異議申し立てをしないと、「仮執行宣言付支払督促」が送付される
- 「仮執行宣言付支払督促」にも2週間以内に異議申し立てをしないと支払督促が確定
この時点で時効のカウントがリセットされ、新たに5年の時効期間がスタートします。
仮執行宣言付支払督促
支払督促の手続きに仮執行の効力を付与したもの。
これにより、債権者は強制執行の手続きに移行でき、債務者の財産や給与を差し押さえることができます。
参照:e-GOV法令検索|民法第147条
消費者金融の借金を時効援用する手続きの流れ
借金の時効期間が経過しても、時効を援用しなければ返済義務は消滅しません。
ここでは、時効援用の手続きについて解説します。
- 1.時効期間の経過確認
- 2.時効援用通知書の作成・送付
- 3.債権者の確認
- 4.時効の成立
1.時効期間の経過確認
まず、借金が時効を迎えているかを確認することが重要です。
5年あるいは10年の時効期間が経過していても、途中で債権者から支払督促や裁判上の請求を受けていた場合、時効期間が中断・リセットされている可能性があります。
次の表は、時効期間の経過を確認する方法をまとめたものです。
| 確認方法 |
内容 |
| 契約書・督促状などで確認する |
契約書や請求書、取引履歴から借金の返済期日や最終返済日を調べます。督促状や催促の通知が届いているときは、最新の文面で最終返済日や最終期日を確認します。 |
| 個人信用情報機関に開示請求する |
返済期日や最終返済日がわからない場合は、個人信用情報機関に取引情報を開示請求します。個人信用情報機関には、本人を識別する情報のほか契約内容や返済状況に関する情報が登録されています。 |
| 消費者金融業者に問い合わせる |
消費者金融事業者に直接問い合わせる場合は、時効援用の意思を伝えないように注意が必要 |
| 専門家(弁護士・司法書士)に相談する |
弁護士や司法書士が本人の代理人として取引履歴の開示請求をすることも可能ですが、時効援用の意思が伝わらないように行う必要があります。 |
時効期間の経過を確認すると同時に注意しなければならないのが、確定判決や債務の承認で時効が更新されていないかという点です。
消費者金融業者が訴訟や支払督促を申し立て確定している場合、時効期間はリセット(更新)されています。
通常、判決書などは自宅宛てに送達されますが、中身を開けずに破棄していたり、転居届を出さずに引越ししている場合、知らないうちに時効期間がリセットされている可能性があります。
また、借金の一部を返済していた場合、債務の承認にあたり時効期間は更新されるため、記憶をしっかりと思い出すことも大切です。
個人信用情報機関は、個人のクレジットやローンの契約・返済状況などの情報(信用情報)を収集・管理する機関です。金融事業者は、信用情報に基づいて融資や貸付けの可否を判断します。
日本には主に以下の3つの個人信用情報機関があります。
・株式会社シー・アイ・シー(CIC):主にクレジットカード会社や信販会社が加盟
・株式会社日本信用情報機構(JICC):主に消費者金融やクレジット会社が加盟
・全国銀行個人信用情報センター(KSC): 全国銀行協会が運営し、主に銀行が加盟。
2.時効援用通知書の作成・送付
時効期間が経過していると確認できれば、時効援用通知書を作成し、消費者金融業者へ送付します。
時効援用通知書は、消滅時効を利用し、債務が消滅した旨を債権者に通知するための書類です。
口頭での通知は、言った言わないの水掛け論になる可能性があるため、時効援用通知書を作成し内容証明郵便で送付することが一般的です。
時効援用通知書の書式に決まりはありませんが、次のような情報を盛り込みます。
- 作成日・発送日
- 債権者の住所・会社名
- 自分の住所・氏名・生年月日
- 消滅時効を主張する意思表示
- 契約を特定できる事項(契約番号など)
- 信用情報の削除・訂正の依頼など
3.債権者の確認
時効援用通知書を受け取った消費者金融業者は、時効期間が経過しているかどうかを確認します。
時効期間が経過している場合、通常は借金が消滅しますが、もし時効期間が経過していない場合、債権者から一括請求や法的措置を取られるリスクもあります。
時効期間の計算ミスや過去に時効が中断・リセットされていた可能性もあるため、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。
4.時効の成立
債権者が時効期間の経過を認めた場合、正式に借金の返済義務がなくなります。
このとき、債権者から借金がないことの証明となる「債務不存在証明」が届くことがあります。
証明書が届かない場合は、時効援用が認められたことを確認する書面を、内容証明郵便で送付しておくとよいでしょう。
万が一、消滅時効が完成しているにもかかわらず、消費者金融業者が時効を認めない場合や請求を続ける場合は、弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
消費者金融の借金を時効まで待ち続ける6つのリスク
消費者金融の借金が時効で消滅する可能性があるとはいえ、何もしないで待ち続けることには大きなリスクもあります。
ここでは、時効を待ち続けることで起こりうる6つのリスクについて詳しく解説します。
- 1.遅延損害金がかさむ
- 2.信用情報についた傷が残り続ける
- 3.裁判を起こされるリスクがある
- 4.消費者金融からの督促は続く
- 5.過払金請求をし逃すリスクがある
- 6.勤務先に借金がバレる可能性が高まる
1.遅延損害金がかさむ
借金の時効完成を待つことは、長期間、返済を滞納することを意味します。
そのため、遅延損害金がどんどん膨らんでいきます。
遅延損害金とは、返済期日を過ぎても支払いが行われない場合に発生するペナルティのようなもので、通常は年率が最大20%(元本100万円以下の場合)と高い利率が設定されることが一般的です。
時効が成立すれば、遅延損害金を含めて支払う必要はありませんが、成立しなかった場合は、元本に利息、さらに遅延損害金をすべて支払う必要があります。
例えば、50万円の借金を5年間放置した場合、遅延損害金だけで50万円近くになる可能性があります(50万円×20%×5年)。
つまり、時効完成を待って滞納を続けることは、結果的に、借金の総額が2倍に膨らむリスクがあるわけです。
2.ブラックリストに入り続ける
借金を返済せず時効の完成を待ち続ける間、個人信用情報機関に事故情報が登録される、いわゆる ブラックリスト入りの状態になります。
ブラックリストとは、信用情報機関に事故情報が登録された状態を指す俗称で、実際に「ブラックリスト」という名簿が存在するわけではありません。
ブラックリストに載ると金融事業者からの信用を失い、少なくとも完済から5年間はローンを組んだり、クレジットカードを利用することはできません。
ブラックリストに載り続けることで、次のような影響があります。
- クレジットカードの新規発行できない・使えない
- 住宅ローンやカーローンの審査が通らない
- スマホ・携帯電話の分割購入ができなくなる
- 賃貸住宅の審査が厳しくなる
- ローンや奨学金の保証人になれない など
クレジットカードの新規発行ができない・使えない
ブラックリストに載ると、基本的にクレジットカード新規発行はできず、利用中のクレジットカードも利用できなくなります。
これは、カード発行時の審査で信用情報を照会されるためで、事故情報が登録されている状況で審査に通ることはありません。
また、利用中のクレジットカードも滞納してすぐに使えなくなるとは限りませんが、クレジットカード会社が信用情報を確認した時点で使えなくなります。
なお、ブラックリストに載っている状態でも、口座から直接お金を引き落とすデビッドカードや現金チャージ型の電子マネーなどは利用可能です。
住宅ローンやカーローンの審査が通らない
ブラックリストに載っている間は、家や車をローンを利用して購入することはできなくなります。
融資を行う際、金融機関やローン会社は信用情報を必ずチェックします。特に、融資金額も多く、返済期間が長くなる住宅ローンやカーローンの場合、返済能力の審査は厳しくなります。
なお、家や車のローンをブラックリスト入りしている家族の名義で組むことは可能です。ブラックリストに載っている人の配偶者や親などのローン契約まで影響することは基本的にありません。
スマホ・携帯電話の分割購入ができなくなる
ブラックリストに入ると、スマートフォンや携帯電話端末を分割購入できない可能性が高くなります。
これは、分割購入(割賦購入契約)では、契約時に信用情報の照会が行われるため、事故情報が付いていると審査に通らないためです。
対処法としては、一括払いで購入できる機種を探す、あるいはプリペイド携帯やレンタル携帯を利用するなどの方法を考えることが必要になります。
賃貸住宅の審査が厳しくなる
ブラックリストに入っていると、住宅ローンが組めないだけでなく、賃貸住宅の契約ができないケースもあります。
マンションやアパートを借りる際に保証会社の利用を求められる場合がありますが、保証会社は、借主の返済能力を確認するための審査を行います。この時、信用情報に事故情報があると賃貸契約は難しくなります。
特に、保証会社が信販系の会社である場合、入居審査で信用情報の照会を必ず行うため、支払い能力に問題ありと判断されれば借りることはできません。
対処法としては、信用情報機関に加盟していない保証会社を探す、あるいは連帯保証人を立てたり、UR賃貸や公営住宅を検討するなどが考えらえます。
ローンや奨学金の保証人になれない
ブラックリストに載っている間は、ローンや奨学金の保証人になることはできません。
保証人の役割は、債務者(お金を借りている人)が返済できなくなったときに代わりに支払うためです。
そのため、ブラックリストに載っている間は、子どもが部屋を借りる際の賃貸借契約や奨学金の保証人になることはできないと考えておいたほうがよいでしょう。
対処法としては、一定の収入がある家族や親戚に頼むか、奨学金であれば機関保証を検討する必要があります。
このように、ブラックリストに入り続けることは、日常の生活だけでなく、家や車を購入する、あるいは子どもの進学などのライフイベントにも影響することになります。
消滅時効の完成を待ち続けるとしても、長期の視点で自分だけでなく家族への影響も含めてリスクを考えることが必要です。
3.裁判を起こされるリスクがある
滞納期間が長くなるほど、消費者金融業者からさまざまな取り立てや督促を受けることになります。
もし、債務者に裁判を起こされた場合、以下のようなリスクがあります。
- 確定判決が出ると時効が10年に延びる
- 財産を差し押さえられる可能性がある
確定判決が出ると時効が10年に延びる
消費者金融業者から裁判を提起されると、時効の進行が中断されます(民法第147条1項1号裁判上の請求)。
この時点で、その裁判手続きが終了するまでの間、時効の完成が猶予されます。
また、裁判を提起した結果、消費者金融業者の訴えが認められ、確定判決、あるいは確定判決を同一の効力を有するもので権利が確定すると、手続きが終了した時点で時効が更新されます(同条2項)。
つまり、滞納を続けている以上裁判で争うことは難しく、訴訟を提起された確定した時点で時効期間がリセットされるリスクがあるわけです。
さらに、裁判上の確定判決によって確定した権利については、時効期間に10年より短い定めがある場合でも、時効期間が10年となります(民法第169条1項)。
そのため、裁判を提起されると、裁判の終了から新たに10年の消滅時効期間がスタートすることになり、事実上時効での借金帳消しが困難になるといえます。
参照:e-GOV法令検索|民法第147条・169条
財産を差し押さえられる可能性がある
また、消費者金融側が裁判で勝訴すると、強制執行の手続きにより、財産や給与が差し押さえられる可能性があります。
たとえば、確定判決が出てから給与を差し押さえるまでの流れは次のとおりです。
- 裁判を起こし勝訴判決を得る
- 判決を基に、消費者金融が裁判所に強制執行を申し立てる
- 裁判所が債務者と勤務先の会社に債権差押命令を送付する
- 会社は裁判所の命令に従い、債務者の給料の一部を差し押さえる
- 差し押さえた給料を会社から債権者に支払う
また、差し押さえの対象となる財産には、以下のようなものがあります。
| 強制執行の対象となる財産 |
内容 |
| 預貯金の差し押さえ |
債務者の銀行口座が差し押さえられ、預金を引き出せなくなります。 |
| 給与の差し押さえ |
債務者の勤務先に対して給与の差し押さえ命令が出され、給与の一部が強制的に回収されます。
民事執行法第152条により、手取り額の4分の1までが差押え可能。ただし、手取り額が44万円を超える場合、33万円を超える部分が差押えの対象となります。 |
| 動産・不動産の差し押さえ |
動産では、現金・車・有価証券・宝石など、不動産では、土地・建物が対象。ただし、不動産の差押えには、競売など手続に費用と時間を要するため、換金しやすい他の財産から差し押えられるケースが多くなります |
1度強制執行の手続きを取られてしまうと、基本的に債務者から手続きを止めることはできません。
強制執行になると、財産や生活に深刻な影響を及ぼすため、借金の返済で悩んでいる場合は、早めに弁護士や司法書士の専門家へ相談し、適切な対応を取ることをおすすめします。
4.消費者金融からの督促は続く
借金を滞納している間、消費者金融業者は、時効の完成を阻止し、借金を回収するために督促を続けるでしょう。
特に時効完成が近づくと、より積極的な取り立てが行われることがあり、精神的な負担も大きくなります。
貸金業法では、債権者が債務者に対して行う取り立て方法について定めており、次のものがあります。
- 電話や面会による取り立て
- 内容証明郵便を送付する取り立て
- 訴訟や強制執行による取り立て
- 連帯保証人や保証人への取り立て
深夜や早朝の電話・訪問などの取り立ては禁止されていますが、督促が続くことで精神的なストレスは大きくなります。
家族や職場に借金が発覚するリスクも高まるため、無視し続けることは危険です。
さらに、債権者から裁判所を通じて支払督促が届いた場合は、時効の進行が6か月間ストップ し、その間に裁判を起こされた場合、時効はリセットされる可能性があります。
5.過払金請求をし逃すリスクがある
かつて、利息制限法を超える高金利(いわゆるグレーゾーン金利)で貸付けを行っていた消費者金融は少なくありませんでした。
グレーゾーン金利とは、利息制限法と出資法の上限金利の間の金利をいいます。
金利の上限を定めたこの2つの法律のうち、利息制限法では金利の上限を15~20%と定め、出資法では上限を超えた場合に刑事罰の対象となる金利を29.2%と定めていました。
そのため、利息制限法の上限を超えていても、出資法の上限を超えない限り刑事罰は科せられず、長年、貸金業者は、この「グレーゾーン金利」による金利を設定し違法な金利を取っていました。
このような高金利で借り入れをしていた場合、本来支払う必要のなかった利息、つまり過払金を取り戻せる可能性があります。
しかし、過払金請求には、時効完成を目指して借金を放置している場合、リスクが伴います。
なぜなら、過払金を確認するためには、消費者金融に取引履歴の開示を求める必要があり、その請求をきっかけに借金の存在を債務者自身が認めたとみなされ、消滅時効がリセットされてしまうおそれがあるからです。
さらに、過払金の返還請求権も、最終取引日から10年で時効により消滅します。
つまり、時効完成を待ち続けている間に、本来返還を求められる過払金の請求権まで失ってしまうリスクがあるのです。
消滅時効の成立を狙う場合でも、過払金の有無や請求のタイミングには十分な注意が必要です。
6.勤務先に借金がバレる可能性が高まる
借金を滞納し続けていると、借金の回収のため、消費者金融から勤務先に連絡することがあります。
通常、業者は本人に連絡を取ろうとしますが、電話に出ない・住所不明などの状況が続くと、勤務先に連絡が入り、借金がバレる可能性が高まります。
勤務先に連絡がいくケースとして次のものがあります。
- 本人の連絡が取れない場合
- 保証人や緊急連絡先が会社の同僚などの場合
- 法的措置(給与差し押さえ)が取られた場合
消費者金融業者は、勤務先に督促の連絡をする際、会社名や用件を名乗ることはありません。これは、法律上本人の借金に関する事実をほかの人に話すことが禁じられているためです。
ただし、「〇〇様はいらっしゃいますか?」「至急連絡をいただきたいのですが…」といった連絡が勤務先に入ることになります。
家族以外の人から直接会社宛てに連絡が入り、会社名も用件も名乗らないとなれば、同僚や上司に不信感を抱かれる可能性は高いでしょう。
また、消費者金融業者が裁判で勝訴すると、確定判決をもとに裁判所に強制執行を申し立て、給与を差し押さえることができます。
このとき、会社の経理担当者宛に裁判所から通知が届き、給与の一部が天引きされます。会社は裁判所の指示に従う義務があり、借金の事実が職場に知られることになります。
消費者金融の借金に困ったら、弁護士に相談して債務整理も検討しよう
ここまで紹介したように、消滅時効を待つことはさまざまなリスクやデメリットが伴うため、安易に進めることは危険です。消費者金融の借金の返済が困難な場合、弁護士に相談することがおすすめです。
借金問題に精通した弁護士であれば、借金や収入、生活の状況を踏まえて、最適な対応方法を提案してもらえます。
ここでは、消費者金融の借金を減額・免除できる3つの方法を解説します。
- 任意整理|元本だけなら返済できる人
- 個人再生|借金を減額したい人
- 自己破産|借金が大きすぎて返済できない人
任意整理|元本だけなら返済できる人
任意整理は、裁判所を通さずに消費者金融業者と直接交渉し、借金の減額や返済条件を提示し・合意を目指す手続きです。
利息のカットや返済期間の延長を交渉し、無理のない返済計画を立てることを目指します。
●任意整理のメリット・デメリット
| メリット |
デメリット |
・毎月の返済額を減額できる
・将来利息がカットされ、返済総額が減る
・裁判所を通さずに手続きが進めやすい
・特定の借金のみを整理できる(住宅ローンや車のローンを除外可能)
・財産を処分せずに済むため、生活への影響が少ない
・比較的短期間(3〜6ヶ月程度)で完了する
・債権者からの請求。督促が止まる |
・元本の返済義務は残る
・信用情報に傷がつき、最低5年間はクレジットカードやローンの審査に通らない
・債権者(消費者金融)によっては交渉に応じない場合がある
・税金や社会保険料などの公的な支払いは整理できない
・交渉を依頼するための弁護士費用や司法書士費用が発生する |
任意整理の最大のメリットは、利息カットや返済回数の見直しで毎月の返済額を減らせることです。交渉次第では、滞納期間中の遅延損害金もカットできる可能性があります。
また、任意整理を行う過程で過払い金の有無を確認します。これまで払い過ぎていた利息がある場合は、戻ってきた過払い金を元金の返済に充て、返済負担を軽くすることが可能です。
一方、任意整理は元本の返済義務は続き、他の債務整理の方法と比べると借金の減額幅は小さくなります。
また、あくまでも債権者との交渉であるため、合意できなければ元の条件で返済を続けるか、裁判所を介した手続きを検討する必要があります。
個人再生|借金を減額したい人
個人再生は、裁判所を通じてすべての債権者の借金を大幅に減額し、残額を原則3〜5年で分割返済する再生計画を認めてもらう手続きです。
また、住宅ローンがある場合、自己破産と異なり、一定の用件を満たすことで家を維持しながら借金を整理できる点が特徴です。
●個人再生のメリット・デメリット
| メリット |
デメリット |
・借金を元本の5分の1から10分の1に減額できる
・住宅ローンを残したまま借金を整理できる
・借金の原因に制限がない
・3~5年の返済計画で完済を目指せる
・自己破産のような、弁護士や公務員などの職業制限がない |
・手続きに時間がかかる(半年〜1年程度)
・手続きする債務を選べない
・事故情報として登録され、完済から5~7年間ローンやクレジットカードが利用できない
・継続的な収入が必要(無職や不安定な収入では利用不可)
・借金の減額幅に制限がある( 例えば、100万円以下の借金は減額されない可能性がある)
・保証人付きの借金を整理すると、保証人に請求がいく可能性がある
・官報に氏名・住所が掲載される
|
個人再生のメリットは、生活の基盤となる家を残しながら、借金を大幅に減額できる点です。また、自己破産のように借金の理由に制限がないため、税金や社会保険料など一部の債務を除きすべての債務を対象とすることができます。
ただし、任意整理のように手続きの対象とする債務を選ぶことはできず、保証人付きの債務があれば、保証人に迷惑がかかる可能性があります。
また、自己破産のようにすべての債務が免除されるわけではないため、手続きをするには安定した収入が必要です。
自己破産|借金が大きすぎて返済できない人
自己破産は、裁判所に申し立てることで、すべての借金を免除(免責)してもらう手続きです。
裁判所から債務を免除するという免責許可決定が下りると、税金や社会保険料などの非免責債権を除き、すべての借金の支払い義務はなくなります。
借金の返済を継続することが困難な場合に認められ、生活に最低限必要なもの以外は、債権者への返済のため処分されます。
●自己破産のメリット・デメリット
| メリット |
デメリット |
・税金などを除きすべての借金が免除される
・差し押さえ中の給与も、破産手続きにより停止される
・収入要件がない(無職でも利用可能)
・手続き完了後は新たな生活をスタートできる |
・住宅・車・高額な貯金など一定額以上の財産は処分される
・信用情報に事故情報として、7年程度登録される
・(弁護士や司法書士など)破産手続き中、資格制限を受ける
・保証人付きの借金は、保証人に一括請求される可能性がある
・税金や養育費・慰謝料などは免除されない
・手続きに時間がかかる(半年〜1年程度)
・官報に氏名・住所が掲載される
|
自己破産のメリットは、税金や養育費などを除き、すべての債務の支払い義務がなくなることです。個人再生のような収入要件もないため、安定した収入がなくても手続きができます。
ただし、住んでいる家を含めて、必要最低限の財産以外は、債権者への返済のため処分されます。また、ギャンブルや著しい浪費で作った借金などの免責不許可事由に該当すると自己破産が認められない可能性があります。
免責不許可事由とは、借金の返済義務を免除することが認められない事由です。破産法第252条1項に規定されています。
自己破産が認められると、債権者は泣き寝入りをするしかないため、あまりにも不公平と考えられる借金などの場合、裁判所から免責許可を受けることができません。
まとめ
消費者金融の借金は5年で時効を迎える可能性がありますが、単に期間が経過すれば自動的に成立するわけではありません。
時効を成立させるためには、「時効援用」の手続きを行う必要があり、途中で借金の一部でも返済や督促に応じると時効がリセットされるリスクがあります。
また、時効を待ち続けることには、遅延損害金の増加や信用情報の悪化、給与や財産の差し押さえの可能性など大きなリスクが伴います。
裁判で敗訴すると時効時効が10年に延びるため、借金の帳消しはさらに困難になるでしょう。
そのため、借金の返済が難しい場合、時効の完成を待つだけではなく、弁護士や司法書士に相談することが重要です。
借金や収入の状況に合わせて、任意整理や個人再生、自己破産などの債務整理を活用すれば、借金の負担を減らすこともできます。
借金や収入の状況に合わせて、より確実な解決策を見つけるためにも、借金問題に強い専門家に相談してみましょう。
消費者金融の借金の時効に関するよくある質問
時効援用の手続きにかかる費用はいくらが目安?
時効の援用手続きにかかる費用は、内容証明郵便の利用料金と専門家に依頼する場合の費用です。弁護士・認定司法書士・行政書士と依頼先によって、費用の相場は異なります。
| 項目 |
費用目安 |
| 内容証明郵便 |
・配達証明あり:1,279円~
・配達証明なし:959円~ |
| 弁護士費用 |
5~8万円 |
| 認定司法書士費用 |
3~5万円 |
| 行政書士費用 |
1~3万円 |
行政書士の費用は、弁護士・司法書士と比べ安い傾向ですが、時効成立の調査や援用が失敗した際の消費者金融との交渉は依頼できません。
一方、弁護士や認定司法書士は、時効成立の調査から援用が失敗した際の対応も依頼可能です。
ただし、認定司法書士が対応できる債務額は1社あたり140万円までです。140万円を超える借金は、弁護士に依頼しましょう。
消費者金融への借金について、時効が完成したらどんな影響がある?
借金について時効が完成すると、債務が消滅するため、個人情報機関に登録されていた事故情報が抹消されます。
ただし、個人信用情報機関によって対応が異なるため、抹消されたか確認したい場合は、開示請求を利用しましょう。
事故情報が消えると、新たなクレジットカードの作成やローン契約の審査には通りやすくなりますが、消滅時効を援用した相手の消費者金融や系列会社からの借り入れは難しくなります。
また、借金の担保として家に抵当権が設定されていた場合、消滅時効が成立すると債務がなくなるため、その担保として存在する抵当権も原則として消滅します。
時効の完成日は、どうやって確認すればよい?
時効の完成を確認する方法には、次のものがあります。
・契約書や取引履歴で最終返済日を確認
・信用情報機関(CIC、JICCなど)で取引情報を調べる
・消費者金融業者に問い合わせる
・専門家(弁護士や司法書士)に相談する
時効期間は、途中の停止や中断を含めて完成しているかの判断には、法律的な知識も必要となります。弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
民法改正前にした消費者金融の借金も時効は5年?
2020年4月1日施行の民法改正前にした消費者金融からの借金については、借金の種類によって時効期間が異なります。
消費者金融や金融機関からの借金の消滅時効は、債権者が「権利を行使できるときから5年間」です。
一方、友人や知人からの借金、信用金庫や住宅金融支援機構の住宅ローン、奨学金などは、「権利を行使できるときから10年間」です。