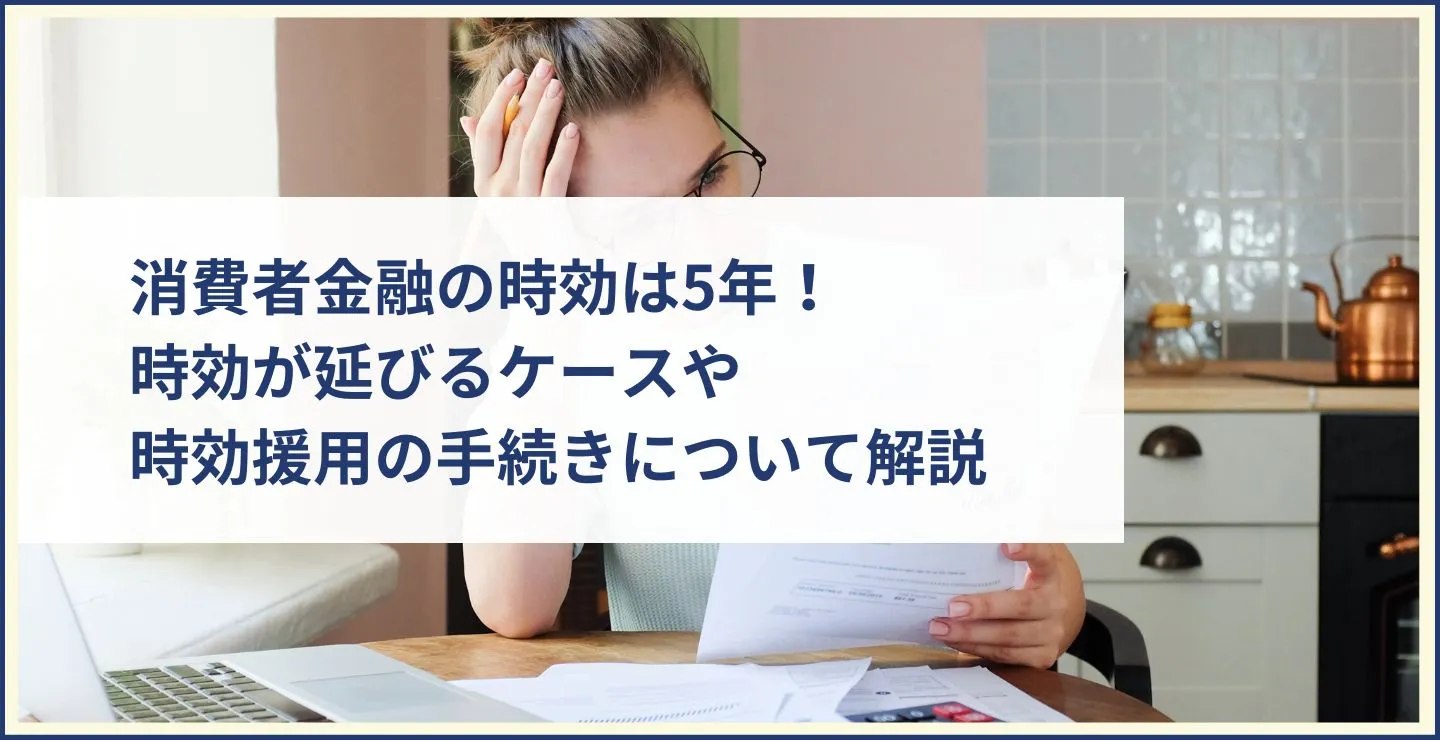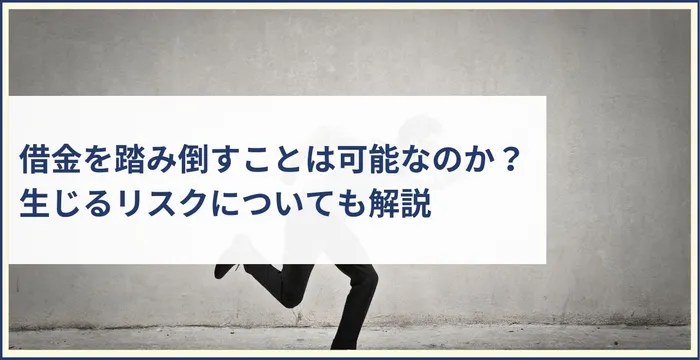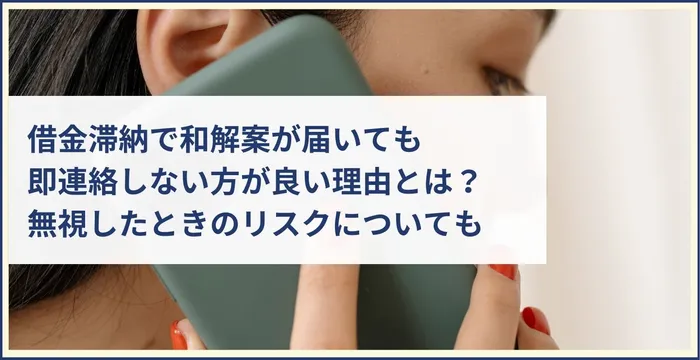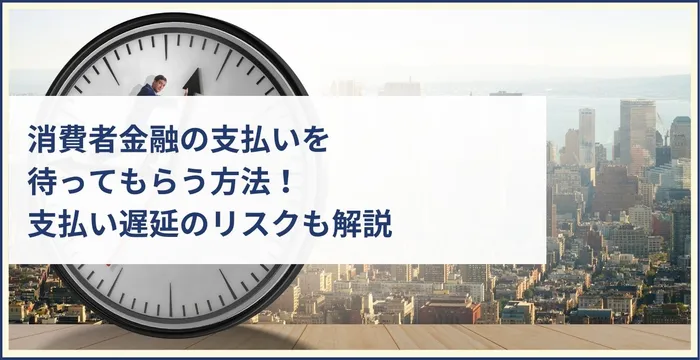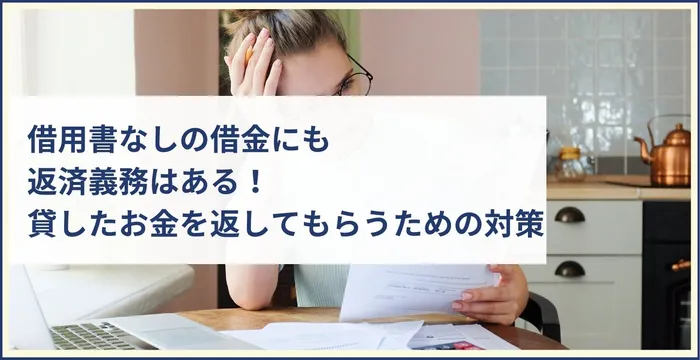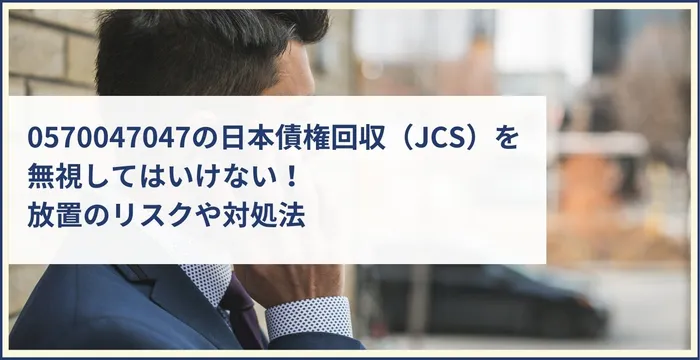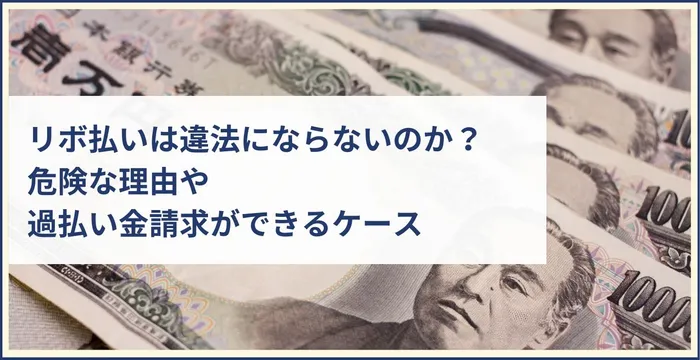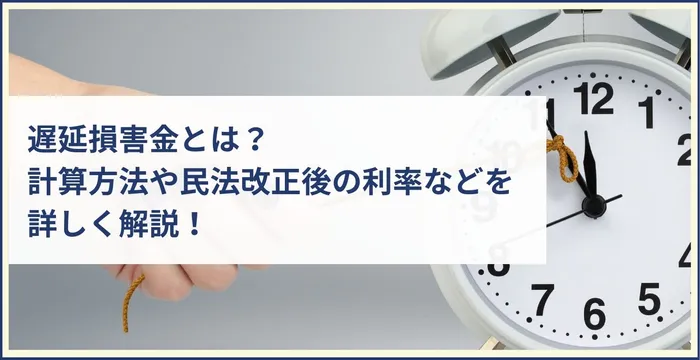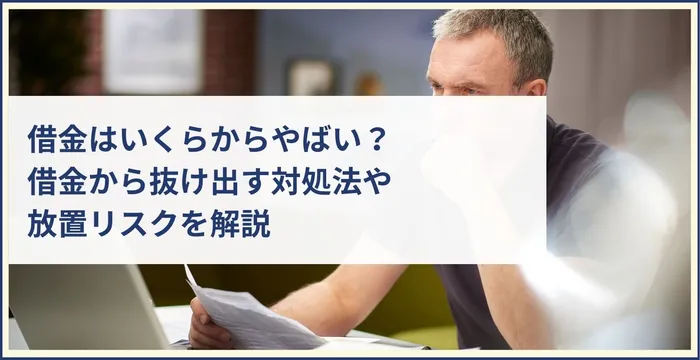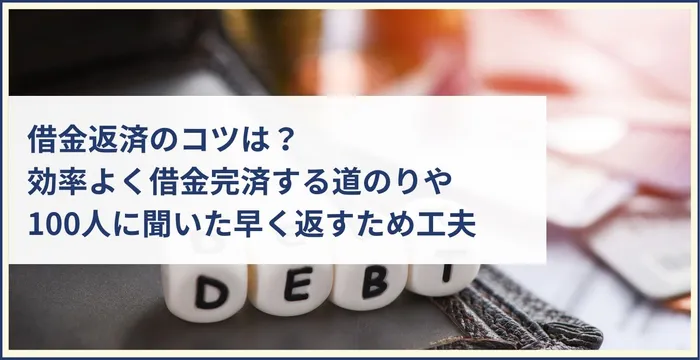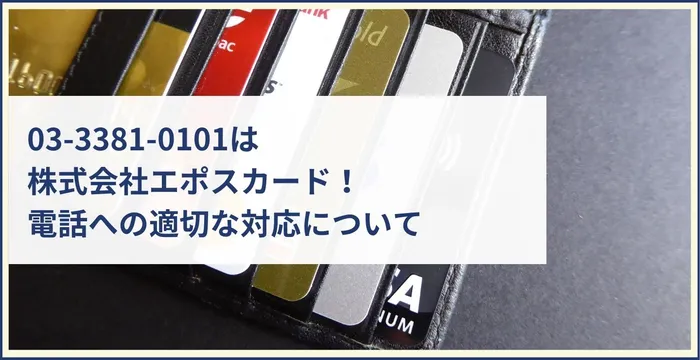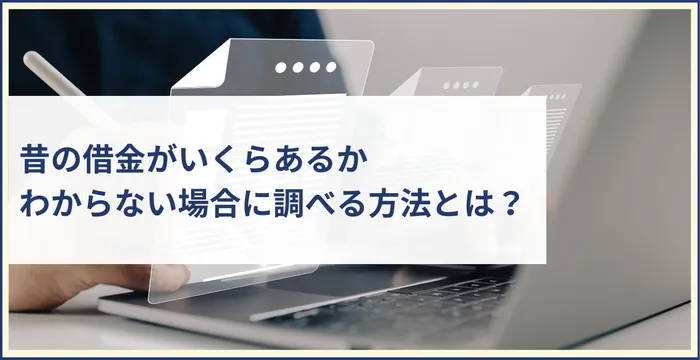消費者金融の借金の時効は最終返済日から5年
消費者金融の借金に関する時効は、最終返済日から5年です。ここで「最終返済日」とは、契約上の返済予定日や実際に最後の支払いを行った日を指します。この時効期間が経過すれば、消滅時効が成立し、借金の返済義務がなくなる可能性があります。ただし、たとえ少額でも途中で返済をした場合は、その最後の支払い日が基準となり時効のカウントがリセットされます。そのため、最終返済日を正確に確認し、時効成立の条件を満たしているか慎重に確認することが重要です。
2020年4月に施行された民法改正では、借金の時効期間が借入先を問わず5年に統一されました。以前の法律の規定では、消費者金融や銀行などの法人からの借金は5年、知人や信用金庫などの個人や非営利組織からの借金は10年と異なっていました。しかし、民法改正により、すべての借金が同じ基準で扱われるようになり、時効制度がシンプルになりました。消費者金融の借金については、民法改正前から時効期間が5年とされており、今回の改正による変更はありません。
その他の時効が成立する条件
消費者金融の借金の時効は最終返済日から5年であるということの他に、時効が成立する条件として下記の2つの条件があります。
- 時効が延びる理由が存在しない
- 時効援用の手続きを行う
以下では、それぞれの条件について解説します。
時効が延びる理由が存在しない
消費者金融の借金において、時効を成立させるためには「時効が延びる理由がないこと」が重要な条件の一つです。時効が延びる主な理由としては、「請求」「差押・仮差押・仮処分」「承認」の3つが挙げられます。
1つ目の「請求」とは、債権者が裁判を通じて債務者に返済を求める行為です。裁判所での請求があれば、時効の進行が中断し、その時点から新たに時効期間がスタートします。2つ目の「差押・仮差押・仮処分」は、債権者が債務者の財産を法的に押さえる手続きで、これも時効を延ばす要因になります。3つ目の「承認」は、債務者が自ら借金を認める行為を指します。例えば、一部でも返済を行った場合や、債権者に対して借金の存在を認める発言をした場合が該当します。
これらのいずれかの行為が行われると、時効の進行がリセットされて、再び最初から時効期間がカウントされます。そのため、これらの理由が存在しないことが、時効成立の基本条件です。
具体的な延長ケースや対処方法については、次章以降で詳しく解説します。
時効援用の手続きを行う
借金の消滅時効が成立していても、そのままでは借金が自動的に消えるわけではありません。債務者が「時効援用」という手続きを行い、時効の利益を受ける意思を表明する必要があります。
時効援用は口頭で行うことも可能ですが、証拠が残らないため、一般的には内容証明郵便を使用して債権者に通知します。内容証明郵便を利用することで、手続きの日時や内容を証明することができ、後のトラブルを避けることができます。
<時効援用通知書に記載する主な内容>
時効援用通知書を作成する際には、以下の内容を記載する必要があります。
|
作成日
|
通知書を作成した日付を明記します。
|
|
債権者の情報
|
住所や会社名など、債権者を特定する情報を記載します。
|
|
債務者の情報
|
住所、氏名、生年月日など、自身の情報を記載します。
|
|
意思表示
|
「時効の援用を行う」という明確な意思を示します。
|
|
借金の特定情報
|
借入契約年月日、借入額、契約番号など、どの借金に対する時効援用なのかを具体的に記します。
|
|
信用情報機関への依頼
|
時効成立後、事故情報の削除を求める文言を含めます。
|
通知書作成や債権者とのやり取りに不安がある場合は、弁護士などの専門家に依頼するのが安心です。
時効援用の手続きについては、下記の 「消費者金融の借金の時効が成立するまでの流れ」の章で詳しく解説します。
消費者金融の借金の時効が延びてしまうケース
借金の時効が成立するには、5年の時効期間を満了する必要がありますが、特定の事由が発生すると時効の成立までの期間が延びる場合があります。その主な理由として、「時効の更新」や「時効の完成猶予」が挙げられます。
時効の更新とは、時効完成前に特定の行為が行われた場合に、時効の進行がリセットされ、新たに最初から時効期間がカウントされることです。一方、時効の完成猶予は、時効の進行を一時的に停止させる制度で、特定の期間中は時効が完成しない仕組みです。これらの事由が発生すると、時効成立の予定が大幅に遅れる可能性があります。
ここでは、これらの「時効の更新」と「時効の完成猶予」による時効延長の仕組みと具体的なケースについて詳しく解説します。
時効の更新により最初から期間がカウントされる
時効の更新とは、時効完成前に特定の事由が発生した場合、時効期間の進行がリセットされ、新たに最初から時効期間がカウントされることです。以下の3つのケースが時効の更新事由として挙げられます。
- 債務者が借金の返済意思を示した場合
- 裁判で和解や確定判決が成立した場合
- 財産が差し押さえられた場合
債務者が、たとえわずかな金額でも返済をしたり、債権者に「返済を続ける」と伝えたりするとその時点で時効は更新されます。こうした行為は債務を承認したとみなされ、進行中の時効がリセットされてしまうのです。
また、債権者が裁判を起こして、和解が成立したり、判決が確定したりした場合も時効が更新されます。こうした法的な手続きは、債務の存在を確認する行為に該当するため、時効の進行が止まります。
さらに、債権者が債務者の財産を差し押さえるなどの手続きに踏み切った場合も、時効が更新されます。差し押さえされるということは、裁判所が借金返済を請求する権利の存在を証明し、その権利を強制的に行使してもよいと許可しているということです。
これらの事由が発生すると、それまでの時効期間が無効となり、新たに5年がカウントされることを理解しておく必要があります。
時効の完成猶予により時効の進行が一時的に止まる
時効の完成猶予とは、時効が完成する前に特定の事由が発生した場合に、時効期間の進行が一時的に停止する制度を指します。この猶予期間中は時効が成立せず、猶予が解除された後に時効の進行が再開されます。
時効の完成が猶予される主なケースは以下の通りです。
|
猶予されるケース
|
解説
|
|
裁判上の請求(民法第147条)
|
債権者が裁判を起こして債務の返済を求めた場合、判決が確定するまで時効は停止します。
|
|
強制執行(民法第148条)
|
財産の差押えや競売などの強制執行が行われた場合、執行が完了するまで時効が停止します。
|
|
仮差押え・仮処分(民法第149条)
|
債権者が仮差押えや仮処分の手続きを行った場合、その期間中は時効が進行しません。
|
|
裁判を通さない催告(民法第150条)
|
債権者が催告を行った場合、6か月間だけ時効が猶予されます。
|
|
協議を行う旨の合意(民法第151条)
|
債務者と債権者が協議を行う合意をした場合、その期間中は時効が進行しません。
|
|
未成年者または成年被後見人(民法第158条)
|
債務者が未成年者や成年被後見人の場合、特定の状況で時効が猶予されます。
|
|
夫婦間の権利(民法第159条)
|
配偶者間の権利に関する場合、特定の条件下で時効が猶予されます。
|
|
相続財産(民法第160条)
|
相続財産が未確定な場合、その期間中は時効が停止します。
|
|
天災(民法第161条)
|
地震や台風などの天災が原因で手続きが進められない場合、一定期間時効が猶予されます。
|
これらのケースが発生すると、時効の成立は予定よりも遅れるので注意が必要です。
消費者金融の借金の返済義務を無視し続けるリスク
借金を抱えている方の中には、返済義務を無視しても何とかなると思う方がいるかもしれません。しかし、借金を放置し続けることは大きなリスクを伴います。
消費者金融からの借金の返済を無視し続けることで、財産の差し押さえや信用情報の低下、さらには遅延損害金の増加といった深刻な事態を招く可能性があります。また、時効援用に失敗して債権者から一括請求を受けるリスクも考えられます。
ここでは、借金を放置することで起こり得るリスクについて具体的に解説します。
財産を差し押さえられる可能性がある
消費者金融からの借金を無視し続けると、最終的には財産を差し押さえられる可能性があります。債権者は、債務者が返済に応じない場合に、裁判所を通じて強制執行の手続きを行うことができます。債務者の預貯金、不動産、給与などの財産が差し押さえの対象です。
特に給与の差し押さえは多くのケースで行われる手続きの一つです。この場合、裁判所の命令によって勤務先に対して差し押さえの通知が送られるため、職場に借金問題が知られるリスクがあります。また、預貯金が差し押さえられると生活費に直接影響を及ぼし、日常生活が困難になることも考えられます。
滞納期間が長いとブラックリストに載る
消費者金融からの借金を滞納し続けると、信用情報機関に事故情報が登録され、いわゆる「ブラックリスト」に載ることになります。この状態では、新たな借入ができなくなるだけでなく、クレジットカードの発行や利用も難しくなります。ブラックリストに載ると、日常生活にも大きな影響を及ぼします。
一般的に、借金の滞納が2〜3か月以上続くと信用情報機関に登録される可能性が高いです。一度事故情報が登録されると、その記録は5年間保持され、期間中は金融機関からの信用を得られず、ローンや分割払いの審査に通りにくいなどの支障が生じます。特に住宅ローンや車のローンなど、大きな買い物が必要な場面で大きな障害となるでしょう。
さらに、ブラックリスト入りした情報は、借金を返済してもすぐに解消されるものではありません。そのため、滞納を放置せず早期に解決を目指すことが重要です。
遅延損害金が増え続ける
消費者金融からの借金を無視し続けると、元金だけでなく遅延損害金が増え続け、最終的に返済すべき金額が大きく膨らむリスクがあります。遅延損害金とは、契約で定められた返済期日を過ぎても返済が行われない場合に発生するペナルティ的な金利です。これは法定の上限金利(通常年20%以下)で計算され、借金を放置すればするほど総額が増え続けます。
例えば、借入金が50万円の場合、遅延損害金が年間10万円(年率20%の場合)に達する可能性があります。返済が長期間滞るほど、元金を大幅に超える金額を負担しなければなりません。また、債権者が裁判を起こした場合、その後は裁判所が定めた利率でさらに遅延金が加算されることも考えられます。
遅延損害金が膨らむと返済がますます難しくなり、解決へのハードルが高まります。
時効の援用に失敗すると一括請求されるリスクがある
借金を無視し続けて消滅時効の援用を試みた場合に、手続きが適切に行われないと、債権者から遅延損害金を含めた借金全額の一括請求を受けるリスクがあります。
例えば、時効が成立していない段階で援用を行ったり、書類の不備があった場合、債権者は時効の成立を認めないだけでなく、滞納していた分の全額返済を要求する可能性があるのです。こうしたケースでは遅延損害金も含まれるため、金額が大幅に増える場合もあります。
一括請求のリスクを回避するためにも、時効援用は専門知識を持つ弁護士のサポートを受け、失敗する要因がないかを確認しながら行うことが重要です。
過払い金が請求可能なことに気づかない場合がある
借金を無視し続けることで、本来なら返還されるべき過払い金に気付かず損をしてしまう可能性があります。過払い金とは、利息制限法の上限を超える金利で支払った利息のことで、法律に基づいて返還請求が可能です。しかし、過払い金請求には10年の消滅時効があるため、それを過ぎると権利が失われてしまいます。
過払い金があるかを調べるためには、消費者金融からこれまでの取引履歴を取り寄せ、その内容を精査する必要があります。ただし、取引履歴の請求を行うことで、消費者金融が借金の返済を求めてくる可能性があるので注意しなければなりません。こうしたリスクを避けるためには、弁護士や司法書士などの専門家に相談すると良いでしょう。
消費者金融の借金の時効は専門家に相談するのがおすすめ
消滅時効の成立には専門的な知識や正確な手続きが求められるため、簡単に成功するものではありません。誤った判断や手続きにミスがあった場合、時効が成立しないばかりか、一括返済の義務が生じるリスクもあります。そのため、時効援用を検討している場合は、弁護士などの専門家に相談することがおすすめです。
弁護士に相談することで、借金の状況を総合的に判断し、時効が成立しているかの確認や、債務整理を行うべきかの適切な選択ができます。また、時効援用に必要な「消滅時効援用通知書」の作成や、債権者への対応をすべて任せられるので、手間や時間を大幅に削減できます。特に債務整理に強い弁護士であれば、債務者の状況に応じた最善策を提案してくれるでしょう。
消費者金融の借金の時効が成立するまでの流れ
時効を成立させるには、正しく手続きを進める必要があります。
消費者金融の借金の時効が成立するまでの流れは、下記のとおりです。
- 時効期間が満了しているかを確認する
- 内容証明郵便で時効援用通知書を債権者に送る
- 時効援用通知書を債権者が受け取る
- 時効成立で借金の返済義務がなくなる
それぞれのプロセスについて、詳しく解説します。
1.時効期間が満了しているかを確認する
消費者金融の借金について時効援用を行う前に、まず時効期間が満了しているかを正確に確認することが重要です。貸金業者からの借金は、民法改正前の契約(2020年3月以前の契約)であっても時効期間は5年間とされています。そのため、最終返済日から5年以上が経過しているかを確認する必要があります。
時効が成立しているかどうかは、以下をチェックします。
- 債権者からの通知書を確認する
- 信用情報機関に照会する
- 債務を承認していないか思い出す
- 支払督促や判決を受けていないか確認する
最初に、債権者から送られてきた通知書や書類を確認し、最終返済日や返済予定日を特定します。これが時効の起算日となるので重要な情報です。また、信用情報機関に照会することで自分の取引履歴や債務状況を確認でき、債権がまだ有効かどうかを把握できます。
次に、過去に債権者に対して返済の意思を示したり、一部でも返済した記憶がないか確認することが必要です。こうした行為があれば、時効がリセットされている可能性があります。
また、裁判所から支払督促や判決を受けていないかも確認しておきます。これらの手続きが行われている場合、時効が中断または延長されている可能性があるので、しっかり確認しておいたほうが良いでしょう。
かなり前にした借金の滞納で和解案が届いても即連絡しない方が良い理由については、こちらの記事にまとめていますのでご参照ください。
2.内容証明郵便で時効援用通知書を債権者に送る
消費者金融の借金の時効が成立するためには、「時効援用通知書」を内容証明郵便で債権者に送付する必要があります。時効援用通知書は、借金の時効を主張し返済義務を正式に消滅させる意思を伝えるための重要な書類です。内容証明郵便を使用することで、通知を送付した事実と内容を証明できるため、後のトラブルを防ぐ効果があります。
時効援用通知書には、以下のような情報を記載します。
時効援用通知書
以下の借金につきましては、最終返済日(弁済期)である2021年〇月〇日からすでに5年が経過しており、時効消滅しております。そのため、本書をもって当該借金の時効を援用いたします。
借入人氏名:〇〇〇〇(ふりがな)
住所:東京都〇〇区〇〇
生年月日:○○〇〇年〇月〇日
当初借入日:2021〇〇年〇月〇日
当初借入額:〇〇円
また、本書面受取後、速やかに信用情報機関に通知を行い、登録されている事故情報を抹消する手続きをしていただきますよう合わせてお願いいたします。
信用情報機関に対して事故情報の抹消を依頼する文言を加えることで、新たな借入や信用取引の回復がスムーズになる可能性があります。
3.時効援用通知書を債権者が受け取る
内容証明郵便には配達証明を付けて送付するため、債権者が確実に受け取ったかを確認でき、債務者が正式に時効援用を主張した証拠が残ります。
債権者側は、通知書を受け取ると債務者との取引履歴や経過期間を詳細に確認します。この過程で、もし時効が成立していない場合、債権者は時効更新の手続きを行ったり、一括請求を求めてくる可能性があります。そのため、通知書を送付する前に、時効成立の条件が確実に満たされているかを慎重に確認することが重要です。
時効援用通知書の送付にはリスクも伴うため、最初の段階で弁護士に相談しておくと良いでしょう。弁護士のアドバイスを受けることで、時効成立の条件を正確に把握し、適切な手続きを進められます。また、万が一債権者が時効を認めず法的手段に訴える場合にも、専門家のサポートがあると安心です。
4.時効成立で借金の返済義務がなくなる
時効援用通知書を送付した後、債権者が取引履歴や経過期間を確認し、消滅時効の成立を認めれば、借金の返済義務は正式に消滅します。この時点で、債務者は法律上の返済義務から解放されます。債権者が時効の成立を確認した場合、通知として「債務不存在証明書」が送付されることがあります。この証明書は、時効が成立した事実を公式に確認する重要な書類です。
ただし、債務不存在証明書が必ず送られてくるわけではありません。債権者が書面を発行しない場合もあります。そうした場合は、債権者が時効援用を認めたことを確認するために、再度内容証明郵便を送付し、時効成立を認めた旨を明示するように依頼すると良いでしょう。
消費者金融の支払いを待ってもらう方法について知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。
消費者金融の時効援用にかかる費用相場
消費者金融の借金に対する時効援用を専門家に依頼する際の費用は、依頼先によって異なります。以下に、各専門家への依頼費用の目安をまとめました。
|
費用の内訳
|
相場
|
|
内容証明郵便の発送費用
|
1,279円
|
|
専門家への依頼費用
|
1万~8万円程度
|
|
信用情報機関への情報開示請求費用
|
500~1,500円程度
|
|
合計
|
1万5,000円~8万5,000円程度
|
行政書士は、時効援用通知書の作成などの書類作成業務を主に行っています。ただし、代理人として債権者との交渉や手続きを行うことはできません。そのため、費用は比較的安価ですが、対応範囲が限定されます。
司法書士は、書類作成に加えて借金の時効成立の調査や、1社あたりの元金が140万円以下の場合に限り代理人として債権者との交渉や手続きを行うことが可能です。そのため、行政書士よりも対応範囲が広く費用もやや高くなります。
弁護士は、借金額に関係なく、時効援用に関するすべての手続きや債権者との交渉を代理人として行うことができます。また、時効援用が認められなかった場合でも、債務整理などの他の法的手段を提案・実施することが可能です。そのため、費用は他の専門家よりも高くなる傾向があります。
時効援用の手続きは、自分で行うことも可能ですが、専門的な知識が求められるため、専門家に依頼するのが一般的です。依頼する際は、各専門家の対応範囲や費用を比較検討し、自分の状況に適した選択をすることが重要です。
まとめ
ここまで消費者金融からの借金の時効について解説しました。
消費者金融の借金における時効は、最終返済日から5年が経過することで成立します。ただし、成立にはいくつかの条件と手続きが必要です。時効期間中に債権者が請求や差押えなどを行った場合や、債務者が返済意思を示した場合は、時効が延びるリスクがあります。また、時効が成立しても援用手続きを行わなければ、借金の返済義務は消滅しません。
時効援用の手続きでは、内容証明郵便で通知書を送付する必要があります。通知書には、借金の特定情報や時効を援用する旨の意思を明記し、信用情報の抹消を求める内容を記載することがおすすめです。通知書の送付後も、債権者が時効を認めない場合があるため、慎重な対応が求められます。
時効援用の手続きや確認には専門的な知識が必要であり、弁護士や司法書士に相談することで、手続きをスムーズかつ確実に進められます。借金問題を解決し、安心して新たな生活を始めるためには、時効成立までの正しい知識と対応が不可欠です。