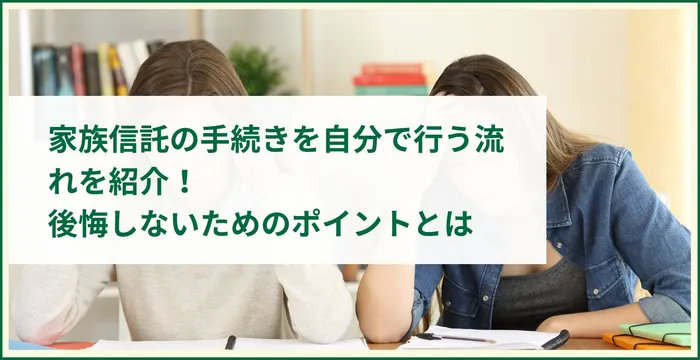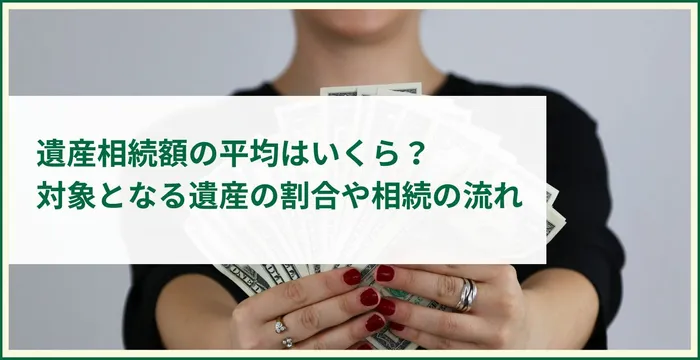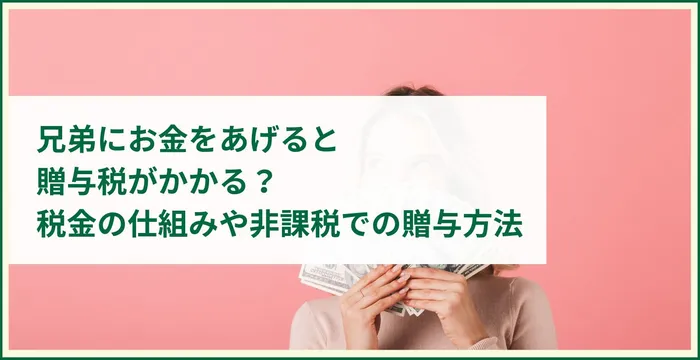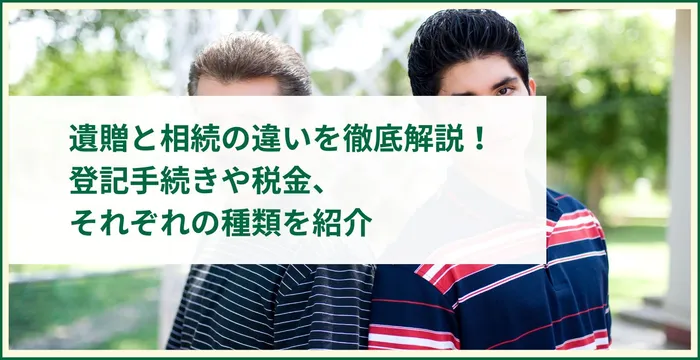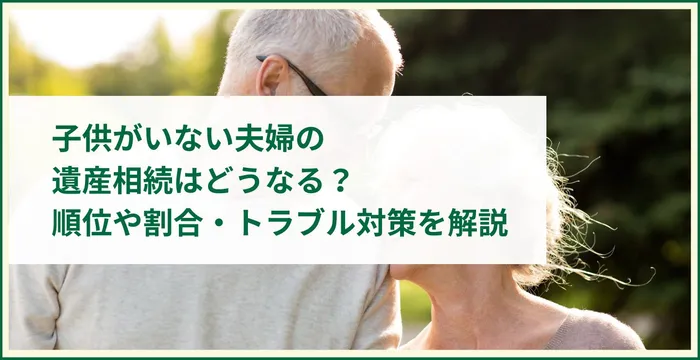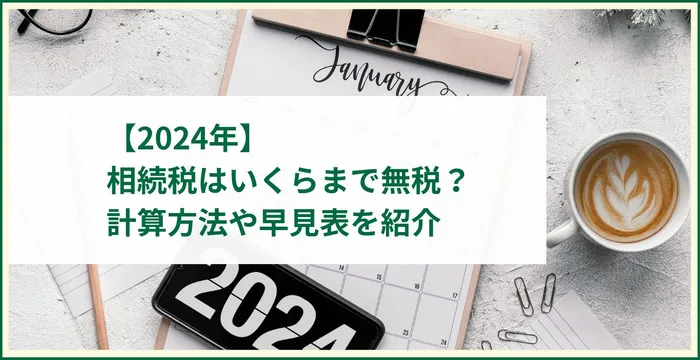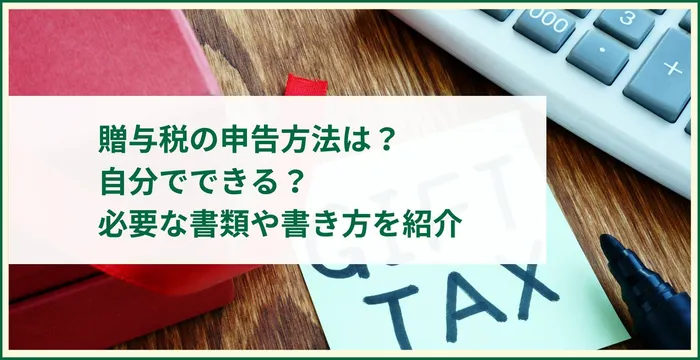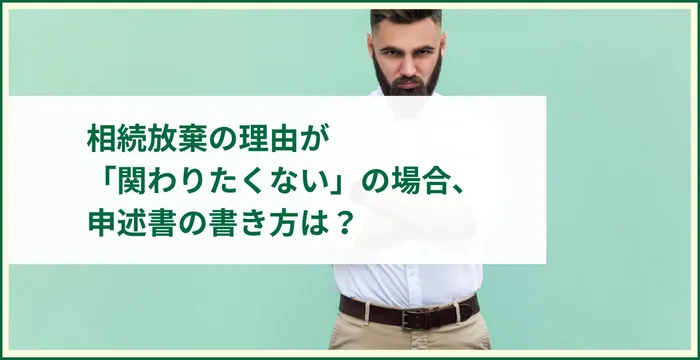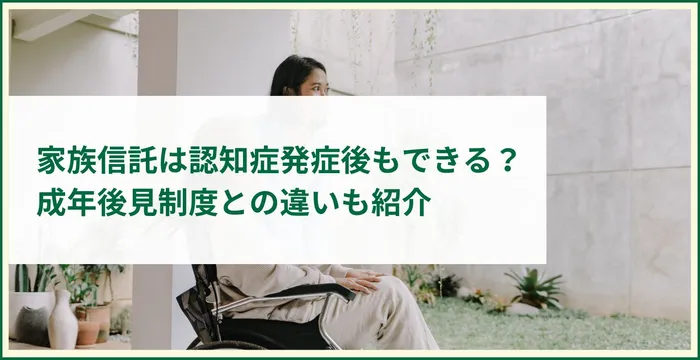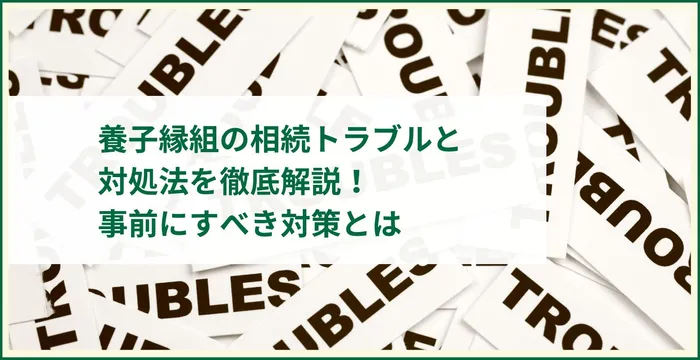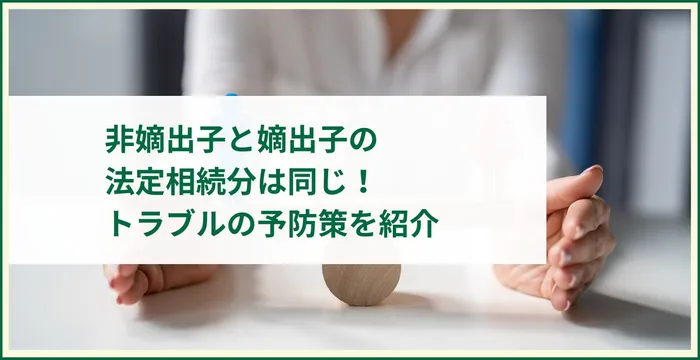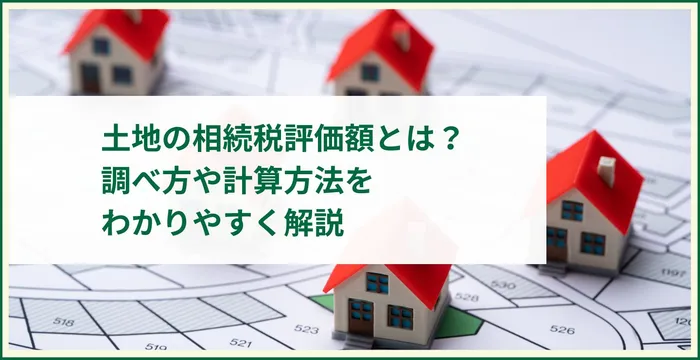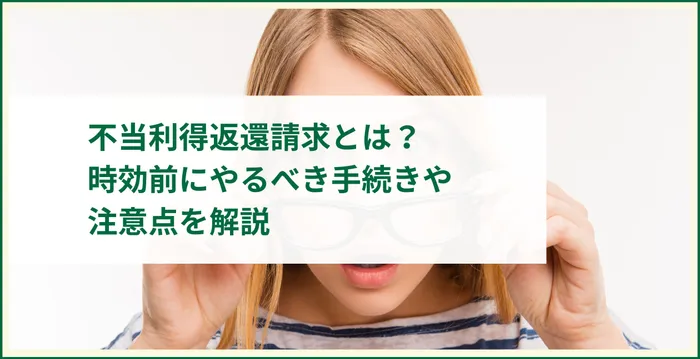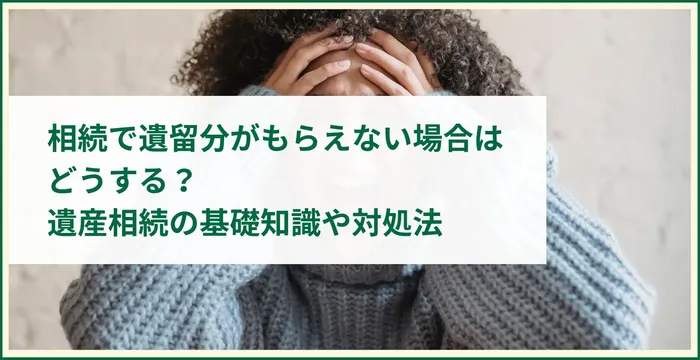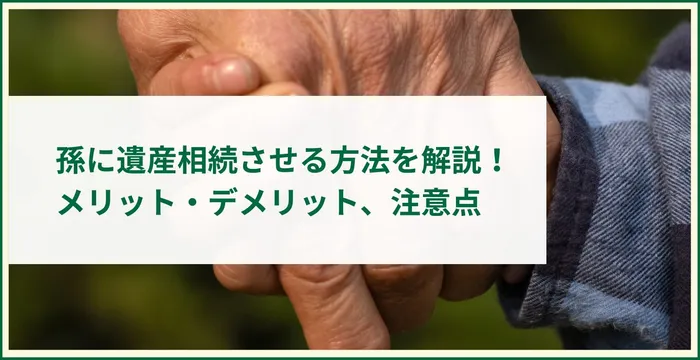相続放棄は、相続人が権利を放棄する手続きです。主な必要書類は住民票除票と戸籍謄本などであり、相続人によって追加の書類が必要となります。本記事では相続放棄にまつわる必要書類について解説します。
『ツナグ相続編集部』執筆のコラム一覧
家族信託の手続きを行う流れは、「家族会議・内容決定・信託契約書の公正証書化・信託登記・口座開設・財産管理スタート」の6ステップです。この記事では自分で手続きするための方法や後悔しないポイントを解説します。
親の遺産額をある程度把握していれば早めに相続の準備や節税対策が行えますが、親に遺産額を直接聞くのは少々気が引けるでしょう。 そこで本記事では、遺産相続の平均額や平均年齢、遺産の内訳や相続の流れについて解説していきます。
配偶者や子どもへ遺産を譲る際にはさまざまな控除制度がありますが、兄弟へ遺産を譲る際に非課税でおこなう方法はあるのでしょうか?非課税で贈与できる暦年贈与について解説すると共に、理解しておくべき税金の仕組みと兄弟間贈与の注意点を説明します。
遺贈と相続には違いがあります。 遺贈は第三者や団体・法人などにも継承できますが、相続は相続人に限られます。 本記事を読むと、遺贈の種類や相続・贈与との違いがわかります。 遺言書の種類や記載する内容、遺贈を行う際の注意点も解説します。
相続税の申告を自分でできるかどうかの判断基準と、手続きの流れを解説します。相続税は自分で申告できるものの、内容が複雑であり申告までに時間がかかるため、自分でできるか判断することが大切です。自己申告を考えている人はぜひチェックしてください。
子供がいない場合の遺産相続について、法定相続人の順位や相続分について解説します。法定相続人でもっとも重要視されるのは配偶者であり、どのような状況でも常に第一優先の相続人となります。
他の相続人が何も言ってこずに遺産相続の手続きが勝手に行われていた場合、手続きは無効です。遺産分割協議をやり直しましょう。本記事は相続が発生しているかの確認方法や相続が遅れた場合のリスクを解説しています。
相続税は、相続した財産から控除や特例分を差し引き、算出された金額に対して課せられる税金です。正しい計算方法を知り、正確な相続税額を納付しましょう。本記事では、相続税が無税になる目安や計算の早見表、控除や特例の種類、計算方法を紹介しています。
贈与税の申告方法や書類の書き方の解説。税金がいくらかかるかや、節税に繋がる特例や控除についても解説します。
故人や親族に関わりたくないという理由で相続放棄をする場合の申述書の書き方や、申請の流れ、相続放棄をする際の注意点についてわかりやすく解説します。
亡くなった人が連帯保証人だった場合に、連帯保証債務を相続する可能性があるのは法定相続人です。連帯保証債務の確認方法から相続放棄の可否、知らずに相続した場合の対策まで解説します。
家族信託は認知症になるとできません。しかし、公証人や司法書士が「判断能力がある」と判断した場合は可能です。この記事では、認知症でも家族信託が可能かどうかや成年後見制度との違いを解説します。
養子縁組が関係する場合、法定相続人が増え、他の相続遺産に影響を与えることからトラブルが起きやすくなります。養子縁組の相続トラブル事例から解決方法、事前にできる遺言書などの対策について解説します。
非嫡出子にも相続権が与えられます。相続割合も、嫡出子と同じです。非嫡出子を含む相続は、トラブルに発展する可能性が高いのが特徴です。この記事では、非嫡出子の相続における問題点や、トラブルに対する解決策を紹介しています。
相続税評価額とは、財産ごとに決められた計算式に基づいて算出する財産の価額のことです。本記事では、土地の相続税評価額の計算方法や土地の相続税について詳しく紹介します。
相続財産がすでに何者かによって使い込まれていた場合は、不当利得返還請求で取り戻せる可能性があります。不当利得の返還を求める場合にはどんな点に注意すればいいのか、またやるべき手続きや弁護士に依頼する際の費用相場について解説します。
遺言書の内容や生前贈与の有無などによっては、取得できるはずの遺留分がもらえないケースがあります。本記事では、相続で遺留分がもらえなかったときの対処法や、遺産相続の基礎知識などについて詳しく解説します。
家族信託契約書の書き方には、いくつか注意点があります。内容に不備があると、契約書が無効になってしまうためです。この記事では、信託契約書の書き方や自分で作成する際の注意点を解説します。
通常孫は法定相続人になれないため、生前に何らかの相続対策をしておかないと孫に遺産を相続させられません。そこで本記事では、孫に遺産相続させる方法やメリット・デメリット・注意点について解説していきます。