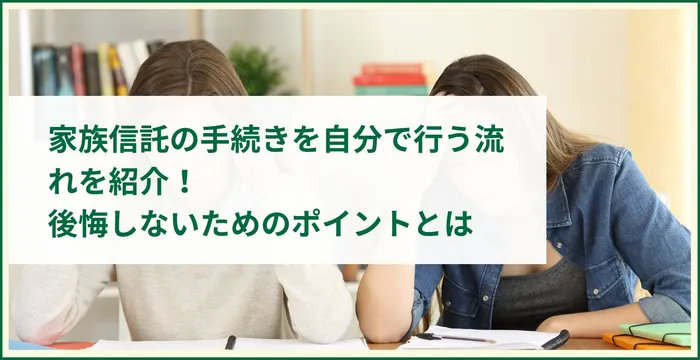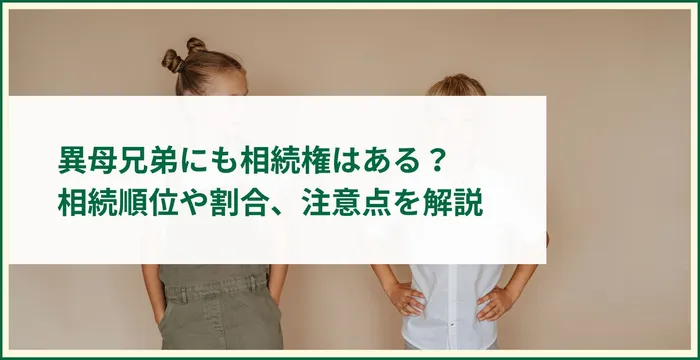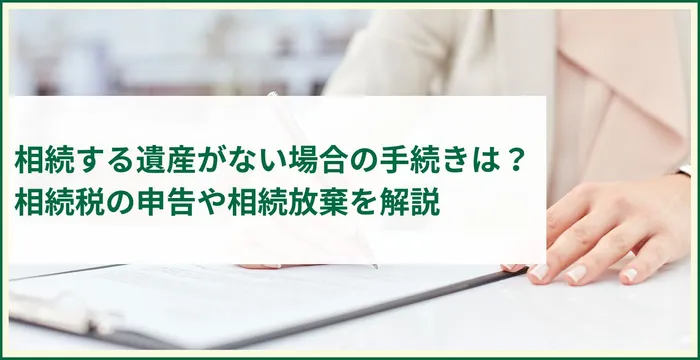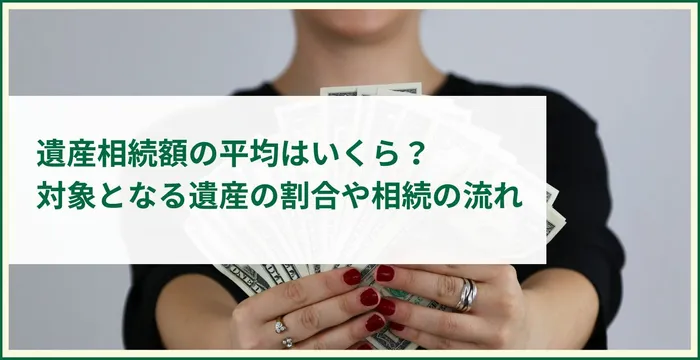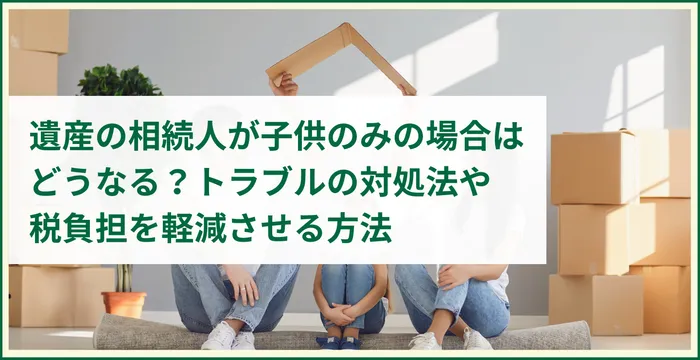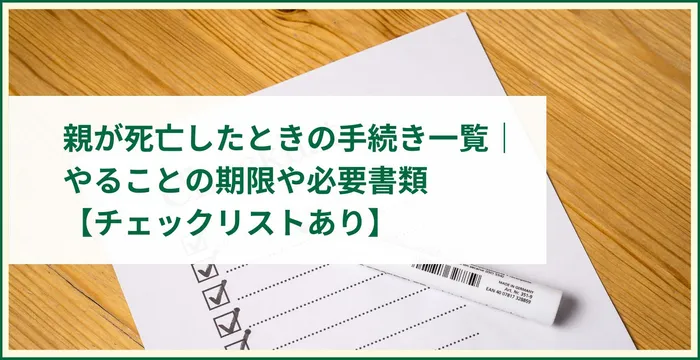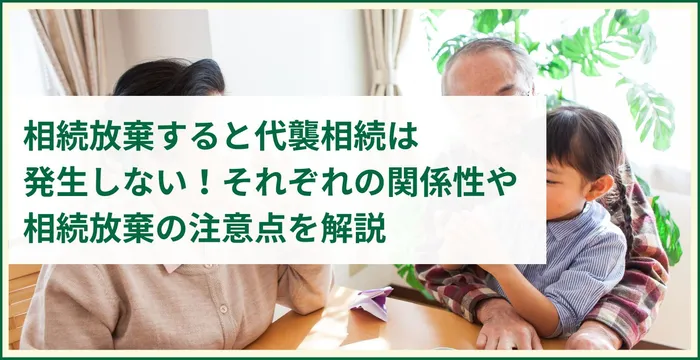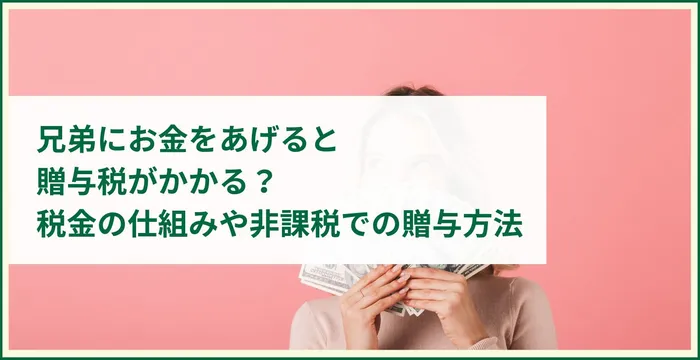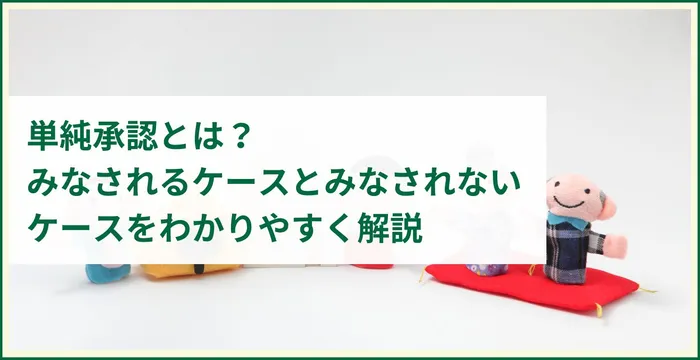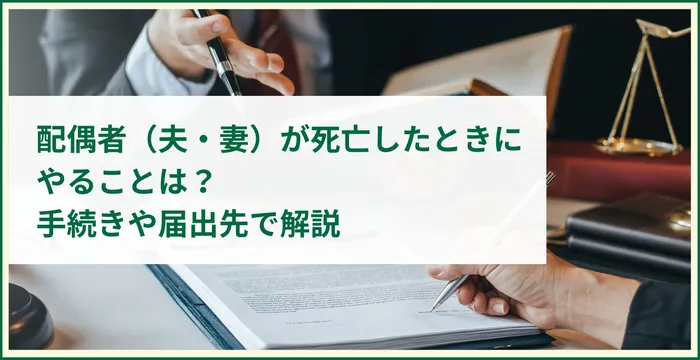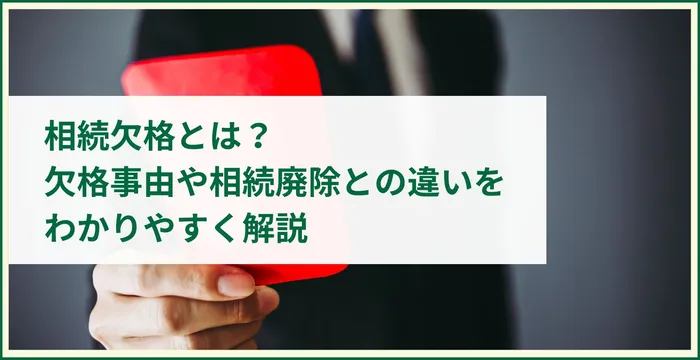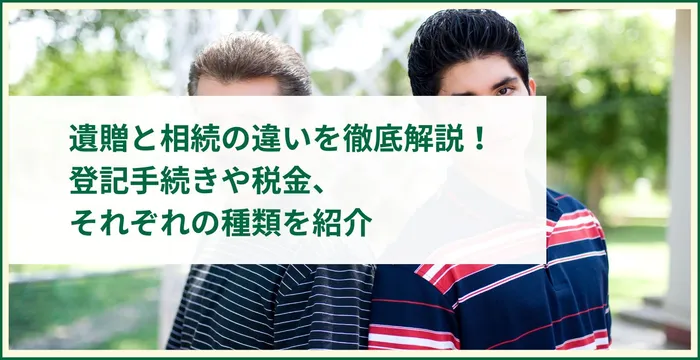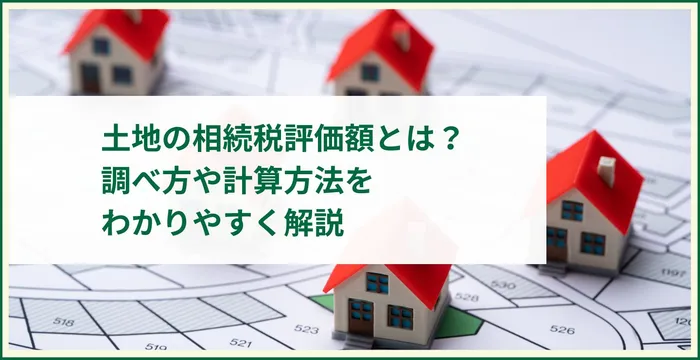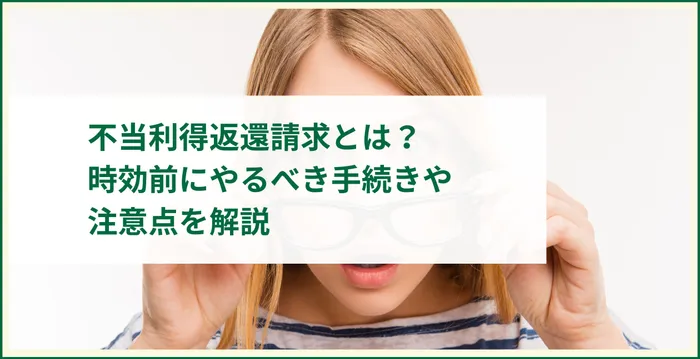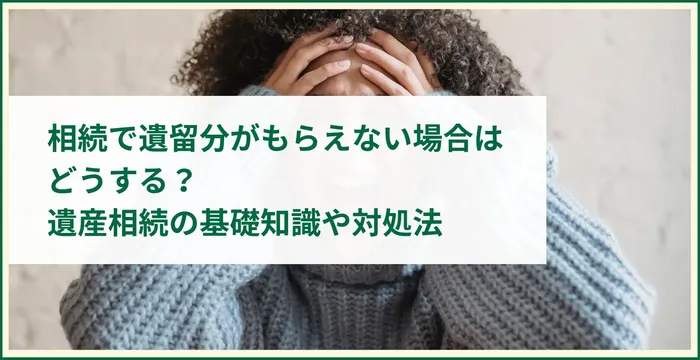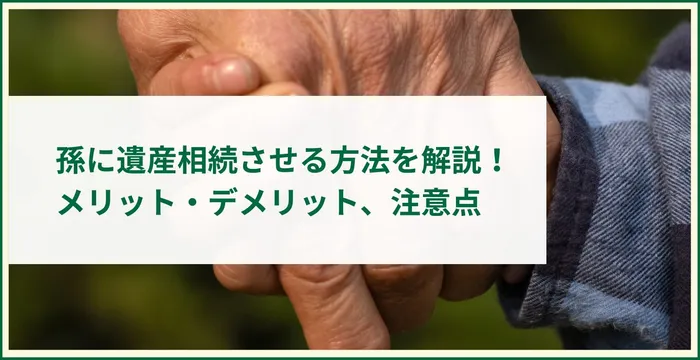家族信託の手続きを行う流れは、「家族会議・内容決定・信託契約書の公正証書化・信託登記・口座開設・財産管理スタート」の6ステップです。この記事では自分で手続きするための方法や後悔しないポイントを解説します。
相続コラム一覧
カテゴリーから相続コラムを探す
相続放棄の手続きは自分で行うことも可能ですが、手続きが複雑になる場合は弁護士に相談するのが得策です。この記事では、相続放棄を自分で行う際の手続き方法や費用相場などを解説しています。
異母兄弟は相続権を有します。 本記事を読むと異母兄弟の相続順位や割合、遺産分割協議の際に起こりやすいトラブルや注意点がわかります。 相続前にしておくべき対策も解説します。
相続する遺産がないなら遺産相続は必要なく、手続きをすることもありません。しかし、実際は何らかの遺産があり、本当は手続きが必要であるケースも考えられます。本記事では、相続する遺産がないときに覚えておきたいポイントを紹介します。
親の遺産額をある程度把握していれば早めに相続の準備や節税対策が行えますが、親に遺産額を直接聞くのは少々気が引けるでしょう。 そこで本記事では、遺産相続の平均額や平均年齢、遺産の内訳や相続の流れについて解説していきます。
本記事では、遺産の相続人が子供のみという場合ではどのように遺産相続をするのか紹介します。また、子供のみが遺産相続をする際に起こり得るトラブル、対処法なども併せて紹介します。
親が亡くなった後に何をするべきか知りたい方に向けて、葬儀の段取りをはじめ、役所・年金事務所などで行う手続き、相続に関する手続きなどを時系列に解説しています。亡くなった後に銀行口座の預金を引き出す制度などもあわせてご確認ください。
相続放棄をしても代襲相続が発生するのか、不安を感じている方に向けて、代襲相続の仕組みや相続放棄の手続き・注意点などをわかりやすくまとめました。基本的な知識を身につけて、相続手続きをスムーズに進めましょう。
配偶者や子どもへ遺産を譲る際にはさまざまな控除制度がありますが、兄弟へ遺産を譲る際に非課税でおこなう方法はあるのでしょうか?非課税で贈与できる暦年贈与について解説すると共に、理解しておくべき税金の仕組みと兄弟間贈与の注意点を説明します。
単純承認とは、故人の財産や債務を無条件で全て承継する相続方法です。単純承認を選択した場合、他の相続方法は選択できなくなるため、不利益を被らないように基本的な知識を身につけておきましょう。
配偶者(妻・夫)の死亡時にやることや手続きまとめた記事です。配偶者の死亡時には、病院でやることや役所での申請をはじめ、さまざまな手続きが発生します。急いでやることから一定の準備期間があるものまで、さまざまな手続きに関して解説しています。
相続欠格は、欠格事由に該当する場合に相続人の資格を失う制度です。相続欠格者がいる場合、相続手続きにもさまざまな影響が生じます。相続欠格と似た制度として相続廃除があります。この記事相続欠格の制度や効果、相続廃除との違いについて解説します
遺贈と相続には違いがあります。 遺贈は第三者や団体・法人などにも継承できますが、相続は相続人に限られます。 本記事を読むと、遺贈の種類や相続・贈与との違いがわかります。 遺言書の種類や記載する内容、遺贈を行う際の注意点も解説します。
親の借金は原則、子供に返済義務はありません。しかし契約方法によっては返済義務が生じるケースがあります。親の生前、死亡後で異なる回避方法と、負担を減らす方法を解説します。
相続税評価額とは、財産ごとに決められた計算式に基づいて算出する財産の価額のことです。本記事では、土地の相続税評価額の計算方法や土地の相続税について詳しく紹介します。
相続財産がすでに何者かによって使い込まれていた場合は、不当利得返還請求で取り戻せる可能性があります。不当利得の返還を求める場合にはどんな点に注意すればいいのか、またやるべき手続きや弁護士に依頼する際の費用相場について解説します。
遺言書の内容や生前贈与の有無などによっては、取得できるはずの遺留分がもらえないケースがあります。本記事では、相続で遺留分がもらえなかったときの対処法や、遺産相続の基礎知識などについて詳しく解説します。
家族信託契約書の書き方には、いくつか注意点があります。内容に不備があると、契約書が無効になってしまうためです。この記事では、信託契約書の書き方や自分で作成する際の注意点を解説します。
通常孫は法定相続人になれないため、生前に何らかの相続対策をしておかないと孫に遺産を相続させられません。そこで本記事では、孫に遺産相続させる方法やメリット・デメリット・注意点について解説していきます。
遺産分割協議書に印鑑を押してくれないときは、相続人が納得いくよう協議するか、弁護士や家庭裁判所を介して交渉を進めます。記事では調停や審判、実印がないときの対処法の詳細を解説しています。