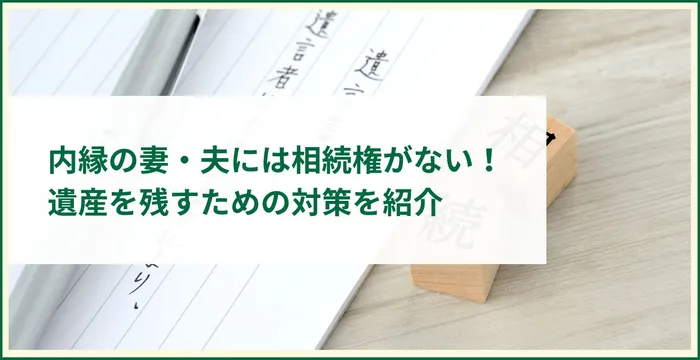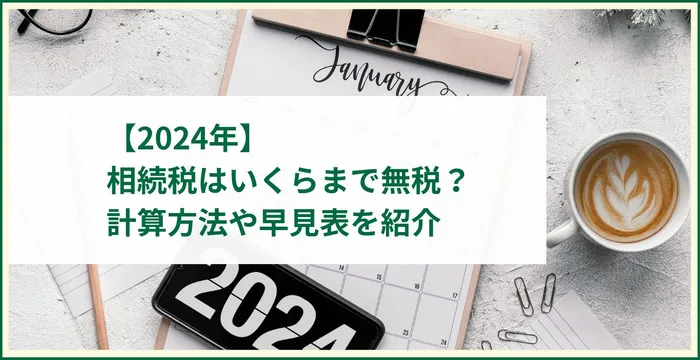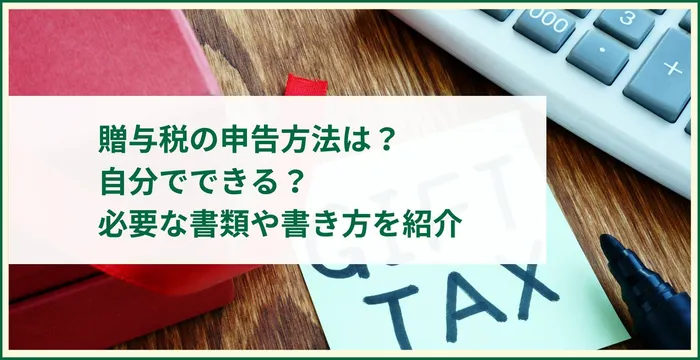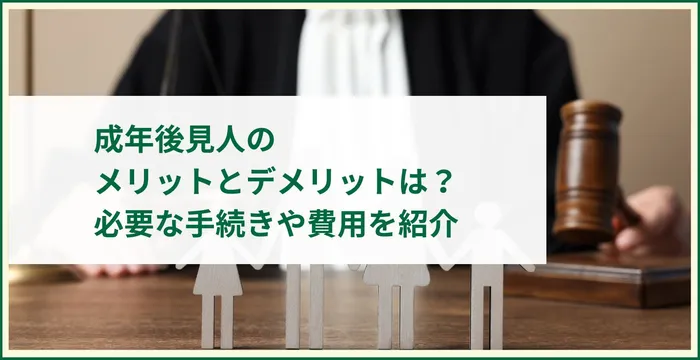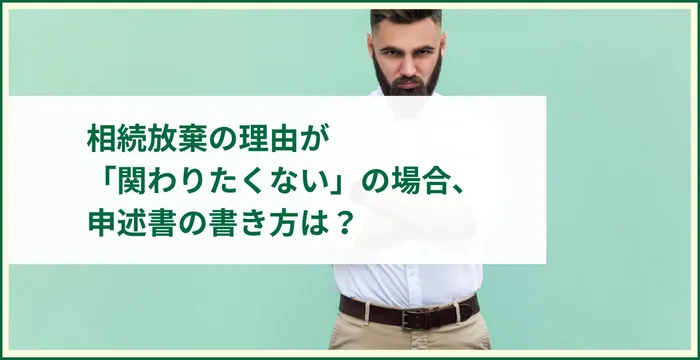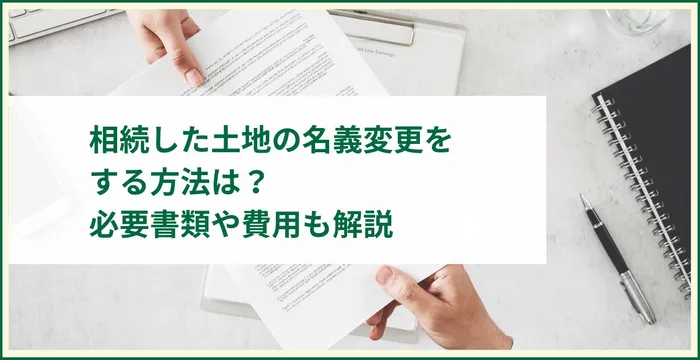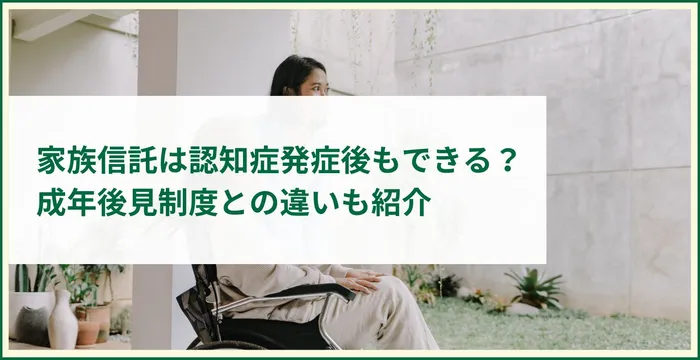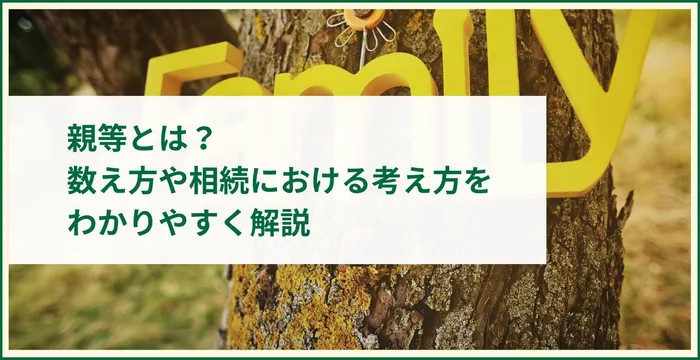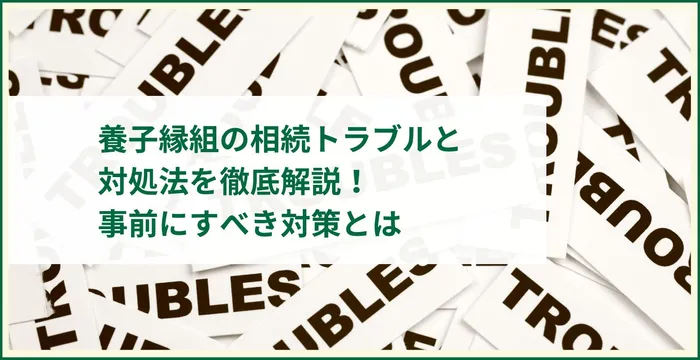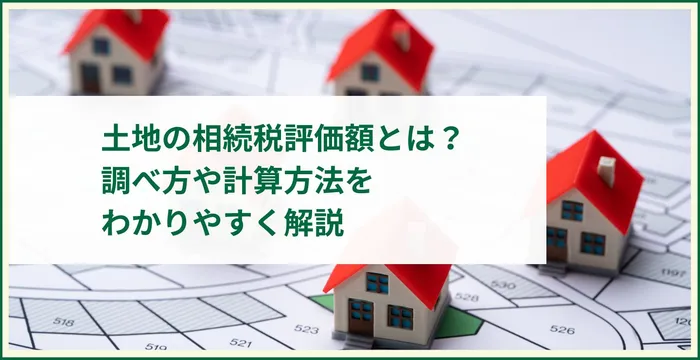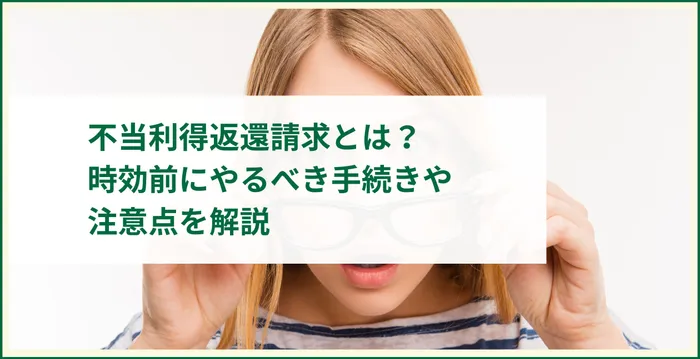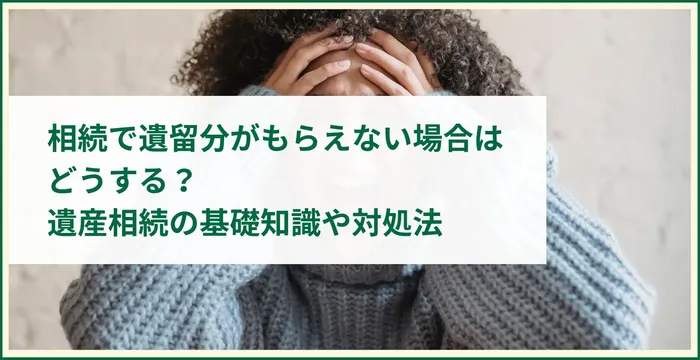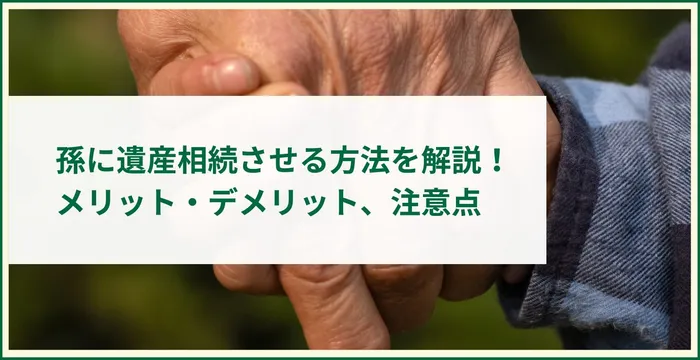他の相続人が何も言ってこずに遺産相続の手続きが勝手に行われていた場合、手続きは無効です。遺産分割協議をやり直しましょう。本記事は相続が発生しているかの確認方法や相続が遅れた場合のリスクを解説しています。
相続コラム一覧
カテゴリーから相続コラムを探す
法律上、内縁の妻や夫には相続権がありません。しかし、事前に対策を講じることで遺産の全部または一部を内縁の妻や夫に相続させられます。この記事では、内縁の妻や夫に遺産を相続させるための具体的な方法と、遺産を相続する際の注意点を詳しく解説します。
相続税は、相続した財産から控除や特例分を差し引き、算出された金額に対して課せられる税金です。正しい計算方法を知り、正確な相続税額を納付しましょう。本記事では、相続税が無税になる目安や計算の早見表、控除や特例の種類、計算方法を紹介しています。
相続税対策に有効な株式の生前贈与ですが、上場株式か非上場株式かで生前贈与する際の手続きが異なります。この記事では、株式の生前贈与の手続きをわかりやすく解説します。
贈与税の申告方法や書類の書き方の解説。税金がいくらかかるかや、節税に繋がる特例や控除についても解説します。
家族が認知症になったときに利用できる「成年後見制度」について、成年後見人のメリット・デメリットや、必要な手続き、費用について解説します。
故人や親族に関わりたくないという理由で相続放棄をする場合の申述書の書き方や、申請の流れ、相続放棄をする際の注意点についてわかりやすく解説します。
相続放棄申述書は、相続人が故人からの遺産を法的に放棄する意志を表明するために家庭裁判所に提出する公的な書類です。申述書には、申述人および被相続人の情報、相続放棄の理由、相続財産の内容を正確に示す必要があります。
亡くなった人が連帯保証人だった場合に、連帯保証債務を相続する可能性があるのは法定相続人です。連帯保証債務の確認方法から相続放棄の可否、知らずに相続した場合の対策まで解説します。
相続した土地の名義は被相続人のものになっているため、相続後に名義変更の手続きをしなければなりません。本記事では、相続した土地の名義変更をする方法や必要書類、費用などについて詳しく解説します。
家族信託は認知症になるとできません。しかし、公証人や司法書士が「判断能力がある」と判断した場合は可能です。この記事では、認知症でも家族信託が可能かどうかや成年後見制度との違いを解説します。
親族間の距離を表す親等は、遺産相続における相続の順位や相続税の負担に関係することがあります。親等の数え方や注意すべきケースについて解説します。
養子縁組が関係する場合、法定相続人が増え、他の相続遺産に影響を与えることからトラブルが起きやすくなります。養子縁組の相続トラブル事例から解決方法、事前にできる遺言書などの対策について解説します。
相続税の納付を延滞したり、無申告や過少申告をした際に課せられるのが追徴課税です。追徴課税が発生しやすいパターンや、税務調査対象にならないための対策、課税の負担を軽減するための対策を解説します。
相続税評価額とは、財産ごとに決められた計算式に基づいて算出する財産の価額のことです。本記事では、土地の相続税評価額の計算方法や土地の相続税について詳しく紹介します。
相続財産がすでに何者かによって使い込まれていた場合は、不当利得返還請求で取り戻せる可能性があります。不当利得の返還を求める場合にはどんな点に注意すればいいのか、またやるべき手続きや弁護士に依頼する際の費用相場について解説します。
遺言書の内容や生前贈与の有無などによっては、取得できるはずの遺留分がもらえないケースがあります。本記事では、相続で遺留分がもらえなかったときの対処法や、遺産相続の基礎知識などについて詳しく解説します。
家族信託契約書の書き方には、いくつか注意点があります。内容に不備があると、契約書が無効になってしまうためです。この記事では、信託契約書の書き方や自分で作成する際の注意点を解説します。
通常孫は法定相続人になれないため、生前に何らかの相続対策をしておかないと孫に遺産を相続させられません。そこで本記事では、孫に遺産相続させる方法やメリット・デメリット・注意点について解説していきます。
遺産分割協議書に印鑑を押してくれないときは、相続人が納得いくよう協議するか、弁護士や家庭裁判所を介して交渉を進めます。記事では調停や審判、実印がないときの対処法の詳細を解説しています。