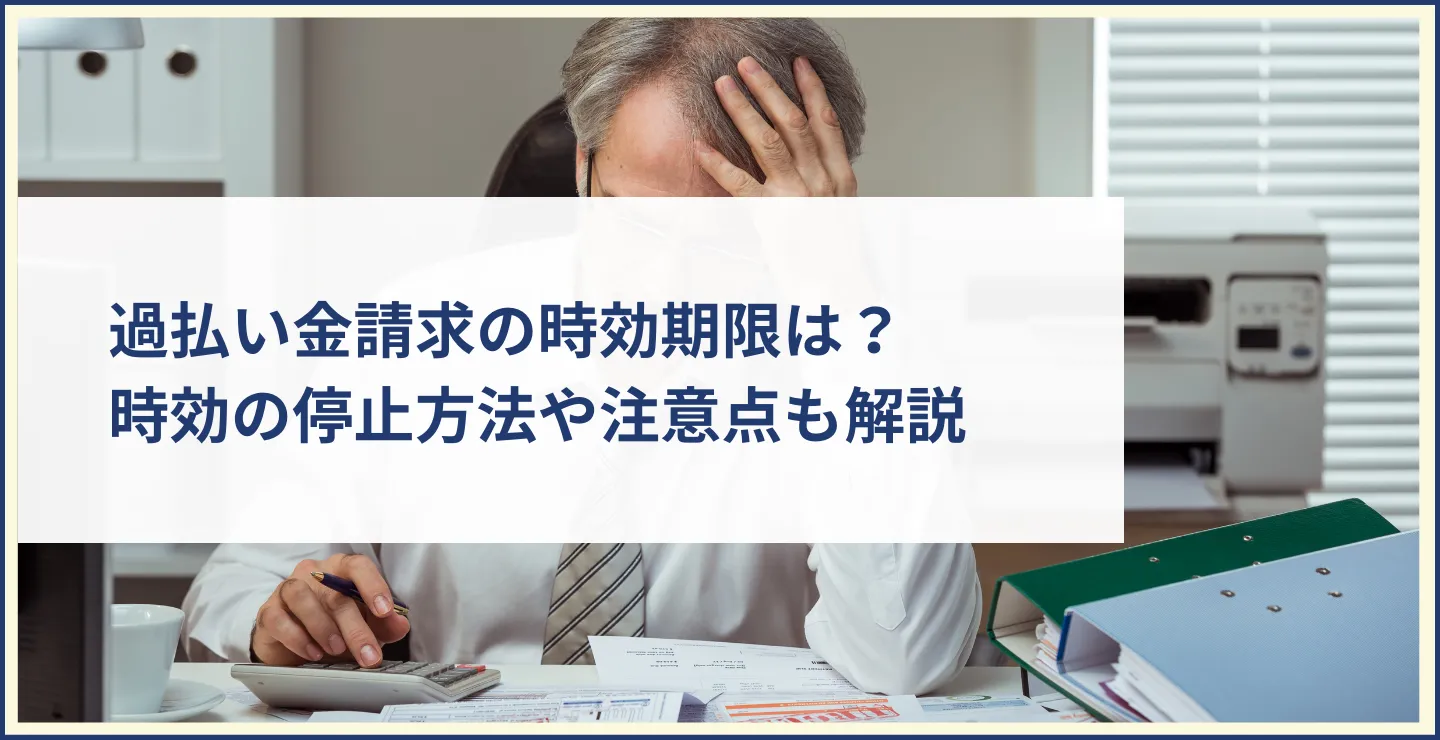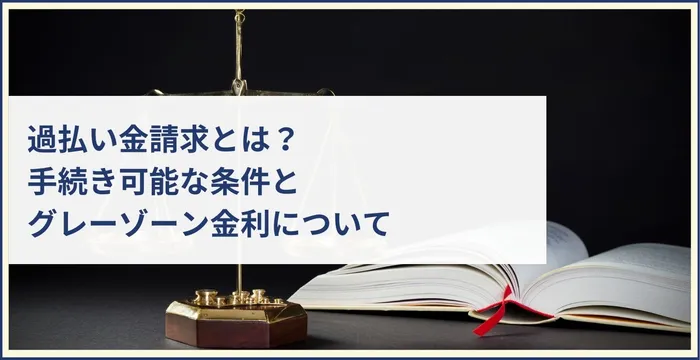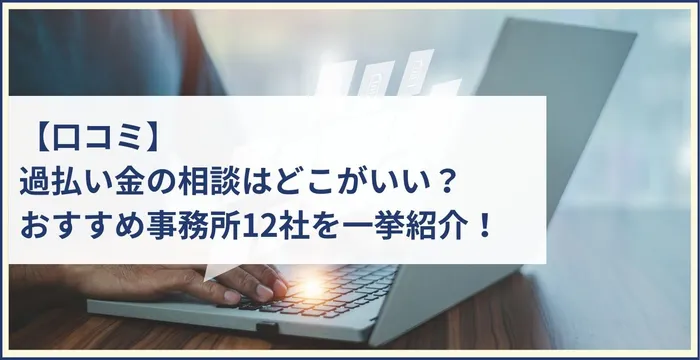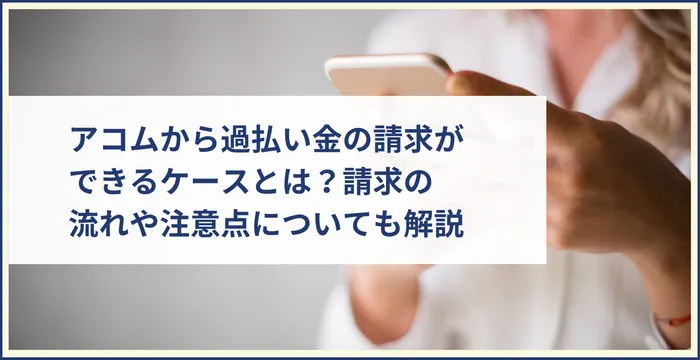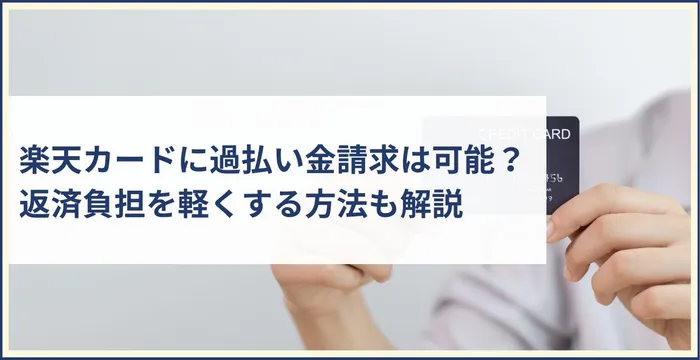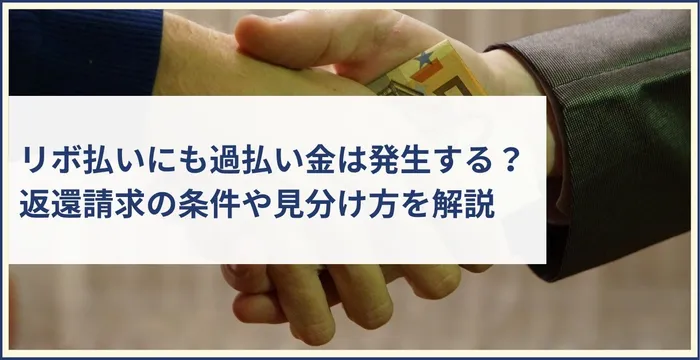過払い金請求の時効は取引終了時期によって変わる
過払い金の請求権は、借金の完済から10年で消滅するのが基本です。返済中の場合は、毎月きちんと返済している限り時効を気にする必要はありませんが、最後に返済したときから10年放置すると消滅します。
ただし、取引終了のタイミングによって以下のように異なります。
- 取引終了が2020年3月31日以前:完済から10年
- 取引終了が2020年4月1日以降:完済から10年または権利行使できることを知ったときから5年
2020年3月31日と4月1日で時効の期間が異なる理由は、2020年4月1日に民法の消滅時効に関する規定が変更されたためです。そのため2020年3月31日までは改正前、4月1日以降は改正後の民法が適用されます。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
引用元 民法第百六十条|e-Gov法令検索
ここでは、過払い金請求の時効について解説します。
過払い金請求の手続き可能な条件とグレーゾーン金利については、以下の記事を参考にしてください。
2020年3月31日までに終了の取引|完済から10年
取引が2020年3月31日までに終了している借金については、完済から10年で時効を迎えます。
たとえば2020年2月1日に借金を完済したあと、その賃金業者からは借入れを行っていなかった場合、時効は完済から10年後の2030年2月1日に成立します。
つまり、過払い金を請求したいなら、2030年2月1日までに以下の手続きを終えておく必要があるということです。
- 取引履歴の開示
- 過払い金の引き直し計算
- 過払い金返還請求書の送付
せっかく過払い金を請求できる権利をもっていても、請求しないまま時効を迎えてしまうと請求できなくなってしまいます。そのためできるだけ早く弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
2020年4月1日以降終了の取引|完済から10年 or 権利行使できることを知ったときから5年
2020年4月1日以降に取引が終了した借金に関しては、改正後の民法が適用されます。
以下のうち、早く経過したほうのタイミングで消滅時効が完成します。
- 完済から10年
- 権利を行使できると知ったときから5年
たとえば、2020年10月1日に借金を完済したとします。過払い金を請求できると知らない場合、10年後の2030年10月1日に時効が完成しますが、2030年9月1日に過払い金を請求できることを知ったなら、時効はそこから5年の2035年10月1日です。
ポイントは、過払い金を請求できることを知ったタイミングです。上記のケースのように、完済から10年が経つ直前まで過払い金を請求できると知らなければ、結果的に完済から10年以上時効は完成しません。
反対に、完済後すぐに過払い金が請求できると知ったときはそこから5年で時効が到来してしまうため、時効の完成までの期間が短いと感じるでしょう。
ただしどちらの場合も、うっかりしていると請求できる機会を逃してしまいます。請求できる可能性があると気づいたら、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
過払い金の時効10年が過ぎていても請求できると判断されるケース
中には以下のように、過払い金の時効である「10年」が過ぎていても請求できるケースがあります。
- 同一の貸金業者から繰り返し借入・返済を行なっている場合
- 貸金業者による不法行為があった場合
それぞれ解説します。
同一の貸金業者から繰り返し借入・返済を行なっている場合
完済から10年経っていても、その後同一の賃金業者から繰り返し借入・返済を行っているときは、「一連の取引である」と判断されて請求が認められる可能性があります。
たとえば以下のケースで考えてみましょう。
・2018年4月1日に1回目の借金を完済した
・2018年7月1日に2回目の借入をし、さらに7カ月後の2019年2月1日に2回目の借入分を完済した
この場合、一連の取引であると判断されれば、1回目の完済からではなく2回目の完済から10年後が時効となる可能性があります。つまり、2028年4月1日を過ぎても、2029年2月1日までであれば過払い金を請求できるということです。
また、一連の取引として扱われると1回目の借入も過払い金請求の対象になるため、その分過払い金の金額が大きくなります。
しかし1回目・2回目の借入をそれぞれ「別の取引」として見るなら、時効は「1回目の完済から10年」と「2回目の完済から10年」の2つ存在することになります。
一連の取引かどうかを判断するポイントは以下のとおりです。
- 契約番号や会員番号が同じである
- 完済から再借り入れまでの空白期間が短い
- 完済から再借り入れまでの空白期間に貸金業者から積極的にキャッシングの勧誘があった
- 借入時の利息などの条件が同じである
それぞれ解説します。
契約番号や会員番号が同じである
1回目も2回目も契約番号や会員番号が同じなら、一連の取引であると判断されやすいです。そのため1回目の完済から10年を過ぎていても、2回目の完済から10年経っていなければ過払い金を請求できる可能性があります。
とくに同じクレジットカードでの借入れは、ほとんどのケースで一連の取引とみなされます。
注意点は、支払い回数が1回の場合、同一の賃金業者から借入を繰り返していても「別の取引である」と判断されることがある点です。
1回目の借入で使用したクレジットカードが失効していたケースも要注意です。クレジットカードが失効してしまうと、カードを再発行することになり会員番号も変わるため、1回目とは別の取引とみなされます。
そもそも、完済後にカードの失効手続きをされた時点で、カード失効前の取引とその後の取引が一連であるとは考えにくいでしょう。そのため、一連の取引であったことを主張する際に不利に働くおそれがあります。
クレジットカードの過払い金を調べる方法や請求の条件については、以下の記事を参考にしてください。
完済から再借り入れまでの空白期間が短い
借金を完済してから次の借入をするまでの空白期間が短ければ、一連の取引と判断してもらえる可能性が高くなります。
目安は、「365日以内かどうか」です。裁判所も、裁判の際は空白期間が365日以内か超えているかを基準に判断する傾向にあります。
ただし契約内容にもよるため、必ずしも365日以内であれば一連として認められ、365日を超えていたら認められないとは言い切れません。
たとえばケースによっては、365日以内でも別の取引と判断されることや、その逆もあり得ます。中には、完済から3カ月間新たな借入を行わないと契約番号が変わり、その後借入をしても一連ではなく別の取引とみなされる場合があります。
そのほか、空白期間前の取引の長さも重要です。
たとえば3年にわたって返済を続け、完済した人がその半年後に2回目の借入をした場合と、1カ月で完済し、同じく半年後に再度借入をした場合なら、3年にわたって返済していた人のほうが一連の取引であると判断されやすいでしょう。
なお、クレジットカードの1回払いは、空白期間が短い場合でも別の取引であると判断されることがありますが、裁判では一連の取引だと認められる傾向にあります。
完済から再借り入れまでの空白期間に貸金業者から積極的にキャッシングの勧誘があった
完済後の空白期間に賃金業者から連絡が入り、キャッシングをすすめられた場合も一連の取引だと認めてもらいやすくなります。賃金業者から声をかけてくるということは、まだ取引が継続しているととれるためです。
ただし、「何度も勧誘の電話がかかってきた」と言ったところで証拠がなければ立証することは難しく、一連の取引であることを主張する際、有利に働かない可能性があります。
借入時の利息などの条件が同じである
借入時の利息や限度額などの条件が前回借入れた際と同じなら、契約自体が前回と同一であると判断されやすいです。反対に、条件が異なると賃金業者から別の取引であると主張される可能性があります。
なお、利率に関しては、法改正を受けて変更される場合があります。そのため、利率の変更を理由に別の取引であると賃金業者に主張されたときは、利率の変更が法改正の影響によるもので、取引の分断にあたらない旨を反論する必要があるでしょう。
貸金業者による不法行為があった場合
賃金業者から受けた行為が不法行為にあたる場合は、時効を過ぎていても過払い金を請求できる可能性があります。
たとえば、以下のような行為です。
- 暴行・脅迫によって返済を迫る
- 過払い金が発生していることをわかっていて請求する
- 毎日電話し、しつこく取り立てる
- 正当な理由なく深夜や早朝(午後9時〜午前8時)に電話・訪問する
- 正当な理由なく債務者の勤務先に電話・訪問する
- 債務者の家族・友人に取り立てる
- 返済させるために、ほかの金融機関などから借金をするよう要求する
- 3人以上で訪問する
賃金業者から不法行為を受けたときの時効は、「過払い金があることを知ったときから3年」です。つまり、最後の取引から10年経っていても、過払い金の存在を知らなければ時効は完成しません。
しかし、不法行為を行うような悪質な業者から過払い金を取り戻すのは難しいでしょう。相手が応じなければ過払い金を取り戻せず、訴訟を提起するにもその業者の所在が明らかであり、不法行為の証拠がなければなりません。
「不法行為に該当するかどうかの判断が難しい」「どのようなものが証拠になるかわからない」というときは、弁護士に相談することをおすすめします。
過払い金請求の時効を中断するために行うべきこと
時効は時間の経過とともに進んでいきますが、「中断」することによって一旦ストップさせたりリセットしたりすることが可能です。
過払い金請求の時効を中断するために行うべきことは以下の2つです。
- 過払い金請求を裁判所に申し立てる
- 貸金業者に過払い金返還請求書を送る
それぞれ解説します。
過払い金請求を裁判所に申し立てる
時効を中断する方法の1つは、過払い金請求を裁判所に申し立てることです。申立てが認められると時効が中断され、進行していた時効が一旦ストップします。
さらにそのあと判決が下されると時効はリセットされ、また1から進行します。つまり、時効が10年延長されるのと同じです。
なお、以下の申立てを行ったときも、過払い金請求を申し立てた場合と同様に時効が中断されます。
過払い金を請求する際は、賃金業者から取引履歴を取り寄せたり信用情報機関に開示請求したりなどして、正しい取引期間を調べる必要があります。
取引履歴や信用情報の開示請求は自分でもできますが、個人からの請求は後回しにされる可能性があるため、時効が迫っているときは自分で対応するよりも弁護士や司法書士といった専門家に依頼したほうがよいでしょう。
過払い金の請求を専門家に依頼した場合でも、申立ての準備に時間がかかることがあります。そのため専門家に依頼するときは、できるだけ早めに相談することをおすすめします。
貸金業者に過払い金返還請求書を送る
賃金業者に「>過払い金返還請求書」を送ることでも時効は中断できます。過払い金返還請求書を送る行為は、時効を中断する「催告」にあたるためです。
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
引用元 民法第百五十条|e-Gov法令検索
【過払い金返還請求書とは】
過払い金を返還してもらえるよう求める請求書のこと。いつ誰が誰にどのような文書を送付したかを郵便局に証明してもらえる「内容証明郵便」で送付するのが多い。期限を設けて回答をもらえるようにし、期日までに回答がない場合はやむを得ず訴訟を提起する旨を記載するのが一般的。
過払い金返還請求書を送付すると、6カ月間だけ時効を止められます。
注意点は、一度きりしか使えない点です。たとえば過払い金返還請求書を送ることで時効を止め、時効がまた進行し始める直前に再度請求書を送っても、時効の中断をさらに6カ月延長することは不可能です。
このように、催告には時効を一時的に止める効果しかありません。前項で解説したような「裁判上の請求」をしなければ、時効はリセットできないことを念頭に置いておきましょう。
また、過払い金返還請求書を作成するためには、以下の手順で過払い金の正確な金額を調べる必要があります。
- 賃金業者に取引履歴を開示請求する
- 引き直し計算をする
【引き直し計算とは】
取引履歴をもとに、利息制限法に基づく利率を用いて利息を計算し直すこと。
引き直し計算は、方法さえわかれば自分でもできます。
しかし、慣れていなければミスをする可能性があり、正確な金額を算出できません。弁護士や司法書士に対応を依頼するのが確実でしょう。
なお、取引履歴を開示請求しただけでは時効を止められません。債権者に過払い金返還請求書を送付しなければ、時効は中断できないことを覚えておきましょう。
過払い金の計算方法については、以下の記事を参考にしてください。
過払い金請求の際に対応すべきこと
過払い金を請求する際は、以下のことを行う必要があります。
- 時効の起算点と時効の時期がいつかを確認する
- 貸金業者が倒産していないか確認する
- 過払い金請求が得意な弁護士へ相談する
それぞれ解説します。
時効の起算点と時効の時期がいつかを確認する
過払い金を請求するときは、まず「時効の起算点」と「時効の時期」を確認しましょう。
時効の起算点とは、時効のカウントを始めるタイミングです。「過払い金請求の時効は取引終了時期によって変わる」で解説したとおり、以下の2つのパターンがあります。
- 2020年3月31日以前:取引終了(完済・借入・返済)のタイミング
- 2020年4月1日以降:取引終了か権利を行使できると知ったタイミング
取引終了のタイミングとは、最後の取引があったときです。完済のほかにも、借入や返済を最後に取引が終わっているときは借入や返済が最後の取引になります。
権利を行使できると知ったタイミングについては、賃金業者に取引履歴を開示請求し、過払い金があることを知ったときと考えればよいでしょう。
いつ取引を終了したかを覚えていないときや手元に利用明細書が残っていない場合は、取引履歴で確認できます。
ただし、起算点は契約内容や債務状況、賃金業者によって異なるケースがあるため注意しましょう。たとえば「貸付停止措置」をとられていると、貸付が止められたときが起算点であると債権者側から主張される可能性があります。
【貸付停止措置とは】
以下のような理由から、賃金業者が貸付を止めること。
・債務整理手続きを開始した
・ブラックリストに載った
・滞納や利息しか払えない状態が続いている
・転職先を賃金業者に伝えなかった
・カードを解約した
・賃金業者が廃業した
取引履歴は電話やFAX、郵送などで請求できますが、賃金業者によって異なります。中には、専用の開示請求書が必要なところもあるため、まずは電話やホームページなどから問い合わせてみるとよいでしょう。
請求から開示までにかかる期間も、1週間〜10日、1カ月など、賃金業者によってまちまちです。費用は1,000円程度かかる場合があります。
貸金業者が倒産していないか確認する
賃金業者が倒産していないかどうかも確認する必要があります。吸収合併であればまだ請求できる可能性はありますが、倒産してしまった場合は時効完成前でも過払い金を請求できなくなるためです。
現に、過払い金の請求が頻繁に行われるようになったことで多くの賃金業者が経営難に陥り、倒産に追い込まれています。中には武富士やクラヴィスなど、大手消費者金融が倒産した例もあります。
とくに完済から時間が経っていれば、「昔借入をしていた業者が知らないうちに倒産していた」ということも珍しくないでしょう。
なお、倒産していなくても、賃金業者の経営状況によっては予算がなく、取り戻せるお金が減ってしまうケースもあります。
今後も賃金業者の倒産によって過払い金を回収できなくなるケースは増える可能性があるため、過払い金の請求を検討しているなら早めに行動したほうがよいかもしれません。
過払い金請求が得意な弁護士へ相談する
過払い金を請求したいなら、過払い金請求を得意としている弁護士に相談するのがおすすめです。
過払い金請求を弁護士に依頼したほうがよい理由は以下のとおりです。
- 過払い金を正確に計算してもらえる
- 個人からの取引履歴開示請求を賃金業者が後回しにする場合がある
- 自分で交渉するよりも多くの過払い金を取り戻せる可能性がある
- 弁護士をつけないまま裁判になった場合、相手に弁護士がついているとこちらが不利になるおそれがある
過払い金は自分でも請求できますが、自分で請求した場合、まず正確な計算ができない可能性があります。
また、賃金業者のほとんどが、過払い金を請求されても満額の支払いに応じてくれないのが現状です。賃金業者と交渉し、できる限り有利な結果に持っていくには、知識と経験がなければ難しいでしょう。
裁判になったときも、弁護士がついていなければ自分で書面を作成し、相手の主張に反論していかなければなりません。しかし弁護士に依頼すれば、手続きや法的知識が必要な場面でも対応を一任できます。
なお、取引履歴の開示や引き渡し計算に時間がかかるため、請求するまでに数カ月かかることもあります。とくに時効が迫っている状況なら、できるだけ早く弁護士に相談すべきでしょう。
まとめ
過払い金請求の時効期限や時効の停止方法、注意点について解説しました。
過払い金請求の時効は、基本的には「完済から10年」です。ただし2020年4月1日以降に終了した取引に関しては、完済から10年または権利行使できることを知ったときから5年です。
時効を過ぎると過払い金請求権は消滅し、請求できなくなるため時効を迎える前に請求しなければなりません。
例外的に10年を過ぎていても請求できるケースには、同一の賃金業者から繰り返し借入と返済を行っているときや、賃金業者から不法行為を受けていた場合などが該当します。
過払い金を請求する際は時効の起算点や時効の時期、賃金業者が倒産していないかなどを確認しましょう。
ベストなのは、過払い金請求が得意な弁護士に相談することです。弁護士に相談・依頼することで、自分で手続きするよりもスムーズに請求できたり過払い金を多く取り戻せたりといったことが期待できます。
時効が迫っているなら、できるだけ早く相談することをおすすめします。
過払い金請求の時効についてよくある質問
時効がすぎていないのに、過払い金請求できないパターンはありますか?
時効が過ぎていなくても、以下のケースではそもそも過払い金が発生しない可能性があります。
- 2010年6月の賃金業法改正以降に借入をした
- 利息制限法の範囲内での借入だった
- クレジットカードのショッピング枠のみ利用していた
- 借入をした賃金業者が倒産している
賃金業法が改正されたあとに借入れた分については、過払い金が発生する原因となる「グレーゾーン金利」で借入をしていないと考えられるため、過払い金が発生しない可能性が高いです。
【グレーゾーン金利とは】
利息制限法と出資法が定めるそれぞれの上限金利の間の金利のこと。2006年に出資法の上限金利(29.2%)が20%に引き下げられるまでは、利息制限法の上限金利(15〜20%)を超えていても出資法の上限金利を超えない限り刑事罰の対象にならなかったため、違法な金利を取られていた。
また、金利が利息制限法の範囲内で設定されていた場合や、クレジットカードのショッピング枠のみを利用していたケースも、過払い金は発生しないため請求できません。
そのほか、記事の中で解説したとおり、借入をした賃金業者がすでに倒産しているときも請求できません。
このように、時効を過ぎていなくても、過払い金を請求できないケースはあります。
なお、もし時効を過ぎても、すぐに.請求できなくなるわけではありません。時効は、債権者が「時効の援用」をしてはじめて効果が発生するためです。
【時効の援用とは】
時効が完成したことを主張すること。
賃金業者が時効を援用しなければ、過払い金返還請求権は消滅しません。
とはいえ、賃金業者が時効の完成を見落とすとは考えにくいため、時効が過ぎてしまった場合は時効を援用されるのが通常であると思っておきましょう。
過払金調査や無料診断は気軽に受けても大丈夫でしょうか?
過払い金調査や無料診断は、口コミや評判を見てから受けたほうがよいでしょう。
過払い金調査や無料診断を行っている事務所のうち、一部の事務所は債務者側ではなく賃金業者側寄りの立場で「時効が完成しているか」「過払い金が請求できるか」といったことを判断しているためです。
実際に、過去の判例から一連の取引であると認めるのが妥当といえる取引に対して、すでに無効であると回答した例もあります。
過払い金の無料診断を利用するデメリットや注意点については、以下の記事で解説しています。あわせてチェックしてみてください。