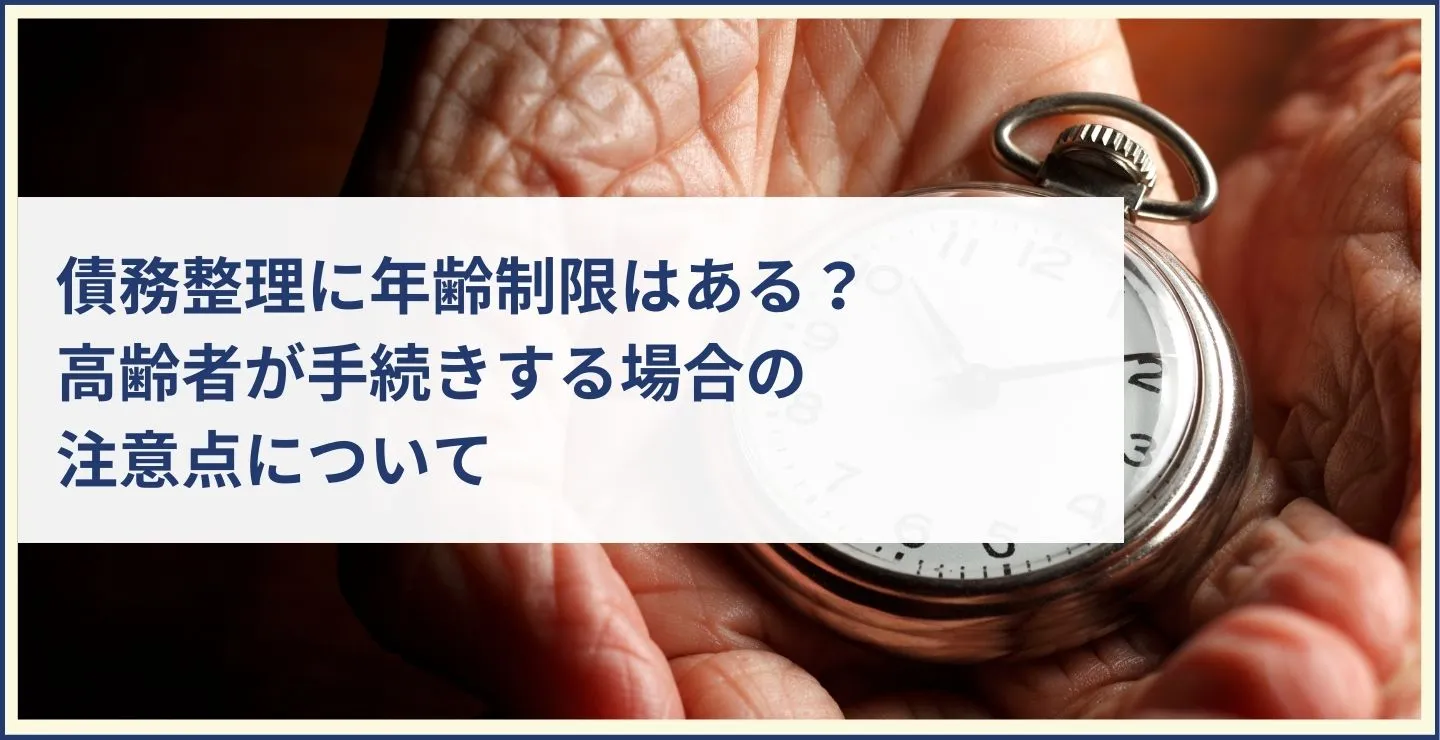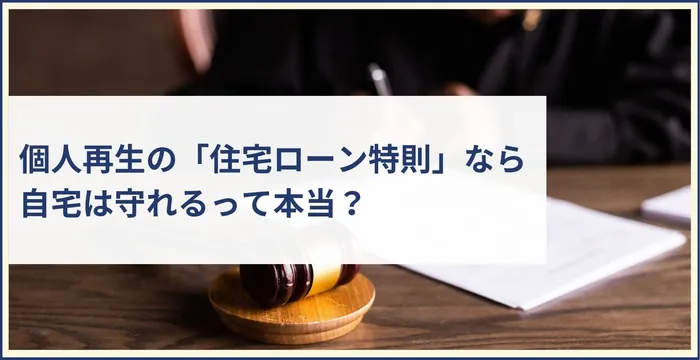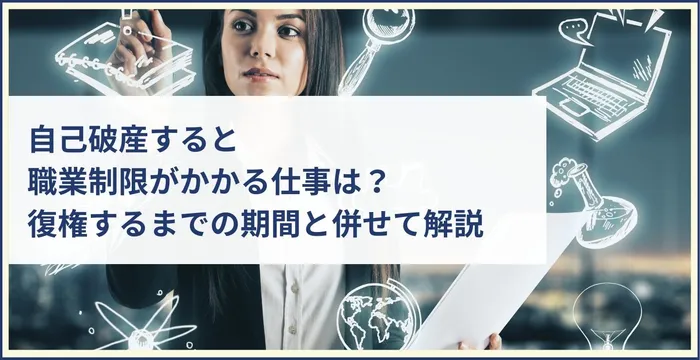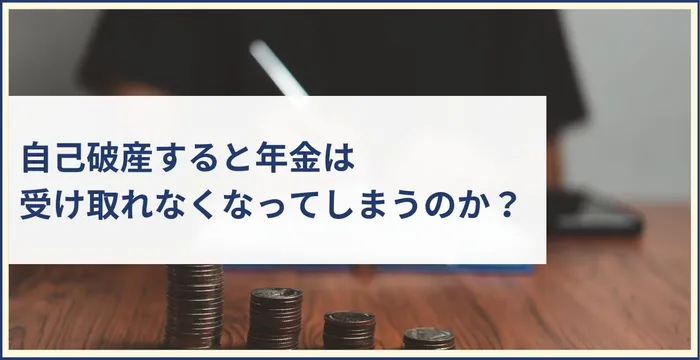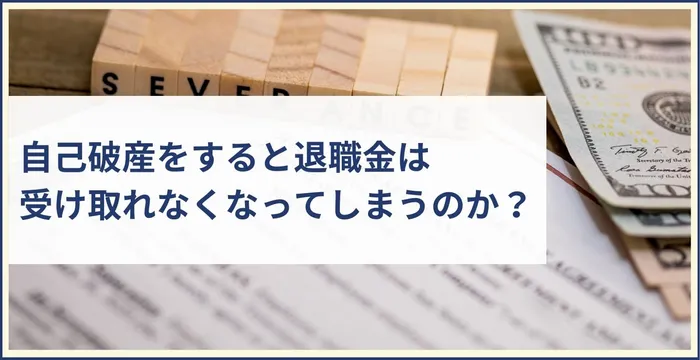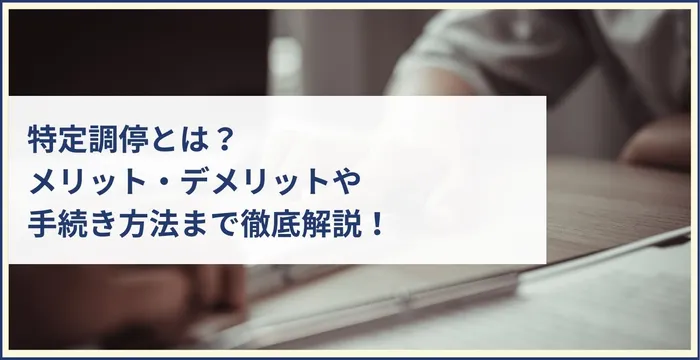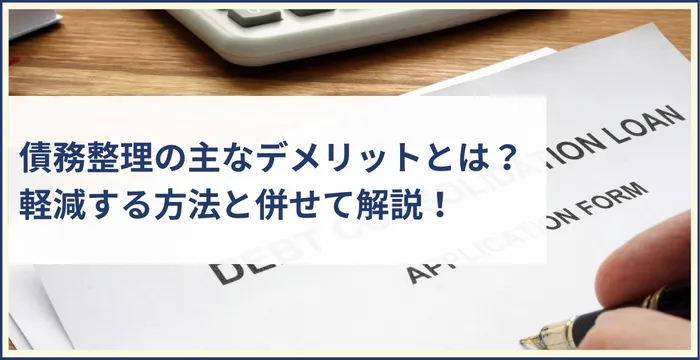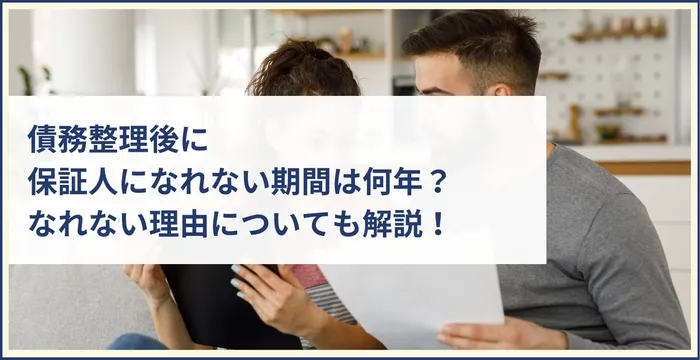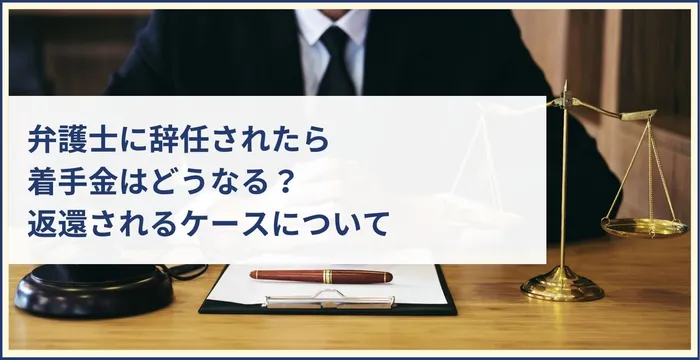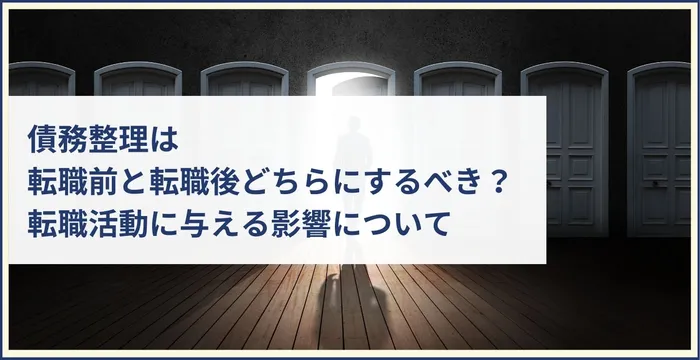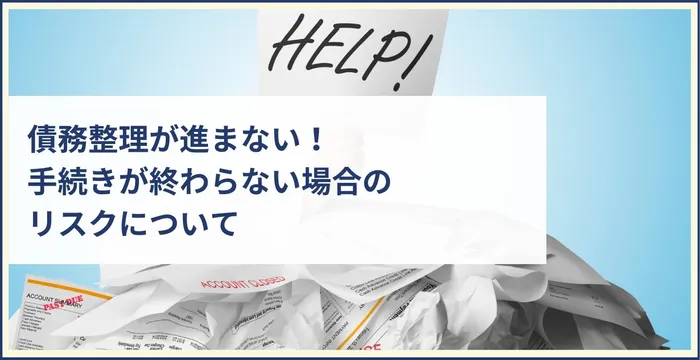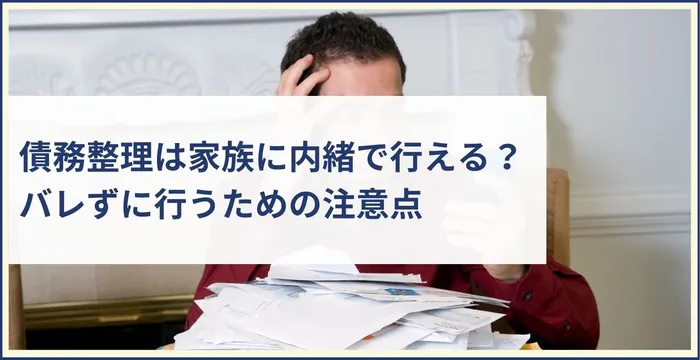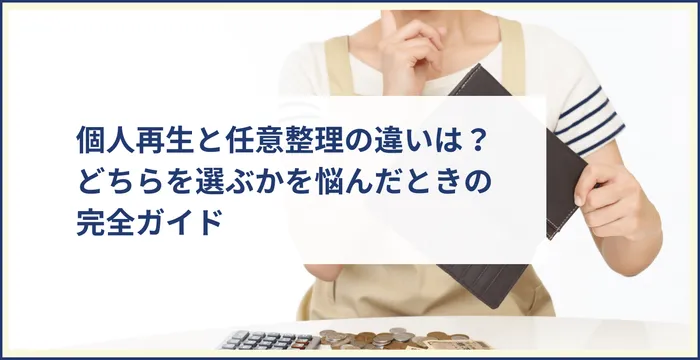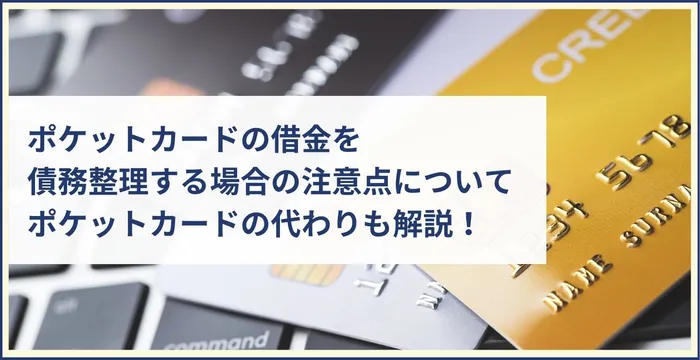債務整理の手続き自体に年齢制限はない
債務整理の手続きには「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類ありますが、いずれも年齢制限はありません。任意整理は債権者と個別に交渉する裁判外の手続きなので、年齢を理由に手続きを制限する法律上の規定はありません。
自己破産と個人再生は、それぞれ下記の法律に基づいて手続きが行われますが、いずれの法律にも年齢に関する条文は存在しません。
そのため、各手続きの条件を満たしていれば、原則的には何歳であっても債務整理が行えます。
債務整理をするには各手続きの条件を満たしている必要がある
債務整理に年齢制限はありませんが、債務整理をするには各手続きの条件を満たしている必要があります。債務整理をするための条件は、下記のように手続きの種類によってそれぞれ異なります。
|
条件 |
| 任意整理 |
・債権者が交渉に応じてくれる
・借金額が比較的少なく、継続的かつ安定した収入がある
・減額後の借金を原則3~5年以内に完済できる見込みがある
・借金を返済した実績がある |
| 個人再生 |
・住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下
・継続的かつ安定した収入がある
・減額後の借金を原則3年以内に完済できる見込みがある |
| 自己破産 |
・支払不能な状態である
・免責不許可事由に該当していない
・非免責債権に該当しない債務がある |
ここからは、それぞれの条件について詳しく解説していきます。
任意整理をするための条件
任意整理とは、返済計画を見直してもらうために裁判外で債権者と直接交渉する手続きです。任意整理をするためには、以下の4つの条件を満たす必要があります。
- 債権者が交渉に応じてくれる
- 借金額が比較的少なく、継続的かつ安定した収入がある
- 減額後の借金を3~5年以内に完済できる見込みがある
- 借金を返済した実績がある
前提として、任意整理はあくまで「話し合いによる合意」が前提となるため、債権者が交渉に応じてくれなければ、任意整理は成立しません。
任意整理の交渉が成立した場合、手続き後に元金自体を3年~5年程度で返済していくことになるケースが多く、期間内に完済できるだけの安定した収入が必要です。そのため、安定した収入さえあれば、年金生活者やアルバイトでも任意整理できる見込みはあります。
「収入に対して借金額が多い」「収入が不安定」などの理由で3~5年以内に完済できる見込みがない場合は、他の手続きを検討する必要があるでしょう。また、借金を返済した実績が一度もない場合は、債権者が任意整理に応じてくれない可能性が高いです。なぜなら、最初から借金を返済できないことが分かっていながら、それを隠して借金をしたと債権者に思われる可能性があるためです。
そのため、任意整理に応じてもらうためには、一定期間返済実績を作って債権者と信頼関係を築いておくことが重要になります。
個人再生をするための条件
個人再生とは、裁判所に申し立てを行い、認可を受けることで借金の元本を大幅に減額してもらい、原則3年で分割返済していく手続きです。借金を5分の1から10分の1程度に圧縮できるため、任意整理では返済が難しい方にも有効な手段となります。
個人再生をするためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 住宅ローンを除く借金の総額が5,000万円以下
- 継続的かつ安定した収入がある
- 減額後の借金を原則3年以内に完済できる見込みがある
民事再生法231条では、住宅ローンを除いて借金の総額が5,000万円以下の場合のみ個人再生の申し立てを認めています。
第二百三十一条 小規模個人再生において再生計画案が可決された場合には、裁判所は、第百七十四条第二項(当該再生計画案が住宅資金特別条項を定めたものであるときは、第二百二条第二項)又は次項の場合を除き、再生計画認可の決定をする。
二 無異議債権の額及び評価済債権の額の総額(住宅資金貸付債権の額、別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債権の額及び第八十四条第二項に掲げる請求権の額を除く。)が五千万円を超えているとき。
引用元 民事再生法 | e-Gov 法令検索
住宅ローンを除外しても借金の総額が5,000万円を超える場合は、自己破産を検討する必要があるでしょう。また、個人再生も任意整理と同じように手続き後も返済義務が残り、減額後の借金は原則3年かけて分割で返済していくことになります。
そのため、個人再生をするには継続的かつ安定した収入が必要です。
なお、雇用形態に明確な決まりはないため、年金受給者やアルバイト・パートであっても収入の継続性と安定性があれば認められるケースもあります。
自己破産をするための条件
自己破産とは、裁判所に申し立てて免責許可を得ることにより、原則すべての借金の返済義務を免除してもらう手続きです。自己破産をするためには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 支払不能な状態である
- 免責不許可事由に該当していない
- 非免責債権に該当しない債務がある
自己破産は収入が不安定な人や無収入の人でも手続きが可能ですが、支払不能な状態に陥っていることが条件になります。破産法では、支払不能な状態を借金の返済に充てる収入や資産が不足しており、借金を期日までに返済できない状況が継続している状態と定義しています。
第二条
11 この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。
引用元 破産法 | e-Gov 法令検索
そのため、一時的なに返済が難しくなっており、今後仕事に復帰して借金を返済できる見込みがある場合や、収入が不安定・無収入でも高額な預貯金や高価な財産を保有している場合は支払不能とはいえず、自己破産が認められない可能性があります。
また、借金の理由や行動が免責不許可事由に該当していたり、債務の内容が非免責債権に該当していたりする場合は、原則として裁判所から免責許可が下りません。
非免責債権とは、自己破産で免責が認められたとしても、支払い義務が一切免除されない債権のことをいいます。
具体的には、以下のような行為が免責不許可事由や非免責債権に該当します。
| 免責不許可事由 |
非免責債権 |
・特定の債権者にだけ返済した
・差押えを逃れるために家族や親戚に財産を渡した
・財産目録に財産を正確に記載しなかった
・収入に見合わない浪費やギャンブルで多額の借金を抱えた
・裁判所の調査で説明を拒否したり、虚偽の説明をしたりした
・過去7年以内に自己破産をした
|
・租税公課(税金や社会保険料など)の滞納分
・罰金や科料、過料、反則金、刑事訴訟費用の滞納分
・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償義務
・故意や重い過失により加えた、人の生命や身体を害する不法行為に基づく損害賠償義務
|
ただし、免責不許可事由の場合は、該当していても裁判所の裁量で自己破産が認められるケースもあります。一方、非免責債権に該当する債務しかない場合は、自己破産しても支払い義務がそのまま残るため、そもそも手続きを行う意味がありません。
そのため、分割支払いや交渉による和解など別の方法を検討する必要があるでしょう。
高齢者が債務整理をする場合に事前に知っておくべきこと
債務整理には年齢制限がないため、高齢者であっても年齢だけが原因で手続きを行えないことはありません。しかし、高齢者の場合には収入などが原因となって、債務整理が難しくなるケースも少なくないため、事前に下記のポイントを把握しておくようにしましょう。
- 高齢の場合には任意整理や個人再生が難しいケースがある
- 債務者が認知症の場合には成年後見人が必要なことがある
- 債務整理によって持ち家を失うケースがある
ここからは、それぞれの確認事項について1つずつ詳しく解説していきます。
高齢の場合には任意整理や個人再生が難しいケースがある
任意整理や個人再生は、手続き後も借金を返済していかなければならないため、返済に充てられるだけの安定した収入が求められます。
借金問題に直面している高齢の方のなかには、公的年金のみで生活している方や、体調面の理由から就労が難しい方もいることでしょう。
特に年齢を重ねると、加齢に伴う体力の低下や持病の悪化など、将来的な健康状態の変化も考慮する必要があります。
今は健康的に仕事を続けられる状態であっても、数ヶ月後や1年後には健康上の問題で仕事を続けられなくなってしまう可能性は否定できません。
そのため、収入面に加えて健康状態が良好であることも求められたり、高齢であることを理由に債権者に任意整理を断られたりする場合もあります。これらを踏まえると、高齢者が任意整理や個人再生をするのは現役世代と比べてハードルが高いといえます。
債務者が認知症の場合には成年後見人が必要なことがある
債務者が認知症を発症している場合、症状の程度によっては債務整理の際に成年後見人が必要になる場合があります。
成年後見人とは、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人に代わり、財産管理や契約締結などを行う人のことで、家庭裁判所によって選任されます。
判断能力が不十分な人の法律行為は無効になるため、認知症の進行によって債務者に十分な判断能力がない場合は、債務者の住所地を管轄する家庭裁判所に成年後見人の選任を申し立てる必要があります。
成年後見人になるのに特別な資格はなく、下記の通り民法847条で定められた欠格事由に該当していない人なら誰でも候補者になれます。
第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。
一 未成年者
二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
三 破産者
四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
五 行方の知れない者
引用元 民法 | e-Gov 法令検索
ただし、成年後見人は家庭裁判所の裁量で選任されるため、申し立ての際に希望した候補者が必ず選任されるとは限りません。家族や親族以外だと、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースが多いです。
専門家が選任された場合は、あくまでも目安ですが、報酬として毎月2〜6万円前後の費用が発生するのが一般的です。さらに、成年後見制度は一時的な制度ではなく、原則として下記のケースに該当しない限りは継続されます。
- 認知症を患っている本人が亡くなった
- 判断能力が回復して家庭裁判所が後見開始の審判を取り消した
- 後見人が本人にとって不利益となる不正を働いているのが見つかり解任された
後見人が亡くなったり辞任したりした後も、本人が回復しない状態で存命の限り成年後見制度は続きます。そのため、「債務整理の手続きを済ませるためだけに、一時的に成年後見制度を利用する」といった使い方はできません。
上記の条件により利用が終了するまでは、毎月報酬が発生し続けることも頭に入れておきましょう。
債務整理によって持ち家を失うケースがある
任意整理や個人再生の場合、住宅ローンがない持ち家であれば手元に残したまま手続きが可能です。しかし、持ち家の住宅ローンの返済がまだ終わっておらず、その住宅ローンも債務整理の対象に含まれる場合は持ち家を没収されてしまいます。
ただし、任意整理と個人再生の場合は、下記の対処法を利用することで、住宅ローンが残っていても持ち家の処分を回避できます。
| 任意整理 |
債務整理の対象から住宅ローンを外す |
| 個人再生 |
「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用する |
対して自己破産の場合は、住宅ローンの返済状況にかかわらず、原則として持ち家は没収されてしまいます。自己破産は借金を帳消しにする代わりに、換価価値が原則20万円を超える本人名義の財産は、手放さなければなりません。
個人再生では住宅ローン特則を使用すれば家の没収を回避できる
住宅ローン特則とは、個人再生手続きの中で住宅ローンを対象から除外し、マイホームを手放さずに他の借金だけを減額できる制度です。住宅ローンの返済をこれまで通り継続しながら、カードローンや消費者金融などの無担保債務のみを大幅に圧縮できます。
そのため、住宅を維持したい人にとっては非常に大きなメリットとなるでしょう。ただし、利用する際は下記の条件を満たす必要があります。
- 住宅の購入、又は改良に必要な資金であること
- 対象となる住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されていないこと
- 本人が所有し、居住している住宅であること
- 保証会社による代位弁済後、6か月を経過していないこと
- 税金を滞納していないこと
住宅ローン特則は、該当する家が「生活の拠点」であることが大前提となります。そのため、名義上は本人の所有であっても、実際に居住していない場合は対象から外れます。
また、住宅に住宅ローン以外の抵当権が設定されている場合、その債権者が抵当権を行使して住宅を競売にかける可能性があります。その場合、住宅は強制的に競売にかけられてしまうため、住宅ローン特則の利用自体ができません。
関連して注意すべきなのが「代位弁済」です。これは、住宅ローンの契約者が返済できなくなったときに、保証会社が本人に代わってローンを肩代わりする仕組みです。
この代位弁済が行われた場合、その日から6か月以内に個人再生を申し立てなければ、住宅ローン特則は利用できません。期限を過ぎると、保証会社が抵当権を行使して住宅を競売にかける可能性が高くなります。
さらに、税金は債務整理の手続きにかかわらず優先的な返済を求められる「一般優先債権」に該当します。差し押さえの原因となるため、特則を適用しても家を守りきれないリスクがあることも覚えておきましょう。
高齢者が債務整理をする場合に生じる生活への影響は?
高齢者が債務整理をすると、年金の受給や退職金の受け取り、同居する家族などに影響を及ぼさないか心配という方も多いでしょう。高齢者が確認しておきたい債務整理による生活の影響としては、以下の4つが挙げられます。
- 家族と同居していても債務整理はできるが間接的に悪影響を及ぼす可能性がある
- 職業によっては一定期間業務が行えない可能性がある
- 債務整理をしても公的年金は受け取れる
- 債務整理をしても退職金は受け取れる
ここからは、それぞれの影響について1つずつ詳しく解説していきます。
家族と同居していても債務整理はできるが間接的に悪影響を及ぼす可能性がある
家族と同居していても債務整理はできますが、間接的に家族に悪影響を及ぼす可能性があります。基本的に、債務整理によるデメリットは債務者自身だけに影響するため、直接的な影響は家族に出ることはありません。
そのため、家族名義の財産が処分されたり、家族もブラックリスト入りになったり、家族の仕事に影響を及ぼしたりすることもないのが一般的です。しかし、状況によっては以下のように家族にも間接的な影響を及ぼす場合があります。
- 本人名義の持ち家が処分され、同居家族も転居を余儀なくされる可能性がある
- 家族が連帯保証人となっている借金を債務整理すると、その家族が債権者から一括請求を受ける
- 本人名義のクレジットカードに付帯する家族カードが使えなくなる
- 債務整理をした本人は子供の奨学金の連帯保証人になれない可能性がある
家族と同居している場合や家族が連帯保証人になっている場合は、事前にこれらの影響について家族に説明しておくことをおすすめします。
職業によっては一定期間業務が行えない可能性がある
自己破産の場合のみ、下記の表に該当する職業は一定期間業務が行えない可能性があります。なぜなら、いずれも高い社会的信用が求められる職業であるためです。自己破産が本人の責任でない場合でも、破産に対する世間のマイナスイメージにより、職業全体の信頼性が損なわれるおそれがあります。
また、弁護士や後見人、警備員などのように、他人の財産を管理・保護する職業では、破産者がその職に就くことで依頼者から不安を抱かれるリスクがあるのも職業制限が設けられている理由です
|
職業制限を受ける職業・資格 |
| ジャンル |
職業制限を受ける職業・資格 |
| 士業系 |
弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士、弁理士、土地家屋調査士、不動産鑑定士、宅地建物取引士、中小企業診断士、通関士など |
| 公職系 |
人事院の人事官、教育委員会の教育委員、公正取引委員、公証人、固定資産評価員など |
| 団体企業の役員 |
日本銀行、信用金庫、商工会議所、金融商品取引業、労働派遣業などの役員 |
| 会社法上の役員 |
取締役、執行役員、監査役など |
| その他 |
警備業者の責任者や警備員、貸金業者の登録者、生命・損害保険募集人、証券外務員、旅行業務取扱の登録者や管理者、質屋を営む者など |
これらの職業に従事している人は、破産手続開始が決定してから免責が確定して資格制限が解除されるまでは、一時的に仕事ができなくなります。
あくまでも目安ですが、破産手続開始決定から免責確定までは4ヶ月〜1年程度かかるのが一般的です。そのため、その期間は勤務先に相談して別の部署で働いたり、一時的に休職したりなどの対応が必要です。
なお、自己破産のみを理由に会社を解雇されることは基本的にありません。しかし、人事院の人事官や教育委員会の委員、公正取引委員会の委員といった一部の公務員は、法令によって退職させられることになります。
会社役員や団体企業の役員は破産手続開始決定後に一旦退任となりますが、会社役員は手続き中でも株主総会で再任されれば役員に留まることが可能です。免責許可が下りた後に復権すれば以前と同じように働けるようになり、役員にも復帰できるようになります。
債務整理をしても公的年金は受け取れる
債務整理の手続きが終了した後も、公的年金はこれまで通り受給できます。公的年金とは国が管理・運営する年金制度のことで、具体的には以下のものが公的年金に該当します。
| 公的年金の種類 |
概要 |
| 国民年金 |
20歳以上の人に加入が義務付けられている年金 |
| 厚生年金 |
会社員や公務員が加入する年金 |
| 共済年金(現在は厚生年金に統一) |
公務員や私立学校教職員などの共済組合員が加入する年金 |
公的年金の受給権は最低限の生活を保障するものとして差し押さえが法律で禁止されているため、どの債務整理をしても公的年金が受給できなくなったり、減額されたりすることはありません。
ただし、年金が振込まれる銀行口座が債権者によって差し押さえられると、口座の中の年金分まで一時的に引き出せなくなるおそれがあります。年金を受け取る口座は、債務整理の対象となっていない金融機関に変更しておくのが安全です。
個人年金は処分の対象になるため注意
自己破産しても公的年金は処分されませんが、個人年金は処分の対象になります。個人年金とは、民間の保険会社との契約に基づいて積み立てている年金のことです。
個人年金は公的年金とは違って法律で差し押さえが禁止されておらず、現金や預貯金、不動産、車などと同様に金銭的価値がある財産として扱われます。
そのため、個人年金の返戻金が原則20万円を超える場合は強制解約され、債権者への配当に回されるため、個人年金は受給できなくなります。
債務整理をしても退職金は受け取れる
債務整理をしても退職金の受け取りは可能ですが、債務整理の種類によって下記のように受け取れる金額は異なります。
| 債務整理 |
処分される退職金 |
| 任意整理 |
原則なし |
| 個人再生 |
原則なし |
| 自己破産 |
しばらく退職の予定がない場合:退職金支給見込額の8分の1
近々退職する予定がある場合:退職金支給見込額の4分の1
すでに退職金を受け取っている場合:残っている退職金全額 |
ここからは、それぞれの債務整理で受け取れる退職金について見ていきましょう。
任意整理は退職金を全額受け取れる
基本的に任意整理では、退職金を含む財産の処分は求められません。退職金の受け取りに影響はなく、手元に残しておけます。
ただし、債権者との交渉の中で、退職金の支給が確実と見込まれる場合には、「その一部を返済にあててほしい」と求められるケースがあります。
退職金を返済に充てるのは法律上の義務ではありません。しかし、分割返済の合意を得るための条件として話し合いの中で出されることがあるのです。
そのため、近いうちに退職を予定している方が任意整理を行う場合は、退職金の使い道も含めて弁護士に相談し、無理のない返済計画を立てることが大切です
個人再生は退職金が清算価値に含まれる可能性がある
個人再生も、任意整理と同様に退職金を退職金を含む財産の処分は求められません。ただし、退職金の見込額や退職する時期によっては「清算価値」として計上されます。
清算価値とは、債務者の差し押さえ禁止財産以外を売却したと仮定して算出された財産の価値のことです。
個人再生では、この清算価値をもとに「最低限返済しなければならない金額」が決まります。退職金も金額や時期によっては下記のように返済額の算定に影響を与えるため、場合によっては高額な残債を支払わなければならない可能性があります。
| 退職金を既に受け取っている場合 |
受け取った退職金の全額が清算価値に計上される |
| 近々退職する予定がある場合 |
退職金見込額が80万円以上ある場合:4分の1が清算価値に計上される
退職金見込額が80万円以下の場合:清算価値に入らない |
| 退職の予定がない場合 |
退職金見込額が160万円以上ある場合:8分の1が清算価値に計上される
退職金見込額が160万円以下の場合:清算価値に入らない |
個人再生手続きでは、まだ退職していない場合も退職金の見込額を証明するために、勤務先から「退職金見込額証明書」を取得して提出する必要があります。退職金見込額証明書には、現在の勤続年数や退職金の計算方法、見込額などが記載されます。
個人再生について会社に知られずに退職金見込額証明書を取得したい場合は、下記の方法で取得するのがおすすめです。
- 「住宅ローンの審査に必要」と伝える
- 退職金規程に関する記載があれば「就業規則」などで代用できる場合もある
自己破産は一部退職金が処分される
自己破産した場合は、将来受け取る予定の退職金も処分の対象になります。しかし、処分の対象となる退職金の金額は、手続きを開始した時点の状況によって異なります。
| 状況 |
処分対象の範囲 |
| しばらく退職の予定がない場合 |
退職金支給見込額の8分の1 |
| 近々退職する予定がある場合 |
退職金支給見込額の4分の1 |
| すでに退職金を受け取っている場合 |
残っている退職金全額 |
退職金支給見込額の4分の3は法律で差し押さえが禁止されているため、退職金をまだ受け取っていない場合は残りの4分の1が処分の対象になります。
しかし、しばらく退職の予定がない場合は将来の不確定要素が考慮されるため、多くの裁判所では8分の1のみを処分の対象とするように定めています。
なお、以下の退職金は法律で全額差し押さえが禁止されているため、自己破産しても全額受給することが可能です。
| 退職金制度の種類 |
該当する退職金 |
| 確定拠出年金制度 |
個人型確定拠出年金(iDeCo)、企業型確定拠出年金 |
| 確定給付企業年金制度 |
確定給付企業年金、厚生年金基金 |
| 退職金共済制度 |
中小企業退職金共済、小規模企業共済、社会福祉施設職員等退職金手当共済 |
一方すでに退職金を受け取っている場合、手元に保管している退職金は「現金」、口座に預けている退職金は「預金債権」として扱われます。
そのため、現金は99万円を超える部分、預金債権は20万円を超える部分が処分の対象になります。
借金返済が困難であれば年齢に関係なく債務整理を検討するべき
債務整理には年齢制限がありませんが、先延ばしにしてしまうと手続きの選択肢が限られたり、家族に負担をかけてしまったりするリスクもあります。
そのため、年齢に関係なく借金の返済が難しいと感じたら、できるだけ早く債務整理を検討することが大切です。
以下に、早めの債務整理を検討すべき主な理由を3つ紹介します。
- 早く債務整理を行うとブラックから外れる時期も早まる
- 借金が増えるとデメリットが高い手続きしか取れなくなる
- 借金を抱えたまま亡くなると子に相続される
早く債務整理を行うとブラックリスト入りから外れる時期も早まる
債務整理の手段3つに共通するデメリットとして、信用情報機関に債務整理をしたという履歴が登録され、しばらくクレジットカードを作ったりローンを組んだりする審査に通りづらくなることが挙げられます。
いわゆるブラックリストと呼ばれる状態になるのです。信用情報機関が管理している信用情報は、金融機関がローンやクレジットカードの申込を受けた際に、申込者の信用情報を照会するのに使用されるのが一般的です。
このときに、債務整理などの金融トラブルの履歴が残っていると、「返済能力に問題があるのでは?」と判断される可能性があります。そのため、ブラックリスト入りしている間は審査に通りづらくなってしまうのです。
日本には信用情報機関が3つあり、債務整理の履歴が残る期間は以下のように定められています。
| 信用情報機関 |
登録される債務整理情報 |
登録期間 |
| CIC |
自己破産のみ |
会員会社が「免責許可が出た」と報告してきた時点から最長5年間 |
| JICC |
・任意整理
・個人再生
・自己破産 |
任意整理:契約期間中+完済から最長5年
個人再生:契約期間中+完済から最長5年
自己破産:会員会社が「免責許可が出た」と報告してきた時点から最長5年間 |
| KSC |
・自己破産
・個人再生 |
破産・個人再生手続開始決定決定日から最長7年 |
債務整理についてすべて登録されるのは、JICCのみです。最もリスクが低い任意整理でも、返済期間に加えて完済後も最長5年経つまではブラックになります。
なお、任意整理と個人再生の契約期間は下記が一般的です。
- 任意整理:弁護士からの受任通知が届いてから完済するまで
- 個人再生:手続開始決定から完済するまで
受任通知とは、弁護士や司法書士が債務整理の依頼を受けたときに、債権者に対して「この方の債務整理を私が担当します」と伝える正式な通知です。
最も登録期間が短い任意整理で3年で完済できたとしても、契約期間と完済後の登録機関を合わせると8年はブラックリスト入りの状態です。
そのため、借金を抱えたまま悩み続けるよりも早めに債務整理を行うほうが、ブラックリストから外れる時期も早まります。
たとえば、3年悩んでから債務整理をすると、ブラック状態はそこから完済後も最長5~7年間続きます。逆に、早めに手続きを済ませれば、その分だけ早くクレジットカードやローンの審査に通る状態に戻れるのです。
借金問題を長引かせることは、精神的な負担や生活の質の低下にもつながります。人生100年時代といわれる今、早期に債務整理を行い、経済的な不安から解放された生活を取り戻すことは、前向きな選択といえるでしょう。
借金が増えるとデメリットが多い手続きしか取れなくなる
借金債務整理は、減額幅が大きいほどデメリットが多くなるのが特徴です。以下の表では、各手続きごとの主なデメリットを比較してみました。
|
任意整理 |
個人再生 |
自己破産 |
| ブラックリスト登録期間 |
あり(完済後も最長5年) |
あり(完済後も最長5年) |
あり(最長7年) |
| 財産の処分 |
なし |
なし(清算価値により手続き後の返済額あり) |
あり(20万円超の財産は処分) |
| 官報掲載 |
なし |
あり |
あり |
| 手続き後の返済 |
あり(元金を完済) |
あり(減額後の元金を原則3年で返済) |
なし(原則すべての借金が免除) |
債務整理を検討している場合、「なるべくデメリットが少ない方法で借金問題を解決したい」と考える人もいるかもしれません。
しかし、借金問題が長期化すればするほど、返済不能になるリスクは高まります。その場合、デメリットが大きい自己破産を選択せざるを得ない状況にもなりかねません。
たとえば、現状であれば任意整理で借金問題を解決できる状況であっても手続きをしなければ、収入減などの影響によって今後は返済が不可能になってしまい、任意整理を選択できない状況に陥る可能性もあるのです。
前述の通り、高齢の場合には体力の低下や持病の悪化など、将来的な健康状態の変化も考慮する必要があります。そのため、借金問題を抱えている場合には、なるべく早期で問題を解決できるように弁護士や司法書士に相談しておくことが得策と言えます。
借金を抱えたまま亡くなると子に相続される
相続財産には、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。そのため、万が一借金を抱えたまま亡くなってしまった場合、その借金は配偶者や子供などの相続人に引き継がれることがあります。
そのため、借金額によっては、配偶者や子供も借金の返済で生活が立ち行かなくなってしまう恐れもあるでしょう。
相続人が借金を相続したくない場合は、家庭裁判所で手続きを行うことで相続放棄ができますが、相続放棄を選択した相続人はプラスの財産も一切引き継げなくなってしまいます。
借金を抱えたままにしておくと、相続人になる予定の家族や親族に迷惑をかける可能性があるため、借金問題は早めに解決すべきだといえます
なお、相続財産は、原則として法定相続人(民法で定められた相続人)が引き継ぎ、法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と一定範囲の血族です。配偶者は常に相続人となりますが、血族には相続できる優先順位があり、最も優先順位が高い血族のみが相続人になれます。
| 相続の優先順位 |
相続人 |
| 常に相続人 |
配偶者 |
| 第一順位 |
子供(子供が死亡している場合は孫) |
| 第二順位 |
父母(父母が死亡している場合は祖父母) |
| 第三順位 |
兄弟姉妹(兄弟姉妹が死亡している場合は甥・姪) |
まとめ
債務整理には年齢の制限がないため、何歳でも債務整理による借金問題の解決が望めます。しかし、任意整理や個人再生の場合は手続き後も借金の返済が続くため、継続的かつ安定した収入が必要になります。
特に高齢者は、年金収入しかない、健康上の問題で働けないなどの理由で完済の見込みが立たず、手続きが行えないケースも少なくありません。
その場合は自己破産を検討することになりますが、借金が帳消しになる代わりに持ち家や車など財産の大半を手放すことになるため、今後の生活や同居家族への影響などを考慮したうえで慎重に検討する必要があります。
とはいえ、借金問題を後回しにしていると状況は悪化する一方です。万が一借金抱えたまま亡くなってしまった場合は、相続人になる子供や配偶者にも迷惑をかけることになります。どうしても借金の返済が難しい場合は、早めに弁護士や司法書士に相談し、債務整理の利用を検討してみましょう。