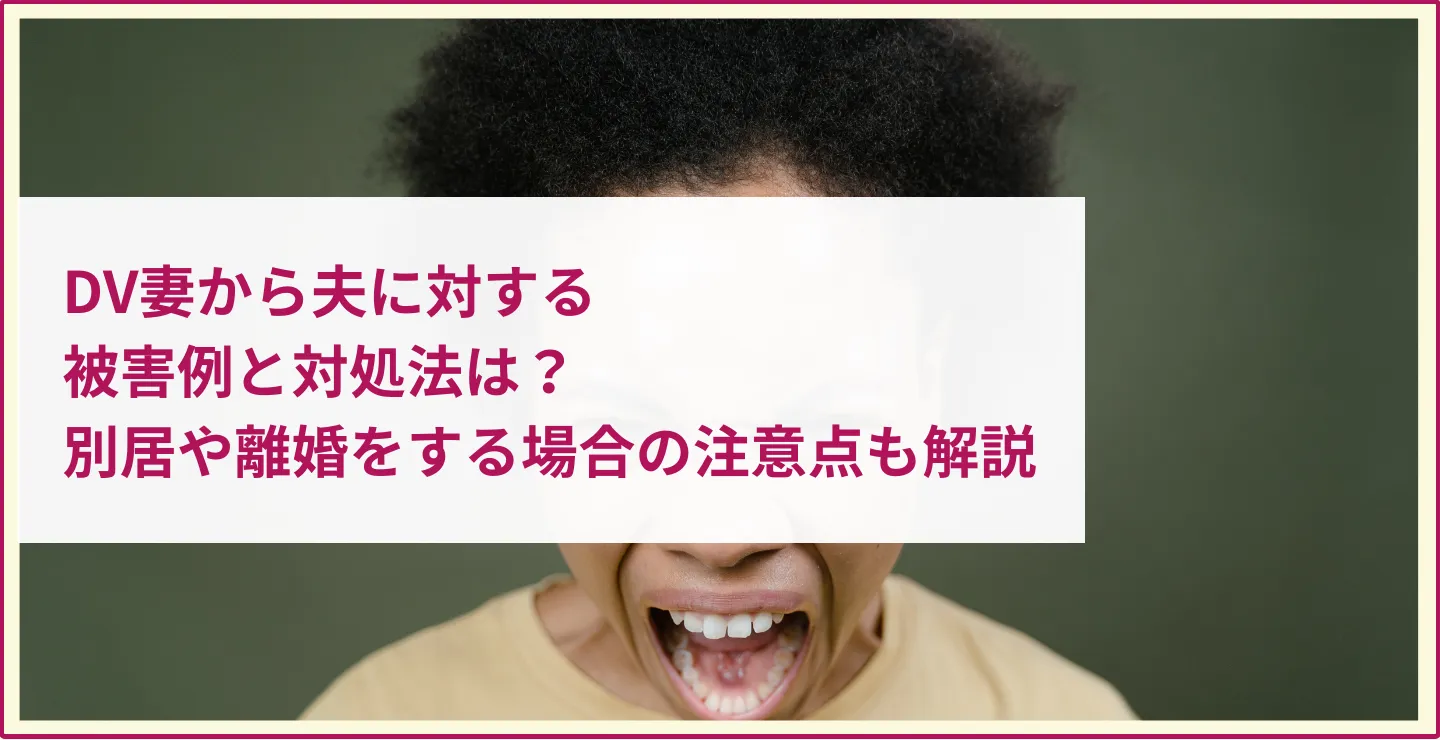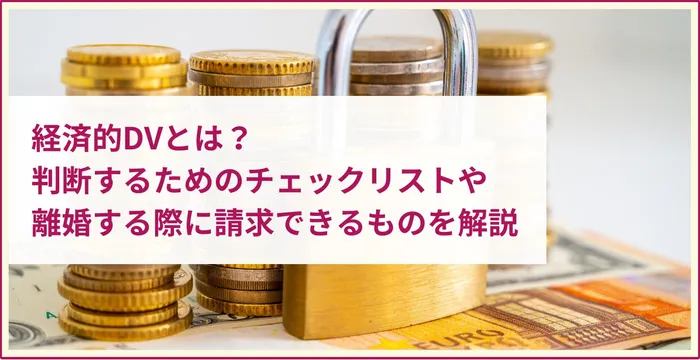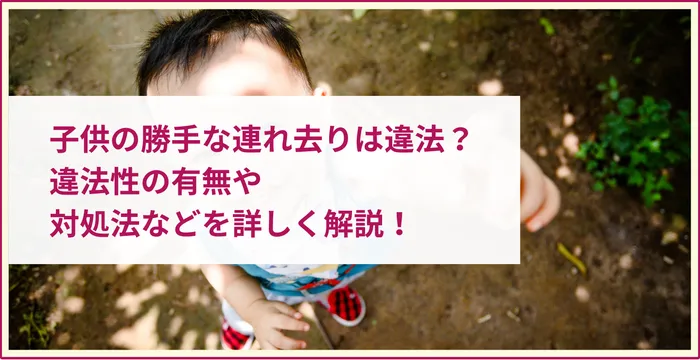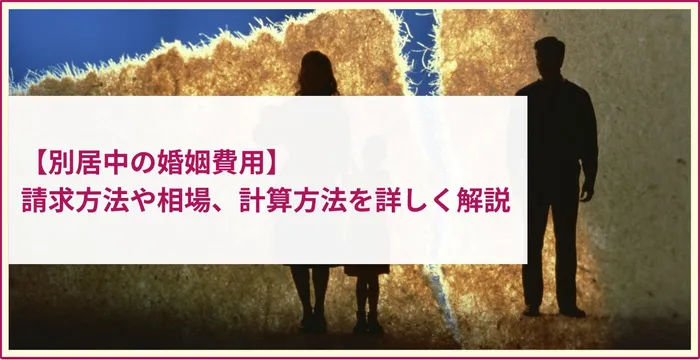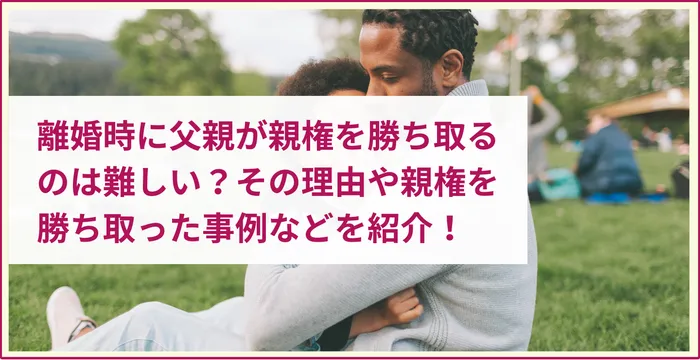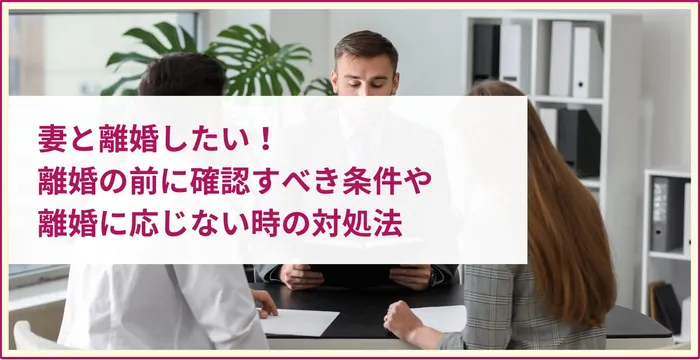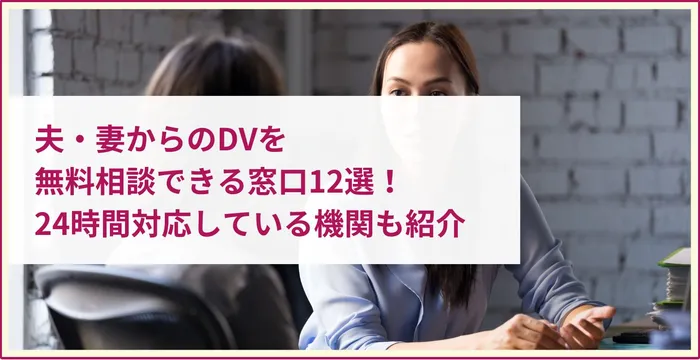夫から妻へのDV被害を耳にしたことがある人は多いでしょうが、実は妻から夫へのDV被害・相談件数も一定数あり、近年は増加傾向にあります。
男性DV被害者への支援や相談機関は、十分に整備されているとはいえません。そのため、妻からのDVを理由に別居や離婚を考えるのであれば、後々不利な状況に追い込まれないよう、弁護士への相談が有力な選択肢となります。特に、慰謝料を請求したい場合・妻が離婚を拒否する場合・親権を争う場合は、早期に弁護士に相談して、より証拠能力の高い証拠を集めるなどの状況に応じた適切な対応が必要です。
本記事では、妻から夫へのDV被害の現状や被害事例、妻からDVを受けた時の対処法、DVを理由に別居・離婚したい時の注意点を紹介します。
【妻からDVを受けた時の対処法】
・暴力でやり返さない
・妻がDVをする原因を探る
・専門機関・専門家に相談する
・妻から受けるDVの程度を見きわめる
・こどもへの影響を考える
・別居や離婚をするかどうかを考える
その他、妻からDVを受けた経験がある男性255人を対象に実施した独自アンケートをもとに、よくある被害についてもお伝えします。
妻からDVを受けている夫は少なくない
警察庁や内閣府の調査によると、妻からDVを受けている夫は、DV被害のうち約3割にも上り、近年は相談件数が年々増加しています。まずは、男性のDV被害の実態についてみていきましょう。
DV相談者・被害者の約3割は男性
実は、DV相談者・被害者における男性の割合は少なくありません。警察庁「令和5年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」によると、配偶者からのDV相談88,619件のうち、27.9%にあたる24,684件が男性からの相談でした。
また、内閣府「男女間における暴力に関する調査(令和5年度調査)」によると、配偶者から被害を受けたことがある462人のうち、約37.4%にあたる173人が男性でした。
参考:警察庁「令和5年におけるストーカー事案、配偶者からの暴力事案等、児童虐待事案等への対応状況について」
参考:内閣府男女共同参画局「男女間における暴力に関する調査(令和5年度調査)」
男性DV相談者・被害者数は増加傾向にある
警察庁の統計によると、令和元年の男性配偶者からのDV相談は17,815件でしたが、令和5年では24,684件に増加しています。
【男性被害者からの相談件数】
|
|
令和元年
|
令和2年
|
令和3年
|
令和4年
|
令和5年
|
|
男性
|
17,815
|
19,478
|
20,895
|
22,714
|
24,684
|
上記の通り、男性からのDV相談は増加しています。配偶者への暴力というと男性から女性への暴力をイメージする人が多いでしょうが、実際には全体の約3割は女性から男性へのDVであり、男性のDV被害の相談を多く受けている弁護士も「ここ4~5年で被害相談も増えている」と語っています。
ただし、女性から男性へのDVは、男性が被害を認識していなかったり、DVの被害者=女性という偏見が強く、警察への相談・被害申告がされにくい実態もあります。実際には、統計に表れない男性被害者が多くいることが推測されています。
夫255人に聞いた!DV妻による被害でよくあるケースとは
弊社クランピーリアルエステートがDV妻を持つ夫255人にアンケートを採ったところ、DV妻による加害行動には以下のような回答が得られました。
・殴る蹴るなど暴行する
・謝罪や土下座を強要する
・夫が寝ているところに熱湯や水をかける
・「男のくせに」「死ね」「給料が低い」などと毎日のように暴言を吐く
・いつ何時でも無視を続ける
・夫の仕事の書類やPC、趣味の物を勝手に捨てる
・十分な生活費を渡さず、過度な倹約を強要する
・子どもの前で夫を罵倒する
・人間関係を制限し、家族や友人との関係を絶たせる
・性行為を強要する
・無理矢理性的な動画や画像を撮影する
・位置情報アプリやGPSタグで行動を監視する など
DVには、身体的暴力・精神的暴力・経済的暴力・社会的暴力・性的暴力・デジタル暴力などさまざまなものがあり、多くのケースで複数の暴力が並行して行われています。
妻からDVを受けている場合の対処法
それでは。妻からDVを受けている男性は、どのように対処するのがよいのでしょうか。
- 暴力でやり返さない
- 妻がDVをする原因を探る
- 専門機関・専門家に相談する
- 妻から受けるDVの程度を見きわめる
- こどもへの影響を考える
- 別居や離婚をするかどうかを考える
DVにも程度があり、妻への気持ちや関係修復への意思の有無など、ケースバイケースで適切な対処法は異なります。今後、どうしたいのかを考えながら対処法を選択しましょう。
暴力でやり返さない
まず重要なのが、暴力を受けたからとやり返してしまうと、自分までDV加害者になりかねないという点です。
身体的暴力の場合、身体的に有利な男性からの暴力のほうが被害が大きくなりやすく、離婚の際に妻がDV被害を主張すると、夫側が不利になるリスクがあります。また、妻に有利な条件が認められなかったとしても、両成敗として、夫側にも有利な条件が認められないこともあるでしょう。
DVを受けたらやり返さず、第三者からみても自分が被害者であるとわかるDV被害の証拠集めを始めましょう。
妻がDVをする原因を探る
続いて、DVが始まった原因について思い当たることはないか考えてみましょう。特に、関係の修復を考えている場合・こどもがいる場合は、原因が判明すれば、改善や対策を図ることができます。
DVに至るには、どのようなケースでも何かきっかけや原因があるものです。例えば、精神疾患や摂食障害のような病気が原因の場合は、心療内科や精神科への通院することで改善できる可能性があります。性格的な問題であっても、本人に直したい意思があれば、カウンセリングで改善することもあるでしょう。
また、単に妻だけが悪いのではなく、夫の家庭への無関心や家事・育児のキャパオーバーが原因でDVに繋がることも珍しくありません。この場合は、夫も自分の行動を見直すことで、DVを止められる可能性があります。
妻から受けるDVの程度を見きわめる
DVの程度の見極めも重要です。DVによって、夫やこどもの生命や心身の健康に重大な危険・悪影響を及ぼしている場合は、離婚するにしても関係を修復するにしても、できるだけ早く距離を置く必要があります。対して、DVの程度が軽ければ、話し合いやカウンセリング、通院などで改善できる可能性があります。
離婚したいのか関係修復したいのかによって対処法が変わってくるため、直ちに物理的に距離を置く必要があるのか、妻の意思や治療の意思などを含めて慎重に確認が必要です。
専門機関・専門家に相談する
DVの被害を受けていると、精神的なストレスやプレッシャーから、正常な判断や適切な対応ができないこともよくあります。「DVかもしれない」と感じたら、専門機関や専門家に相談して、プロのアドバイスを受けたり、場合によっては弁護士やカウンセラーに間に入ってもらうことが大切です。
【DV被害の相談機関】
|
相談機関
|
相談受付時間
|
連絡先
(「一覧」の部分はクリックすると表示されます)
|
|
性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター
|
-
|
#8891
センター一覧
|
|
男女共同参画関係機関(男性相談員)
|
-
|
センター一覧
|
|
性暴力に関する SNS相談「 Cure time」
|
17:00~21:00
|
チャット・メール相談
|
|
都道府県警察の性犯罪被害相談電話
|
24時間
|
#8103
|
|
都道府県警察本部の警察相談専用総合窓口
|
平日:8:30~17:15
|
#9110
|
|
犯罪被害者の援助を行う民間の団体
|
-
|
団体一覧
|
|
法テラス犯罪被害者支援ダイヤル
|
平日:9:00~21::00
土曜日:9:00~17:00
|
0120-079714
|
|
法務局・地⽅法務局 人権相談窓口
|
平日:8:30~17:15
|
電話:0570-003-110
インターネット窓口
LINE窓口
|
|
違法・有害情報相談センター
|
24時間
|
インターネット上の相談フォーム
|
|
セーフライン
|
24時間
|
リベンジポルノの通報
|
こどもへの影響を考える
夫婦間のDVは、こどもへの悪影響や虐待にまで繋がります。内閣府「男女間における暴力に関する調査(令和5年度調査)」によると、こどもの被害経験の内容では、「心理的虐待」が23.8%と最も多く、次いで12.8%「身体的虐待」と続きます。
こどもの目の前で配偶者に暴力をふるったり、著しい拒絶的な対応をしたりする行為は「面前DV」と呼ばれます。面前DVは児童虐待防止法のなかで心理的虐待のひとつとして認定されています。こどもにとって親同士のDVは、恐怖やトラウマを植え付けるものであり、健全な成長を阻害し、心身にさまざまな悪影響を与えかねません。こどもの前でもDVが行われるようであれば、速やかに別居や離婚を検討したほうがよいでしょう。
別居や離婚をするかどうかを考える
DVは改善しようとしても、すぐになくなるものではありません。話し合いやカウンセリングを繰り返しても、加害が続いてしまうこともあります。
離婚するという選択をする人も少なくありませんが、「こどもがいるから」「相手が変わってくれると期待している」といった理由で、別れず関係修復を目指す人もいます。実際に内閣府の調査では、DV被害に遭った男性のうち離婚に至った割合はわずか9.8%でした。離婚するか否かは、DVの程度やこどもの有無、自分のメンタルヘルスなど、総合的に判断するようにしましょう。
ただし、DVが自分やこどもの心身に悪影響を及ぼしている場合は、まずは別居をしてから、これからどうするのか考えることが大切です。物理的な距離を置くことでお互いに冷却期間ができ、夫婦それぞれが冷静に考えることができます。
妻からのDVを理由に別居・離婚する場合の注意点
DVの被害を理由に別居・離婚する場合、思い付きで行動するのはおすすめできません。下記のような準備をしておくことが重要です。
- DVの証拠を収集・保存する
- 妻に無断で別居をしない
- 別居中も婚姻費用は分担する
- 親権などについて考えておく
- 弁護士にアドバイスや代理交渉をしてもらう
ここからは、上記のような妻からのDVを理由に別居・離婚する場合の注意点をまとめてお伝えします。
DVの証拠を収集・保存する
DVを理由に離婚や慰謝料を請求する場合、DVがあったことを立証しなければなりません。そのためには、別居や離婚を切り出す前に、証拠集めが必要です。
以下のような記録は、DVの証拠として認められやすいです。
- 医師の診断書や通院記録
- 配偶者暴力相談支援センター・警察等への相談記録
- 友人や家族の目撃・相談の証言
- ケガや壊れた物、荒れた部屋の写真
- 加害が分かるメッセージのやり取り
- DV中の音声・動画の記録
- されたことや言われたこと、日時が記載されたメモや日記
- 経済的に困窮していることが分かる預金通帳や家計簿 など
妻に無断で別居をしない
民法第752条によって、夫婦には同居義務があります。「正当な理由がなく同居を拒否する」「相手の同意なく勝手に別居を始めるといった行為は、原則として認められていません。そのため、別居をするときには、妻に伝えてから家を出る必要があります。
直接対面で伝えられない場合は、置き手紙を残したりメッセージを送ったりするだけでもよいので、一方的に別居を始めないことが重要です。ただし、相手がメッセージを確認しなければ、無断で別居を始めたことになりかねません。確実に伝えるためには、手紙のほうがよいでしょう。勝手に別居を始めると、「悪意の遺棄」とみなされ、相手方が慰謝料を請求できるようになる可能性があります。
なお、こどもがいる場合、原則としてこどもの勝手な連れ去りは違法行為となります。しかし、日本国内であれば、DVの被害者が暴力から逃れるためにこどもを連れて家を出る行為は基本的には違法とみなされないでしょう。
別居中も婚姻費用は分担する
別居中であっても、夫婦には婚姻費用の分担義務があります。そのため、衣食住の生活費や医療費、こどもの教育費や養育費、 交際費などは、収入に応じて負担しなければなりません。別居をしていても収入が多いほうが少ないほうに金銭(=婚姻費用)を渡す義務があり、一般的には夫のほうが妻よりも収入が高いため、被害者であっても夫の金銭的な負担が必要です。
なお、離婚手続きに入っても、婚姻関係は続いているため、婚姻費用は負担しなければなりません。万が一、妻が離婚を拒否し、調停や裁判までもつれ込むことになると、離婚までの数ヶ月~2年程度金銭的な負担が発生し続けることになります。
親権などについて考えておく
未成年のこどもがいる場合は、離婚後のこどもの親権者を決めなければなりません。離婚の原因が妻のDVである場合でも、妻がこどもを虐待していなければ、妻がこどもの親権者になる可能性は十分にあります。
基本的に親権者は、これまで主に育児を担ってきた親が獲得します。夫が親権者になることを望む場合は、父親として子育てに関わってきたことが分かる資料を揃え、こどもにとってより良い経済・居住・養育・教育の環境を提供できることを認めさせなければなりません。
ただし、0~5歳の乳幼児は母性優先の原則があるため、親権争いでは母親が有利です。一方で、10歳以上であればこどもの意思も考慮され、15歳以上であればこどもが親を選ぶことができます。
なお、親権の獲得に関わらず、面会交流や養育費についても決める必要があります。
弁護士にアドバイスや代理交渉をしてもらう
当事者同士の離婚交渉は通常の場合であっても難しいものです。DVが遭った場合は、夫婦としての正常な関係性は崩れており、被害者・加害者となっているためさらに難易度が上がります。それ以上、状況が悪くなる前に、まずは弁護士に相談するようにしましょう。
状況に応じた適切な対処や、今後に向けた準備についてアドバイスをもらえるだけでなく、離婚条件や親権獲得の代理交渉を弁護士に依頼することで、より希望に近い形で離婚できるでしょう。離婚の決意が固まっても、初動で失敗すると、不利な条件で離婚せざるを得ないこともあり得ます。また、別居や離婚を切り出したことで、DVが悪化するケースもあるようです。
まとめ
近年、男女平等意識が広まり、男性のDV被害者が表面化してきました。女性から男性のDVでは、男性から女性へのDVと同様に、殴る蹴る・暴言を吐くといった心身への暴力や、金銭的な自由を奪う経済的暴力、他者との繋がりを絶って社会的に孤立させようとする社会的暴力などがあります。
妻からDVを受けた際には、やり返さず、まずは専門機関や専門家に相談してみましょう。そして、自分が配偶者と関係を修復したいのか、離婚したいのかをよく考えてください。生命の危険がある場合やメンタル不調が出ている場合は、置き手紙を残したうえで、直ちに物理的な距離を取ることをおすすめします。
すぐに離婚するかを決められない場合も、日記や画像・動画、メッセージのやり取りなどDV被害の証拠は準備しておきましょう。証拠のある・なしが、離婚時の慰謝料・財産分与・養育費の支払い・親権の獲得を左右します。
よくある質問
妻からDVを受けていると相談したら「男なんだから」などと言われたりしませんか?
人格否定や罵詈雑言、差別的な発言は、精神的なDVです。ジェンダーバイアスが根付いている人に相談すると、「そんなはずない」「男のくせに」などと反応されてしまうことがあるのも事実です。しかし、女性から男性へのDV被害を否定する意見は、単に男性DV被害者への理解不足によるもので、きちんと配偶者暴力相談支援センター・警察などの専門機関や専門家である弁護士に相談すれば、「男なんだから」などと言われず配偶者からのDVが認められます。現状を理解してもらえるよう、相談をするときは、DV被害を受けていることを証明できる証拠を持参するようにしましょう。
男性でも利用できるシェルターはありますか?
女性DV被害者の数が非常に多いため、
男性用のシェルターの整備まで支援が追いついておらず、利用できるシェルターは少ないのが現状です。配偶者暴力相談支援センターに相談すれば、紹介してもらえる可能性はあります。
ただし、男性用シェルターを確保している自治体は、47都道府県のうち北海道や宮城県、京都府、熊本県など11道府県に留まります。
妻が別居を許してくれない場合はどうしたらよいですか?
適切な対応は状況に応じて異なるため、まずは弁護士に相談し、アドバイスに従って行動するようにしましょう。同意を得なくてもDVから避難するために家を出ることは可能です。置き手紙でもいいので別居する旨を伝えたら、転居先を教える必要はありません。別居期間中は、住民票もそのままで構いません。
住民票を移した時は、転居先の市区町村でDV等支援措置を利用しましょう。DV等支援措置を利用することで、妻が住民票の閲覧や写しの交付を制限し、居場所を知られることを防止できます。
妻が離婚に応じてくれない場合はどうしたらよいですか?
妻が協議離婚に応じない場合は、離婚調停を経て、離婚裁判を起こす必要があります。調停とは、家庭裁判所で行われる当事者同士の話し合いです。調停委員会が話し合いを仲介してくれるため、夫婦2人での話し合いよりも合意に至りやすくなります。調停でも合意に至らなかった場合は、裁判となり、裁判官の判決により、離婚の可否や離婚条件を判断してもらうことになります。
調停や裁判では、妻からのDV加害を証明し、法定離婚事由として認められている「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することを立証しなければなりません。いずれにしても、DVの被害状況や頻度がわかる証拠を集めておく必要があります。
離婚をする場合、妻に慰謝料を請求することはできますか?
DVは不法行為に当たるため、
DVを理由とした離婚が認められた場合は、加害者である妻に対して慰謝料を請求することが可能です。
ただし、実際に請求すると、支払いを拒絶されたり、金額についての折り合いがつかなったりします。離婚する際には、慰謝料請求以外にも、財産分与や年金分割、こどもの親権・養育費、面会交流など決めなければならない事柄が多くあるため、早めに弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
逆に妻から「夫からDV・モラハラを受けている」と訴えられてしまいました。どうしたらよいですか?
DV・モラハラをでっち上げられた場合には、冷静にそのような事実がないことを反論する必要があります。
妻がDVやモラハラの証拠を提示してきたら、事実ではないことを裏付ける証拠を集めて反証しなければなりません。
通常、妻がDV・モラハラをでっち上げようとする場合、妻が不貞行為をしていたり夫婦の貯金を使い込んだりなどやましい理由があります。弁護士にサポートを依頼し、アドバイスのもとで行動するほうがよいでしょう。
DVやモラハラは、自身が加害している自覚がないことも多く、お互いが相手を加害者であると主張するケースもあります。そのため、軽度のDV・モラハラであれば、責任の追及をするよりも早期離婚できる道を探るほうが精神衛生上よいこともあるでしょう。
自分の不倫がきっかけで妻がDVをするようになりました。それでも離婚をすることはできますか?
法律上、
不貞行為をした側は有責配偶者にあたるため、原則として離婚を求めることはできないことになっています。ただし、妻からのDV行為も不法行為に該当するため、暴力の頻度や程度、社会的・経済的に自立していないこどもの有無によっては、例外的に夫から離婚請求が認められるケースもあります。
ただし、有責配偶者の離婚請求のハードルは高く、相手が離婚に合意しない場合、離婚訴訟を提起したり長期間の別居をしたりと簡単には認められません。自分にも有責事由がある場合には、弁護士に相談して最適な対応を検討しましょう。