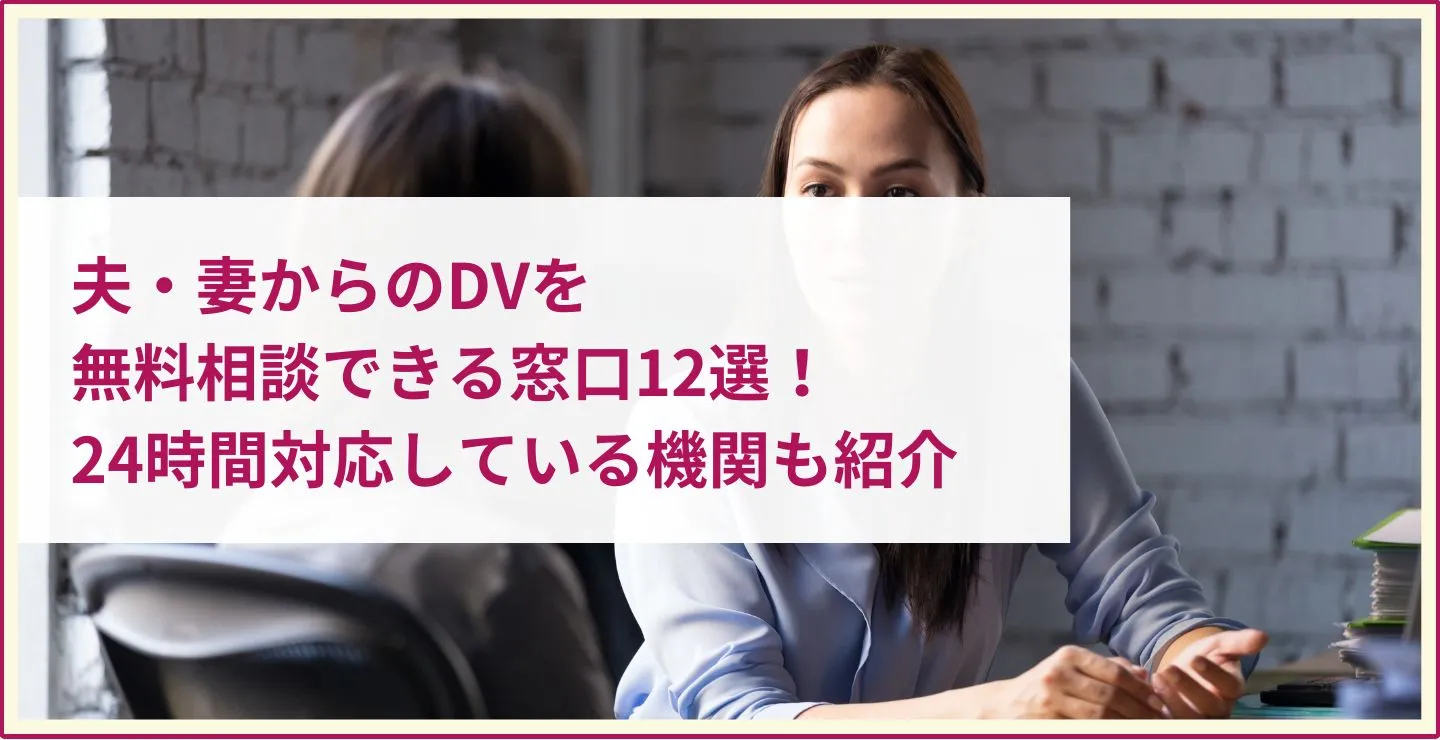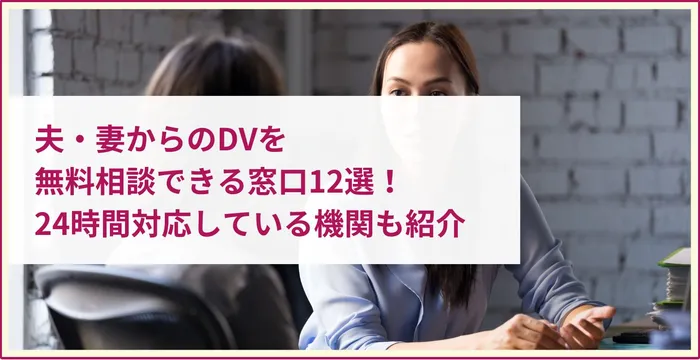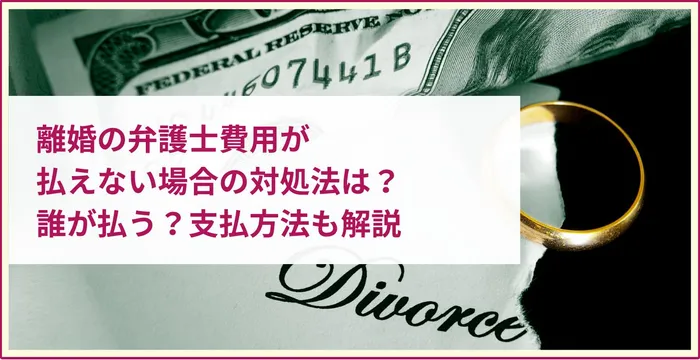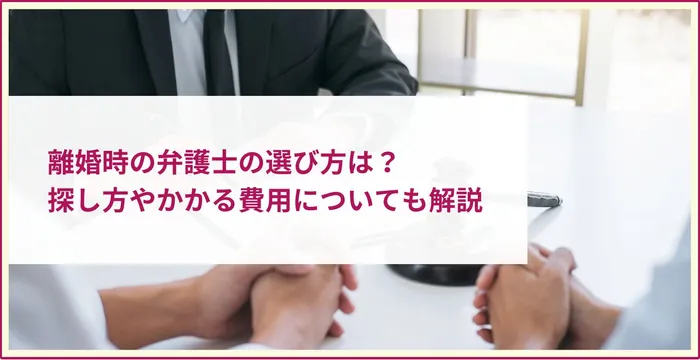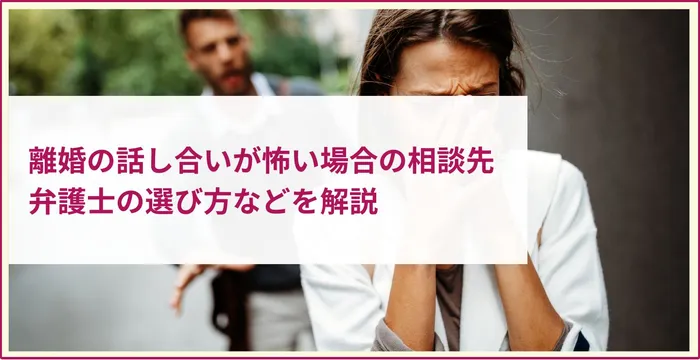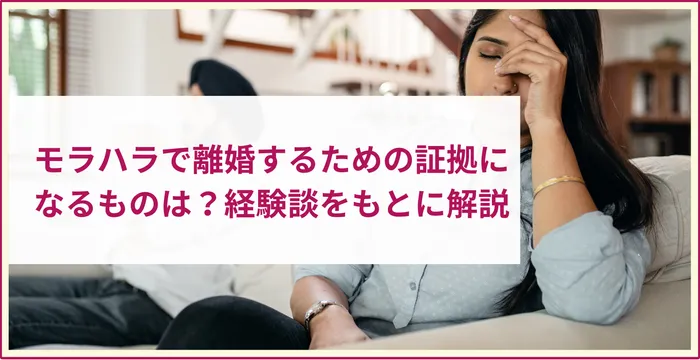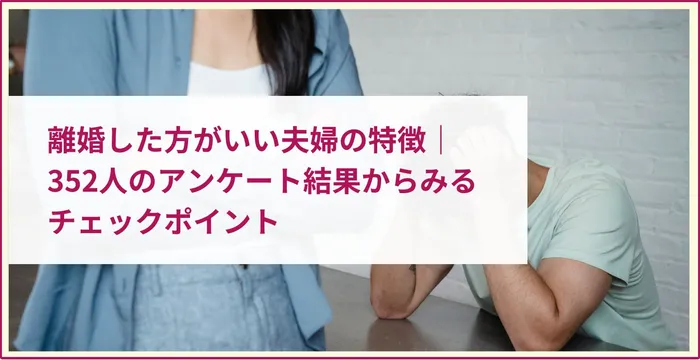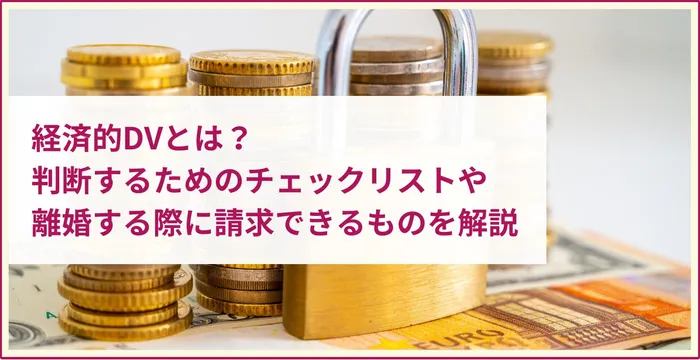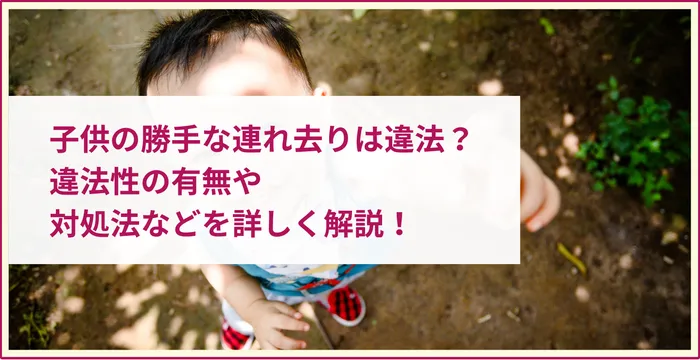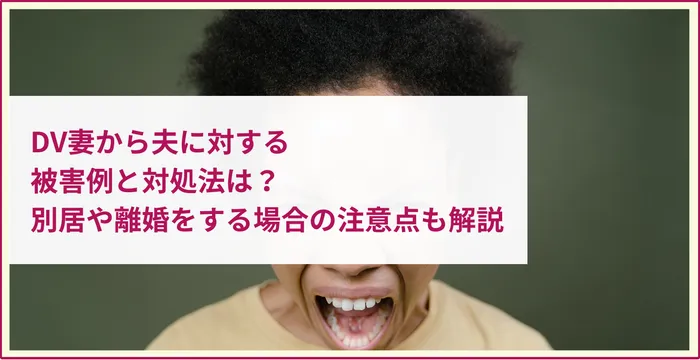【目的別】DVについて無料相談できる窓口12選!
DVについて無料相談できる窓口を、目的に応じて3つに分類しました。
- 弁護士:離婚や慰謝料請求など法的手続きをしたい
- 公的機関:DVから逃れる方法を知りたい
- NPO法人:どこに相談すべきかわからない
それぞれの窓口について、特徴や相談方法を解説します。
弁護士:DVを理由に離婚・慰謝料請求などの法的な手続きをしたい
DVを理由に離婚や慰謝料請求を考えている場合は、法的な手続きについてアドバイスが受けられる弁護士に相談するとよいでしょう。
DV問題について無料相談できる弁護士の窓口には、以下の4つがあります。
- 弁護士事務所
- 市区町村の無料法律相談
- 法テラス
- 弁護士会の法律相談センター
それぞれ詳しく解説します。
弁護士事務所|法律のプロから法的なアドバイスをもらえる
弁護士事務所では、初回の法律相談を30分〜1時間程度、無料で行っている事務所もあります。
一方で、無料相談を実施していない事務所では、30分あたり5,000円〜10,000円程度が相場です。
弁護士は法律の専門家であり、DVに関する法律や制度に精通しています。
DVの問題を法的な視点から分析し、離婚や慰謝料請求、養育費、財産分与、証拠集めについてのアドバイスをしてくれます。
また、無料相談後にそのまま依頼すれば、訴訟の代理や手続きなども行ってくれます。
相談する際は、DVやモラハラ、離婚問題などに強い弁護士事務所を選ぶとよいでしょう。
無料相談を受けたからといって、必ずその弁護士に依頼しなければならないわけではありません。
複数の事務所で相談し、比較したうえで、自分に合う弁護士を選ぶことも可能です。
無料相談は相談時間が限られ、一般的なアドバイスにとどまることが多いため、より詳しい相談や具体的な対応が必要な場合は、有料相談を検討するとよいでしょう。
市区町村の無料法律相談|身近な場所で弁護士に相談できる
市区町村では、役所などで定期的に無料の法律相談を実施しており、弁護士に直接相談できる機会が設けられています。
多くの自治体では月に1~数回程度の開催が一般的で、予約が必要な場合がほとんどです。
相談時間は15〜20分程度と短めなので、あらかじめ相談内容や質問事項を整理しておくとよいでしょう。
市区町村の法律無料相談は、以下のような方に向いています。
- 弁護士に依頼するかどうかを判断したい方
- 費用をかけずに、まず簡単なアドバイスを受けたい方
- 弁護士を探しているが、どんな人に相談すべきか迷っている方
ただし、市区町村の相談では、必ずしも離婚問題に詳しい弁護士にあたるとは限りません。
そのため、相談内容が複雑であったり、専門的な対応を求めたりする場合は、はじめから法律事務所で相談することをおすすめします。
法テラス|条件を満たせば最大3回まで無料相談できる
法テラス(日本司法支援センター)は、法的トラブルに悩む方が、弁護士などの専門家から必要な支援を受けられるように国が設立した法的支援機関です。
全国に相談窓口が設けられており、多くの地域で法的サポートを受けやすい体制が整えられています。
法テラスでは、経済的に困っている方を対象に、弁護士や司法書士との法律相談を無料で行っており、対面のほか、電話でも相談可能です。
1回あたりの相談時間は約30分で、条件を満たせば最大3回まで無料で相談できます。
「弁護士に依頼すべきかわからない」「ちょっと聞いてみたい」というような相談にも応じてもらえます。
ただし、無料相談を利用するには、収入や資産が一定基準以下であるなどの条件を満たす必要があります。
なお、法テラスでは弁護士を自分で選ぶことはできません。
希望する分野を伝えることはできますが、必ずしもその分野に詳しい弁護士が対応するとは限らず、希望に沿わないケースもあります。
そのため「離婚・DVに特化した弁護士に相談したい」「専門性や相性を重視したい」といった方は、 法律事務所に直接相談する方が適している場合もあります。
| 項目 |
内容 |
| 電話番号 |
0570-078374
|
| 受付時間 |
平日9:00〜21:00 土曜日9:00〜17:00
|
| URL |
法テラス 公式ホームページ
|
弁護士会の法律相談センター|全国約300箇所に設置されている
弁護士会は、日本全国の弁護士が会員となっている団体です。
弁護士会が運営する「法律相談センター」は、地域により無料または有料の法律相談を実施しており、全国約300ヵ所で対応しています。
たとえば、大阪弁護士会総合法律相談センターでは、離婚に関する法律相談を30分間無料で受け付けています。
相談の予約は電話のほか、インターネットからも可能です。
なかでも、日本弁護士連合会が運営する「ひまわり相談ネット」を利用すれば、24時間いつでもオンラインで予約申し込みできます。
法律相談後には、相談を担当した弁護士に直接依頼することも可能です。
公的機関:DVから逃れる方法を知りたい
DVから逃れる方法を知りたいときは、公的機関が提供する無料の相談窓口を活用するのがおすすめです。
公的機関による無料相談窓口は、以下の7つがあります。
- DV相談プラス
- 東京ウィメンズプラザ
- 配偶者暴力相談支援センター
- よりそいホットライン
- 婦人相談所
- 女性の人権ホットライン
- 児童相談所
これらの窓口では、DV被害者が自身の安全を確保するためのアドバイスや心のケアのほか、シェルターへの案内などが受けられます。
それぞれの窓口について、詳しくみていきましょう。
DV相談プラス|DVに関するあらゆる問題について相談できる
DV相談プラスは、内閣府が運営するDV専門の相談窓口です。配偶者やパートナーからの身体的・精神的・性的・経済的暴力など、さまざまなDV被害について、専門知識をもった相談員が対応します。
電話・メール(プラス相談箱)は24時間対応、オンラインチャットは12:00〜22:00に相談可能です。
さらに、相談員が必要と判断した場合は、面接相談や同行支援、安全な避難場所への案内などの支援も行われます。
DVに関することなら、どのような内容でも相談可能です。
たとえば、以下のような悩みにも対応しています。
- これはDVにあたるのか判断がつかない
- 暴力を受けているが、どうしたらよいかわからない
- 今すぐパートナーから逃げたいが、どうしたらよいかわからない
- 子どもの安全が心配
こうした不安や迷いを感じたときも、ひとりで悩まず、まずは相談してみてください。
| 項目 |
内容 |
| 電話番号 |
0120-279-889
|
| 受付時間 |
電話・メール:24時間受付
チャット相談:12:00~22:00
|
| URL |
DV相談プラス|内閣府
|
東京ウィメンズプラザ|東京都に在住・在勤・在学の方におすすめ
東京ウィメンズプラザは、男女平等参画社会の実現に向けた、具体的で実践的な活動を推進する場所として都民と行政が共同で取り組んでいる施設です。
原則として、東京都に在住、在勤、在学の方を対象に、配偶者からの暴力(DV)や交際相手からの暴力(デートDV)に悩む方の無料相談を受け付けています。
相談は匿名で行うことができ、秘密は厳守されます。
電話相談は毎日9時から21時まで対応しており、年末年始を除いて利用可能です。
また、必要に応じて面接による相談(予約制)も実施されています。
さらに、女性弁護士による法律相談や精神科医師による面接相談も行っており、いずれも電話予約が必要です。
| 項目 |
内容 |
| 電話番号 |
03-5467-1721
|
| 受付時間 |
毎日9:00~21:00(年末年始を除く)
|
| URL |
東京ウィメンズプラザ
|
配偶者暴力相談支援センター|すべての都道府県に設置されている
配偶者暴力相談支援センターは、全ての都道府県に設置されている公的な機関です。
配偶者からの暴力を防ぎ、被害者を保護するため、以下のようなサービスを提供しています。
- 相談や相談機関の紹介
- カウンセリング
- シェルターでの一時保護
- 裁判所への保護命令の申立て
- 自立生活のための支援や情報提供
利用を希望する場合は、事前に電話で連絡を取ったうえで訪問するのがおすすめです。
センターごとに対応時間が異なるため、あらかじめ確認しておきましょう。
よりそいホットライン|DV被害を受けているかわからない場合も相談できる
よりそいホットラインは、妊娠、中絶、性的被害、DV、セクハラ、パワハラ、離婚など、さまざまな問題に直面している女性を支援するための相談窓口です。
専門の相談員が、それぞれの悩み・問題に応じた情報提供や支援を行っています。
「これはDVと言えるのか?」「性暴力に該当するのか判断がつかない」といったケースでも、相談することが可能です。
電話相談は24時間受け付けており、全国どこからでも利用できます。
また、電話が難しい場合は、FAXでの相談にも対応しています。
さらに「困りごと情報提供女性相談」では、専門の相談員によるオンラインでのチャット相談も可能です。チャットの返答時間は、水曜・木曜の15〜21時となっています。
婦人相談所|女性に関するさまざまな問題を相談できる
婦人相談所は、女性に関するさまざまな問題に対応するために設けられた公的な相談機関です。
もともとは、売春を行うおそれのある女性に対する相談や指導、一時保護を目的として設立されました。
しかし、平成13年4月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が施行されたことにより、現在では配偶者暴力相談支援センターの機能も一部担うようになりました。
婦人相談所では、国籍や年齢に関係なく、問題を抱える女性からの相談に対応し、自立に向けた適切な支援の提供が可能です。
売春防止法第34条に基づき、各都道府県には必ず1つの婦人相談所が設置されており、一時保護所も併設されています。
電話相談後、面接相談や巡回相談が可能なケースもあります。
女性の人権ホットライン|どこに相談すればよいのか迷っているときに
女性の人権ホットラインは、DVをはじめとするさまざまな人権問題の相談窓口です。
電話をかけると、最寄りの法務局に直接つながり、女性の人権問題に詳しい法務局職員や人権擁護委員が相談に応じてくれます。
受付時間は平日の8時30分から17時15分までとなっています。
また、インターネットからの相談も可能です。
相談フォームに氏名・住所・年齢・相談内容などを記入して送信すると、後日、最寄りの法務局からメールや電話、場合によっては面談などで回答が提供されます。
児童相談所|子供への暴力についても相談したいときに
児童相談所は、18歳未満の子どもに関するさまざまな問題について相談を受け付け、必要な支援を提供している公的機関です。
DVに関する相談にも対応しており、子どもが被害を受けている場合や、そのおそれがある場合に重要な窓口となります。
「児童相談所虐待対応ダイヤル(189)」に連絡すると、お住まいの地域の児童相談所につながります。
通告や相談は匿名でも可能で、相談内容が外部に漏れることはありません。
DVが発生している家庭では、子どもが直接暴力を受けるだけでなく、夫婦間の暴力を目撃する「面前DV」も深刻な心理的虐待とされています。
NPO法人:どんな専門家に相談すべきかわからないとき
どんな専門家に相談すべきかわからない場合は、NPO法人に相談するのも1つの方法です。
ここでは、NPO法人よつばについて紹介します。
NPO法人よつば|各分野の専門カウンセラーが対応している
NPO法人よつばは、男女間・夫婦間の問題、浮気・不倫、離婚やDVなどに関する相談を受け付けている非営利団体です。
電話(受付時間:9時〜20時)やインターネットを通じて、年中無休で相談を受け付けています。
対面での相談を希望する場合は、無料相談フォームを利用するか、電話での予約が必要です。
相談には各分野に精通した専門カウンセラーが対応し、必要に応じて複数のカウンセラーが連携してサポートする場合もあります。
「これってDVなの?」「誰に相談すればいいのかわからない」と迷っている方でも、相談できます。
DVで身の危険を感じたらすぐに警察や民間シェルターへ
DVで身の危険を感じた場合、すぐに警察や民間シェルターへ相談するようにしましょう。
DVの被害者は、自分自身の安全が最優先であり、早期の対応が被害の拡大を防ぎます。
警察|DV被害者を保護し法的な手続きをしてくれる
警察はDV被害者を保護し、必要に応じて加害者への口頭での注意、被害届の受理、刑事事件としての捜査対応などを行います。
相談する際は、これまでの被害内容をメモにまとめ、暴力の証拠(写真・録音・診断書など)を持参するとよいでしょう。
全国の警察署の連絡先は、以下のリンクから確認できます。
都道府県警察の連絡先、警察署一覧|警察庁
警察署の相談窓口の受付時間は、午前8時30分〜午後4時30分が一般的ですが、地域によって異なる場合があります。
夜間や緊急性が低いと判断された相談は、平日の日中に訪問するよう案内される場合もあります。
「いきなり警察に連絡するのは不安」という方は、全国共通の相談ダイヤル「#9110」を活用するのも1つの方法です。
「#9110」はストーカーやDV、悪質商法など、緊急性は低いけれども警察に相談したい場合に利用でき、電話をかけた地域の警察本部の相談窓口につながります。
なお、警察に相談する際は、あらかじめ避難先を確保しておきましょう。
警察に相談してもすぐに保護されるとは限らず、家に戻った際に加害者からの報復を受ける可能性があります。安全を最優先に、相談後の行動を準備しておくことが大切です。
民間シェルター|DV被害から緊急一時避難できる
民間シェルターとは、民間団体によって運営されている施設で、DV被害者が一時的に緊急避難できる場所です。
相談対応や自立支援、心理的ケアなど、被害者の自立に向けたさまざまなサポートを行っています。
具体的な支援内容は以下のとおりです。
- 専門スタッフによる相談・カウンセリング
- 就労支援や生活スキルの指導
- 心理的ケア
- 生活相談や各種情報提供
民間シェルターは、公的シェルターに比べて個室を提供している施設も多く、生活時間(起床・食事・就寝時間など)に関しても比較的柔軟な運用をしている場合があります。
利用期間も1ヵ月程度、または個人の状況に応じて柔軟に対応している施設が多く、長期利用が可能です。
なお、公的シェルターは複数人での共同生活が基本です。利用期間は原則として2週間程度の場合が多いですが、自治体や状況によって、延長されるケースもあります。
ただし、公的シェルターが無料で利用できるのに対し、民間シェルターは1日あたり約1,000〜1,500円の利用料がかかります。
また、民間・公的いずれのシェルターも、被害者の安全確保のため、所在地は公開されていません。
利用方法や条件については、配偶者暴力相談支援センターや女性相談センターなどの公的機関に相談してください。状況に応じて、シェルターの案内や利用について説明を受けられます。
シェルター利用後も、就労支援や住まい探しなど、各機関による自立支援が提供される場合があります。継続的な支援を希望する場合は、シェルター利用時や公的機関での相談時にその旨を伝えておきましょう。
DV被害を専門家に相談するべき理由
DV被害についての相談は、決して恥ずかしいことではありません。
むしろ一人で抱え込むことで、心身に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。
DV被害に対して専門家に相談するべき理由は以下のとおりです。
- 自分では気づきにくいDV被害を客観的に判断してくれる
- DVに対する具体的な対処方法がわかる
- DVにより離婚を考えている場合は今後どう動くべきか助言してくれる
DVは、相手の自由や尊厳を奪い、深い苦痛を与える行為です。
もし自分がDVの被害者かもしれないと感じたら、すぐに専門家に相談するようにしましょう。
自分では気づきにくいDV被害を客観的に判断してくれる
DV被害は、自分では気づきにくいものです。加害者が暴力を徐々にエスカレートさせることで、被害者がその行為を「普通のこと」と誤って受け入れてしまうことがあるためです。
さらに、日常的にDVにあっていると、適切な判断力が失われる可能性もあります。
「これは自分のためを思っての行動かもしれない」「これくらいは誰でも我慢している」と感じている場合でも、まずは専門家に相談してみましょう。
専門家への相談は、自分がDV被害にあっているかどうかを客観的に確認する機会になります。
カウンセリングを通じて、DVの兆候を把握し、被害者が自分自身の状況を理解する手助けをしてくれます。
DVに対する具体的な対処方法がわかる
DV被害を受けている場合、現状から抜け出し、再び被害に遭わない生活を送るための方法を検討する必要があります。
そのためには、DVに対してどのような対策が取れるのかを理解し、状況に応じた支援を受けることが大切です。
専門家は、サポートサービスの紹介や法的手続きの説明、一時的な保護施設(シェルター)への案内などを行ってくれます。
こうした専門的な支援を受けることで、支援機関とともに、自分自身や子どもの安全を守るための具体的な行動計画を立てることができます。
DVにより離婚を考えている場合は今後どう動くべきか助言してくれる
DVにより離婚を考えている場合、専門家は今後の動きについてもアドバイスしてくれます。
相手がDV加害者であっても、必ず離婚できるとは限りません。
交渉や調停による離婚の場合、相手の合意を得る必要があったり、DV被害を受けたことを証明する証拠が必要だったりするからです。
一方、裁判に進んだ場合は、相手が離婚を拒否していても、裁判所が離婚を認めれば成立します。
離婚手続きには協議・調停・裁判という段階があり、たとえば裁判を行うためには調停を経なければなりません。それぞれの段階で資料や話す内容についての準備が必要です。
また、離婚が成立する場合は、親権・財産分与・慰謝料などの条件について取り決める必要があります。
法的な助言は弁護士が対応し、キャリア支援や心理的サポートについては支援機関やカウンセラーなど、専門分野ごとのサポートが受けられます。
DVの相談をするうえで気をつけるべきこと
DVを受けている場合、専門家への相談は重要です。
ただし、相談を行う際には以下の3つのポイントに注意する必要があります。
- 加害者に気づかれない時間帯を選んで相談する
- DVによる怪我の写真や診断書は見つからない場所に保管しておく
- DVの相談履歴はバックアップを取ったうえでスマホなどの端末から削除しておく
DV被害から身を守るためにも、これらのポイントを理解しておきましょう。
加害者に気づかれない時間帯を選んで相談する
DVについて相談する際は、加害者に気づかれないようにすることが重要です。
加害者が相談の事実を知ると、行動がエスカレートし、さらに深刻な暴力行為を引き起こすおそれがあります。
そのためDVについて相談する際は、加害者に気づかれない時間帯を選びましょう。
たとえば、加害者が仕事や趣味で外出している時間、または深夜や早朝など、睡眠中の時間帯を活用するのがおすすめです。
DVによる怪我の写真や診断書は見つからない場所に保管しておく
DVを警察に報告したり、離婚や慰謝料を請求したりする際には「証拠」が必要です。
DVによる怪我の写真や診断書は、法的手続きにおいて有力な証拠として扱われます。
これらの資料は、加害者に発見されないよう、信頼できる人に預けるか、安全な場所に保管しておくことが大切です。
DVの相談履歴はバックアップを取ったうえでスマホなどの端末からは削除しておく
DVについて相談する際は、その履歴をスマートフォンなどのデバイスから削除しておくことが大切です。
DV加害者が被害者の通話履歴やメール履歴などを監視・管理している可能性があるため、履歴が残っていると相談の事実が発覚し、行動がエスカレートするおそれがあります。
ただし、相談の履歴は、DV被害の証拠として重要な役割を果たします。
そのため、削除する前に必ずバックアップを取っておきましょう。
また、インターネットでDVや相談窓口について調べた際も、ブラウザの検索履歴を消去することが重要です。
これらの対策を講じておくことで、DV加害者に相談した事実を知られるリスクを減らし、安全に相談を進められる可能性が高くなります。
「DV」にあたる行為とは?
配偶者から受けた行為が、本当にDVなのかどうか判断に迷っている方も多いでしょう。
具体的には、以下のような行為がDVにあたります。
- 身体的暴力|殴る、蹴るなど
- 精神的暴力|暴言を吐く、物を壊すなど
- 性的暴力|性行為を強いる、中絶を強要するなど
- 経済的暴力|十分な生活費を渡さない、勝手に借金するなど
- 社会的暴力|外出させない、携帯を細かくチェックするなど
- 子どもを巻き込む暴力|子どもに暴力を見せる、子どもを取り上げるなど
DVは、殴る・蹴るなどの身体的な行為だけでなく、怒鳴る・無視するなどの心理的な攻撃や、生活費を与えない、働くことを制限するなどの経済的な圧迫も含まれます。
また、相手が嫌がっているにも関わらず性的な行為を強要することも、性的な暴力として扱われます。
どのような行為がDVにあたるのかを正しく理解することは、自分自身の状況を客観的に見つめ直すうえで大切です。
身体的暴力|殴る、蹴るなど
DVにあたる行為の1つに、殴る、蹴る、首を絞める、包丁を突き付ける、物を投げつけるといった身体的な暴力があります。
これらの行為は身体に危害を及ぼすものであり、刑法第204条の傷害や第208条の暴行に該当する違法行為です。
配偶者間であっても、こうした行為は刑事責任を問われる可能性があります。
身体的な暴力は、ケガなどの直接的な被害にとどまらず、心にも深い傷を残します。
たとえば、暴力を受けた際の恐怖感が消えず、情緒不安定になったり、PTSD(心的外傷後ストレス障害)を発症したりするなど、心の健康に深刻な影響を及ぼすこともあるでしょう。
また、刃物を突き付ける、振り回すなどの行為も、たとえ実際にケガをさせていなくても重大なDVです。
命の危険を感じさせるような威嚇的行為は、身体的な暴力と同様に、深刻な恐怖と不安を引き起こします。
精神的暴力|暴言を吐く、物を壊すなど
言葉や態度によって相手の尊厳や自由を奪い、心理的に追い詰める行為は「精神的暴力」にあたります。「何でも従え」と命令したり、何を言っても無視したり、大声で怒鳴ったりする行為が該当します。
被害者は次第に自尊心を失い、強い不安感や恐怖に悩まされ、うつ症状やPTSDなどを発症する場合もあるでしょう。
継続的な暴言や侮辱行為があった場合、内容によっては侮辱罪や名誉毀損に問われるケースもあります。
性的暴力|性行為を強いる、中絶を強要するなど
パートナーに無理やり性行為を強要する行為は、DVの一種である「性的暴力」に該当します。
相手が頼んでいるのに避妊に協力しない、ポルノビデオやポルノ雑誌を一方的に見せつける、子どもができないことを一方的に非難する、中絶を強要するといった行為も、性的暴力に含まれます。
これらは、相手の意思や尊厳を無視し、深い精神的苦痛を与える深刻な問題です。
性的DVは、外からは見えにくいうえ、被害にあっていても自分では気づきにくいことがあります。
また、恥ずかしさや恐怖から誰にも相談できず、ひとりで悩みを抱えてしまうケースも少なくありません。
「これってDVなのかな」と感じた段階でも、まずは誰かに相談してみることが大切です。
経済的暴力|十分な生活費を渡さない、勝手に借金するなど
経済的暴力とは、配偶者やパートナーなどから金銭的な自由を奪い、相手を支配しようとする行為です。
たとえば、生活費を渡さない、外で働くことを妨げる、収入や支出を一方的に管理する、勝手に借金をするなどの行動が経済的暴力に該当します。
このような行為が続くと、被害者は生活資金を自由に使えなくなり、経済的に加害者に依存せざるを得ない立場に追い込まれてしまいます。
とくに、生活費を渡さない行為は、夫婦間の「扶養義務」に違反する行為にあたる可能性もあるでしょう。
自分の意思で働くことやお金を使うことができない状況に心当たりがある場合は、早めに専門機関へ相談することをおすすめします。
社会的暴力|外出させない、携帯を細かくチェックするなど
社会的暴力とは、パートナーの社会的な行動や人間関係を制限・遮断する行為です。
たとえば、自由に外出させない、交友関係を細かく監視する、電話やメールを細かくチェックするといった行動が該当します。
こうした行為は配偶者を社会的に孤立させ、自分以外とのつながりを絶つことで、支配しようとする行為です。
社会的暴力は、被害者の行動の自由を奪うだけでなく、孤立感や無力感を強め、深刻な精神的ダメージを与えることもあります。
子どもを巻き込む暴力|子どもに暴力を見せる、子どもを取り上げるなど
子どもに暴力を見せたり、一方的に子どもを取り上げたりする行為はDVにあたり、子どもの心身に深刻な影響を及ぼします。
たとえ子どもが直接暴力を受けていなくても、夫婦間の暴言や暴力を目の当たりにすることで、強い恐怖や不安を感じるようになります。これは「面前DV」とも呼ばれ、心理的虐待にあたります。
また、「子どもを連れていく」「お前には会わせない」などと脅す行為は、子どもを失う不安を被害者に与え、加害者に逆らうことを難しくさせてしまうでしょう。
このような暴力が子どもに与える影響としては、以下のような例が挙げられます。
- 不安・緊張・怒りなどの感情をうまくコントロールできなくなる
- 夜尿・睡眠障害・体調不良などの身体的な症状があらわれる
- 学校での集中力の低下や成績不振、人との関わりを避けるようになる
- 将来、恋人や配偶者との関係で暴力を容認・模倣してしまうことがある
こうした子どもへの悪影響は、目に見えない形で長期的に続くことがあります。とくに小さな子どもほど、傷が深くなりやすい傾向にあります。
子どもを巻き込むDVは、本人だけでなく子どもの未来までも壊してしまう可能性があるため、早期の対応が何より重要です。
少しでも「おかしい」と感じたら、迷わず専門機関に相談してみましょう。
DV被害を相談するタイミング
DV被害に直面している、あるいはその可能性に不安を感じている方の中には、「今すぐ相談すべきかどうか」迷ってしまう方も少なくありません。
DVは一時的に収まるように見えても、繰り返されるうちに徐々に深刻化していく傾向があることが、厚生労働省や内閣府の報告書でも指摘されています。
これは「DVのサイクル理論」と呼ばれ「緊張の蓄積→暴力の爆発→謝罪・優しさ」という段階を繰り返すことで、次第に暴力の頻度や強度が増していくとされています(内閣府「配偶者からの暴力に関する資料」)。
次のような状況に当てはまる場合は、早めに信頼できる機関や専門家へ相談することが大切です。
- 配偶者が暴力と謝罪を繰り返す
- 夫または妻を「怖い」と感じるようになったとき
- 夫・妻から暴力を受けても「自分が悪い」と感じる
- 夫・妻が子供に暴力をふるったとき
それぞれのケースについて、詳しくみていきましょう。
配偶者が暴力と謝罪を繰り返す
配偶者が暴力をふるったあとに謝罪し、しばらくすると再び暴力を繰り返すというような「暴力と謝罪のループ」は、DVの典型的なサイクルの一つです。
一時的な謝罪は問題が改善されたように思わせる一方で、暴力は再び繰り返される可能性が高いといわれています。
このサイクルが繰り返されることで、暴力の発生頻度や激しさが増し、被害者の心身に深刻な影響をおよぼすおそれがあります。
少しでも身の危険を感じたら、「今は大丈夫だから」と我慢せず、早めに支援機関へ相談することが大切です。
夫または妻を「怖い」と感じるようになったとき
パートナーに対して「怖い」と感じるようになったときは、DVを疑い相談を検討すべきタイミングです。
恐怖心を抱くほどに緊張を強いられ、自分の安全が脅かされていると感じるような関係は、対等な関係性が保たれていない状態であり、自分の安全が脅かされている可能性があります。
「まだ我慢できる」と思っても、その感情を軽視せず、自分自身の心の声に耳を傾けることが大切です。
迷いや不安があるときこそ、信頼できる第三者に相談してみましょう。
夫・妻から暴力を受けても「自分が悪い」と感じる
DVの被害者が相談するタイミングの1つは、夫または妻から暴力を受けても「自分が悪い」と感じる場合です。
加害者は、暴力の原因が被害者にあると思い込ませることで、相手を支配しようとする傾向があります。その影響で、被害者は自己否定を深め、自分を責めてしまうことも少なくありません。
しかし、どのような理由があっても、暴力が正当化されることはなく、責任は加害者にあります。
相談を先延ばしにしてしまうと、暴力がエスカレートしていくおそれもあるでしょう。
「自分が悪いのかも」と感じ始めたときは、1人で抱え込まず、早めに専門機関に相談することが大切です。
夫・妻が子どもに暴力をふるったとき
配偶者が子どもに対して暴力をふるった場合、それはDV被害の相談を真剣に検討すべき警告サインです。
児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)では、配偶者への暴力を子どもに見せる行為も「心理的虐待」に該当するとされています(同法第2条第4号)。
したがって、配偶者が子どもに暴力をふるう、または暴力の場面を子どもに目撃させる行為は、家庭内で児童虐待が発生している状態です。
子どもの身体的な安全だけでなく、心理的な健康と発達にも深刻な悪影響を及ぼすおそれがあります。
子どもは自分で状況から逃れることが難しいため、大人が代わって適切な支援機関に相談し、保護する責任があります。
たとえ子どもが直接的な暴力を受けていなくても、配偶者間の暴力を目撃する「面前DV」は、心理的虐待に該当し得るとされています。
こうした経験により、子どもは深刻な心理的ダメージを受けることがあり、その影響は決して軽視できません。
まとめ
DV被害にあっている、またはその可能性がある場合は、早めに専門機関に相談することが重要です。
警察や民間シェルター、弁護士、公的機関など、目的に応じて利用できる無料相談窓口が整備されています。
DVは身体的暴力に限らず、精神的・性的・経済的・社会的な隔離や、子どもを巻き込む行為も含まれます。
相談の際は、加害者に気づかれないよう配慮しながら、避難先の確保や緊急連絡先の共有、相談記録や暴力の証拠を残す準備も進めましょう。
家庭内でDVを受けているとき、誰にも相談できずに我慢してしまう方は少なくありません。
しかし、DVは深刻な問題であり、自分ひとりで解決するのは困難です。迷いや不安を感じたら、ためらわずに専門家の力を借りましょう。