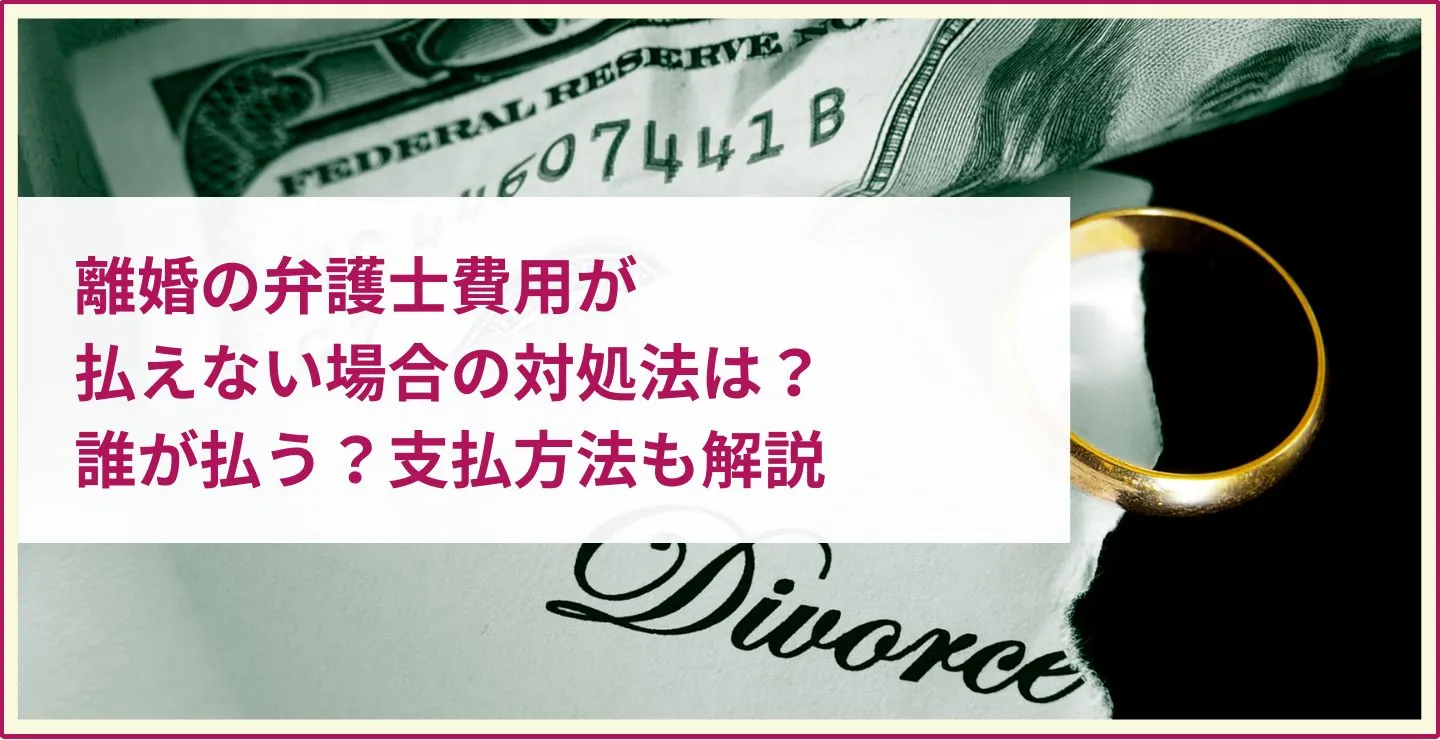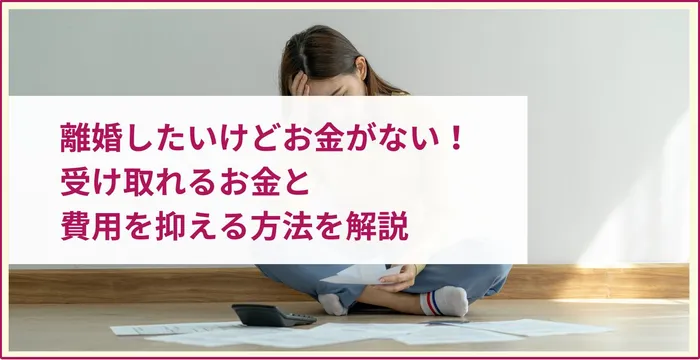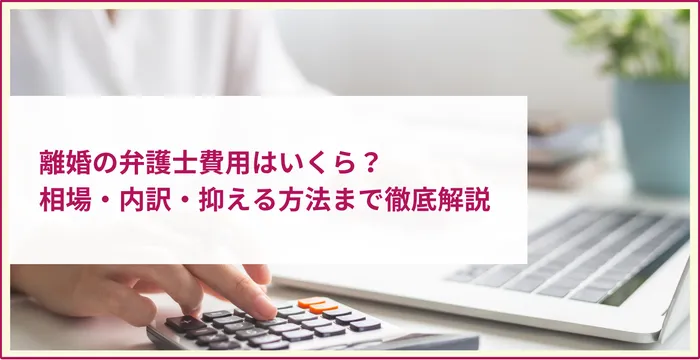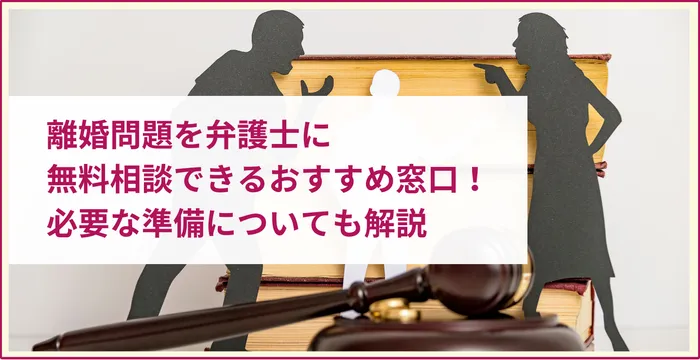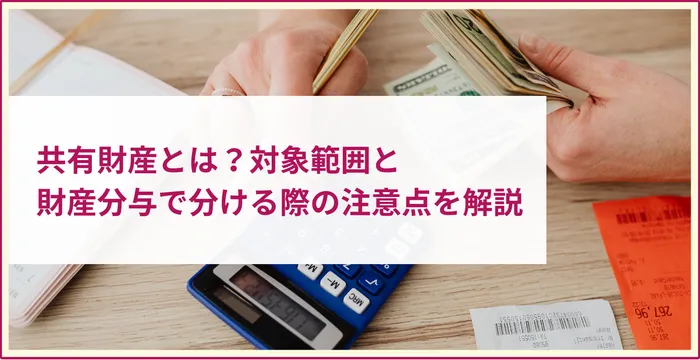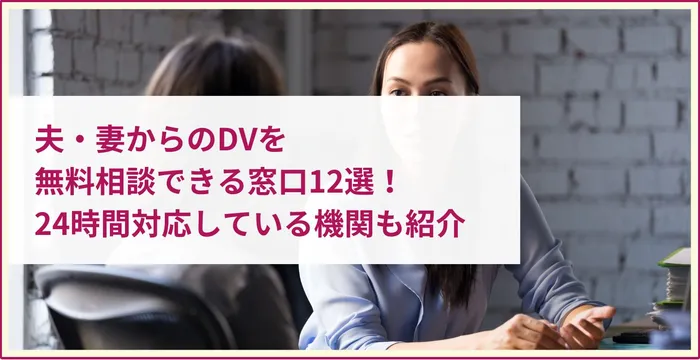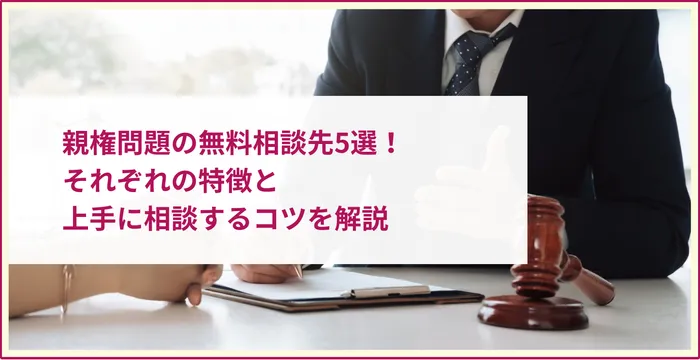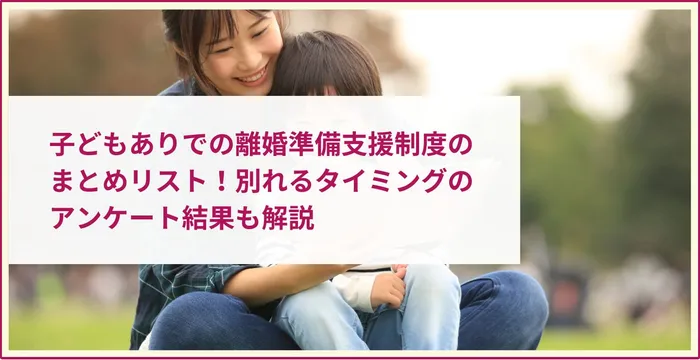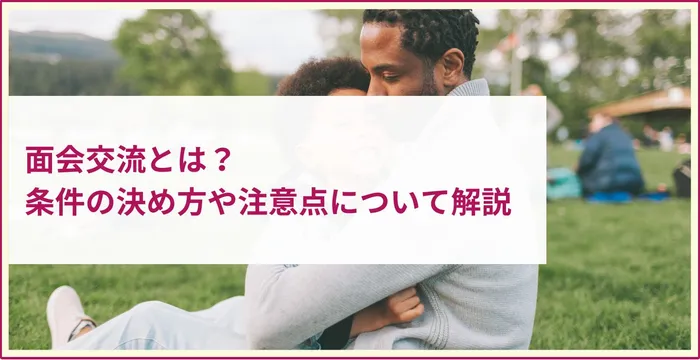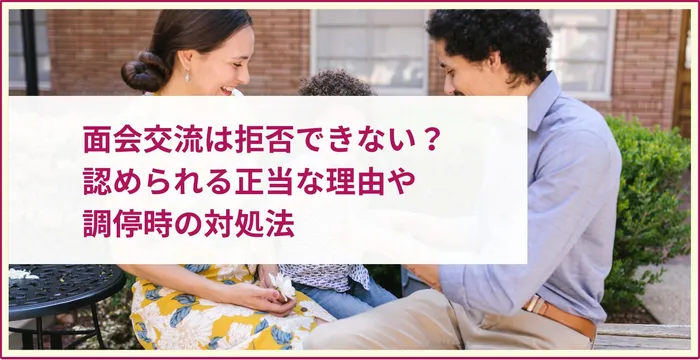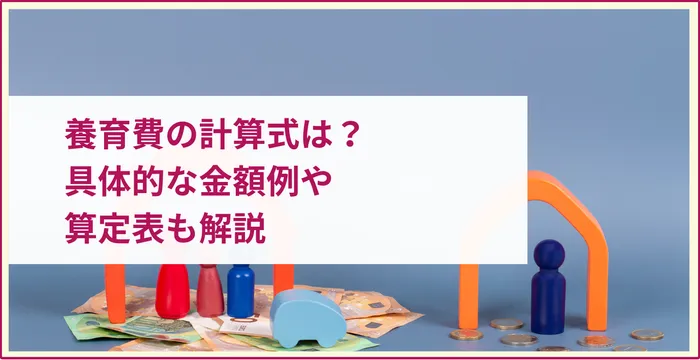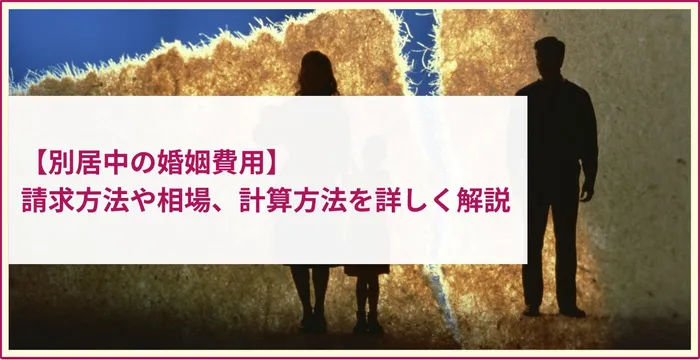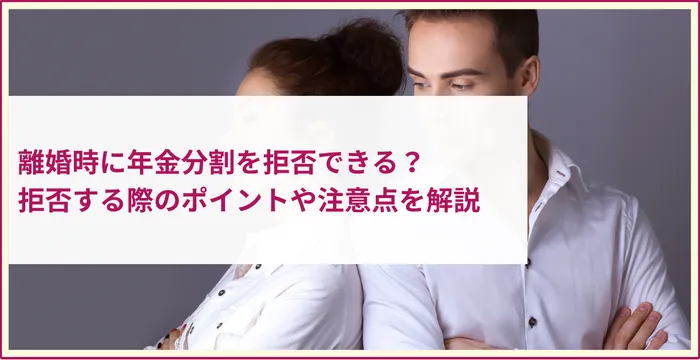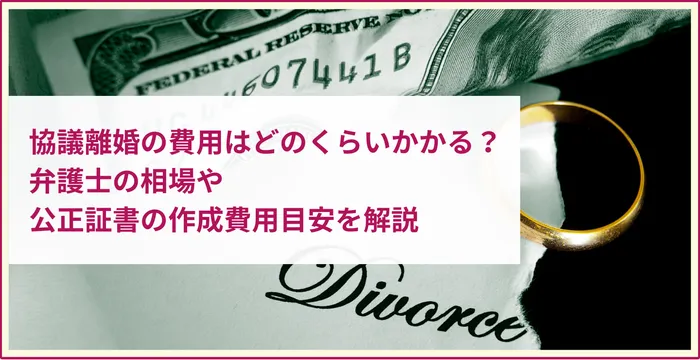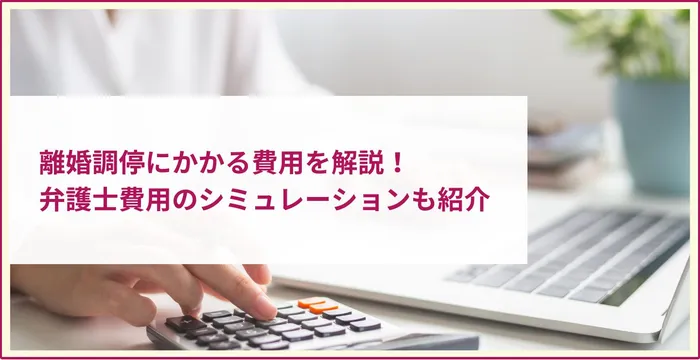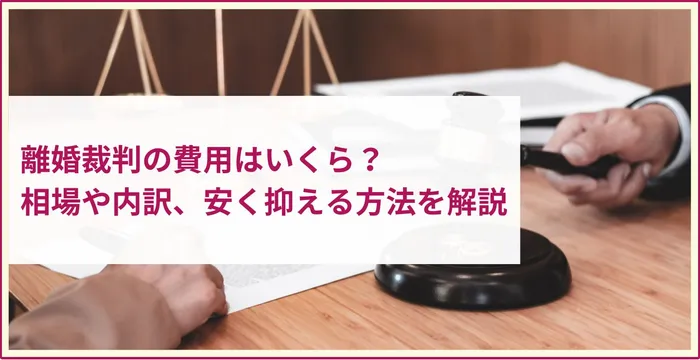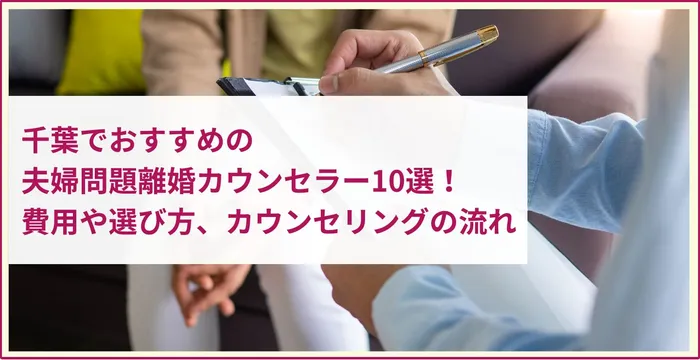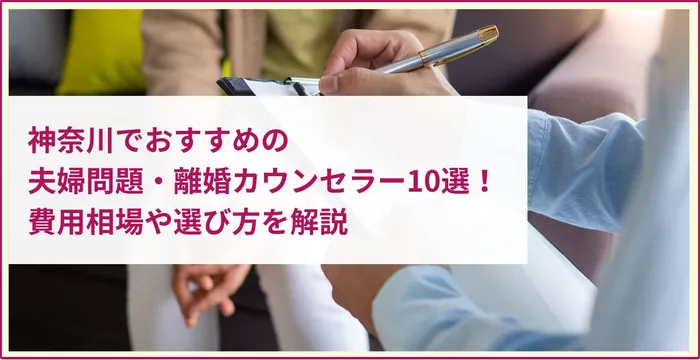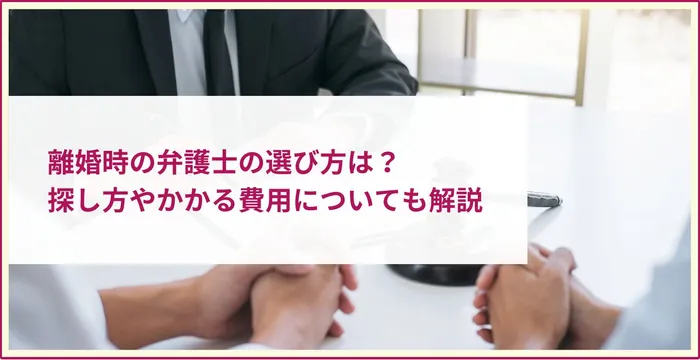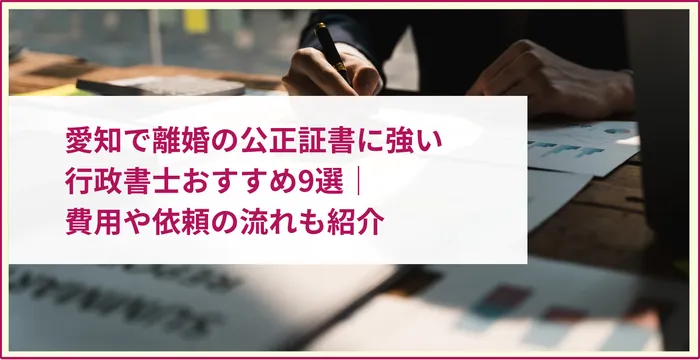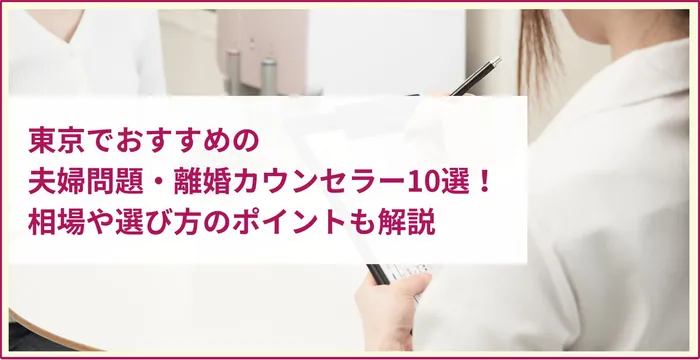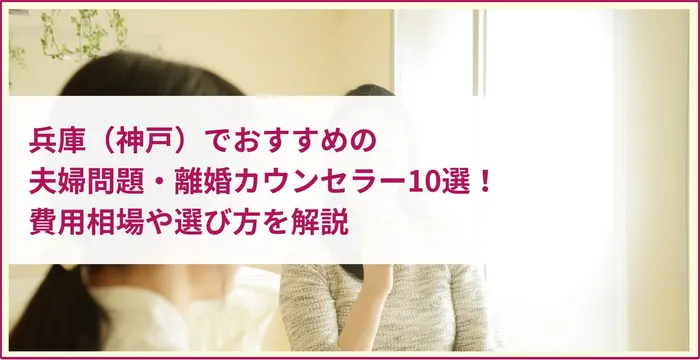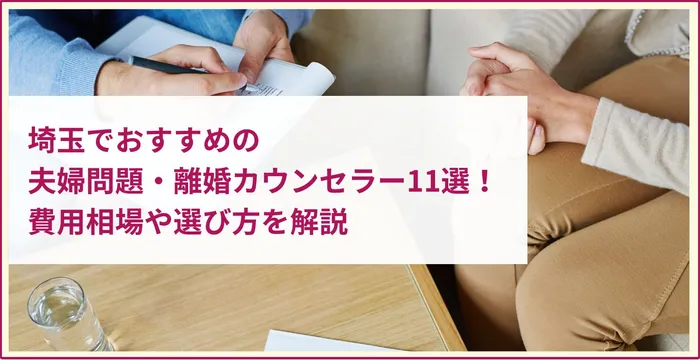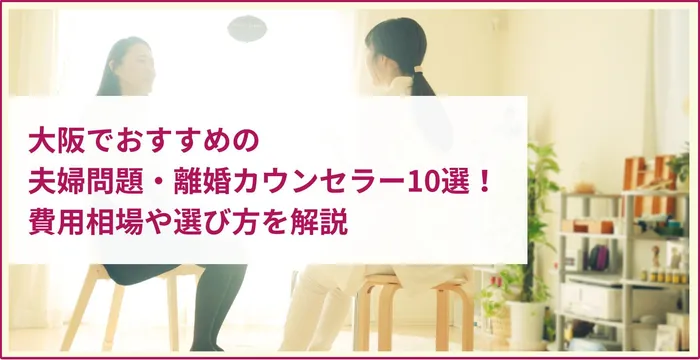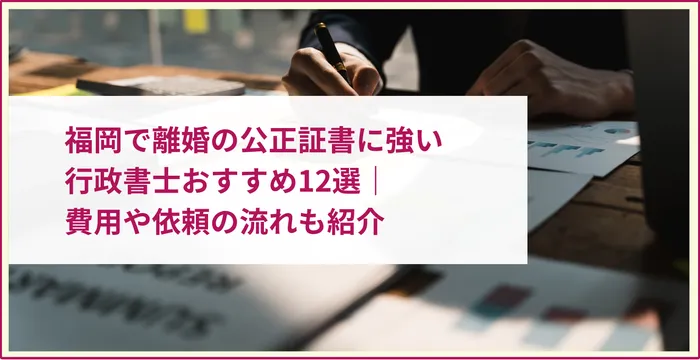離婚の弁護士費用が払えない時の支援「法テラスの代理援助」
法テラスとは、国が設立した法的トラブルを解決するための総合案内所です。法テラスにはさまざまな制度がありますが、そのなかの1つに「代理援助」があります。
代理援助とは、経済的に余裕がない人に対して、弁護士や司法書士にかかる費用の立て替えを行うための援助です。簡単にいえば、弁護士費用を用意するのが難しい場合、その費用を一時的に肩代わりしてもらえる制度です。
法テラスの代理援助で立て替えてもらえた弁護士費用は、援助開始が決まってから分割で支払っていきます。最初の支払いは離婚問題を依頼した弁護士と契約してから原則2ヵ月後です。
利用後は、原則として3年以内に完済できるように月々分割で返済していきます。離婚問題が解決するまでの間は、月々5,000〜1万円程度が目安となります。
つまり、代理援助を利用すれば、費用を一括で用意できない場合であっても、離婚問題を弁護士に依頼することができるのです。
なお、生活保護を受給している方や、支払いが著しく困難と判断された場合は、償還が免除される制度(償還免除)が適用される可能性もあります。
法テラスの代理援助の利用条件
法テラスの代理援助を利用するには、以下の条件を満たす必要があります。
- 収入と資産が一定以下であること
- 勝訴の可能性があること
- 報復や宣伝などの目的ではないこと
参照元:法テラス「民事法律扶助業務」
利用条件が定められている以上、代理援助は誰でも利用できるものではありません。
ここからは代理援助の利用条件をそれぞれ解説します。
離婚の弁護士費用に悩んでいる方は、自分が対象になるかどうか、確認する参考にしてください。
収入と資産が一定以下であること
代理援助は経済的に余裕がない人を対象にした制度です。そのため、一定以上の収入と資産がある場合には、代理援助を利用できません。
まず、収入の条件については以下のように定められています。
| 家族構成 |
月収 |
| 単身者 |
182,000円以下
(200,200円以下) |
| 2人家族 |
251,000円以下
(276,100円以下) |
| 3人家族 |
272,000円以下
(299,200円以下) |
| 4人家族 |
299,000円以下
(328,900円以下) |
参照元:法テラス「代理援助及び書類作成援助資力基準」
※()内の金額は東京・大阪などの大都市の基準価格
※5人家族以上は、1人増えるごとに30,000円(33,000円)が加算される
※医療費、教育費などの出費がある場合、一定額が考慮される
ただし、家賃や住宅ローンを自身で負担している場合、以下の金額を最大として月収の条件に負担金額が加算されます。
- 単身者:41,000円
- 2人家族:53,000円
- 3人家族:66,000円
- 4人家族:71,000円
たとえば、大都市以外の単身者の場合、代理援助の対象となるのは月収182,000円以下の場合です。しかし、自身で毎月5万円の家賃を負担している場合は41,000円が条件に加算されるため、月収の基準は223,000円となります。
次に、保有資産の条件です。保有資産には、「現金」「預貯金」「有価証券」「自宅と係争物件を除いた不動産」が該当します。
代理援助を利用するには、保有資産の価値の合計が以下の基準を下回っていなければなりません。
| 家族構成 |
保有資産の合計金額 |
| 単身者 |
180万円以下 |
| 2人家族 |
250万円以下 |
| 3人家族 |
270万円以下 |
| 4人家族 |
300万円以下 |
※医療費、教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます
たとえば、単身者の場合、保有資産に関する条件は180万円までです。現金や預貯金などの合計が180万円を超えていると、原則代理援助の対象外となります。
なお、収入や資産の基準は原則として世帯全体で判断されますが、離婚などで配偶者が訴訟の相手方となる場合は、本人の収入と資産のみで審査されます。同居していても、配偶者が相手であれば合算されません。
申請時には、源泉徴収票や通帳の写しなどの証明書類を提出し、収入や資産の条件を満たしているかどうかが審査されます。
また、法テラスでは、代理援助の利用条件を満たしているかの相談が可能です。収入や資産の条件はやや複雑なため、不安がある場合は、法テラスの「相談窓口・法制度」を参考にし、早めに問い合わせてみるとよいでしょう。
勝訴の可能性があること
離婚問題を弁護士に依頼する際、裁判に発展する可能性もあります。その場合、勝訴の可能性があることが代理援助の条件となります。
勝訴とは、訴訟(裁判)に勝つこと、または有利な判決を受けることです。離婚問題における勝訴の見込みがないケースには以下のようなものが挙げられます。
- 法テラスの利用者が離婚原因をつくった場合
- 法定離婚事由が存在しない場合
- 法定離婚事由があっても、証明する主張や証拠が不十分な場合
このように、離婚理由に法的根拠がない場合や、証拠が不十分なケースでは、勝訴の見込みがないと判断される可能性があります。
法定離婚事由とは、民法第770条(裁判上の離婚)によって定められている、裁判で離婚が認められる理由です。具体的には以下の5つが法定離婚事由として規定されています。
| 法定離婚事由 |
概要 |
| 不貞行為 |
配偶者以外と肉体関係を持つこと(貞操義務違反) |
| 悪意の遺棄 |
正当な理由なく同居・協力・扶助義務を放棄すること |
| 生死不明 |
配偶者の生死が3年以上明らかでない場合 |
| 回復見込みのない強度の精神病 |
配偶者が重い精神病で回復の見込みがないとき
※2024年の法改正により削除されました。
ただし、状況によっては第5号「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当する可能性があります。 |
| 婚姻を継続しがたい重大な事由 |
暴力や価値観の不一致など、結婚生活の継続が困難な場合 |
参考:民法第770条 裁判上の離婚|民法
離婚問題で裁判を視野に入れている場合、これらの法定離婚事由を証明できなければ、代理援助を利用できません。裁判を検討している場合には、条件を満たしているか確認しておきましょう。
なお、離婚問題は必ず裁判になるわけではなく、多くの場合は和解や調停、示談で解決します。その場合も、多くのケースで「勝訴の可能性がある」と判断されます。
※補足:2024年の法改正により、「強度の精神病」は裁判上の離婚理由から削除されました。
これは、介護や支援により婚姻の継続が可能な場合があることや、精神疾患に対する差別的な扱いを避けるためとされています。
ただし、精神疾患が原因で夫婦関係が破綻している場合は「婚姻を継続しがたい重大な事由」(第5号)として離婚が認められる可能性があります。
報復や宣伝などの目的ではないこと
法テラスでは、代理援助の利用条件として「民事法律扶助の趣旨に適していること」を定めています。民事法律扶助とは、資力が乏しい人のために法律相談を行ったり、司法書士や弁護士を利用する場合に発生する費用を立替えたりするものです。
弁護士に依頼する目的が、感情的な報復や宣伝目的、あるいは法律的な根拠が薄い訴訟を起こすことが目的の場合、民事法律扶助の趣旨に反するため、代理援助だけでなく、法テラスも利用できません。
そのほか、以下のような場合も民事法律扶助の趣旨に反するとして、代理援助は利用できない可能性があります。
- 訴額が極端に少ない場合
- 相手から資産を回収できない場合
- 他人への嫌がらせが目的の場合
- 反社会的な行為が目的の場合
- 違法行為を目的とした場合
- 立替費用の返済意思がない場合
代理援助は「援助がなければ弁護士に依頼できない人」を対象にした制度です。「相手に仕返ししたい」といった感情的な目的での利用は認められていません。
法テラスの代理援助を利用した場合の弁護士費用の支払方法
法テラスの代理援助を利用すると、発生した弁護士費用はいったん法テラスが立て替え、あとから分割で返済していく形になります。原則として、弁護士と契約してから2ヵ月後から、口座引き落としによる毎月の支払いが始まります。
金融機関ごとの支払い日は以下のとおりです。
|
ゆうちょ銀行 |
ゆうちょ銀行以外の金融機関 |
| 返済日 |
毎月15日または25日 |
毎月27日 |
| 引き落とし手数料 |
33円 |
40円 |
※返済日が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日に引き落とし
なお、担当弁護士に相談すれば、数ヵ月分をまとめて支払ったり、残額を一括返済したりすることも可能です。
「いまは費用の用意が難しくても、離婚問題解決後はある程度余裕ができる」という場合は、返済を長引かせないためにも、まとめて支払うなどの対応を検討するとよいでしょう。
詳しくは、法テラスの公式サイト「弁護士費用等の立替え制度」もあわせてご覧ください。
法テラスを利用する際の注意点
法テラスの代理援助を利用する場合、以下のポイントに注意しましょう。
- 飛び込みで利用する場合は弁護士を選べない
- 審査に時間がかかる
- 無料相談は3回までしか受けられない
- 熱心に対応してもらえない場合がある
以下では、利用前に知っておきたい主な注意点を解説します。
飛び込みで利用する場合は弁護士を選べない
まず、法テラスの窓口で直接申し込む(飛び込みで利用する)場合、原則として弁護士を自分で選ぶことはできません。
そのため、離婚問題で相談したいのに対応する弁護士が離婚事件に不慣れなケースもあり、相談者との間でミスマッチが起こる可能性があります。
ミスマッチを避けたい場合は「持ち込み方式」を利用するのがおすすめです。持ち込み方式とは、法テラスと契約している弁護士に自ら相談し、その弁護士が法テラス制度を利用して受任する形をいいます。
法テラスと提携する弁護士のなかから離婚問題に精通している弁護士を探し「法テラスの法律扶助制度を利用したい」と伝えてみるとよいでしょう。弁護士が制度の利用に同意すれば、そのまま相談・申込み・手続きまで一括して対応してもらえます。
なお、持ち込み方式を利用するには、希望する弁護士が法テラスの「民事法律扶助取扱登録弁護士」である必要があります。
審査に時間がかかる
法テラスの代理援助を利用するには、収入・資産・事件内容などに関する審査が必要で、書類提出から2週間〜1ヵ月程度かかることがあります。
そのため、すぐに調停や訴訟対応が必要な場合など、時間的な余裕がないときは、代理援助の利用が間に合わない可能性があります。
法テラスの利用を検討している場合は、審査の期間を考慮して早めに相談を始めることが大切です。
代理援助が間に合わない場合は、分割払いや後払いなどに対応している弁護士事務所を探すのも1つの方法です。
無料相談は3回までしか受けられない
法テラスでの無料相談は1件につき原則3回までで、各回の相談時間は30分が上限とされています。
30分の相談時間では離婚問題に関する悩みや疑問を聞ききれない場合もあるため、すべての不安を解消できるとは限りません。
できるだけ時間を有効活用するためには、現在の状況や弁護士に相談したい内容を書面にまとめておくなどの工夫が必要です。
熱心に対応してもらえない場合がある
法テラスを通じて依頼する場合、担当弁護士によっては対応が形式的になってしまうケースもあるようです。これは、法テラス経由の案件は報酬額が一定額に抑えられているためです。
そのため、相談前に「法テラスの制度を利用しても丁寧に対応してもらえるか」を確認したり、実際のやりとりで信頼できるかどうかを見極めたりすることが大切です。
もし信頼関係を築くのが難しいと感じた場合は、自分で弁護士を探すことも検討してみましょう。
法テラス以外で弁護士費用を用意する方法
法テラスの代理援助は利用条件があるため、誰でも必ず利用できる制度ではありません。そのため「弁護士費用を払えないうえに代理援助も利用できない」というケースも考えられます。
そのような場合には、以下の方法を検討してみましょう。
- 着手金の分割や後払いに対応してもらえるか相談する
- 日弁連の法律援助を申し込む
それぞれの方法について、詳しく解説します。
着手金の分割や後払いに対応してもらえるか相談する
弁護士事務所によっては、着手金の分割払いや後払いに対応している場合もあります。そのような事務所であれば、弁護士費用を一括で用意する必要がないため「費用が足りない」という場合でも依頼しやすくなります。
着手金は契約時に支払うのが一般的ですが、必ずしも法律で定められているわけではありません。そのため、事務所や弁護士との交渉次第では、分割払い・後払いに応じてもらえる可能性があります。
たとえば、以下のような場合、分割払いや後払いに応じてもらえる可能性があります。
- 事件の終結後に経済的利益を得られる可能性が高い
- 弁護を依頼する際に経済的に困窮している
- すぐには着手金を用意できないが、近い将来に収入が確実に見込める
- 弁護士と依頼者の間に信頼関係が構築されている
ただし、分割払いや後払いを選んだ場合、通常どおり弁護士費用を支払うよりも、総額が高くなる可能性があります。
少しでも弁護士費用を抑えながら離婚問題の解決を依頼したい場合は、複数の弁護士事務所に相談して見積もりを出してもらい、比較することが大切です。
着手金を通常どおり支払う場合と、分割払いや後払いにする場合を比較したり、弁護士事務所ごとの費用を比べたりして、自分に合った支払い方法を選びましょう。
日弁連の法律援助を申し込む
日本全国すべての弁護士が登録をしている「日本弁護士連合会(日弁連)」は、法律援助事業も行っています。
日弁連の法律援助事業は、法テラスの制度の対象とならない場合をカバーするための事業であり、依頼者の弁護士費用の援助を行っています。
そのため、法テラスの代理援助を利用できない場合でも、日弁連の法律援助を申請することで弁護士に離婚問題を依頼できる可能性があるのです。
日弁連の法律援助の申請は、弁護士を通して行う必要があります。また、援助の可否は依頼者の状況や案件の内容によって判断されるため、弁護士に離婚問題を相談する際に、日弁連の法律援助を受けられるかどうかも相談してみるとよいでしょう。
なお、日弁連の法律援助制度は主に刑事事件や少年事件、DV保護命令などを対象とした制度であり、一般的な離婚事案については対応していない可能性もあります。事案によっては法テラスを通じた支援のほうが適している場合もあるため、まずは相談時に対象となるか確認しておくとよいでしょう。
離婚問題の弁護士費用は自己負担が原則
離婚問題を弁護士に依頼した場合、費用は原則として自己負担になります。相手に弁護士費用を請求することは、基本的に難しいと考えておきましょう。
たとえば、配偶者が離婚を申し立て、自分は離婚を望んでいない状況であっても、自分の弁護士費用は自己負担となるのが通常です。
ただし、相手に重大な落ち度がある場合などには、例外的に弁護士費用の10%を請求できるケースもあります。
ただし、相手に重大な落ち度がある場合などには、例外的に弁護士費用の一部(10%程度)を請求できるケースもあります。たとえば、不貞行為を理由とした損害賠償請求訴訟で、<東京高等裁判所が平成10年12月21日に言い渡した判決では、慰謝料200万円の支払いに加え、弁護士費用としてその10%にあたる20万円の負担が認められました。
なお、裁判所が弁護士費用相当分の請求を認めるのは、慰謝料などの金銭支払いを命じる判決が出た場合に限られるため、示談や調停では適用されません。
ただし、示談交渉の過程で、弁護士費用の一部を相手方に負担させる合意が成立する場合もあります。
このように、状況によっては相手に弁護士費用を請求できる可能性もゼロではないため、初回相談の際に「弁護士費用を相手に請求できる見込みがあるかどうか」を確認しておくとよいでしょう。
離婚問題にかかる弁護士費用の相場は「20~110万円」
離婚問題にかかる弁護士費用の相場は20万~110万円程度とされています。費用に幅があるのは、問題解決の難易度によって費用が変動するためです。一般的には、協議離婚、離婚調停、離婚裁判の順に費用が高くなる傾向にあります。
具体的な弁護士費用としては相談料や着手金、成功報酬、日当・実費が発生します。各費用のおおよその目安は以下のとおりです。
| 項目 |
費用相場 |
| 相談料 |
0円~1万円(1時間あたり)
※無料相談の弁護士事務所もあり
|
| 着手金 |
0円~40万円
※着手金が無料の弁護士事務所もあり |
| 報酬金 |
離婚成立:20万~30万円
慰謝料請求:獲得金額の10~20%
財産分与:獲得金額の10~20%
親権の獲得:10万~20万円
養育費の獲得:合意金額の2~5年分の10~20%
|
| 日当 |
1日あたり3万~5万円 |
| 実費 |
都度発生 |
それぞれ詳しくみていきましょう。
相談料は1時間あたり0円~1万円程度
相談料とは弁護士が依頼を受ける前に、利用者がどのような悩みを抱えているのかヒアリングする際に発生する費用です。
無料相談を受けたからといって、その弁護士事務所に必ず依頼しなければならないわけではありません。まずは複数の事務所に相談して、自分に合った弁護士を探すことが大切です。
着手金は0円~40万円程度
着手金とは、実際に弁護士に対応を依頼する際に支払う手付金です。
この費用は、弁護士が業務に着手するために必要とされるものであり、結果にかかわらず原則として返金されません。たとえば、希望どおりの解決に至らなかった場合や、途中で依頼を取り下げた場合でも返金はされない点に注意が必要です。
着手金の金額は、業務内容の難易度や案件の見通しなどによって異なります。離婚問題では20万~40万円程度が一般的ですが、依頼する弁護士事務所によって変動します。
なお、着手金を無料としている弁護士事務所もありますが、その場合は成功報酬が高めに設定されているケースもあるため、事前にトータルの費用を確認しておくことが大切です。
報酬金は20万~30万円(+経済的利益の10%~20%)程度
報酬金とは、離婚が成立した場合や、離婚により経済的利益が得られた場合に支払う弁護士への報酬です。
事務所によって報酬金の設定は異なりますが、一般的には以下のような金額が相場とされています。
| 項目 |
報酬金の相場 |
概要 |
| 離婚成立 |
20万~30万円 |
協議・調停・裁判のいずれかで離婚が成立した場合 |
| 慰謝料請求 |
経済的利益の10~20% |
獲得できた慰謝料額に応じて算出 |
| 財産分与 |
経済的利益の10~20% |
分与された資産額に応じて算出 |
| 親権の獲得 |
10万~20万円 |
親権が争点となった場合 |
| 養育費の獲得 |
合意金額の2~5年分の10~20% |
継続的な給付に対する報酬 |
たとえば「離婚成立で20万円」「経済的利益×10%」を報酬金としている弁護士事務所に依頼した場合の報酬金は以下のとおりです。
例)離婚成立、財産分与500万円
20万円+(500万円×10%)=70万円
ここでいう「経済的利益」とは、慰謝料や財産分与、養育費のように、依頼者が弁護士の関与によって金銭的に得た成果を指します。現金だけでなく、不動産や株式、退職金の分割といった現物支給も経済的利益として評価される場合があります。
報酬金の有無や金額は「どこまで達成できれば成功とみなすか」によって異なるため、あらかじめ弁護士と取り決めておくことが大切です。なお、依頼者に経済的利益がまったくなかった場合は、報酬金が発生しないケースもあります。
日当は1日あたり3万~5万円程度
日当とは、弁護士が事務所外で活動した場合に発生する費用です。裁判所への出廷や、相手方との交渉で居住地に出向く場合などに発生します。
日当の相場は1日あたり3万~5万円程度ですが、旧日弁連の報酬基準に基づき、往復に4時間以上かかる場合は10万円程度に設定されているケースもあります。
日当の金額や発生条件は弁護士事務所によって異なるため、依頼前に必ず確認しておくことが大切です。
実費は都度発生
実費とは、離婚問題の解決に際して弁護士が実際に出費した費用です。
主な実費の例は以下のとおりです。
- 収入印紙代・郵便切手代
- コピー代
- 交通費・宿泊費
- 保証金・供託金
- 公正証書作成費用
これらの費用は、基本的に弁護士が立て替えたうえで、後から精算して請求されるのが一般的です。ただし、事務所によっては着手金のなかに実費が含まれている場合もあります。
依頼前に、実費の取り扱いや請求方法について確認しておきましょう。
離婚問題を弁護士に依頼した場合の費用相場については、以下の記事も参考にしてください。
離婚の弁護士費用を少しでも抑えるための対策
離婚の弁護士費用は高額なため、少しでも費用を抑えたいと考える人もいるでしょう。その場合、以下のような対策があります。
- 無料相談を利用する
- 協議や調停の段階で解決できるように弁護士に相談をする
- 複数の弁護士事務所に費用を見積もってもらう
- 裁判なら訴訟救助制度を活用する
- 親族や知人から支援してもらう
1つでも多くの対策を講じることで、弁護士費用の負担を軽減できる可能性があります。状況に応じて、実行しやすい方法から検討してみてください。
無料相談を利用する
離婚問題の弁護士費用を抑えるためには、無料相談を利用するのもおすすめです。
弁護士事務所は無料相談に対応しているのが一般的です。無料相談では、費用をかけずに弁護士からの専門的な意見を聞くことが可能です。
また、離婚問題や弁護士費用の目安についても相談できるため、今後の見通しを明確にできるなどのメリットがあります。
さらに、無料相談に対応してくれた弁護士を信頼できると感じた場合、無料相談後にそのまま見積もりや対応を依頼することもできます。
なお、無料相談を利用する場合、離婚問題について相談できることを謳っている弁護士事務所を利用するのがおすすめです。弁護士事務所が無料相談に対応するジャンルは、その弁護士事務所が注力している分野である可能性が高いためです。
弁護士に相談するためのお金の余裕がない場合は、離婚問題に強い弁護士事務所の無料相談を利用しましょう。
ただし、無料相談の多くは初回相談に限られ、時間も30分から1時間程度となっています。具体的な戦略提案や文書作成までは対応していない場合もあるため、あくまで費用や対応方針の確認にとどめておくとよいでしょう。
無料相談の窓口については、以下の記事でも詳しく解説しています。
協議や調停の段階で解決できるように弁護士に相談をする
離婚問題にかかる弁護士費用は、問題が深刻化するほど高額になるのが一般的です。裁判にまで発展すれば、100万円ほどの費用がかかるケースもあります。
そのため、可能であれば協議や調停の段階で離婚問題を解決させることが弁護士費用を抑える対策ともいえます。
協議や調停であっても、弁護士に正式に依頼すれば着手金や報酬金が発生しますが、裁判に進むより費用は抑えられるのが一般的です。
また「相談のみ」にとどめれば、費用を最小限にしながら弁護士の専門的なアドバイスを受けることが可能です。協議や調停の準備段階で適切な助言を得られれば、裁判を避けられる可能性も高まります。
離婚問題を弁護士に相談する際は、裁判に発展しないようにどのような選択肢があるか確認しておくとよいでしょう。
複数の弁護士事務所に費用を見積もってもらう
弁護士費用は弁護士事務所によって異なり
ます。そのため、依頼したい弁護士が定まっていない場合は、複数の事務所に費用の見積を依頼してみましょう。
複数の見積もりを比較することで、費用の相場や各事務所の対応内容が見えてきます。そのうえで、費用を抑えながら信頼できる弁護士を選ぶことが可能になります。
一般的に法律事務所では、初回無料相談に対応しています。初回無料相談の際には、具体的にどれほどの費用がかかるのか確認しておくとよいでしょう。
裁判なら訴訟救助制度を活用する
離婚問題によっては、裁判が必要なケースもあります。裁判に発展した場合、弁護士費用だけでなく、裁判所に支払う費用も必要です。
裁判所に支払う費用は、裁判の内容によって異なります。たとえば、離婚のみを求める場合は13,000円程度、慰謝料や財産分与などもあわせて請求する場合は20,000円ほどかかるのが一般的です。
これらは弁護士費用とは別にかかるため、経済的な負担が大きくなる場合もあります。そのような場合に検討したいのが、訴訟救助制度の利用です。
訴訟救助制度は、裁判に必要な費用の用意が難しい人に対し、印紙代や郵便切手代などの支払いを猶予する制度です。裁判終了時まで支払いが猶予されるため、一時的な費用負担を軽減できます。
ただし、訴訟救助制度を利用できるのは、勝訴の可能性がある場合のみです。利用を希望する場合は、あらかじめ弁護士に相談し、勝訴の可能性について意見をもらったうえで申請に進むとよいでしょう。
なお、訴訟救助の申請は原則として本人が行いますが、弁護士の協力を得ながら準備することも可能です。
親族や知人から支援してもらう
離婚問題の弁護士費用を少しでも抑えたい場合、親族や知人に支援してもらうのも1つの方法です。
離婚に関して弁護士へ対応を依頼したい事情を真剣に説明すれば、援助を申し出てくれる人が見つかる可能性があります。
離婚は人生において大きな出来事の1つです。弁護士に依頼できなかった結果、不利な条件で離婚が成立してしまい、後悔するケースもあり得ます。
費用の面で弁護士への依頼をためらっている方は、まずは信頼できる人に相談してみるのも選択肢の1つです。
なお、金銭的な支援を受ける場合は、将来的なトラブルを避けるために、支援の金額や返済条件を書面に残しておくことをおすすめします。
可能であれば、第三者に立ち会ってもらうことでより安心できる環境を整えられます。
費用がかかっても弁護士への依頼をおすすめするケース8選
これまで見てきたように、離婚問題を弁護士に依頼すれば、一定の費用がかかります。費用面を理由に、依頼をためらう人もいるかもしれません。
しかし、状況によっては、費用をかけてでも弁護士に対応を依頼したほうがよいケースもあります。とくに以下のような争点がある場合は弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
- 財産分与
- DV被害
- 親権争い
- 面会交流権の争い
- 養育費争い
- 慰謝料争い
- 婚姻費用争い
- 年金分割争い
これらの問題は複雑になりやすく、自分だけで対応すると不利な条件で合意させられてしまうおそれもあります。弁護士に依頼すれば、法的な主張や交渉を適切に行ってもらえるため、自分にとって納得のいく結果を得やすくなるでしょう。
財産分与
財産分与について協議する場合、弁護士に対応を依頼したほうがよいでしょう。財産分与は離婚条件として争いになるケースが多く、当事者同士の対立が激しくなりやすいためです。
財産分与とは、結婚してから夫婦が協力して築いた財産を、離婚する際に公平に分け合う制度のことをいいます。多くの場合、夫婦の財産を清算する「清算的財産分与」が行われます。
結婚生活を営むなかで取得した財産は、共有財産となるのが原則です。たとえば、夫が支払って取得した家や自動車などの財産でも、妻の協力があって取得できたものとして考えられるため、片方の収入が少ない場合でも夫婦の共有財産となるのが一般的です。
財産分与の対象となる代表的な財産は以下のとおりです。
| 財産の種類 |
具体例 |
| 共有名義の財産 |
建物や土地などの不動産 |
| どちらのものかわからない財産 |
家具、家電などの家財 |
| 単独名義の財産 |
夫婦どちらかの不動産や車、預貯金、有価証券など |
婚姻前から保有していた財産や、相続・贈与によって取得した財産は「特有財産」とされ、原則として財産分与の対象には含まれません。
基本的に財産分与は夫婦同士の判断に委ねられますが、簡単には解決できないケースも多くあります。
離婚時の財産分与は、知識がないまま進めると不利な合意となる可能性があります。とくに財産が多いケースでは夫婦間の対立が深まり、合意が難航しがちです。
財産分与の協議は弁護士に依頼することで、保有財産をより公平に分けられる可能性が高まります。また、交渉を任せることで、時間や労力を抑えられ、精神的な負担も軽くなるでしょう。
なお、財産分与について離婚後に協議することもできますが、相手が財産を処分したり、使ったりするリスクがあるほか、離婚から2年が経過すると財産分与を受ける権利が消失するなど、トラブルに発展する可能性もあります。
財産分与については、離婚成立前に弁護士に入ってもらい、スムーズに協議を終わらせることが大切です。また、そもそも共有財産がどれくらいあるのか正確に把握するために、助言してもらう段階から弁護士に相談すれば、その後の交渉を依頼する場合も安心できるでしょう。
財産分与の対象となるもの・ならないものについては以下の記事を参考にしてください。
DV被害
DV被害を受けている場合は、早い段階で弁護士に相談・依頼することをおすすめします。弁護士に相談すれば、身の安全を確保しながら、必要な法的手続きを適切に進めやすくなります。
DV(ドメスティック・バイオレンス)とは、配偶者や恋人のような親密な関係にある人から振るわれる暴力です。身体的暴力だけでなく、精神的・経済的・性的・社会的な暴力も含まれます。
主な種類と具体例は以下のとおりです。
| DVの種類 |
具体例 |
| 身体的暴力 |
殴る、蹴る、物を投げる、髪を引っ張る、首を絞めるなど |
| 精神的暴力 |
暴言、無視、脅迫、人格否定、過度な束縛や監視など |
| 経済的暴力 |
生活費を渡さない、勝手に財産を使う、就労を妨害するなど |
| 性的暴力 |
同意のない性的行為、避妊を拒否する、性的な言動を強制するなど |
| 社会的暴力 |
実家や友人との連絡を絶たせる、外出を制限するなど |
DV被害を受けている場合、対応を弁護士に依頼するメリットは次のとおりです。
- 相手との交渉を代行してくれる
- 保護命令の申し立てを依頼できる
- 適正な慰謝料を請求できる
弁護士に依頼することで、DV加害者と直接やり取りせずに離婚を進められます。調停や裁判になった場合でも、対応を任せられるため、依頼者の安全確保につながります。
状況に応じて裁判所に対して保護命令の申し立てを行うことも可能です。
保護命令の種類と内容は以下のとおりです。
| 命令の種類 |
内容 |
期間 |
| 接近禁止命令 |
申立人の住居や勤務先などに近づくことを禁止 |
6ヵ月 |
| 電話等禁止命令 |
電話・SNS等での面会要求や脅迫的言動を禁止 |
6ヵ月 |
| 子どもへの接近禁止命令 |
子どもの身辺や学校などに近づくことを禁止 |
6ヵ月 |
| 親族等への接近禁止命令 |
申立人の親族や関係者への接近を禁止 |
6ヵ月 |
| 退去命令 |
相手に家から退去し、家の付近の徘徊を禁止 |
2ヵ月 |
参考:保護命令の申し立てを希望される方へ|裁判所
相手が保護命令に違反した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
申し立てには、DV被害を相談した証拠(相談記録や被害届の控えなど)が必要になります。そのため、事前に配偶者暴力相談支援センターや警察などに相談し、記録を残しておくようにしましょう。
また、離婚の原因が相手のDV行為である場合、不法行為にもとづく損害賠償請求(慰謝料)も可能です。慰謝料の相場は50万〜300万円程度で、DVの内容や婚姻期間などによって異なります。
DV被害によって離婚を検討している場合は、弁護士に相談・依頼することで、安全かつ有利に手続きを進められる可能性が高まります。
DVの無料相談ができる窓口については、以下の記事で詳しく解説しています。
親権争い
親権争いが発生する場合も、弁護士に対応を依頼するのが賢明です。子どもの親権を夫婦のどちらが得るのかは、離婚協議での争点になりやすいためです。
離婚時の子どもの親権は、母親が有利とされる傾向がありますが、裁判所は「子の福祉」を最優先に、どちらが主に監護していたか(主たる監護者)を重視して判断します。また、子どもがおおむね10歳以上であれば、本人の意思も尊重される傾向にあります。
裁判所が親権者を決める際は、子どもの年齢や性別、兄弟姉妹との関係、監護環境の安定性なども考慮されます。
親権争いの対応を弁護士に依頼した場合のメリットは次のとおりです。
- 交渉を有利に進められる
- 調停や訴訟を見据えて交渉できる
- 調停や訴訟で有利になる証拠を集められる
- 手続きを任せられる
弁護士に早い段階で依頼しておけば、調停前から主張や証拠の準備を整えやすくなり、交渉を優位に進められる可能性があります。調停が訴訟に発展した場合も、弁護士が粘り強く対応してくれるため、安心して手続きを進められるでしょう。
また、親権の獲得に向けて有利になる事情や証拠を整理し、客観的な視点で主張を組み立ててくれる点もメリットです。調停や訴訟に関する煩雑な手続きはすべて弁護士が対応してくれるため、精神的・時間的な負担を軽減できます。
親権の獲得を強く希望する場合は、できるだけ早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
親権問題の無料相談先や、子連れ離婚になる場合に知っておきたいことについては以下の記事を参考にしてください。
面会交流権の争い
相手方と面会交流権を争う場合も、弁護士に対応を依頼したほうがよいでしょう。依頼者にとって有利な条件で面会交流権に関する取り決めができるためです。
面会交流権とは、子どもと別居して暮らす親が、子どもと会ったり連絡を取ったりする権利です。民法第766条に基づき、「子どもの利益」が最も重要な判断基準とされています。
面会の可否や方法を決める際には、子どもの年齢や生活環境、親子関係、精神的な影響などが総合的に考慮されます。たとえば、過去にDVや虐待があった場合や、子どもが強く拒否しているようなケースでは、面会交流を制限または拒否できる正当な理由になることがあります。
面会交流について弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
- 冷静な協議や取り決めができる
- 希望する面会条件を具体的に主張できる
- 公正証書や調停調書を通じて将来のトラブルを予防できる
夫婦間の感情がもつれていると、当事者同士で落ち着いた話し合いをするのは難しくなりがちです。弁護士に同席や代理を依頼すれば、冷静かつ法的に適切なかたちでやり取りを進めやすくなります。
また、面会交流を求める側・拒否したい側のいずれであっても、弁護士が入ることで、根拠ある判断や主張ができるようになります。希望を正しく伝えやすくなるだけでなく、不利益な条件を回避するためのサポートも受けられます。
取り決めた内容は、書面に残しておくことが大切です。公正証書にすれば証拠性が高くなりますし、調停で合意した場合は「調停調書」として強制力を持たせることが可能です。これらの書面作成も、弁護士に任せることができます。
面会交流について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
養育費争い
相手と養育費について争う場合も、弁護士に対応を依頼するとよいでしょう。子どもの利益を確保できるほか、養育者の負担を軽減できるためです。
養育費とは、子どもの監護や教育に必要な費用です。一般的には子どもが経済的・社会的に自立するまで必要な費用で、衣食住に必要な経費や教育費、医療費などが該当します。
離婚後も、子どもを扶養する義務は両親にあるため、親権を持たない側も、原則として養育費を支払う義務があります。資力が極端に乏しい場合を除き、支払い義務が免除されることはほとんどありません。
養育費争いへの対応を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりです。
- 相手方と直接交渉する必要がなくなる
- 適正な養育費の金額が算定できる
- 調停や訴訟になっても対応しやすくなる
- 未払いへの対策を講じられる
養育費は、家庭裁判所が公表している養育費算定表を目安にできます。
算定表は、両親の収入や子どもの人数・年齢に基づいて、おおよその金額を算出します。ただし、子どもに特別な医療費や学費がかかる場合などは、事情を考慮した金額設定も可能です。
弁護士に対応を依頼することで、子どもや養育者の事情を考慮して適正な養育費の金額を算定できるほか、有利に交渉を進めてもらえます。
また、交渉も弁護士が代理してくれるため、相手と直接やり取りする必要がなくなり、精神的な負担を大きく減らすことができます。仮に調停や訴訟へと発展しても、冷静に対応しやすくなるでしょう。
さらに、養育費の取り決め内容を「強制執行認諾文言付き」の公正証書にしておけば、相手が支払いを怠った場合でも、裁判を経ずに財産差押えが可能です。支払いの確実性を高めるためにも、公正証書化しておくことをおすすめします。
養育費の算出方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
慰謝料争い
離婚に際して慰謝料が発生する場合も、弁護士に対応を依頼したほうがよいでしょう。適切な金額の算定や証拠整理、交渉対応などを通じて、有利に進められる可能性が高まります。
慰謝料(離婚慰謝料)とは、離婚の原因をつくった配偶者に対して、民法709条に基づき、精神的苦痛に対する損害賠償として請求する金銭です。
たとえば、不貞行為やDV、モラハラ(モラルハラスメント)などの不法行為が原因で離婚に至った場合、相手に慰謝料を請求できる可能性があります。
以下のようなケースでは、慰謝料請求が認められる場合があります。
- 不貞行為(不倫・浮気)
- 暴力(身体的DVや精神的DVなど)
- 悪意の遺棄(例:生活費を渡さない、無断で別居を続ける)※民法770条1項2号
- 性交渉の拒否(ただし、継続的かつ一方的な拒否である必要あり)
- 婚姻生活への非協力(家事・育児放棄などが該当する場合もあり)
※ただし、個別の事情によっては慰謝料請求が認められない場合もあります。
妥当な慰謝料の金額は状況に応じて異なります。しかし、感情的な対立により冷静な交渉が難しくなることも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、過去の判例や状況をもとに適正な慰謝料額を見積もり、証拠に基づいた主張で交渉を有利に進めることが可能です。
一般的な相場は50万~300万円程度ですが、婚姻期間や被害内容によっては500万円を超える場合もあります。
また、慰謝料を請求される側も弁護士に対応を依頼するのがおすすめです。請求された金額が高すぎると感じる場合や、事実関係に争いがある場合は、減額や請求自体の否認も検討できます。
減額や分割払いを主張する正当な理由や資料があれば、弁護士が代理人として相手方と交渉し、柔軟な解決を目指すことができます。
ただし、感情的に反論するだけでは不利になる可能性があるため、証拠や事情を整理したうえで対応するとよいでしょう。
婚姻費用争い
婚姻費用について争う場合は、弁護士への依頼を検討するとよいでしょう。支払いを確実に受けられる可能性が高まるためです。
婚姻費用とは、家族(夫婦と未成熟の子ども)が収入や財産、社会的な地位に応じて通常の生活を維持するために必要な生活費です。居住費や食費、医療費、教育費などが婚姻費用に該当します。
法律において、婚姻費用に関しては夫婦が負担できる能力に応じて分担する義務を負います。たとえ別居状態でも義務がなくなることはありません(民法760条)。
収入が多い側の配偶者は、収入が低い配偶者に対して婚姻費用を支払う必要があります。支払い義務は、原則として離婚が成立するまで継続するため、別居が長期化する場合は早めに取り決めておくことが大切です。
婚姻費用は、まず夫婦で話し合って決めるのが一般的ですが、金額や支払い方法をめぐって合意できないケースも少なくありません。婚姻費用算定表を参考にすることで、両親の収入や子どもの人数・年齢に応じた妥当な金額の目安を確認できます。
弁護士に対応を依頼することで、適切な金額の算出だけでなく、支払時期や方法などについても交渉してもらえます。結果として、スムーズに請求・受領できる可能性が高まるでしょう。
また、不払いへの対策や未払い分の請求・交渉代行を任せられる点も大きなメリットです。
婚姻費用については、以下の記事も参考にしてください。
年金分割争い
年金分割について争う場合は、弁護士への依頼を検討しましょう。交渉や申請手続きを任せられるほか、分割後の年金額や将来の生活設計についても相談できます。
年金分割とは、離婚した夫婦が婚姻期間中に納めた年金保険料を分割し、公平に年金額を算出する制度です。保険料の納付記録を分ける仕組みで、将来の受給額に反映されます。
分割により、年金が少ない側も一定の受給額を確保できる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、相手と顔を合わせることなく交渉を進められるほか、申請書類の準備や提出も代行してもらうことが可能です。
年金分割の制度は複雑で、種類(合意分割・3号分割)や相手の年金加入状況によっては、分割できないケースもあります。対象となる条件や注意点については、以下の記事をご確認ください。
離婚問題を弁護士に依頼しない場合に知っておきたいこと
離婚の手続きは、弁護士を依頼せずに進めることも可能です。夫婦の話し合いによる「協議離婚」はもちろん、家庭裁判所で行う「調停離婚」さらには「離婚裁判」であっても、弁護士をつけずに対応することは可能です。
ただし、離婚を有利な条件で進めたい場合や、養育費・財産分与・親権などで意見が対立している場合には、法的知識がないまま手続きを進めるのはリスクが伴います。
正式に依頼せずとも、事前に弁護士へ相談しておくことで、トラブルを防ぎやすくなります。
弁護士への相談だけでも利用する
裁判官に離婚を認めてもらう離婚裁判と異なり、協議離婚や離婚調停は夫婦の合意による離婚を目指す場です。そのため、弁護士を依頼せずに離婚を成立させることも可能です。
しかし、次のような場合には、事前に弁護士へ相談することをおすすめします。
- 相手が離婚に応じない
- 慰謝料や財産分与の金額で揉めている
- 親権や養育費を巡って意見が対立している
相談だけであれば、1時間あたり5,000円〜1万円程度で済むケースも多く、必要な法的アドバイスだけを受けることができます。
「離婚できる条件に該当するか」「慰謝料や養育費の相場はいくらか」「離婚協議書に何を記載すべきか」など、弁護士に相談しておくことで、後から不利な状況に陥るリスクを軽減できるでしょう。
離婚調停の流れを知っておく
弁護士に依頼せず、家庭裁判所で離婚調停を進める場合は、調停の基本的な流れや進め方をあらかじめ理解しておくことが大切です。
離婚調停は、当事者同士の話し合いが難航している場合に、裁判所の調停委員を間に入れて話し合いを行う手続きです。法的な知識がなくても申し立ては可能ですが、主張の整理や書類準備などを自分で行う必要があります。
調停の大まかな流れは次のとおりです。
| ステップ |
内容 |
| 1. 申立て |
家庭裁判所に「夫婦関係調整調停申立書」などの必要書類を提出します。 |
| 2. 期日の通知 |
裁判所から調停の日時や場所の通知が届きます。 |
| 3. 調停の実施 |
調停委員を交えて個別に意見を聴取され、複数回の期日を重ねながら合意を目指します。 |
| 4. 合意・成立 |
夫婦双方が合意すれば、調停調書が作成され、法的に効力のある離婚が成立します。 |
| 5. 不成立の場合 |
合意に至らなければ「調停不成立」となり、離婚裁判に進むことになります。 |
弁護士をつけずに調停を進める場合、以下のような点に注意しておくとよいでしょう。
- 申立書に何を書くか(主張の軸)
- 証拠資料の準備方法
- 調停委員とのやり取りでどこまで主張を通すか
これらを自分で対応する場合、事前の知識があるかないかで調停の進行に大きな差が出るケースもあります。とくに争点が多い場合や感情的な対立が強い場合は、途中から弁護士を依頼する選択肢も視野にいれておきましょう。
また、法テラスの代理援助を利用する予定がある場合は、調停前に申請を済ませておく必要があるため、スケジュール管理にも注意が必要です。
離婚裁判の場合は弁護士がいないと不利になる
離婚裁判に弁護士をつける義務はありませんが、裁判では法律に基づいた主張や証拠の提出が必要です。弁護士のいない状況では自分の主張がうまく伝わらず、不利な判決が下されるおそれがあります。
とくに相手が弁護士を依頼している場合は、法的な知識や交渉力の差が結果に影響する可能性が高くなります。また、裁判は平日の日中に行われ、複数回の出廷が必要となるため、仕事や家庭との両立も負担になるでしょう。
離婚裁判は1~2年にわたる長期戦になることも珍しくないため、裁判に発展する可能性があるなら、早めに弁護士への依頼を検討するのが賢明です。
まとめ
離婚問題に関して弁護士費用の支払いが難しい場合でも、法テラスの代理援助を利用すれば、弁護士に依頼することが可能です。
また、着手金の分割や後払いに対応してもらったり、日弁連の法律援助を利用したりすれば、法テラスの代理援助を利用できない場合でも、離婚問題を弁護士に相談や依頼ができます。
弁護士費用は、弁護士事務所や対応内容によって異なります。複数の弁護士事務所で無料相談を受け、費用や弁護士との相性を確認するとよいでしょう。
離婚に関する問題では、当事者だけでの解決が難しいケースも少なくありません。とくに離婚裁判に進んだ場合や、相手が弁護士をつけている場合は、自分の不利益を防ぐためにも、早めに弁護士への相談を検討しましょう。
不安を抱えたまま手続きを進めるのではなく、信頼できる専門家のサポートを受けながら、納得のいく解決を目指してください。
離婚問題の弁護士費用に関するFAQ
どうしても弁護士費用が払えないときは、どうすればいいですか?
法テラスの代理援助が使えず、費用を分割でも支払えない場合であっても、無料相談を利用して弁護士にアドバイスを求めることは可能です。
費用の支払いが難しい状況でも、離婚問題を整理し、解決の方向性を見出すヒントが得られる場合があります。正式な依頼を前提としなくても、まずは相談してみるのがおすすめです。
協議離婚、離婚調停、離婚裁判の弁護士費用はどのくらいかかりますか?
目安としては以下のとおりです。
- 協議離婚:20万円~60万円
- 離婚調停:50万円~100万円
- 離婚裁判:60万円~110万円
離婚の方法や争点の内容によって費用は異なります。詳細については、以下の記事も参考にしてください。