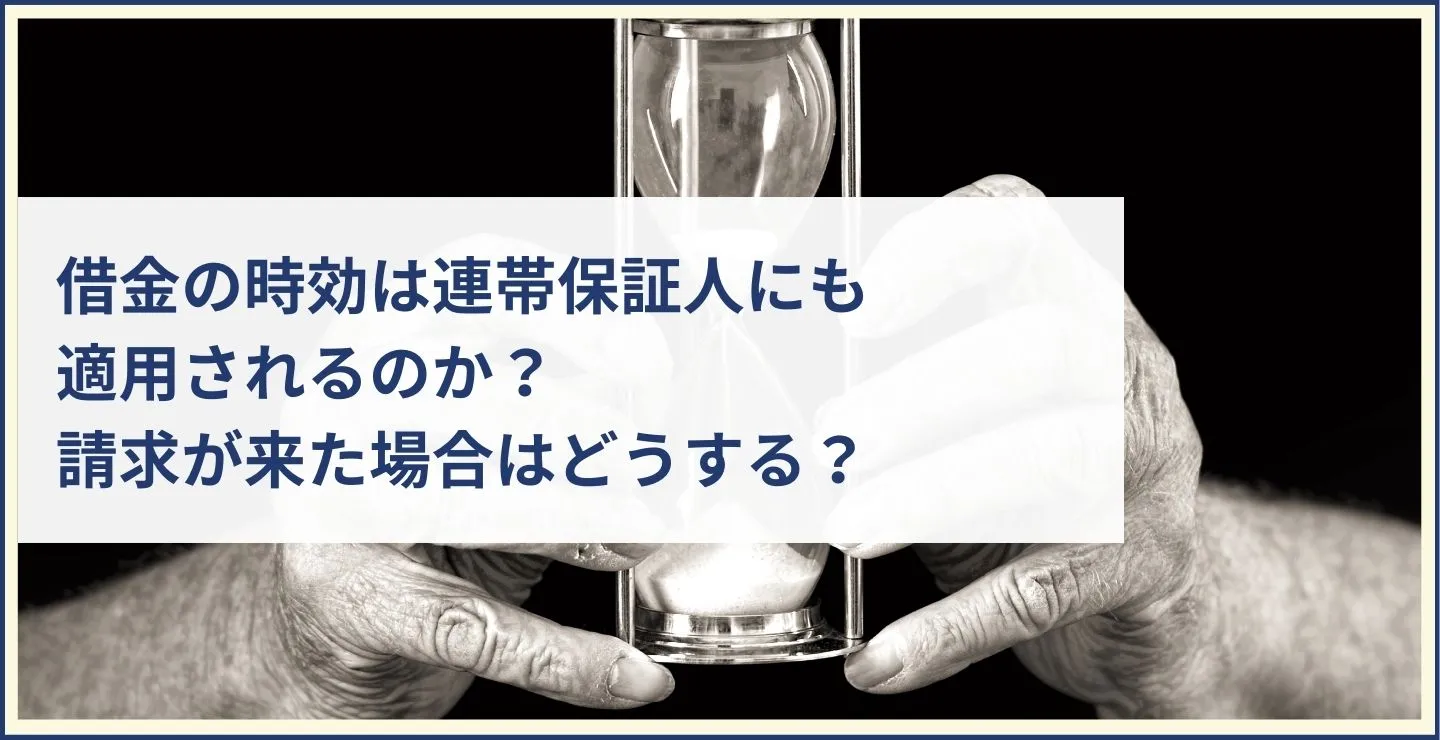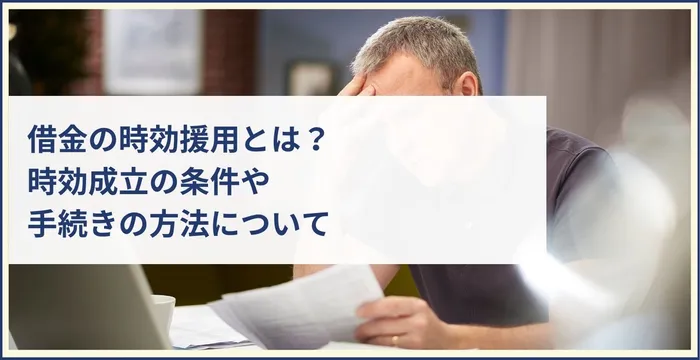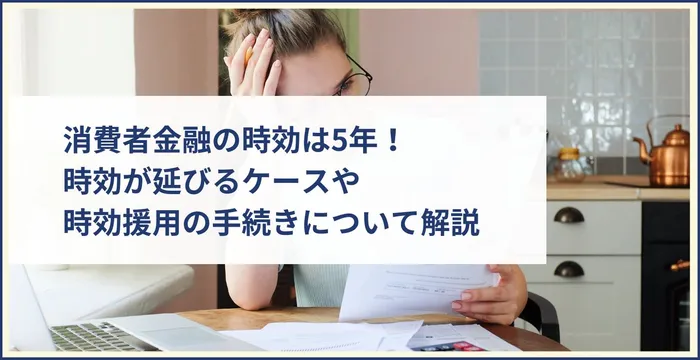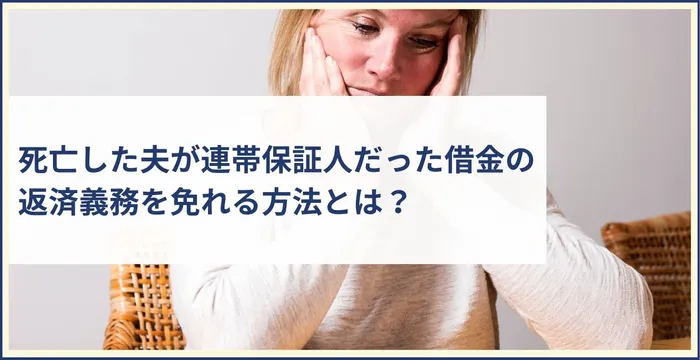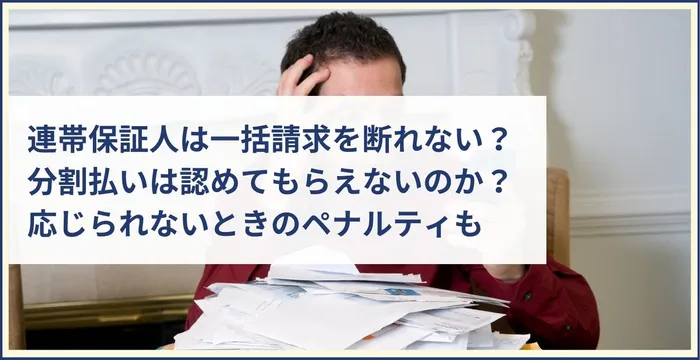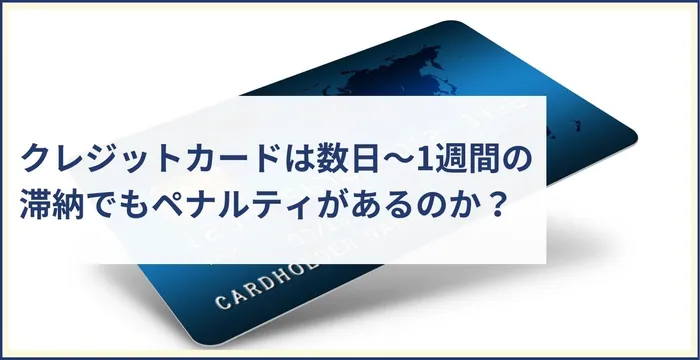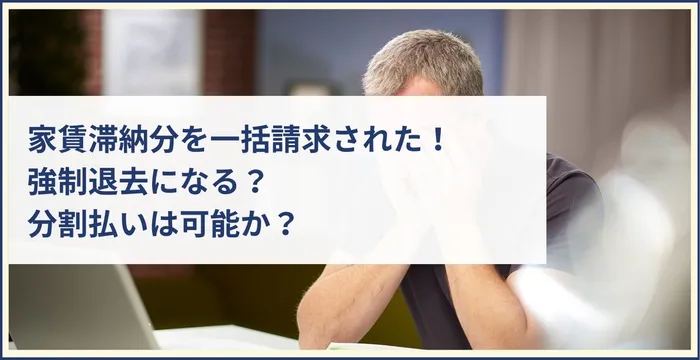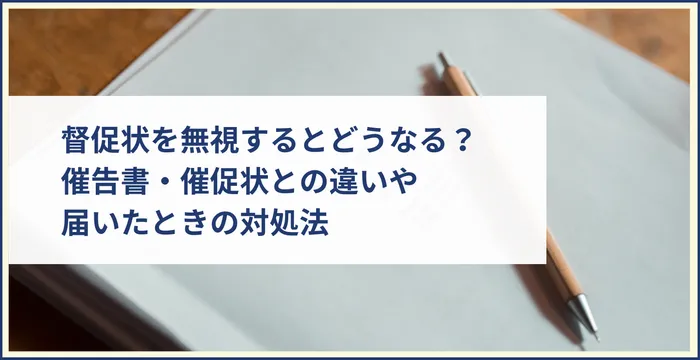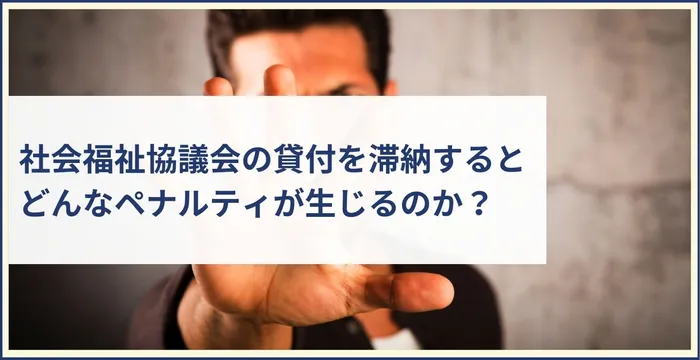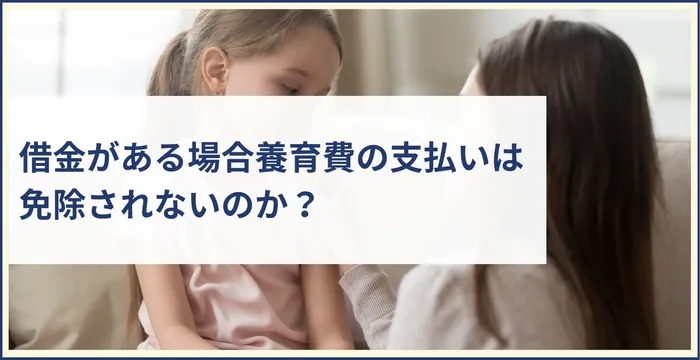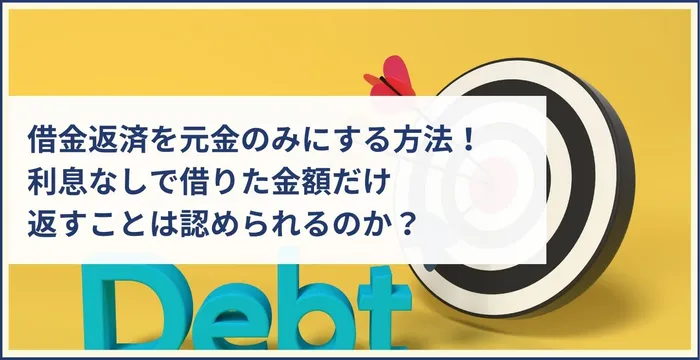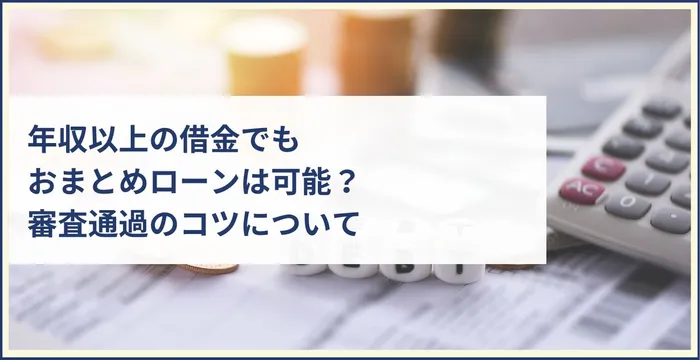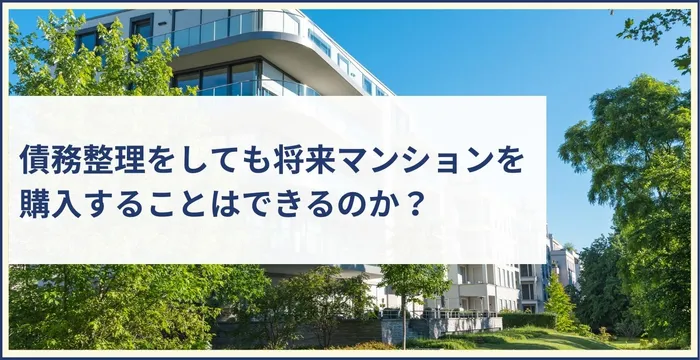連帯保証人も時効の援用手続きは行える
連帯保証人も、主債務者と同様に時効期間が経過すれば時効の援用手続きが行えます。
時効の援用とは、時効の成立によって利益を受ける者(債務者)が、権利を失う者(債権者)に対して時効の成立を主張することです。
時効の援用手続きによって時効が成立すれば、連帯保証人の返済義務は消滅します。
連帯保証人と主債務者の債務は時効が別のカウントで進行する
連帯保証人は、主債務者と連帯して債務を負担する「連帯保証債務」を負います。
これは、実際に債権者からお金を借りた主債務者が負う「主債務」とは別個の債務として扱われるのが一般的です。
つまり、主債務の時効が経過していなくても、保証債務の時効が経過していれば、時効の援用手続きは行えます。
連帯保証人の時効が成立する条件
連帯保証人が時効を成立させるには、以下の3つの条件を満たす必要があります。
- 時効の更新や中断の事由がない
- 最終返済日から原則5年以上経過している
- 時効の援用手続きをしている
ここからは、それぞれの条件に付いて1つずつ詳しく解説していきます。
時効の更新や中断の事由がない
時効を成立させるには、時効の更新(中断)の事由が生じていないことが条件になります。
時効の更新(中断)とは、一定の事由があった場合にこれまでカウントしていた時効期間をリセットし、ゼロからカウントし直すことです。
民法で規定されている時効の更新(中断)事由は、大きく分けて以下の3つあります。
| 時効の更新(中断)事由 |
時効期間がリセットされるタイミング |
| 債務の承認 |
債務の存在を認めた時点 |
裁判上の請求
(支払督促、訴訟、和解、調停、破産手続参加など) |
確定判決や判決と同一の効力を有する権利が確定した時点 |
| 強制執行 |
強制執行が終了した時点
(強制執行後も債務が残っている場合) |
時効が成立する前に時効の更新(中断)事由が生じると、時効期間のカウントが振り出しに戻ってしまうため、本来の時効期間を迎えても時効が成立しません。
最終返済日から原則5年以上経過している
借金の主債務と保証債務の時効は、どちらも最終返済日から原則として5年です。
借金を返済しなくなってから5年以上経過していれば、連帯保証人の返済義務が消滅する可能性があります。
ただし、時効期間の進行中に主債務者が時効の更新(中断)事由に該当する行為をしてしまうと、主債務者だけでなく連帯保証人の時効期間もリセットされてしまうため、最終返済日から5年経過していても時効が成立しないケースもあります。
2020年3月以前の借金は借入先によって時効が10年になる
2020年3月31日以前の借金は、借入先によっては時効が10年になる場合もあります。
理由として、2020年4月1日に借金の時効に関する民法が改正されたことがあげられます。
改正前の民法では、借入先が消費者金融や銀行などの営利目的の商人であれば時効は5年、借入先が個人であれば時効は10年となっていました。
しかし、2020年4月1日の民法改正により、借金の時効は借入先にかかわらず一律5年に変更されました。
現在は改正後の民法が適用されますが、2020年3月31日以前の借金は改正前の民法が適用されます。個人から借金したのが2020年3月31日以前であれば、時効期間は5年ではなく10年となります。
主債務の時効が10年であれば、連帯保証債務の時効も10年になるので注意しましょう。
主債務者の最終返済日を確認する際は債務の承認をしないよう注意
連帯保証人が時効を援用するには、主債務者の最終返済日を把握しておく必要があります。主債務者も連帯保証人も最終返済日が分からなければ、債権者に直接確認しなければなりません。
その際に、債務の承認とみなされるような言動をとらないように注意しましょう。債務の承認とは、債務者が債務の存在や返済義務があるのを認めることで、具体的には以下のような言動を指します。
- 元本や利息の一部を支払う
- 借金の返済を約束する
- 返済期限の延長を申し出る
- 債務の存在を認める書面にサインをする
債務の承認は時効の更新(中断)事由に該当するため、連帯保証人が債務の承認とみなされる言動をすると、保証債務の時効期間がリセットされてしまいます。
そのため、最終返済日を確認する際は、債務の存在を認めずに債権者から最終返済日を上手く聞き出す必要があります。
時効の援用手続きをしている
借金の時効は、最終返済日から原則として5年(場合によっては10年)ですが、単に5年経過しただけで直ちに時効が成立するわけではありません。
連帯保証人の時効を成立させるためには、主債務者または連帯保証人が、時効期間の満了後に時効の援用手続き(債務者が債権者に時効の成立を主張すること)を行う必要があります。
時効の援用手続きに成功すれば、連帯保証人の返済義務が消滅します。
時効の援用手続きの方法には法的に決まったルールはありませんが、口頭では「言った」「言わない」の水掛け論に発展するリスクが高いです。
そのため、日付や内容の証拠を残すために時効援用書を内容証明郵便で送付するのが一般的です。
連帯保証人には主債務者に対して「付従性」を持つ
連帯保証人は、主債務者に対する「付従性(ふじゅうせい)」を持ちます。付従性とは、保証債務や担保物権などの担保義務が、主債務の事情に影響される関係であることをいいます。
この付従性により、主債務で生じた事由は、原則として保証債務にも効力が及びます。たとえば、主債務の時効が更新されれば保証債務の時効も自動的に更新され、主債務の時効が成立すれば保証債務の時効も自動的に成立します。
なお、この付従性は連帯保証人が主債務者に対して持つ性質であるため、逆に主債務者は連帯保証人に対する付従性を持ちません。
保証債務で生じた事由は主債務に効力が及ばないため、保証債務の時効が更新・成立しても、主債務の時効は更新・成立しません。
|
主債務への影響 |
保証債務への影響 |
| 債権者が主債務者に裁判を起こした |
時効が更新される |
時効が更新される |
| 主債務者が債務を承認した |
時効が更新される |
時効が更新される |
| 連帯保証人が債務を承認した |
時効は更新されない |
時効が更新される |
| 主債務者が主債務の時効を援用した |
時効が成立する |
時効が成立する |
| 連帯保証人が保証債務の時効を援用した |
時効は成立しない |
時効が成立する |
このように主債務で生じた事由によって保証債務の時効期間にも影響を及ぼすため、連帯保証人が時効を援用する際は基本的に主債務の時効期間を軸に考える必要があります。
債権者が主債務者に裁判を起こすと連帯保証人の時効も10年間延びる
債権者が主債務者に裁判を起こして判決が確定すると、時効期間が5年の債務も判決確定日から10年に延長されます。
また、裁判は時効の更新(中断)事由に該当するため、判決が確定した時点でこれまでカウントしていた時効期間もリセットされるのが一般的です。
この主債務で生じた時効の延長や更新は、前述した付従性によって連帯保証債務にも影響を及ぼします。
そのため、債権者が主債務者に対して起こした裁判で判決が確定すると、主債務者だけでなく連帯保証人の時効も判決確定日から10年に延長されます。
主債務者が債務承認をすると連帯保証人の時効も更新される
債務の承認は時効の更新(中断)事由に該当するため、債務の承認とみなされる言動をすると、その時点でこれまでの時効期間がリセットされます。
債務の承認によって主債務の時効が更新されると、前述した付従性によって連帯保証人が負う保証債務にも効力が及びます。
そのため、連帯保証人は債務の承認とみなされる言動をしていなくても、主債務者が債務の承認をしてしまうと、連帯保証人の時効期間もリセットされてしまいます。
主債務者が時効成立すれば連帯保証人も時効成立を主張できる
主債務に対する付従性を持つ連帯保証債務は、そもそも主債務が存在しなければ成り立ちません。
主債務者が時効の援用手続きを行って主債務の時効が成立すれば、前述した付従性によって連帯保証債務も消滅するため、連帯保証人の時効も自動的に成立します。
連帯保証人の時効が中断しても時効の成立を主張できる
実は連帯保証人は、連帯保証債務だけでなく主債務の時効援用手続きも行えます。そのため、連帯保証債務の時効が経過していなくても、主債務の時効が経過していれば時効の成立を主張できます。
なお、連帯保証人は主債務者に対する付従性を持ちますが、逆に主債務者は連帯保証人に対する付従性を持っていないため、主債務は連帯保証債務で生じた事由による影響を受けません。
時効期間の進行中に連帯保証人が借金の一部を支払い、連帯保証債務の時効が中断したとしても、主債務の時効は中断されずに進行し続けます。
主債務者が支払いをせずにそのまま5年経過すれば、そこで連帯保証人は主債務の時効援用手続きが行えるため、主債務の消滅によって連帯保証人としての返済義務も消滅します。
連帯保証人は単独での時効援用手続きが可能
連帯保証人は、主債務者が時効の援用手続きを行ってくれなくても、単独で時効援用手続きが可能です。なお、連帯保証人は自己の連帯保証債務だけでなく、主債務の時効援用手続きも単独で行えます。
連帯保証債務と主債務のどちらかの時効援用手続きが成功すれば、連帯保証人としての返済義務は消滅します。
連帯保証債務の時効援用
連帯保証債務については、主債務者が最後に返済してから5年(場合によっては10年)経過した場合に時効の援用手続きが行えます。
しかし、時効期間が経過する前に主債務者が債務を承認したり、債権者に裁判を起こされたりして時効が更新された場合は、連帯保証債務の時効も更新されるため、そこから5年(場合によっては10年)経過しないと時効の援用手続きが行えません。
ただし、主債務者に時効の更新事由が生じたタイミングが時効期間の経過後である場合、時効更新の効力は連帯保証債務に及びません。
連帯保証人に時効の更新(中断)事由が生じていなければ、連帯保証人は単独で連帯保証債務の時効成立を主張でき、借金の返済義務から免れられます。
主債務の時効援用
主債務についても、連帯保証人は時効期間が経過している場合に時効の援用手続きが行えます。主債務は連帯保証債務に対する付従性を持たないため、連帯保証人が債務を承認するなどして連帯保証債務の時効が更新されたとしても、主債務の時効は更新されません。
そのまま主債務の時効期間が経過すれば、連帯保証人は主債務の時効成立を単独で主張できます。
主債務の時効が成立すれば、連帯保証債務の時効も自動的に成立するため、連帯保証人としての返済義務は消滅します。
ちなみに連帯保証人が主債務の時効を援用しても、主債務者の返済義務は消滅しないため、主債務者は自分で時効の援用を行う必要があります。
特殊なケースでの時効援用
連帯保証人が時効援用手続きを行う際、以下のような特殊なケースに該当する場合は特に注意が必要です。
- 主債務者が死亡している場合
- 連帯保証人が複数いる場合
ここからは、それぞれのケースについて1つずつ詳しく解説していきます。
主債務者が死亡している場合は主債務者の相続人の行動が重要
主債務者が死亡した場合、主債務者の地位は原則として法定相続人にそのまま引き継がれます。そのため、連帯保証人は新たに主債務者となった法定相続人と連帯して借金を返済する義務を負うことになります。
法定相続人が主債務者の地位を相続した場合は、これまで通り主債務者が返済できない状況に陥らない限り、連帯保証人に請求が行くことは基本的にありません。しかし、法定相続人全員が相続放棄をした場合は注意が必要です。
法定相続人全員が相続放棄すると、法定相続人は主債務者の地位を放棄できますが、借金そのものが帳消しになるわけではないため、連帯保証人の地位は放棄できません。
いずれの場合でも連帯保証人としての返済義務は残りますが、法定相続人全員が相続放棄した場合は連帯保証人が主債務者の代わりに残債を一括で支払うことが確定します。
つまり、連帯保証人としての立場は相続人が主債務者の地位を引き継ぐかどうかで大きく左右されることになります。
連帯保証人が複数いる場合は時効が個別に進行する
連帯保証人が複数いる場合、各連帯保証人の連帯保証債務はそれぞれ別個で扱われるため、時効も個別に進行します。
たとえば、連帯保証人がA・B・Cの3人いる場合、Aが債務の承認をして時効がリセットされても、B・Cの時効はリセットされません。Bが時効の援用を行って時効が成立しても、A・Cの時効が自動的に成立することもありません。
連帯保証人としての返済義務を放棄するためには、他に連帯保証人がいるかどうかに関係なく、時効期間が経過したら必ず自分で時効援用手続きをしなければならないので、連帯保証人が複数人いる場合は注意が必要です。
連帯保証人の時効援用に失敗した場合の対処法
連帯保証人の時効援用に失敗した場合の対処法としては、以下の4つが挙げられます。
- 時効にこだわるなら次の時効まで待つ
- 債権者に分割してもらえないか交渉する
- 裁判を起こされているなら和解する
- 債務整理で借金の負担を減らす
ここからは、それぞれの対処法について1つずつ詳しく解説していきます。
時効にこだわるなら次の時効まで待つ
時効の成立にこだわるのであれば、時効期間が経過するまで待つしかありません。時効援用に失敗した後は債権者から支払い請求を受けることになりますが、債務を承認すると時効が更新されてしまうため、支払いに一切応じずに時効の成立を待つことになります。
ただし、債務者が支払いに一切応じない場合、債権者は時効を阻止するために裁判を起こしてくるケースが多いです。裁判で下された判決で権利が確定すると、これまでの時効期間はリセットされ、時効期間は判決確定日から10年に延長されてしまいます。
判決確定後も支払いをせずに時効の成立を目指そうと思っても、強制執行によって給与や債務者名義の財産を差し押さえられてしまう可能性が高いです。
財産の差し押さえを受けなかったとしても、時効の更新には回数の上限はありません。そのため、時効が成立する前に債権者から再び裁判を起こされると、さらに時効期間が10年延長されてしまいます。
時効の成立前に裁判を繰り返し起こせば、債権者は半永久的に時効期間を延長できてしまうため、時効の成立を目指すのは極めて困難であるということは理解しておきましょう。
債権者に分割してもらえないか交渉する
請求金額を一括で支払うのが難しければ、分割払いにしてもらえないか債権者と直接交渉してみましょう。主債務者が自己破産した場合や、主債務者の法定相続人全員が相続放棄を選択した場合、債権者は連帯保証人に対して一括で支払うように請求してきます。
しかし、債務の金額が大きすぎて一括での支払いが難しいケースも多いです。その場合は、債権者に相談することで分割払いに対応してもらえる可能性があります。
債権者も連帯保証人に自己破産されて債権を回収ができなくなるよりかは、分割払いに対応して債権を少しでも多く回収したいと考えるのが通常なので、支払いをする意思を見せれば柔軟に対応してもらえるかもしれません。
ただし、債権者によっては分割払いを一切認めてくれなかったり、1年以内の短期間の分割しか応じてくれなかったりするケースもあります。自力で債権者と交渉するのが難しければ、弁護士への相談も検討してみましょう。
裁判を起こされているなら和解する
債権者から裁判を起こされているなら、裁判に出席して債権者と和解する方法もあります。裁判所を交えて債権者と話し合い、双方が合意すれば和解成立となり、裁判が終了します。
ただし、裁判上で和解する場合、将来の利息のカットは認められる可能性はありますが、和解までの未払い分の利息や遅延損害金のカットは基本的に認められません。
和解成立後は元本と未払い分と利息、遅延損害金を全額支払っていくことになります。和解で取り決めた約束を破った場合は、強制執行による財産の差し押さえを受ける可能性があるため、その点も考慮して和解するか慎重に判断しましょう。
債務整理で借金の負担を減らす
借金を返済するのが困難な状況であれば、債務整理の利用を検討してみましょう。債務整理とは、合法的に借金を減額・免除できる借金救済制度です。債務整理には、以下の3通りの方法があります。
| 債務整理の種類 |
特徴 |
| 任意整理 |
裁判所を介さずに債権者と直接交渉を行って将来利息や遅延損害金をカットしてもらい、元本を3~5年かけて分割で返済する |
| 個人再生 |
裁判所に返済が困難であることを認めてもらい、5分の1~10分の1程度に減額した借金を3~5年かけて分割で返済する |
| 自己破産 |
裁判所に返済不能であることを認めてもらい、財産の大半を手放す代わりに借金の全額を免除してもらう |
ただし、債務整理には以下のようなデメリットもあります。
- 信用情報機関の信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録される
- 他の連帯保証人に返済義務を押し付けてしまう(個人再生・自己破産)
- 官報に氏名と住所が掲載される(個人再生・自己破産)
- 手続き中は一部の職業・資格が制限される(自己破産)
- 手続き中は引っ越しや旅行の際に裁判所の許可が必要(自己破産)
- 手続き中は郵便物を破産管財人に管理される(自己破産)
借金の減額幅が大きい方法ほどデメリットとなる部分も大きいため、借金額や年収、生活スタイルなどに適した方法を選ぶことが大切です。
また、債務整理には法律の専門的な知識やノウハウが必要になるため、債務整理を利用する際は借金問題に強い弁護士に相談しましょう。
まとめ
連帯保証人は、主債務または連帯保証債務の時効期間が経過すれば単独で時効の援用が行えます。
ただ、連帯保証人と時効の関係は非常に複雑なため、個人では時効援用できるか判断が難しいケースが多いです。
時効の援用ができるか分からない場合や、時効の援用に失敗して借金の返済が困難な場合は一人で悩まず早めに弁護士に相談しましょう。
連帯保証人になっている借金のよくある質問
連帯保証人の地位を相続した場合の時効は?
相続によって連帯保証人の地位を引き継いだ場合の時効は、連帯保証契約が成立した時期によって異なります。
| 連帯保証契約の成立時期 |
時効期間 |
| 2020年4月1日以降 |
債権者が権利を行使できるのを知った時から5年、または権利を行使することができる時から10年のいずれか早い方 |
| 2020年3月31日以前 |
貸金業者からの借金は5年
個人からの借金は10年 |
相続した連帯保証債務の時効期間のカウントは、そのまま相続人に引き継がれます。たとえば、相続が発生した時点で貸金業者からの借金の時効期間が3年経過していれば、あと2年で時効の援用手続きが行えます。
連帯保証人は支払いを拒否できますか?
連帯保証人は債権者から支払いを求められた場合、支払いの拒否はできません。連帯保証人は主債務者と同等の責任を負っているため、債権者に借金の全額を返済する義務があります。
主債務者が支払えなければ、連帯保証人が代わりに支払わなければなりません。支払いに応じなかった場合は債権者から裁判を起こされ、強制執行による財産の差し押さえを受ける可能性があります。
連帯保証人の地位は相続放棄できますか?
連帯保証人の地位を相続放棄できるかどうかは、被相続人が誰かの連帯保証人であるか、それとも相続人が被相続人の連帯保証人であるかどうかで異なります。
被相続人が誰かの連帯保証人である場合なら、相続人は相続放棄をすることで連帯保証人の地位を放棄できます。
ただし、相続放棄をすると預貯金や株式、不動産などのプラスの財産も一切相続できなくなるため、遺産の中に高額な預貯金や不動産が含まれている場合は慎重に判断しなければなりません。
一方、被相続人が主債務者で相続人が連帯保証人である場合は、相続によって連帯保証債務を引き継ぐわけではないため、相続放棄をしても連帯保証人の地位は放棄できません。