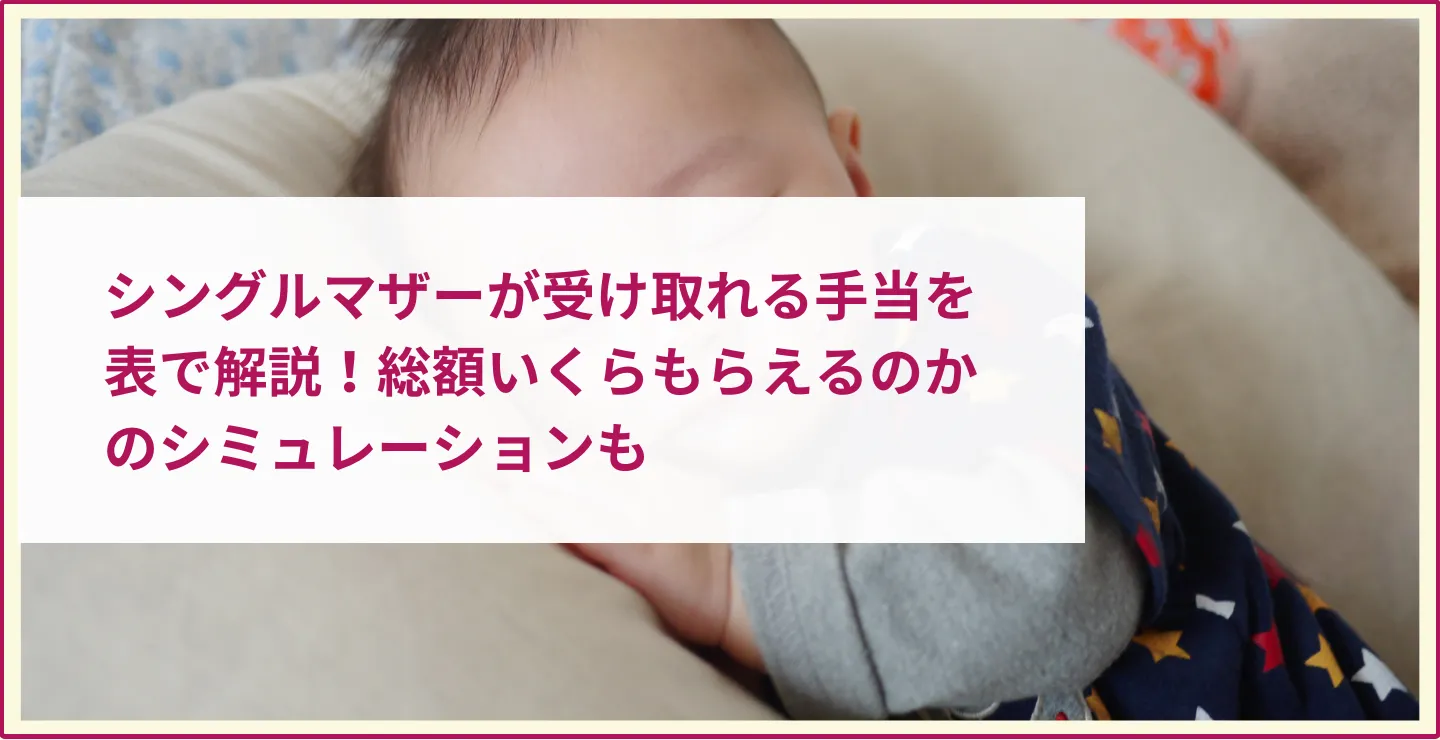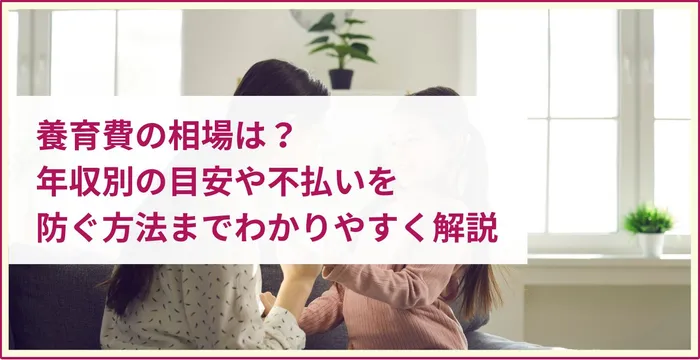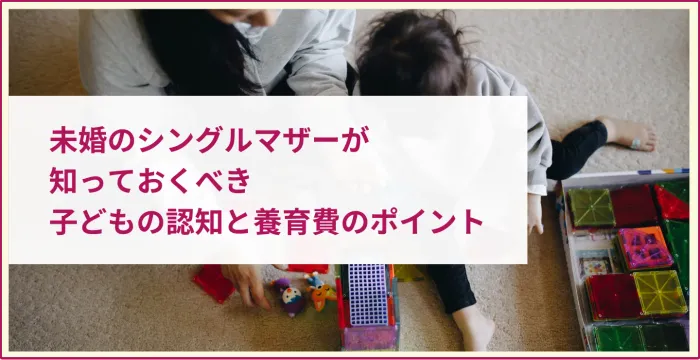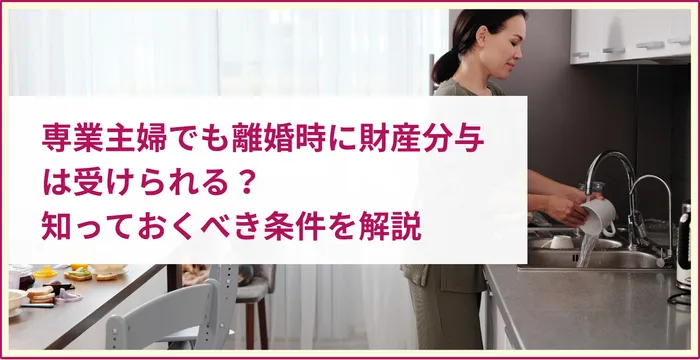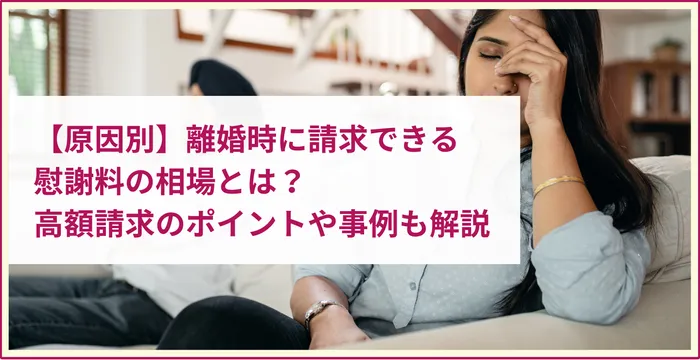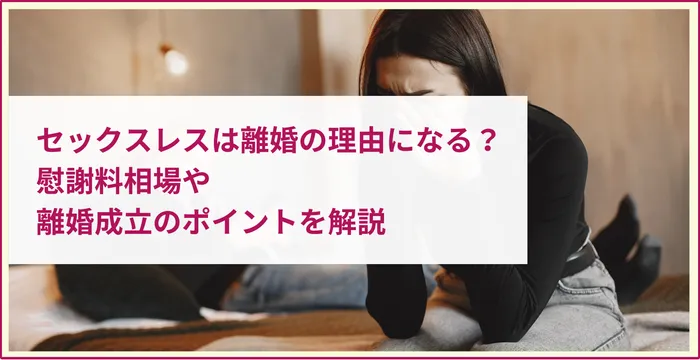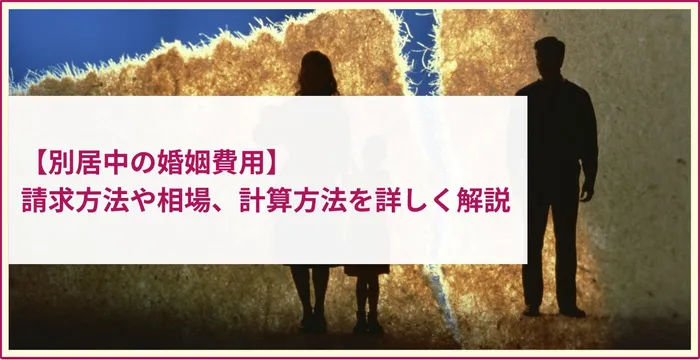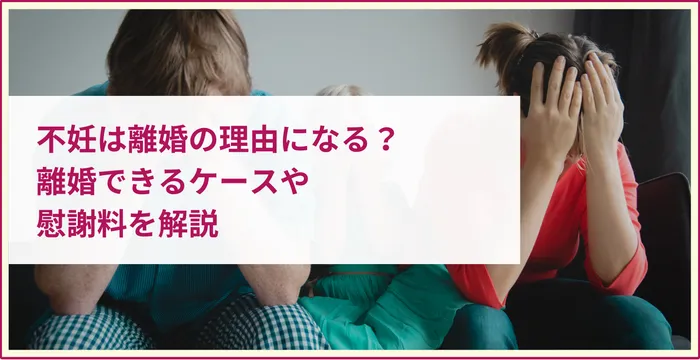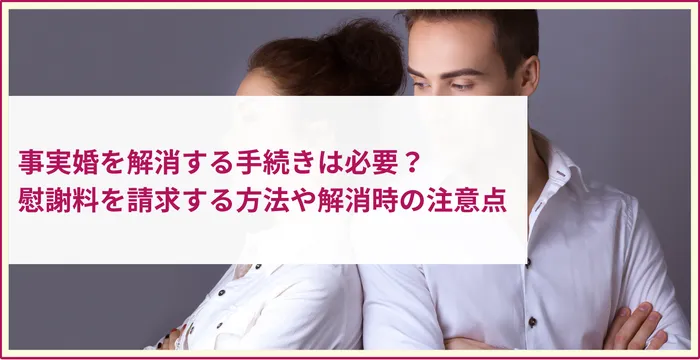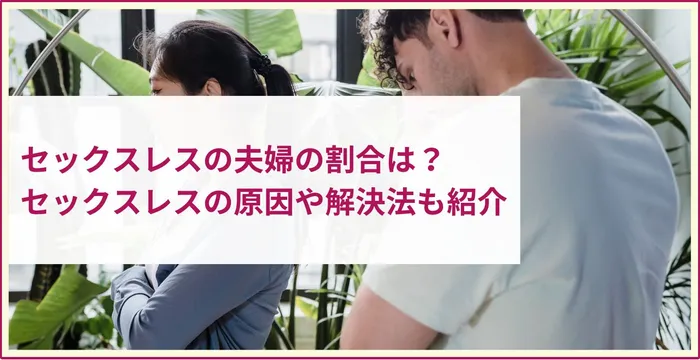シングルマザーがもらえる9種類の手当とシミュレーション
それでは早速、シングルマザーが受けられる手当や利用できる制度について紹介します。状況によって利用できる手当や制度が異なるため、対象になるかをよく確認しましょう。
|
手当・制度
|
支援額
|
期間
|
|
児童手当
|
最大30,000円/人
|
高校卒業まで
|
|
児童扶養手当
|
最大46,690円/人
|
原則高校卒業まで
|
児童育成手当
(東京都民のみ対象)
|
最大15,500円/人
|
原則高校卒業まで
|
|
特別児童扶養手当
|
最大55,350円/人
|
満19歳まで
|
|
障害児福祉手当
|
15,690円/人
|
満19歳まで
|
|
ひとり親家庭等医療費助成制度
|
保険診療の自己負担額
|
原則高校卒業まで
|
|
ひとり親家庭住宅手当
|
自治体による
|
満19歳まで(自治体による)
|
|
遺族年金
|
年間816,000円+子の加算額
|
5年または終身
|
|
生活保護
|
世帯構成・地域によって大きく異なる
|
不要になるまで
|
なお、制度によっては、「扶養する親族の数が0人」であっても、手当の支給対象に含まれるケースがあります。これは、ひとり親家庭において、扶養者と実際に一緒に生活している親が異なる場合が該当します。例えば、離婚後に子どもは父親の扶養となっているものの、生活は母親としている場合。扶養者は父親なので、母親の扶養児童は0人とカウントされます。
それでは、各手当・制度について、概要や対象者、支援額、支給されるケースの例を詳しく見ていきましょう。
1.児童手当|最大30,000円/人|高校卒業まで
児童手当とは、児童がいる世帯の生活の安定や、次代の社会を担う子どもたちの健やかな成長のための制度です。児童を養育している全ての世帯を対象に、児童1人ずつ、年齢に応じた金額が支給されます。
|
支給対象者
|
0歳から18歳になる年度の3月31日まで
|
|
支給時期
|
2月・4月・6月・8月・10月・12月
(偶数月に、まとめて2ヶ月分を支給)
|
支給額
(1人あたり月額)
|
3歳未満:1万5,000円(第3子以降:3万円)
3歳以上:1万円(第3子以降:3万円)
|
|
申請場所
|
住所地の市区町村の窓口
※公務員の場合は、勤務先で申請
|
例えば、5歳と8歳の2人の子どもがいる家庭では、月額2万円が支給されることになります。
児童手当制度は、2024年7月から制度改正により、所得制限の撤廃や支給対象年齢の拡大、第三子以降の手当額の増額が行われました。支給回数も年3回4ヶ月分ずつ支給から、年6回2ヶ月分ずつ支給に変更され、月々の生活費の補填がしやすく、急な出費にも対応しやすくなりました。
参考:こども家庭庁「児童手当制度のご案内」
2.児童扶養手当|最大46,690円/人|原則高校卒業まで
児童育成手当とは、ひとり親家庭の生活の安定や自立を促すための制度です。離婚や死別などによってひとり親状態になっている世帯に対し、児童1人ずつ、年齢に応じた金額が支給されます。
|
支給対象者
|
0歳から18歳になる年度の3月31日までの間にある児童を監護する者
|
|
支給時期
|
1月・3月・5月・7月・9月・11月
(奇数月に、まとめて2ヶ月分を支給)
|
支給額
(1人あたり月額)
|
1人目(全部支給):4万6,690円
1人目(一部支給):4万5,490~1万740円
2人目以降(全部支給):1万750円
2人目以降(一部支給):1万740~5,380円
|
|
申請場所
|
住所地の市区町村の窓口
|
支給金額は、前年の所得に応じて所得制限が設定されており、支給対象でも手当の全額を支給する「全部支給」と、手当の一部のみを支給する「一部支給」の2パターンがあります。支給を受けられるか、全部支給・一部支給いずれに該当するかは、以下の表に沿って判断されます。
|
扶養する親族の数
|
全部支給となる所得制限
|
一部支給となる所得限度額
|
|
収入ベース
|
所得ベース
|
収入ベース
|
所得ベース
|
|
0人
|
142万円
|
69万円
|
334万3,000円
|
208万円
|
|
1人
|
190万円
|
107万円
|
385万円
|
246万円
|
|
2人
|
244万3,000円
|
145万円
|
432万5,000円
|
284万円
|
|
3人
|
298万6,000円
|
183万円
|
480万円
|
322万円
|
|
4人
|
352万9,000円
|
221万円
|
527万5,000円
|
360万円
|
|
5人
|
401万3,000円
|
259万円
|
575万円
|
398万円
|
例えば、世帯年収が240万円で、5歳と8歳の2人の子どもがいるひとり親家庭の場合、全部支給の対象です。そのため、1人目の4万6,690円+2人目の1万750円で、月額5万7,440円が支給されます。
参考:こども家庭庁「児童扶養手当について」
3.児童育成手当(東京都)|最大15,500円/人|原則高校卒業まで
児童育成手当とは、児童の心身の健やかな成長を支援する東京都の制度です。国の制度ではないため東京都民が対象で、都内の各区市町村が条例によって実施しています。
育成手当は、父母の離婚や死亡などによってひとり親となった家庭に対して支給され、障害手当は、心身に障害のある児童を養育している家庭に対して支給されます。
|
支給対象者
|
受給資格のある、0歳から18歳になる年度の3月31日までの間にある児童を扶養する者
|
|
支給時期
|
2月・6月・10月
(年に3回、まとめて4ヶ月分を支給)
|
支給額
(1人あたり月額)
|
育成手当:1万3,500円
障害手当:1万5,500円
|
|
申請場所
|
市区町村の児童育成担当課(名称は自治体により異なる)の窓口
|
育成手当・障害手当には、共通で所得制限が設定されています。支給を受けられるかは、以下の表に沿って判断されます。
|
扶養する親族の数
|
所得制限
|
|
0人
|
360万4,000円
|
|
1人
|
398万4,000円
|
|
2人
|
436万4,000円
|
|
3人
|
474万4,000円
|
|
4人
|
512万4,000円
|
|
5人以上
|
1人につき38万円加算
|
例えば、世帯年収が240万円で、5歳と8歳の2人の子どもがいるひとり親家庭が東京都内に住んでいた場合、1万3,500円の2人分で、月額2万7,000円が支給されます。
なお、ひとり親家庭や障害児を扶養する家庭であっても、児童が福祉施設に入所していたり、父または母の再婚相手に養育されていたりすれば支給対象外になるケースもあります。
参考:東京都福祉局「児童手当 児童育成手当 児童扶養手当」
4.特別児童扶養手当|最大55,350円/人|満19歳まで
特別児童扶養手当とは、障害を持つ児童の福祉増進を目的とした制度です。精神または身体に障害のある20歳未満の子どもを家庭で監護・養育している保護者に対し、所得に応じて支給されます。
|
支給対象者
|
20歳未満(満19歳)で、精神または身体に障害を持つ児童を家庭で監護・養育している者
|
|
支給時期
|
4月・8月・12月
(年に3回、まとめて4ヶ月分を支給)
|
支給額
(1人あたり月額)
|
障害等級1級:5万5,350円
障害等級2級:3万6,860円
|
|
申請場所
|
住所地の市区町村の窓口
|
特別児童扶養手当には、所得制限が設定されているため、受給資格者(障害児の父母など)または、受給資格者の配偶者・生計を同じくする扶養義務者の前年の所得によっては手当が支給されません。支給を受けられるかは、以下の表に沿って判断されます。
|
扶養する親族の数
|
受給資格者の所得制限
|
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得制限
|
|
0人
|
459万6,000円
|
628万7,000円
|
|
1人
|
497万6,000円
|
653万6,000円
|
|
2人
|
525万6,000円
|
674万9,000円
|
|
3人
|
573万6,000円
|
696万2,000円
|
|
4人
|
611万6,000円
|
717万5,000円
|
|
5人
|
649万6,000円
|
738万8,000円
|
例えば、世帯年収が240万円、障害等級2級の5歳と、同じく障害等級2級の8歳の子どもがいる家庭の場合、3万6,860円の2人分で、月額7万3,720円が支給されます。
参考:厚生労働省「特別児童扶養手当について」
5.障害児福祉手当|15,690円/人|満19歳まで
障害児福祉手当とは、特別障害児の福祉の向上を図るための制度です。重度障害児の精神的・物質的な特別の負担を軽減できるよう、精神または身体に重度の障害を持っている20歳未満の者に支給されます。
重度障害児とは、日常生活において常時介護を必要としている、障害児の中でも特に重度の障害を持つ者を指します。
|
支給対象者
|
20歳未満(満19歳)で、精神または身体に重度の障害を持ち、日常生活に常時介護を必要とする者
|
|
支給時期
|
2月・5月・8月・11月
(年に4回、まとめて3ヶ月分を支給)
|
支給額
(1人あたり月額)
|
1万5,690円
|
|
申請場所
|
市区町村の窓口
|
障害児福祉手当には、所得制限が設定されているため、受給資格者(重度障害児)または、受給資格者の配偶者・生計を同じくする扶養義務者の前年の所得によっては手当が支給されません。支給を受けられるかは、以下の表に沿って判断されます。
|
扶養する親族の数
|
受給資格者の所得制限
|
受給資格者の配偶者・扶養義務者の所得制限
|
|
0人
|
360万4,000円
|
628万7,000円
|
|
1人
|
398万4,000円
|
653万6,000円
|
|
2人
|
436万4,000円
|
674万9,000円
|
|
3人
|
474万4,000円
|
696万2,000円
|
|
4人
|
512万4,000円
|
717万5,000円
|
|
5人
|
550万4,000円
|
738万8,000円
|
例えば、世帯年収が240万円で、5歳と8歳の子どもがいずれも重度障害を持っている家庭の場合、1万5,690円の2人分で、月額3万1,380円が支給されます。なお、障害児福祉手当は、特別児童扶養手当と併給が可能です。
参考:厚生労働省「障害児福祉手当について」
参考:e-GOV法令検索「特別児童扶養手当等の支給に関する法律(用語の定義)」
6.ひとり親家庭等医療費助成制度|保険診療の自己負担額|原則高校卒業まで
ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭の医療費の自己負担分について、一部を自治体が助成する制度です。ひとり親家庭の子どもだけでなく、ひとり親や両親がいない児童を養育している人が病院で診断を受けた際にも助成を受けられます。
助成範囲には、医療保険の対象となる医療費と薬剤費が含まれます。ただし、医療保険の対象外となる健康診断・予防接種・差額ベッド代や、他の公費医療で助成される医療費などは、助成の範囲に含まれません。また、生活保護を受けていたり、児童が児童福祉施設に入所していたりすれば制度の対象外となるケースもあります。
|
支給対象者
|
・児童を監護しているひとり親
・両親がいない児童を養育する養育者
・ひとり親家庭の子ども、または両親がおらず養育者に養育されている0歳から18歳に達した後の最初の3月31日までの間にある児童(障害がある場合は20歳未満)
|
|
支給時期
|
各自治体によって異なる
|
支給額
(1人あたり月額)
|
各自治体によって異なる
|
|
申請場所
|
住所地の市区町村の窓口
|
自治体が実施している制度なので、対象者の範囲や支給額、所得制限などについては、各自治体によって異なります。自己負担分の全額が負担されることもあれば、一部のみ負担してもらえることもあります。そのため、制度を利用したい場合は、居住地の自治体の役場に詳細を確認・相談ください。
例えば、東京都豊島区在住で、ひとり親家庭の子どもが骨折をして入院や通院が必要になった場合、入院の自己負担額上限は5万7,600円/月、外来の自己負担額上限は1万8,000円/月なので、自己負担額は最大でも7万5,600円/月となります。
なお、助成を受けるためには、自治体の役場で「ひとり親家庭等医療費受給者証(マル親医療証)の交付」を受けなければなりません。申請時の持ち物は自治体によって異なりますが、健康保険証の写しや戸籍謄本、所得証明書、マイナンバーカードなどが必要です。
参考:東京都福祉局「ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)」
7.ひとり親家庭住宅手当|自治体による|〜満19歳まで(自治体による)
ひとり親家庭住宅手当とは、ひとり親世帯に対する家賃を補助する制度です。ひとり親家庭の生活の安定と自立を促し、福祉の増進を図ることを目的としています。
各自治体が実施しており、助成の範囲や内容、金額はそれぞれ異なります。名称も「ひとり親家庭等家賃補助」「母子家庭等家賃助成」「ひとり親家庭等家賃助成」などさまざまです。
例えば、東京都千代田区の支給対象・支給額・支給時期などは以下の通りです。
|
制度の名称
|
居住安定支援家賃助成
|
|
支給対象者
|
・18歳以下の子と同居し扶養しているひとり親世帯
・DV(家庭内暴力)被害者世帯 など
|
|
支給条件
|
・千代田区内に引き続き2年以上居住し、住民登録している
・住民税を滞納していない
・生活保護を受給していない
・所得が規定以下である
|
支給要件
(いずれかに該当する必要がある)
|
・現在の住宅から1年以内に退去を求められている
・安全上・衛生上劣悪な状態の住居に居住している
・やむを得ない理由により世帯所得が著しく減少した
|
|
助成内容
|
・家賃補助:最大5万円/月(最長5年)
・転居一時金:礼金・仲介手数料の合算額(上限あり)
・契約更新助成:賃貸借契約の更新のために支出した更新料の額(上限あり)
・火災保険料助成:最大7,500円
|
|
申請場所
|
区役所の窓口
|
支給要件・条件を満たす世帯であれば、家賃の一部を助成してもらえます。月に3万円支援があれば、年に36万円の経済的余裕が生まれます。
参考:東京都千代田区「居住安定支援家賃助成」
8.遺族年金|年間816,000円+子の加算額|5年または終身
遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者が亡くなった際に、遺族が受け取ることができる公的年金制度です。生計を支えていた家族が突然亡くなっても、遺族が生活できるよう一定の所得を保障しており、亡くなった人の配偶者や子どもなどに対して支給されます。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類があります。遺族基礎年金は、自営業者やフリーランス、専業主婦など国民年金の加入者が亡くなった場合に、遺族に対して支給される年金です。遺族厚生年金は、会社員や公務員など厚生年金加入者が亡くなった場合に支給されます。
なお、亡くなった人(被保険者)の職業や加入していた年金や加入状況、家族構成、配偶者の年齢など、支給額や支給期間が異なります。生涯に渡って支給されるケースもあれば、亡くなった人の死後数年後には支給が打ち切られるケースもあり、状況によってさまざまです。
|
遺族基礎年金
|
|
支給対象者
|
・子のある配偶者
・子
|
|
受給要件
|
・被保険者が国民年金の加入期間中に死亡した
・老齢基礎年金の受給権者が死亡した
・老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡した など
|
|
支給額
|
年間81万6,000円+子の加算額
|
|
申請場所
|
・住所地の市区町村の窓口
・年金事務所の窓口
・年金相談センターの窓口
|
|
遺族厚生年金
|
|
支給対象者
|
・子のある配偶者
・子のない配偶者
・父母
・孫(未成年または20歳未満で障害者)
・祖父母
|
|
受給要件
|
・被保険者が厚生年金保険の加入期間中に死亡した
・1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている人が死亡した
・老齢厚生年金の受給権者が死亡した
・老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡した など
|
|
支給額
|
加入状況による
|
|
申請場所
|
・年金事務所の窓口
・年金相談センターの窓口
|
受け取れる年金額の算出方法は、日本年金機構「遺族年金ガイド令和7年度版」で確認できますが、考慮すべき要素が多く、自力での計算は簡単ではありません。正確な金額を知りたい場合は、年金事務所や年金相談センターに相談するのが確実でしょう。
参考:日本年金機構「遺族年金」
参考:JA共済「ご存じですか 遺族年金のこと」
9.生活保護|地域・世帯構成によって大きく異なる|不要になるまで
生活保護は、収入が国が定める最低生活費に満たない人や世帯に対する保護制度です。困窮状態にある人や世帯に対して、健康で文化的な最低限度の生活を送るための支援を行い、自立を助長することを目的としています。
|
支給対象者
|
・働くことができない人
・働いても最低生活費が得られない人
・現金化できる資産を持たない人
・年金や手当など他の制度を利用しても最低生活費が得られない人 など
|
|
支給時期
|
自治体によって異なる
(一般的には毎月1~5日のいずれか)
|
|
支給額
|
・国が定める最低生活費と収入の差額の生活費
・その他、家賃・医療費・出産・葬儀・教育・介護などにかかる必要費
|
|
申請場所
|
住所地を管轄する福祉事務所の生活保護担当窓口
|
生活保護の場合、ひとり親家庭であっても、一定以上の収入があれば支援の対象外となります。また、生活保護の支給金額は、地域や家族構成、世帯人員などによって異なります。
生活保護には、支給額がプラスされる「母子加算」があります。母子加算は、「母子」という名称ではありますが、父子家庭も含む、ひとり親世帯に対する支援です。母子加算の金額は、子どもの数と住んでいる地域の等級によって変わります。これは、物価が高騰しやすい都市部と、比較的物価が安い地方部に住む世帯が平等な生活を送るための仕組みです。
|
子どもの人数
|
1級地の加算額
|
2級地の加算額
|
3級地の加算額
|
|
1人
|
2万2,790円
|
2万1,200円
|
1万9,620円
|
|
2人
|
2万4,590円
|
2万2,890円
|
2万1,200円
|
3人以上
(1人につき加算)
|
920円
|
850円
|
780円
|
各地域の級地区分は、厚生労働省「お住まいの地域の級地を確認」で確認できます。
さらに、中学校修了前の子どもを養育する場合は、3歳未満・中学生は15,000円、3歳~小学校終了まで1万円(第3子以降は1万5,000円)の児童養育加算の受け取りも可能です。
例えば、5歳と8歳の子どもが2人いる全く収入がないひとり親世帯の場合、生活を維持するために支給される金額は、東京都在住で約19万1,000円が、地方在住で約17万円が支給されます。そのほか、必要に応じて住宅や医療への支援が支給されます。
参考:厚生労働省「○ 生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法(平成30年4月現在)」
参考:厚生労働省「生活保護制度」に関するQ&A
シングルマザーが利用できる子どもの学費を支援する3つの制度
子どもを育てる上で、学費は避けて通れない大きな出費です。生活が厳しい家庭では、支払いが困難になることもありますが、子どもが教育を受ける機会を失わないよう、下記のような制度が設けられています。
- 高校生等奨学給付金(教育費の支援)
- 高等教育の修学支援新制度(入学金・授業料の減免や生活費の支援)
- 母子父子寡婦福祉資金貸付金制度(就学・修業に必要な資金の貸付)
こちらも1つずつ概要や受けられる支援内容をみていきましょう。
1.高校生等奨学給付金
高校生等奨学給付金とは、高校に通う意思のある子どもが教育を受けられるよう、授業料以外(教材費・学用品費・生徒会費など)の教育費を支援する制度です。高校生等奨学給付金では、高校生がいる低所得世帯に対し、返還不要の給付金が支給されます。
|
給付対象者
|
・生活保護受給世帯
・非課税世帯
・家計が急変し、非課税相当になった世帯
|
|
給付対象
|
授業料以外の教育費
(教材費・学用品費・通学用品費・生徒会費・PTA会費・入学学用品費・修学旅行費・通信費など)
|
給付額
(2025年度)
|
■生活保護受給世帯
・国立・公立高等学校に在学:年額3万2,300円
私立高等学校に在学:年額5万2,600円
|
■非課税世帯(全日制)
国立・公立高等学校に在学:年額14万3,700円
私立高等学校に在学:年額15万2,000円
|
■非課税世帯(通信制)
国立・公立高等学校に在学:年額5万500円
私立高等学校に在学:年額5万2,100円
|
|
申請場所
|
・都道府県の担当部署
・進学する学校
高校生等奨学給付金の問合せ先一覧
|
参考:文部科学省「高校生等奨学給付金リーフレット」
2.高等教育の修学支援新制度
高等教育の修学支援新制度とは、大学や専門学校に進学したい子どもが高等教育を受けられるよう金銭的に支援する制度です。高等教育の修学支援新制度には、「授業料・入学金の免除または減免」と「給付型奨学金の支給」という2つの支援が用意されています。
|
支援対象者
|
・世帯収入や資産の要件を満たしている学生
・進学先で学ぶ意欲がある学生
|
|
支援対象
|
・入学金
・授業料
・在学期間中の生活費
|
支援金額
(住民税非課税世帯の場合)
|
■授業料等減免の上限額
・国公立大学(昼間制):入学金約28万円/授業料54万円
・私立大学(昼間制):入学金約26万円/授業料70万円
・国公立専門学校(昼間制):入学金約7万円/授業料17万円
・私立専門学校(昼間制):入学金約16万円/授業料59万円
|
■給付型奨学金の給付額
・国公立大学・専門学校:自宅生2万9,200円/自宅外生6万6,700円
・私立大学・専門学校生:自宅生3万8,300円/自宅外生7万5,800円
|
|
申請場所
|
・入学金・授業料:進学先の学校
・給付型奨学金:日本学生支援機構(JASSO)
|
支援を受けられる金額は、世帯収入や進学先の学校の種類、自宅から通うのか・1人暮らしをするのかなどによって異なります。また、支援が決まっても、単位の取得数や出席率が悪かったり、学修に対する意欲が低いと判断されたりすれば、支援が打ち切られたり、支給された支援の返還が求められたりする可能性があります。
支援の対象になるかは、日本学生支援機構「進学資金シミュレーター」で確認できます。
参考:文部科学省「高等教育の修学支援新制度」
参考:日本学生支援機構「奨学金ホームページ」
3.母子父子寡婦福祉資金貸付金制度
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度とは、ひとり親世帯の経済的な自立を促すための貸付金制度です。20歳未満の児童を扶養している配偶者のないひとり親が対象で、用途によって12種類用意されています。このうち、子どもの教育支援には「修学資金」、就学・修業への支援には「就学支度資金」という貸付金が該当します。
|
|
修学資金
|
就学支度資金
|
|
貸付対象者
|
・母子家庭の母が扶養する児童
・父子家庭の父が扶養する児童
・父母のない児童
・寡婦が扶養する子
|
|
貸付対象
|
高等学校や短大・大学・大学院などに就学させるための授業料・交通費などに必要な資金
|
就学・修業に必要な衣類などの購入資金
|
貸付額
(限度額)
|
・高校:月額5万2,500円
・短期大学:月額13万1,000円
・大学:月額14万6,000円
・大学院(修士):月額13万2,000円
・大学院(博士):月額18万3,000円 など
|
・小学校:6万4,300円
・中学校:8万1,000円
・国公立高校:16万円
・私立高校:42万円 など
|
|
償還期間
|
・20年以内
・専修学校:5年以内
|
・就学:20年以内
・修業:5年以内
|
|
利率
|
無利子
|
|
申請場所
|
住所地の市区町村の福祉担当窓口
|
母子父子寡婦福祉資金貸付金制度は、あくまでも貸付金なので、指定された期間中に返済が必要です。なお、一般的な借入とは違い、利子は付きません。
参考:男女共同参画局「母子父子寡婦福祉資金貸付金制度」
シングルマザーが利用できる6つの無料サービス・減免制度
続いては、シングルマザーが利用できる可能性のある無料のサービスや減免制度についてみていきましょう。
- ひとり親控除(住民税・所得税の税制優遇)
- 寡婦控除(住民税・所得税の税制優遇)
- 国民健康保険の免除
- 国民年金の免除
- 上下水道・バス・電車など公共サービスの割引
- 保育料の減免・免除
1つずつ支援の対象者や内容について詳しく解説します。
1.ひとり親控除
ひとり親控除とは、納税者がひとり親だった場合に適用される所得控除です。一定が所得以下のひとり親の所得税・住民税の計算時に、所得額から一定額が差し引くことで、税金の負担を軽減することができます。
|
対象者
|
・その年の12月31日時点で婚姻をしていない、または配偶者の生死が明らかでない人
・事実上の婚姻関係にあると認められる人もいない人
・生計を一にしている(日常生活の資金が共通している)子どもがいる人
・扶養親族の所得が48万円を超えていない人
・合計所得金額が500万円以下である人
|
|
控除対象
|
所得税・住民税
|
|
控除額
|
所得税35万円・住民税30万円
|
|
申告方法
|
年末調整または確定申告で申告
|
参考:国税庁「No.1171 ひとり親控除」
なお、ひとり親控除は拡充が予定されています。計画通り施行されれば、所得制限が500万円から1,000万円まで引き上げられ、所得税の控除額も35万円から38万円に拡大されることとなります。
2.寡婦控除(住民税・所得税の税制優遇)
寡婦控除とは、納税者自身が寡婦(かふ)である場合に、所得税・住民税の税制優遇を受けられる制度です。寡婦控除を受けるには、原則としてその年の12月31日時点でひとり親に該当せず、以下の表で説明している「対象者」に当てはまっていることが条件となります。
|
対象者
|
・夫と死別した後再婚をしていない女性
・夫と離婚した後に再婚しておらず、扶養親族がいて、合計所得額が500万円以下の女性
・夫の生死が明らかではなく、合計所得額が500万円以下の女性
|
|
控除対象
|
所得税・住民税
|
|
控除額
|
27万円
|
|
申告方法
|
年末調整または確定申告で申告
|
参考:国税庁「No.1170 寡婦控除」
なお、先述したひとり親控除と寡婦控除は併用できず、原則としてどちらか一方の適用となります。
現在はひとり親控除の方が適用範囲が広く、控除額も大きいため、条件に該当すればひとり親控除が優先されます。
3.国民健康保険の免除
国籍や年齢を問わず国民健康保険への加入は義務ですが、所得が一定以下の場合、国民健康保険の免除を受けることができます。シングルマザーなどひとり親家庭だけでなく、所得が低い場合は健康保険料の軽減・減免の対象となります。
保険料や軽減・減免の所得基準、軽減割合は自治体によって異なります。ここでは、東京都中央区の例を見てみましょう。
|
|
7割軽減
|
5割軽減
|
2割軽減
|
|
所得基準
|
世帯総所得が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円以下
|
世帯総所得が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(30.5万円×被保険者数)以下
|
世帯総所得が43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円+(56万円×被保険者数)以下
|
|
基礎分保険料
|
1万4,190円
|
2万3,650円
|
3万7,840円
|
|
後期高齢者支援金分保険料
|
5,040円
|
8,400円
|
1万3,440円
|
|
介護分保険料
|
4,980円
|
8,300円
|
1万3,280円
|
その他、生活が一時的に困難になった時や、産前産後、被災した時などやむを得ない事情がある場合は保険料が減免されることがあります。減免の対象になるかは、自治体の担当部署に問い合わせが必要です。
参考:東京都中央区「国民健康保険料の軽減・減免」
4.国民年金の免除
国民健康保険料の免除と同様に、所得が一定以下の場合は、国民年金の免除や納付猶予を受けることができます。こちらも、ひとり親家庭に限らず、所得が低く、年金保険料の支払いが困難な世帯が対象です。
年金と健康保険は社会保障費としてひとまとめに考えられがちですが、全く別の制度であり、国民健康保険が免除されなかった人でも国民年金は免除してもらえる可能性があります。
|
対象者
|
・世帯総所得が一定以下の人
・失業した人
・経済的に納付が難しい人
・DV被害を受けている人
・産前産後の人
・学生の人
・震災・風水害等で被災した人
・特別障害給付金を受けている人
・厚生労働省令で定める生活保護法による生活扶助以外の扶助やその他の援助を受けている人
|
|
免除区分
|
・保険料の全免(全額免除)
・保険料の4分の3免除
・保険料の半額免除
・保険料の4分の1免除
|
|
所得基準
|
ひとり親の場合、免除の承認基準が変わるため要問合せ
|
|
申請期間
|
納付期限から2年を経過していない期間
|
|
申請場所
|
・住所地の市区町村の国民年金担当窓口
・年金事務所
※郵送可
|
ただし、保険料の納付の免除を受けると納めた保険料が少なくなるため、将来的に受け取れる年金額が少なくなる可能性があります。年金の保険料は、納付期限から10年間さかのぼって納付できるため、経済的な余裕ができたら後から納付することで、将来的な年金受給額を満額に近づけることが可能です。
参考:日本年金機構「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度」
5.上下水道・バス・電車の割引
自治体・公共交通機関によっては、経済的に困窮している世帯に対して、上下水道・バス・電車といった公共サービスの割引制度を用意しているところがあります。
近年は、ひとり親世帯への支援が広がっており、自治体ごとにさまざまな支援が用意されているため、住んでいる地域や企業の支援や取り組みを調べてみるとよいでしょう。
|
割引サービスの例
|
|
東京都交通局
|
児童扶養手当を受けている世帯・生活保護受給者への無料乗車券の配布
|
|
JR各社
|
児童扶養手当を受けている世帯・生活保護受給者の通勤定期乗車券運賃の3割引
|
|
東京都練馬区
|
児童扶養手当・特別児童扶養手当・生活保護の受給世帯の水道料金の減免
|
|
大阪府大阪市
|
18歳になる年度の3月31日までの児童を養育しているひとり親世帯の駐輪場利用料金の割引
|
|
愛知県名古屋市
|
市内に居住するひとり親世帯の名古屋市有施設の入場料無料化
|
参考:東京都交通局「都営交通無料乗車券」
参考:西日本旅客鉄道株式会社「児童扶養手当や生活保護の支給を受けていますが、定期券が割引になりますか。」
参考:東日本旅客鉄道株式会社 特定者用定期乗車券発売規則
参考:練馬区ひとり親家庭支援ナビ「その他の割引や免除」
参考:大阪市「ひとり親家庭等への支援」
参考:名古屋市「ひとり親家庭市有施設優待利用事業」
6.保育料の減免・免除
シングルマザーになってから世帯収入が減った場合、保育料の減免・免除が受けられる可能性があります。
保育園の保育料は子どもの年齢と保護者の前年所得額または住民税金額で決まりますが、住民税が非課税の世帯は認可保育園の保育料は無料です。課税世帯であっても、世帯所得が360万円未満であれば、1人目の保育料は半額、2人目以降の保育料は無料となります。
具体的な保育料については、各自治体によって異なるため、住んでいる市区町村の役場に問い合わせてみましょう。自治体によっては、保育料だけでなく、給食費も無償化されるところもあります。
シングルマザーの就職や自立を助ける6つの支援制度
シングルマザーが長期的に安定した生活と、安心して子どもを養育・教育できる環境を得られるよう、就職支援や技能習得に対する支援も実施されています。
- 高等職業訓練促進給付金/ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
- 母子家庭等就業・自立支援センター事業
- ひとり親家庭の在宅就業推進事業
- 母子・父子自立支援プログラム策定事業
- 高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
- 母子家庭等自立支援給付金事業
ここからは、金銭的な支援ではなく、シングルマザーの就職や自立を助ける制度についてみていきましょう。
1.高等職業訓練促進給付金/ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
高等職業訓練促進給付金とは、ひとり親が就職に必要な資格を取得できるよう、学校などの養成機関に通う期間中に金銭的な支援を受けられる制度です。給付金を受け取るためには、審査を通過する必要があります。
|
支給対象者
|
・児童扶養手当の支給を受けている人
・児童扶養手当の支給対象者と同等の所得水準にある人
・養成機関で半年以上のカリキュラムを受講し、資格の取得が見込まれる人
・仕事や育児と修業の両立が難しい人
|
|
支給対象資格
|
就職で有利になる資格
(看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・調理師・デジタル分野の民間資格など自治体ごとに設定)
|
|
支給額
|
訓練期間中:月額10万円/住民税課税世帯は月額7万500円
訓練修了後:5万円/住民税課税世帯は2万5,000円
|
|
申請場所
|
住所地の都道府県または市区町村窓口
|
参考:こども家庭庁「カテゴリ別支援事業一覧(高等職業訓練促進給付金)」
高等職業訓練促進給付金を受けた人は、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業も利用できます。ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業とは、就職に有利な資格を取得しようとしているひとり親が通う、養成機関の入学金や就職準備金、家賃を貸し付けてくれる制度です。こちらは貸付なので原則返済が必要となりますが、一部自治体が定める条件によっては、返済が不要になるケースもあります。
|
貸付対象者
|
■入学準備金・就職準備金
20歳未満の子供を養育する親で、高等職業訓練促進給付金の支給を受けている人
|
■住宅支援
児童扶養手当受給者(同等の水準にある人を含む)のうち「母子・父子自立支援プログラム」で、自立に向けて意欲的に取り組んでいるひとり親
|
|
貸付対象
|
・入学準備金(入学金・教材費・交通費など)
・就職準備金(転居費用・通勤費など)
・住宅の家賃
|
|
貸付額
|
・入学準備金:50万円以内
・就職準備金:20万円以内
・家賃:入居している住宅の家賃(上限4万円/原則12ヶ月)
|
|
利子
|
■入学準備金・就職準備金
連帯保証人あり:無利子
連帯保証人なし:返済猶予期間の経過後は年1.0%
|
■住宅支援
無利子
|
|
申請場所
|
都道府県や指定都市の担当課窓口
|
参考:こども家庭庁「カテゴリ別支援事業一覧(高等職業訓練促進給付金)」
2.母子家庭等就業・自立支援センター事業
母子家庭等就業・自立支援センター事業では、ひとり親の自立支援と就業支援を効果的に実施するため、包括的な支援を行っています。日常生活における悩みから、就業について、養育費や面会交流に関する法的な内容まで相談が可能です。
|
支援対象者
|
ひとり親
|
|
支援内容
|
・生活相談
・就業相談
・就業支援講習会の実施
・就業情報の提供
・養育費の取り決めなど法律相談
・養育費・面会交流に関する相談
・在宅就業のためのPCの貸与や訓練環境の整備
|
|
相談方法
|
・面接
・電話
(自治体によってはオンライン相談も対応可)
|
|
実施場所
|
・母子家庭等就業・自立支援センター
・男女共同参画センター
・福祉事務所 など
|
実施場所は、各都道府県ごとに異なるため、母子家庭等就業・自立支援センター事業実施先一覧から最寄りの実施先を確認してください。
参考:こども家庭庁「母子家庭等就業・自立支援センター事業について」
3.ひとり親家庭の在宅就業推進事業
ひとり親家庭の在宅就業推進事業では、在宅就業やテレワークを希望するひとり親を支援しています。
ひとり親が外に働きに出ると、子どもの世話ができる保護者がいなくなったり、遅刻・早退などで職場に迷惑をかけたりと、親も子どもも精神的に安定して生活できない状況になりがちです。在宅での就業を目指すことで、時間的にも精神的にも余裕をもった生活が期待できます。
|
支援対象者
|
・在宅での就業を目指すひとり親とその子ども
・離婚前から支援が必要な家庭
|
|
支援内容
|
・在宅就業コーディネーターによるアドバイス
・発注者との契約に関するアドバイス
・業務スケジュール管理など業務に関するノウハウの提供
・必要な知識・技能習得のための情報提供
・情報共有のためのサロンの開催
・スキルアップのためのセミナー開催
|
|
申請場所
|
住民票のある都道府県や市区町村の担当課
|
※自治体によって異なります。
参考:こども家庭庁「カテゴリ別支援事業一覧(母子家庭等就業・ 自立支援事業(在宅就業推進事業))」
4.母子・父子自立支援プログラム策定事業
母子・父子自立支援プログラム策定事業とは、母子・父子自立支援プログラム策定員のもと自分の状況に応じた支援プログラムを作る取り組みを指します。画一的な支援ではなく、個々の生活の状況や就業への意欲、取得したい資格、抱えている悩みに応じた支援やフォローを行ってもらえます。
|
支援対象者
|
・児童扶養手当受給者(同等の水準にある人も含む)
・離婚前から支援が必要な家庭
|
|
支援内容
|
・面談による生活・子育て・健康・収入・就業など現状の把握
・自立や就業ができない原因と課題整理
・問題を解決するための支援策の提案
・自立目標の設定
・支援の経過と支援内容の評価記録
|
|
申請場所
|
住民票のある都道府県や市区町村の福祉事務所
|
参考:こども家庭庁「カテゴリ別支援事業一覧(母子・父子自立支援プログラム策定事業)」
5.ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業とは、高等学校を卒業していないひとり親が、高卒認定試験合格を目指すための支援です。高卒認定に合格すれば、高校を卒業した者と同等の学力があることが認定され、より良い条件での就職・転職が期待できます。
|
支援対象者
|
・児童扶養手当受給者(同等の水準にある人も含む)
・高等学校卒業程度認定試験に合格することが適職に就くために必要と判断される人
|
|
支援額
|
■通信制の場合
・受講開始時給付金:受講費用の最大4割(上限10万円)
・受講修了時給付金:受講費用の最大1割(受講開始時給付金と合わせて上限12万5,000円)
・合格時給付金:受講費用の1割(上記2つの給付金と合わせて上限15万円)
|
■通学または通学・通信制併用の場合
・受講開始時給付金:受講費用の最大4割(上限20万円)
・受講修了時給付金:受講費用の最大1割(受講開始時給付金と合わせて上限25万円)
・合格時給付金:受講費用の1割(上記2つの給付金と合わせて上限30万円)
|
|
申請場所
|
住民票のある都道府県や市区町村
|
参考:こども家庭庁「カテゴリ別支援事業一覧(ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業)」
6.自立支援教育訓練給付金
母子家庭等自立支援給付金事業とは、自主的に能力開発に取り組むひとり親を支援する制度です。対象となる教育訓練を受講・修了した場合に、受講料に対する金銭的な支援を受けられます。新たに知識や技術を学ぶことで、より良い条件での就職・転職に繋がることが見込まれます。
なお、給付金を受けるためには、審査を通過する必要があります。
|
給付対象者
|
・20歳に満たないこどもを扶養しているひとり親
・児童扶養手当受給者(同等の水準にある人も含む)
・指定の教育訓練を修了することが適職に就くために必要と判断される人
|
|
給付対象
|
・雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座
・都道府県が対象とする講座
|
|
給付額
|
・対象となる教育訓練を受講・修了した場合:経費の60%(下限は1万2,001円)
・雇用保険の一般教育訓練給付・特定一般教育訓練給付の対象講座を受講した場合:最大20万円
・雇用保険の専門実践教育訓練給付の対象講座を受講した場合:修学年数×40万円(最大160万円) など
|
|
申請場所
|
住民票のある都道府県や市区町村
|
参考:こども家庭庁「カテゴリ別支援事業一覧(自立支援教育訓練給付金)」
離婚時には養育費や慰謝料も請求しておきましょう
シングルマザーは、働き方や時間の制約があるため、経済的に困窮しがちです。離婚時には、相手方に金銭の給付を請求しましょう。
離婚時に請求できる離婚給付は、下記の3つです。
- 養育費(子どもの監護や教育に必要な費用)
- 財産分与(婚姻中に築いた財産)
- 慰謝料(相手の不法行為により受けた精神的苦痛に対する損害賠償)
離婚時にしっかりと金銭の請求をしておくことで、離婚後の経済的な負担が大きく変わってきます。なお、いずれのお金も、弁護士を入れて交渉することで、受け取れる金額が大幅に上がる可能性があります。確実に、適正な金額を受け取るためには、弁護士に相談しつつ離婚を進めるのがおすすめです。
養育費|子どもの監護や教育に必要な費用
養育費とは、子どもが経済的・社会的に自立するまでの間、監護・教育するために必要なお金です。
【養育費に含まれるもの】
- 住居費
- 食費
- 水道光熱費
- 教育費
- 医療費
- 交通費
- 娯楽費
- 子どもへのお小遣い など
養育費の相場は2~5万円程度ですが、子どもの人数や、両親の年収、職業などによって金額は大きく変わります。一般的に、出産や育児でキャリアがストップしにくい父親のほうが、母親より収入が多いため、父親が支払う金額が高くなる傾向があります。
日本では母子家庭が約119.5万世帯、父子家庭が約14.9万世帯と、ひとり親世帯の約89%は母子世帯です。しかし、母子家庭のうち約72%は父親から養育費を受け取れていません。シングルマザーが養育費をきちんと受け取るためには、離婚時に公正証書を作成し、相手が支払わなかった場合に財産や給料を差し押さえられる「強制執行認諾条項」を盛り込んでおくのが効果的です。
参考:厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査の概要」
財産分与|婚姻中に築いた財産
財産分与とは、夫婦が婚姻中の共同生活において協力して形成した財産の公平な分配や、離婚後の生活の保障のため、相手方に財産の分与を請求できる制度です。夫婦が協力して形成した財産は、名義を問わず、財産分与の対象となります。
【財産分与の対象となるもの】
- 不動産
- 現金
- 預貯金
- 経済的価値のあるもの
- 保険
- 退職金
- 年金 など
原則として財産分与の割合は2分の1です。夫が外で働き、妻が専業主婦であった場合でも、妻が家事・育児をすることによって財産の形成ができたといえるため、2分の1で分けられるのが一般的。ただし、財産分与の割合は、財産の形成における貢献度で判断するため、夫婦の片方の特別な努力や特殊な能力によって大きな資産が形成された場合は、分与の割合が変わることがあります。
また、婚姻前から所有していた財産や、夫婦で協力して築いたいえない財産、自分のために借り入れた借金については、財産分与の対象外です。例えば、婚姻前に溜めていた預貯金や、自分の親族から相続した遺産については、基本的に財産分与の対象とはなりません。
なお、婚姻中であっても、相続や贈与によって取得した財産など「特有財産」に該当するものは、財産分与の対象とはなりません。
慰謝料|相手の不法行為により受けた精神的苦痛に対する損害賠償
慰謝料とは、離婚に際して相手から受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。離婚をすれば必ずしも請求できるお金ではありませんが、相手に不法行為やハラスメント行為があった場合には請求できる可能性が高いといえます。
【慰謝料が請求できるケース】
- 肉体関係のある浮気・不倫行為(不貞行為)
- DV・各種ハラスメント
- 浪費癖やギャンブルによる借金
- 正当な理由のないセックスレス
- 悪意の遺棄(悪意を持って配偶者を見捨てる行為) など
慰謝料が請求できるかは、状況によって異なります。例えば、単に借金があるというだけでは、慰謝料の請求が認められない可能性が高いですが、ギャンブルにハマって生活費を浪費していた場合は慰謝料が認められる可能性があります。
慰謝料の金額は、離婚原因や相手に受けた苦痛の期間・程度などによってケースバイケースです。例えば、不貞行為で慰謝料が認められる場合、相場は100万~300万円程度ですが、不貞の期間や精神的苦痛の大きさ、婚姻期間などといった具体的な事情によって増減します。
まとめ
今回は、シングルマザーが受け取れる金銭的な支援や利用できる制度について、詳しく解説しました。
ひとり親世帯、特に母子家庭では経済的に困窮しやすく、手厚いセーフティーネットが用意されています。しかし、どれも母親自らが申請しなければ、活用することはできません。今は支援を受けられなくても、どのような支援・制度があるのかを知っておけば、条件を満たした時点で申請することができます。
シングルマザーで経済的に困窮している人や就業できずに困っている人は、まずは住んでいる自治体に相談してみましょう。
また、離婚時には、相手方としっかり協議し、子育てに必要な養育費の支払いや、夫婦で築いた財産の正当な分与を求めることも重要です。シングルマザーの場合、養育費や慰謝料についての悩みやトラブルは、無料で法律相談や弁護士の紹介を行ってくれる「法律扶助」を受けられる可能性もあります。活用できないか、一度確認してみるのもよいでしょう。