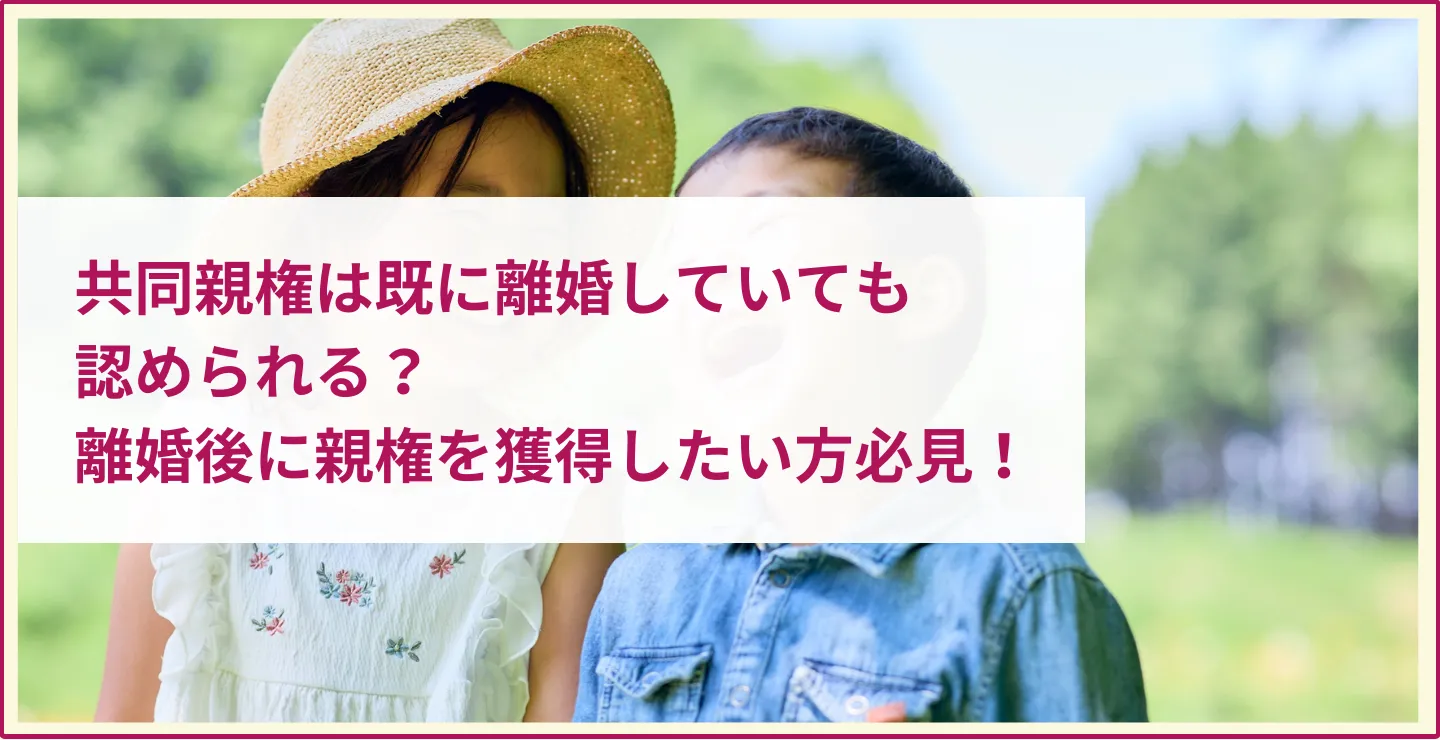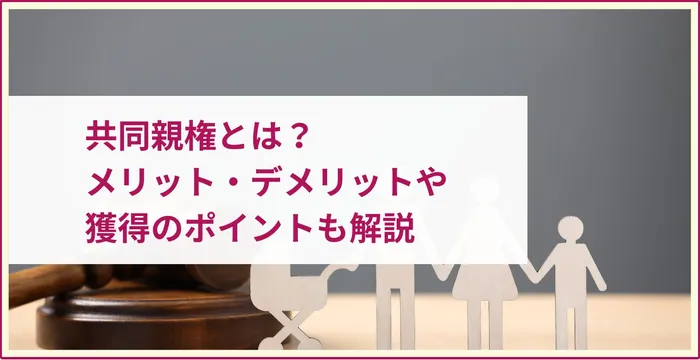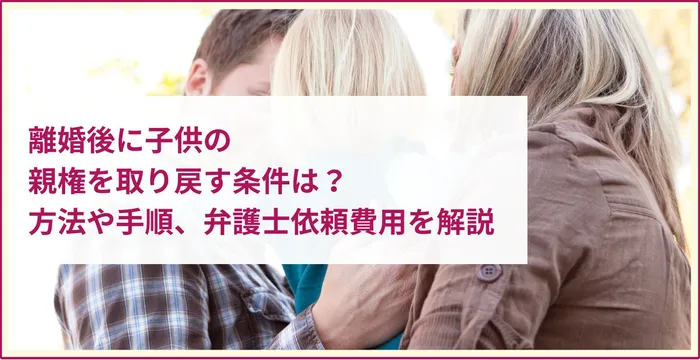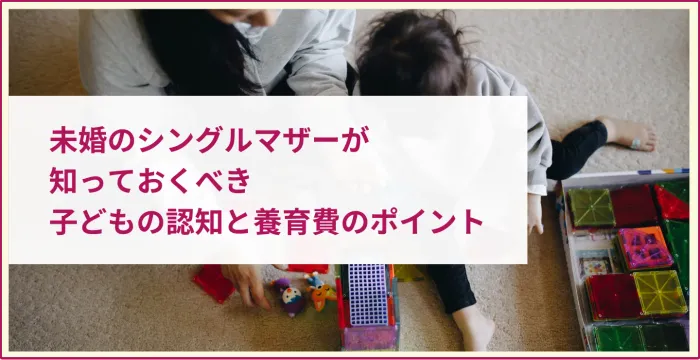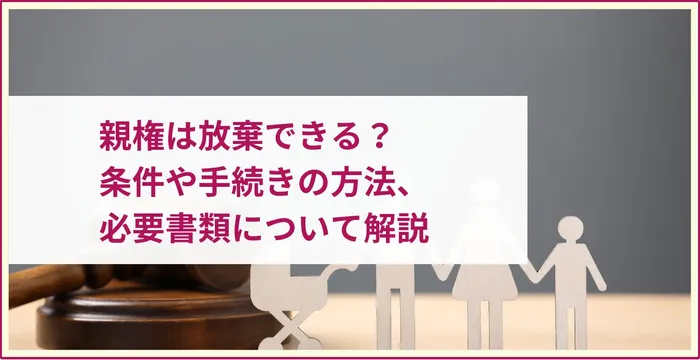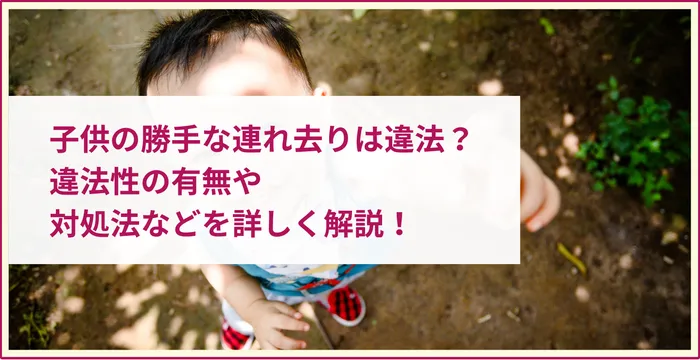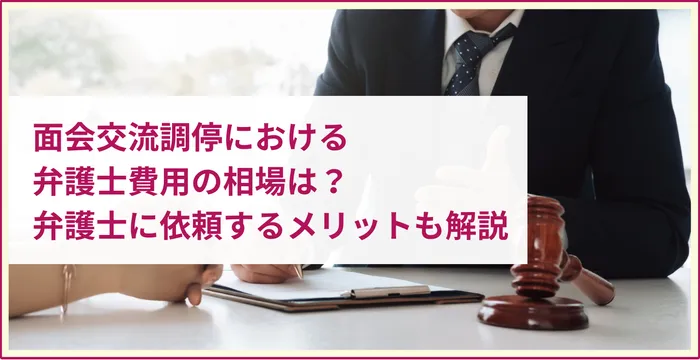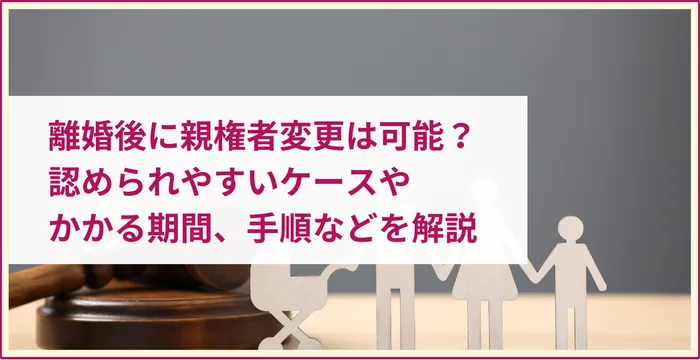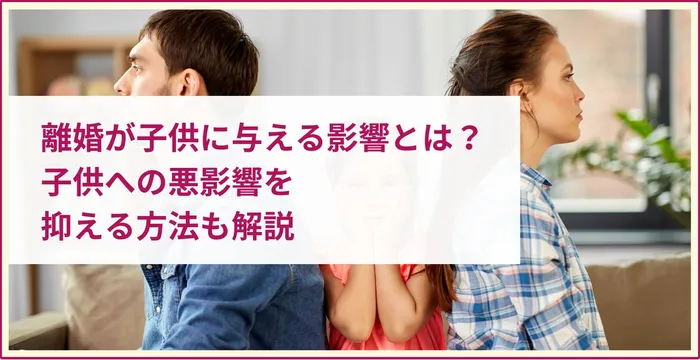77年ぶりに親権に関する民法の改正が行われ、これまで単独親権しか認められてこなかった日本で、2026年までに共同親権が認められるようになる予定です。共同親権が始まれば、離婚した後も父母ともに子どもと交流することができ、それぞれが責任を持って子どもを育てる選択ができるようになります。
民法改正前に既に離婚している場合でも、親やその子どもが家庭裁判所に申し立てを行い、認められれば、共同親権の選択が可能です。本記事では、共同親権の概要や共同親権導入の背景、メリット・デメリットを解説します。既に離婚している人向けに、現時点で親権を獲得する方法や、単独親権を得られなくても子どもと一緒に暮らせる手段についてもみていきましょう。
既に離婚していても親権者変更の申し立てが認められれば共同親権にできる
2026年までに施行されることになっている改正民法の施行後は、施行前に離婚しており、父母どちらか一方が親権を持っているケースでも、裁判所に親権者変更の申し立てを行い、認められれば共同親権になれるようになります。改正民法の施行後は、いつ離婚したかを問わず、共同親権を選択できる可能性があるのです。
ただし、今まで通り、父母どちらかの一方のみを親権者とする単独親権がなくなるわけではありません。親権者として認められるためには、裁判所による「子どもの利益のため必要である」という判断が必要となります。
なお、改正民法の施行前だと共同親権は認められないものの、現在でも親権を取り戻し、単独親権を得るための申し立ては可能です。
■親権とは
親権とは、子どもの監護・教育や、居住地の決定、財産の管理、法律行為の代理を行って、成人まで育て上げるために親が負う権利および義務を指す。親権は子どもが成人となるまで行使することができるが、18歳になると消滅する。
共同親権とは両親のどちらもが子どもの親権者となること
そもそも、共同親権とは、父母の両方が子どもの親権者になることを指します。
従来の単独親権では、親権を持たないほうの親と疎遠になるケースが非常に多く、会いたくても会えなかったり、養育費が支払われなかったりとさまざまなトラブルが発生しています。特に近年は、ひとり親家庭の世帯数の増加と貧困化が問題となってきました。
実は、G20を含む24か国のうち、既に22か国で共同親権が導入されています。既に諸外国では共同親権が主流になっていることもあり、日本でも2024年に衆参両議院で共同親権の導入が可決、2026年までに施行されることが決まりました。共同親権を選択できるようになることで、両親が離婚しても、子どもは父母のどちらかを失うことなく育つことができ、子育ての負担がどちらか一方に偏ることも少なくなるでしょう。
ただし、共同親権の導入により、単独親権では起こらなかった新たなトラブルが起きることも懸念されています。共同親権のメリット・デメリットについて、下記で簡単にまとめました。
参考:法務省民事局「父母の離婚後の子の養育に関する海外法制調査結果の概要」
共同親権のメリットは3つ
- 子どもに対する責任を1人で背負わなくても良くなる
- 養育費の支払いが滞りにくい
- 交流面会が適切に行われやすい
共同親権になることで、父母ともに子どもとの交流が持ちやすく、養育費も適切に支払われることが期待されています。
単独親権になると、どうしても親権者に子どもを育てる責任と負担が偏ってしまいます。本来、両親ともに子どもを成人まで育てる責任・義務があるにも関わらず、離婚後に協力して子育てできる元夫婦は少ないものです。特に親権を取ることが多い母親がシングルマザーとなり、困窮するケースが多々ありました。
現在、日本のひとり親世帯の相対的貧困率は48.3%と非常に高く、ひとり親世帯の約89%は母子世帯ですが、このうち父親から養育費を受け取れているのは約28%に留まっています。
また、単独親権では、離婚後に子供と離れて暮らす親が、子どもに会いたくても、親権者に子どもとの関わりを制限されるという問題も起きていました。面会交流に関する調停の申立件数は、2020年時点で約1万3,000件にも上ります。子どもとの交流が少なくなることで、子どもに対する養育への責任感や愛情が薄れ、養育費の不払いの原因にもなってきました。
共同親権になることで、ひとり親の負担が経済的にも精神的にも軽減でき、親権者ではない親が子どもの成長を近くで見守れるようになるのです。
参考:厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査の概要」
参考:日本財団「ひとり親家庭の貧困率は約5割。子育てに活用できる国や自治体の支援制度」
参考:朝日新聞「増える別居親子の「面会交流」 調停申し立ては10年余りで1.5倍」
共同親権のデメリットは4つ
- 子どもへ心身の負担がかかる
- 教育方針で対立してしまう可能性がある
- 遠方へ引っ越しにくい
- DVやモラハラが避けられない可能性がある
共同親権の導入により、単独親権で起きていた問題が解決できる期待がある一方で、夫婦でない父母がスムーズに協力できるとは限りません。共同親権になることで、子どもの心身の負担が増大したり子どもの利益が阻害されたりする恐れがあります。
単独親権では親権者が方針を決めることができましたが、共同親権では父母のどちらにも子どもの世話や教育をする権利と義務があり、意見が一致しないと子どもが両親の板挟みになることも予想されます。両親の不仲により子どもにプレッシャーを与えると、子どもの健全な成長に悪影響を及ぼし、大人になっても社会生活や人間関係の構築に支障をきたしかねません。
また、他人となった父母が協力して子育てをするためには、近くに住む必要があり、父母ともに仕事や家庭の事情で遠方に引っ越すことも難しくなります。父母が離れられない状況は、DVや虐待、モラハラから逃れにくくなる懸念もされています。単独親権では親権者が子どもとの面会交流を拒否できましたが、共同親権になることで遠くに逃げたり関係を絶ったりできず、加害行為から逃げられなくなるリスクがあります。
そのため、いかに裁判所が家庭内というクローズドな環境での加害行為を見抜き、共同親権から除外できるかが注目されています。
既に離婚済みの人が親権を取り戻せる可能性のあるケース
民法改正前であっても、状況によっては、現在親権を持っていない親が親権を取り戻し、単独親権を得ることが可能です。ただし、親権を取り戻すためには、裁判所に子どもの利益のため親権を移動させる必要があると判断されなければなりません。
ここからは、既に離婚による親権が決まった後に、親権を取り戻せる可能性のあるケースをみていきましょう。
- 親権者が子どもを虐待している
- 親権者が子どもを監護できない状態になっている
- 親権者が死亡してしまった
- 子どもが親権者の変更を望んでいる
無条件で共同親権が認められるわけではない点には留意が必要です。
親権者が子どもを虐待している
親権者が子どもを虐待している場合は、早急に子どもの身の安全を確保しなければならないため、現在親権を持っていない親が親権を取ることができます。虐待とは、身体的虐待・性的虐待・育児放棄・心理的虐待のいずれかに該当する子どもに対する加害行為です。
|
身体的虐待
|
暴行を加え、身体に痛み・傷・あざを与える行為
|
|
性的虐待
|
子供へのわいせつ行為・性的な行為の強要・性的なものを見せる行為
|
|
育児放棄(ネグレクト)
|
食事を与えない・病院に連れて行かない・自宅に置き去りにするなど、保護者としての責任を怠る行為
|
|
心理的虐待
|
言葉・態度・嫌がらせ・無視などで精神的に苦痛を与える行為
|
なお、共同親権が導入された後も、虐待がある場合は虐待していない親の単独親権となります。
親権者が子どもを監護できない状態になっている
親権者が子どもを監護できない場合も、親権を変更できるケースです。例えば、親権者が病気や怪我で入院したり、海外赴任に行ったりと、子どものそばにいて、するケースが該当します。親権者として、子どもの監護責任を適切に果たせていない状況では、親権変更が認められる可能性があります。
■子どもの「監護」とは
監護とは、継続的に子どもを保護・監督し、身の回りの世話をすること。具体的には、「食事・衣類・日用品・住環境の提供」「病気の際の看病・受診」「学校教育・家庭教育の提供」などが挙げられる。
親権者が死亡してしまった
親権者が死亡した場合、子どもを監護できる人がいなくなることを意味するため、親権の変更が認められやすくなります。
ただし、自動的に親権者が移るのではなく、まずは選任された「未成年後見人」が親権者の代わりに子どもの監護・教育や財産管理をすることとなります。親権者が死亡し、自分が親権者になりたい場合は、親権者変更を裁判所に申し立て、認められれば親権を得ることが可能となります。必ずしも親権者の変更が認められるわけではなく、子どもの健全な成長や幸せを考え、未成年後見人から親権の変更が必要だと判断された場合に限ります。
■未成年後見人とは
未成年後見人とは、未成年者の法定代理人となる人。親権者と同一の権利・義務がある。未成年後見人の選定方法は、親権者による遺言の指定、または家庭裁判所による選定の2種類がある。
子どもが親権者の変更を望んでいる
子ども自身が親権者の変更を望んでいる場合、希望を考慮して親権を変更してもらいやすくなります。
離婚時に子どもが15歳以上の場合、自分の意思や希望をはっきりと示せる年齢であるとして、必ず本人に意思を聴取し、子どもの意思を尊重した判断がなされます。15歳未満の場合は、子どもの養育実績や離婚後の養育環境、経済的状況などをふまえ、裁判所が親権者を判断します。ただし、15歳未満でも、自分の意思や希望を持つようになる10歳程度から、子ども自身の意向も考慮されるようになります。
離婚時に子どもの意思が反映されなかった場合や、親権者の養育状況が変化した場合、15歳以上の子どもが親権者の変更を望めば、子どもの意思が尊重され、変更の申し立てが認められることがあるのです。
親権を獲得できなかった場合は監護権を得ることも検討する
親権を獲得できなかった場合や父母ともに親権を主張して譲らない場合は、親権ではなく監護権を取ることも一手です。
監護権とは、子どもと一緒に暮らし、子どもの身の回りの世話や教育、しつけをする権利・義務で、親権の一部です。親権と監護権を父母で分けた場合、親権者には、財産を管理する権利が残ります。
一般的には、親権者と監護権者を一致させますが、親権者が看護者として適当でない場合に、親権者と監護権者が別になるケースがあります。例えば、下記のようなケースでは、親権者と監護権者が別になることが考えられます。
- 親権者が出張や海外赴任で子どもを監護できない
- 親権者が病気やケガで子どもを監護できない
- 親権者が子どもを虐待している
- 幼い子どもの養育には母親が適しているが、財産管理は父親が適している
監護権は裁判所を挟まなくても、父母の話し合いで自由に決めることができます。
まとめ
既に離婚している元夫婦が、民法改正後に共同親権にできる可能性があるのかについて解説しました。2026年に施行が予定されている共同親権。民法改正前に離婚していても、改正後に裁判所に申し立てを行い、子どもの利益のため必要であると判断されれば、共同親権に変更することが可能です。
なお、共同親権が認められる前でも、親権者が適切に子どもを監護・教育できない場合や、子どもが15歳以上になって希望する場合には、親権変更が認められる可能性があります。たとえ親権の獲得・変更が認められなくても、監護権を得れば、子どもと一緒に暮らすことは可能です。
いずれにしろ、将来的に共同親権を目指すのであれば、何が子どもにとって最善なのかをしっかり話し合い、子どもの負担にならないよう配慮しなければなりません。共同親権の導入にはまだ課題も残っており、国も具体的な体制整備や運用について検討を続けている状態なので、今後も動向を注視していきましょう。