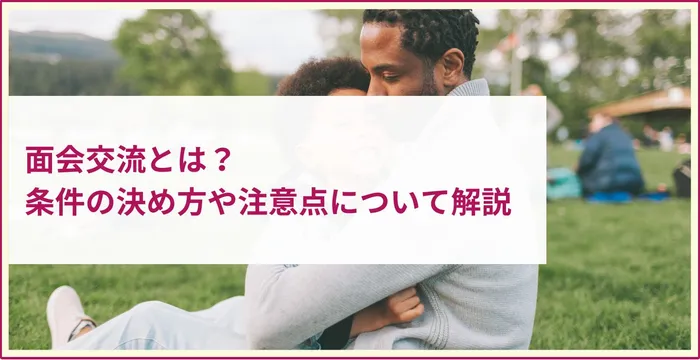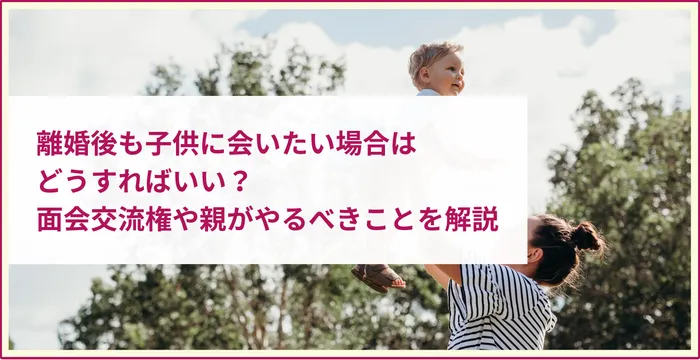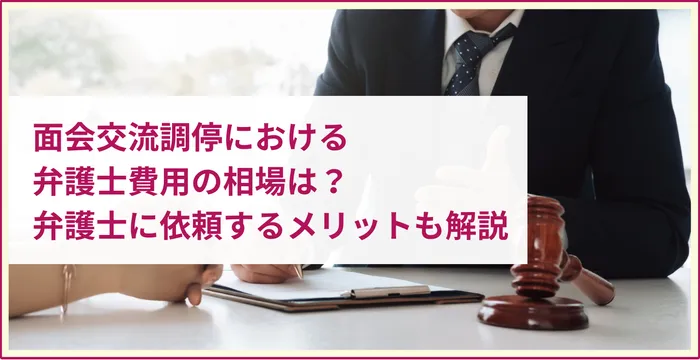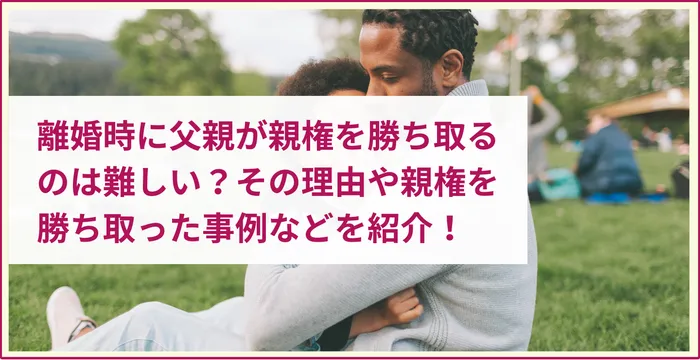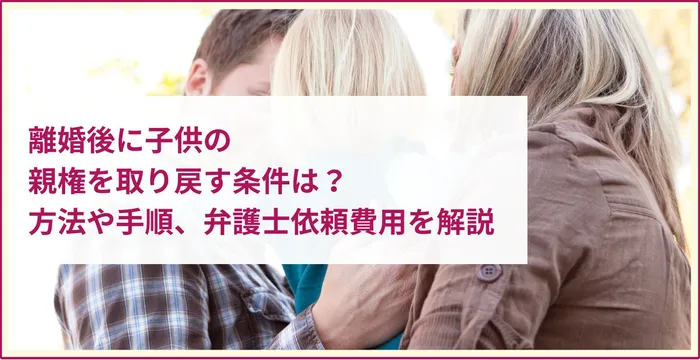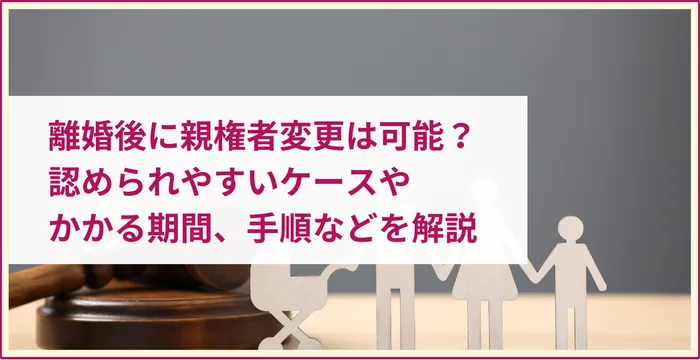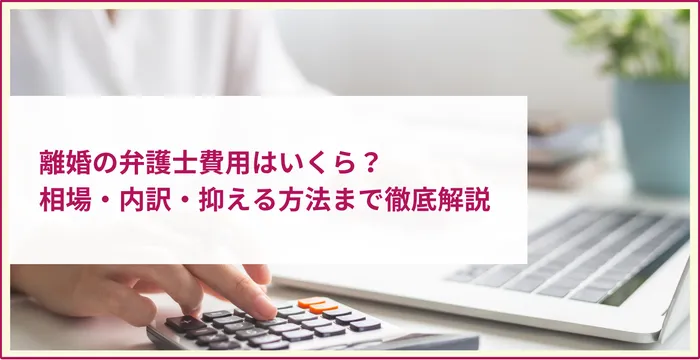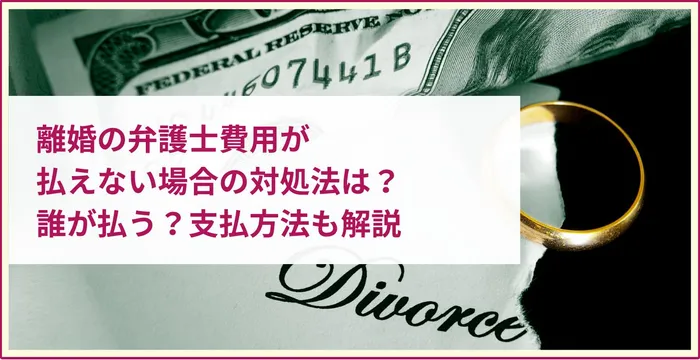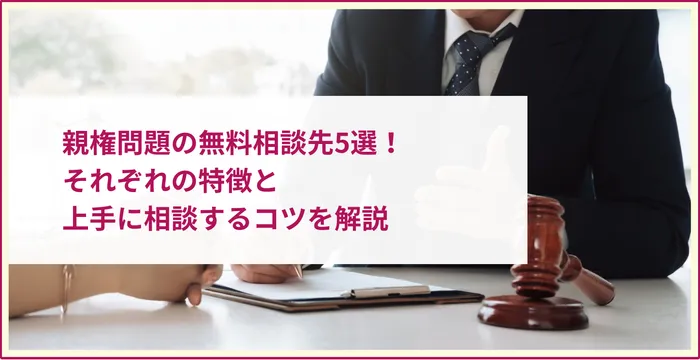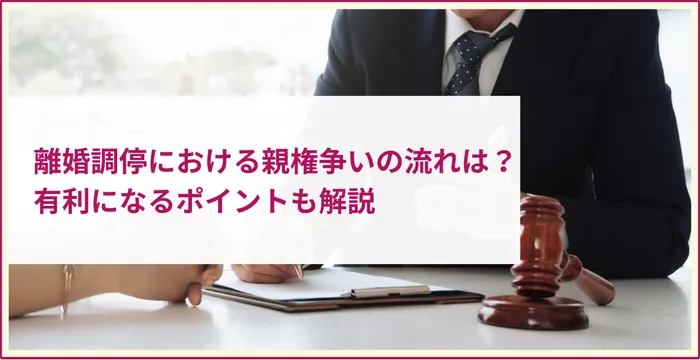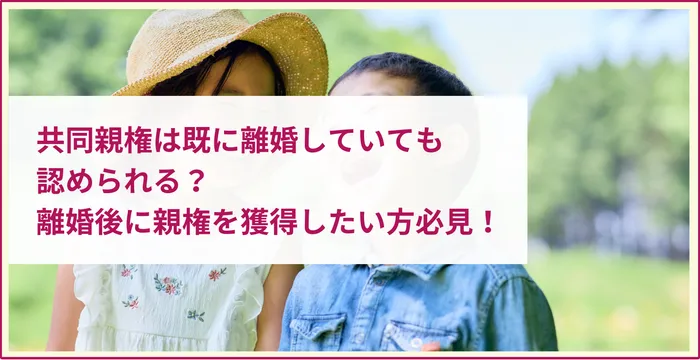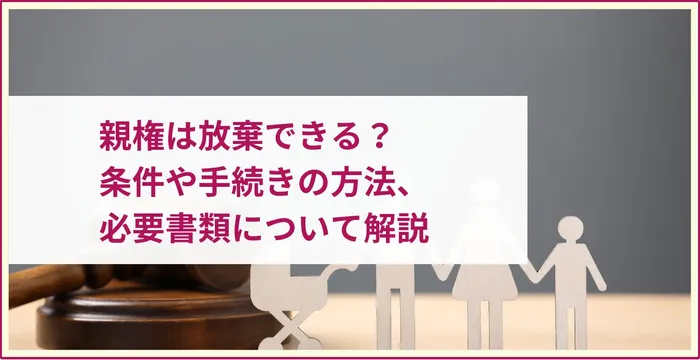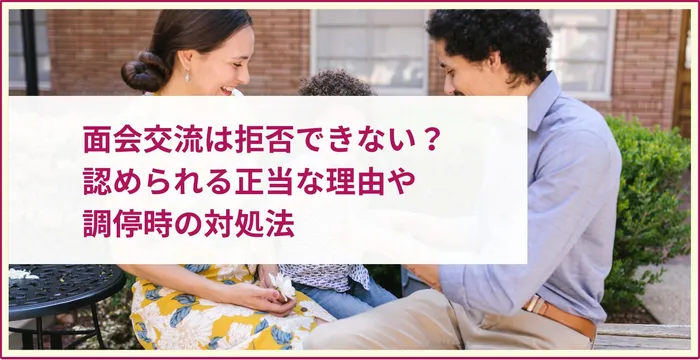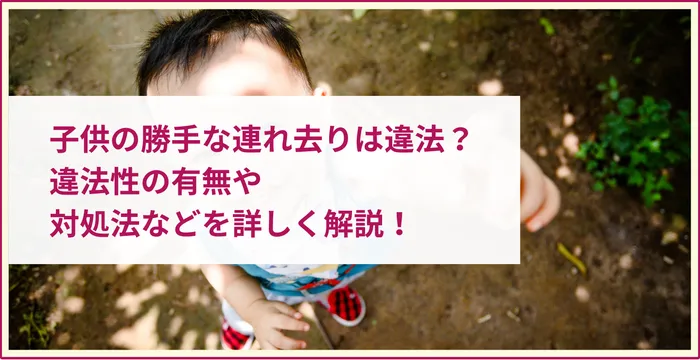親権問題を弁護士に相談するメリット
離婚に際して親権争いが生じる可能性があるときや離婚後に親権者となりたいときなど、親権問題は弁護士に相談することが大切です。
親権問題を弁護士に相談するメリットを以下にまとめました。
弁護士に相談するメリットを理解することは、親権の獲得など有利な解決につながります。ぜひ確認してください。
法的な観点から親権に関するアドバイスをもらえる
親権問題が生じたとき、どのような行動をとるべきか明確な答えが出せる方は多くないでしょう。
親権問題について弁護士に相談すると、法律の専門家による法的な観点から、親権に関するアドバイスをもらえます。
親権問題は基本的に話し合いで決着を図りますが、話し合いで解決できない場合は、裁判所での調停や訴訟で解決を図ります。
親権問題に強い弁護士なら、最終的な親権者の判断がされる訴訟を見据えてアドバイスしてくれるため、有利な解決を見込める可能性が高くなるでしょう。
具体的には、審判例や裁判例をもとに、親権争いでは監護の実績があるほうが有利になることなどをわかりやすく説明してくれるはずです。そのうえで、具体的にどうすべきかといった行動のアドバイスを受けられます。
親権争いに勝つためにとるべき具体的な行動がわかる点で、親権問題に強い弁護士に相談することは非常に大切です。
親権獲得のための交渉を一任できる
親権問題は、基本的には相手との話し合いで解決を図ります。しかし、夫婦間で親権が問題になるのは夫婦関係が破綻したときが多く、相手との話し合い自体が精神的な負担となることも少なくありません。
親権問題に強い弁護士に相談すると、精神的な負担の大きい相手との話し合いや交渉を任せることもできます。
当事者だけでは話し合いが進まなくても、弁護士が入ることで解決につながった事例も少なくありません。DVやモラハラがある場合は、相手との話し合いが困難であり、弁護士に依頼する必要性は特に高いといえます。
また、離婚時は親権だけでなく慰謝料や養育費、財産分与などについて夫婦間で意見が合わないことも少なくありません。このような離婚時の重要な問題も、まとめて弁護士に交渉を任せられます。
交渉を弁護士に任せることで精神的な負担が軽減するほか、離婚後の新生活に向けた準備も進められるでしょう。
調停や裁判になったとき、法的手続きを任せられる
親権問題は調停や訴訟に至ることがあり、これらの裁判所での手続きに慣れている方はそう多くありません。
調停はあくまでも話し合い(協議)なので手続きはそれほど難しくありませんが、訴訟は期日の進行や書面の提出などについて法律(民法、民事訴訟法)の知識が必要です。
初めて訴訟を経験する際、例えば以下のような問題があります。
- 裁判所に提出する書面はどのように書けばよいか
- 裁判所に提出する書面にはどのような内容を記載すべきか
- 裁判所に提出すべき証拠はどのようなものか
- 裁判所にはどのように証拠を提出すればよいか
提出する書面の内容や証拠は、父母のどちらを親権者に指定するか裁判官が判断する資料となる大切なものです。親権争いで有利な解決を実現するためには、裁判官が自身に有利に判断してくれるような書面や証拠を提出する必要があります。
しかし、有利な解決に導けるような書面や証拠の提出は、法律の専門家でなければ難しいのが現実です。
親権問題について弁護士に依頼すると、上記のような法的手続きを任せられ、結果的にご自身に有利な解決を見込めます。
親権獲得が難しいときに、監護権や面会交流に関する交渉を行ってもらえる
現実問題、弁護士に依頼したからといって、必ず親権を獲得できるわけではありません。親権獲得の見込みが低い場合は、子どもの監護や面会交流など、子どもとの関わりの確保が大切です。
もし親権争いにだけ固執して監護や面会交流に関する交渉をしなければ、離婚後、子どもとの関わりを確保できないおそれがあります。
子どもとの関わりを確保する観点では、親権だけでなく、監護や面会交流に関する交渉も重要です。
親権問題に強い弁護士に依頼することで、親権の獲得が現実には厳しい場合でも、監護や面会交流といった子どもとの関わりを確保するための交渉やアドバイスを期待できます。
もっとも、監護権や面会交流の交渉について経験や実績が豊富な弁護士は、それほど多くいません。相談する弁護士を選ぶ際は、監護権や面会交流について対応した実績があるかも確認しましょう。
親権問題について弁護士を選ぶポイントについて、詳しくは後述しています。
監護権や面会交流など子どもとの関わりを確保する制度について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
親権獲得後のトラブル発生を防げる
実は、親権を獲得できても、離婚後に子どもをめぐるトラブルが発生することも珍しくありません。多いのは、非親権者である相手(別居親)から養育費が支払われないといったトラブルです。
養育費とは子どもの監護に要する費用のことで、一般的には子どもの生活費や教育費、医療費を指します。
現行民法では、離婚後に父母の一方のみが親権者となる単独親権です。ただし、子どもの親(父母)である以上は、親権者でなくても子どもを扶養する責任があります。
以下のような理由で養育費を支払わないことは、法律上、許されません。
- 不倫した相手に養育費を支払いたくない
- 不倫したのに慰謝料の支払いを拒絶されている
- 子どもと一緒に住んでいない
- 子どもに会わせてくれない
- 親権を譲ってくれなかった
そもそも、養育費は親権者を誰にするかと同様に、離婚時に話し合って決めておく必要がある問題です。しかし、養育費の約束があっても、実際には支払われないか、支払われなくなることも少なくありません。
このような場合でも養育費の支払いを確保するためには、養育費や親権者など離婚時に話し合った内容の結果を、離婚協議書として書面にまとめておくことが大切です。
弁護士に相談すると、養育費の支払いがないときに訴訟をすることなく差し押さえ(強制執行)ができる離婚公正証書の作成などを提案してくれる場合があります。
離婚は、親権や養育費、慰謝料、財産分与など多くの問題が絡みます。トラブルを避けて安定した再スタートを切るために、弁護士からアドバイスを受けることが大切です。
親権について弁護士に相談すべきケース
親権をめぐるトラブルについて有利な解決を図り、離婚後のトラブルを避けるには、親権問題に強い弁護士に相談することが大切です。
相手が親権者になりたいと言う可能性がある、現に親権について意見が合っていないといった状況の場合、まずは弁護士に相談することを検討してください。
さらに、以下のケースでは弁護士に相談する必要性が特に高いといえます。
上記のケースで弁護士に相談する必要性が高い理由や、具体的に弁護士がどう対応してくれるのかなどを解説します。該当する場合は、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。
話し合いに応じてもらえない・決裂した
親権者を誰にするかは夫婦間で話し合って決めるのが原則です。しかし、実際には相手が話し合いに応じなかったり、話し合っても意見が合わず決裂したりするケースも少なくありません。
このようなケースでは、親権に強い弁護士に相談することが大切です。
夫婦間で親権についての話し合いがまとまらなくても、原則として親権者を決めずに離婚することはできません。そのため、離婚するには裁判所で話し合う調停という手続きが必要です。
調停とは、裁判所において、夫婦の間に調停委員と呼ばれる人が入って話し合いを進める制度です。裁判所の手続きですが、あくまでも性質は裁判所における夫婦間の話し合いであり、裁判官が親権者を決めるわけではありません。
調停の期日は基本的に平日であるため、会社員であっても時間をつくって裁判所に行く必要があります。また、調停で有利な解決を図るには、法律の知識を備えて根拠のある主張をすることも大切です。
弁護士に依頼すると調停の期日は弁護士が参加してくれるほか、調停でご自身に代わって有効な主張をしてくれます。
配偶者が子どもを連れて行ってしまった
離婚する前に、夫婦が別居することは珍しくありません。夫婦が別居する場合、相手が子どもを連れて行ってしまうこともあります。
このような場合には、早急に親権問題に強い弁護士に相談することが大切です。
親権者を決めた裁判例のなかには、子どもの環境を変えないことや、実際に子どもの監護を継続している親が誰なのかを重視して親権者を決めたものがあります。つまり、別居後、実際に子どもと一緒に暮らしている親のほうが親権獲得に有利で、暮らしていない親は不利です。
離婚するまでの別居が長期化すると、子どもも別居後の暮らしに慣れてしまうかもしれません。別居後、ようやく慣れてきた暮らしが親権者の決定によりまた変わるとなると、子どもにかかる負担も小さくないでしょう。
そのため、配偶者が子どもを連れて行ってしまった場合は、その状態を長引かせないためにも早急に弁護士に相談して解決を図る必要性が高いといえます。
なお、別居後に勝手に子どもを連れ去るような行為は、犯罪に該当する可能性もあります。
弁護士への相談・依頼は、細かな手続きに手間や時間をかけることなく、早期に手続きを進められる点がメリットです。また、子の引渡し調停や監護者指定調停といった手続きの提案も受けられ、場合によっては子どもを連れ戻すこともできます。
配偶者からDVやモラハラ被害を受けている
DVやモラハラ被害を受けており、離婚を検討している方も少なくありません。
DVやモラハラがある場合、親権はもちろん、慰謝料や財産分与、養育費など離婚に関する問題全般について、充実した話し合いの機会を確保することは困難です。
無理に話し合いを進めようとしても、暴力や暴言の影響で真意とは異なる意思を表示したり、話し合いを求める度に被害に遭ったりする可能性も否定できません。
話し合いの機会を保護し、さらなる被害の拡大を防ぐには、弁護士に依頼して交渉を進めることが有用です。弁護士が代理人となれば、相手と接することなく離婚の話し合いを進められます。
それだけでなく、場合によっては相手のDVやモラハラを指摘し、ご自身の親権獲得に有利な根拠ある主張を組み立ててくれるでしょう。
なお、DVやモラハラがある場合は、相手に対して慰謝料の請求もできる可能性があります。親権とあわせて、慰謝料についても相談するとよいでしょう。
親権獲得に不利な状況である
親権者になりたくても、以下のような状況は、親権の獲得が不利な状況と評価せざるを得ません。
- 育児放棄・ネグレクトをしていた
- 相手と比べて育児への関与が少ない
- 身体的虐待をしていた
- 精神的虐待をしていた
- 子どもとの別居期間が長期化している
- ケガや病気で養育が難しい
- 犯罪歴がある
- 薬物依存がある
- アルコール依存がある
- ギャンブル依存がある
- 収入が安定していない
親権を獲得できないと決まったわけではありませんが、一般的には親権獲得に不利な事情の1つであり、弁護士に依頼しても親権の獲得が難しい場合もあります。
親権獲得に不利な状況では、親権に強い弁護士による強力なサポートが大切です。子の利益に悪影響を及ぼさないことや改善が見られる事実などを弁護士が主張することで、不利な状況から一転して親権を獲得できる場合もあります。
仮に親権を獲得できなくても、前述のとおり子どもとの関わりを確保するため監護権や面会交流の確保に動いてもらえるでしょう。
自分は父親で親権を取りたいと思っている
実務上、父親の親権獲得は母親よりもハードルが高いのが現実です。母子(母性)優先の原則などと呼ばれ、特に乳幼児など子どもが小さいほど父親の親権獲得は難しいといわれています。
その理由は、父親は日中仕事で子どもと接する時間が母親と比べて短いことなどです。監護状態の維持や、監護実績を重視する考え方とも共通します。
もちろん、夫は外で仕事をして妻は家で家事をするといった考え方は必ずしも現在において一般的とはいえません。実際、共働き家庭の割合は増えており、社会状況は過去から変わったといえます。
裁判官によって異なりますが、判断基準としての母子優先の原則は、現在において過去ほど重視されていないといえるでしょう。
しかし、現在でも訴訟では父親の親権獲得が難しいといわれることがあります。父親の立場では、できるかぎり訴訟の前に弁護士に依頼したうえで、協議・調停での解決を図ることが有効でしょう。
仮に審判や訴訟に至ったとしても、弁護士がより具体的な親子関係を主張することで、母子(母性)優先の一般論を適用するのが妥当ではないことを説得的に主張してくれるはずです。
【離婚済みの場合】手放した親権を自分に変更をしたい
離婚時に決めた親権者は、離婚後でも変更することができます(民法第819条第6項)。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。引用元 民法第819条第6項
しかし、離婚後の親権者変更は、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。 家庭裁判所の関与なく、父母の協議だけで親権者を変更することは認められません。
さらに子の利益のため必要があると認められることが変更の要件です。
親権者の変更は離婚時の親権獲得よりもさらにハードルが高いため、弁護士のサポートを得る必要性が特に高いといえます。
離婚後に子どもの親権を取り戻したい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
親権に強い弁護士を選ぶポイント
これまで、親権に強い弁護士に相談することの大切さや有効性について解説しました。しかし、「親権に強い弁護士」とは具体的にどのような弁護士で、具体的にどのように探せばよいかを把握することも大切です。
結論、親権に強い弁護士を選ぶ際のポイントは以下のとおりです。
上記のポイントを重視すべき理由などを解説するので、ぜひ弁護士選びの参考としてください。
親権問題に関する実績が豊富か
弁護士探しでまず知っておくべきことは、弁護士でも親権に関する相談や依頼を受けたことがない弁護士もいる点です。
例えば、債務整理に関する相談や依頼を受けることがほとんどといった弁護士がいます。つまり、弁護士でも分野ごとに専門性の有無や得手不得手があるのが現実です。
親権問題について相談したいのに、あえて親権問題を取り扱ったことがない弁護士に相談することはおすすめできません。親権問題に関する経験が豊富な弁護士を選ぶべきでしょう。
具体的には、弁護士のホームページなどで親権について詳しく記載があるか、対応実績が豊富などの記載があるかを重視して選ぶことがポイントです。
親権問題の経験が豊富な弁護士なら、専門性の高い知識や経験にもとづく的確なアドバイスや、スムーズな交渉・手続きの進行を期待できます。
コミュニケーションが取りやすく心に寄り添ってくれる
弁護士は、親権など分野ごとの専門性だけでなく、コミュニケーションの取りやすさや対応の良さなども重視して選びましょう。
例えば、以下のような弁護士はおすすめできません。
- 返事が遅い
- なかなか電話がつながらない
- 対応が丁寧ではない
- 説明がわかりにくい
1日でも早い解決を望んでいる場合は、スムーズなコミュニケーションができるどうかを確認することが大切です。常に多くの事案を抱えており、どうしても返事が遅くなる弁護士もいます。
しかし、1日でも早い解決を望む依頼者の立場からは、返事が遅かったり折り返しの電話がなかったりするのは致命的です。親権者がどちらになるか不安定な状態が長く続くと、子どもの健やかな成長を阻害しかねません。
コミュニケーションに関する不安や不満をなくすために、法律相談の段階からスムーズなコミュニケーションができるかを確認しましょう。
また、弁護士の対応に丁寧さや誠実さが欠けるところはないか気にかけておくことも大切です。
なお、弁護士による説明がわかりにくい場合は、その弁護士への依頼は慎重になるとよいでしょう。訴訟では、家族でも弁護士でもない第三者である裁判官に対し、自己に有利な判断を促す主張をしなければなりません。
裁判官をはじめ、他人にわかりやすく説明ができることは、弁護士にとって重要なスキルの1つです。
親権問題に関する調停・裁判の事例
親権問題に関する調停や裁判の事例を紹介します。
実際に親権問題に直面した当事者(父母・親子)が、どのように解決してきたのかといったリアルな情報です。
「自分もこうしてみよう」と思えるような事例に出会える可能性もあるため、ぜひ1つずつ確認してください。
娘が夫との面会交流を拒否し親権者が母親になった事例
初めに紹介するのは、妻が離婚を求めているものの、夫が娘と別居したくないために離婚に応じなかった事案です。
弁護士が間に入って話し合いをしたところ、夫は離婚の条件として親権を求めました。しかし、実は子どもは夫との接触を避けており、実際に面会交流を試みた結果、子どもが拒絶してしまいます。
その状況を認識した夫は、親権を求めていた態度から変容し、離婚に応じることとなりました。
事例1
| 項目 |
内容 |
| 概要 |
離婚前の別居中、別居親は離婚の条件として親権を希望していたが、子どもが実際に面会交流を試みた結果、円満な親子関係の維持は現実的でないと納得して離婚協議が進んだ |
| 親権の争い |
夫婦どちらも譲らなかった |
| 面会交流の争い |
夫婦(父母)は否定しなかったが、子どもが拒絶 |
| 結果 |
夫(父)が面会交流と親権を諦め、離婚に応じた |
| 解決ポイント |
離婚前の別居中に面会交流を試みたことで、解決につながった |
父母の双方が親権を譲らないといったよくある事案でしたが、面会交流に望む子どもの拒絶的な態度を把握してからは、父が親権の獲得を諦めました。本事案では、子どもの意思・意向が親権者を決めたといえます。
親権を獲得したい側にとって、子どもとの関係が相手と比べて良好であれば、本事案のように離婚前の面会交流を試みるといった手段は有効かもしれません。
姉には母・弟には父が親権者になった事例
次に紹介するのは、2人の子について、それぞれ親権者が別になった事例です。
夫婦については、子どもの長期休暇の際、妻が2人の子どもを連れて別居を開始し、妻から離婚を持ちかけました。別居中も、父は子どもとの面会は継続しています。
すると長男(11歳)は父と暮らしたいと言うようになり、長男の意向などをもとに、長男(兄)は父、長女(妹)は母がそれぞれ親権者とする審判となりました。
事例2
| 項目 |
内容 |
| 概要 |
離婚前の別居中に父子は面会交流をしており、長男が父との暮らしを望んだ結果、長女は母、長男は父が親権者となった |
| 子どもの人数・年齢 |
兄である長男11歳、妹である長女7歳 |
| 面会交流の争い |
別居後も当然のように面会交流があった |
| 結果 |
長男については父、長女については母が親権者となり、離婚が成立した |
| 解決ポイント |
子どもが父との暮らしを強く希望し、子ども2人との面会交流も良好に継続できることから、兄弟姉妹の親権者が分かれることとなった |
本事案は、事例1とは対称的に別居親と子どもとの関係が良好で、子ども自ら別居親との暮らしを望んだやや珍しいケースです。
実務上、兄弟姉妹の親権者が分かれることは避けるべき、母を優先すべきとの考え方があります。本事案では、面会交流を通じて兄弟姉妹の交流を継続でき、兄弟姉妹の分断は避けられると判断されました。
本事案の父は、子ども本人の意向と良好な父子関係もあり、低くないハードルを乗り越えて長男の親権を獲得したといえます。
本事案からは、別居親が子どもの親権を獲得する際は、以下の3点を説明することが有効になる場合があることがわかりました。
- 自身が親権者になることは子ども本人の意向と合致すること
- 親子関係が良好であること
- 兄弟姉妹の親権者が分かれても兄弟姉妹の関係に悪影響を与えないこと
特に子ども本人の意向については、15歳以上であれば子ども本人の陳述(意見)を聴くことが裁判所の法律上の義務とされています。
4 裁判所は、第一項の子の監護者の指定その他の子の監護に関する処分についての裁判又は前項の親権者の指定についての裁判をするに当たっては、子が十五歳以上であるときは、その子の陳述を聴かなければならない。
引用元 人事訴訟法第32条第4項
ただし、本事案では、15歳以上ではないにしても長男が11歳で小学校の高学年であったこと、連休中で父子の面会交流をする時間的な余裕があったことが判断に影響しているかもしれません。
例えば、長男が5歳程度だった場合は、本人の意向をそのまま汲むのではなく、より慎重に受け止める必要があるでしょう。また、子どもが自分と暮らしたいという意向があり親子関係が良好と主張しても、時間に余裕がなく面会交流の実績がなければ説得力は乏しくなるかもしれません。
妻の連れ子と夫婦間に長男が生まれて親権争いになった事例
続いて紹介するのは、父母間の親権獲得争いで父が勝利した事例です。
専業主婦である妻が子ども2人を実家に連れて別居する計画を知ったフルタイムの公務員である夫は、生後6ヶ月の長男と、別居アパートで2人暮らしを開始しました。父は、自身の母(子にとって祖母)の援助で長男を監護していたようです。
すると間もなく、母は子の監護者を指定する審判などを裁判所に申し立てました。父が単独で監護してから1週間という短期間での申立てです。
審判の結果、一審では長男の監護者は父と指定され、母は抗告を申立てたものの棄却されたため、一審の判断が維持されました。
結果的に、監護者となれなかった母は離婚後の親権の取得を諦め、父を親権者として協議離婚が成立しています。
事例3
| 項目 |
内容 |
| 概要 |
父は離婚前に生後6ヶ月の長男を連れて別居し、その後間もなく申立てられた審判で監護者と指定され、結果的に離婚後の親権も獲得した |
| 子どもの人数・年齢 |
妻の連れ子と当時生後6ヶ月の長男 |
| 面会交流の争い |
特に争いはない |
| 結果 |
長男について、父が監護者・親権者となり、協議離婚が成立した |
| 解決ポイント |
監護実績を証明できる十分な証拠があった |
本事案は、専業主婦の妻(母)ではなく、フルタイムで働いていた夫(父)が監護権と親権を獲得した珍しいケースです。
母が監護者指定の審判を申し立てたタイミングも、父側の単独監護期間が1週間と短い時であり、父にとっては監護者・親権者となるのが容易ではないと評価できる状況でした。
それにもかかわらず父が監護者・親権者となれたのは、母よりも父のほうが長男の監護に関わっていたことを示す証拠があったからです。本事案のように、監護者・親権者の判断では、監護実績が最重要視されることがあります。
もっとも、裁判官が違えば、結論が異なった可能性も否定できません。一見して不利な状況で満足の行く解決を実現した本事案は、弁護士の手腕が十分に発揮された事案だったとも考えられます。
裁判官を説得できるほどに説得力の高い弁護士を選ぶことも、当事者である父母としては重要な問題といえるでしょう。
妻の不貞行為が原因で親権争いになった事例
続いて紹介するのは、離婚前の別居中における監護者争いにおいて妻(母)の不貞行為が考慮された事例です。
不貞行為をしたのは妻(母)であり、これを夫(父)が指摘したところ、母は4歳の女児を実家に連れ帰ってしまいました。
婚姻同居中の監護の状況は、父母ともに同等に分担していたようです。
監護者指定の審判では父が指定され、母は控訴したものの棄却された結果、監護者は父で確定しました。
母は離婚前別居中における監護者争いに敗れたため、離婚後の親権については、それほど争うことはありませんでした。
事例4
| 項目 |
内容 |
| 概要 |
父母の親権争いで、母の不貞行為や子どもの連れ去りが考慮され、父が監護権利と親権を獲得した |
| 子どもの人数・年齢 |
4歳の女児 |
| 面会交流の争い |
特に争いはない |
| 結果 |
父が監護者・親権者となり、離婚が成立した |
| 解決ポイント |
不貞行為と子どもの連れ去りが監護者・親権者争いにおいて不利な事情となった |
従来、父母間で監護能力や監護実績に大きな差はないものの、子どもが4歳と幼い点からすると、母が監護者と指定されることが一般的でした。
本事案は、それでも母を優先することなく、母の不貞行為による婚姻生活の破壊や子どもの連れ去りが考慮され、父が監護者と指定されました。
もっとも、必ずしも不貞行為や連れ去りが監護者・親権者争いに影響するとは限りません。実際に、子どもを連れ去った父母が監護者・親権者となった事例をすでに紹介しました。
しかし、裁判官によっては不貞行為や連れ去りの事情が考慮される可能性は否定できません。子どもの親権獲得に万全を期すためには、不貞行為を避けるほか、子どもを無断で連れ去ることがないようにすることが大切です。
なお、別居時に子どもを連れ出す際は、相手から口頭で同意してもらうだけでは不十分です。口頭だけでは、調停や審判となった際、「無断で連れ出した」と主張された際に反論できる証拠がありません。
可能な限り、別居時のやり取りは記録し、調停委員や裁判所に提出できる状態にしておきましょう。
夫のDV・モラハラが原因で離婚し親権争いになった事例
最後に紹介するのは、夫のDV・モラハラで別居・離婚を決意した妻(母)が、激しい親権争いの結果、調停で親権を獲得した事例です。
夫は妻に対して交友関係の制限や暴力的行為をしており、首を締めることもありました。そのようなDV・モラハラから逃れるため、妻は子どもを連れて別居します。
一方、夫は「親権とられたらぶっ殺す」といった旨を知人に話していたようで、これを知った妻は離婚調停を申し立てました。
調停では激しく対立していましたが、家庭裁判所調査官の調査を経てなんとか夫(父)が譲歩し、妻(母)を親権者とすることで調停が成立しました。
事例5
| 項目 |
内容 |
| 概要 |
父母の親権争いで、家庭裁判所調査官の調査を経てようやく父が譲歩し、母を親権者とする調停が成立した |
| 子どもの人数・年齢 |
子ども2人 |
| 面会交流の争い |
特に争いはない |
| 結果 |
母が親権者となり、離婚が成立した |
| 解決ポイント |
調停を利用し、かつ家庭裁判所調査官による調査を経た結果、相手の譲歩を引き出せた |
本事案では、父母の双方が親権について譲歩せず、両者激しく対立しました。
もっとも、夫のDV・モラハラが激しかったため、そもそも調停でなければ夫婦の双方が対等に話し合うことは困難だったでしょう。その点、弁護士に相談して調停の機会を確保できたことには大きな意義がありました。
また、家庭裁判所調査官による調査が実施された点も、本事案の特徴です。調査結果は裁判官が判断する際の資料となるため、母側に有利な調査結果があるからこそ、父の譲歩を引き出せたのかもしれません。
さらにいえば、本事案では夫(父)の妻(母)に対するDV・モラハラがあったため、母としては児童虐待を理由に自らが親権者となるのが相当といった主張ができた余地もあったでしょう。
内閣府男女共同参画局のWebページでは、夫婦間のDV・モラハラは子どもへの心理的虐待にあたるとされています。
子ども自身が直接暴力を受けている場合は当然ですが、子どもの見ている前で夫婦間で暴力を振るうこと(面前DV)は子どもへの心理的虐待にあたります。
また、DV被害を受けている人は、加害者に対する恐怖心などから、子どもに対する暴力を制止することができなくなる場合があります。
DVや児童虐待によって、家族間の信頼関係が崩れていくこともあるのです。引用元 内閣府男女共同参画局
DV・モラハラがある場合には、早期に弁護士への相談や調停の申立てをすることが、1日でも早く親権問題を解決するためのポイントとなるでしょう。
親権獲得に向けた弁護士費用
親権に強い弁護士への相談には、法的なアドバイスをもらえるほか、交渉や手続きを任せられるなどのメリットがあることは前述しました。
しかし、弁護士への相談には、費用がかかる場合があります。
実際は弁護士によって異なりますが、初回相談は無料とし、2回目以降は30分までごとに5,500円(税込)程度と設定されているのが一般的です。
弁護士に相手との交渉や調停、訴訟について対応を依頼する場合には、上記の法律相談料ではなく、着手金や報酬金も請求されます。
法律相談料や着手金、報酬金の相場を、以下の表にまとめました。
弁護士費用の相場
| 項目 |
概要 |
相場 |
| 法律相談料 |
法律相談の対価として支払う費用 |
30分までごとに5,000円~1万円 |
| 着手金 |
弁護士に依頼したときに支払う初期費用 |
協議・調停:20~50万円
審判・訴訟:20~60万円 |
| 報酬金 |
成功の度合いに応じて事件終了時に支払う費用 |
協議・調停:20~50万円
審判・訴訟:20~60万円 |
ただし、相場はあくまでも目安であり、実際に負担する費用は弁護士との契約内容次第です。
例えば、着手金について協議からの依頼は10万円、調停からは20万円、訴訟からは30万円としている弁護士事務所があります。協議から調停になると10万円、訴訟になるとさらに10万円加算されるイメージです。
加えて、離婚自体、慰謝料、面会交流について争いがあれば、それぞれについて10~20万円ほど加算される場合があります。
親権に限らず、離婚における弁護士費用の相場や費用を抑える方法については、以下の記事をご覧ください。
弁護士事務所以外で親権について法律相談できる窓口
弁護士への相談は弁護士事務所に直接連絡する方法のほか、以下の窓口からも相談ができます。
各窓口ごとに特徴が異なるため、ぜひ詳細を確認してご自身に適した窓口を探してください。
弁護士に依頼する経済的な余裕がない場合は法テラス、相談のみが目的で無料にこだわる場合は自治体、相談後、同じ弁護士への依頼も考えている場合は弁護士会といった使い分けをするとよいでしょう。
法テラス
法テラスとは、国が運営する司法支援機関です。具体的には以下のサービスを提供しています。
法テラスのサービス概要
| サービス |
内容 |
| 情報提供 |
悩みに応じた法制度や相談窓口を、メールやチャット、電話などで案内する |
| 民事法律扶助(一般法律相談援助) |
経済的に余裕のない方を対象に、無料での法律相談を提供する |
| 民事法律扶助(弁護士費用等の立替え) |
実質的に、弁護士費用を分割払いにできる |
例えば、夫婦で離婚の話し合いで「親権を譲らなければ離婚しない」と言われて困っているとき、法テラスに電話やチャットなどで「どうすればいいか」といった相談ができます。
すると、法テラスのオペレーターから家庭裁判所に離婚調停を申立てることができるといった法制度の案内を受けられるでしょう。
そこで自分自身で調停を申立てるのが不安で弁護士に依頼したいと考えたとき、一定の条件を満たすと法テラスの代理援助・書類作成援助の利用ができます。代理援助・書類作成援助とは、弁護士費用を分割で支払える制度です。
しかし、法テラスで無料法律相談や弁護士費用の立替え払い(実質的に分割払い)を利用するには、以下の条件があります(日本司法支援センター業務方法書第9条)。
- 賞与を含む手取りの平均月収が、住んでいる地域と家族の人数に応じた基準以下であること
- 現金や預貯金、不動産、有価証券などの資産額が、住んでいる地域と家族の人数に応じた基準以下であること
- 勝訴の見込みがないとはいえないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
民事法律扶助の趣旨に適することの条件は、単に報復的感情を満たすためなど、法律上・経済上の利益のためではない場合には援助しないというものです。また、請求額が極端に少なかったり、勝訴しても回収可能性がなかったりする場合も、費用対効果の観点から援助の対象外とされています。
通常、問題となるのは収入基準と資産基準です。
収入基準には、家賃や住宅ローンを負担している場合の基準緩和や、医療費や教育費などやむを得ない出費で生計が困難となっている場合には基準を満たすものとされる取り扱いなどがあります。
実際に法テラスの無料法律相談や弁護士費用の立替え払いを利用できるかどうかは、実際に法テラスに相談した際にご確認ください。
弁護士会の相談窓口
弁護士会は、その弁護士会に登録している弁護士が相談に対応する法律相談センターを運営しています。
例えば、東京の弁護士会(東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会)は、法律相談サイト「弁護士会の法律相談センター」を共同で運営しており、Webサイト上で法律相談センターでの相談の予約が可能です。
一例として、新宿総合法律相談センターにおける親権に関する法律相談料は、30分までごとに5,500円(税込)、延長15分までごとに2,750円(税込)とされています。また、愛知県弁護士会では、離婚問題などの相談が初回無料です。
相談の当日は受付で書類を記入し、担当の弁護士と相談します。
自治体の法律相談窓口
市区町村では、当該市区町村に住んでいるか働いている個人を対象に、弁護士による無料法律相談を定期的に提供しています。
ただし、あくまでも相談に応じてアドバイスを提供する制度であり、相談した弁護士に相手との交渉や書類作成を依頼することはできないのが一般的です。
また、1回30分までと時間が厳格に定められている場合がある点にも注意が必要です。
弁護士への相談から親権獲得までの流れ
最後に、弁護士への相談から親権を獲得するまでの流れを紹介します。
親権獲得までの流れは個別のケースによって異なりますが、ここでは訴訟まで争う場合を解説します。
重要な手順が漏れていないか、次にやるべきことはなにかといった視点でぜひ参考にしてください。
親権問題が発生しそうならすぐに相談する
親権問題が発生しそうなら、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。具体的なタイミングの例は以下のとおりです。
- 離婚したいと考え始めた
- 相手が離婚したいと言うようになった
- 共同親権を希望しており、共同親権の選択が可能となる民法の改正法が施行された
- 離婚後相手が親権者となったが、子どもが自分と暮らしたいと言うようになった
- 離婚後相手が親権者となったが、相手の育児の状況が不適切に感じる
共同親権に関する民法改正法は、2026年5月までに施行されます。
なお、離婚や親権について配偶者に話をする前に、弁護士に相談することがおすすめです。先に配偶者と話すと、相手は親権獲得を意識して行動を変えるかもしれません。
できるかぎり早期に弁護士に相談しておくと、弁護士も余裕を持った対応が可能です。相談者・依頼者としても、早めにアドバイスを受けることで不利になる行動を避け、有利になる行動をとることができます。
弁護士を通じて協議する
弁護士に相談し、依頼する契約を締結すると、弁護士があなたの代理人として(代わりになって)相手と交渉ができます。
具体的な交渉の方法は、弁護士事務所などでの話し合いや書面を通じた話し合いなどです。事案に応じた方法が選択されます。
夫婦だけでは話し合いが進まなくても、弁護士が交渉することで解決に至るケースも少なくありません。
交渉力の高い弁護士であれば協議での解決となり、調停や審判・訴訟をする負担もなくスムーズな解決が可能です。
調停を申し立てる
弁護士を通じた協議でも話し合いがまとまらない場合、裁判所を通じた話し合いである調停を申立てます。
申立てる調停は、離婚前であれば夫婦関係調整(離婚)調停、離婚後であれば親権者変更調停です。また、親権者とは別に、子の監護者の指定調停を申立てることも有効です。
各調停の概要を以下の表にまとめました。
参照:予納郵便切手一覧表(令和7年1月版)(東京家庭裁判所)
なお、提出を求められる書式や郵便切手の額は各家庭裁判所の運用次第で、時期によっては変更される可能性があります。収入印紙代や郵便切手の額は弁護士から実費として請求されるものなので、詳しくは弁護士にご相談ください。
調停では、必要に応じて家庭裁判所調査官による調査も実施されます。具体的な調査方法は、調査官による子どもとの面談や家庭訪問、学校訪問などです。
調停で親権者が決まれば、裁判所書記官がその旨を含めた調停調書(実質は離婚協議書)を作成します。
離婚後に申し立てる親権者変更調停では、父母の意見が合わず調停不成立となっても、自動的に審判に移行して裁判官が親権者を決めます。
離婚調停の場合は、不成立になっても自動的に審判に移行することはありません。離婚調停が不成立になった場合、離婚について決着をつけるためには、改めて後述する離婚裁判(訴訟)を起こす必要があります。
なお、離婚調停で合意が成立しなかった場合、自動的に審判に移行することはありませんが、「調停に代わる審判」という制度が利用される場合があります。
「調停に代わる審判」とは、調停が成立しない場合において裁判官が必要と判断したときに、諸事情を考慮して解決に必要な判断がされるものです。
訴訟を申し立てる
調停でも話し合いがまとまらなければ、親権者の指定の主張を含む離婚訴訟を提起して解決を図ります。
協議・調停と異なり、審判や訴訟では裁判官が親権者を決めます。
裁判官の判断に納得いかない場合は、離婚訴訟であれば控訴、審判であれば抗告といった不服申立ての手続きが可能です。ただし、不服を申立てられる期間は2週間など短期間なので、弁護士と細かな連携をとって対応することが重要といえます。
親権を獲得する
親権者を定める審判や訴訟の判決が確定したら、親権争いは解決です。ただし、戸籍関係の手続きを忘れてはいけません。
離婚訴訟の場合、提訴した側(原告)は、裁判(判決)が確定した日から10日以内に、確定証明書と判決謄本を添えて離婚届書を市区町村に届け出なければなりません(戸籍法第77条が準用する戸籍法第63条)。
もし原告が期限までに戸籍の届出をしない場合は、被告が届け出ることもできます。
まとめ
親権に強い弁護士に相談・依頼をすることで、裁判例などをもとに、親権を獲得するためにとるべき行動をアドバイスしてくれます。
相手と直接話し合いをしたくない場合でも弁護士が代わりに交渉してくれるほか、調停や審判、訴訟でも裁判所に対して有利な解決が得られるような書面や証拠を提出してくれます。
弁護士による交渉の結果、相手から親権の譲歩を得られることもあります。
親権争いに勝つ見込みが薄い場合でも、監護権や面会交流の枠組みで子どもとの関わりを確保できるよう動いてくれます。
しかし、親権問題を扱った実績がない弁護士もいるため、弁護士を選ぶ際は、同様の事案を取り扱った実績が豊富かどうかを重視して選ぶことが大切です。