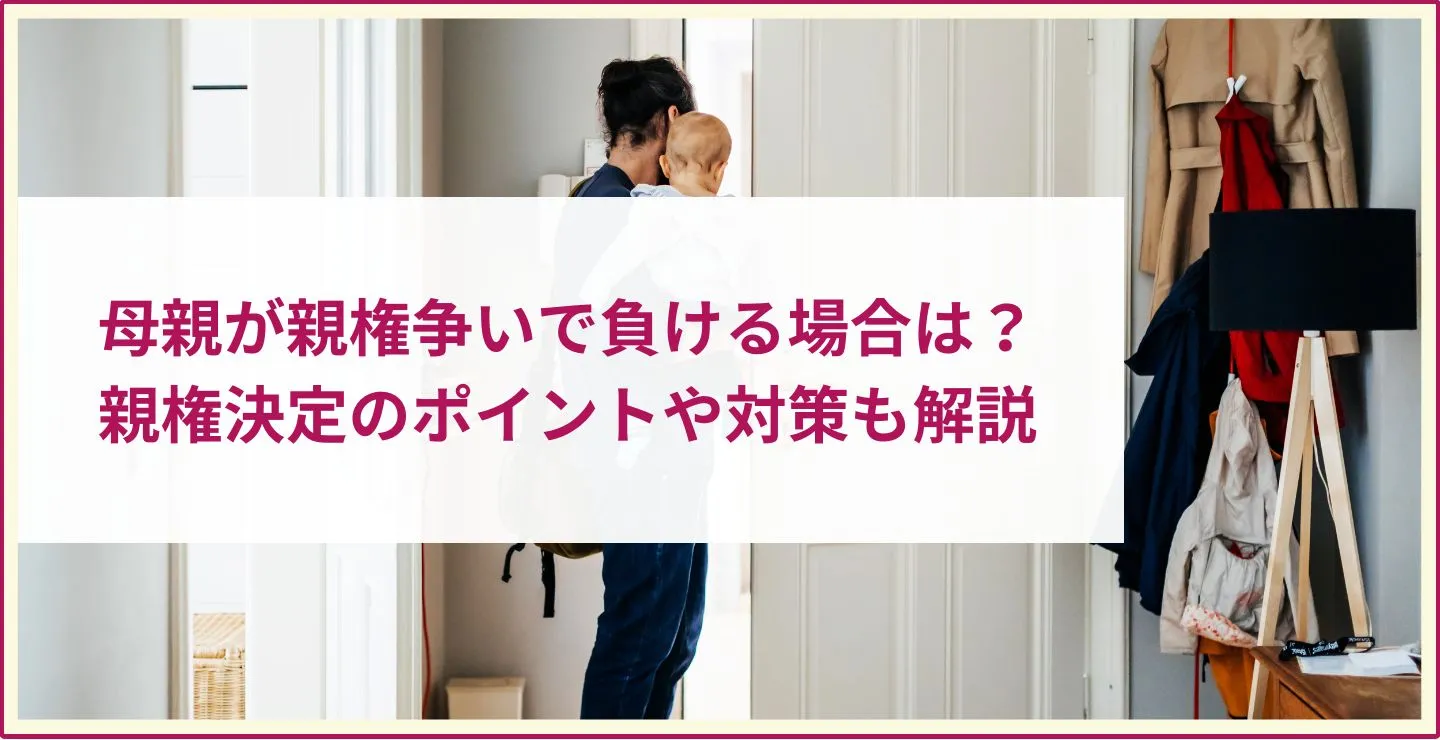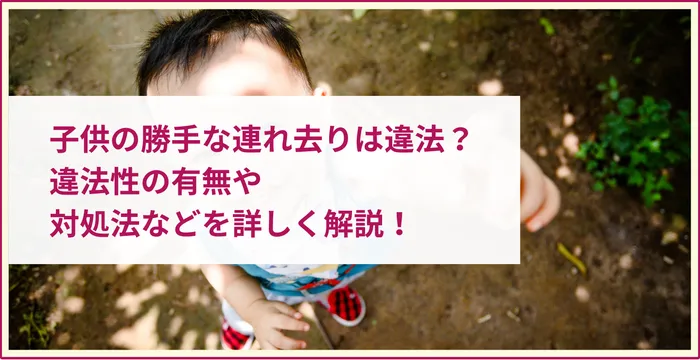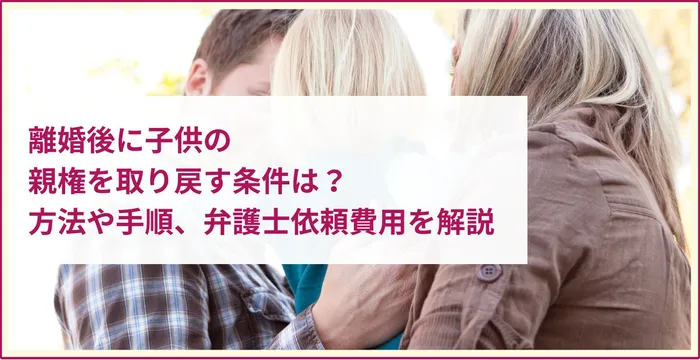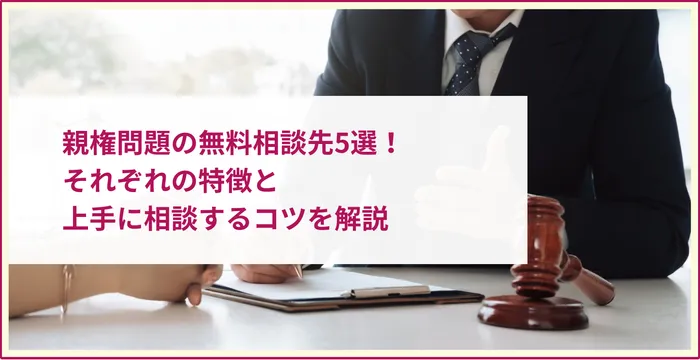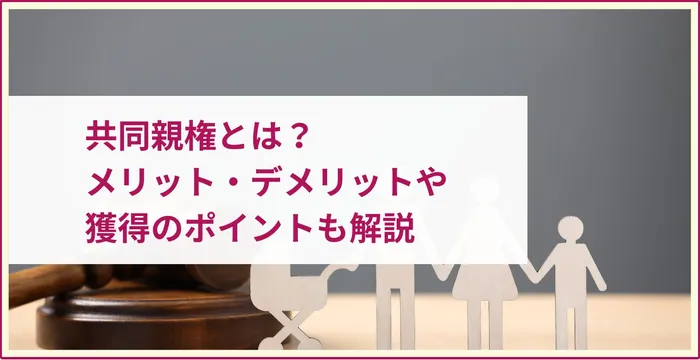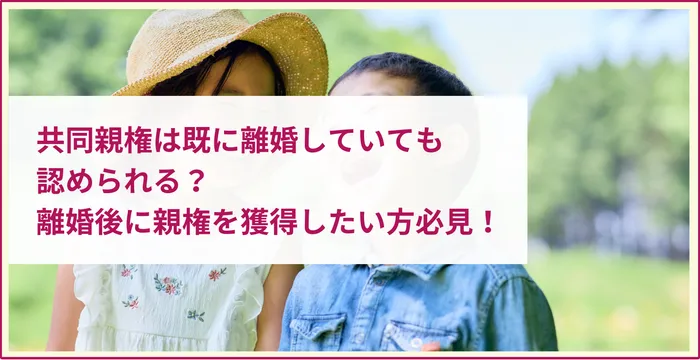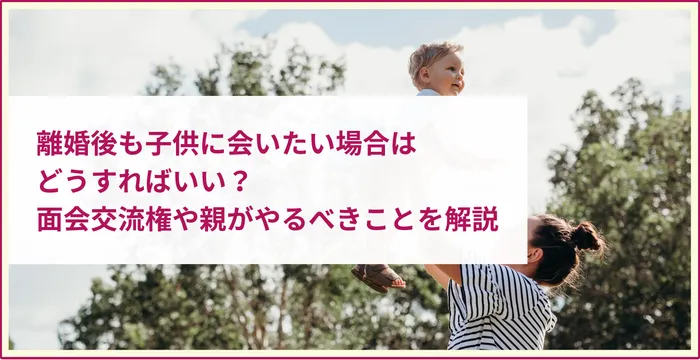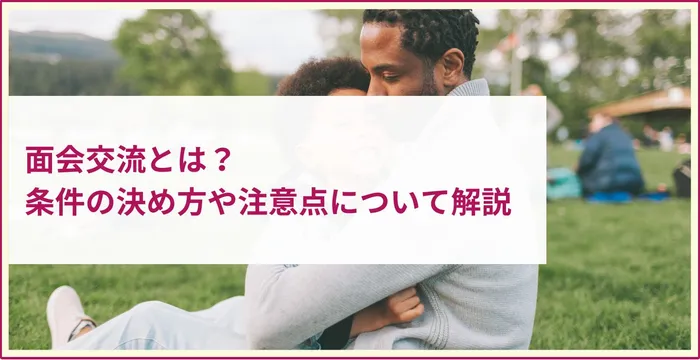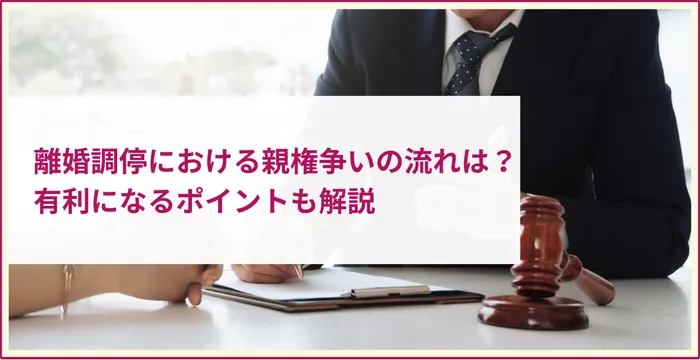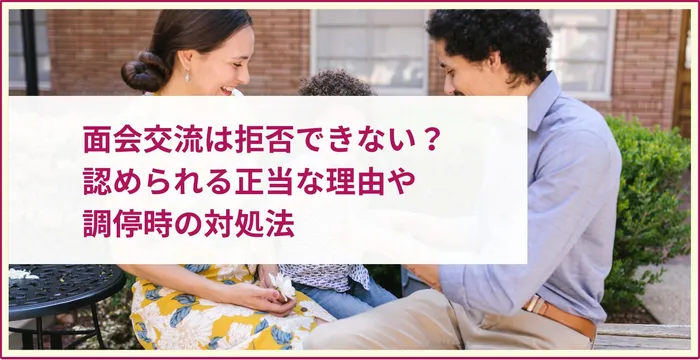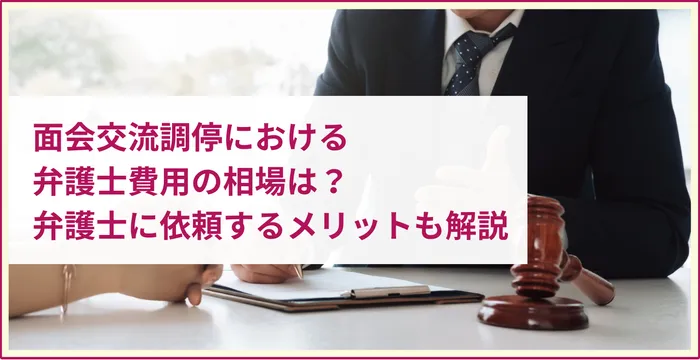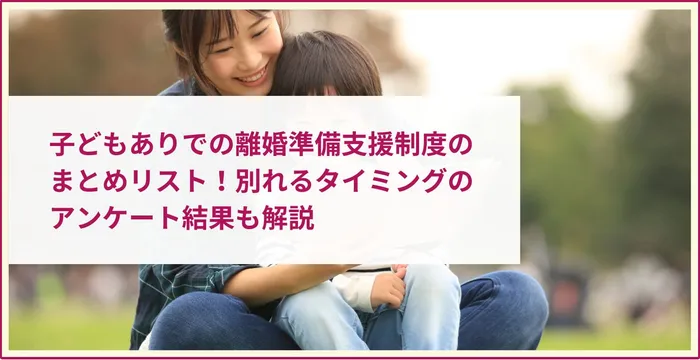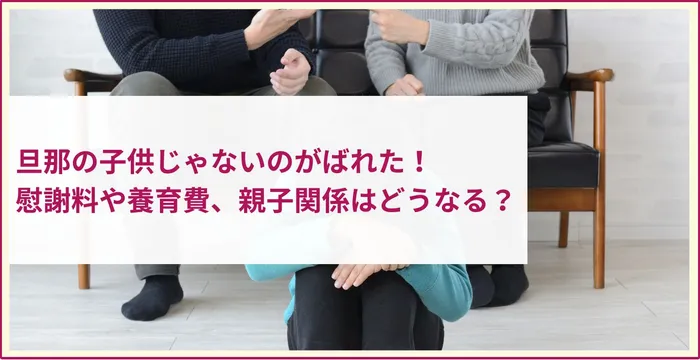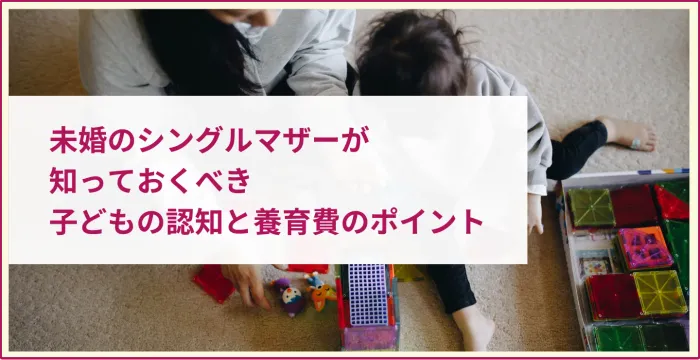親権は母親が持つケースが圧倒的に多い
日本で離婚をした夫婦で親権を持つのは、母親側が圧倒的に多いのが実情です。たとえば裁判所の「司法統計」によると、離婚調停・審判で母親側が親権を獲得しているのが過去3年間で90%を超えています。
|
総数 |
親権者が母親 |
親権者が父親 |
| 令和5年 |
1万6,103 |
1万5,128
(93.9%) |
1,290
(6.1%) |
| 令和4年 |
1万6,747 |
1万5,714
(93.8%) |
1,423
(6.2%) |
| 令和3年 |
1万9,915 |
1万8,678
(93.8%) |
1,795
(6.2%) |
参考:裁判所「令和5年度 司法統計」
参考:裁判所「令和4年度 司法統計」
参考:裁判所「令和3年度 司法統計」
また、日本の離婚の約9割を占める協議離婚(話し合いによる離婚)のときも、「母親が親権を持つケースが多い」と話す弁護士は非常に多く見られます。
父親が親権を獲得する可能性はゼロではなく、子どもの関係性や監護実績などを総合的に判断したうえで母親が負けることも十分にありえます。しかしこれまでの裁判例、生活環境の実態などを考慮すると、母親が親権を獲得しやすい環境にあるのも事実です。
以下では、母親が親権を持つケースが多い理由や、経済力不足や不貞行為の有無が親権にどう影響するのかなどを解説します。
「親権」と一言に言っても、正確には「身上監護権」と「財産管理権」に分けられます。身上監護権とは、日常的に子どもの世話・教育をする、子どもと一緒に住む、子どもの就業を許可するなどの権利です。財産管理権は、子どもの預貯金や子どもへの贈与などの財産管理を認める権利です。親権獲得とは身上監護権・財産管理権のどちらも得ることを指すのが一般的ですが、事案によっては別々に帰属させるケースもあります。
母親が親権を持つケースが多い理由
民法などの法律を見ても、親権争いで母親が有利に働くような規定が明確に定められているわけではありません。では、なぜ母親のほうが父親よりも親権を持つことが多いのでしょうか。これは「母親のほうが育児に費やす時間が多い日本の家庭環境」や、乳幼児と母親との関係などを考慮すると、母親が有利になるケースが自然と増加するからだと考えられています。
親権の判断で母親が有利になる理由は、主に次の通りです。
- 子どもの食事、教育、そのほかの世話といった監護を母親が担当する家庭が多いから
- 「乳幼児は母親の存在が必要不可欠」などから子どもが小さいと母親が重視される傾向があるから(母性優先の原則)
- 仕事に出ている父親だと子どもと過ごせる時間が母親よりも少なくなりがちだから
- 母親が中心に育児をしていると子どもが母親に懐きやすいから
詳細は後述しますが、親権を獲得するには「婚姻期間中にどれだけ子育てしたのか」「子どもの気持ちはどうか」「離婚した後に育児をサポートする環境や監護補助者が揃っているか」などが考慮されます。
総務省統計局「令和3年度社会生活基本調査結果」によると、週全体の家事関連時間は男性が51分に対して女性が3時間21分と、約4倍の差が生まれています。6歳未満の子どもがいる世帯の家事関連時間だと、夫は1時間54分に対して妻が7時間28分と大きな差となっていました。
「家族のために働いて収入を得る」という形で育児に貢献している夫であっても、監護実績や子どもとの関係性を持ちやすい母親のほうが、親権獲得へ有利に働くのが現在の状況だと言えます。
後述する裁判例である「年100日面会交流事件」でも、「地裁判決では父親が勝訴したものの、高裁判決で母親が逆転勝訴して親権を得た」という結果となりました。このように、父親と比較して母親のほうが親権争いを有利に進められる事例は多々存在します。
上記はあくまで「親権はどちらにするかが決まっていない」というケースです。話し合いの末に夫婦双方の合意があれば、法的争いなく父親が親権を得られます。
経済力不足や不貞行為などでも親権争いに母親が負けないケースがある
父母の親権争いを見ていると、母親側に問題がありそうなのにそれでも母親が親権を得ているケースが多数見られます。
以下では、「こんな状態でも母親が親権を獲得できるの?」と思われるケースをいくつか紹介します。
| 不利な状況でも母親が親権を獲得する可能性が見られるケース |
概要 |
| 離婚の原因が母親の不倫 |
・不貞行為といった夫婦間の問題は子どもの養育には関係がない
・不倫が原因で育児が疎かになる、浪費が激しいなどの問題があると不利になる可能性がある |
| 離婚の原因が母親の借金 |
・借金のせいで子どもに悪影響が出ない限りは母親が親権を取る可能性がある
・育児よりギャンブルを優先する、生活費をギャンブルにつぎ込むなどの問題があると不利になる可能性がある |
| 母親の経済力に不安あり |
・専業主婦で現在の収入がゼロでも働ける見込みがあり、親族からの援助、養育費・財産分与などで経済的な問題が解消できるなら親権獲得は可能
・シングルマザーでも児童手当や児童扶養手当などの国・自治体の援助制度あり |
| 母親が父親の合意なく子どもを連れ去った |
原則として違法だが父親側がDV・モラハラがひどかったり連れ去られてから一定時間が経過していたりすると母親側に親権が認められる可能性がある |
| 母親の健康状態が父親より悪い |
親権争いで不利になるのは「病弱が原因で育児に支障をきたすレベル」であり少し健康状態が悪いくらいでは親権争いに影響はない
・病弱気味でも親族や地域のサポートが受けられるなら問題なしと判断される可能性が高い |
親権を獲得するかを決める基準は、「親権を持つと子どもに不利益を与えないか」や「親権を持つのにふさわしい人物であるか」など、子の利益(子の福祉)への考慮が最優先になります。民法上の根拠は、第766条と第819条です。
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
e-Gov法令検索 民法第766条
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
e-Gov法令検索 民法第819条の6
つまり子の利益を害する要素が少ないのであれば、母親側に問題視される事実が存在しても、親権判断において不利に働かないことも珍しくありません。
子の利益(子の福祉)とは、子どもの生活環境、子どもの意思、子どもの健康・心理状態などの子どもの成長・幸せを向上させるための考え方です。明確な基準はなく、さまざまな要素を考慮して複合的に判断されます。
離婚時の親権争いで母親が負ける場合の7つの具体例
「母親が親権を持つケースが多い理由」や「現在の経済力や不貞行為などは親権獲得にあまり関係ない」といった事実関係を考えると、父親より母親のほうが親権を獲得しやすい事実は自然なことであるとわかります。
しかし、それでも離婚時に親権争いで母親が父親に負けるケースは存在します。親権争いで母親が負けるのは、「母親に親権を渡すと子の利益が損なわれること」が明らかなときです。
民法上においても、「親権者は子の利益のために子の監護および教育をする権利を有し、義務を負う」「親権者は子の人格を尊重し、年齢や発達の程度を配慮し、体罰そのほか子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない」と明記されています。
(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
e-Gov法令検索 民法第820条
(子の人格の尊重等)
第八百二十一条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
e-Gov法令検索 民法第821条
本来は親権争いで有利になりやすいのに母親が負けるのですから、子どもに対して相当な不利益を与えるリスクがあると思われたと言えるでしょう。
以下では、離婚時の親権争いで母親が負ける場合がある7つの具体例を解説します。
- 母親が虐待や育児放棄(ネグレクト)している
- 父親が主に子育てをしており母親に監護の実績がない
- 母親が精神疾患などの病気にかかっていて養育できない
- 父親と子どもが一緒に暮らし母親だけが離れて暮らしている
- 子どもが父親と暮らすことを選択した
- 監護補助者(育児をサポートしてくれる人)がいない
- 母親が子どもに悪影響を与えると判断された
母親が虐待や育児放棄(ネグレクト)している
母親が子どもに対して日常的に虐待・育児放棄(ネグレクト)をしているケースだと、母親であっても親権争いに負ける可能性が高くなります。また、離婚成立後に子どもへの虐待・育児放棄が発覚したときも、父親側から親権者変更調停を申し立てられて親権争いに発展することも想定されるでしょう。
虐待は身体への攻撃だけではなく、暴言などの精神的な暴力も含まれます。また心身への直接的な虐待はなくとも、子どもの衣食住を保障しない育児放棄が確認されれば、子への不利益や子どもの保護観点などから親権者として不適格と判断されてもおかしくありません。
母親による虐待・育児放棄が認められる例は次の通りです。
| 虐待・育児放棄の例 |
具体例 |
| 身体的虐待 |
殴る・蹴る、髪の毛を引っ張る、体を強く揺さぶる、熱湯をかける、性的暴行など |
| 精神的虐待 |
暴言を吐く、能力や見た目を下げる言葉をかける、無視する、日常的に怒鳴りつける、性的な言動を繰り返すなど |
| 育児放棄 |
食事を与えない、お風呂に入れない、不衛生な環境に置いたままにする、病気・けがをしても病院に連れて行かない、学習の機会を与えないなど |
虐待・育児放棄を証明する証拠を協議や法廷で提出されると、母親でも親権争いに負ける可能性がより高くなります。虐待・育児放棄の証拠の例は次の通りです。
- 虐待や育児放棄を実際におこなっている現場の写真・動画
- 虐待を受けたときに子どもが受診した医療機関の診断書やケガの写真
- 虐待や育児放棄について記録した日記やそのほかの記録
- 虐待・育児放棄を受けたという子どもの証言および証言している動画・音声など
- 虐待・育児放棄したことを認めたと判断できる母親の証言および証言している動画・音声など
なお虐待・育児放棄は、民法第770条の「法定離婚事由(裁判離婚が認められる民法上の理由)」における「悪意の遺棄」や「そのほか婚姻を継続し難い重要な事由」に該当する可能性が非常に高いです。離婚や親権の争いだけではなく、慰謝料請求の対象になります。
参考:裁判所「親権者変更調停」
父親が主に子育てをしており母親に監護の実績がない
育児放棄とまでは行かなくても、父親が子育てをメインでおこなっており、母親側に監護実績がほとんど認められなかったときは親権争いで母親が負ける可能性があります。監護実績の有無は調停や裁判などにおいても親権判断の重要な材料となっており、父親の親権獲得の決め手になるケースも少なくありません。
たとえば静岡家庭裁判所での審判では、「別居前から夕方以降や休日のほとんどで父親が子どもの面倒を見ていた」「別居後も父親だけで監護している実績があった」などの監護実績が考慮され、父親が監護権を獲得した事例があります。
日本において母親側が親権獲得に有利な理由に、「夫が働いて妻は家庭に入る」という価値観がまだ残っている点が挙げられます。専業主婦やパート・アルバイトで働く人のほうが子育てに充てる時間が多くなりやすく、監護実績が積みやすい環境になるからです。
反対に、ほとんど子育てにかかわっていないと判断されると、専業主婦の母親でも親権争いで不利になります。たとえば母親がフルタイムで働いて父親が専業主夫となっている夫婦だと、父親のほうが監護実績が多く認められる可能性が高くなります。
親権争いにおける監護実績の例は、主に次の通りです。
- 子どもの食事、入浴、排泄、着替えなどの毎日の世話をした
- 保育園、幼稚園、小学校などの送迎を継続しておこなった
- 子どもの病気やけがの際に病院への付き添いや看病などをした
- 子どもの生活環境維持や友人関係の把握など子どもの生活を守る努力をしている
- 子どもの習い事、クラブ活動、部活動、塾などの送迎・手配などをしている
- そのほか子どもの健康管理、精神安定、学習環境について継続的な支援をしている
自分の監護実績を証明したいときは、虐待・育児放棄と同じく「監護をした証拠」を集めるのが効果的です。監護実績の証拠となるものは、主に次の通りです。
- 食材の買い出し記録やレシート
- 保育園・幼稚園や学校の行事への参加記録
- 食事、送迎、着替え、入浴などをしてきたことを証明する写真や動画
- 子どもの宿題の添削や学校側とのやり取りの記録
- そのほか母子手帳、健康診断記録、予防接種の記録、育児日記など子どもの育児に関する記録(アプリなどでも可)
母親が精神疾患などの病気にかかっていて養育できない
重い精神疾患などの病気にかかっており、なおかつ「子育てをするのが難しい状態」と判断されると、母親でも親権争いに負ける可能性があります。「〇〇病にかかったら親権が取れない」ではなく、あくまで「病気であっても育児ができるか否か」「病気でも周囲にサポートしてくれる人間がいるか」などが親権判断のポイントです。
とはいえ病気の特性上、子育てに支障をきたしやすい病気はいくつか存在します。子育てに影響が出やすい精神疾患等の例は次の通りです。
- うつ病、双極性障害(躁うつ病)
- 統合失調症
- 認知症
- アルコール依存症
- 薬物依存症
父親と子どもが一緒に暮らし母親だけが離れて暮らしている
母親が子どもを残して家出して父親が引き続き子どもと一緒に暮らしている状態だと、父親に親権争いで負ける可能性が高くなります。理由は次の通りです。
- 育児放棄や育児意欲なしなどと判断されやすい
- 父親側の監護実績が増えやすい
- 子どもが父親と接する機会が増えて子どもが父親に懐く
- 父親と子どもの生活が通常となり子どもの生活の安定性が重視される(継続性の原則、現状維持の原則)
もし母親が無断および正当な理由なく家を出ている場合だと、民法第752条における「同居、協力および扶助の義務(夫婦は一緒に暮らして協力し合って生活すべしという義務)」に違反している状態です。また、民法第770条における悪意の遺棄に該当する可能性が高くなります(父親からのDVやモラハラなどから逃げるためなど正当な理由があるときは父親側に法的責任が出る可能性あり)。
子どもが父親と暮らすことを選択した
夫婦の親権争いにおいて、子どもとの関係性や子どもの気持ちは重要視されます。子どもが父親と暮らしたいと強く願っている場合は、親権争いで父親側が有利になるのは間違いありません。
とくに子どもの年齢が15歳以上だと、子どもがついていきたいと答えた親側に親権を与えることも実務上多く見られます。もし生活環境、経済状況、監護状況が不利な立場にある父親でも、15歳以上の子どもが「父親と一緒に暮らしたい」と答えたときは、父親が親権を獲得する可能性は高くなるでしょう。
家事事件手続法第169条や人事訴訟法第32条には「親権者指定・変更の審判において、裁判所は15歳以上の子の陳述を必ず聴かねばならない」と明記されており、15歳以上の子どもの意思が親権獲得に大きく影響することがわかります。
また、子どもが15歳未満であっても、10歳前後の年齢以上なら親権者選びに子どもの意思を尊重するのが一般的です。家事事件手続法第65条にも、「子どもの意思を把握できるよう努め、子どもの年齢や発達の度合いに応じて意思を考慮すべき」とはっきりと記載されています。
第六十五条 家庭裁判所は、親子、親権又は未成年後見に関する家事審判その他未成年者である子(未成年被後見人を含む。以下この条において同じ。)がその結果により影響を受ける家事審判の手続においては、子の陳述の聴取、家庭裁判所調査官による調査その他の適切な方法により、子の意思を把握するように努め、審判をするに当たり、子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない。
e-Gov法令検索 家事事件手続法第65条
とはいえ、子どもの意思1つで100%親権者が決まるわけではありません。子どもの意思に加えて、子どもの年齢・性別、監護実績、親の経済力、愛情の度合い、サポート体制なども考慮した総合的な判断がなされます。
たとえば子どもの年齢が低いうちだと、「周囲の影響を受けやすい」「一時的な好き嫌いで判断してしまう」といった、精神面の幼さを考慮して意見をどの程度尊重するかを慎重に決めます。
東京高裁平成11年9月20日の判決だと、子どもが母親を非常に強く拒否した事実があるにもかかわらず、「子どもを無断で連れ出した父親の影響があることを否定できない」「5,6歳の子どもは周囲の影響を受けやすい」といった背景や監護状況などを考慮し、父親を監護者とする一審の判決の取り消し・差し戻しとしています。
参考:e-Gov法令検索「家事事件手続法第169条」
参考:e-Gov法令検索「人事訴訟法第32条」
監護補助者(育児をサポートしてくれる人)がいない
母親が親権を獲得した後でも母親以外に監護補助者(育児をサポートしてくれる人)がいるかどうかは、親権争いで考慮されるポイントの1つです。
<監護補助者の例>
- 日中に子どもの面倒を見てくれる両親や祖父母
- 保育園や学校などの送り迎えをしてくれる親族
- 親として子どもの監護全般をおこなう再婚相手
監護補助者がいない状況でも、母親1人でも育児できると認められれば問題ありません。
逆に母親1人で育児が難しい状況で監護補助者もいないケースだと、親権が父親側に与えられる可能性が出てきます。「離婚前まで育児は父親が中心だった」「母親の仕事が忙しく監護をする時間がない」といったケースだと、監護補助者がいないと親権争いが不利になるかもしれません。
親権を獲得するにあたって不安な要素があるなら、別居の際は実家に帰るなどして、監護補助者を周りに作りましょう。
母親が子どもに悪影響を与えると判断された
上記までの内容とは別に、母親が子どもに悪影響を与えると判断された場合は、親権獲得に不利に働く可能性が高まります。主に以下の例などが挙げられます。
- 子育てに悪影響が出るレベルでの浪費癖やギャンブルによる借金
- 酒癖にともなう暴力・暴言行為や悪意の遺棄のリスク
とはいえ、これらの過去があったからといって必ずしも親権争いで負けるとは限りません。
これからの生活で子どもにとって悪影響を及ぼすかどうかが重要なので、まだ離婚する前なら今からでも改善して、子どもに悪影響を与えるような行為はできるだけ避けましょう。
離婚して調停や裁判で親権者を判断する際の基準
夫婦が話し合って離婚を決める場合、どのような理由や離婚条件でも当事者同士の合意があれば離婚は成立します。もし「監護実績が少ない」「精神的に不安定」など法的に親権争いが不利になる状況下の母親でも、夫婦の合意によって親権を得ることが可能です。
一方で、話し合いだと親権が決まらないときは、離婚調停で争うことになります。
離婚調停とは、最高裁判所が選定した調停委員と裁判官が夫婦の間に入り、家庭裁判所にて離婚について話し合う手続きです。離婚調停でも親権者争いが決着しないときは、離婚審判や裁判にて裁判官が最終的な判決を下します。
離婚調停・審判・裁判にて親権を判断する際には、「子の利益」を優先的に考慮した以下の基準を基に判断がくだされます。
- 母性優先の原則
- 監護の実績と継続性
- 子どもの意思
- 兄弟不分離
- 面会交流の実施
- 育児のサポート体制の有無
親権は母親が持つケースが圧倒的に多いにて解説した通り、離婚調停や裁判の場では母親側に親権が認められるケースが圧倒的多数です。上記の判断基準も、実質的に母親が有利になりやすいものとなっています。
しかし、離婚時の親権争いで母親が負ける場合の7つの具体例でも示したように、母親が負ける場合も十分に想定されます。負ける場合の7つの具体例も、調停・裁判などにおける判断基準の有無が大きく反映されたものです。
親権時に親権を争うときは、調停を飛ばしていきなり裁判から始めることができません。必ず調停での話し合いを経ないと訴訟を提起できないことを義務付ける、「調停前置主義」が採用されています。離婚後の親権者変更なら調停前置主義ではないものの、それでも実務上は調停から申し立てるよう要請されるのが一般的です。
母性優先の原則
母性優先の原則とは、「子どもがまだ幼い場合、親権者は母性を有する者が望ましい」とする、家庭裁判所における親権の判断基準の1つです。「親権者は母親が望ましい」と直接的に解釈されることもあります(母子優先の原則と呼ぶこともあり)。
とくに乳幼児にとって母親は必要不可欠であるケースが多く、子どもの年齢が低いほど母性優先の原則が親権獲得に有利に働くケースも珍しくありません。
とはいえ時代の変化とともに価値観が変化しており、近年では「監護の実績と継続性」や「一定の年齢以上の子どもの意思」などのほうが、親権決定に関して大きなウェイトを占めている傾向が見られます。
なお、母性の解釈は専門家の間でも分かれるほど曖昧な概念であり、何を持って母性とするかは夫婦ごとの事案によって変化します。また、母性は母親だけではなく父親も有するものと考えられています。
監護の実績と継続性
監護の実績と継続性とは、今まで子育てをしてきた実績があり、さらにその環境を継続できる親が親権を得やすいという考え方です。
子育てをしてきた実績があるなら、離婚後も子どもが健やかに育ちやすいと考えられますし、その環境が継続できるなら、子どもにとってストレスがありません。
そのため、これまで父親が常に子育てをしてきた場合は、父親が親権を得る可能性が高くなるでしょう。
子どもの意思
前述したように、15歳以上の子どもには判断能力が認められ、調停や裁判の場においても陳述を聴くべしと法律で定められています。また実務上は、10歳前後から子供の意見が聞き入れられる場合も多いです。
つまり、子どもが大きいほど親権判断に子どもの意思が反映されるようになり、調停や裁判の場においても重要な判断材料となります。
兄弟不分離の原則
離婚裁判をする際は、兄弟・姉妹を分離するべきではないという考え方があります。これを「兄弟不分離」といいます。
そのため、裁判をする場合は「兄弟・姉妹を分離し、母親・父親それぞれが別々の親権者になる」という事態は避けられる傾向にあると理解しておきましょう。
ただし、以下のような要因で親権者が別々に指定されることもあります。
- 兄弟・姉妹の意思
- 離婚前から兄弟・姉妹は分離し別居している
たとえば、すでに離婚が成立していて乳幼児の次男の親権が母親側、10歳の長男が自分の意志で父親と暮らすことを選んだ場合、兄弟が別々になっても父母それぞれが親権者になる可能性があります。
面会交流の実施
面会交流の実施にどれだけ前向きなのかも、親権者を決める要因の一つになります。子どもの利益を考慮する場合、離婚をした後も子どもは母親・父親ともに交流することが望ましいとされています。
そのため「離婚をしたら子供は元配偶者に一切合わせたくない」と考えている親は、親権争いで不利になるかもしれません。
「離婚をしても面会交流は頻繁にしてもよい」と考えている親なら、子どもにとってどちらの親とも交流ができて健全であると判断されて、親権争いも多少有利になるでしょう。実際に面会交流を100日程度を認める提案をした父親が、地裁にて親権を勝ち取った裁判例も存在します(高裁敗訴、上告不受理)。
なお、前提として面会交流は子どもの権利であり、一度決定した面会交流の実施を親権者が正当な理由なく拒否することはできません。正当な理由なく面会交流を拒否することは親権者の適格性に問題ありとされて、親権者変更調停を申し立てられる可能性もゼロではありません。
育児のサポート体制の有無
育児のサポート体制がどれだけ整っているかも非常に重要な要素です。調停や裁判においても、子育てのサポート体制の有無が親権の判断材料となります。
たとえば、仕事が忙しくてもご自身の両親が子育てを手伝ってくれるなら親権を獲得しやすいといえます。また、ご自身の両親が資金を援助してくれて、仕事をしなくても子育てに集中できる環境がある場合も、親権は獲得しやすいでしょう。
反対に、仕事が忙しくて育児に充てられる時間が少なく、さらに周りに育児をサポートしてくれる環境がない場合は親権争いで不利になる可能性があります。
離婚時の親権争いで母親が負けた事例
ここからは、実際の裁判例で母親が親権争いで負けた事例をいくつか紹介します。父親が親権を獲得する裁判例では、「母親が親権者として不適格」「父親のほうが監護実績が多い」といった背景が見られました。
千葉県で子どもを連れ出し5年以上別居した母親が父親を訴えた事例
年に約100回もの面会交流を提案したことでニュースとなり注目を浴びた、本判決まで5年以上子どもを連れ出して一緒に暮らした母親の裁判例です。本裁判は最高裁判所への上告が退けられて父親の逆転敗訴が確定したものの、地裁では父親が勝訴して親権を獲得している背景から、父親が親権を勝ち取るうえで重要なポイントが審理されたとして弁護士にもよく取り上げられています。
本裁判は、母親が父親に無断で当時2歳4か月の長女を連れ出し、後に母親が父親を相手取って親権や離婚について争ったものです。
千葉家裁でおこなわれた第一審では、父親側からの「母親に年100日程度の面会交流を認める」「電話交流も毎日でも問題なし」といった積極的な提案が評価され、「父親が親権者でも、長女は両親からの愛情を離婚後も受けられる」と判断されました。
面会交流を積極的に提案し離婚後も親同士で有効的な関係を築こうとする姿勢について、欧米などで採用される親権の基準である「フレンドリーペアレント」の考え方を、千葉家裁が適用したとされています。そのため、日本においては非常に珍しい裁判例であると言えるでしょう。
とはいえ、続く控訴審にて母親側がこれまで長女を育ててきた監護の継続性を主張し、東京高裁も「監護や子の意思などと比較して、面会交流を過度に重視するのはふさわしくない」と指摘しました。結局父親側が負けることになりましたが、仮に極度に面会交流に消極的だと、母親でも親権争いで不利になる可能性を示した事例となっています。
参考:産経新聞「「同居の妻に親権」確定 年100日面会提案の夫敗訴 最高裁」
母親の面会交流拒否や育児放棄が見られた事例
離婚時に母親が親権者になったものの、母親側が面会交流を拒否し始め、加えて育児放棄も見られるようになった事例です。
とくに育児放棄の面では、「子どもの住む自宅がゴミ屋敷みたいになっている」「子どもが深夜に出歩き、不登校気味だった」といった状況が近隣住民や学校などから報告され、一時的に児童相談所が子どもを一時保護するまでにいたりました。父親が親権者変更調停を申し立てた後に審判まで進み、母親から父親への親権者変更を認める判決が下されています。
本事例は、育児放棄や面会交流拒否などの親権者としての不適格な行為が見られると、たとえ母親であっても親権者としての適格性が問われ、親権者変更の判断が下される可能性を示しています。
参考:「育児放棄の母親から父親へ親権者変更が審判により認められた事例【横浜市港南区の弁護士離婚相談】上大岡法律事務所」
婚姻中・離婚後で実際に子どもを養育していた父親に親権が変更された事例
福岡高裁平成27年1月30日の判決にて、親権者であった母親から父親に親権が変更された事例です。親権者変更審判にて親権者変更は却下されたものの、抗告後に父親を親権者として認めています。本裁判の流れは次の通りです。
- 離婚時に母親を親権者とする旨に同意していたが、母親側の不貞行為などが原因で母親に親権が渡ることを父親が拒否した
- 協議の末、父方の祖母が母親の生活が安定するまで監護を申し出て母親が承諾し、母親を親権者とする旨で合意して離婚が成立した
- 母親は不動産会社への就職が決まり、住居も確保していた
母親が親権者である旨の合意や生活環境の準備があったにもかかわらず、父親側に親権が認められたのは、以下の監護実績や適格性についての判断があったからだとされています。
- 婚姻期間中は父親が2人の子ども(未成年)の入浴・就寝を見ていた
- 婚姻期間中の母親は食事の面倒を見ていたものの、夜間アルバイトなどの影響で子の幼稚園の欠席人数が多く母親も幼稚園の行事参加に消極的だった
- 平成25年以降は主に父親と父方の祖母が子どもを監護していた
- 親権者であるにもかかわらず母親は保育料を支払っていなかった
- 母親側に監護補助者がいなかった
- 母親は婚姻期間中に不貞行為をしており適格性が疑われる部分があった
母親の不貞行為と子の連れ去りが問題となり父親が親権を獲得した事例
静岡地裁にて父親が監護者に指定され、東京高裁への控訴も棄却されて判決が確定した裁判例です。4歳の女の子の親権を父親が獲得した、非常に珍しいケースだと言えるでしょう。
本裁判における親権者争いの始まりは、母親の不貞行為を父親が咎めた後、母親が子どもを連れて実家に帰って別居が始まったことです。父親が「監護者の指定審判」「子の引き渡し審判」「損害賠償請求」を、静岡地裁に申し立てています。
本ケースでは、夫婦が共働きで監護能力・実績は双方同じくらいと判断されました。それでも父親が親権を獲得したのは、「母親の不貞行為が原因で婚姻関係が破壊された」「母親が父親に無断で子どもを連れ去った」といった点が考慮されたからだと言われています。
不倫は親権判断にそこまで影響しないとされるのが一般的な反面、不倫によって夫婦生活が破綻し子の利益を害したときは親権の適格性判断の材料になるケースがあるようです。また本裁判は子どもの連れ去りという刑事罰に相当する行為が見られたことも、親権判断において大きなマイナスポイントとなりました。
調停や裁判で父親に親権争いで負けないためのポイント
母親が調停または裁判にて、父親に親権争いで負けないためには以下のポイントに留意しましょう。
- 子どもの意思をしっかりと確認する
- 父親が子どもを連れて別居した場合は早めに調停や人身保護請求で対処する
- 面会交流には積極的に応じる
- 離婚するために親権を譲らない
- 家庭裁判所調査官や調停委員にアピールできる「自身の監護実績」や「相手が親権者として不適格」についての証拠を集める
子どもの意思をしっかりと確認する
親権について具体的に争う前には、必ず自分自身から子どもに「両親のどちらについていきたいのか」の意思を確認しておきましょう。親権は子の利益を最優先に考えて決定されるものであり、子どもの意思や気持ちを無視するのは法律・倫理の両面から避けるべきと言えます。
子どもの意思を確認するときは、以下のポイントを意識してください。
- 夫婦どちらかの偏った意見を鵜呑みにして子どもが判断をしていないかを見る(父親側の人々が母親について悪口を吹き込んでいるかなど)
- 「なぜ離婚するのか」「母親についていくとどうなるのか」など離婚に関する事柄を一通り説明して公平に判断してもらう
- 子どもの意思や意見を聞いたうえで自分も「本当に離婚すべきなのか」をもう一度考えてみる
仮に10歳以上の子どもが「父親についていきたい」と答えたときは、調停や裁判でも子の意思が大きく反映される可能性も高くなるでしょう。子どもが父親についていく強い意思を見せたときは、親権獲得に固執しすぎず面会交流やそのほかのサポートで子どもとかかわれないかを模索するのも1つの選択肢です。
父親が子どもを連れて別居した場合は早めに調停や人身保護請求で対処する
父親が子どもを連れて別居した場合は早めの対処が求められます。前述したように、子どもと父親が長く過ごせば過ごすほど監護の実績と継続性が認められてしまいます。
そのため、父親と子どもの別居を放置すればするほど親権争いでは不利です。
父親と子どもの別居に対処する方法は以下の通りです。
- 話し合いをして自宅に帰ってきてもらう
- 子の引き渡し調停・子の監護者の指定調停をする
- 人身保護請求をする
離婚して別居した場合は、子どもは親権者のもとに行きますが、離婚をしていない状態で別居する場合は「子の監護者の指定調停」で監護者を指定して、子どもはその人のもとで生活することになります。
人身保護請求は、子どもの身に危険が及ぶ場合に行います。たとえば「DVをしている父親が子どもを連れて出ていった」という場合です。いずれかの方法で子どもを取り戻して、一緒に生活できるように努めましょう。
人身保護請求とは、法律上の正当な手続きによらず顕著な違法性が認められる子どもの拘束があり、ほかに適切な救済方法がない場合に、子どもの引き渡しを弁護士を通じて求める手続きです。人身保護法にて定められています。
参考:e-Gov法令検索「人身保護法」
面会交流には積極的に応じる
父親と子どもの面会交流には、積極的に応じましょう。裁判所では、子どもは母親・父親ともに交流することが望ましいと考えられているため、面会交流に積極的に応じる親であれば、子どもにとってよい環境ができると判断されやすいです。
また、現状で別居しており母親が子どもと一緒に住んでいる場合でも、積極的に父親との面会交流を決めておくのがよいです。離婚後の面会交流に前向きであることの証明にもなりますし、離婚をしても関係性が円満なままで子どもにストレスを与えにくくなると判断してもらえるためです。
反対に、母親は面会交流に非協力的で、父親が面会交流に前向きだと親権争いで不利に働く可能性が出てきます。夫との関係性が悪化していると「親権を得たら面会交流なんてしたくない」「一切子どもとかかわらせたくない」という気持ちにもなるかもしれませんが、基本的に親の都合で面会交流を拒否することはできません。
面会交流によって父親から子どもへの暴力行為や連れ去りが懸念されるときは、面会交流の制限・停止に向けて動きましょう。正当な理由があってそれを証明できるなら、面会交流を拒否しても親権争いで不利になることはないと思われます。
離婚するために親権を譲らない
離婚成立を優先させすぎないことも大事です。中には「親権はほしいけど早く離婚したいから諦めてしまった」「離婚を成立させていち早くDVやモラハラから逃げるために親権を譲ってしまった」という人もいます。また、親権者は離婚後も変更できるため「とりあえず離婚だけして親権は後で取り返す」という考えの人もいるでしょう。
しかし、離婚後に子どもの親権者は簡単に変更できません。すでに離婚して子供が父親のもとで過ごしている状態から、親権者が変わり子どもの生活環境が変わるというのは、子どもの福祉に好ましくありません。
そのため、たとえ離婚前にたくさん育児をしてきた母親でも、離婚後だと親権者変更の裁判で負けてしまう可能性も十分考えられます。
このような事態を避けるためにも、たとえ「夫からいち早く離れたい」「すぐに離婚したい」という考えがあっても、親権は譲らないようにしましょう。夫と一緒に過ごしたくない場合は、子どもと一緒に別居をすることをおすすめします。
夫と離婚の話し合いをしたくない場合は、弁護士に依頼して代理してもらうことも可能です。弁護士は離婚の手続きや、離婚条件のアドバイス、親権獲得のアドバイスなどもしてくれるので、離婚を円滑に進めたいならぜひ検討してみてください。
家庭裁判所調査官や調停委員にアピールできる「自身の監護実績」や「相手が親権者として不適格」についての証拠を集める
離婚裁判や離婚調停で、夫婦の意見が食い違うケースは少なくありません。とくに子育ての実績がある方ほど親権を獲得しやすいため「自分の方が子育てをしている」と意見が食い違うケースは非常に多いです。
証拠がないと、たとえ自分の方が本当に育児をしていたとしても、親権を獲得できないリスクが発生してしまいます。
そのため、今後の調停や裁判に備えて、監護実績をアピールできる証拠を作っておきましょう。
写真や動画など、育児を証明する直接的な証拠がなくても、育児の記録をした日記でも問題ありません。具体的に育児の内容を記録してください。夫からDVやモラハラを受けている場合も、日記が証拠になります。またDVやモラハラの証拠を示せれば、離婚の際に慰謝料を請求しやすくなります。
母親が子どもを連れて別居する際の注意点
母親は子どもを連れて別居することで、監護実績を作れますし、監護の継続性によって親権を認められやすくなります。離婚をする際は母親は一人で別居するのではなく、子どもを連れて別居したほうが親権判断において有利に働きやすくなります。
ただし、別居をすることで問題が発生することもあるので、以下の注意点も確認しておきましょう。
- 別居前に子どもの意向を確認する
- 合意なしで子どもを連れ去った場合は違法になる
- 合意なしの連れ去りでも違法にならないためには条件がある
- 父親に婚姻費用を請求する
別居前に子どもの意向を確認する
別居する前に子どもの意向を確認することも大事です。別居をすることで子どもの学校が変わってしまうこともありますし、それに伴って友達と別れることもあります。
そのため、これらの要因によって子どもが母親を嫌いになってしまうことも考えられます。特に子どもが小学校高学年にもなると、子どもの意思が親権争いにも響きやすくなってきますし、親権を得られたとしても嫌われてしまった子どもと過ごし続けるのは悲しいものです。
子どもを連れて別居する場合は、まずは本人の意思を確認しましょう。子どもが別居を拒否した場合はあきらめましょう。
合意なしで子どもを連れ去った場合は違法になる
父親の合意を得ないまま子どもを連れ去ると違法になる可能性があります。夫婦には協力義務・同居義務などさまざまな義務があります。父親の合意を得ないまま子どもを連れ去ってしまうと、これらに違反してしまい慰謝料を請求される恐れがあります。
また、子どもが嫌がっているのにも関わらず、父親の合意なしで無理やり連れて行った場合は、実の親子であっても「未成年者略取及び誘拐罪」に該当してしまう可能性も捨てきれません。家族内の問題でもあるため、刑事事件になる可能性は低いでしょうが、可能性はゼロではないと考えたほうが良いでしょう。
合意なしの連れ去りでも違法にならないためには条件がある
別居する際は、必ずしも父親の合意が必要というわけではありません。以下のケースであれば、父親の合意を得ずに別居しても違法になりません。
- 父親が子どもに虐待をしている
- 父親からDVやパワハラを受けている
- そのほか子どもの教育上不適切な環境になっている
つまり「父親といると危険」というような、れっきとした理由が必要です。単純に「父親が嫌いだから」「一緒にいたくないから」というのは理由にはならないため、違法になる可能性があります。
夫に婚姻費用を請求する
夫婦が別居をしたときに、収入が少ない方は収入が多い方に対して婚姻費用を請求できます。夫婦には協力義務・扶養義務というのがあるため、婚姻関係にある以上、別居したとしても夫婦は同等の生活を送らなければいけません。婚姻費用とは夫婦が同等の生活をするために支払う費用です。
そのため、別居をして夫の方が収入が大きい場合は、妻は婚姻費用を請求できます。
しかし、別居というのは同意を得たとしても「勝手に出ていった」というイメージが強く、夫側からすれば「自分の都合で出ていったのに費用も払わないといけないなんて納得できない」と、支払いに応じないケースも多いです。
別居をすると新生活も始まって忙しいこともあり、婚姻費用の請求手続きは簡単ではありません。そのため、弁護士に依頼して手続きを代行してもらいましょう。弁護士が代行することで、夫に対してプレッシャーを与えられて、婚姻費用を支払ってもらいやすくなります。
親権争いがある場合は、離婚に強い弁護士に相談を
これまで紹介しているように、別居をする場合は違法になるケースがあるほか、婚姻費用についても考える必要があるなど、離婚というのは親権争いだけに限らず非常に複雑です。
離婚する場合は、財産分与をしたり、相手に離婚の原因がある場合は慰謝料を請求したりと、お金が絡むことが非常に多いです。個人の判断で離婚を進めると、財産分与で不利になったり、慰謝料が請求できなかったりと、損をしてしまうこともあります。
そのため、離婚をする際は弁護士に相談することをおすすめします。離婚の際に弁護士に依頼すると以下のようにさまざまなメリットが生まれます。
- 親権を得やすくなる
- 財産分与で有利になる
- 慰謝料請求の額や養育費の額を増やせる
- 婚姻費用を請求しやすくなる
- 離婚に関するさまざまな手続きを代行してもらえる
- 離婚に関する相談ができる
弁護士のなかには「親権争いの実績あり」「離婚全般に強い」といった、親権争いを始めとする離婚分野に精通した事務所が存在します。親権争いがあるときは、親権関係に強い弁護士への相談を推奨します。
無料で相談できる場合もあるので、ぜひ検討してみてください。当サイト「ツナグ離婚弁護士」なら、親権関係に強い弁護士を都道府県別に無料検索できます。ぜひご活用ください。
まとめ
本記事で紹介したように母親が親権争いで負けてしまうケースはあります。特に母親が虐待・育児放棄をしていたり、育児の実績がなかったりする場合は親権争いでは不利になるでしょう。
しかし、離婚時の親権争いは「母性優先の原則」によって基本的には母親が有利です。さらに日本では一般的に母親の方が育児・家事をする期間・割合が多いこともあり、おおよそ9割ものケースで親権争いは母親が勝っています。
親権争いはさまざまな要因・事情が絡むため、一概には言えませんが、一般家庭並みに家事・育児をしており、虐待や育児放棄など子どもにとってマイナスになるようなことをしていない場合は、母親の方が親権を得やすいと考えて良いでしょう。
「親権を得られるかどうか不安」「絶対に親権を渡したくない」と考えているなら、弁護士に相談するのも一つの手です。弁護士に相談すれば、親権を得るための立ち回り方を教えてもらえるだけでなく、財産分与や養育費に関することも有利に進められるでしょう。
離婚して母親が親権に負ける場合に関するよくある質問
共同親権が始まるとどうなる?
共同親権(離婚後も父母それぞれが子どもの親権を持つ制度)が始まったとしても、日常の行為(一緒に住む、教育するなど)については「監護親」が単独で決定できるとされています。とはいえ共同親権がスタートすると以下の事態が想定されるため、一度目を通しておくことをおすすめします。
- 離婚時の親権争いが柔軟になり親権争いを回避する方法が増える(単独親権を求める相手とのあらたな争いになる可能性あり)
- 別居した側の親も以前より子どもの育児にかかわりやすくなる
- 面会交流が実施されやすくなる
- 養育費の支払いが促進される
- DVやモラハラ、子どもへの虐待から逃げづらくなるリスクが懸念される
- 親権者それぞれが異なる主張をおこない子どもの利益を害する可能性がある
2025年5月時点では、2026年5月までに共同親権が開始される予定です。共同親権が導入された後は、離婚時に単独親権と共同親権のどちらにするかを選択することになります。
家庭裁判所の調査官の調査はどのようにおこなわれる?
一般的な離婚調停・裁判では、夫婦の主張をもとに進行・判断をします。しかし、子どもに真意を確認しなければ親権の判断が難しい、子どもの意思が親権に大きく影響するというケースでは、
家庭裁判所の調査官が、事実を確認することがあります。
極端な例を言えば、調停にて夫婦がどちらも「相手が子どもに対してDVをしている」と発言している場合、親権者の判断を誤ってしまうと子どもの福祉に多大な影響を与えかねません。
このような事態を避けるために、以下のような調査が行われます。
- 子どもの監護状況を調査する
- 子どもの意向を調査する
子どもの監護状況を調査する
子どもの監護状況、つまりどれだけ子どもの世話をしたのかなどを調査します。離婚調停・裁判では「私の方が家事や育児をしている」と言い合いになることも少なくありません。
このような事態を避けるため、親・子どもとの面談のほか、学校や保育園・幼稚園での調査などを行い、監護状況の実態を確認します。
子どもの面談をする際は、子どもを家庭裁判所へ連れていく場合もありますし、調査員が家に訪問する形で行われることもあります。
子どもの意向を調査する
子どもの意向、つまり両親が離婚したときにどちらについていきたいかを調査することもあります。
明確な基準はありませんが、おおむね子どもが10歳以上なら「意向調査」といって、子どもの意思を確認します。もちろん、発言がすべて子どもの意思とも限らないことも考慮し、発言の背景も考慮したうえで調査を行います。
10歳未満の子どもは判断力があるとは言えない年齢です。そのため「心情調査」といって、子どもの意思ではなく心情を読み取ったうえで意向を調査します。
このようにして調査した内容をもとに、調停・裁判は進められていきます。
なお、調査内容が必ずしもご自身に有利になるとは限りません。そのため、離婚調停・裁判をする際は、弁護士に相談して有利な立ち回りについて教えてもらうと良いでしょう。
親権争いで負けた母親が取るべき子どもへの対応は?
親権争いで母親が負けたときでも、子どもへの対応としてするべきことはあります。
面会交流の取り決めを行う
親権を失ったとしても、子どもと離れて暮らす親には面会交流権があります。面会交流権とは、子どもと離れて暮らす親が、子どもと会う、プレゼントを贈るなどして、親子の交流をする権利です。
しかし、離婚をすると「子どもと会わせたくない」「面会交流のために元配偶者と会いたくない」というトラブルも起こり得ます。そのため、事前に面会交流については内容を決めておきましょう。
主に決めておくべきことは以下のとおりです。
- 面会交流の頻度や日時
- 面会の場所
- 子どもの引き渡し方法
- 学校行事の参加の可否
- プレゼントの可否
養育費の支払いを行う
親は子どもを養育する義務があります。これは親権を持っていない親でも同様です。そのため、親権者は、親権を得られなかった非親権者に対して養育費を請求できます。
つまり、母親が親権を得られなかった場合は、父親が母親から養育費を受け取ります。養育費は男性が女性に払うものではなく、非親権者が親権者に払うものなので間違えないようにしましょう。
養育費の額は子供の数、非親権者の収入などを参照して夫婦で相談しながら決めます。「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について」では、養育費の大まかな目安を算出できるので、ぜひ活用してください。
離婚時に親権者を決定する流れは?
離婚時に親権者を決定する大まかな流れは以下のとおりです。
- 夫婦で協議する
- 離婚調停を申し立てる
- 離婚裁判を起こす
夫婦で協議する
離婚をする際は必ず親権者を決めなければいけません。離婚届には親権者を記入する欄があり、18歳未満の子どもがいる場合は親権者を決めなければ離婚届を受理してもらえないためです。
そのため、離婚時に18歳未満の子どもがいる場合は、どちらが親権を得るのかまずは夫婦で相談して決めます。
これまで「母性優先の原則」や「監護実績」など、親権を得るために重要な要素を紹介しましたが、それらは夫婦の話し合いで解決できなかったときに参照されるものです。つまり、夫婦の話し合いによって親権を決められるなら、たとえ子育ての実績がなくても問題ありません。
離婚調停や裁判は時間や手間がかかるため、夫婦の協議によって離婚できるに越したことはありません。話し合いによってスムーズに親権争いを解決したいなら、弁護士に相談することも検討しましょう。
弁護士に相談すれば、裁判をした場合どちらが親権を得られるのか、どうすれば親権を得られるのか、どのように話し合いを進めるべきなのかなどを提案してくれます。話し合いで解決できなかった場合も、弁護士がいれば離婚調停や離婚裁判を有利に進められるでしょう。
離婚調停を申し立てる
話し合いで親権が決まらなかった場合は、離婚調停を申し立てます。離婚調停とは家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いをすることです。これまでの監護実績や今後の育児のサポート体制などを考慮して、2人にとってより妥当な解決方法を調停委員とともに探します。
夫婦が直接話し合いをする必要はなく、調停委員が仲介に入って話し合いをすることが可能です。そのため、夫婦の関係が大幅に悪化し「顔も見たくない」という状態でも健全に話し合いを進められるようになっています。
また、離婚調停では子どもの意思を確認するために、家庭裁判所の調査官が調査をすることもあります。調停が成立した場合は親権者が決まり離婚を進められるようになります。
離婚裁判を起こす
調停が不成立となった場合は、裁判を申し立てることになります。監護実績などの事情を踏まえたうえで、どちらが親権者になるのか裁判所が決めます。
話し合いの段階は終了しているため、裁判によって判決が下されたら基本的には従わなければいけません。
しかし、納得がいかない場合は、判決文が送達された翌日から2週間の間に控訴、つまり再度審理を申し立てられます。
なお、離婚裁判をする場合は特に弁護士に依頼することをおすすめします。証拠の集め方をアドバイスしてもらえたり、書面の作成をしてもらえたりして、親権を獲得できる可能性が高くなります。相談にも乗ってくれるので、離婚時の不安を解消できるでしょう。