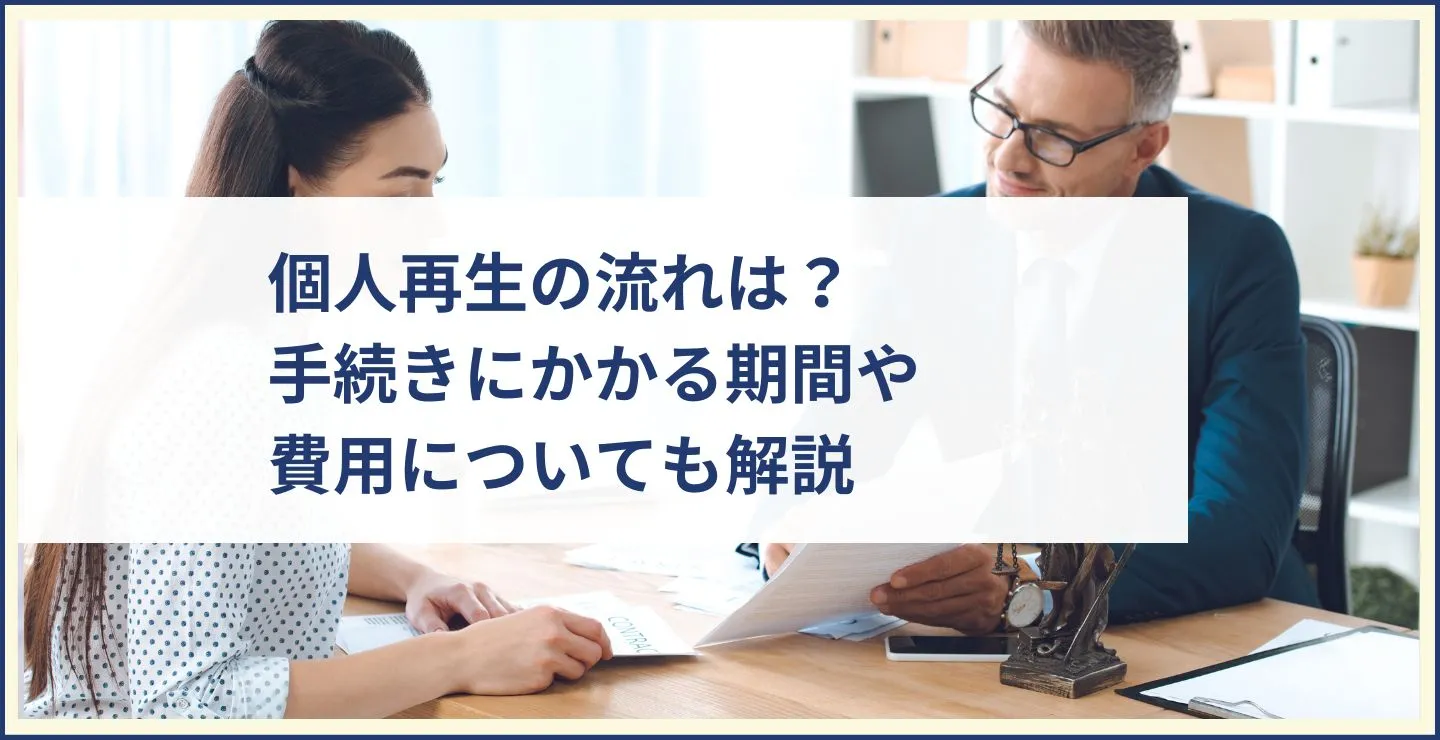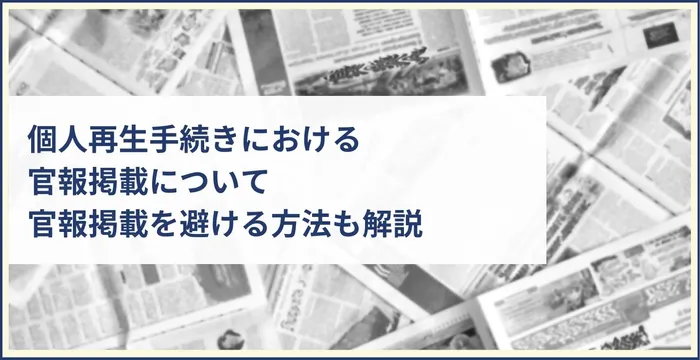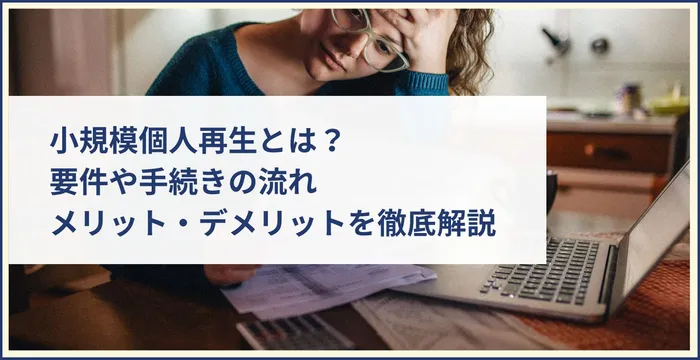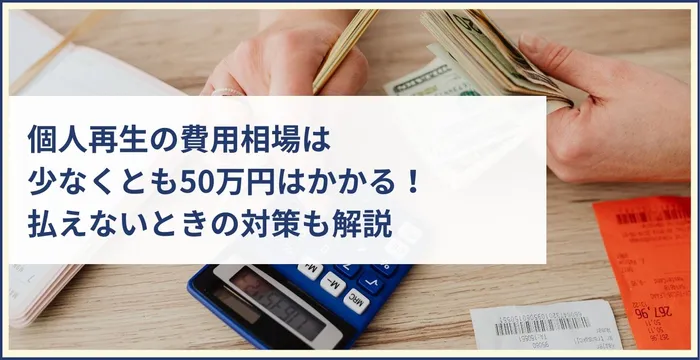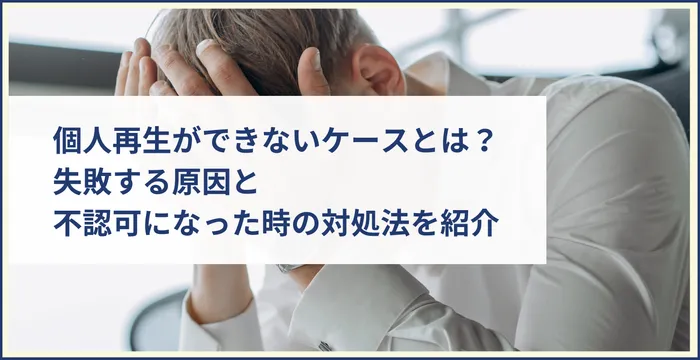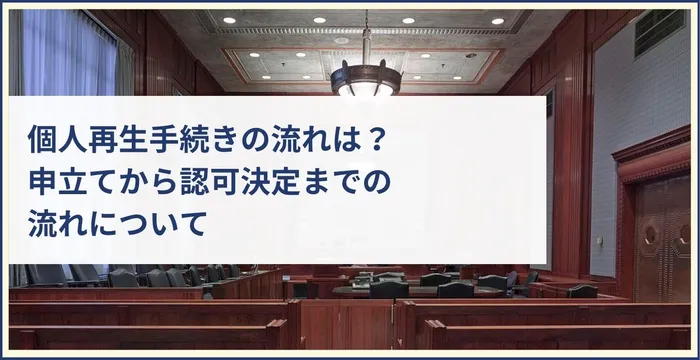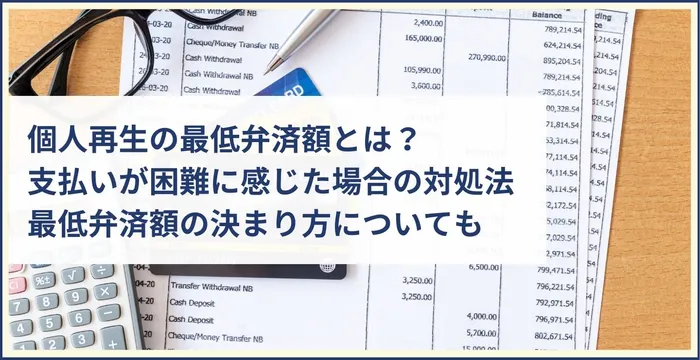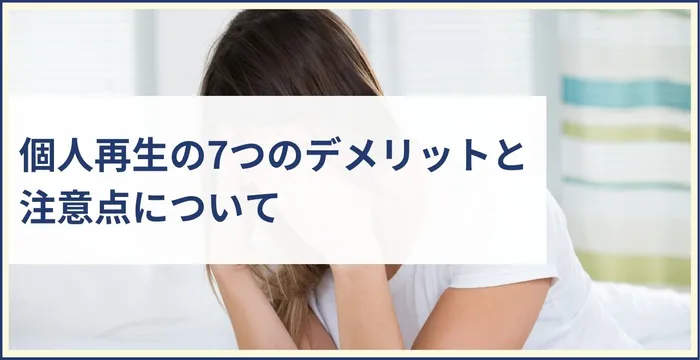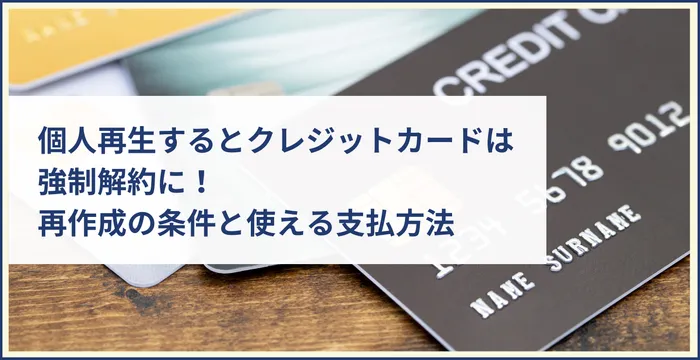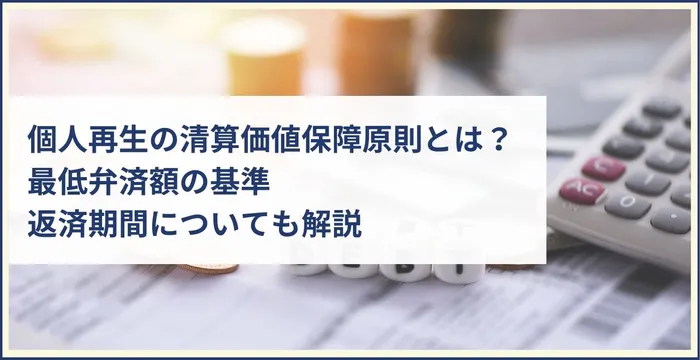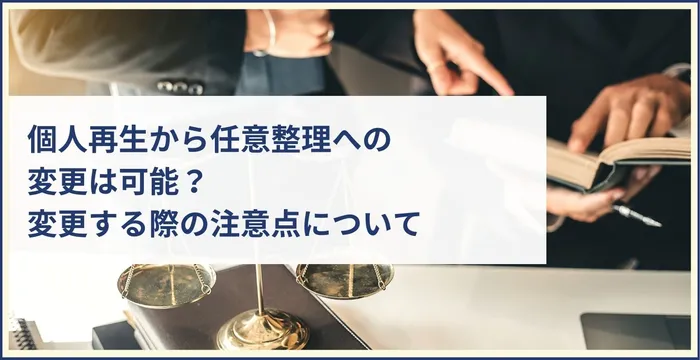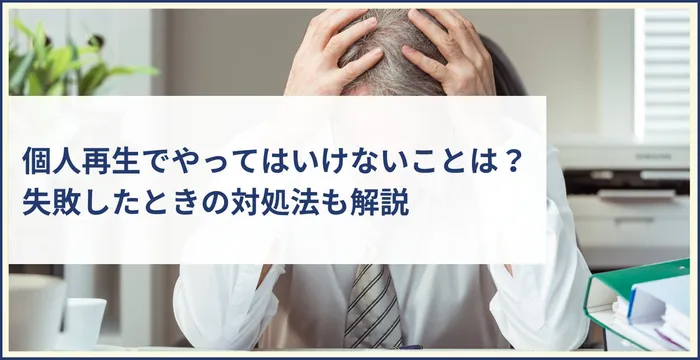個人再生の流れ【個人再生の申立て準備~申立て:3~6ヶ月程度】
個人再生の申立て準備から裁判所へ個人再生を申し立てるまでにかかる期間は、3~6ヶ月程度が目安です。
- 弁護士に相談・契約
- 債権調査(引き直し計算)
- 申立書類の準備
- 裁判所に個人再生を申し立てる
ここからは、それぞれの手続きの内容について1つずつ詳しく解説していきます。
1.弁護士に相談・契約
まずは、個人再生の実績が豊富な弁護士に相談します。相談の場では、借入総額や借入社数、裁判になっているかなど、現在の状況を包み隠さず伝えましょう。
また、個人再生の進め方や費用、手続きにかかる期間などについて何か分からないことがあれば、その場で必ず質問するようにしてください。弁護士によって相性があるため、複数の事務所に相談することをおすすめします。
相談するうちに、「この人に手続きを任せたい」と思える弁護士が見つかったら、正式に委任契約を結びます。契約の際は契約書の内容をしっかりと確認し、不安や疑問点があればその場ですぐ確認するようにしてください。
受任通知の送付
弁護士に個人再生の手続きを正式に依頼すると、弁護士が全ての債権者に対して「受任通知」を送付し、取引履歴の開示請求を行います。受任通知とは、弁護士が債務者の代理人になったことを債権者に通知するための文書のことです。
受任通知を受け取った債権者は正当な理由がない限り、債務者に対して直接返済を求めることができなくなります。そのため、受任通知が送付された後は債権者からの督促や借金の返済が一時的にストップし、代理人となった弁護士が債権者とやり取りを行うのが一般的です。
取引履歴は開示請求をしてから1ヶ月程度で債権者から回答が届くため、弁護士はこれをもとに「引き直し計算」を行い、現在の借金総額を確定させます。引き直し計算とは、現在の利息制限法に基づく金利で利息を改めて計算し、過払い金がないか調査することです。
過払い金が発生している場合は、弁護士が債権者に対して過払い金の返還を請求します。特に、2010年以前に借り入れた場合は過払い金が発生している可能性が高いです。
過払い金の金額によっては、現在の債務と相殺されて支払いの義務がなくなる可能性もあります。そのため、過払い金がないか確認のみを依頼するのもおすすめです。
2.債権調査(引き直し計算)
債権調査とは、個人再生や他の債務整理手続きに先立って、債務の正確な金額や内容を把握するための重要な作業です。具体的には、貸金業者から開示される取引履歴をもとに、15〜20%の法定金利に基づく引き直し計算を行い、実際の借入残高を確定します。
取引履歴は、1〜3ヵ月で開示されるのが一般的です。この作業によって、過去に払い過ぎていた利息、いわゆる過払い金が判明した場合には、過払い金返還請求も行われます。
また、弁護士から受任通知を送ると、債権者から「債権調査票」などの書類が届きます。債権調査票には、現在の借金の残高や取引の内容が書かれており、現在どれだけ借金が残っているかを正確に確認するために重要です。
調査の結果、思っていたより借金が多かったり、逆に少なかったりすることがあり、その場合は手続きの内容を見直す必要が出てくることもあります。さらに、住宅ローンを抱えている人が「住宅ローン特例」を利用する場合は、住宅ローンのある銀行などにも、個人再生手続きを行うことをあらかじめ知らせておく必要があります。
3.申立書類の準備
弁護士に個人再生の手続きを依頼したら、次に個人再生の申立てに必要な書類を準備します。個人再生を弁護士に依頼した場合でも、下記4つ書類は基本的に自分で用意しなければなりません。
- 役所で取得する書類
- 居住関係の書類
- 収入・勤務先関係の書類
- 財産関係の書類
ここからは、それぞれで必要な書類を具体的にみていきましょう。
【役所で取得する書類】
| 役所で取得する書類 |
概要 |
| 住民票 |
世帯全員・本籍地の記載があり、マイナンバーが記載されていないもの |
| 税金、健康保険、国民年金などの滞納書面 |
滞納がある場合の額や支払い計画の確認に必要 |
| 課税証明書 |
直近2年分必要 |
| 年金、児童手当などの通知書 |
受給している場合 |
個人再生に限らず、税金や健康保険料などの支払いは免除されません。そのため、滞納がある場合は役所と協議し、支払い計画を立てる必要があります。
滞納があると手続きに影響を与える可能性があるため、早めに役所に相談しましょう。マイナンバーカードを活用すれば、住民票や課税証明書はコンビニでも取得可能なので、時間がない方はぜひ活用してみてください。
【居住関係の書類】
| 居住関係の書類 |
概要 |
| 賃貸借契約書 |
借りている物件の契約内容を証明 |
| 住宅使用許可書 |
同居人が契約している賃貸物件に住んでいる場合に必要 |
| 光熱費の支払い方法が分かる通帳や領収書 |
実際にその住所で生活していることを証明するのに必要 |
| 住宅ローンの契約に関する書類 |
住宅ローン特則を利用する場合に必要 |
個人再生では、賃貸契約者が本人でない場合、「住宅使用許可書」を同居人(契約者)に作成してもらう必要があります。これは、実際にその物件に居住していることを証明するためです。
また、持ち家がある場合、ローン返済中であっても「住宅ローン特則」を利用することで、家を手放さずに手続きを進められます。そのためには、下記の書類を用意し、裁判所に住宅の資産価値やローンの支払い状況を正しく報告することが重要です。
- 住宅ローンの契約書
- 保証委託契約書
- 住宅ローンの返済計画表
- 不動産登記事項証明書
【収入・勤務先関係の書類】
| 収入・勤務先関係の書類 |
概要 |
| 給与明細書 |
直近2~3ヶ月分必要 |
| 源泉徴収票 |
直近2年分必要 |
| 退職見込額証明書または退職金規程(就業規則)のコピー |
退職金制度の有無や見込額を確認するために必要 |
| 確定申告書 |
自営業の場合 直近2年分必要 |
| 積立金の証明書 |
財形貯蓄や社内積立などがある場合に必要 |
| 同居人の収入に関する書類 |
同居人が収入を得ている場合に必要 |
個人再生では、安定した収入があり、返済を継続できることを裁判所に証明する必要があります。そのため、給与明細や源泉徴収票、自営業の場合は確定申告書の控えなどが必要です。
また、個人再生では退職金をまだ受け取っていなくても、「退職金の見込額」は財産として扱われます。これは、仮にその時点で退職すれば受け取れるであろう金額が、債務者の資産として評価されるためです。
ただし、退職金は確実に受け取れる保証がないため、全額が清算価値に含まれるわけではなく、通常は「退職金の見込額の8分の1」が財産として計算されるケースが多いです。
特に、退職の予定がある場合や退職金額が大きい場合は財産評価に大きく影響するため、「退職金規定」や「退職金見込額の証明書」を準備し、正確な金額を把握しておくことが重要 です。
【財産関係の書類】
| 財産関係の書類 |
概要 |
| 過去2年分の全ての預金通帳またはウェブ明細の印刷 |
預金がいくらあるのか、収入や支出の流れを確認するために必要 |
| 保険証券・解約返戻金計算書のコピー |
実際は解約しなくても、保険に加入している場合は必要 |
| 自動車検査証 登録事項証明書 車の購入価格がわかる書類 |
自動車を所有している場合 車の市場価値や所有者を確認するために必要 |
| 不動産登記簿謄本 固定資産評価証明書 査定書 |
不動産を所有している場合に必要 |
| 株・証券・投資信託の取引明細 |
株や投資信託などの金融資産も申告が必要 |
個人再生では、すべての財産を裁判所に正確に申告することが求められるため、正確に把握しておくことが重要です。不動産や車を所有している場合は、固定資産税の評価証明書や査定書を取得し、現在の市場価値を証明できるように準備しましょう。
また、株や投資信託などの金融資産も対象となるため、証券会社から取引明細を取得する必要があります。
3.裁判所に個人再生を申立てる
申立書類の準備が終わったら、住所地を管轄する地方裁判所に必要書類を提出し、個人再生を申立てます。申立ての際には申立手数料として以下の書類を申立書に添付してください。
また、個人再生では再生手続き開始時と認可決定時に官報への掲載がありますが、それにかかる費用も申立て時にあらかじめ支払っておく必要があります。
個人再生の流れ【裁判所の手続き~認可:4ヶ月~1年程度】
個人再生の申立てから再生計画が認可されるまでにかかる期間は、4ヶ月~1年程度が目安です。
- 申立後、裁判所の手続きの開始
- 再生委員の選任と面談
- 履行テストの開始
- 再生手続き開始決定
- 債権届出・異議申述
- 再生計画案の作成・提出
- 再生計画認可決定
履行テストが実施されない場合は6ヶ月以内で認可が下りるケースが多いですが、履行テストが実施される場合は手続きが6ヶ月程度長引くため、認可が下りるまでに1年程度かかるケースもあります。ここからは、それぞれの手続きの内容について1つずつ詳しく解説していきます。
1.申立後、裁判所の手続きの開始
裁判所に個人再生を申立てた後、提出した書類に不備がなければ裁判所での手続きが開始されます。個人再生を申立ててから手続きが開始されるまでは、通常1ヶ月程度かかります。
2.再生委員の選任と面談
申立て先の裁判所や債務者の状況などによっては、裁判所から個人再生委員が選任されるケースもあります。個人再生委員とは、申立人の収入や財産などを調査したり、再生計画案の作成について指示を出したりするために裁判所から選任される人のことです。
個人再生委員は、通常個人再生の手続きに精通した弁護士の中から選任されます。裁判所での手続きが開始されてから1週間以内で選任され、選任されてから約1週間後に個人再生委員との面談が設けられます。
面談では、個人再生委員から申立書に記載されている内容(個人再生申立てに至った事情や収入・財産状況など)について確認されます。
3.履行テストの開始
東京地方裁判所などの一部の裁判所では、個人再生の申立てから約1週間後に「履行テスト」が開始されます。履行テストとは、申立人が再生計画に従って借金の返済を続けられるのか確認するためのテストのことです。
履行テストが開始されたら、再生計画に記載されている毎月の返済予定額を、代理人の預かり口座や個人再生委員が指定した口座に毎月振り込みます。履行テストの途中で支払いが遅れたり、支払いができなかったりすると、3年間返済を続けるのは困難だと判断されます。
すると、再生認可が下りない可能性が高くなるため、履行テストは確実に成功させなければなりません。履行テストの期間は裁判所によって異なりますが、通常は6ヶ月間です。
履行テスト中に十分な支払い能力があると判断された場合は、履行テストが早めに切り上げられることがあります。履行テストが終了した後は、テスト期間中に振り込んだお金から個人再生委員の報酬が差し引かれた残額が返還されます。
4.再生手続き開始決定
再生手続き開始決定は、個人再生の申立てからおおよそ1ヶ月程度で下されます。まず、個人再生委員が申立内容に問題がないかを確認し、その結果を「意見書」として裁判所に提出します。
通常、この意見書は申立てから3週間ほどで作成されます。裁判所はその意見書をもとに審査を行い、個人再生の手続きを進めてもよいと判断されれば、「再生手続き開始決定」が出される流れです。
この決定が出ると、債務者の氏名や住所、そして個人再生の開始決定があったことが官報に掲載されます。官報は一般に広く公開される公的な情報ですが、一般の人が日常的に目にするものではないため、掲載による影響はそれほど大きくありません。
ただし、開始決定に至るまでに手続き上の不備があったり、必要な対応ができていなかった場合には、却下されるおそれもあるため注意が必要です。
5.債権届出・異議申述
再生手続きが開始決定すると、まず裁判所から各債権者に対して「個人再生手続開始決定書」と「債権届出書」が送付され、その後は以下の流れで進んでいきます。
- 各債権者が債権届出書を裁判所に提出する
- 裁判所から債務者の代理人弁護士に債権届出書が送付される
- 「債権認否一覧表」を作成し、提出期限までに裁判所に提出する
- 一般異議申述期間が3週間程度設けられる
各債権者は、債権届出書に記載されている債権が正しいか確認し、再生手続き開始決定から約6週間後までに提出しなければなりません。また、債権認否一覧表 とは、債権届出書に記載された借金の額や内容について、申立人(または代理人弁護士)が認めるかを一覧にまとめた書類のことです。
もし、債権者が過大な請求をしていたり間違った金額を記載していたりする場合は、異議を申し立てて修正を求められます。
6.再生計画案の作成・提出
債権届出書の提出が完了し、債権認否一覧表にも問題がなければ、債務者は代理人弁護士と相談しながら再生計画案を作成します。再生計画案とは、債務者がこれからどのように借金を返済していくかを具体的に示した計画書のことで、下記項目を中心に作成します。
- 返済総額
- 返済方法
- 返済の開始時期
- 住宅ローン特則の利用の有無
再生計画案は、再生手続き開始決定から約3~4ヶ月後までに作成し、裁判所に提出しなければなりません。
提出期限を過ぎてしまうと再生認可が下りず、手続きが途中で終了してしまうため、提出期限は必ず守りましょう。裁判所に提出した再生計画案に問題がなければ、債権者による書面決議・意見聴取が2週間程度行われます。
その際、小規模個人再生手続と給与所得者等再生手続では、認可までの流れが異なります。
| 小規模個人再生手続 |
自営業者やフリーランス、収入が不安定な人向けの個人再生の方法 |
| 給与所得者等再生手続 |
会社員や公務員など、安定した収入がある人向けの個人再生の方法 |
小規模個人再生の場合は、裁判所の認可に加えて債権者の書面決議による同意が必要となります。債権者数の過半数もしくは債権額の2分の1を超える不同意がある場合は再生計画案が否決となり、個人再生は認められません。
給与所得者等再生の場合は債権者からの同意を得る必要がないため、債権者からの意見聴取のみ行われます。
7.再生計画認可決定
提出した再生計画案が債権者に認められた場合は、裁判所が提出された再生計画案通りに返済できそうか判断し、再生計画の認可または不認可を決定します。再生計画認可決定にかかる期間は、裁判所に再生計画案を提出してから1~3ヶ月程度が目安です。
再生計画の認可または不認可が決定すると、約2週間後に氏名と住所が官報に掲載されます。それから約2週間後に再生計画の認可または不認可の決定が確定し、これで個人再生の手続きが終了します。
裁判所から再生認可が下りず個人再生に失敗してしまった場合は、以下の方法で対処するのが一般的です。
- 不認可となった原因を分析・改善してから、再度個人再生を申し立てる
- 自己破産を申し立てる
返済開始:3~5年程度
裁判所から再生計画の認可が下りたら、再生計画案に従って各債権者に対する返済を開始します。毎月返済する場合は、認可の決定が確定した翌月から返済開始です。
返済期間は原則として3年ですが、3年以内に返済するのが難しい事情がある場合は、最長5年まで返済期間の延長が認められる可能性もあります。再生計画案通りに借金を返済できないと、債権者から個人再生の取り消しを申立てられ、裁判所から再生認可を取り消されることがあります。
再生認可を取り消されると免除された借金が復活してしまい、個人再生する前の状態に戻ってしまうため、その場合は自己破産を選択するしかないでしょう。そのため、毎月の返済を確実に行い、計画通りに完済を目指すことが重要です。
ただし、借金の返済が困難になった事情によっては「ハードシップ免責」の適用により、残りの借金の支払い義務が免除される可能性があります。ハードシップ免責とは、債務者に責任のない事情(急病やリストラなど)で返済が困難になった場合に、すでに再生計画の返済総額の4分の3以上の返済が終わっていれば、残りの借金が全額免除される制度のことです。
ハードシップ免責を利用するには一定の条件を満たす必要があります。そのため、もし返済が厳しくなりそうな場合は、早めに弁護士や司法書士に相談し、返済計画の見直しや債権者との交渉を検討しましょう。
個人再生の費用は弁護士費用と裁判所費用で50万~90万円程度
個人再生にかかる費用は弁護士事務所や裁判所によって異なりますが、50~90万円程度が相場です。個人再生にかかる費用には、以下の2つあります。
個人再生の費用は一括払いが基本ですが、弁護士費用の場合は弁護士の裁量で分割払いを認めてもらえる可能性もあります。
弁護士費用(50万~60万円程度)
個人再生の手続きを弁護士に依頼する場合は弁護士費用が発生し、主に下記の3つあります。
弁護士費用は依頼先の弁護士事務所によって異なりますが、総額50~60万円程度と、個人再生にかかる費用の大半を占めます。
| 弁護士費用の内訳 |
概要 |
費用の相場 |
| 相談料 |
弁護士に法律相談をする際に発生する費用 |
1万円程度(1時間あたり) |
| 着手金 |
弁護士に案件を依頼する際に発生する費用 |
30万円程度~ |
| 報酬金 |
依頼した案件が成功した際に発生する費用
|
住宅なしの場合:20万円程度~
住宅ありの場合:30万円程度~ |
弁護士費用は一括で支払うのが原則ですが、一括払いがどうしても難しい場合は分割払いに応じてくれる可能性もあります。
裁判所費用(数万〜25万円程度)
個人再生は裁判所を介して行う手続きなので、裁判所費用が必ず発生します。東京地方裁判所などの一部の裁判所や債務者の状況によっては個人再生委員が選任されることがありますが、その場合は個人再生委員の報酬も発生します。
裁判所費用は申立先の裁判所や個人再生委員の有無によって異なりますが、総額で数万〜25万円程度かかります。費用についての詳細は下記の通りです。
| 裁判所費用の内訳 |
概要 |
費用の相場 |
| 予納金(官報掲載料) |
個人再生を申し立てる際に官報掲載料としてあらかじめ支払う費用 |
13,000円程度 |
| 収入印紙(申立手数料) |
個人再生を申し立てる際に必要な手数料で、手数料分の収入印紙を申し立書に添付して支払う |
1万円程度 |
| 郵便切手(通知呼出料等) |
裁判所から債権者へ通知する際に必要となる郵便切手代で、申立書に添付して支払う |
2,000~5,000円程度 |
| 個人再生委員の報酬 |
15万円~25万円程度 |
裁判所費用は、個人再生の申立て時に一括で支払う必要があるため、分割払いは認められていません。個人再生委員の報酬は申立てが受理されて個人再生委員が選任された後に支払いが発生しますが、通常は履行テストで積み立てたお金から充当されます。
まとめ
個人再生を行えば借金の負担を大幅に減額できますが、個人再生は債務整理の中でも特に手続きが複雑で、費用も時間もかかります。個人再生の手続きには法的な専門知識や経験が求められるため、一般の方が書類の準備や手続きをスムーズに進めるのは困難です。
個人再生を弁護士に依頼すれば、必要な手続きのほとんどを弁護士に任せられるため、手続きにかかる負担を軽減できます。個人再生を検討している場合は、まず個人再生の実績が豊富な弁護士に一度相談してみましょう。
個人再生に関するよくある質問
個人再生のメリット・デメリットは何ですか?
個人再生には、以下のようなメリット・デメリットがあります。
| メリット |
・借金を5分の1程度減額できる
・原則として財産の処分はなく、ローンの支払いが終わっていれば持ち家も車も残せる
・住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンが残っている持ち家も残せる可能性がある
・職業や引越し、旅行などで制限がかからない
・借金の原因が浪費やギャンブルでも手続き可能 |
| デメリット |
・手続きに手間と時間がかかる
・官報に氏名・住所が掲載される
・ローンの支払いが残っている持ち家や車は処分されてしまう可能性がある
・保証人・連帯保証人に返済義務を負わせてしま
・信用情報機関のブラックリストに登録される |
個人再生の手続きで気をつける点は?
個人再生の手続き中や手続き後は、以下のような行動をしないように注意しましょう。
| 手続き中 |
・書類や費用を期限内に提出・納付しない
・特定の債権者だけに返済する
・虚偽の説明をしたり、説明を拒否したりする
・履行テスト中に支払いを怠る
・新たな借金をする |
| 手続き後 |
・返済期限に遅れたり、滞納したりする
・浪費やギャンブル
・収入が下がる転職や退職 |
個人再生後に繰上げ・一括返済はできますか
個人再生後に繰上げ・一括返済することは可能ですが、以下の条件を満たす必要があります。
繰上げ・一括返済によって債権者にデメリットが生じることはないため、債権者に拒否されることは基本的に考えにくいです。ただ、個人再生後にすぐ繰上げ・一括返済を申し出ると、「返済できる余裕があるのになぜ個人再生をしたのか」「財産隠しをしているのではないか」と債権者に疑われる可能性があります。
財産隠しをしておらず、臨時のまとまった収入があって繰上げ・一括返済をする場合でも、当面は再生計画に従って返済を続け、タイミングを見計らって繰上げ・一括返済を申し出た方が賢明です。
債権者から繰上げ・一括返済の合意を得られた場合は、「債権者平等の原則」というルールに従い、全ての債権者が平等になるように返済していかなければなりません。特定の債権者のみの繰上げ・一括返済は、「債権者平等の原則」に反するとして返済総額が増額されたり、認可決定を取り消されたりする恐れがあるので絶対にやめましょう。