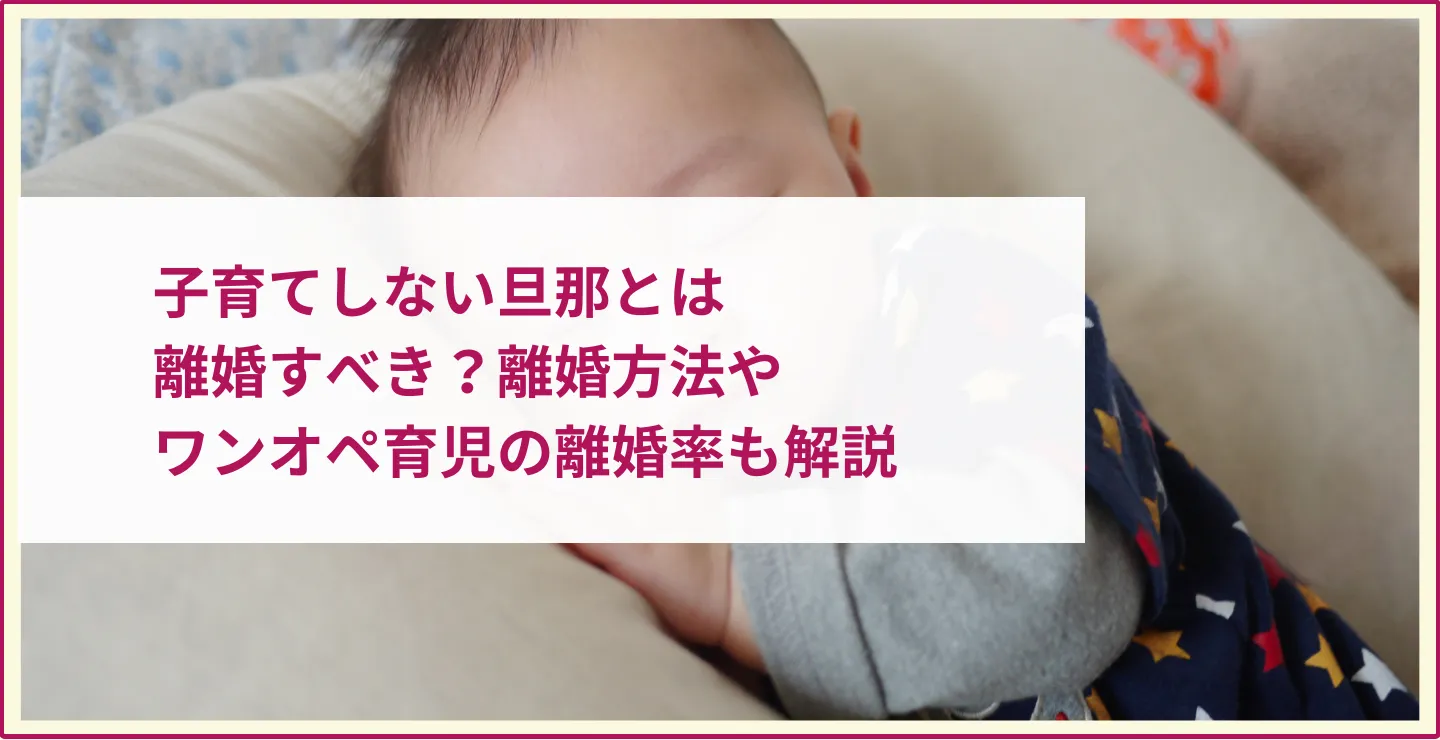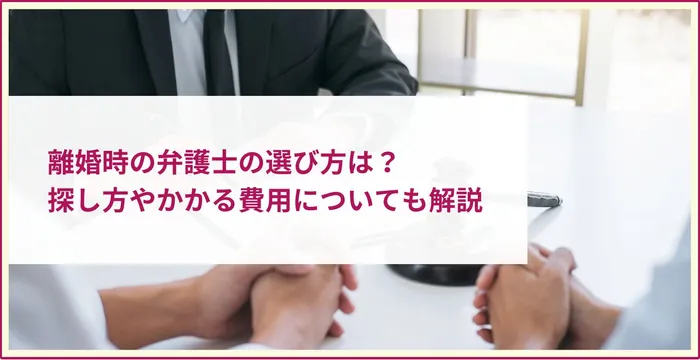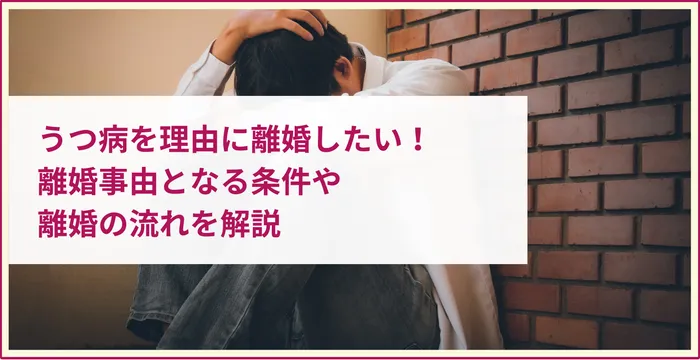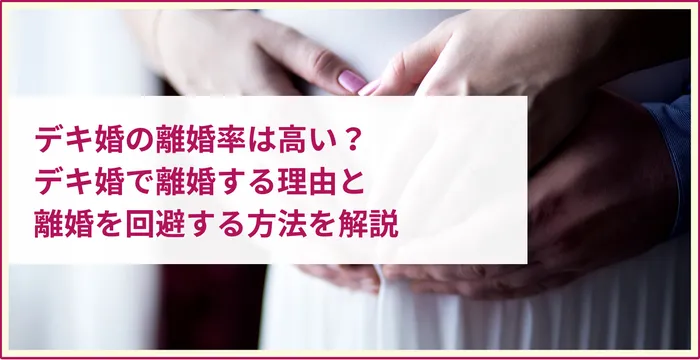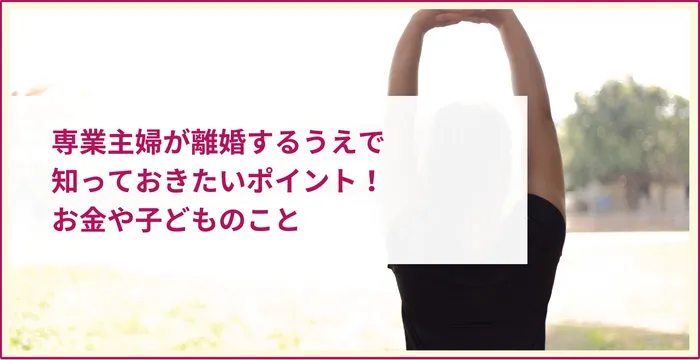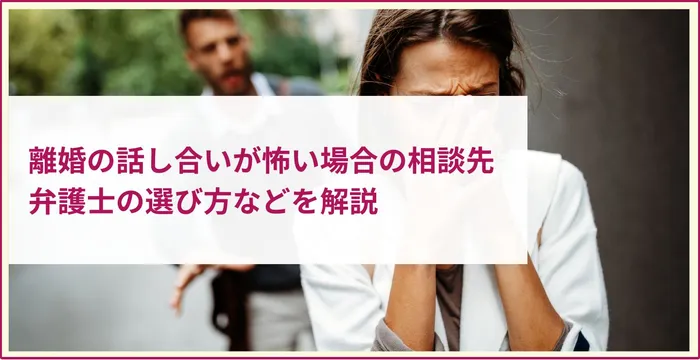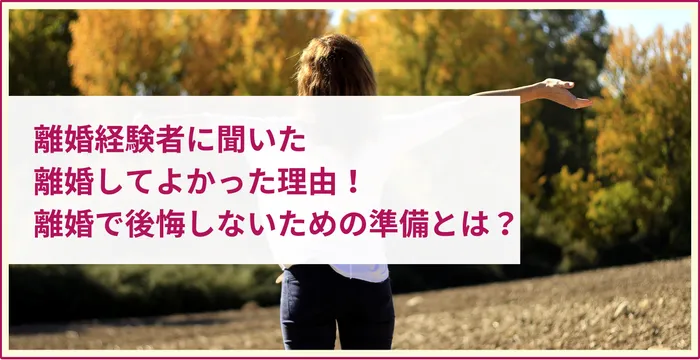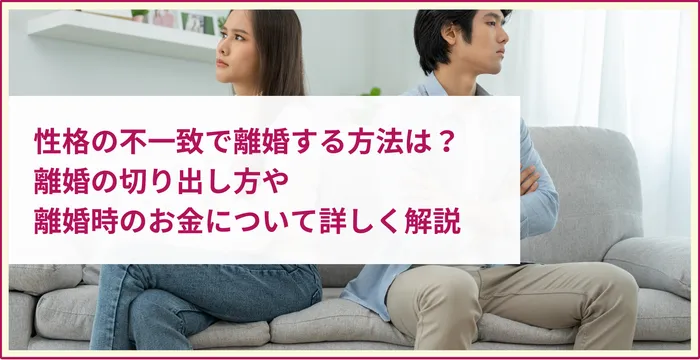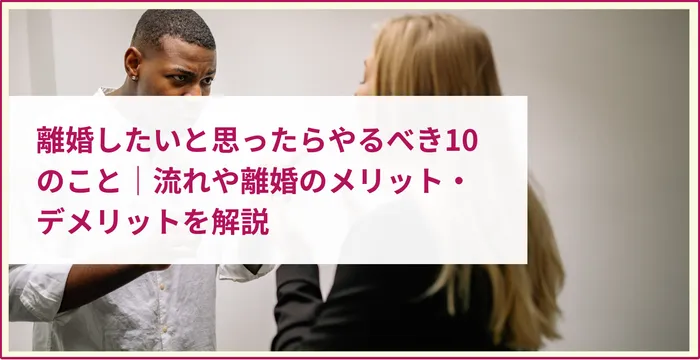子育てしない旦那とは離婚すべき?ワンオペ育児を理由に離婚できるのか
子育てしない旦那と離婚すべきかどうかは、夫婦関係や状況などにもよるため、一概には言えません。
しかし、旦那が子育てに非協力的で改善の見込みもない場合は、ワンオペ育児が離婚の原因になってしまうのも事実です。
子育てしない旦那と離婚する際には、まず離婚協議や離婚調停で話し合いをしましょう。お互いが離婚条件に合意すれば、子育てをしない旦那との離婚が可能です。
もしも旦那が離婚に納得せず裁判に発展した場合、法定離婚事由に該当することを証明しなければ離婚ができません。
次の項目から、ワンオペ育児を理由に離婚する方法について具体的に解説します。
離婚協議と離婚調停では合意があればできる
離婚協議は夫婦で話し合って離婚するかどうかを決める方法です。お互いが合意すれば離婚が成立するため、どのような理由であっても問題はありません。
そのため、旦那と話し合いをした上でお互いが離婚に納得すれば、ワンオペ育児を理由に離婚することが可能です。
夫婦の話し合いだけでは離婚条件がまとまらない場合、家庭裁判所に申し立てて離婚調停を実施する方法もあります。離婚調停は、家庭裁判所の調停委員を通して離婚の話し合いを進める方法です。
離婚調停では、話し合いを進めた上で夫婦の両方が離婚に合意すれば離婚成立となります。
第三者を通して話し合いが進められるため、旦那と直接話をしたくない場合や、別居しながら話し合いをしたい場合におすすめです。
ただし、離婚調停は基本的に1ヶ月に1回のペースで実施されることから、双方の合意がなかなか得られなければ離婚までの日数が長引いてしまいます。
子育てしない旦那と早めに離婚したい場合は協議離婚で説得し、どうしても相手が納得しない場合のみ、離婚調停に進みましょう。
離婚裁判では法定事由に該当する必要がある
子育てしない旦那が調停でも離婚に合意しなかった場合は離婚裁判を起こし、判決によって離婚の可否を決定することになります。
離婚裁判で離婚を成立させるためには、民法第770条の法定離婚事由に1つでも当てはまっていることを証明しなければなりません。
民法で定められている離婚事由は以下の5つです。
| 離婚事由 |
概要 |
| 不貞行為 |
配偶者以外の異性と性的関係を持った |
| 悪意の遺棄 |
夫婦の同居・協力・扶助の義務を正当な理由なく放棄した |
| 配偶者が3年以上生死不明 |
配偶者と連絡が取れず生死不明の状態が3年以上続いている |
| 配偶者が強度の精神病 |
配偶者が夫婦の協力義務を果たせないほどの精神病に陥っており、回復の見込みがない |
| その他婚姻を継続し難い重大な事由 |
DV、モラハラ、浪費による借金、長期にわたる別居など |
ワンオペ育児は法定離婚事由には該当しないため、裁判で離婚成立の判決を得るためには、その他の理由が必要になる可能性が高いです。
ワンオペ育児以外にも旦那に問題がある場合には、法定離婚事由に該当する証拠を集めてください。
たとえば旦那が子育てをせず不倫をしているのであれば、不倫相手とホテルに出入りしている写真やメッセージやり取り、探偵会社の調査報告書などが証拠になります。
ワンオペ育児以外に問題がない場合は、3年以上にわたる長期間の別居をすれば離婚できる可能性が高くなります。長期間の別居は「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されるためです。
裁判に発展しそうなときは、まず法定離婚事由に該当する部分がないかどうかを探し、特になければ別居を経て離婚する方法を検討してみてください。
ワンオペ育児の離婚率は約80%
法務省が公開している「協議離婚に関する実態調査」によると、離婚の際にワンオペ育児の状態だった夫婦の割合は79.9%にも上っています。
夫婦のすべてがワンオペ育児を理由に離婚しているわけではありませんが、割合が高いことから離婚原因と一定の相関性があることが推測されます。
ワンオペ育児の状態になると夫婦の一方のみに負担がかかり、精神的に追い込まれてしまいます。配偶者と育児のことで口論になり、険悪になってしまうことも少なくありません。
また、配偶者との育児に対する認識の違いも、離婚の原因になります。
たとえば、夫は妻に頼まれてオムツ替えやゴミ捨てなどをしており、家事育児に協力しているつもりではあるものの、妻は「頼まないと何もしてくれない」と感じているケースなどです。
ワンオペ育児をきっかけに夫婦間に亀裂が生じ、離婚につながってしまうケースは決して珍しくはありません。
参照:令和2年度 協議離婚に関する実態調査結果の概要|法務省
ワンオペ育児が離婚につながる4つの理由
ワンオペ育児が離婚につながる原因として、主に以下の4つが考えられます。
- 夫に対する不信感が増す
- 精神的・肉体的に疲れ切っている
- 夫との喧嘩が増えてしまう
- 子どものために別れた方がよいと判断した
それぞれの原因について詳しく解説します。
1.夫に対する不信感が増す
本来であれば、子育ては夫婦が協力して取り組むべきことであるのにもかかわらず、 夫が育児から逃げるような姿勢を見せると、不信感が増してしまいます。
妻が助けを求めているのに対して「育児は女性の方が向いている」「自分は仕事をしているから家では休みたい」などと言い、育児に参加しない夫には不信感が募って当然です。
また、言葉にして直接言われなかったとしても、夫の態度や姿勢から価値観の違いが浮き彫りになることもあります。
たとえば夫が「家族のために稼いでいるから疲れている」と言い訳して育児をしない場合、「自分の方が収入が上だから、家事育児は妻の仕事」という価値観を持っていることが透けて見えます。
価値観が違う夫とは、話し合いをしても解決できないことが多いです。むしろ話し合いをすることで価値観の違いがより明確になり、不信感がさらに増すというケースもあります。
夫に対する不信感は、離婚につながる大きな原因の1つです。
2.精神的・肉体的に疲れ切っている
子育て中は睡眠時間の確保が難しい上、子供の命を守るために常に気を張っている状態になります。
そのため、夫が子育てに全く参加せず、頼りにできない状況が毎日続くと、精神的にも肉体的にも疲れ切ってしまうでしょう。
精神的・肉体的に疲れ切ってしまうと、以下のような考えに至り、離婚につながります。
- 実家に帰って両親に育児を手伝ってもらいたい
- 夫がいなければ旦那の分の家事をやる必要がない
- 夫がいない方がストレスなく生活できる
夫が子育てをしない場合は自分の両親に育児を手伝ってもらうという方法もありますが、実家に帰ったり両親を家に呼んだりすることに対し、夫が難色を示すケースもあります。
また、夫と離婚すれば家事の負担が減る上に喧嘩することもなくなるため、肉体的・精神的な疲労から解放されるのではないかと考える方も多いです。
精神的な余裕がなくなると夫への愛情も薄れていき、離婚を決断するに至ります。
3.夫との喧嘩が増えてしまう
ワンオペ育児で妻が大変な状況にあるにもかかわらず、夫が見て見ぬふりを続けているとストレスが溜まります。
ストレスが溜まった末に喧嘩に発展すると、お互いの主張をぶつけ合うだけになってしまうため、冷静な解決が望めません。
また、感情的になっていると育児に関すること以外にも言及してしまい、収拾が付かなくなるというケースもあります。
喧嘩が何度も繰り返されると徐々に夫婦関係の溝が大きくなっていき、離婚の原因につながります。
4.子どものために別れた方がよいと判断した
子育てしない夫との関係は自分にとって良くないものであると同時に、子供にも悪影響を与えてしまう恐れがあります。
ワンオペ育児が原因で夫婦関係が悪化して喧嘩が絶えない場合、子供にも喧嘩している姿を見せることになってしまいます。
子供にとって両親が喧嘩をしている姿は非常に恐ろしいものであり、精神的に大きなストレスを与える可能性が高いです。
また、子供の前での夫婦喧嘩は、一種の心理的虐待にも該当します。幼少期のトラウマは将来的にも悪影響を及ぼすことがあるため、非常に危険です。
夫婦関係の修復が見込めないのであれば、離婚して子供の将来を守った方がよいと判断し、離婚に至るケースも少なくありません。
子育てしない旦那に慰謝料や養育費は請求できる?
基本的に、ワンオペ育児だけを理由に慰謝料を請求することはできません。子育てをしない旦那に対して慰謝料を請求するためには、ワンオペ育児以外の特別な事情が必要です。
一方、子供が経済的に自立していないのであれば、養育費の請求は可能です。養育費の支払いは法律上で義務付けられているため、どのような理由であれ支払いを拒否することはできません。
次の項目から、子育てしない旦那に慰謝料や養育費を請求する方法について、詳しく解説します。
慰謝料を認めさせるには特別な事情が必要
ワンオペ育児だけを理由とした慰謝料の請求は難しいため、慰謝料を勝ち取るためにはその他の特別な事情が必要です。
一例として、離婚の際に慰謝料請求が認められるケースを紹介します。
- 不倫をしていた
- DVや虐待があった
- 日常的にモラハラを受けていた
- 悪意の遺棄(生活費を渡さない、正当な理由のない別居など)があった
- 浪費による借金を重ねていた
夫が上記のような行為をしていた場合、夫婦関係を破綻に追い込んだ不法行為とみなされ、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。
なお、慰謝料を請求するためには不法行為があったという証拠を示す必要があります。
たとえばDVや虐待などがあった場合、暴力を受けている動画や傷跡の写真、病院の診断書などが証拠になります。
子育てしない旦那に慰謝料を請求する際は、ワンオペ育児以外の事由がないかどうかを確認の上、適切な証拠を集めましょう。
子どもの親権と養育費は認められるのが一般的
旦那が子育てをせずワンオペ育児をしていた場合、基本的には妻に親権が認められます。
親権を決める際には、今までの監護実績が重要視されるからです。
ワンオペ育児の状況下においては、妻が監護の大半を担っていることが予想されます。仮に旦那が親権を持つことを望んだとしても、よほどの問題がない限り妻が親権を取ることになるでしょう。
また、子供が経済的に自立していない場合は養育費の請求が可能です。
養育費の支払いは親の義務であるため、親権者でなかったとしても支払う必要があります。
なお、子供の養育費は裁判所が公開している「養育費の算定表」に基づき、子供の年齢や人数などによって決定します。
養育費の支払いに関しては旦那と揉める可能性も高いため、弁護士に仲介してもらいながら金額や支払期間などを決めるようにしてください。
参照:養育費・婚姻費用の算定|裁判所
子育てしない旦那と離婚する前にすべきこと
旦那が子育てをしないからといって、いきなり離婚すると後悔につながる可能性があります。
離婚後は完全に1人で子供を育てなければならず、時間や経済的な余裕がなくなることが懸念されるためです。
子育てしない旦那のことで悩んでいるときは、離婚する前に以下の行動を実践してみてください。
- 夫婦で話し合いの場を設ける
- 夫に家事育児へ参加するチャンスを挙げる
- 自分達がやらなくていいことはサービスを活用する
- 別居することを検討する
次の項目から、子育てしない旦那と離婚する前にすべきことについて詳しく見ていきましょう。
夫婦で話し合いの場を設ける
夫が子育てに参加しないときは、妻が家事育児の負担に苦しんでいることに気付いていない可能性もあります。
そのため、いきなり離婚を切り出すのではなく、まずは話し合いの場を設けてみてください。
話し合いをする際のポイントとして、夫を責めるような態度を取ると喧嘩になる可能性があるため、自分の気持ちや考えなどを淡々と伝えるようにしましょう。
夫にしてほしいことや望んでいる生活などを事前に取りまとめておけば、感情的になることなく冷静な話し合いができます。
また、話し合いの場を設けることにより、夫が育児に参加しない理由を聞く機会にもなります。
ワンオペ育児が続いているときは夫婦の間に考え方の違いが生じているケースも多いため、離婚する前に夫と真剣に話し合いをしてみましょう。
夫に家事育児へ参加するチャンスを挙げる
ワンオペ育児が長く続いているときは、夫がどのように家事育児をすれば良いのかわからず、参加したくてもできない状況になっているケースもあります。
まずは簡単な作業から夫に頼んでみて、どのように家事育児をすれば良いのかを根気よく教えてあげましょう。
たとえば郵便物の確認やゴミ出し、食後の洗い物などは単純な作業なので、やる気さえあればできるはずです。
慣れてきたらお風呂やトイレの掃除、日用品の補充、子供の入浴補助や歯みがきなど、家事育児の範囲を少しずつ広げていってください。
夫に家事育児を頼む際のポイントとして、手伝ってもらったときは感謝の気持ちを伝えてあげましょう。
また、すぐにはできなくても文句や不満を言うことは避け、できるようになるまで粘り強く教えることが大切です。
自分達がやらなくていいことはサービスを活用する
夫に家事育児を手伝ってもらうことが難しい場合、家事育児の代行を活用しても良いかどうかを相談してみましょう。
家事育児の代行とは、料理の作り置きや掃除、洗濯、子供の世話や送迎などを依頼できるサービスです。一定の費用は発生するものの、家事育児全般を依頼できるため、負担が大幅に軽減されます。
ほかには、便利な家電製品を導入して家事の時間を短くする方法もおすすめです。たとえば衣類乾燥機や食器洗浄機、ロボット掃除機、電気圧力鍋などを導入すれば、家事の時間が削減されます。
家事育児に対してお金をかけることに抵抗がある場合は、少しずつサービスや家電などを導入するのも一つの手です。
まずは家事育児の代行サービスで子供を1日だけ預け、自分の時間を作ってリフレッシュすれば気持ちを切り替えられるかもしれません。
家事育児の負担を軽減できるサービスや家電などは、ぜひ積極的に活用してみてください。
別居することを検討する
夫と話し合いや家事育児へ参加するチャンスを促しても取り合ってもらえなかったときは、離婚を視野に入れた別居を検討する必要があります。
別居をしても、離婚が成立するまでは「婚姻費用」の名目で夫に生活費の要求が可能です。
婚姻費用は生活を維持するために必要な費用のことであり、別居中でも収入の高い方の配偶者は、収入が低い方の配偶者に婚姻費用を支払わなければなりません。
子供を連れて別居しても一定の生活水準をキープできるため、仕事や保育所を自分のペースで探しつつ、離婚に向けての準備を始められます。
また、別居期間が長くなれば夫婦関係が破綻していると判断されやすくなり、離婚が成立する可能性が高くなります。
ワンオペ育児の改善が難しい場合は、いったん別居してから離婚の準備を進めましょう。
まとめ
子育てしない旦那とは、お互いの合意があれば離婚が可能です。
相手が離婚を拒否して離婚裁判に発展した場合は、法定離婚事由に該当することを証明しなければ離婚が認められません。
ワンオペ育児は法定離婚事由には該当しないため、不倫やDV、モラハラなどの不法行為があったことを証明する必要があります。特に不法行為がない場合は、長期間の別居をして離婚する方法がおすすめです。
子育てしない旦那と本気で離婚したいと考えている場合は、離婚問題に強い弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談すれば有利な条件で離婚する方法を提示してもらえる上、旦那との交渉や裁判への出廷などもすべて任せられます。