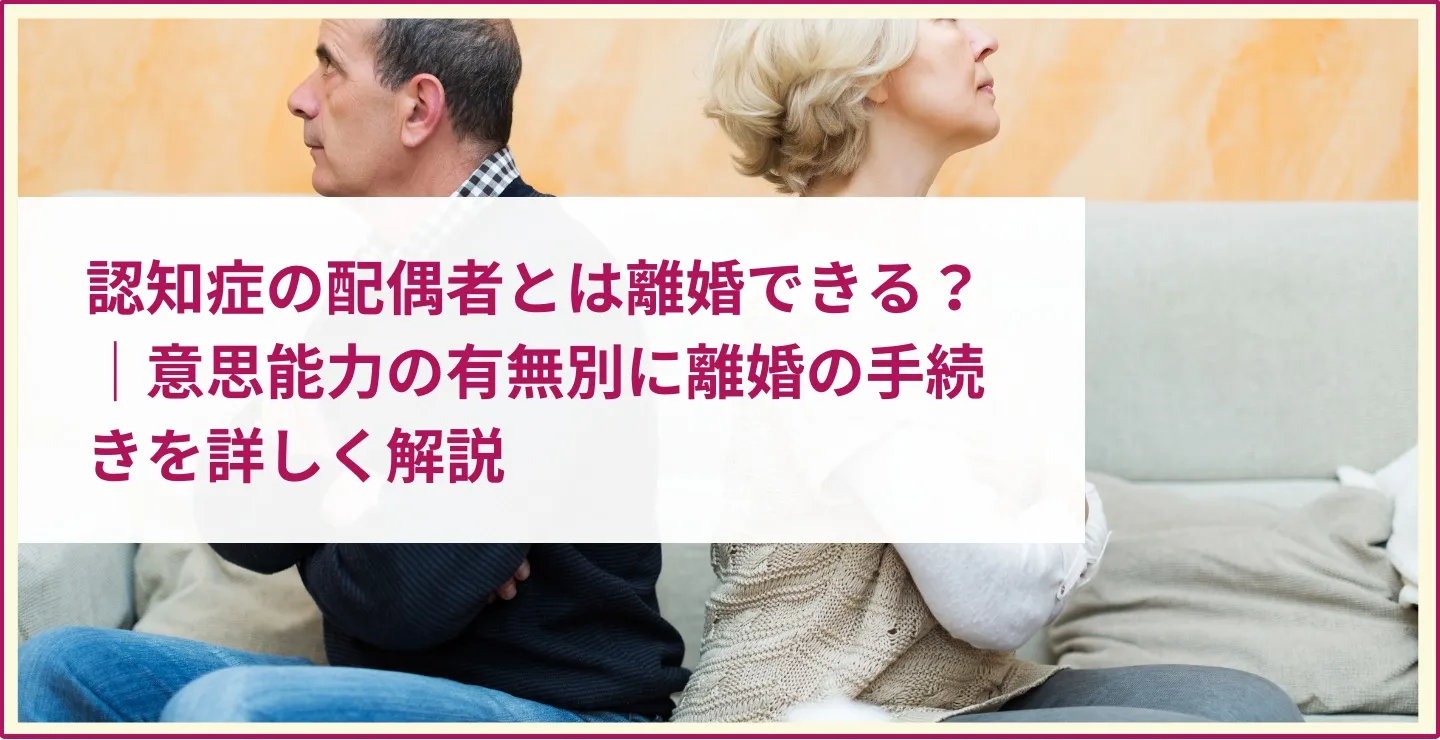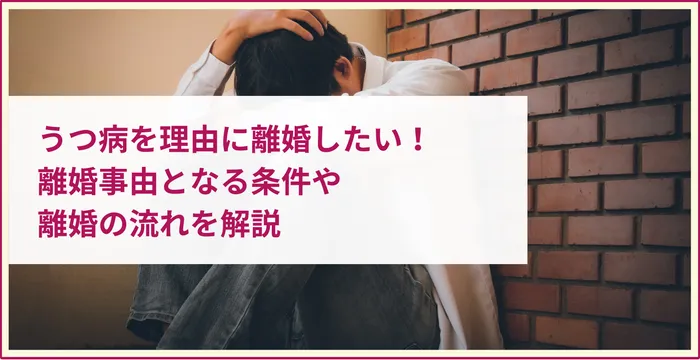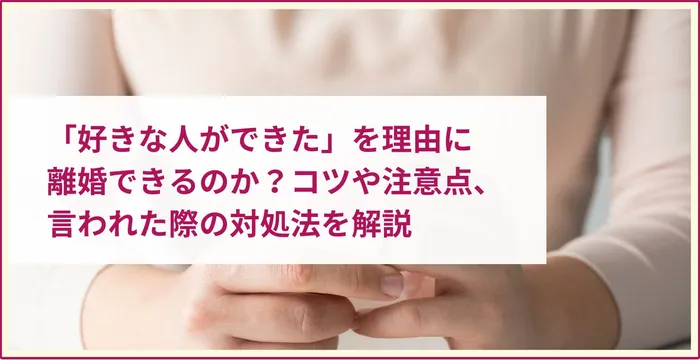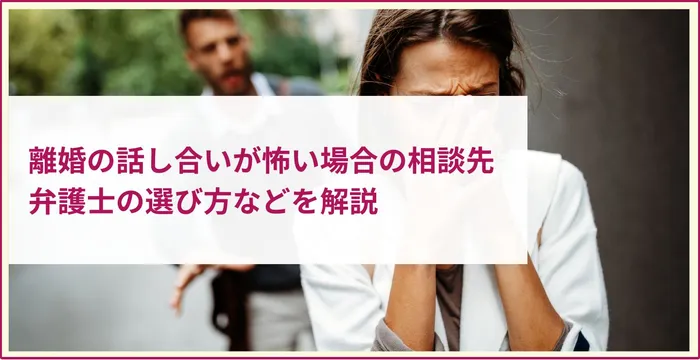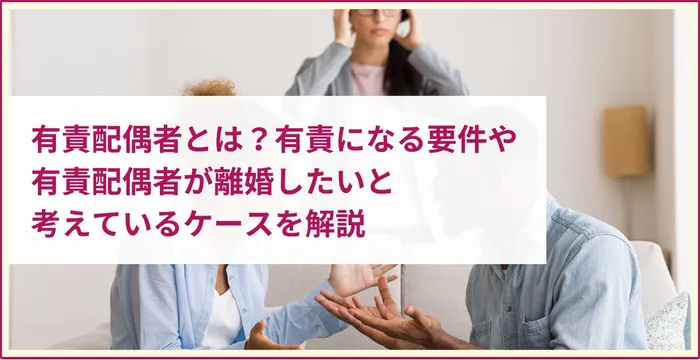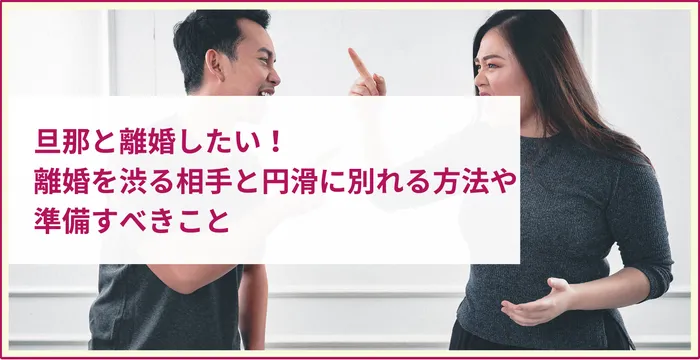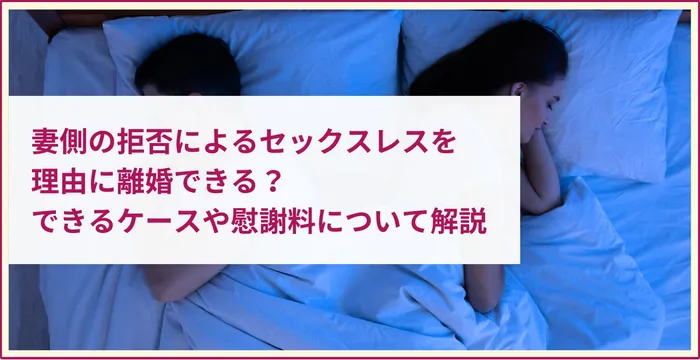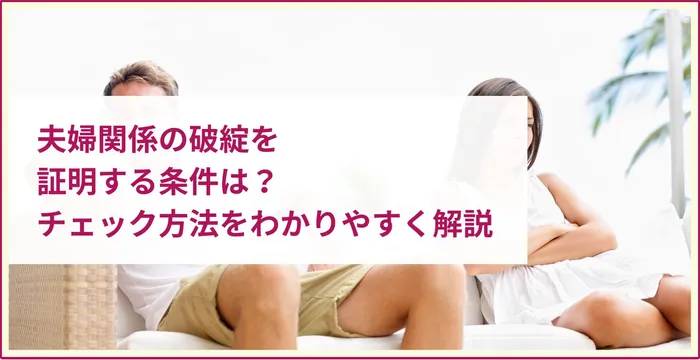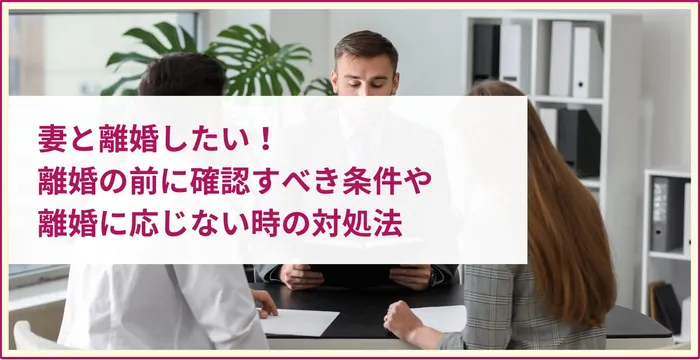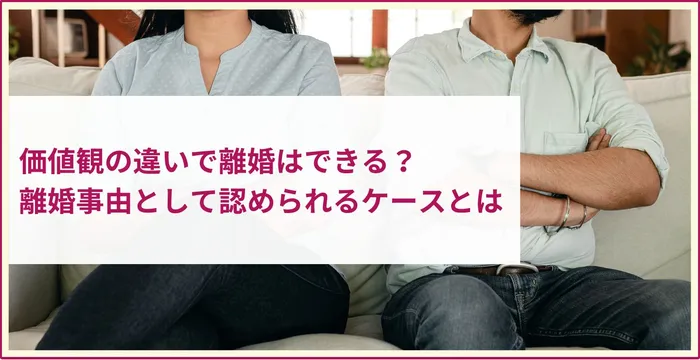配偶者が認知症になった場合は、病気への理解や介護は欠かせません。しかし、認知症は意思疎通ができなくなることも多く、介護生活が非常に苦しくなるケースもあるでしょう。
残りの人生を介護に捧げることを考えると、離婚を視野にいれるべきか悩んでしまうものです。
結論、認知症の配偶者と離婚できるかは以下の表のように認知症の程度で変わります。
|
認知症の程度
|
離婚する方法
|
|
判断能力があると認められる場合
|
協議離婚や離婚調停で合意が取れれば離婚できる。合意が取れなければ、裁判で離婚を認めてもらう必要がある
|
|
判断能力があると認められない場合
|
認知症の配偶者に成年後見人をつけて、離婚裁判を起こし、離婚を認めてもらう必要がある
|
ちなみに、協議離婚や離婚調停、裁判離婚の説明は以下の通りです。
|
離婚の方法
|
概要
|
|
協議離婚
|
裁判所を利用せずに、夫婦間の話し合いで成立させる離婚のこと
|
|
離婚調停
|
家庭裁判所で離婚に関する問題を話し合い、合意を目指すこと
|
|
裁判離婚
|
上記2つの方法でも離婚の合意ができない場合に、裁判所に訴訟して離婚を成立させること
|
また、離婚裁判によって離婚が認められるには、離婚したい理由が以下の法定離婚事由に該当することが必要です。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- その他婚姻を継続しがたい重大な事由
もし、認知症が理由で離婚裁判になった際は、上記のうち認知症の発症が「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかが争点となります。
また、医師によって意思能力が著しく低下していると認められるケースでは、配偶者の代わりに意思決定を行う成年後見人を選定し、その方に対して裁判を提起しなければなりません。
成年後見人とは、認知症などにより判断力が低下した人の代わりに法的手続きや生活サポートを行う人を指します。
このように、認知症の配偶者との離婚は、病状に合わせて複雑な手続きが求められます。また、裁判の場合は認知症の進行が法定離婚事由に該当するかだけでなく、離婚後の配偶者側の生活なども加味して審理が決定します。
認知症の配偶者との離婚は配偶者側の離婚後の生活などを配慮しながら慎重に進められるため、離婚や介護を専門とする弁護士に相談して専門家の力を頼ることが大切です。
なお、多くの方が認知症のパートナーを残して離婚しても本当に良いのだろうかと悩むでしょう。早急に離婚を考える前に、次のようなサービスを利用することで介護の援助が受けられたり、メンタル的なケアをしてもらえたりすることが期待できます。
- 認知症カフェに参加
- 地域包括支援センターやケアマネージャーに相談
- 弁護士や夫婦カウンセラーなど専門家を頼る
この記事では認知症の配偶者との離婚を解説しています。病状の重さに合わせた手続きの違いなど詳しく紹介しているので、参考にしてください。
認知症の配偶者と離婚するには双方の合意が必要
認知症の配偶者と離婚するには双方の合意が必要です。ただし、双方の合意が認められるには認知症の配偶者に意思能力があることが認められる場合に限ります。
ここでは認知症の配偶者と離婚する際の合意について解説します。
- ただし合意が認められるには意思能力が必要
- 意思能力の有無は医師が診断する
ただし合意が認められるには意思能力が必要
認知症の配偶者と離婚する際は双方の合意が必要ですが、合意自体が法的に認められるには、配偶者が「意思能力」を有していることが前提です。意思能力とは離婚という重大な法律行為について、その意味や影響を理解し、自らの意思で判断できる能力を指します。
具体的には離婚するかだけでなく、財産分与や慰謝料、親権といった条件についても理解して意思表示できるかが重要です。日本の民法第3条2項では、意思能力を欠く状態での法律行為は無効とされています。
第三条の二 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。
引用元 e-GOV
したがって、認知症の程度が重く、本人が意思能力を欠くと判断される場合は当事者だけの話し合いで離婚は成立しません。このような場合には成年後見人を選任するなどの法的措置が必要になります。
意思能力の有無は医師が診断する
意思能力の有無は、医師による診断を基に判断されます。特に要介護認定の際に主治医が作成する「意見書」は、認知症の症状や状態に加え、意思能力の評価も記載されているので、離婚に合意できるかを判断する重要な資料となります。
認知症の配偶者と離婚を検討する場合には、まず医師に相談し、正確な診断を得ることが必要です。適切な診断が行われれば後々のトラブルを防ぐだけでなく、自立支援医療の手続きなど離婚後の生活を維持する手続きも可能となります。
なお、認知症で意思能力があるかを判断するには、次のテストを行うことが一般的です。
| テスト名 |
やり方 |
| 長谷川式スケール |
精神科医の長谷川和夫氏が開発したテスト。
9つの質問に回答するのみで検査できるため、5~10分で認知症化を判定できる。 |
| MMSE |
アメリカ発祥の認知機能テスト。
長谷川式スケールとほぼ同じだが、本テストは11項目の質問に回答する。
所要時間は10分~15分。 |
認知症の疑いがある際は医療機関にて上記のテストを実施して、まずは認知症かを確定することが必要です。
意思能力がある場合の離婚の手続き
認知症の配偶者に意思能力がある際は、以下の流れで離婚手続きを行います。
- 夫婦で話し合いをする(離婚協議)
- 話し合いがまとまらない場合は裁判所に仲介してもらう(離婚調停)
- 裁判所に仲介をしてもらっても合意できない場合は裁判を起こす(離婚裁判)
①夫婦で話し合いをする(離婚協議)
意思能力がある場合、まず夫婦間で離婚について話し合う「離婚協議」を行います。離婚協議では双方が離婚を冷静に話し合い、離婚後の財産分与や親権、慰謝料などの条件を具体的に決めていきます。
話し合いが円満に進み合意に至れば、法律上の離婚理由を問わず離婚が可能です。離婚協議がまとまったら、夫婦で合意した内容を基に離婚届を作成し、市区町村役場に提出することで正式に離婚が成立します。
話し合いの際は特に条件面を細かく確認し、双方が納得できる形にすることが重要です。なお、必要に応じて離婚を専門に扱う弁護士を交え、法的なアドバイスを受けることも検討するとよいでしょう。
②話し合いがまとまらない場合は裁判所に仲介してもらう(離婚調停)
意思能力がある配偶者との離婚協議がうまくいかず、話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停は、裁判所が任命した調停委員が中立な立場から夫婦それぞれの意見を聞き、合意に向けた調整を行う場です。
第三者が間に入り、夫婦間の感情的な対立を和らげながら、冷静かつ公平に話し合いを進めることを目指します。
離婚調停では双方が家庭裁判所に出向き、それぞれが調停委員と話し合いながら調停が進みます。配偶者と顔を合わせないように配慮してくれるので、夫婦仲が険悪なケースでも安心です。
話し合いの結果、提示された条件に双方が納得すれば、離婚理由を問わず法的に離婚が成立します。その際には法的根拠を持った調停調書が作成されるため、養育費や財産分与は必ず履行しなければなりません。
また、例外的に裁判官が「離婚相当」と判断した場合には、「調停に代わる審判」が下ることもあります。
「調停に代わる審判」とは調停が成立しない場合に、家庭裁判所が当事者の事情などを考慮して審判を行う制度です。以下のような非常に限定的な状況で適用されます。
- 調停の際に、当事者の一方が出席できない場合
- 離婚条件に概ね納得しているものの、細かい点で合意できない場合
いずれの場合も、法的手続きが複雑になる可能性があるため、離婚を専門に扱う弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。
③裁判所に仲介をしてもらっても合意できない場合は裁判を起こす(離婚裁判)
離婚調停が不成立となり、夫婦間での合意が得られない場合には、家庭裁判所に訴えを起こして離婚裁判を行います。
裁判で離婚が認められるには、離婚理由が民法770条1項に定められた「法定離婚事由」に該当することが必要です。具体的な離婚事由には、次のものがあげられます。
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
引用元 e-GOV
認知症が理由で離婚するケースでは、主に五項の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」に該当するかが焦点となることが多いです。ただし、認知症により、日常的な暴力やDVなどが認められる場合は二項の「悪意の遺棄」に該当するケースもあります。
いずれの場合も裁判で主張を立証するには、証拠が重要です。例えば、認知症介護を記した日記やメモ、暴力行為の映像など客観的に状況を裏付ける資料を用意することも求められます。
認知症を理由とした離婚の場合は、介護費用の増大を示す家計簿や領収書なども裁判を優位に進める際に有効です。
裁判は時間や費用がかかり、精神的な負担も大きい手続きです。特に認知症が理由の場合は、配偶者の離婚後の生活も大きな争点となるため、慎重な判断が下される傾向があります。
精神的かつ時間的コストを下げる意味でも、離婚を専門とする弁護士に相談しながら準備を進めることが重要です。
「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは
民法770条1項には、離婚が認められる法定事由の一つとして「その他婚姻を継続し難い重大な事由」が定められています。この条項は、不貞行為や悪意の遺棄など具体的な事由に該当しない場合でも、夫婦関係の継続が著しく困難な事情が認められた場合に適用されます。
例えば、認知症が理由で以下の状況に陥っている場合は、この条項に該当する可能性が高いです。
- 配偶者に対する介護の負担が一方に集中している
- 意思疎通が完全に不可能となり夫婦間の協力関係が維持できない
ただし、認知症であること自体が自動的に離婚を認める理由にはならず、離婚後の配偶者の生活がどのように保障されるかなどの点も重要な判断材料となります。
実際に平成2年9月17日の長野地方裁判所の判例では、妻が重度の認知症とパーキンソン病を患い、夫のことを認識できず日常会話も困難な状況で離婚が認められています。
夫は妻を長期間看病し、施設入所後も定期的に見舞いを続けていましたが、病状が回復する見込みはなく、離婚後は妻の療養費が全額公費で賄われることも考慮され、離婚が認められました。この判例では夫婦関係が破綻していることに加え、離婚後の生活基盤が保証されている点が重要視されています。
つまり、病気を理由に単に配偶者を見放す形での離婚は民法第2条の信義則に反し認められません。
一方で配偶者の生活や介護体制を確保し、誠実な対応を尽くした場合には、離婚が許容される可能性があります。このように、認知症が法定離婚事由に該当するかは、夫婦関係や離婚後の生活保障に対する配慮がどの程度行われているかによって判断されるのです。
意思能力がない場合の離婚の手続き
認知症の配偶者に意思能力がない場合は、以下の流れで離婚手続きを行います。
- 裁判所に後見人選任の申立てをする
- 後見人に対して離婚裁判を起こす
①裁判所に後見人選任の申立てをする
認知症の配偶者が意思能力を欠いている場合、通常の離婚協議や調停による話し合いで離婚を進めることはできません。したがって、家庭裁判所に対して成年後見人を選任する手続きを行うことが必要です。
成年後見人とは認知症の当事者に代わり、その利益を守りながら法律行為などを行う役割を指します。
成年後見人は欠格事由がなければ誰でもなれますが、頼れる人が周りにいない場合は弁護士が担うことも可能です。具体的には次の流れに沿って成年後見人の手続きを行います。
| 手順 |
内容 |
| 申立人を決めて必要書類を揃える |
申立人は本人または本人の四親等以内の親族が行う。
以下の必要書類を揃えて家庭裁判所に申立を行う。
・申立書
・診断書
・登記されていない証明書
・戸籍や住民票、固定資産評価証明書
・登記事項証明書または登記謄本
・預貯金や有価証券の証明書
|
| 家庭裁判所に持ち込みか郵送 |
本人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立を行う。 |
| 調査官が面談調査を実施 |
家庭裁判所が申立書やほかの必要書類をチェックして、本人や関係者と面談を実施。
申立書に記載された内容をもとに確認を行う。
|
| 家庭裁判所が本人の判断能力を調査 |
調査官が本人と面談して判断能力を確認。
裁判所が独自に依頼した医師が精神状態を鑑定。
|
| 家庭裁判所が後見人の選定を行う |
書類や面談、精神鑑定などを基に後見人を選任する。
必ずしも候補者が後見人に指定されるわけではなく、場合によっては後見人を監督する後見監督人が選任されるケースも。
|
また、場合によっては認知症の配偶者が認知症発症前に後見人契約を結ぶ「任意後見人制度」を利用しているケースもあります。任意後見人制度がすでに結ばれている状態の場合は、任意後見人に対して離婚裁判を起こすことが必要です。
なお、自分自身が認知症である配偶者と後見契約を結んでいる場合には、成年後見監督人または任意後見監督人の選任しなければなりません。
後見監督人は、特別な事情がある際に後見人が正しく義務を履行しているかを監督する役割を担います。
実際に選任するには、後見人の種類に合わせて家庭裁判所に以下の申立書を提出することが必要です。
- 成年後見監督人:家事審判申立書
- 任意後見監督人:任意後見監督人申立書
上記申立書を提出すると家庭裁判所が審理を行い、必要に合わせて監督人を任命します。
②後見人に対して離婚裁判を起こす
判断能力がない認知症の配偶者と離婚する場合は、成年後見人や任意後見監督人に対して、離婚裁判を起こす手続きを進めます。
裁判で離婚を認めてもらうには、通常の離婚裁判と同様に法定離婚事由に該当しているかが重要な判断材料になります。認知症で判断力がない場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性が考えられるでしょう。
ただし、単に認知症であることが理由で離婚が認められるわけではありません。配偶者の介護負担や夫婦関係の実態、経済的事情などの具体的な証明が必要です。
通常の離婚裁判のように法定離婚事由となりうる証拠が求められるので、円満な解決を図るためにも離婚を専門に扱う弁護士に依頼するのがおすすめです。
認知症の配偶者と離婚するか悩んでいる方へ
認知症の配偶者と離婚することは制度上できるものの、悩むのは当然です。ここでは離婚を決断する前にやるべきことを紹介します。
- 離婚を思いついてもすぐ行動に移さない
- 認知症カフェなどに参加する
- 介護サービスや介護施設を利用する
離婚を思いついてもすぐ行動に移さない
認知症の配偶者と向き合い介護を続けていくことは、心身ともに大きな負担となる場合があります。そのため、離婚という選択肢が頭をよぎることは決して珍しいことではありません。
しかし、離婚を決断する前にすぐ行動を起こさず、一度冷静になって状況を整理することが重要です。
まずは別居を検討して心身を休めながら、自分自身と向き合う時間を持つのも一つの方法です。物理的な距離を取ることで、離婚という選択が本当に自分にとって最善なのかをじっくり考えられます。
具体的には、以下の点について慎重に検討することが大切です。
- 離婚して後悔しないか
- 残りの人生をどのように過ごしたいのか
- 配偶者と添い遂げる可能性を完全に排除してよいのか
一時的な感情で決断を急ぐと、後々後悔することも少なくありません。家族や離婚を専門に扱う弁護士などにも相談しながら、心を整理することをおすすめします。
認知症カフェなどに参加する
認知症の配偶者との関係に悩んでいる場合、一人で抱え込まず、地域で行われている「認知症カフェ」や「おれんじドア」といったイベントに参加してみるのも良い方法です。
認知症カフェやおれんじドアは認知症当事者やその家族が集まり、日々の体験や悩みを共有し合う場です。
他の家族がどのように介護や心の整理に向き合っているのかを聞くことで、自分の状況を冷静に見つめ直すきっかけになります。
また、専門家やサポートスタッフが参加している場合もあり、具体的なアドバイスを得られることもあります。当事者やその家族、専門家との交流を通じて孤立感を和らげたり新たな視点を得たりすることで、離婚について今一度冷静に考えられるでしょう。
これらのイベントは地域包括支援センターや市区町村役場で紹介してもらえることが多いです。情報収集をして、気軽に参加できる場所を探してみるのがおすすめです。
地域包括支援センターや弁護士に相談する
認知症の配偶者との離婚を悩んでいる場合は、専門家に相談するのもおすすめです。特に次のような専門家は、介護に関する悩みや不安に専門的な視点で寄り添ってくれます。
- 地域包括支援センターのスタッフ
- 医療ソーシャルワーカー
- ケアマネージャー
上記のような人たちに相談すれば、日々の介護負担や今後の見通しに対する具体的なアドバイスが得られます。介護者自身のメンタルを整える方法や具体策も提案してもらえるでしょう。
専門的な視点で援助を受けられれば、介護に関する悩みを軽減できる可能性があります。
一方で、離婚に関する悩みは以下のような専門家を頼るのがおすすめです。
特に弁護士は離婚に関して法的な観点からアドバイスしてくれるとともに、必要に応じて法的手続きをサポートしてくれます。離婚協議を円滑に進める方法を教えてもらえるだけでなく、いざ離婚調停や離婚裁判となった際は、あなたの代弁者として心強い味方になってくれるでしょう。
話を聞いてもらうだけでも気持ちが軽くなり、冷静になれるケースもあるので、悩んでいる際は早めに相談することが大切です。
介護サービスや介護施設を利用する
認知症の配偶者との生活に行き詰まりを感じたときは、介護サービスや介護施設の利用を検討することが大切です。地域包括支援センターに相談し、要介護認定を受けることで、利用できるサービスが広がります。
また、在宅で介護を続ける場合は、ヘルパーの派遣やデイサービスを利用するのもおすすめです。レスパイトケアのような介護者が休息するための一時的な施設利用も活用すれば、自分の時間を持つ余裕も得られるでしょう。
特に認知症の介護は、身体的負担だけでなく精神的負担も大きくなりがちです。一人で抱え込まずプロの支援を取り入れることで、介護そのものが効率的になり、家族関係の悪化を防ぐ助けにもなります。
状況によってはグループホームや特別養護老人ホームなどの施設利用も検討することで、介護者だけでなく配偶者にとってより適切な環境を整える選択肢が見えてくるケースもあるでしょう。
介護がつらい場合は早急に離婚を選択するのではなく、地域包括支援センターに相談し、自分たちに合った支援を見つけることが大切です。
まとめ
今回は認知症の配偶者との離婚について解説しました。認知症の配偶者との離婚は、意思能力の有無によって手続きが変わります。
認知症の程度が軽く、意思能力がある場合は、夫婦における協議離婚や離婚調停によって離婚成立を目指すことが可能です。話し合いがまとまらない際には離婚裁判を起こすこともできるので、一般的な離婚と手続き上変わりありません。
一方で重度の認知症により意思能力がない場合は、離婚する前に後見人を付けてもらう手続きが必要です。家庭裁判所に後見人選定の申立てを行ったうえで、後見人に対して離婚裁判を起こします。
どちらの場合であっても、認知症が関わる離婚は法的な観点に基づいて慎重に審理が進められます。特に配偶者の意思能力がない場合は、離婚後の生活も踏まえたうえでの審理が必要になるため、離婚の正当性を主張するには法的な知識が不可欠です。
離婚を専門とする弁護士に相談して、後悔のない選択ができるように最善を尽くしましょう。
なお、介護に困っている場合は、すぐさま離婚を決断するのはおすすめできません。地域包括支援センターなど介護の専門家や夫婦カウンセラーなどに相談して、冷静に考えることが大切です。
自分や相手の人生、今後の生活などを踏まえたうえで、決断しましょう。
よくある質問
認知症の夫からのモラハラを原因とした離婚をしました。相手方に慰謝料を請求することはできますか?
認知症の夫からのモラハラを理由に離婚した場合、
慰謝料を請求できる可能性があります。ただし、この場合は認知症の症状や程度、モラハラの内容やその継続性・深刻度によって判断が分かれる点に注意が必要です。
例えば、認知症の症状が進行している場合、相手が意図的にモラハラを行っていると認められないケースもあります。
請求が認められるためには、モラハラがどのような形で行われ、どれほどの精神的苦痛を受けたかの証明が必要です。裁判を有利に進めるためには、次のような証拠を揃えておくことをおすすめします。
- モラハラに該当する行動や発言の録音
- 日記やメモの記録
- 医師の診断書など精神的苦痛を受けた客観的な資料
配偶者からのモラハラは非常に複雑かつ個別の要件によって判断も異なるため、離婚やモラハラを専門とする弁護士に相談することがおすすめです。弁護士からの専門的なアドバイスに合わせて適切な準備と対応をすることで、スムーズに手続きを進められるでしょう。
夫と任意後見契約を結んでいるのですが、その夫が認知症になってしまいました。離婚することは可能ですか?
認知症を発症した夫と任意後見契約を結んでいる場合でも、
必要な手続きを踏めば離婚は可能です。ただし、夫自身に判断能力があるかで手続きが次のように変わります。
- 判断能力あり:夫と離婚協議→離婚調停→離婚裁判の順に手続きする
- 判断能力なし:家庭裁判所で成年後見監督人の選任を行ってから、成年後見監督人に対して離婚裁判する
夫自身に判断能力がある場合は、通常の離婚と同様の流れで離婚が成立します。しかし、夫に判断能力がない場合は、家庭裁判所にて成年後見監督人の選任を申し立てることが必要です。
家庭裁判所に対して「家事審判申立書」を提出することで、成年後見監督人を選任する審理が行われます。成年後見人が選任されたうえで、離婚裁判を実施する流れとなります。
ただし、後見人自体の立場や職務は離婚しても消滅しないため、離婚後も後見人としての義務は果たすことが必要です。後見人を辞める場合は別途「後見人等辞任許可」の申立をして、家庭裁判所から辞任許可の審判を受けて初めて辞められます。
認知症の配偶者との離婚は複雑な手続きを踏む必要があるため、離婚を専門に扱う弁護士に相談することが大切です。
夫と協議離婚することになりましたが、夫は認知症にかかっています。離婚公正証書を作成するときに、夫婦ふたりで手続きをしなければいけませんか?
離婚公正証書を作成する際には、
原則として夫婦そろって公証役場に出向き、手続きを行うことが必要です。特に夫婦どちらかが認知症の場合は、公証人に意思能力の有無を確認してもらうためにも夫婦で手続きを行います。
ただし、夫が認知症の影響で公証役場に出向くことが難しいと公証人が認める場合は、例外的に夫自信が選んだ代理人を立てることも可能です。
また、公証人から代理人を認めてもらうには、夫が意思能力を有していることを示すための証明書類や診断書などが求められます。
手続きの詳細や代理人を立てられるかは法律の知識が必要になるため、離婚を専門に扱っている弁護士に相談するのがおすすめです。
認知症の義親の介護を理由に離婚することはできますか
義親の介護を理由に離婚を考える場合、まず
配偶者が離婚に同意すれば、法律上、理由を問わず離婚は可能です。一方で、話し合いがまとまらず離婚裁判に進む場合には、義親の介護がきっかけで夫婦関係が破綻していると認められる場合に限り、裁判所が離婚を認める可能性があります。
裁判で離婚が認められるためには、介護が原因で夫婦関係が破綻していることを証明する必要があるため、弁護士に相談し準備を進めることが大切です。
また、法律上、義親の介護義務は原則としてありません。ただし、義親と同居している場合や義親と養子縁組を結んでいる場合、あるいは家庭裁判所が「特別な事情」を認めた場合には例外的に介護義務が生じることがあります。
義親の介護が直接の理由で離婚を考える場合では、家庭の状況や法的な位置付けによって義務が発生するケースもあるのです。義親の介護を理由に離婚する場合も、離婚を専門とする弁護士に相談することをおすすめします。