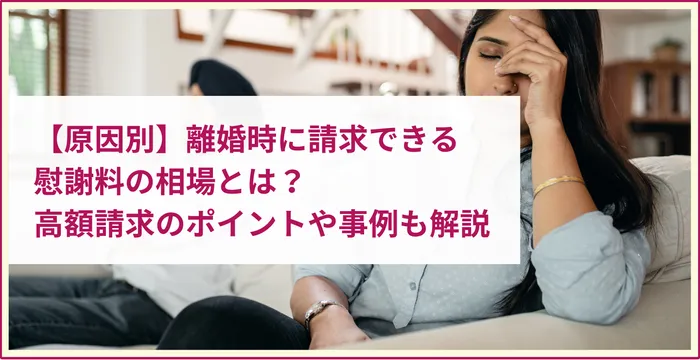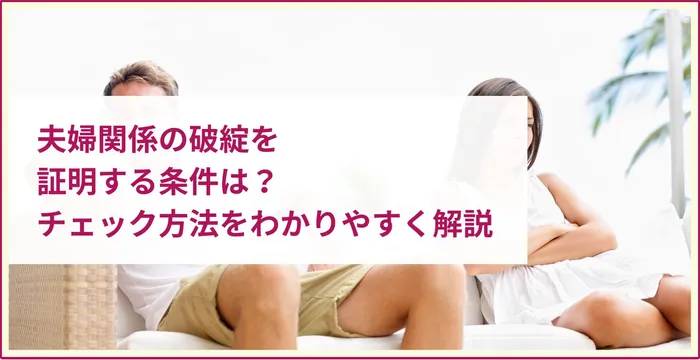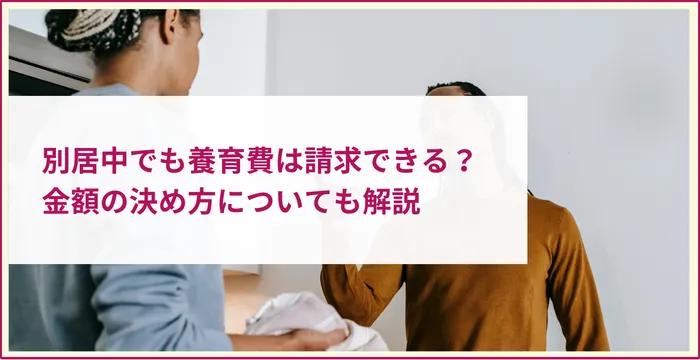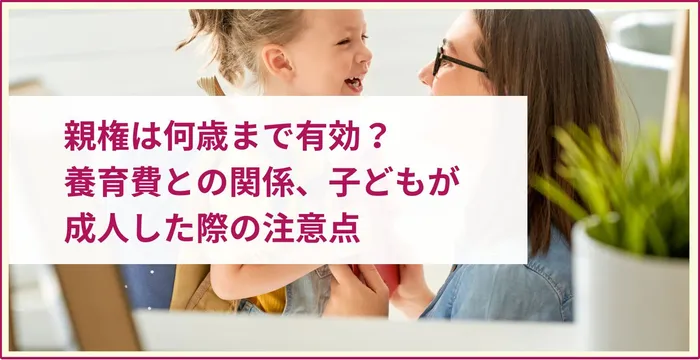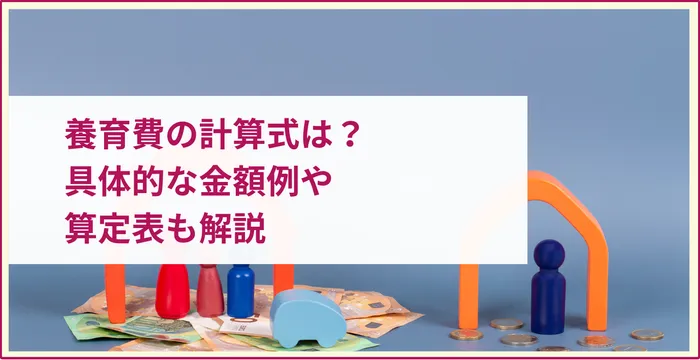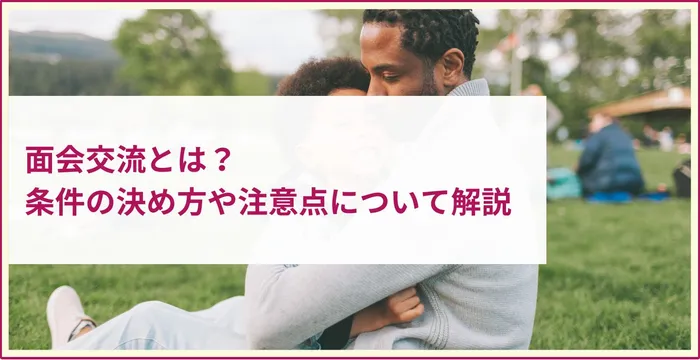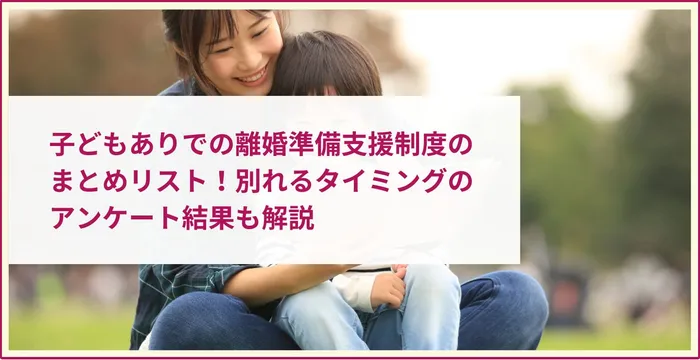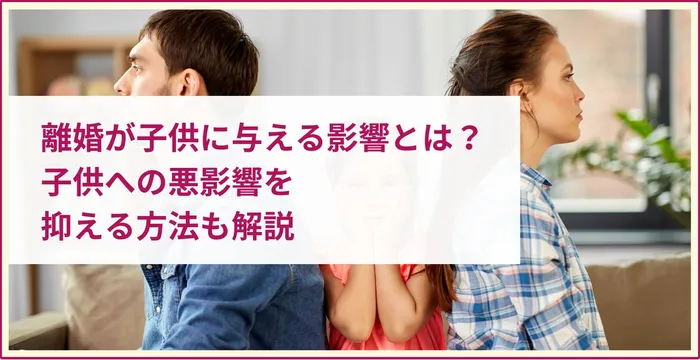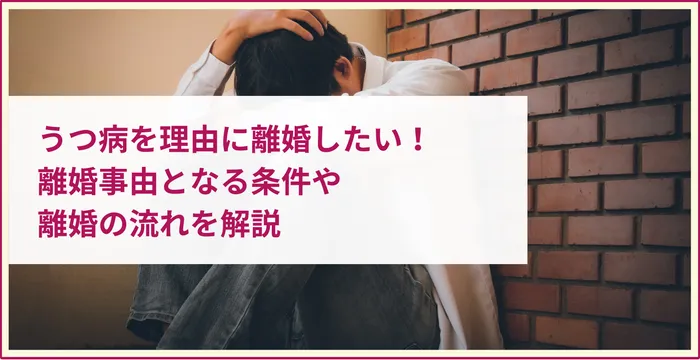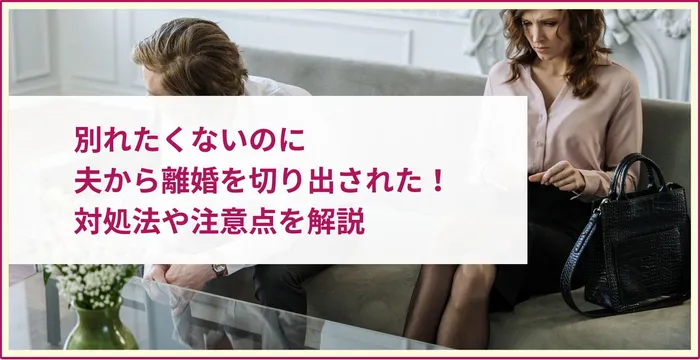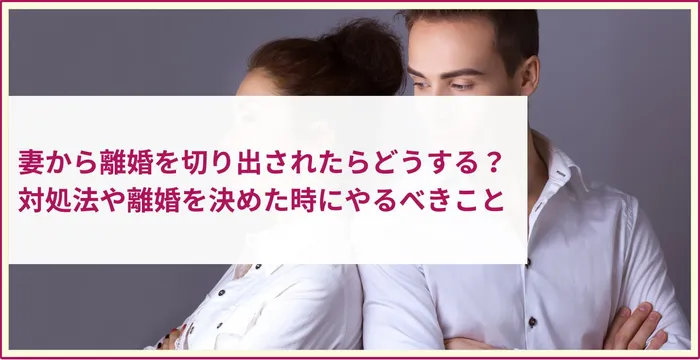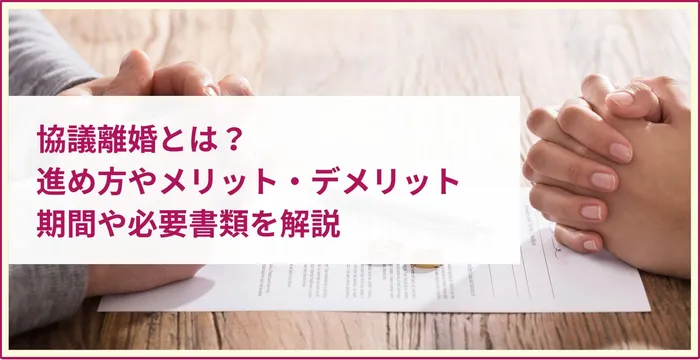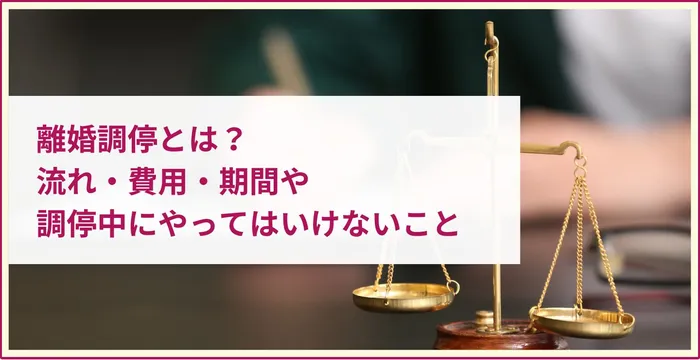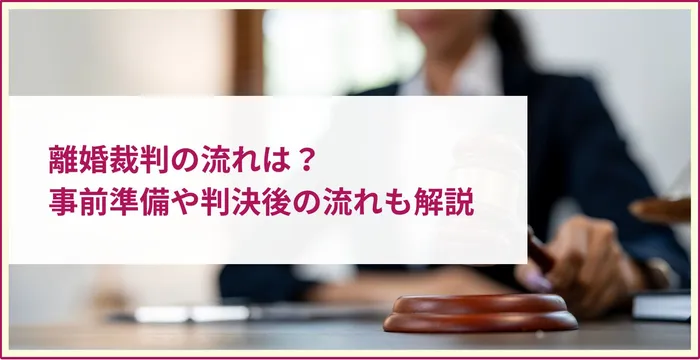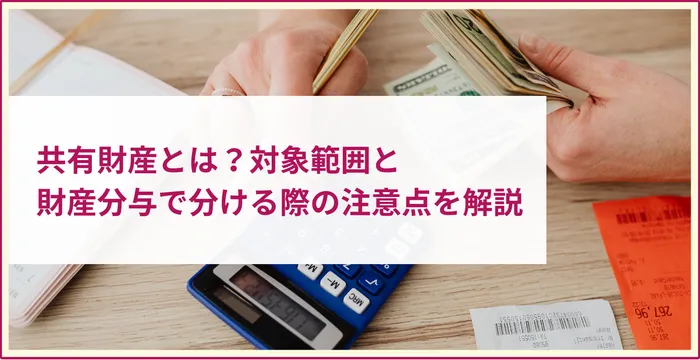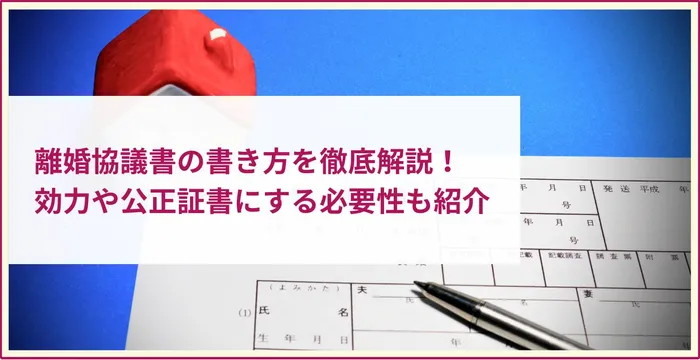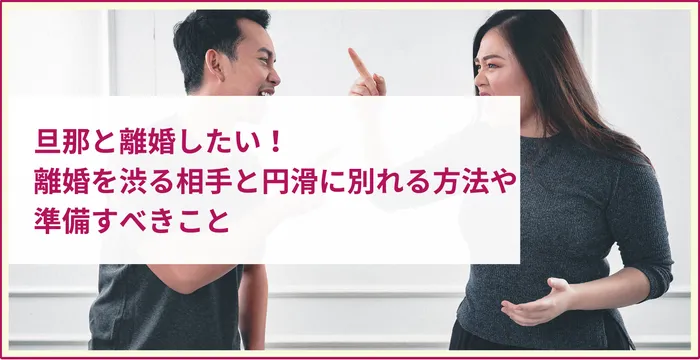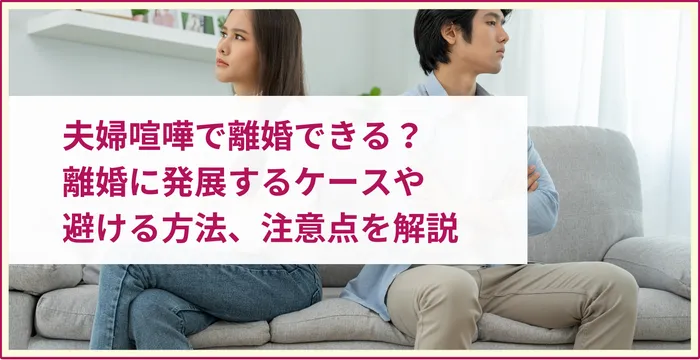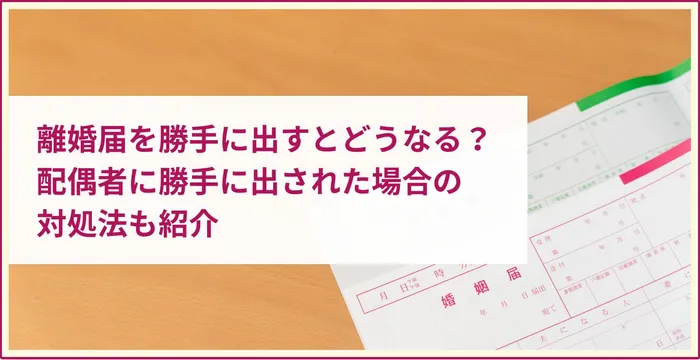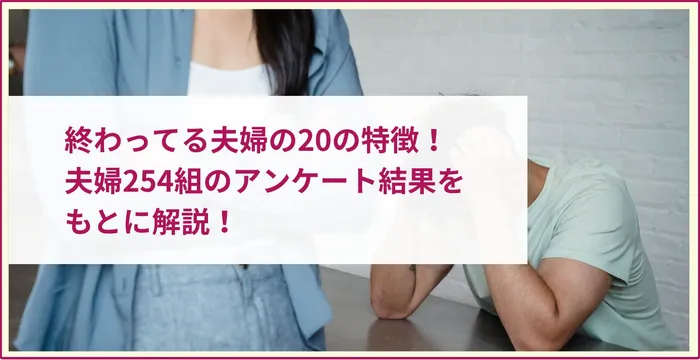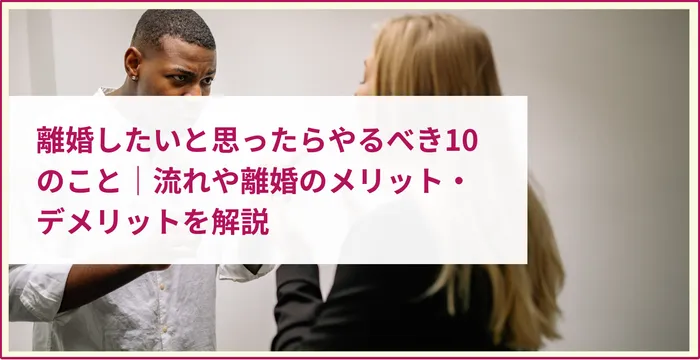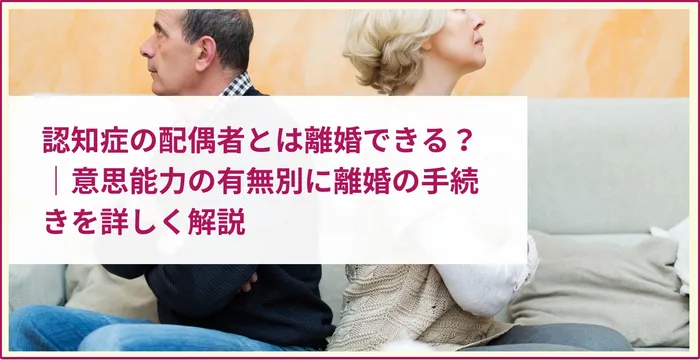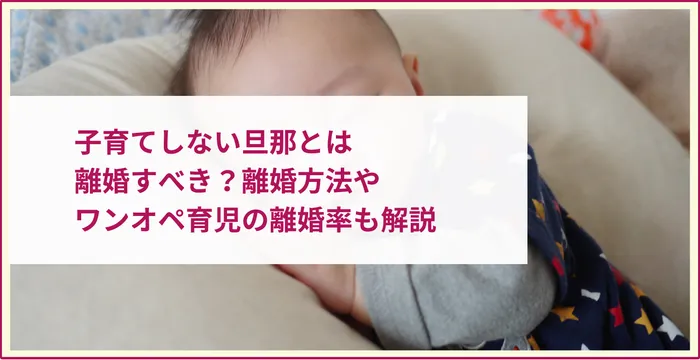産後うつとは、出産後に女性が感じる感情的な不安定や抑うつ症状のことです。一般的に、出産後数週間から数カ月以内、特に産後1~2か月頃に多いとされています。出産前は夫婦関係が良好だった場合でも、産後うつが原因で関係が悪化し、最終的に離婚を考えるようになってしまった方もいるのではないでしょうか。
離婚を考える場合、協議離婚や調停離婚では、夫婦双方が合意すれば離婚が可能です。協議や調停で合意に至らない場合、裁判で離婚を請求することになります。
裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要です。法定離婚事由には、下記が該当します。
- 不貞行為(配偶者以外との肉体関係)
- 悪意の遺棄(正当な理由のない同居義務違反等)
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みがない強度の精神病(民法改正により2026年5月までに削除予定)
- その他婚姻を継続し難い重大な事由(長期間の別居、DV、モラハラなど)
つまり、感情的に不安定であったり抑うつ症状にあるといった単なる産後うつというだけでは、法定離婚事由には通常該当せず、裁判で離婚が認められる可能性は低いと言えます。
この場合、産後うつが原因かに関わらず、夫婦が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する状況にあるかがポイントとなります。
夫婦関係の破綻とは、夫婦が婚姻継続の意思をなくしていたり、夫婦としての共同生活を回復する見込みがない状態を指します。具体例としては、長期間の別居やDV・モラハラなどが挙げられます。さらに、夫婦の意志疎通が完全に途絶えた場合や、一方が婚姻生活を維持する意思を持たない場合なども破綻に該当します。
婚姻関係の破綻が認められる場合、法定離婚事由に該当し、裁判で離婚が認められる可能性が高くなります。ただし、裁判で離婚が認められるかどうかを法的知識のない個人が判断するのは難しいため、離婚問題を扱う弁護士の無料相談を受けてみることをおすすめします。
なお、うつ状態にあるときは、正常な判断が難しくなることがあります。衝動的に離婚を決断するなど、大きな環境変化を行うことは後悔を招く可能性もあります。症状が落ち着くまで大きな決断は避け、医師やカウンセラー、親族など、第三者に相談して助言を受けることをおすすめします。
もし別居後に相手より収入が低かったり、子供を引き取っている場合は、生活費や養育費として婚姻費用を請求することができます。別居を考える場合は、婚姻費用の金額や別居期間についても予め決めておくことが重要です。
産後うつがひどく、話し合いが難しい場合は、弁護士に相談し、同席してもらうことも有効です。弁護士が間に入ることで、冷静な対応ができ、スムーズに問題を解決できる場合があります。
本記事では、産後うつを理由とした離婚の可否や条件、離婚手続きの方法、そして離婚を避けるための対策について詳しく解説していきます。産後うつが原因で離婚を検討されている方は、参考にされてください。
産後うつとは
産後うつとは、出産後に発症するうつ病の1つです。まずは、産後うつの意味や産後クライシス・マタニティブルーとの違いについて解説していきます。
産後うつは夫婦関係に限らない抑うつ症状
産後うつの症状は、下記の通り一般的なうつ病と基本的には同じです。
- 不眠
- 食欲不振
- 気分の落ち込み
- 強烈な不安
- 涙もろくなる
産後6週から8週の間に発症するケースが多いのが特徴で、夫婦関係に限らず抑うつ症状が表れます。自然に回復する可能性が低く、放置すると症状が悪化して自傷行為や自殺に至ってしまう恐れがあるため、産後うつを発症したら医師に相談して適切な治療を受けることが大切です。
産後クライシスやマタニティブルーとは区別される
産後うつと似たような言葉として「産後クライシス」「マタニティブルー」がありますが、これらは産後うつとは全く異なります。
| 産後クライシス |
出産をきっかけに夫婦間の愛情が薄れ、夫婦関係が急激に悪くなること |
| マタニティブルー |
妊娠中や出産後に生じる一過性の不安症状のこと |
産後クライシスは夫婦関係が危機的状況に陥る現象のことで、産後うつのような心の病気ではありません。産後うつでは「夜眠れない」「食欲がわかない」「気分が落ち込む」など夫婦関係に限らない抑うつ症状が表れます。
一方、産後クライシスでは、下記のように夫婦関係に限定した症状が表れるのが特徴です。
- 些細なことで夫にイライラするようになった
- 夫に対する言動がキツくなった
- 夫婦の会話やスキンシップが減った
マタニティブルーは、出産後に不安症状が表れるという点では産後うつと共通していますが、症状が一過性であるかという点に違いがあります。産後うつの場合は適切に治療しないと症状が改善せず、放置すると症状が悪化していくケースが多いですが、マタニティブルーの場合は2週間程度で自然に治るケースがほとんどです。
ただし、マタニティブルーから産後うつになるケースもあるため、症状が長引く場合は治療が必要になる可能性があります。
産後うつで離婚したくなったら認められる?
産後うつを理由とした離婚の場合、結論からいうと相手の合意次第で離婚できるかが決まります。
相手からの合意があった場合には離婚できる可能性がありますが、相手からの同意が得られず裁判になった場合は離婚が認められない可能性が高いです。
協議や調停では夫婦の合意があれば離婚が認められる
協議離婚や調停離婚の場合は、どんな理由であっても夫婦双方が離婚に合意すれば離婚が成立します。そのため、離婚の理由が産後うつであっても、夫婦間の話し合いや離婚調停の段階であれば、相手から離婚の合意を得ることで離婚できます。
厚生労働省の調査によると、99%は協議離婚または調停で離婚しています。
実際は、離婚する夫婦のうちほとんどが裁判までもつれ込むことはなく、話し合いでの離婚が成立しています。
離婚裁判になった場合は産後うつだけでは離婚は認められにくい
協議や調停で話し合いがまとまらず離婚裁判になった場合、産後うつを理由とした離婚は認められない可能性が高いです。裁判で離婚を認めてもらうためには、民法で定められている「法定離婚事由」(裁判で離婚が認められる正当な理由)が必要です。
民法770条では、以下の5つを法定離婚事由として定めています。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
悪意の遺棄とは、配偶者が正当な理由なく夫婦としての義務を果たさず、一方的に相手を見捨てる行為 のことで、具体的には下記のような行為を指します。
- 生活費を一切渡さない、働かずに家庭を支えない
- 正当な理由なく家を出て戻らない
- 病気やケガをした配偶者を無視する
- 一方的に家事や育児を放棄する
また、離婚理由が不貞行為などの4つの法定離婚事由に当てはまらない場合、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはめて離婚を目指します。一般的に「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に当てはまるのは、下記のようなケースです。
- 暴力(DV)・虐待
- 不貞行為(浮気・不倫)
- 深刻な性格の不一致
- モラルハラスメント(モラハラ)
- 生活の安定が脅かされる程度の浪費・借金
- 宗教・思想の強制
- 長期間の別居
産後うつそのものは、5つある法定離婚事由のどれにも当てはまりません。そのため、産後うつを理由とした離婚は裁判だと認められないのが一般的です。ただし、産後うつのほかにも離婚の原因があり、それが法定離婚事由に該当する場合は離婚が認められる可能性があります。
産後うつを理由とした離婚が裁判所に認められる条件
産後うつを理由とした離婚は裁判だと認められないのが一般的ですが、下記の条件を満たしてれば離婚が認められる場合もあります。
- 夫婦関係が破綻していて修復の見込みがないこと
- 離婚後に妻が生活に困窮する恐れがないこと
- 「回復の見込みがない強度の精神病」を理由に離婚が認められる可能性は低い
ここからは、それぞれの条件について1つずつ詳しく解説していきます。
夫婦関係が破綻していて修復の見込みがないこと
産後うつを理由とした離婚を裁判所に認めてもらうには、夫婦関係が破綻していて修復の見込みがないことを立証する必要があります。協議や調停の場合は、夫婦双方が離婚に合意すれば理由を問わず離婚できますが、離婚裁判の場合は民法で定められている法定離婚事由が必要です。
しかし、前述の通り産後うつそのものは法定離婚事由に該当しないため、裁判では離婚が認められないのが一般的です。ただし、以下のような事情・離婚原因がある場合は、法定離婚事由の1つである「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたるとして離婚が認められる可能性があります。
- 長期間別居している(3~5年程度)
- DVやモラハラを受けている
離婚後に妻が生活に困窮する恐れがないこと
夫婦関係が破綻していて修復の見込みがないケースであっても、離婚後に妻が生活に困窮する恐れがあると判断された場合は離婚が認められない可能性が高いです。そのため、離婚後の妻の生活が困窮しないよう、以下のような方法で見通しを付けておく必要があります。
- 離婚しても妻が生活できるように配慮した財産分与を行う
- 妻の親族に妻の生活をサポートしてもらう
- 妻が障害年金を受給できるように手続きしておく
「回復の見込みのない強度の精神病」を理由に離婚が認められる可能性は低い
産後うつを理由とした離婚では、産後うつが法定離婚事由の「回復の見込みがない強度の精神病」にあたる可能性があります。しかし、産後うつが「回復の見込みがない強度の精神病」にあたるとして離婚が認められるケースはほとんどありません。
産後うつを含むうつ病は、適切な治療を受ければ回復する可能性がある精神病であり、回復の見込みがないとは判断されにくいためです。また、「回復の見込みがない強度の精神病」を理由とする離婚要件は、民法改正により削除が決定しています。
これは、精神障害を理由とする離婚が障害者差別にあたるとの指摘を受けたためです。特に、国連の障害者権利委員会が差別的条項の廃止を勧告したことが影響し、日本政府は2024年に民法改正を成立させました。
ただし、2026年5月23日までに施行予定であるため、現時点(2025年)ではまだ有効 です。そのため、重度の産後うつにかかり、長年治療を受けているにもかかわらず回復の見込みがないと医師が診断した場合は、産後うつが「回復の見込みがない強度の精神病」にあたるとして離婚が認められる可能性があります。
施行後に精神病が理由で離婚する場合は、「婚姻を継続し難い重大な事由」として判断されます。そのため、裁判では夫婦関係の破綻や介護負担など、総合的な事情が考慮されることになります。
(判例:昭和45(オ)426 離婚請求 最判昭和45年11月24日 最高裁判所第三小法廷)
産後うつのみを理由とした離婚では慰謝料請求は認められにくい
産後うつのみを理由とした離婚では、原則として慰謝料の請求はできません。離婚で慰謝料を請求できるのは、相手方の不法行為によって夫婦関係が破綻し、離婚に至ったケースに限られています。
不法行為とは、故意や過失によって他人の権利や利益を侵害する行為のことで、下記の行為が不法行為に該当します。
産後うつを理由とした離婚は、夫婦双方に原因があると判断されることが多いです。そのため、「産後うつでお互いの愛情が冷めた」「産後うつで夫婦関係が悪化した」といったケースだと慰謝料請求は認められません。
ただし、夫が産後うつに無関心で症状が悪化したと認められる場合や、妻に対する言動がモラハラに該当すると評価された場合は、夫が離婚の原因を作ったということで慰謝料の請求が認められるケースもあります。
産後うつで離婚や別居をする場合の注意点
産後うつで離婚や別居をする場合は、以下の点に注意が必要です。
- うつ状態のままで直接離婚の交渉や重要な決断はしない
- 別居したいときは弁護士に相談する
- 親権・養育費・面会交流の方針を決めておく
- お金のことや利用できる制度を調べておく
ここからは、それぞれの注意点について1つずつ詳しく解説していきます。
うつ状態のままで直接離婚の交渉や重要な決断はしない
うつ状態ではしっかりと頭が回らず、冷静に物事を判断するのが難しいです。うつ状態のままで離婚の交渉や重要な決断をすると、症状が悪化したり症状が回復した後に後悔したりしてしまう恐れがあります。
産後うつを理由に離婚を考えている場合は、まずうつ状態を改善するための治療に専念するようにし、離婚の交渉や重要な決断が必要になる場合は弁護士に介入してもらいましょう。
別居したいときは弁護士に相談する
離婚を前提とした別居をする場合は、必ず弁護士に相談するようにしてください。正当な理由や相手の合意なく一方的に別居すると、法定離婚事由の1つである「悪意の遺棄」にあたる可能性もあります。
悪意の遺棄とは、正当な理由や夫婦間の合意なく、夫婦間の義務である「同居義務」「協力義務」「扶助義務」を放棄する行為のことです。民法上の不法行為に該当するため、離婚の原因を作ったとして相手に対する慰謝料請求が認められないどころか、逆に相手から慰謝料を請求されてしまう恐れもあります。
そのため、離婚を前提とした別居する場合は、相手からの同意を得ることが望ましいです。別居の準備をする際は、下記が重要事項になるので必ず確認しておきましょう。
- 相手の収入を確認しておく
- 夫婦の共有財産を共有しておく
- 婚姻費用について取り決めておく
- DVや浮気など産後うつ以外に相手による不法行為がある場合は証拠を集めておく
- 離婚届不受理申出をしておく
「同居義務」「協力義務」「扶助義務」の義務は離婚しない限り有効なため、別居する際も扶助義務により生活費の請求は可能です。この場合、「婚姻費用」として生活費が少ない配偶者は多い配偶者に対して請求できます。
婚姻費用の中には、生活費のほかに子どもの養育費も含まれているため、産後うつで別居する場合は受け取れるようにしておくと安心です。婚姻費用はお互いの年収から決まるため、別居前に相手の年収は必ず把握し、事前に話し合いで金額についても決めておきましょう。
別居のまま離婚を考えている場合は、財産分与や理由によっては慰謝料も発生します。もし、別居の原因に相手の不法行為も含まれているのであれば、写真や動画、不倫相手とのメッセージなど証拠集めもしておきましょう。
また、一度別居すると相手の全財産を把握するのが難しくなってしまう可能性もあるため、なるべく別居前に財産状況まで確認しておくのがおすすめです。
反対に、相手が別居を希望しており、夫婦関係再構築のために別居を選択した場合は、「離婚届不受理申出」を提出しておくとよいです。離婚届不受理申出とは、万が一勝手に離婚届を提出されることを防げる書類です。
特に、妻が別居を希望する場合、産後うつの状態では冷静な判断力がないため、衝動的に離婚届を提出してしまう可能性も少なくありません。一度離婚手続きが受理されると、取り消すのには非常に手間がかかるため、正式に離婚が決定するまでは離婚届不受理申出をしておきましょう。
上記の通り、別居前は準備すべきことが多くあるため、不安なことがある場合は弁護士に相談してアドバイスをもらうのがおすすめです。
親権・養育費・面会交流の方針を決めておく
経済的・社会的に自立していない子どもがいる夫婦が離婚する場合は、親権や養育費、面会交流について夫婦で話し合い、方針を決めておく必要があります。なお、産後うつであっても、それだけが理由で親権者として不適格とされることはありません。
うつの症状が育児に支障がない程度であると判断されれば、親権を獲得できる可能性があります。養育費や面会交流について取り決める際には、主に以下のような項目を決めます。
<養育費について決めておくべきこと>
- 養育費の金額
- 養育費の支払い期間
- 養育費の支払い方法
- 特別費用(養育費に含まれない一時的な大きい出費)が発生した場合の金額や負担割合
<面会交流について決めておくべきこと>
- 面会交流の頻度
- 面会交流の場所
- 面会交流の時間
- 学校行事への参加の可否
- 宿泊を伴う面会交流の可否
- 祖父母の面会交流の可否
- 面会交流の開始時・終了時の子どもの引き渡し方法
- 面会交流に関する連絡方法
産後うつの症状が重い場合は、自分で離婚交渉や重要な判断をすることが難しいため、必ず弁護士に介入してもらいましょう。
お金のことや利用できる制度を調べておく
産後うつを理由に離婚する場合は、離婚後にお金のことで苦労しないよう、離婚時や離婚後に請求できるお金のことや利用できる制度について調べておきましょう。離婚時や離婚後には、財産分与や年金分割を請求できます。
- 財産分与:婚姻中に夫婦で協力して築き上げてきた財産を、離婚の際に夫婦で分け合う制度
- 年金分割:婚姻中に夫婦で払い込んだ厚生年金の年金保険料の記録を、離婚の際に夫婦で分割する制度
また、離婚後に子どもと一緒に暮らして育てる場合は、国や地方自治体などが実施している以下の制度が利用できます。
| 制度の種類 |
対象者 |
支給額 |
| 児童手当 |
0歳~18歳(高校生)で国内に住所がある子ども |
3歳未満:月額15,000円(1人あたり)
3歳以上:月額10,000円(1人あたり)
※第3子以降は月額30,000円(1人あたり) |
| 児童扶養手当 |
18歳までの子ども(障害児の場合は20歳まで)がいる母子家庭・父子家庭 |
月額45,500円(対象の子ども1人で全額支給が認められた場合) |
| 特別児童扶養手当 |
精神または身体に中度以上の障害がある20歳未満の子どもがいるすべての家庭 |
1級(重度):月額55,350円(1人あたり)
2級(中度):月額36,860円(1人あたり) |
| 児童育成手当 |
18歳までの子どもがいる母子家庭 |
月額13,500円(1人あたり) |
| 障害児福祉手当 |
精神または身体に重度の障害があり、常時介護が必要な20歳未満の子どもがいるすべての家庭 |
月額15,690円(1人あたり) |
| 母子家庭の住宅手当 |
20歳未満の子どもがいる母子家庭・父子家庭 |
月額5,000円〜10,000円程度(市区町村によって異なる) |
| ひとり親家庭等医療費助成制度 |
18歳までの子どもがいる母子家庭・父子家庭 |
保険医療費の自己負担額の一部を市区町村が助成 |
| こども医療費助成 |
市区町村によって異なる |
保険医療費の自己負担額の一部を市区町村が助成 |
上記についても夫婦で話し合う必要がありますが、うつ状態が重い場合は無理をせず弁護士に介入してもらってください。
産後うつでの離婚を避けるには
産後うつによる離婚は、夫婦で協力して以下のような適切な対応を取ることで避けられる可能性があります。
- 主治医や専門家に相談する
- こどものケア・サポートをこころがける
- 家事・育児の役割分担を見直す
- 定期的に夫婦ふたりだけの時間を設ける
ここからは、それぞれの方法について1つずつ詳しく解説していきます。
主治医や専門家に相談する
産後うつによる離婚を避けるなら、早めに主治医や専門家に相談しましょう。産後うつは自然に回復する可能性が低く、そのまま放置すると症状がさらに悪化してしまう恐れがあります。
主治医に相談して適切な治療を受ければ、産後うつの症状が改善されることで、離婚の危機的な状況を回避できるかもしれません。また、夫婦関係や育児などで困っている場合は、専門家からの客観的なアドバイスを受けることで、問題の早期解決に期待できます。
可能であれば夫婦で相談に行くのが望ましいですが、配偶者に聞かれたくない場合や一人でいたい場合は一人で相談しても良いでしょう。
| 悩み |
相談先 |
| 医療に関すること |
産婦人科・心療内科・精神科の医師、看護師、医療ソーシャルワーカーなど |
| 心理的な不安に関すること |
心療内科・精神科の医師、心理カウンセラーなど |
| 子育てに関すること |
助産師、小児科の医師・看護師、市区町村の保健福祉センター・保健所の保健師など |
| 福祉に関すること |
市区町村の保健福祉センター・保健所の保健師、児童相談所など |
| 法律に関すること |
弁護士 |
子どものケア・サポートをこころがける
産後うつは子どもの生育に悪影響を及ぼす可能性があります。そのため、産後うつを発症した場合は、無理をせず第三者に相談して、子どものケアやサポートを受けることも検討してみましょう。
子どものケアやサポートに関する相談先は、下記の4つが挙げられます。
| 相談先 |
連絡先 |
| 助産師 |
(日本産婦人科会電話相談窓口)03-3866-3072 |
| 小児科の医師・看護師 |
https://syounika.jp/ |
| 市区町村の保健福祉センター |
お住まいの市区町村+保健福祉センター+子育て相談で検索 |
| 保健所の保健師 |
お住まいの市区町村+保健所+子育て相談で検索 |
| 児童相談所 |
189に電話 |
上記の相談先の職員は、多くの親子を見てきたプロです。相談すれば、一緒に寄り添って解決方法を探してくれます。一人で抱え込むと、産後うつが悪化して子どもにも悪影響を及ぼす可能性があるため、不安なことがあったら必ず相談しましょう。
家事・育児の役割分担を見直す
産後うつの離婚を避けるためには、家事や育児の役割分担について話し合うことも大切です。話し合いの際は、相手に何をやってほしいのか具体的に伝えるようにしましょう。
「相手が察してくれるのでは」という期待を持ったり、「母親(父親)だから○○すべき」という固定概念を押し付けたりしてはいけません。夫婦一方に負担が偏らないよう、双方が納得する形で柔軟に対応しましょう。
定期的に夫婦ふたりだけの時間を設ける
夫婦関係を改善するには、定期的に夫婦ふたりだけの時間を設けることも大切です。日々のできごとや悩み、感謝の言葉など、お互いの気持ちを素直に伝え合うことで、心の距離を縮められるようになります。
その際、相手の意見にはしっかりと耳を傾けるようにし、自分の価値観の押し付けや否定的な言葉はなるべく避けるのが鉄則です。相手のことを完全に理解するのは不可能なので、お互いを尊重し合える関係性を目指しましょう。
逆に、一人になれる時間も必要です。一人の時間がないと、相手がいるのが当たり前になってしまいます。すると、相手に対する感謝がなくなり、些細な事でも喧嘩しやすくなるため離婚に近づく可能性が高いです。
一人時間を設けたほうが、夫婦二人の時間の話題が増えたりより新鮮味を感じたりするため、夫婦関係が改善されやすくなります。お互いに協力し合いながら時間をうまく使い、夫婦関係の改善に努めましょう。
まとめ
産後うつでの離婚は、協議や調停で夫婦双方が合意すれば可能です。協議や調停で話し合いがまとまらなければ裁判で離婚を請求することになりますが、産後うつのみでは法定離婚事由に該当しないため、離婚請求が認められる可能性は低いです。
ただし、相手の不貞行為やDV・モラハラなど産後うつ以外にも離婚の原因があり、それが法定離婚事由にあたると判断された場合は離婚が認められる可能性があります。離婚の手続きは自分でも行えますが、産後うつの症状の程度によってはきちんとした話し合いができず、物事を適切に判断できない恐れもあります。
産後うつで離婚を検討している場合は、早めに離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。
産後うつや離婚に関するよくある質問
産後うつで夫やこどもに迷惑をかけたくありません。どうしても離婚したいのですが可能でしょうか?
協議や調停の場合は、夫婦双方が合意することで離婚できます。しかし、相手が同意せず離婚裁判になった場合、法定離婚事由に該当する離婚の原因がなければ、離婚が認められる可能性は低いです。
産後うつを発症すると冷静に物事を判断するのが難しく、「離婚したい」という気持ちも本心で出たものであるとは限りません。どうしても離婚したい、夫と距離を置きたいという場合でもすぐには離婚せず、夫からの同意を得た上で一時的に別居したり、医者に相談して一時的に入院したりすることを検討してみましょう。
相手から離婚話を切り出されたのですが、私は離婚したくありません。どうしたらよいでしょうか?
離婚したくない場合は、相手に「離婚したくない意思や理由」をはっきりと伝えることが大切です。協議や調停では夫婦双方が合意しなければ離婚は成立しないため、離婚に応じなければ相手からの離婚請求は認められません。
しかし、産後うつの症状によって冷静に話し合いが進められなかったり、相手のペースに流されて離婚に合意してしまったりする可能性もあります。そのため、話し合いができる状況ではない場合や、一人で話し合いに臨むのが難しい場合は弁護士に相談しましょう。
妻が産後うつになってしまいました。妻が離婚したいと言っているのですが、どうすればよいでしょうか?
離婚したくない場合は、相手に「離婚したくない意思や理由」をはっきりと伝えることが大切です。協議や調停では夫婦双方が合意しなければ離婚は成立しないため、離婚に応じなければ相手からの離婚請求は認められません。
しかし、産後うつの症状によって冷静に話し合いが進められなかったり、相手のペースに流されて離婚に合意してしまったりする可能性もあります。そのため、話し合いができる状況ではない場合や、一人で話し合いに臨むのが難しい場合は弁護士に相談しましょう。
離婚の手続きはどのような流れで進みますか?
離婚する際は、まず夫婦間で離婚について協議を行います。相手から離婚の合意が得られなかった場合や交渉がまとまらなかった場合は、家庭裁判所で離婚調停を申し立てて話し合いを行います。
調停も不成立になった場合は離婚裁判を起こし、双方の主張や証拠に基づいて裁判官が離婚の可否を判断することになります。
離婚前にどのようなことを決めておくべきですか?
離婚前に決めるべきことは下記の通りです。
話し合いで取り決めたことは、後でトラブルになるのを避けるため、離婚協議書や離婚公正証書に明記しておきましょう。体調が悪い場合は無理をして交渉せず、弁護士に代理交渉を依頼するようにしてください。