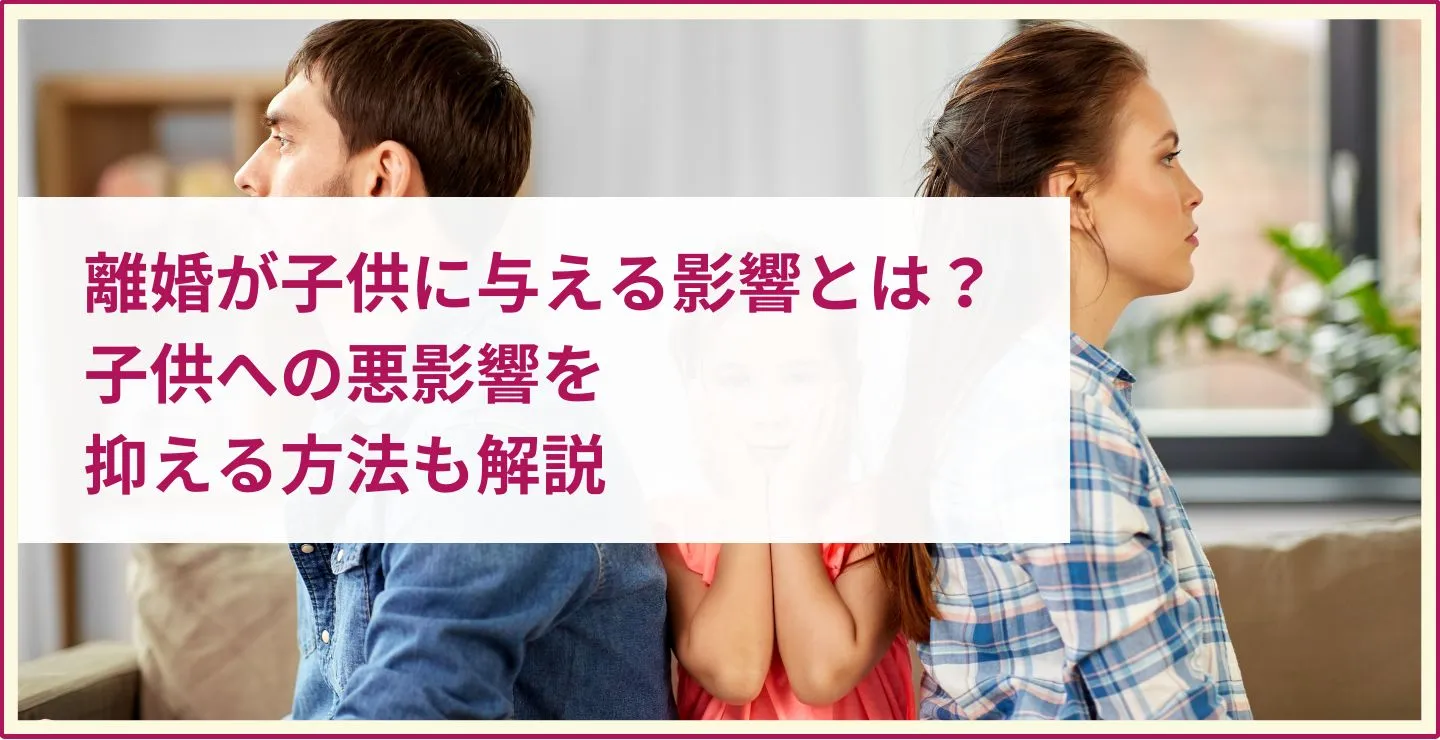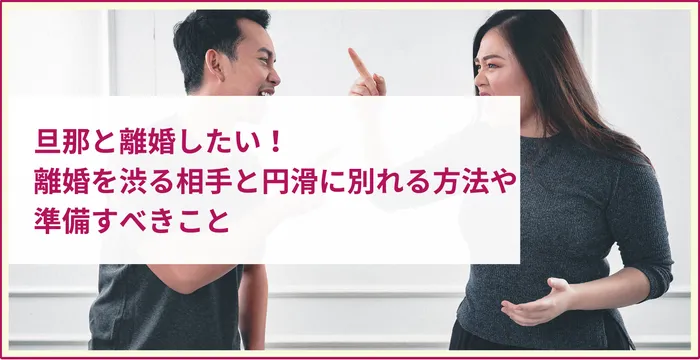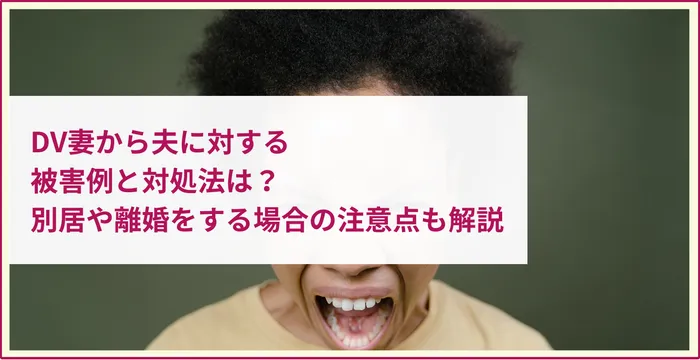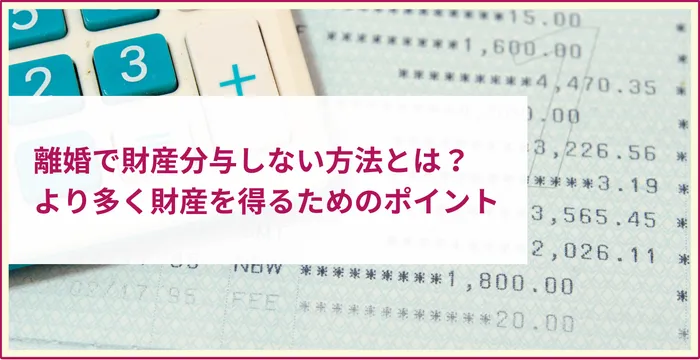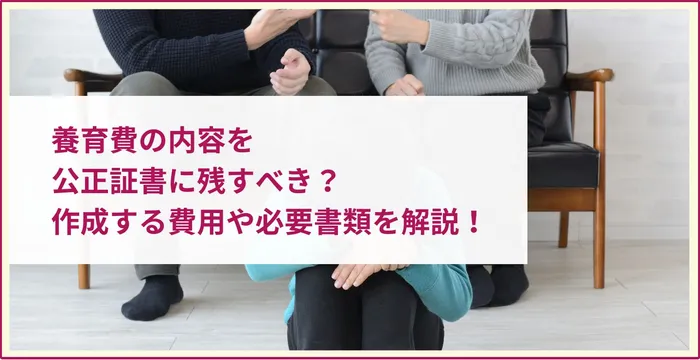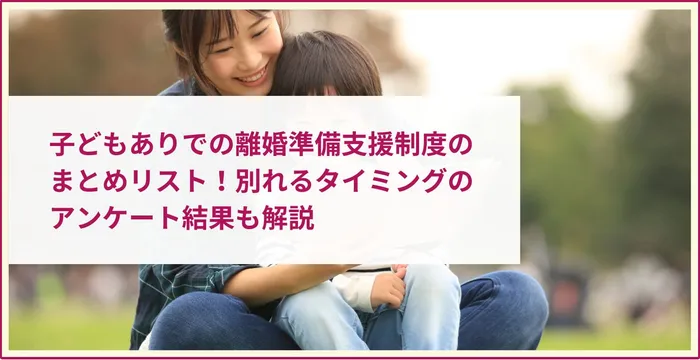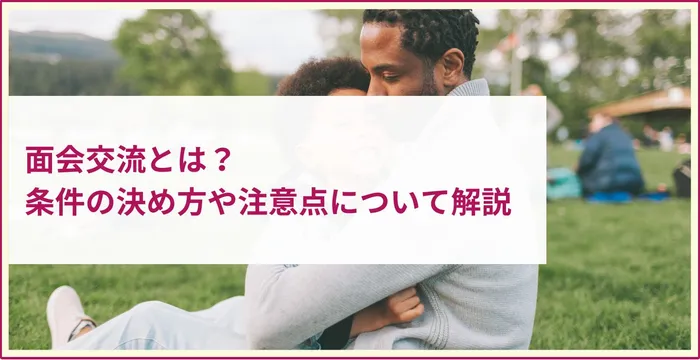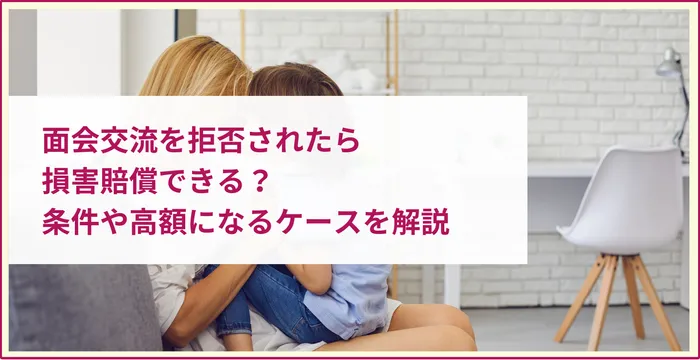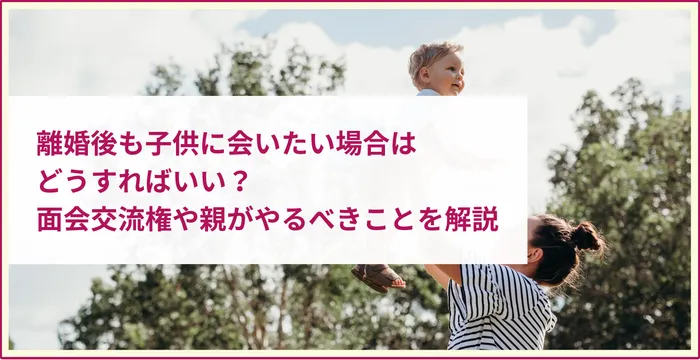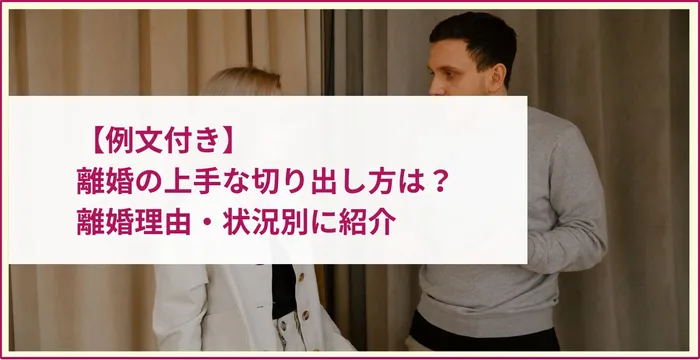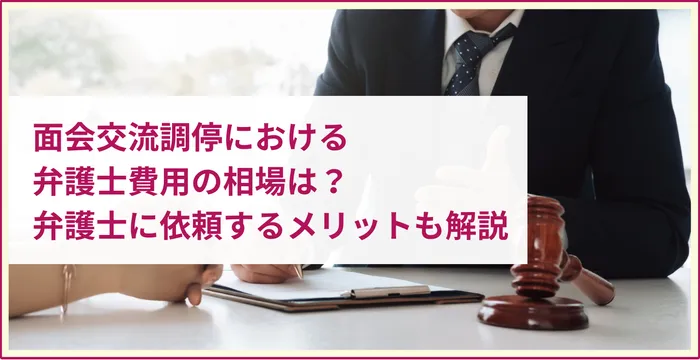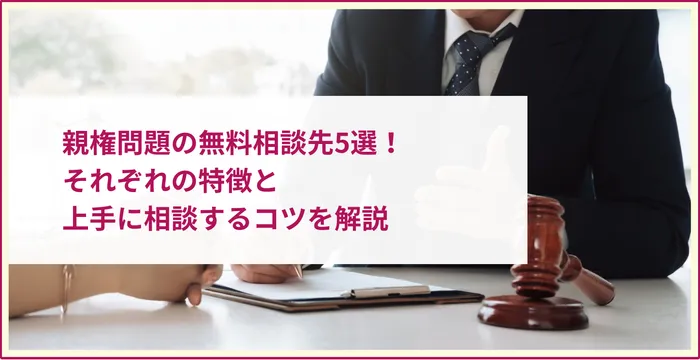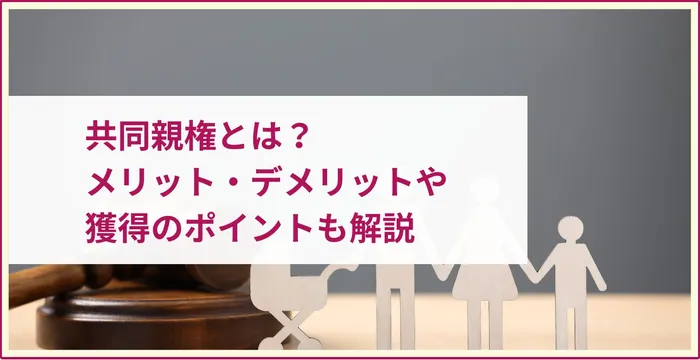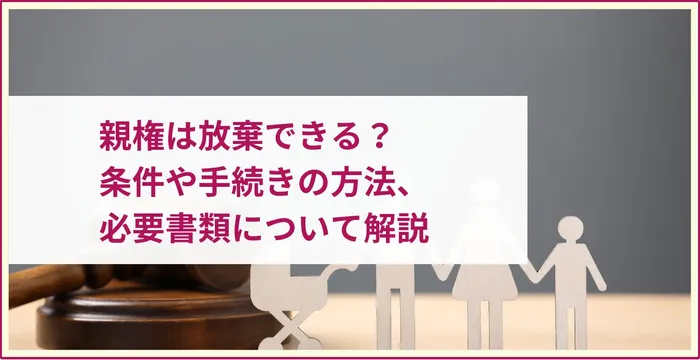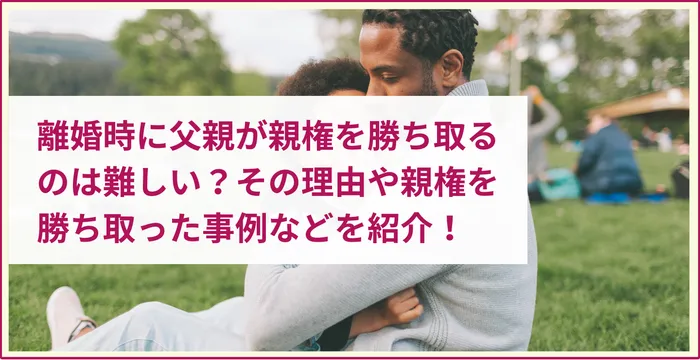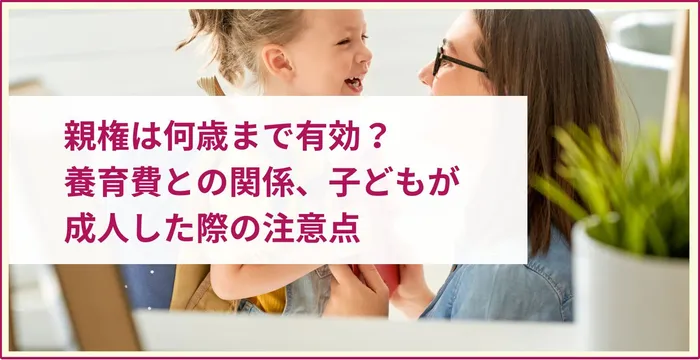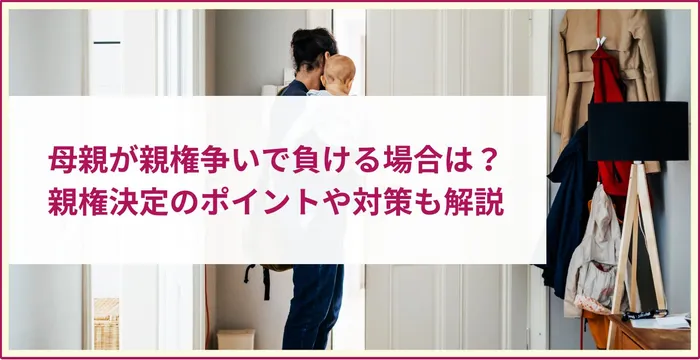離婚が子供に与える影響は?統計やデータを基に解説
離婚が子供に与える影響として気になる人が多いのは、「離婚したら子供に負担をかけるのではないか」「将来に影響しないか」といった影響だと思われます。
離婚によって子供がどのような影響を受けるかは、家庭の事情、周囲のサポートの有無、子供の気持ちなどによって大きく変化します。とはいえ、これまでのさまざまな統計情報や体験談などを確認するに、離婚が子供に与える影響にもある程度の傾向が見られました。
法務省「未成年時に親の別居・離婚を経験した子に対する調査(20~29歳500人、30~39歳500人)」などを参考にした、離婚が子供に与える影響として懸念されるものは主に以下の8つです。
- 離婚時に子供への精神的ダメージが出る
- 片方の親と会う機会が減る
- 経済的に困窮して生活水準が下がる可能性がある
- 引っ越しによって生活環境が変化し苦労する
- 大学進学率が低下する
- 子供の喫煙率や飲酒率が高くなる
- 親が離婚すると子供も離婚するリスクがある
- 子供が将来的に必要以上の負担を背負う可能性がある
離婚時に子供への精神的ダメージが出る
法務省の調査(複数回答可)によると、父母が別居したときに「悲しかった」「ショックだった」と回答した子供の割合が7割を超えています。
| 父母が別居した当時の気持ち |
結果
(609人) |
| 悲しかった |
37.4%
(228) |
| ショックだった |
29.9%
(182) |
| 将来に不安を感じた |
16.1%
(98) |
| ホッとした |
14.3%
(87) |
| 経済的な負担を感じた |
11.2%
(68) |
| 状況が変わることが嬉しかった |
11%
(67) |
| 割り切れなかった |
10.2%
(62) |
| 怒りを感じた |
9.5%
(58) |
| 恥ずかしかった |
7.4%
(45) |
| 自暴自棄になった |
6.1%
(37) |
| そのほか |
2.6%
(16) |
| とくになし |
18.2%
(111) |
参考:法務省「未成年時に親の別居・離婚を経験した子に対する調査」
同調査を見ると、父母が別居を開始する前に不仲であることを「知っていた」「薄々感じていた」と回答した人は80.8%にも上りました。子供は両親の仲の悪さを察していることが多く、離婚する前から日常的にストレスを感じているケースが想定されます。
それに加えて「一緒に暮らしていた親と離れ離れになる」という事実は、子供へ多大な精神的ダメージを与えるかもしれません。別居親と仲がよかったときは、悲哀の度合いがより大きくなるでしょう。
法務省が公開する「父母の離婚が子の生育に及ぼす影響に関する心理学的知見について」を見ても、夫婦間葛藤は子供の発達・適応の多側面でネガティブな影響が出ること、離婚前後の時期での子供の大きなストレス源になることが示されています。
参考:法務省「父母の離婚が子の生育に及ぼす影響に関する心理学的知見について」
片方の親と会う機会が減る
夫婦が離婚すると、原則として子供は別居する親と会う機会が極端に減ります。法務省の調査では、「連絡を取れなかった」「連絡を取りたくなかった」と回答したのが約半数と、離婚後に片方の親に会う機会がなくなった子供が少なくありません。
もし別居した親と会いたいのに会えないという状態になってしまうと、「見捨てられた」「寂しい」「自分は嫌われやすい」といったネガティブな感情を抱き、自己肯定感の低下につながる可能性があります。
また同居している親が別居親の悪口を吹き込むなどの影響で、子供自身が別居親と会うことを正当な理由なく拒否する「片親疎外(片親疎外症候群)」という状態に陥るリスクも存在します。
ただし別居した親と仲が悪かった、暴力・暴言がひどかったなどの状況だった場合は、むしろ会わなくなることがプラスに働くかもしれません。親と会わないで済むメリットは、虐待などから逃げられるにて後述しています。
なお離婚によって、別居親だけではなく同居親と過ごす時間が減る可能性も出てきます。同居親が生活のために仕事時間を増やしたり、仕事や家事で体力を消耗して子供をかまう余裕がなくなったりなどが考えられるためです。
経済的に困窮して生活水準が下がる可能性がある
離婚して片親の家庭になると、経済的に困窮して生活水準が下がる可能性があります。生活が困窮すると、子供に以下の悪影響が出ることが考えられます。
- 子供がほしいものを買い与えられず精神的負担をかける
- 子供が遠慮がちになって自己肯定感の低下や将来への悲観につながる可能性がある
- 子供が塾に行けない、進学を諦めるなど教育や就職に影響が出る
- 周囲との体験格差が生じて友達づくりや性格形成に悪影響が出る
- 食事の量や幅が少なくなることで栄養面の不足や子供の偏食につながる可能性がある
- 日用品や学用品、部活動用の費用などが捻出できなくなる
法務省の調査では、父母の別居が金銭面の生活状況にどのような影響を与えたのかという設問に対し、「生活水準・経済状況は苦しくなった」「若干苦しくなった」と回答したのが約4割となっています。「むしろ好転した」と答えたのは、1割未満に留まっていました。
とくに経済的問題が深刻となるのは、シングルマザーとなった家庭です。厚生労働省の調査によると、世帯の平均年収で父子家庭は518万円であったのに対し、母子家庭は272万円と約半分となっています(平均年間就労収入は父子家庭496万円、母子家庭236万円)。同調査での世帯数は母子世帯が約120万世帯、父子世帯が約15万世帯と、母子家庭が約8割強と圧倒的に多いにもかかわらずです。
日本は雇用形態や価値観の違いなどさまざまな要因によって、女性の平均年収は男性よりも低くなっているのが現実です。日本は「父親が外で稼いで母親が家庭に入る」という考えがまだ残っており、離婚後に収入の柱である父親がいなくなって生活が困窮するパターンが多く見られます。実際にシングルマザーの貧困は、日本でも大きな問題となっています。
なお、「離婚しても養育費があるのでは?」と思われるかもしれませんが、令和3年度の母子世帯の養育費(平均月額5万485円)の受給状況を見ると、56.9%が「養育費を受けたことがない」との結果となっています(平成28年度調査の結果である56%からの推測値)。平均収入が多い父子世帯だと、85.9%です。養育費の未払いも、片親世帯における問題点の1つだと言えるでしょう。
参考:
参考:厚生労働省「令和3年度全国ひとり親世帯等調査」
参考:国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」
引っ越しによって生活環境が変化し苦労する
離婚してマイホームから引っ越す親に子供が着いていく場合、住居や周辺施設・住民が変わったり転校が発生したりなどで、生活環境が一気に変化する可能性が高くなります。
基本的に子供は住む場所を親に依存するため、引っ越しによってこれまでの生活からの変化を受け入れるしかありません。しかし、引っ越しは以下の懸念点が危惧されます。
- 引越し前より狭い家で生活することになりストレスが溜まる
- 仲がよかった友達と離れ離れになってショックを受ける
- 学校や近所で新しい人間関係が築けず馴染めなくなる可能性がある
- 生活環境や人間環境の変化が要因でいじめを受けたり不登校になったりするリスクがある
法務省が公開する資料によると、生活環境の変化によって、0~5歳の子供が「生活環境の変化に対する否定的な情緒反応」、「自分がよい子にしていれば和解してくれるといった両親の仲直りに対する希望が打ち砕かれることによる自己卑下」などによって、食事・睡眠・教育面で悪い影響が出てしまう可能性があると指摘されています。
参考:「父母の離婚が子の生育に及ぼす影響に関する心理学的知見について」
大学進学率が低下する
ひとり親世帯の子供は、高校卒業後の進路で大学進学する割合が全世帯平均よりもやや低いという結果が出ています。
文部科学省の調査によると、子供の大学進学率は59.1%にあるのに対し、ひとり親世帯にフォーカスした厚生労働省の調査では母子家庭41.4%、父子家庭28.5%に留まっています(父子家庭はサンプリング数が少ない影響が出ている可能性あり)。専門学校や短大への進学も、ひとり親世帯のほうが数%ほどですが低いという結果です。
離婚という出来事そのものが、子供の学力の低下につながるという調査結果は見られません。しかし、経済的困窮による塾・習い事の断念、生活環境変化へのストレス、引っ越し対応などによる物理的な時間・労力の浪費などの悪影響が、進学率に影響していると推測されます。
第4回全国家族調査における北海道大学大学院文学研究院の研究では、ひとり親の平均教育期間が13.5年・大卒比率25.2%と、初婚を継続する夫婦の14.6%・48.4%と比較して数値が低くなっていました。ややサンプル数が少ないデータではあるものの、国の調査と合わせてみるとひとり親世帯が子供の教育に影響を与えていると考えられます。
子供の進路は、本人の希望や適性などを総合的に見て検討するものです。大学や専門学校などへの進学が、子供にとって必ずしも正解ではありません。とはいえ、お金や環境といった子供では対処が難しい問題が原因で、子供の可能性が狭まるのは決してよい状況とは言えないでしょう。離婚によって子供への負担や経済的問題が考えられるときは、子供の進路にも影響するリスクも考慮して行動を選択すべきです。
参考:文部科学省「令和6年度学校基本調査(確定値)」
参考:男女共同参画局「「共同参画」2019年2月号
」
参考:全国家族調査(NFRJ)「親の離婚・再婚と子どもの学歴」
子供の喫煙率や飲酒率が高くなる
ひとり親世帯の子供は、喫煙率や飲酒率が高くなる傾向にあると言われています。
たとえば、英国の家庭を対象にしたユニバーシティー・カレッジ・ロンドンのレベッカ・レーシー氏の調査では、7歳までに生物学上の親が不在となった子供は11歳までに喫煙・飲酒に走る可能性が2倍以上高いとの結果が出ています。
国立成育医療研究センターの調査では、3世代同居ではないシングルマザー世帯で母親が毎日喫煙するのが32%、毎日飲酒するのが12%・週に3~6回11%と2人親世帯や三代同居世帯などよりも高く、母親の習慣が子供の健康や成長に悪影響が出る可能性があると同室長が示していました。
実際に同研究センターの別の調査結果を見ると、親が喫煙者の場合だと子供の喫煙率がやや高い傾向が見られており、喫煙が多い傾向にあるシングルマザー世帯の子供の喫煙率が高くなる可能性が推測されます。
日本や外国のほかの調査では「学歴が高いほど喫煙率が低い」「生活への満足度や収入が低いと喫煙率が高い」など、ひとり親世帯が抱えがちな子供への教育・経済面でのリスクが喫煙率と結びつきやすい傾向も見られます。
喫煙や飲酒行為自体は、ストレス軽減や人付き合いの面を考えると悪いことばかりではありません。とはいえ、過度な喫煙・飲酒は健康面への悪影響や浪費などにもつながりやすいのも事実です。未成年喫煙・飲酒の可能性も考えられるので、離婚後に子供へ与える喫煙・飲酒率の影響は考慮しておくべきです。
参考:CNN「11歳までの子どもの喫煙、親と別れたケースで倍増 英調査」
参考:国立研究開発法人 国立成育医療研究センター「一人で乳幼児を育てているシングルマザーの約9人に1人が「こころの不調」の可能性 ~社会から孤立しているため、積極的な支援が必要~」
参考:国立研究開発法人 国立成育医療研究センター「家族のたばこ意識調査」
参考:Yahooニュース「「タバコ」にまつわる経済や健康の「格差」〜2018年の国民健康・栄養調査を考える」
親が離婚すると子供も離婚するリスクがある
親が離婚している子供は、子供も離婚するリスクが高くなる可能性があります。考えられる理由は次の通りです。
- 「離婚しても生活できる」「親も離婚してやっていけたから」と離婚することへのハードルが低くなる
- 夫婦間のコミュニケーション方法や夫婦関係維持のための工夫を学ぶ機会がなくなる
- 子供が結婚に抱くイメージが悪くなり結婚や婚姻継続に消極的になる
日本家族社会学会の研究では、親が離婚を経験した子供で離婚を経験している割合が29.1%と、していない子供の12.5%と2倍強の違いが見られました。
参考:日本家族社会学会「親の離婚が子どもに与える影響」
子供が将来的に必要以上の負担を背負う可能性がある
親が離婚した子供は、離婚による直接的な影響に加えて、性格や手続きなどの面で間接的な負担を強いられる可能性があります。子供が将来的に必要以上の負担を背負う可能性について、いくつか紹介します。
自己肯定感が低下によって人格形成に影響を及ぼす
子供が「離婚の原因は自分ではないのか」「親にとって自分はどうでもよい存在なのだろうか」と感じてしまうと、自己肯定感が低下する可能性があります。自己肯定感の低下は人格形成にも影響を及ぼし、暴力・暴言などの理不尽への諦観や受け入れ、挑戦や努力の否定、対話の経験不足によるコミュニケーション能力低下などの悪影響が考えられます。
相続関係の手続きが複雑化する
実子は離婚に関係なく、父親・母親の財産のいずれも相続する権利を引き続き有します。別居親が再婚して新しい子供をもうけたり、連れ子を養子縁組にしたりしても同様です。
しかし、相続関係の手続きを進める際に、以下の原因で複雑化する可能性があります。
- 疎遠だった親や親族、再婚相手の親族などとの連絡のやり取りが発生する
- 相続権が複雑化して遺産分割などで争いが発生しやすくなる
- 相続人を把握しきれずに手続きがなかなか進められない
片親という理由で結婚を反対される可能性がある
統計データがあるわけではないものの、片親という理由だけで相手の親から結婚を反対される事例や体験談が見られます。
相手の親からすると、「片親だと教育が行き届かずしつけの面で問題があるのではないか」「同居しなければならないのか」「結婚後も経済的支援や介護がつきまとうのでは」などの心配事があるからだと考えられます。
離婚によって子供によい影響を与えるケース
離婚による子供への悪影響が懸念される一方で、むしろ離婚したほうが子供や自分にとってもプラスになるケースも存在します。離婚によって子どもによい影響を与えるケースとしては、以下のものが挙げられます。
- 子供と別居親の仲が悪かったときは子供が生活しやすくなる
- 虐待などから逃げられる
- 財産分与や養育費・借金の状態によってはお金を使いやすくなる
子供と別居親の仲が悪かったときは子供が生活しやすくなる
子供と別居親の仲が悪かったときは、離れたことで子供が生活しやすくなる可能性が高くなります。
親子間の仲が悪いと、子供は「怒られないように無意識に気を使う」「できる限り接触しないように気を張って生活する」「不機嫌な親に対して反抗心や恐怖を覚える」などの心理状態になっている可能性が想定されます。離婚によって仲が悪い親と離れられれば、子供にとってのストレス源がなくなり暮らしやすくなるはずです。
実際に法務局の調査では、離婚によって「ホッとした」「状況が変わって嬉しい」といずれかを回答した人が約25%となっていました。「今の家庭状況が続くくらいなら離婚してほしい」と感じる子供も、一定数見られます。
虐待などから逃げられる
別居親が日常的に虐待や無関心な態度などを子供へおこなっていた場合は、離婚が子供を守ることにつながります。
「逆境的小児期体験が子どものこころの健康に及ぼす影響に関する研究」によると、心理的・身体的虐待やDV被害などの逆境的小児期体験((Adverse Childhood Experience:ACE)スコアが高いほど、自殺企画(自殺を企てること)、薬物注射、鬱気分、性の乱れ、喫煙などのリスクが数倍~数十倍になっていました。
夫婦の離婚による精神的ダメージや喫煙率・飲酒率の上昇なども懸念すべきとはいえ、日常的な虐待などが発生しているときは、子供の心身や将来を考えて離婚・別居をすぐにでも検討すべきでしょう。
参考:公正労働科学研究成果データベース「逆境的小児期体験が子どものこころの健康に及ぼす影響に関する研究」
財産分与や養育費・借金の状態によってはお金を使いやすくなる
離婚による経済的リスクは存在することは、経済的に困窮して生活水準が下がる可能性があるの見出しでも解説済みです。しかし、別居親の借金や浪費などがひどいときは、離婚によって財産や家計を別にすることで、むしろ家族でお金が使いやすくなる可能性があります。
また、離婚によって経済的問題が発生するリスクがあるとは言っても、夫婦で財産を分け合ったり相手へさまざまな請求ができたりなど、離婚時に今後の生活の資金をいくらか確保することは可能です。具体的には次の通りです。
- 原則として夫婦が一緒に築いた共有財産はそれぞれ2分の1ずつ財産分与される
- 相手の不法行為(不貞行為や不貞行為やDV・虐待・育児放棄など)が原因で離婚するときは慰謝料請求ができる
- 適切な養育費を設定すれば毎月の収入になる
- ひとり親向けの公的な支援制度を利用できる
財産分与や養育費については、経済的に安定した生活を送らせるために金銭面を明確に決定するにて詳細を解説しています。
離婚を子供はどのように捉える?成長過程別の接し方も紹介
離婚が決まると、子供はどう思うのか不安に感じる親も多いでしょう。子供が離婚をどう捉えるかは、年齢によって異なる傾向があります。以下では、子供が離婚に対して感じやすいことを、年齢別にまとめました。
- 乳幼児:漠然とした寂しさを覚える
- 小学生:周りの友達と自分の違いを感じる
- 中学生:ひとり親家庭だと強く意識する
- 高校生:離婚の事実を受け入れやすい
【乳幼児~就学前】漠然とした寂しさを覚える
就学する前の乳児・幼児は、両親が離婚したことを理解できないケースがほとんどでしょう。しかし、気を付けなくてはいけないのが「愛情不足」です。
乳幼児期の中でも特に2歳ごろまでは、親の愛情が何よりも大切な時期です。その時期に、片親になって生活を支えなくては…と仕事を頑張りすぎると、子供は親といる時間が少なくなってしまいます。親からの愛情が不足すると、子供は不安定になりやすいです。
また4歳・5歳ごろになると、友達には両親がいるのに自分には親が1人しかいないことに気づき、漠然とした寂しさを感じます。発達が早い子は、両親が離婚したことをなんとなく理解し、親に迷惑をかけちゃいけない、良い子でいなくてはならない、と自分自身を追い込んでしまう場合があるでしょう。
生活リズムを整えながら、子供と触れ合う時間を作るように心がけることが大切です。また親のイライラや不安は子供の人格形成にも影響します。子供の前ではできるだけ穏やかに、そして笑顔で過ごすようにしましょう。
【小学生】両親がいる子供との違いを感じる
小学生になると、両親が離婚した事実をきちんと理解します。そして、両親がいる家庭と自分の家庭は違うことを感じるようになるでしょう。
しかし、事実は理解していてもなかなか気持ちに整理がつかないものです。
親が落ち込んでいたり辛そうにしていたりすると、子供も不安な気持ちになります。親に相談したい悩みがあっても、気を遣って話せなくなる子供も多いです。
幼児期と同様に、常に良い子でなくてはならないと追い込みすぎてしまうかもしれません。子供の不安に寄り添いながら、親が余裕のある態度で接して安心感を与えましょう。
【中学生】ひとり親家庭であることを強く意識しやすい
中学生は、思春期に差し掛かる年代です。とてもデリケートな時期なので、両親の離婚によって「ひとり親家庭」であることを強く意識します。
しかし、親に寂しさや不安を感じ取られるのを嫌い、自分の感情や意思をはっきりと見せなくなることも珍しくないでしょう。子供が平気そうにしているからと不安定な感情を見逃してしまうケースも少なくありません。
もう親のことで頭を悩ませたくない、自立したいという気持ちで非行に走ってしまう場合もあります。親が子供の様子をチェックし、しっかりとサポートしましょう。
総務省の国勢調査や警察庁の犯罪統計書などを見ると、非行少年の出現率が両親あり世帯よりも母子家庭で2~3倍、父子家庭で4~5倍になるとの結果もあります。
【高校生】両親の離婚を受け入れやすい
高校生になると、子供は両親の離婚を素直に受け入れてくれるケースが増えます。親の事情を理解し、冷静に受け止めてくれるでしょう。
自立した人間として子供に接しながら、親として子供に対する責任をしっかりと果たすことが大切です。
特に気を付けなくてはいけないのが、経済状況の心配から子供が希望する進路を諦めなくても良いようにサポートすることです。自分自身の将来を見据えた進路が選択できるように、よく話し合いましょう。
離婚が子供に悪影響を抑える方法
離婚によって想定される子供への悪影響を抑えるには、子どもとの対話や事前準備が非常に重要です。離婚が子供に与える悪影響を抑える方法として、以下のものが挙げられます。
- 離婚についてしっかりと説明する
- 経済的に安定した生活を遅らせるために金銭面を明確に決定する
- 子供と愛情のあるコミュニケーションを取り寂しさや不安を取り除く
- 面会交流の頻度を明確にし別れた相手との交流機会を決めておく
- 子供への影響を抑えられる離婚タイミングを考える
- 第三者のサポートを受ける
離婚についてしっかりと説明する
離婚について子供に話すのは、避けては通れないことです。しかし、伝え方や伝える内容を間違えると、子供に与える精神的ダメージが大きくなってしまう可能性があります。離婚について
以下では、離婚について説明する際の注意点について解説します。
嘘や悪口を言わずに伝える
子供に離婚を伝える際は、別居親や子供に関する嘘や悪口は言わずに伝えることが大切です。
子供にショックを与えないように嘘を伝えようと考えるかもしれませんが、嘘はいつかバレます。嘘がバレたとき、子供は親のことを信じられなくなってしまいます。
また、親の一時的な感情から離婚する相手の悪口を言ったりする行為も禁物です。離婚をする当人同士にとっては、憎い相手かもしれません。しかし、子供にとってはたった一人だけの母親・父親です。
親の悪口を言われることで自分自身を否定されているような気持ちになってしまいます。子供には嘘をつかず正直に、そして悪口を言わずに伝えましょう。
とはいえ、状況によっては子供へ伝えないほうがよい事実もあります。そのときは嘘でごまかすのではなく、子供が大きくなったら話すとあらかじめ伝えたり、子供が自分の意思で知りたいと思うまで自分の中で留めておくなど、誠実さを損なわないうえで伝えない工夫を凝らすことが大切です。
離婚の理由が子供ではないと伝える
両親が離婚すると、子供は自分に原因があったのでは?と思い込んでしまうものです。その思い込みで自責の念に駆られると、子供は辛い思いをし続けてしまいます。
また「あなたのために別れた」という言葉も禁句です。子供のためと思ってした離婚でも、そう伝えると子供は自分のせいだと思ってしまいます。
離婚は絶対に子供のせいではないことは強調し、ちゃんと理解できるまで繰り返し伝え続けましょう。
離れた相手も親であることを伝える
離れて暮らすようになった相手に「捨てられた」と勘違いする子供は多いです。とくに小さな子供は、一緒に暮らさなくなる=自分の親ではなくなった、と理解してしまいます。
離婚をして離れて暮らすようになっても親であることに変わりはない、会いたくなったらいつでも会えると伝えることが大切です。
経済的に安定した生活を送らせるために金銭面を明確に決定する
離婚を検討する際には、経済面の問題が大きな障害になります。子供に経済的に安定した生活を送らせるためにも、金額面での明確な離婚条件の決定や公的制度の利用などが、子供との安定した新生活を送るためのポイントです。
新生活に向けて明確にしておくべき、金銭面の条件などは次の通りです。
- 財産分与を適切におこなう
- 養育費の金額や時期を明確に決めペナルティを定める
- 離婚後も利用できる公的制度を調べておく
財産分与を適切におこなう
夫婦が離婚するときは、婚姻生活中に築いた財産を2分の1ずつ分けるのが原則です。とはいえ、夫婦の合意があれば分配する財産の量や内容を自由に決めることを認められています。
そのため、夫婦間で財産分与について話し合うときは、子供の新生活や将来を考慮した分配できないかを考えることが大切です。「子供のために住居や預貯金は多めにもらう代わりに、車や土地などの財産は多めに譲る」といった折衷案にできないか検討してみてください。
また、財産分与時のポイントとして「子供自身の財産」は分配の対象外になる点も忘れないようにしておきましょう。子供が稼いだアルバイト代、子供がもらったお年玉やお小遣い、入学祝いといった子供自身へのお祝いごとに対するお祝い金など、子供名義の金銭は子供がそのまま所有します。
さらに、「長らく専業主夫(主夫)だったので離婚してすぐに安定した収入を得られない」「子供がまだ幼くフルタイムで働くのが難しい」など、片方の親が離婚後に生活が困窮する懸念がある場合、経済的余裕のある親が一定期間金銭的なサポートをおこなう「扶養的財産分与」が認められる可能性があります。
適切な財産分与には、財産分与の対象になる財産(共有財産)と対象にならない財産(特有財産など)を区別しておくことも重要です。
養育費の金額や時期を明確に決めペナルティも定める
相手からの養育費を確実に受け取るには、必要な生活費や相手の収入を考慮した養育費の金額や支払時期の条件設定が必要です。加えて、養育費が未払いになったときのペナルティも同時に決めておきましょう。
具体的には、「未払いのときは強制執行(裁判所の許可を得て財産を差し押さえる行為)をおこなう」と取り決めておくことです。養育費未払いに関して強制執行をおこなうには、あらかじめ離婚協議書を作成しておき、協議書のなかで強制執行について記載し合意を得ておきましょう。強い証拠力を持つ離婚協議書とするには、公証役場にて公証人の立ち会いのもとで作成する「公正証書」として作成することを推奨します。
離婚後も利用できる公的制度を調べておく
2025年時点では、ひとり親や子供が対象のさまざまな公的制度が設けられています。離婚後の経済的問題の解消に効果的なものばかりなので、利用できないかを一度確認してみてください。
離婚後も利用できる公的制度の例は、次の通りです(2025年5月時点)。
| 公的支援の例 |
概要 |
| 児童扶養手当 |
・父母が離婚した子供、父が死亡した子供などを監護している母または養育者に支給される手当
・1人なら満額4万4,460円、2人目以降は約1万円前後の加算(月額) |
| 住宅手当 |
・ひとり親世代で一定額以上の家賃を支払っている人が対象の手当
・自治体の決まりに応じて数万円程度の支給(月額) |
| ひとり親家庭医療費助成制度やこども医療助成 |
自治体ごとに設定されたひとり親世帯や子供を対象にした医療費助成 |
上記以外にもさまざまな公的制度があるため、一度自治体などへ確認してみてください。
子供と愛情のあるコミュニケーションを取り寂しさや不安を取り除く
親の愛情は、子供にとって「心の栄養」です。常に愛情をもって接するように心がけましょう。離婚後、子供は親からの愛情が感じにくくなると「置き去りにされているのでは?」と不安を覚えます。自分がこれからどうなってしまうのか、とにかく不安だらけです。
子供には愛情を注ぎ続け、態度で示すだけでなく言葉でも伝えるように意識して子供を安心させましょう。寂しさや不安を取り除き、子供の自己肯定感や積極性が育つよう導いてあげることが大切です。
面会交流の頻度を明確にし別れた相手との交流機会を決めておく
離婚の原因が特別なもの(DVや虐待など)ではないなら、別れた親とは面会交流などを通じて交流も継続させるのが理想的です。面会日を定期的に設けるだけでなく、子供が連絡したいときに連絡できるようにしましょう。
また子供の写真や動画を送るなどして、別れた親にも「親」である自覚を持たせる働きかけも重要です。
子供によっては、一緒に暮らしている親に悪いのでは…と遠慮して会いたいと思っていてもなかなか言い出せないことがあります。「親であることに変わりはないから、遠慮せずに交流してほしい」と伝えると、子供も面会交流がしやすくなります。
法務省の「父母の離婚が子の生育に及ぼす影響に関する心理学的知見について」によると、離婚後も両親との関係の良好さや生活環境のよさがネガティブな影響の予防・軽減に影響するとされています。
子供への影響を抑えられる離婚タイミングを考える
離婚するタイミングをある程度コントロールできそうなときは、「子供への影響を抑えられるタイミング」を考えるのも重要です。
たとえば子供が受験期間中だったり、就活中だったりなどの時期だと、離婚によって子供に負担がかかると進路に影響が出るかもしれません。比較的子供の影響を抑えられるとされるタイミングは、主に次の通りです。
| 離婚タイミング |
概要 |
| 離婚後の生活基盤が整ったとき |
新生活の目処が立っているならスムーズに離婚を進められる |
| 離婚に有利な証拠が揃ったとき |
不貞行為や悪意の遺棄などの証拠があれば離婚成立や慰謝料請求の争いで望む結果を得やすくなる |
| 子供の進級・進学に合わせる |
新学期という人間関係が切り替わりやすい時期に合わせた引っ越しや名字変更がしやすい |
| 子供の受験の終わり |
受験を終えて無事に新たな生活への一歩を踏み出す頃に合わせることで受験への影響を最小限にできる |
| 税制を考えた時期 |
・男性なら12月中以外の離婚で配偶者控除や扶養控除を受けられる
・女性なら12月31日までの離婚で寡婦控除・ひとり親控除を1年分の所得に控除が適用される |
株式会社Clamppyが実施したアンケート(281人)を見ると、実際に離婚したタイミングでもっとも多かったのが「離婚後の生活基盤が整ってから」が23.8%(67人)、続いて「離婚に有利な証拠が揃ってから」が12.8%(36人)となっていました。
参考:国税庁「No.1170 寡婦控除」
参考:国税庁「No.1171 ひとり親控除」
第三者のサポートを受ける
子供が親の離婚をなかなか受け入れられず、悩んでいる場合は第三者への相談も視野に入れましょう。子供にとって信頼できる相談相手を見つけることも、親としての役目です。第三者のサポートを受けて離婚をうまく消化できれば、子供のストレス軽減や非行の防止にもつながります。
また、親が頼れる第三者を見つけることも大切です。親族や公的サービスなどを含め、サポートを受けながら子育てをすることが子供の気持ちの安定にもつながります。シングルマザー・ファザーが交流しながら悩み相談ができる民間団体なども利用してみましょう。
親が離婚した人の体験談
実際に親が離婚した人のさまざまな体験談を、以下でまとめました。
中学1年生のときに離婚。原因は母の不倫。「どっちの親についていくのか考えてほしい」と突然言われたが、最終的に金銭的に安定している父を選択。自分の気持ちを理解してくれるかわからない不安や相手の気遣いが嫌だった時期があったものの、高校1年生のときに母の再婚と父の新しい恋を見て「幸せそうな姿が見れて良かった」と感じ、気持ちが落ち着いた。自分が結婚するときも、よい意味で結婚に対して過剰な期待をせずに済んだ、夫婦で納得できるなら世間の考え方は気にする必要がないと思えるようになった。両親に対して許せないと思うこともあるけど、新しい価値観を持てたことにはとても感謝している。ひとり親やこれからひとり親になる人は、お互いに「お前のせいだ」と言ってるくらいなら、それぞれが幸せになる方法を選んでほしいと思う。
別居親が「会いたい」とアクションを起こしてくれる姿勢は純粋に嬉しいが、養育費の支払いを守らなかったことには大人の責任としてどうかと思う。
離婚後も「いつか両親はまた一緒になる」と思っていた。しかし結局は両方とも再婚し、悲しかったが離婚の事実に目を向けられるようになった。
「夫婦間の葛藤に子供を巻き込まないでほしい。子供は両親間の葛藤を見るとキズが増えていく」「子供は状況を一方的に押し付けられるだけなので、大人がもっと理解してほしい」「隠しているつもりでも、子供は親の感情をすぐに察する」
親は子供の気持ちをわかった気にならないでほしかった。聞かれたときは自分の気持ちを言えないままだったし、勇気を持って伝えたときは逆に聞いてもらえず諦めた。
参考:東京都福祉局「中学1年生の時に両親が離婚した麗さんに話を聞きました。」
参考:Yahooニュース「「子どもの気持ちをわかった気にならないで」~親の離婚を経験した当事者たちが大人に伝えたいこと」
複雑な離婚問題は弁護士への相談がおすすめ
離婚が子供へ与える悪影響を抑えたいときに大切なのは、「子供のために財産分与や養育費についてしっかり決める」「面会交流を適度に設定する」「虐待親から迅速かつ安全に引き離す」などが挙げられます。
しかし、これらは相手からの反論や法的な手続きなどが絡んでくるため、合意のうえでの離婚だとしても話し合いがスムーズに進むとは限りません。相手によっては、子供や自分への暴力行為、脅迫、威圧などで無理やり従わせようとしてくる危険性もあります。
子供への悪影響を抑えた離婚にしたい人は、弁護士への相談がおすすめです。離婚に強い弁護士なら、子供の将来に向けた離婚条件を客観的かつ法的に決定・通知できます。弁護士は交渉の代理人にもなれるため、相手と直接やり取りしたくない人は弁護士に代わりの対応を依頼することも可能です。
当サイト「ツナグ離婚弁護士」なら、相談内容や都道府県ごとに条件を絞って弁護士を無料検索できます。弁護士事務所の情報や強みなどをコラム記事にまとめているため、あなたの状況にぴったりの弁護士を見つけられるはずです。
まとめ
離婚は、どのような理由であっても子供に悪い影響を与える可能性があります。両親の離婚で生活環境が変わると「これから自分はどうなってしまうのだろう」と漠然とした不安に襲われるのです。それに拍車をかけるように、親が前よりも忙しくなってコミュニケーション不足になる、離れて暮らす親と気軽に話ができなくなる、経済的に厳しい生活になるなどの変化が、より子供を苦しめます。
子供に与える影響をできるだけ減らすために、離婚をする理由をきちんと説明し、これからも生活は何ら変わりがないこと、両親として生活をしっかりとサポートし、愛情を注ぎ続けることを丁寧に伝えましょう。また、子供にとって影響の少ないタイミングを選び、負担をかけない配慮も大切です。
ただし、家庭内の空気が殺伐としていたりDVやモラハラが起こっていたりする場合は、タイミングを見計らっている場合ではありません。離婚しないことのほうが子供に悪影響を及ぼすため、できるだけ早めの離婚をおすすめします。
離婚が子供に与える影響に関するQ&A
再婚するときに子供へ与える影響は?
離婚と同じく、再婚するときにも子供へ大きな影響が出る可能性があります。悪い影響として挙げられるのは、「再婚相手と子供の相性が悪い」「子供が別居親への依存が強くなる」「再婚相手からの虐待がある」などです。一方、よい影響としては「経済的な安定が得られる」「育児・教育面が充実して子供の健やかな成長につながりやすくなる」などが挙げられます。
すぐに離婚を検討すべきケースはある?
以下の場合は、タイミングや離婚後の生活の不安で悩むよりも先に、
すぐにでも離婚しましょう。
- 家庭環境が殺伐としている
- DVやモラハラが起こっている
家庭環境が殺伐としている
両親の不仲により、毎日のように激しい言い争いをしている場合や家庭内別居状態の場合は、すぐにでも離婚しましょう。子供にとって、親が言い争いをしている姿を見たり、家庭内の不穏な空気を感じ取ったりすることは、大きなストレスです。
ひとり親家庭になるよりも、両親がそろっていることのほうが悪影響を与えます。タイミングを待たず、すぐに離婚を検討してください。
DV・モラハラが起こっている
家庭内でDV・モラハラが起こっている場合は、子供の心身に悪影響を及ぼします。暴力や暴言が普通のことだと思ってしまい、やってはいけないことという認識が育たないケースもあります。そんな親の姿を見ていると、子供自身が他人に暴力をふるったり暴言を吐いたりする人になってしまうでしょう。
そうではなかったとしても、暴力や暴言で傷つけられている親を見ることは、子供にとって辛いものです。攻撃する側の親を軽蔑したり憎んだりして、離婚後は二度と会えなくなる恐れもあります。
子供の心に深い傷を与える前に、今すぐ離婚を決意しましょう。