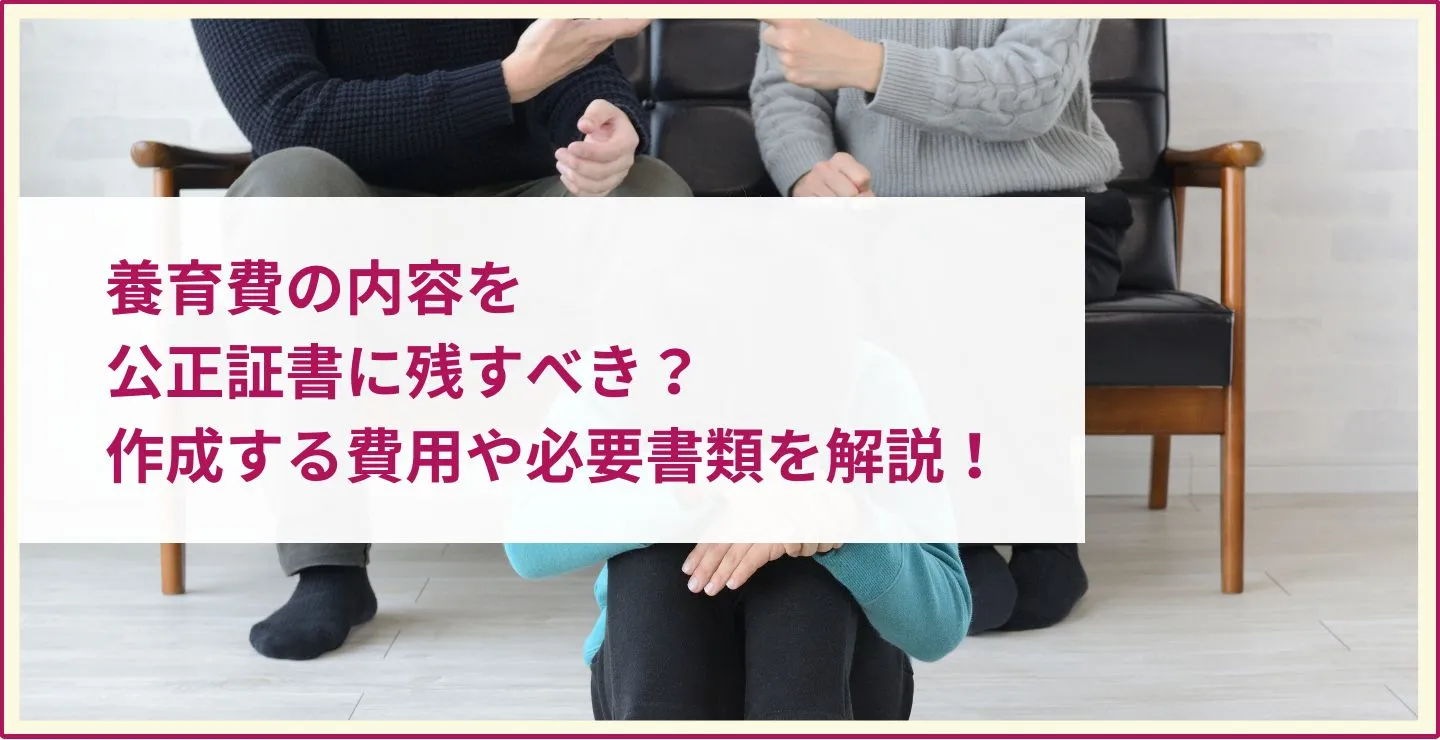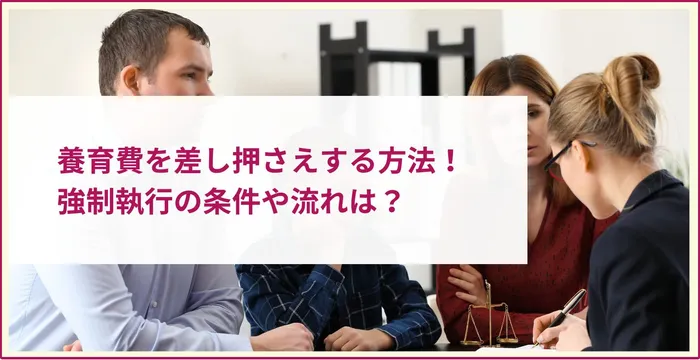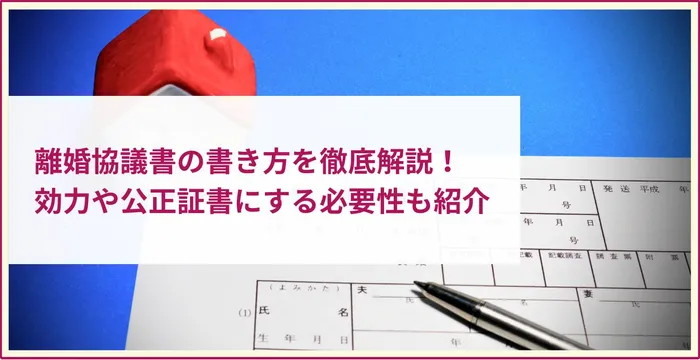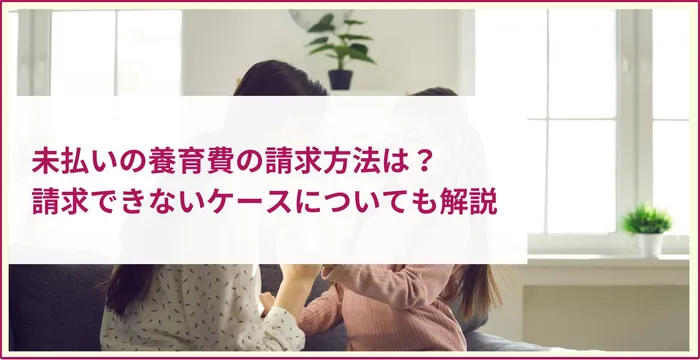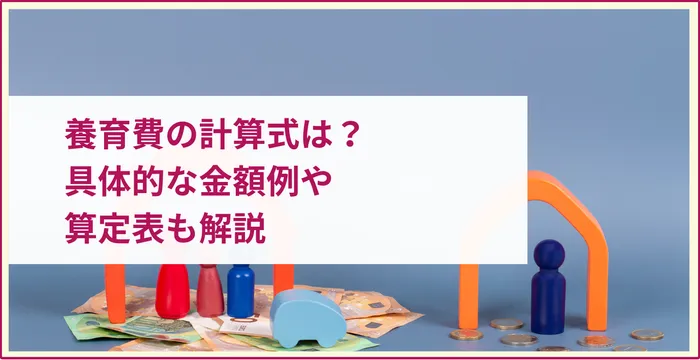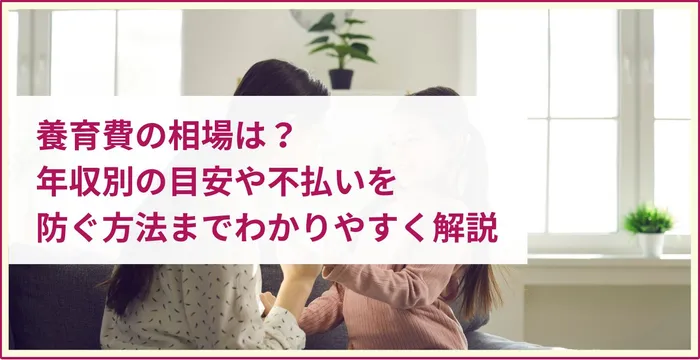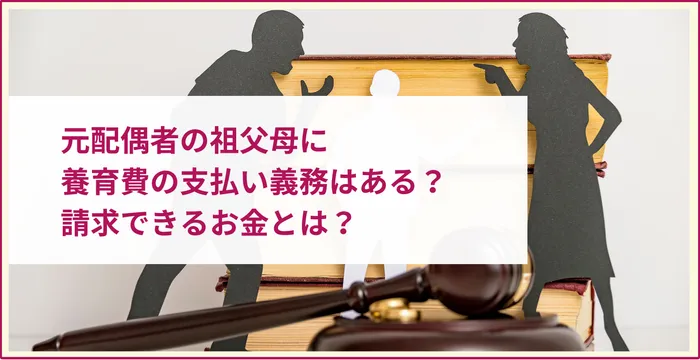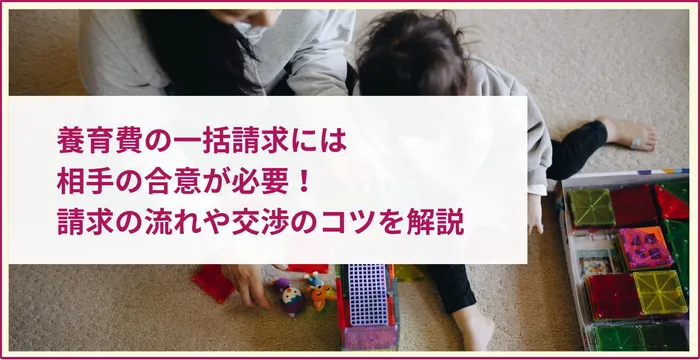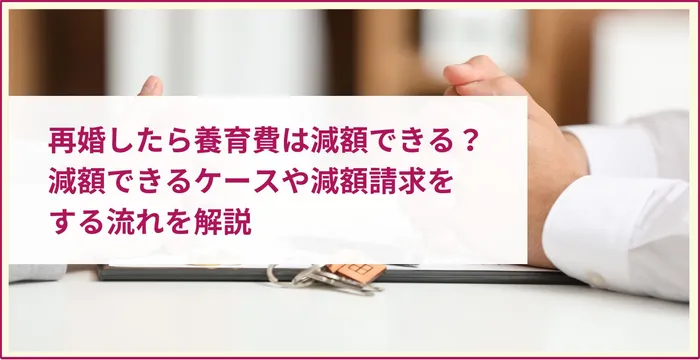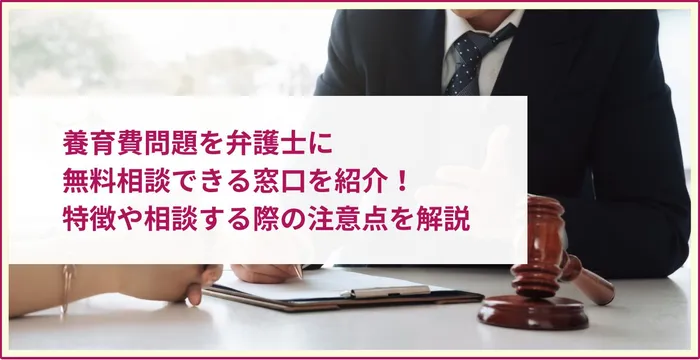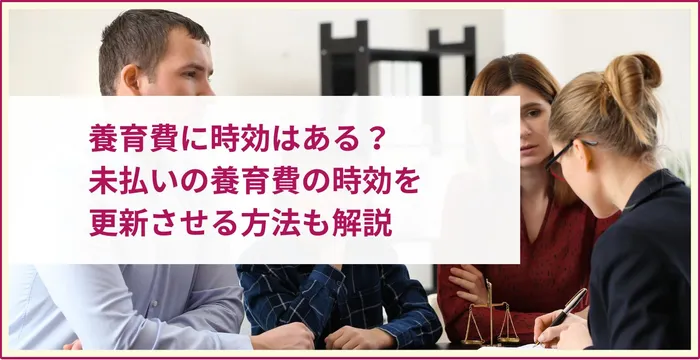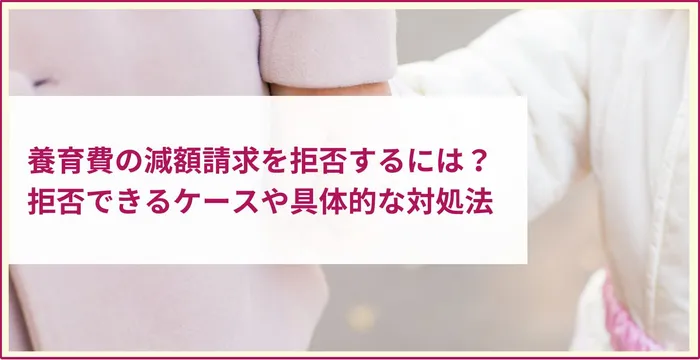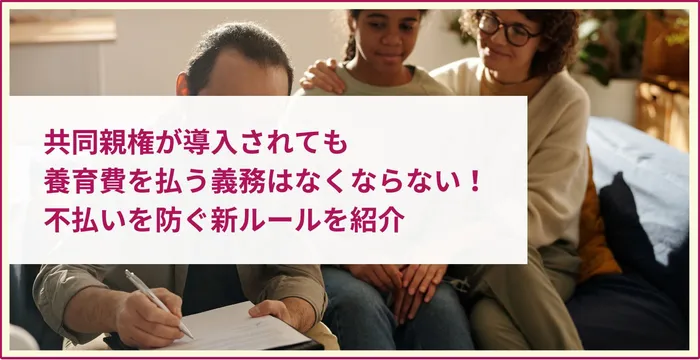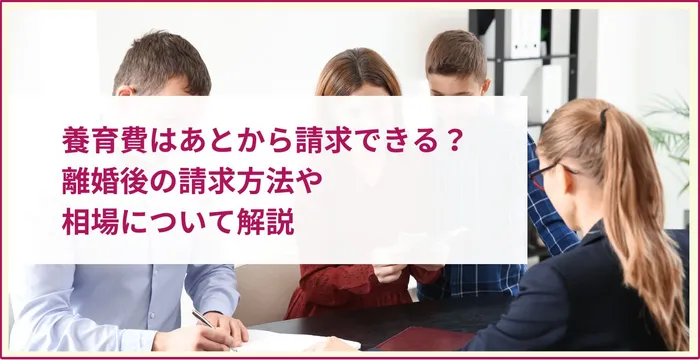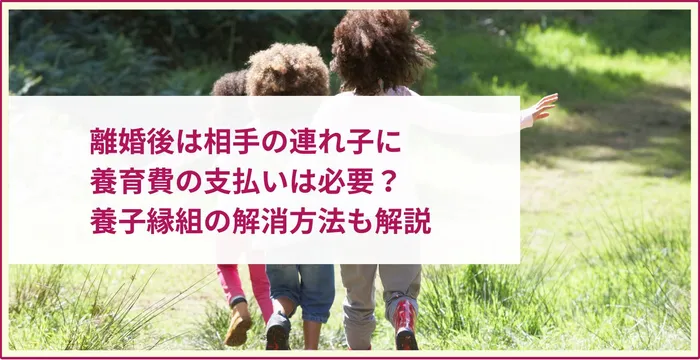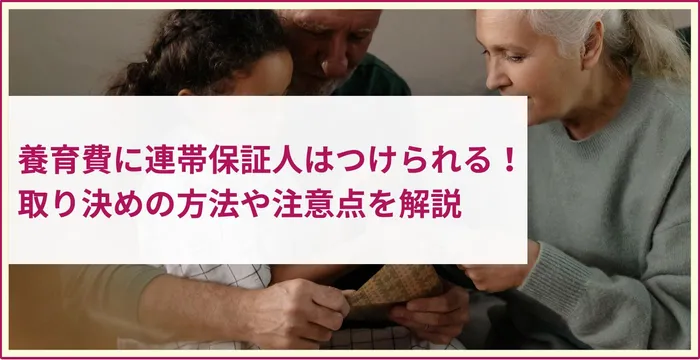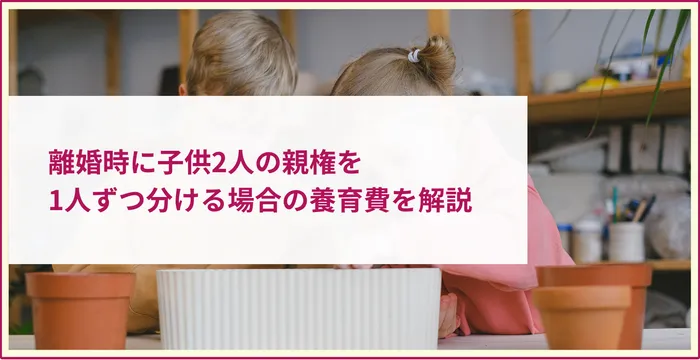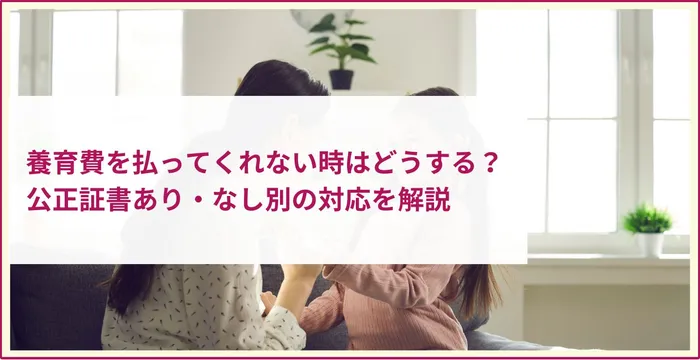養育費の内容を公正証書に残すべき?
結論からいえば、養育費は「強制執行認諾文言」をつけて必ず公正証書を残しておくべきです。なぜなら「強制執行認諾文言」を公正証書に残しておけば、養育費が支払われなかった場合にも、裁判をせずに財産の差し押さえができるためです。
また、公正証書に養育費の内容を残しておくと心理的プレッシャーも与えられ、未払いの予防にもつながります。
口約束だけでも可能ですが実際には、養育費の支払いが途中で止まってしまうケースも少なくありません。現在も養育費を受け取っている母子家庭は28.1%にとどまっているのが実情です。
※参考:令和3年度全国ひとり親世帯等調査
養育費は20年近く支払いが続くケースもあるため、途中で支払いが止まってしまうリスクもあります。支払条件を明確に残すためにも、公正証書を作成しておきましょう。
詳しくは次の章で説明します。
養育費の内容を公正証書に残すメリット
養育費を公正証書に残すメリットは、以下の3つです。
- 強制執行認諾文言を付けておくと裁判をせずに強制執行できる
- 法的な効力があるためトラブルになりにくい
- 心理的なプレッシャーで養育費の未払いリスクを減らせる
それぞれ詳しく解説します。
強制執行認諾文言を付けておくと裁判をせずに強制執行できる
公正証書には「強制執行認諾文言」を残すことができます。
強制執行認諾文言とは、養育費を支払う側の親が支払いを滞った際は、直ちに強制執行されてもやむを得ないという内容を認める旨の文言です。
この文言をつけておけば、養育費の未払いが発生しても調停や審判といった家庭裁判所での手続きをせずに、相手の給料や財産を差し押さえられます。
また、養育費は、将来分もまとめて差し押さえることが認められているため、一度強制執行を行えば、その後は相手の給与から継続的に養育費の支払いを受けることが可能です。
なお、取り決めた養育費の内容について公正証書を作成していても、強制執行認諾文言がなければ強制執行はできません。
そのため公正証書を作成する際は、必ず強制執行認諾文言を付けるようにしましょう。
法的な効力があるためトラブルになりにくい
養育費の取り決めを夫婦間の口約束だけで済ませてしまうと「そんな約束はしていない」「取り決めた内容と違う」といった、トラブルに発展してしまう可能性があります。
一方、公正証書は公証人という法律の専門家が、当事者の立ち会いのもとで内容を確認しながら作成する公文書です。そのため、後になって相手から内容を争われるリスクが低くなります。
また、公証人が当事者からの依頼に基づいて作成しているため、反証がない限り完全な証拠力を有します。
さらに、誤解のないよう明確な表現で文章を作成するため「文言の解釈が違った」といったトラブルも避けやすくなるでしょう。
なお、公正証書は原則20年間、公証役場に原本が保管されます。書面を紛失しても内容の確認や再発行できるため「書類が見つからず請求できない」といったトラブルを防ぐことが可能です。
ちなみに、当事者同士で「離婚協議書」を作成するケースもありますが、公正証書ほどの証拠力はありません。紛失してしまった場合には内容を証明できなくなり、養育費の請求が難しくなるおそれもあるため、養育費の取り決めは公正証書として残しておくとよいでしょう。
心理的なプレッシャーで養育費の未払いリスクを減らせる
公正証書に養育費の内容を残しておくと「きちんと支払わなければいけない」という意識が強まり、支払いを滞らせることへの心理的なブレーキになります。
養育費は、親が子どもの生活を支えるために果たすべき重要な義務です。しかし、養育費を支払う側の親は子どもと離れて暮らすため、時間が経つにつれて親としての自覚が薄れてしまうケースも少なくありません。
とくに、口約束だけで養育費を取り決めていると「今月は出費が多いから払えない」といった曖昧な理由で支払いを止めてしまう場合もあるでしょう。
一方、公正証書に残しておけば「正式な取り決めである」「守らなければ強制執行の対象になる」といった意識が働き、養育費の未払いを防ぎやすくなります。
養育費の内容を公正証書に残すデメリット
公正証書にはさまざまなメリットがありますが、作成にあたっては時間や手続きの面で負担がかかる場合もあります。
主なデメリットは以下の2つです。
- 作成には費用と時間がかかる
- 夫婦2人で公証役場に出向く必要がある
それぞれ詳しく解説します。
作成するのに費用と時間がかかる
養育費の内容を公正証書に残すデメリットとして、作成するのに費用と時間がかかる点があげられます。
公正証書の作成は、着手してから1~2週間ほどかかります。公証人が公正証書の内容や提出された資料を確認しながら作成するためです。
ただし、内容の複雑さや話し合いの進行状況、公証役場の混雑状況によっては、さらに日数がかかる場合もあります。
公証役場は全国に設置されており、居住地に関係なくどの公証役場でも作成できます。そのため早く作成したい場合は、混雑の少ない公証役場に問い合わせてみるのも1つの方法です。
※参考:公証役場一覧 | 日本公証人連合会
なお公正証書の作成にかかる費用は、養育費の合計額や弁護士へ依頼するかどうかによって異なります。くわしくは後述する「公正証書の作成に必要な費用」をご確認ください。
夫婦2人で公証役場に出向く必要がある
公正証書を作成するには、原則として当事者である夫婦がそろって公証役場に出向かなければなりません。つまり、双方が公正証書を作ることに納得し、協力的でなければ作成が難しくなります。
とくに養育費を支払う側の親からすると公正証書を作成するメリットを感じにくいため「毎月遅れずに支払うつもりだから公正証書は必要ない」と反対されてしまうケースも考えられます。
また、公証役場は平日の日中(9時から17時)にのみ対応しており、土日祝や年末年始は原則として営業していません。平日に休みが取れない場合、有休を取得して訪問する必要がでてくるでしょう。
そのため「公正証書を作成したいのに相手の予定が合わない」「そもそも来てくれない」といったケースも想定されます。
このような場合、当事者双方の合意内容が固まっているのであれば、弁護士に代理人を依頼するのも1つの方法です。弁護士は離婚や養育費の手続きに詳しいため、公証人から代理人として認められやすい傾向にあります。
ただし、代理を依頼する場合でも、委任状や本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)の提出が必要です。内容によっては、署名や押印のために本人の出頭を求められるケースもあります。
なお、代理作成が可能かどうかは公証人の判断によるため、事前に公証役場へ確認しておくとよいでしょう。
公正証書の作成に必要な書類
養育費に関する公正証書を作成するには、以下の書類が必要です。
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きのもので有効期限内のもの)
- 認印(シャチハタ不可)
- 戸籍謄本(本籍地のある市町村役場やコンビニ交付(対応自治体のみ)で取得可能)
- 離婚協議書または公正証書原案
本人確認書類は、公証人が当事者の本人確認を行うために必要です。
運転免許証やマイナンバーカードなど、氏名・住所・生年月日が確認できる、顔写真付きの公的書類を用意しましょう。
手続きには認印も必要です。シャチハタは使用できないため、注意してください。
戸籍謄本は、養育費の支払者・受取者を明確にするために必要です。離婚前であれば夫婦・子どもが記載された戸籍謄本、すでに離婚が成立している場合は、当事者それぞれの戸籍謄本が求められます。
離婚協議書または、公正証書原案は、公証人が公正証書を作成する際の元となる資料です。養育費の金額や支払い期間、支払い方法、強制執行認諾文言の有無など、合意した内容をまとめておくとよいでしょう。
なお、弁護士などの代理人が手続きを行う場合は、以下の書類も追加で必要になります。
- 委任状(実印での押印が必要)
- 印鑑証明書(委任状に押印された実印の証明用)
公正証書の作成に必要な書類や手続きの詳細は、公証役場によって異なります。準備をスムーズに進めるためにも、事前に公証役場へ問い合わせて必要書類を確認しておくとよいでしょう。
公正証書の作成に必要な費用
公正証書作成の費用は、作成する目的の価額によって異なります。目的の価額とは、その目的によって得られる一方の利益で、養育費の場合は合計金額が目的の価額にあたります。
| 目的の価額 |
費用 |
| 100万円以下 |
5,000円 |
| 100万円を超え200万円以下 |
7,000円 |
| 200万円を超え500万円以下 |
1万1,000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 |
1万7,000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 |
2万3,000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 |
2万9,000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 |
4万3,000円 |
| 1億円を超え3億円以下 |
4万3,000円+超過額5,000万円までごとに1万3,000円 |
| 3億円を超え10億円以下 |
9万5,000円+超過額5000万円までごとに1万1,000円 |
| 10億円を超える場合 |
24万9,000円+超過額5,000万円までごとに8,000円 |
引用元:手数料 | 日本公証人連合会
費用は「毎月の養育費」ではなく「支払い総額(合計額)」に対して計算されます。たとえば、月5万円の養育費を10年間受け取る場合は以下のとおりです。
50,000(円)×12(ヵ月)×10(年)=6,000,000(合計額)
この場合、目的の価額は600万円となるため、手数料は17,000円です。
※支払い期間が明確に定まっていない場合(例:「子どもが成人するまで」など)は、公証人の判断で1年分の養育費を目的の価額として計算される場合があります。
目的の価額の算出に迷った場合は、事前に公証役場へ相談しましょう。
なお、公正証書に強制執行認諾文言を記載しても、追加費用はかかりません。
また、上記の費用は、夫婦が直接公証役場に出向いて作成した場合です。弁護士に公正証書の作成を依頼する場合は、別途費用(おおよそ5万〜20万円程度)がかかります。
さらに、公正証書の謄本を取得する際は、謄本作成費(1通あたり250〜500円程度)が必要です。内容によっては、登録免許税などの追加費用が発生する場合もあります。
どれだけ費用がかかるか不安な場合は、公証役場で作成費用の概算額をだしてもらうことも可能です。事前に確認しておけば円滑に手続きを進められるでしょう。
公正証書を作成する流れ
公正証書を作成する流れは、以下のとおりです。
- 離婚条件を決め公正証書の叩き台を作成する
- 当事者双方で公証役場に出向き公証人と面談する
- 作成された公正証書の内容を確認し署名・押印する
それぞれの項目について詳しく解説します。
離婚条件を決め公正証書の叩き台を作成する
まずは夫婦で話し合い、離婚条件を決めましょう。
養育費に関しては、以下のような内容を取り決めておく必要があります。
- 毎月の養育費の金額
- 支払日(毎月何日までに支払うか)
- 支払い期間(例:子どもが満20歳になるまで)
- 支払い方法(口座振込など)
また、面会交流や財産分与、慰謝料の有無なども、公正証書に残せます。
離婚に際して、養育費以外でも正式に取り決めておきたい事柄がある場合は、この段階で話し合っておきましょう。
なお作成する原案は、特別な書式があるわけではないため、Wordや手書きなどで要点をまとめたもので問題ありません。
当事者双方で公証役場に出向き公証人と面談する
公正証書に残したい内容が決まったら、公証役場に連絡し、必要書類の確認と面談日時を調整します。
具体的な流れは以下のとおりです。
- 希望する公証役場に電話し、必要書類や受付可能日を確認する
- 面談日時を決める
- 当日、当事者(夫婦)が公証役場へ出向く
- 公証人と離婚協議書や公正証書原案の内容を確認し面談を進める
公証役場は全国どこでも利用可能で、居住地にかかわらず公正証書の作成が可能です。近くの公証役場は「公証役場一覧 | 日本公証人連合会」にて探せます。
なお、打ち合わせの段階では夫婦のどちらか一方だけが訪問しても問題ありません。離婚協議書や公正証書原案の内容に不安がある場合は、事前に確認してもらうとよいでしょう。
作成完了した公正証書の内容を確認し署名・押印する
公正証書の内容や公証役場の混雑状況にもよりますが、手続きしてから1〜2週間ほどで公正証書が完成します。完成後、内容に問題がないか夫婦で確認し、双方が納得したうえで署名・押印を行えば手続きは完了です。
手数料は、公正証書を受け取る際に支払います。
なお、公正証書の原本は公証役場に保管されます。万が一紛失しても再発行が可能であり、内容が無効になることはありません。
養育費に関して公正証書に残すべき内容
公正証書は離婚問題以外の場面でも使われますが、養育費に関して残す場合は以下の内容をまとめます。
- 養育費の月額
- 養育費の支払い日
- 養育費の支払いの開始時期と終了時期
- 養育費の債務者と債権者
- 養育費の支払い方法
- 強制執行を承諾する文言
- 状況変更時の対応を可能とした文言
事前に離婚協議書や公正証書原案を作成する際は、上記の内容を押さえておくとスムーズに公正証書を作成できます。
それぞれの内容を確認しておきましょう。
養育費の月額
厚生労働省の発表した情報によると、令和3年の子ども1人あたりの養育費相場は2〜5万円です。
※養育費を現在も受けている、または受けたことがある世帯で、金額が決まっているものに限られる。
参照:令和 3年度 全国ひとり親世帯等調査結果の概要
さらに、家庭裁判所が公表している養育費算定表を使えば、収入と子どもの人数に応じて目安額を簡単に確認できます。
たとえば「年収400万円の父親(給与所得者)」と「年収100万円の母親(パート収入)」「子どもが1人(14歳未満)」の場合、養育費の目安は月額4〜6万円程度となります。
客観的な資料を参考にしつつ、無理のない範囲で合意できる金額を設定しましょう。
また、生活保護や児童扶養手当などの公的扶助を受けている場合、養育費が収入として認定されるケースがあります。
その結果、支給額が減ったり、支給が止まったりする可能性もあるため、不安がある場合は自治体の窓口で相談しておきましょう。
養育費の支払い日
養育費の支払い日も、公正証書に残しておきましょう。法律上の決まりはありませんが、養育費を支払う側の収入タイミングをふまえて設定することが大切です。
たとえば、養育費を支払う側の給料日前に支払い日を設定すると、相手にお金が足りなくて支払えないリスクが生じます。そのため、給料日当日やその数日後(例:給料日が毎月25日なら27日など)を支払い日に設定するとよいでしょう。
「支払い日は振込手続き日とする」と明記しておくと、送金日と入金日のズレによるトラブルを防げます。
なお、支払いが遅れた場合には、養育費を受け取る側は遅延損害金(民法の法定利率・年3%など)を請求できます。ただし、支払期日が曖昧だと損害金の算出や請求が難しくトラブルになる可能性があるため、日付は明確に定めましょう。
遅延損害金は、請求しない限り自動で相手に課されるものではないため、書面で請求する意思を伝えることが必要です。
さらに公正証書には「毎月〇日までに支払いがない場合は債務不履行とみなす」といった文言も残しておけます。このような文言があると、万が一未払いが発生した際に強制執行を行う根拠として活用しやすくなります。
養育費の支払いの開始時期と終了時期
養育費の支払い期間も、公正証書に明確に残しておきたい項目です。
支払いの開始時期は、離婚が成立した日や、公正証書の作成日・締結日の翌月からとするケースが一般的です。たとえば、4月に離婚が成立した場合は「5月分から支払う」といった形で定める場合が多くみられます。
一方、支払いの終了時期は、子どもが社会的・経済的に自立するまでとするのが一般的です。代表的な例としては、以下のような取り決めがあります。
- 高校卒業まで(満18歳に達する年度の3月末まで)
- 大学卒業まで(満22歳に達する年度の3月末まで)
- 満20歳まで
ただし養育費の終了時期は、法律上で定められているわけではありません。あくまでも当事者の合意により自由に決められます。
家庭の事情や子どもの進学予定、健康状態などをふまえて、話し合いのうえ取り決めましょう。
たとえば、子どもが障害や病気などで就労が難しい場合には、22歳以降も養育費の支払いを継続するケースもあります。また、大学院に進学する場合など、養育費の継続が必要だと判断したときは、事前に双方で合意しておくケースもあるでしょう。
将来の変化に備えて、柔軟に対応できるような文言にしておくことが大切です。
2022年4月の民法改正により、成人年齢は20歳から18歳に引き下げられました。
ただし、民法改正前に「成人に達するまで」と定めていた場合には、従来どおり20歳までと解釈されるケースが多いとされています。
トラブルを防ぐためにも、養育費の終了時期は「成人」などのあいまいな表現ではなく「満◯歳まで」と具体的に残しておくことが大切です。
養育費の支払い期間は、一度決めたら絶対に変更できないわけではありません。将来の事情変更に応じて、双方の合意があれば内容を見直すことも可能です。
養育費の債務者と債権者
養育費に関する公正証書では、「債務者(養育費を支払う人)」と「債権者(養育費を受け取る人)」を残しておく必要があります。氏名・住所・生年月日なども記載し、当事者を特定できるようにしておくことが大切です。
一般的には、親権を得て子どもを育てる側(監護者)が債権者となり、もう一方が債務者になります。たとえば、母親が子どもを引き取って育てる場合は、父親が債務者、母親が債権者となるのが一般的です。
ただし、親権と監護権をわけて決めるケースもあります。
親権:子どもの身分や財産、教育・医療などに関する決定権(民法第820条)
監護権:日常生活で子どもを育て、世話をする権利(民法第821条)
参考:
法務省|民法(e-Gov法令検索)
親権と監護権をわけた場合には、実際に子どもを育てている「監護権者」が債権者(養育費を受け取る側)になるのが一般的です。たとえ親権を有していても、子どもを監護していない場合は、債務者(養育費を支払う側)となるケースもあります。
養育費の債務者・債権者を明確にするには、まず親権や監護権をどちらが持つかを決めておく必要があります。
親権や監護権がまだ決まっていない場合は、養育費の取り決めに入る前に、どちらが親権を持ち、誰が子どもを育てるかについて話し合っておきましょう。
なお、例外的に祖父母など第三者が養育費を支払うケースもありますが、基本的には実親が債務者となるのが原則です。
養育費の支払い方法
養育費の支払い方法についても、公正証書に残しておきましょう。基本的には、毎月決められた金額を、口座振込で支払う方法が一般的です。
なかには「毎月子どもと会うついでに手渡ししたい」と考える方もいますが、手渡しでは支払いの証拠が残らないため、万が一トラブルが起きた際に「支払っていない」と主張されるおそれがあります。
また、養育費の支払いを理由にして面会交流を強要されるなど、精神的な負担につながるケースも考えられます。
そのため、養育費の支払いは必ず口座振込にし、面会交流とは切り離して考えるようにしましょう。
なお、お互いの合意があれば養育費を一括で支払うことも可能です。
一括払いにすれば、将来の未払いリスクを回避できます。ただし、一括払いの場合、その後に支払う側の経済状況が大きく改善したとしても、追加で請求するのは困難です。
また、子どもに思わぬ出費が発生したときにも、改めて話し合う機会が持てなくなる可能性があります。
想定していたよりも早く養育費を使いきってしまうおそれもあるため、一括で受け取っても問題ないか、検討することが大切です。
さらに、公正証書には以下の内容も残しておくことをおすすめします。
- 振込先の金融機関名・支店名
- 口座番号
- 口座名義人(カタカナも含む)
通帳や振込明細は、養育費の支払い実績を示す大切な記録です。将来のためにも、コピーや写真をとって保管しておきましょう。
強制執行を承諾する文言
「強制執行認諾文言」を残しておくと、養育費の支払いが滞ったときにも迅速に対応できます。
この文言があれば、養育費の未払いがあった場合に、裁判所での判決や調停を経ることなく、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえが可能です。
たとえば「債務者は本証書に定めた金銭債務について強制執行を受けても異議ありません」といった文言が、公正証書の末尾に公証人の手で記載されます。
ただし強制執行認諾文言は、債務者(養育費を支払う側)の同意がなければ残すことができません。そのため、公正証書を作成する前に内容を説明し、理解と同意を得ておくことが大切です。
なお、強制執行認諾文言がない場合には、支払いが滞った際に別途訴訟や調停を行う必要があり、時間的・精神的負担が大きくなるおそれもあります。
たとえ、現状で養育費の支払いに前向きだったとしても、今後も確実に支払いが続くとは限りません。
子どもを安心して育てていくためにも、強制執行認諾文言はできる限り残しておきましょう。
状況変更時の対応を可能とした文言
養育費の取り決めを公正証書に残す際は、「将来の状況変化に柔軟に対応できるようにするための文言」も残しておくとよいでしょう。
「状況変更時の対応を可能とした文言」とは、養育費の取り決め後に状況が変わった場合に、再度協議や見直しができるようにするための文言です。
たとえば、次のような事情変更が起きた場合、状況に応じて養育費の金額や支払い方法を見直す必要が生じるケースがあります。
- 子どもが病気や障害を抱え、追加の費用が必要になった
- 失業・不況・病気などにより、養育費を支払う側の収入が減少した
- 自営業になり養育費を支払う側の収入が不安定になった
- 監護者が再婚・転居などで生活環境が大きく変化した
状況変更時の対応を可能とした文言があれば、こうした変化に応じて柔軟に対応できます。
もちろん、このような文言がなくても、当事者同士で合意できれば内容の変更は可能です。ただし、変更が不利になる側が話し合いに応じない可能性もあり、トラブルに発展するおそれも考えられます。
そのため「当事者のいずれかに重大な経済的事情の変更があった場合は、協議のうえ養育費の内容を見直すものとする」といった一文を残しておくと、後々の話し合いがしやすくなります。
なお、内容の変更には当事者双方の合意が必要です。内容変更後の文書も強制執行力を持たせたい場合は、新たに公正証書を作成し直す必要があります。
将来に備え、当事者双方が安心して生活できるように、状況変更に対応できる文言を残しておくことをおすすめします。
弁護士に公正証書作成を依頼した場合の費用相場は5万〜20万円程度
公正証書の作成は、弁護士に依頼することも可能です。弁護士に公正証書の作成を依頼する場合、依頼内容によって費用は異なりますが、おおよそ5万〜20万円が相場とされています。
費用の内訳は、以下のようなケースが一般的です。
- 文案チェックのみ:1万〜3万円程度
- 原案作成・内容調整:3万〜10万円程度
- 交渉・公証役場とのやり取りを含めた一括依頼:10万〜20万円程度
夫婦だけで離婚協議書や公正証書の原案を作成すると、一方にとって不利な内容になってしまうケースも少なくありません。
弁護士に依頼すれば、法的な不備の有無を確認できるだけでなく、自分にとって不利な条項が含まれていないかも確認してもらえます。
すでに作成した協議書や公正証書の原案を確認してもらうだけであれば、比較的低額で対応してもらえるケースもあります。
また、「夫婦で公証役場に行きたくない」「養育費の交渉を直接したくない」という場合は、公証役場とのやりとりや養育費の協議を含めて、弁護士に任せることも可能です。
もちろん養育費だけに限らず、慰謝料や財産分与に関する取り決めも弁護士に依頼できます。
弁護士費用は原則として依頼者の自己負担となりますが、費用面が不安な場合は、事前に見積もりをだしてもらったり、分割払いが可能かどうか相談したりするとよいでしょう。
なお、収入や資産の状況によっては、法テラスの無料相談や費用の立替制度が使える場合もあります。※参考:法テラス(日本司法支援センター)公式サイト不安な方は、事前に法テラスの利用要件を確認してみましょう。
まとめ
養育費の取り決めは、できる限り公正証書に残しておきましょう。とくに「強制執行認諾文言」を付けておけば、未払いリスクを軽減できるうえ、支払いが滞った場合にも、給料や財産を差し押さえることができます。
公正証書を作成する際は、夫婦間でしっかりと話し合い、養育費の金額や支払い期間、支払い日、支払い方法などを具体的に決めておくことが大切です。
ただし、内容によっては一方にとって不利な条件となってしまう可能性もあります。そのため不安がある場合は、弁護士に依頼することも検討しましょう。
弁護士に依頼すれば、養育費だけでなく、慰謝料や財産分与に関する取り決めについてもサポートが受けられます。
将来のトラブルを防ぎ、子どもの生活を安定させるためにも、養育費は公正証書に残しておきましょう。
養育費の公正証書に関するよくある質問
離婚した後に公正証書の作成はできますか?
離婚後でも公正証書の作成は可能です。
ただし公正証書は、基本的に夫婦2人がそろって公証役場に出向く必要があるため、離婚後は相手が協力してくれない可能性があります。
そのため、養育費に関する取り決めは、できる限り離婚前に話し合い、公正証書を作成しておくことをおすすめします。
公正証書の効力に有効期限はありますか?
公正証書そのものに有効期限はありません。ただし、未払いの養育費には時効があります。
調停・裁判で養育費を決めた場合は10年、夫婦間で話し合いをして決めた場合(公正証書も含む)は5年で時効をむかえます。
そのため、未払いがあった場合は放置せず、時効になる前に請求するようにしましょう。
公正証書を作成した後に養育費の減額を申し立てられることはありますか?
たとえ公正証書によって取り決めた内容であっても、状況の変化に応じて養育費の減額を申し立てられることはあります。
ただし、相手が一方的に金額を変更することはできません。
まずは当事者同士で話し合い、そのうえで合意が得られない場合は、家庭裁判所へ調停を申し立てる流れになります。