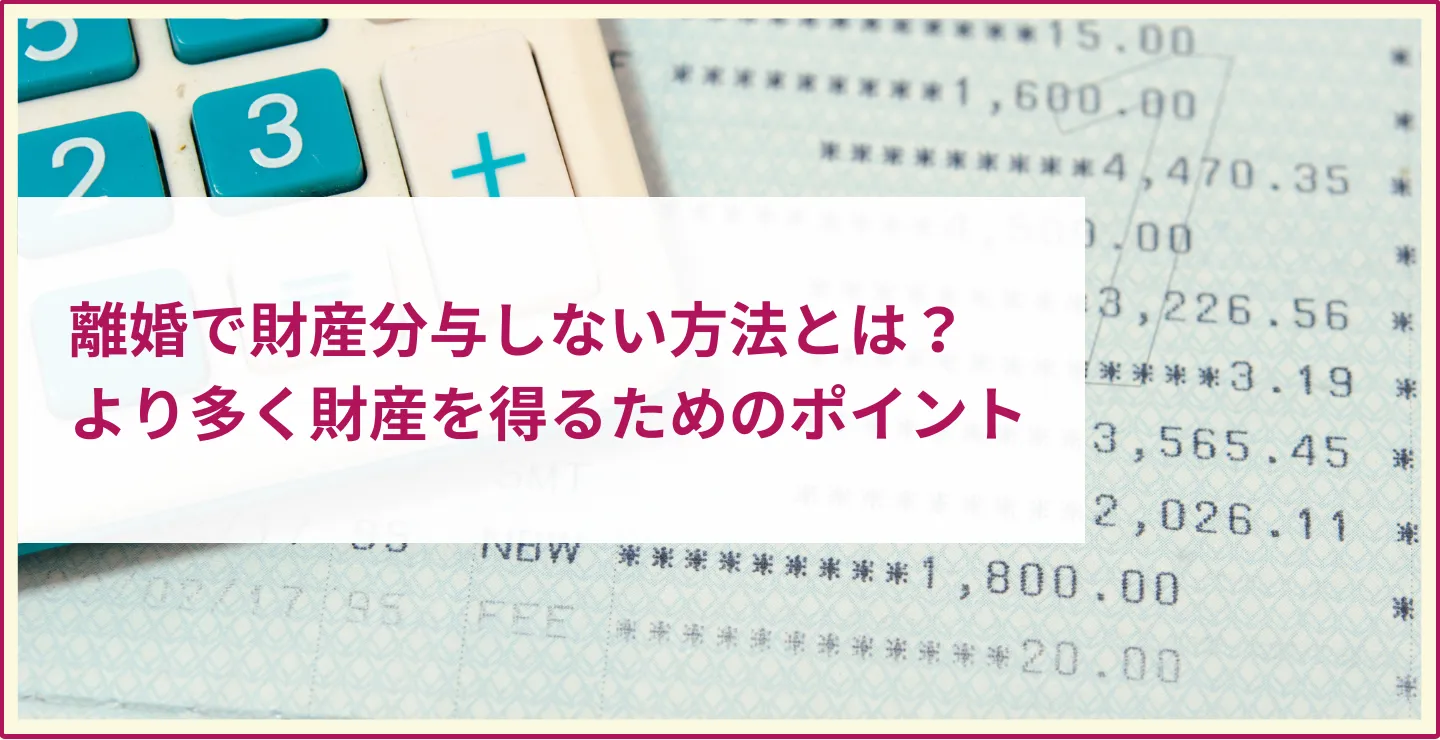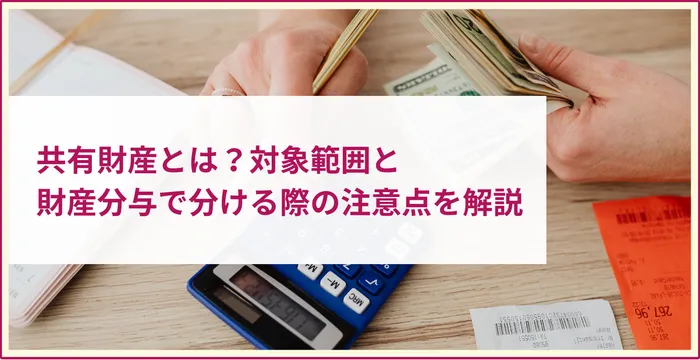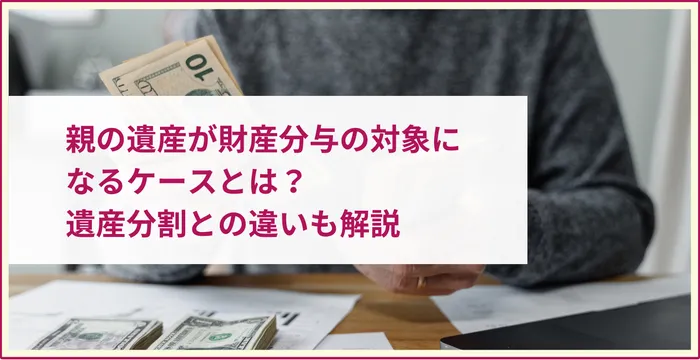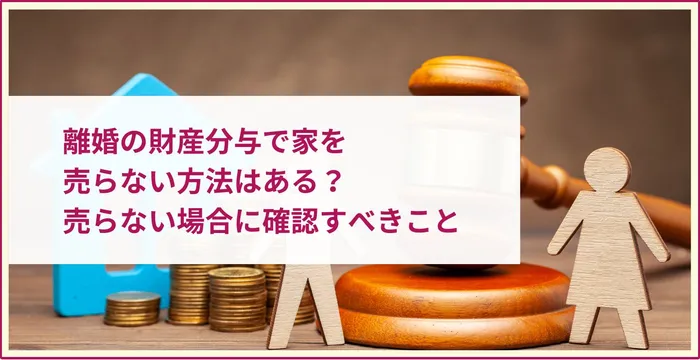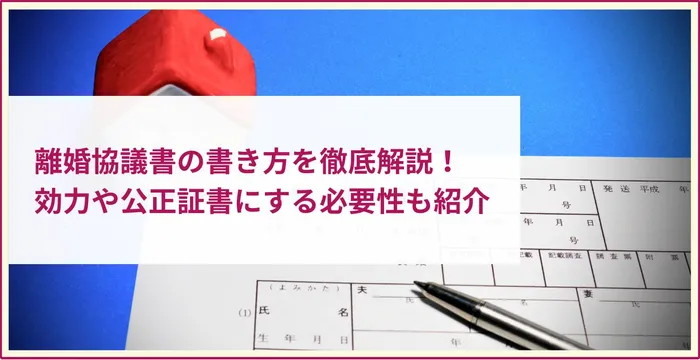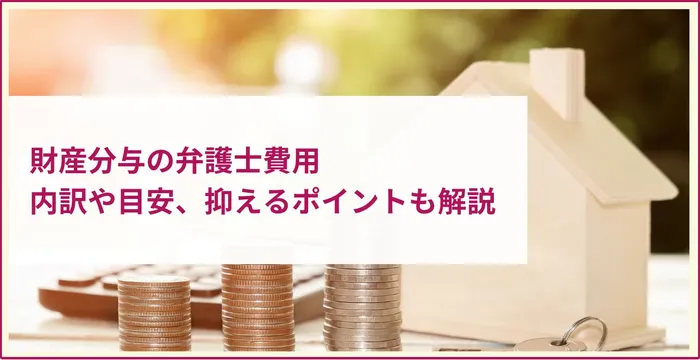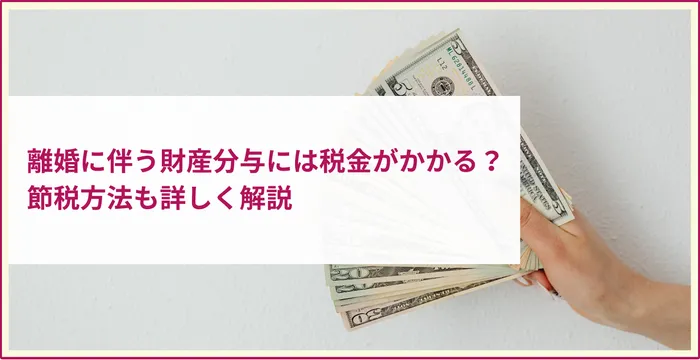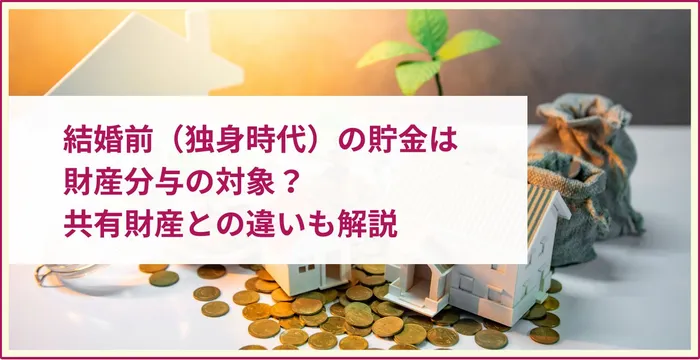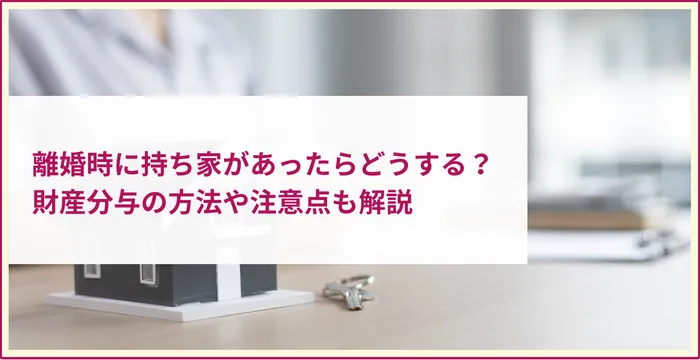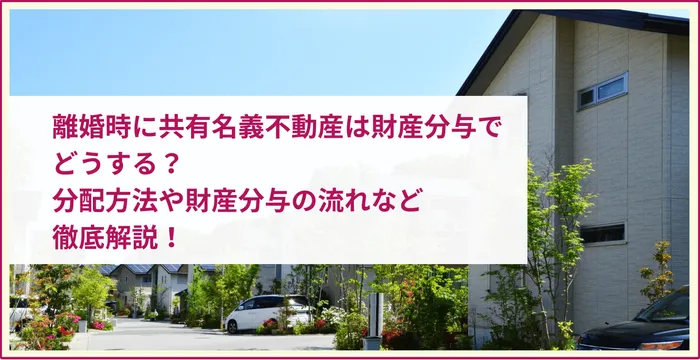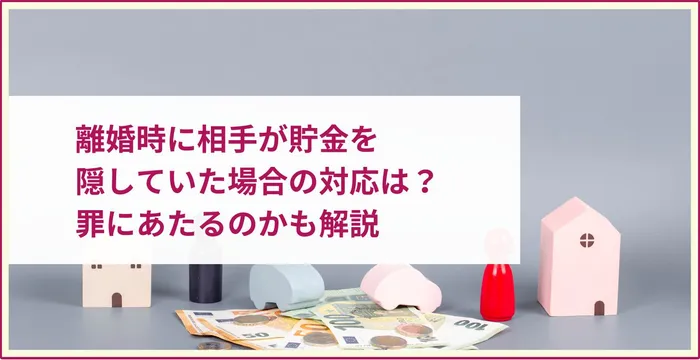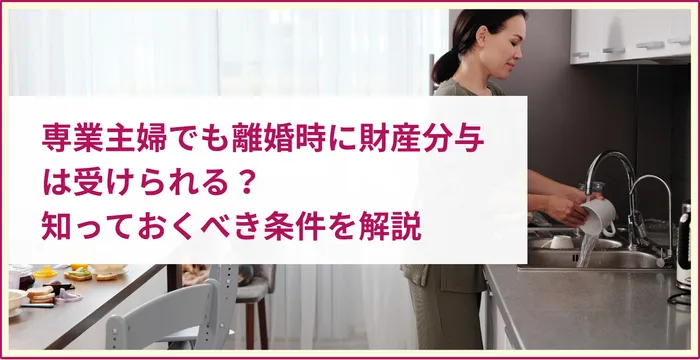相手から財産分与を求められたら原則として拒否できない
「自分のほうが収入を得ているから」「あっちは年収が高くてこっちは子育てがあるから財産は渡さない」といった主張をしても、相手から財産分与を求められたら原則として拒否できません。
民法第768条・771条に基づき、財産の分配を相手に請求できる「財産分与請求権」が、夫婦それぞれに発生しているからです。財産分与請求権が発生するのは、「協議離婚(話し合いで成立)」「調停離婚(家庭裁判所での調停にて成立)」「裁判離婚(訴訟を提起し裁判官の判決にて成立、和解離婚含む)」のいずれにおいても同様です。
(財産分与)
第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
e-Gov法令検索 民法第768条
(協議上の離婚の規定の準用)
第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。
e-Gov法令検索 民法第771条
ただし離婚後に財産分与を請求されてそれを拒否したときは、民法上の「除斥期間」である2年を過ぎているか否かで対応が変わります。除斥期間の詳細は、離婚から2年以上経過していたら「除斥期間」を主張するの見出しをご覧ください。
離婚前に財産分与を拒否したときは、離婚の合意が得られず問題が長期化する可能性が出てきます。話し合いで決まらないなら、相手から離婚調停・離婚裁判などの法的手段を申し立てられて、最終的な決着を付けることになるでしょう。離婚前だと財産分与請求権に除斥期間や時効がないので、相手が諦めず離婚が成立しない限りは問題解決がどんどん後ろ倒しになります。
「じゃあ、財産分与しない方法なんてないのでは?」と思われるかもしれませんが、「そもそも財産分与をしないで済むケース」「財産分与をしない方法・相手に財産分与する割合を少なくする方法」はいくつかあります。
離婚前の財産分与拒否なら、原則として「離婚調停や裁判のなかで財産分与について争う」のが一般的です。対して離婚後に争うときは、財産分与調停・審判で決着するケースが多いようです(いきなり審判から始める事件もあり)。
財産分与の割合はどう決める?基本をおさらい
財産分与しない方法をより理解するには、あらためて財産分与の基本をおさらいするのがおすすめです。財産分与の基本を知っておけば、弁護士に相談したときに説明を受けても頭に入りやすくなるはずです。
まず財産分与には、以下の3種類が存在します。
| 財産分与の種類 |
概要 |
| 清算的財産分与 |
夫婦が共同生活を送るなかで形成した財産を公平に分配すること |
| 扶養的財産分与 |
離婚する際に一方の生活が困窮する恐れがあるとき(長年専業主婦だった、高齢・病気であるなど)に生活保障としておこなう分配のこと |
| 慰謝料的財産分与 |
離婚の原因を作った相手に対して損害賠償的な意味で求める分配のこと |
一般的に財産分与と言われれば、清算的財産分与になります。以下では、清算的財産分与について詳しく見ていきましょう。
扶養的財産分与や慰謝料的財産分与が相手から請求されたときは、個々の状況を見つつ、金額や支給方法を弁護士などへ相談するのがよいでしょう。
財産分与の基本は1/2ずつ
財産分与の割合は、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産を2分の1ずつ分けるという「2分の1ルール」が適用されます。共働き・片方が専業主婦(主夫)などの夫婦関係に限らず、分配割合は原則として同じです。
なかには「相手は専業主婦(主夫)なのにおかしい」と主張されるケースがありますが、財産分与においては一部の例外を除き、収入や社会的地位などが割合に影響を与えることはほぼありません。公平に分配するのは、「夫婦はお互いに平等であること」「家事・育児などのサポートによって財産形成・維持に貢献していること」が前提にあるからです。
ただし、財産分与の対象は住宅ローン、カードローン、夫婦共同の事業関係の債務など、夫婦で築いたマイナスの財産も含まれるので注意が必要です。財産分与は、「資産(プラスの財産)-負債(マイナスの財産))」で計算した金額を基に実施します。
とはいえ、財産分与の対象財産が負債>資産のケースだと、財産分与そのものがおこなわれなくなります。
養育費や慰謝料は別で考える
財産分与とそのほか離婚に関する金銭的問題は、別で考える必要があります。たとえば、「財産分与と養育費の相殺」「財産分与と慰謝料の相殺」は法律上認められません。法的根拠は次の通りです。
双方の合意があれば割合を自由に決定できる
財産分与の割合は、夫婦双方の合意があれば2分の1ルールに縛られることなく自由に決定できます。6:4といった小さな変更から10:0といった極端な割合でも、夫婦が納得していれば分配が可能です。また、分配する財産の種類も合意のうえで好きなように分け合えます。
割合変更について夫婦で合意を求める際の具体例は次の通りです。
- 離婚条件を早めに納得してもらうために相手への財産分与を多めにする
- 子育て分と自分の給与の高さを考慮し親権を持つ相手にマイホーム+多めの預貯金を渡しつつ面会交流の回数を優遇してもらう
- 預貯金などのほかの財産を渡す代わりに株式や美術品など時価が変化しやすい財産を受け取る
話し合いで財産分与の割合・種類を決めるなら、割合の根拠、譲れない条件、妥協する条件を明確にしておき、スムーズに話し合えるよう準備しておきましょう。脅迫や暴力によって無理やり従わせる行為は、離婚の無効や刑事罰となる可能性があるので必ず避けてください。
話し合いがまとまらないときは裁判所にて判断を決める
離婚時の財産分与について話し合いがまとまらないときは、裁判所にて最終判断を仰ぐことになります。
離婚前なら、まず離婚調停の申し立てを家庭裁判所におこないます。離婚は「調停前置主義(調停を経なければ訴訟を提起できない制度)」の対象事件であり、「財産分与について合意できなくて離婚できない」も含まれるからです。
調停とは、裁判官や調停委員を交えて、家庭裁判所で当事者同士の話し合いをおこなうことです。審判や裁判と異なり、裁判官の判決ではなくあくまで当事者同士の合意・不合意によって決まります。
離婚調停でも離婚や財産分与の合意できなかったときは、審判や裁判へ移行し裁判官の判決を待ちます。裁判で争うときは、別途財産分与の付帯処分の申し立てが必要なので注意しましょう。
離婚成立後に別途財産分与について争うときは、財産分与調停を申し立てます。調停前置主義の対象外である財産分与は審判や裁判から始められますが、裁判所の職権により実務上は調停の場が設けられるのが一般的です。
なお、審判・裁判では、よほどの事情がない限りは2分の1ルールに基づいて折半すべしとされています。弁護士実務のうえでも2分の1ルールが強固であり、例外がない限りは折半になると考えられているようです。後述する「財産形成における貢献度や偏り」などが認められたときに、審判・裁判で5:5以外の割合が言い渡される可能性があります。
審判と裁判の違いが少し分かりづらいですが、審判は「調停の内容などを基に裁判官の職権で必要な判断を下す」、裁判は「双方の主張立証を基に判断を下す」という違いがあります。審判は調停の延長線にあるイメージです。審判の結果に不服な場合は、異議申し立てをおこない、裁判への移行や判決差し戻しの判断を待ちます。
離婚をしても財産分与しないで済む可能性があるケース
夫婦の合意がない状態で相手から財産分与を請求されると、前述した2分の1ルールを適用するのが原則です。しかし、一定の状況下では離婚をしても財産分与をしないケースがあります。財産分与が発生しない可能性があるのは次のケースです。
- 配偶者が財産分与を求めてこない
- 共有財産を築いていなかった・特有財産しか存在しなかった
- 住宅ローンなどの負債を考慮すると財産分与できる資産がなくなった
- 婚前に「夫婦財産契約」を締結している
特殊な状況下なので、該当しない人のほうが多いと思われますが、一度確認してみてください。以下では、それぞれの詳細を解説します。
配偶者が財産分与を求めてこない
配偶者がそもそも財産分与を請求せず、そのままでよいと判断しているときは財産分与する必要はありません。財産分与は義務ではなく権利の範疇であり、権利を行使しないことも自由に決められるからです。
とはいえ、相手側が何の意味もなく財産分与を放棄する可能性は低いと思われます。相手が財産分与を放棄する可能性として考えられるケースは、次の通りです。
- 離婚の原因が相手側にあり相手が贖罪の気持ちで放棄する
- 配偶者側が高収入で「自分は最低限の財産で十分」と言って多めに分配してきた
- 財産分与を放棄する代わりに養育費・慰謝料の増額や親権などを求める
共有財産を築いていなかった・特有財産しか存在しなかった
財産分与の対象となるのは、夫婦が婚姻期間中に築いた「共有財産」です。財産分与は共有財産の種類や金額を確認・評価し、2分の1ルールや夫婦が合意した割合に応じて分け合います。
逆に言えば、共有財産以外の財産は財産分与の対象外です。共有財産以外の財産として、「特有財産」が挙げられます。
特有財産とは、夫婦のどちらか一方にのみ帰属する財産です。「夫婦のうち一方が結婚前から持っていた財産」「相続や親族からの贈与などで得た財産」「夫婦の合意によって特有財産としたもの」「どちらか一方の特殊な才能・能力によって得た財産」などが、特有財産に該当します。
<特有財産となる可能性があるものの例(相続・贈与関係以外)>
- 結婚前に貯めた預貯金
- 結婚前に取得した有価証券、ゴルフ会員権、貴金属
- 結婚前に購入した不動産や自動車(結婚後に支払っていたローン分や運営・管理していた分は共有財産となる可能性あり)
- 結婚前に支払っていた保険料分の解約返戻金
- 退職金のうち結婚前の就労期間に属する部分
- 特有財産から発生した利息や収益
- 結婚前に貯めた預貯金を取り崩して得た財産や特有財産を売却して得た収益
- 特有財産の代償財産(特有財産の損失によって発生した保険金など)
- 自営業者の事業用資産のうち共有財産として認められるもの
- 夫婦のうち一方しか使用しない家財
- 夫婦のうち一方の個人的な借金などの負債
- 子どもへのお年玉、子どもが貯めたアルバイト代など
- そのほか夫婦の合意の下で財産分与の対象外としたもの
<特有財産とならない可能性があるものの例>
- 長い婚姻期間において共有財産と混在した特有財産の預貯金
- 法人名義の財産全般(個人の財産が一緒になっている場合を除く)
仮に夫婦生活のうえで共有財産を築いていなかった、お互い特有財産しか持っていなかったといった状況になれば、財産分与自体が発生しない可能性があります。とはいえ非常に限定的な状況ではあるため、財産分与ゼロを目指すと言うより、自分の特有財産を主張して手元に残す財産を多くするように動くのがよいでしょう
住宅ローンなどの負債を考慮すると財産分与できる資産がなくなった
財産分与の対象になるのは、「資産総額から負債総額を差し引いて残った金額」です。つまり、現在所有している資産より負債のほうが高いときは、分配する財産がないものとして財産分与の発生なしと判断されるのが一般的です(扶養的・慰藉料的な分配やそのほか個別の事情にもよる)。
たとえば、財産分与の対象とするのが住宅ローンのみの場合で考えてみます。
もしマイホームの資産価値が2,000万円で残ローン額が1,200万円だった場合は、800万円分が財産分与の対象です。一方でマイホームの資産価値が1,200万円で残ローン額が2,000万円だった場合は、残ローン額のほうが多いので財産分与はなしになります。
離婚後に残ローン額を返済するのは、引き続き住宅ローンの名義人です。「住宅ローンは夫婦一緒のときに契約したから、別れた後も支払ってね」といった主張は、夫婦の同意がない限り法的な支払い義務は生じません。相手が連帯保証人になっているときは、ローンの名義人が支払えなくなった時点で連帯保証人が支払うことになります。
婚前に「夫婦財産契約」を締結している
婚前に財産分与しない旨を定めた「夫婦財産契約」を締結しておくと、離婚時に夫婦のお互いが財産分与請求権を放棄するようにできます。
「夫婦財産契約」とは、婚姻しようとしている者同士の間で締結する、民法の規定に則らない部分に関する契約です。婚前契約(プレナップ)という枠組みのなかの1つというイメージです。民法第755条における、「その財産について別段の契約」が該当します。
(夫婦の財産関係)
第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
e-Gov法令検索 民法第755条
夫婦財産契約では、民法760条・761条・762条に規定された内容や、そのほか夫婦関係に関する決まりごとを、夫婦独自のルールに変更できます。具体的には次の通りです。
| 夫婦財産契約で決められる内容 |
概要 |
| 夫婦における財産の帰属 |
財産分与時の対象財産の範囲 |
| 婚姻費用の分担 |
離婚時においては主に別居中の婚姻費用の支払いについて決めるのが一般的 |
| 日常家事に関する債務の連帯責任 |
日常のクレジットカードの利用などの債務に関する責任の所在など |
夫婦財産契約と言えども、内容によっては無効になる可能性があります。たとえば同居・扶助の義務の否定など婚姻の意味を根本から否定する内容、債務関係の責任の放棄など第三者へ損害を与える内容、養育費を負担しない・面会交流を拒否できるなど子の権利を制限する内容などは、無効となる可能性が高いです。
なお、夫婦財産契約を利用する夫婦は非常に少なく、過去10年間の政府統計を見ても夫婦財産契約の登記件数は年間10~40件程度のみです。財産分与をしなくてよいケースとして紹介したものの、ほぼないケースだと思っていただいて問題ありません。
以前は夫婦間の契約だと婚姻中にいつでも取り消せる「夫婦間契約の取消権(民法第754条)」が定められていましたが、民法改正によって排除されているため夫婦財産契約を途中で取り消すのは困難になっています。
参考:国税庁「夫婦財産契約と贈与税」
参考:e-stat 政府統計の総合窓口「種類別 夫婦財産契約の登記の件数」
離婚時に財産分与しない方法!財産をより多く手元に残すには?
離婚時に財産分与しない方法、および財産分与する金額を適正にして手元に残す資産を増やす方法は主に次の通りです。
| 財産分与をゼロにできる可能性がある方法 |
財産分与時に手元に残す財産を多くできる方法 |
・お互いに財産分与請求権を放棄する旨を公正証書に記す
・離婚から2年以上経過していたら「除斥期間」を主張する |
・財産形成の貢献度や偏りを主張する
・所有する財産は特有財産であると主張する
・離婚について考え直す |
いずれの方法でも、財産分与を100%なしにできるかと言われるとそうではありません。あくまで話し合いや法的根拠をベースに、「渡さなくてもよい財産を明確にして本当の意味で公平に分配する」というイメージになります。以下では、それぞれの詳細を見ていきましょう。
お互いに財産分与請求権を放棄する旨を公正証書に記す
双方の合意があれば割合を自由に決定できるにて解説した通り、夫婦が納得のうえであれば、財産分与の割合を自由に決められます。
つまり、夫婦のお互いが財産分与請求権を放棄する旨に合意すれば、離婚時に財産分与をする必要がなくなります。
しかし契約を口頭のみで交わすと、後で言った言わないのトラブルになる可能性が高いです。財産分与はお金が絡む部分であり、そのときの財産状況や気持ちによって考えが変わることも想定されます。
そのため離婚時にお互いに財産分与請求権を放棄すると決まったら、ほかの離婚条件とともに離婚協議書に記載するのがよいでしょう。文書で合意の証拠を残しておけば、後から相手が後から財産分与を求めてきても、離婚協議書を根拠に拒否できる可能性が高くなります。
離婚協議書に財産分与について記載するときは、公正証書として残すことを推奨します。公正証書とは、公務員である公証人の権限に基づいて作成する公文書です。
公正証書は公証人からの本人確認や意思確認などに基づく強い証拠力を持つため、財産分与請求権を放棄した旨を証明するための強力な根拠にできます。加えて、財産分与や養育費などについての取り決めで不履行が発生したときに、裁判手続きを経ずに強制執行に進める旨を記載できます。
公正証書を作成するには、最寄りの「公証役場」に足を運んで相談してみてください。その後、担当公証人との協議や公正証書案の確認などを経て、当事者双方または双方代理人(一方のみや双方で1人の代理人は認められない)が、予約した日に公証役場へ出頭し作成します。
参考:日本公証人連合会「公証事務」
離婚から2年以上経過していたら「除斥期間」を主張する
離婚前の財産分与請求には時効等がない反面、離婚後は離婚日から2年間という除斥期間が存在します。
除斥期間が経過した時点で財産分与請求権が失われ、財産分与を求めることができなくなります。時効のように、「更新(一度時効期間をリセットし再スタートすること)」や「完成猶予(催告や訴訟提起などの一定の事由の発生によって時効完成が先延ばしになること)」が存在しません。離婚日から2年間が経過した時点で、相手が何もしてこなければ期限終了です。
つまり、2年間の除斥期間が過ぎてから相手が財産分与を主張してきても対応する必要がありません。2年以内に財産分与について協議を始めたとしても、期限内に話がまとまらなければ権利は消滅です(夫婦の合意があれば除斥期間後でも話し合いの継続や財産分与は可能)。
ただし、相手が離婚日から2年以内に財産分与請求調停を申し立てたときは、調停中に2年が経過していても調停成立なら財産分与がおこなわれます。調停不成立でも、そのまま審判や裁判に移行する可能性があります。
また、自分が共有財産を意図的に隠すなど悪質な財産隠しが認められたときは、財産隠しに対する損害賠償請求が可能です。
財産分与請求権の除斥期間2年は、2026年までに5年へ改定されることが決まっています。
所有する財産は特有財産であると主張する
共有財産と特有財産は、必ずしも完全に区別されているとは限りません。財産の区別がはっきりしていない状態だと、本当は特有財産のものが共有財産として扱われて財産分与の対象になる可能性があります。
つまり手元に残す財産を多くするには、自分が所有する財産のうち特有財産であるものを主張・立証するのが大切です。特有財産だと証明するには、具体的な証拠も揃えておきましょう。特有財産の立証に有効なものは、主に次の通りです。
- 結婚前の預金通帳
- 結婚前の保険会社の支払明細書
- 結婚前に支払った頭金や住宅ローンに関する書類(不動産売買契約書や金銭消費貸借契約書など)
- 結婚前の就労状況がわかる雇用契約書・在職証明書や退職金見込額証明書
- 親族からの贈与であることがわかる贈与契約書
- 相続財産であることがわかる遺産分割協議書や遺言書など
ただし、共有財産と特有財産の境界は証拠があっても立証や計算が難しいとされています。正確な区分や金額を出したいときは、財産分与に強い弁護士などへの相談がおすすめです。
財産形成の貢献度や偏りを主張する
原則として夫婦の合意がない場合、財産分与の分配割合は2分の1ルールが適用されます。しかし夫婦の合意がなくても、財産分与の割合変更が認められる場合があります。夫婦の共有財産において、財産形成の貢献度や偏りが発生しているケースです。
財産形成の貢献度や偏りによって2分の1ルールの変更の可能性があるケースは、主に次の通りです。
| 財産分与の分配割合が変更になるケース |
概要 |
| 特殊な才能や能力で財産を築いたと認められた |
会社経営者や士業・医師などの特殊な資格によって高収入となっている場合 |
| 夫婦の一方が財産形成のほとんど寄与していない |
夫婦生活がほぼ一方の収入で成り立っているにもかかわらずもう一方は家事・育児への貢献度が低いと認められる場合 |
| 特有財産が原資となって共有財産を築いている場合 |
一方の特有財産(相続した賃貸物件など)を活用した投資・運用によって共有財産の形成をおこなっている場合 |
| 夫婦の一方の浪費が激しい |
一方のギャンブル、ブランド品の購入、無計画かつ結果が出ない投資などの浪費によって共有財産を著しく減少させた場合 |
たとえば東京地裁平成15年9月26日の判決だと、「共有財産の原資が東証一部上場の経営者だった夫の特有財産であった」「夫が運用・管理に携わり妻の関与を認める証拠が足りなかった」として、共有財産220億円のうち10億円が財産分与の上限だと判断されました。
東京家裁平成6年5月31日の審判による判決だと、芸術家同士の夫婦において「妻が家事・育児をほぼ全面的に担当していたうえで、妻の収入が夫の収入を上回っている」などの事実を総合的に考慮したうえで、割合を6:4とする判断になっています。
このように、財産形成の貢献度や偏りによっては、財産分与の分配割合の変更が認められる可能性があります。
財産分与に不満があっても絶対にやってはいけない行動
収入の違いや家事・育児の貢献度などについては夫婦それぞれ言い分があり、「この財産分与の分配割合は納得できない」と不満を持つケースも珍しくありません。しかし、いくら財産分与に不満があるからといって、絶対にやってはいけない行動が存在します。
財産分与に不満があっても、絶対にやってはいけない行動は次の通りです。
- 共有財産になるものを隠す
- 財産開示に応じない
- 財産分与請求権の放棄や離婚無効とするために相手へ圧力をかける
- 財産分与する旨を決めても支払いを拒否する
上記の行動で財産分与をしない方向に動こうとすると、法的措置による損害賠償に発展する可能性が非常に高いです。法廷での争いでも圧倒的に不利になるでしょう。以下では、それぞれの詳細を解説します。
共有財産になるものを隠す
共有財産になるものを隠して財産分与しないようにする行為は、民法上の不法行為に該当する可能性があります。財産隠しによって相手に損害を与えたときは、損害賠償請求の対象です。離婚協議のやり直しを求められる可能性も高いでしょう。
では、刑事罰はどうでしょうか。財産隠しによって配偶者を欺き財産を栄養とする行為は、刑法上の詐欺罪や窃盗罪などに該当するように思われます。
しかし、夫婦間の一定の犯罪には「親族相盗例(刑法第244条)」と呼ばれる、「親族間で発生した窃盗、詐欺、恐喝、横領、背任などの罪および未遂罪は免除される」というルールが適用されます。そのため、財産隠しに対して刑事責任を問うことはできません(親族以外に共犯がいたときは共犯に対して刑事責任を問える)。
とはいえ、ここで「刑事罰に当たらないなら財産隠しがバレても気にしない」と考えるのは避けましょう。財産隠しによって配偶者に損害を与えると、配偶者や子どもとの関係亀裂、周囲の人間からの信頼低下など、損害賠償に加えて自分の評判を大きく落とすことになります。
なお、逆に相手が共有財産を隠すケースも想定されます。相手が隠した共有財産をすべて出させれば分配金額が増えるため、結果としてこちらが手元に残せる財産も多くすることも可能です。
財産隠しでよくある手口
財産隠しの手法を知っておけば、逆に相手の財産隠しに気づける可能性が上がります。財産隠しでよくある手口は主に次の通りです。
- 配偶者が知らないネット銀行口座に共有財産を移動する
- 貸金庫などに現金やそのほか財産を預けておく
- へそくりやタンス預金など身近な場所に現金として隠しておく
- 有価証券、不動産、自動車、金の延べ棒などの現金以外の資産に換えておく
- 「家や自分のデバイスを使わない」「長期間で少しずつ移動させる」など見つからない工夫をおこなう
財産開示に応じない
相手側から財産開示を求められた場合、素直に応じるようにしてください。財産開示を拒否すると、配偶者から「共有財産を隠しているのでは」と疑われ、法的措置を取られる可能性が高くなります。
もし職場や銀行に対して法的措置を取られると、職場の同僚などからの心象が大きく低下し、仕事などに悪影響が出るでしょう。
そもそも拒否したところで、弁護士照会、裁判所による調査嘱託、調停や訴訟など法的に財産開示を求める方法はいくつも存在します。また夫婦は赤の他人ではないため、相手も財産隠しの証拠なども集めやすいでしょう。そのため、財産開示に応じないのはデメリットのほうが大きいと言えます。
弁護士照会とは、弁護士法第23条に基づき、企業や団体に対して預金口座の有無や残高、契約内容、住所などを弁護士が照会できる仕組みです。裁判所による調査嘱託とは、調査するに足る証拠が認められたときに、必要な相手から必要な情報を開示させられる制度です。
財産分与請求権の放棄や離婚無効とするために相手へ圧力をかける
財産分与請求権の放棄や、離婚そのものの考え直しなどは、離婚成立前なら話し合いで意見を変更できます。しかし、だからといって相手に対して圧力をかけて無理やり要求を飲ませるのは絶対にNGです。
たとえば離婚協議中に「権利を放棄しないとケガじゃ済まされない」「離婚を諦めないと親がどうなるかわからないぞ」といった脅迫的な言動で相手に従わせたときは、後から離婚の取り消しや無効が認められる可能性があります。
また、架空の借金の存在をでっち上げて「離婚しないと迷惑がかかる」「返済が必要だから財産を渡せない」など、詐欺まがいの言動で離婚を成立させたときも取り消しや無効となるケースがあります。
さらに暴力・脅迫行為がひどいときは、刑事罰になるケースも考えられるでしょう。前述した親族相盗例は特定の財産犯にのみ適用されるルールであり、暴力・脅迫行為は対象外です。
財産分与をする旨を決めても支払いを拒否する
財産分与をする旨を協議で決めた後に支払いを拒否すると、相手から法的措置を取られる可能性が出てきます。想定される相手からのアプローチは次の通りです。
- 相手や相手の弁護士から「財産分与は拒否できない」と説得がくる
- 離婚調停・裁判や財産分与調停・審判が申し立てられる
- 公正証書に強制執行の旨を記載していたときは強制執行に移る
もし失業や病気をともなう金銭的な事情などで財産分与が難しくなったときは、財産分与額や分割払いにおける減額交渉を検討してみてください。
余計な財産分与をしないためのポイント
財産分与する必要がない財産まで分配しないことが、財産分与の金額を抑えるために大切な考え方です。余計な財産分与をしないためのポイントは、「自分と相手の財産の調査・評価を徹底すること」「財産分与に強い弁護士に相談すること」の2つが挙げられます。
自分・相手の財産の調査と評価をおこなう
適切な財産分与のために重要なのは、自分と相手の財産の調査・評価をおこない、「共有財産と特有財産を明確に区別する」「財産隠しをされていないか」を確認することです。財産の金額と所在をはっきりさせれば、自分の特有財産を主張しやすい、相手が隠した共有財産を財産分与額に加えられるなどのメリットがあります。
財産の調査方法は、財産の種類によって変わります。
| 財産の種類 |
調査に必要な書類・情報 |
| 預貯金 |
銀行口座の残高、入出金の動向、不自然な出金先の口座 |
| 有価証券 |
証券口座の履歴、取引報告書、残高証明書 |
| 不動産 |
登記簿謄本、不動産売買契約書、固定資産税評価証明書、不動産会社や不動産鑑定士の査定、住宅ローン関係の書類 |
| 貴金属や家具などの動産関係 |
現物の確認、クレジットカード明細やECサイトなどでの購入履歴、銀行口座の出金記録 |
| 自動車 |
自動車の売買契約書、中古車の査定、車検証 |
| 民間保険関係 |
保険料の支払明細書、保険契約書、解約返戻金関係の有無 |
| 退職金 |
勤務先の退職金規定、退職金の支給条件、勤務実態 |
財産隠しを見破るには、弁護士照会による確認も視野に入れましょう。とはいえ弁護士照会だけだと回答を拒否される可能性があるため、裁判所への調査嘱託も検討してみてください。
財産分与に強い弁護士に相談する
離婚時にできる限り財産分与しない方向に話を進めたいときは、財務整理に強い弁護士への相談がおすすめです。弁護士費用20万円以上が見込まれるものの、財産分与に関するさまざまな対応を任せられます。
財産分与に強い弁護士に相談するメリットは次の通りです。
- 財産形成の貢献度や偏りを正確に判断してくれる
- 財産調査のサポートをしてくれる
- 協議・調停・裁判の対応も任せられる
財産分与に強い弁護士なら、当サイト「ツナグ離婚弁護士」にて無料検索できます。都道府県別・相談内容別で検索を絞れるため、あなたにぴったりの弁護士とマッチングが可能です。検索した弁護士事務所の特徴や強み、費用をまとめたコラム記事も掲載しているため、相談前に弁護士事務所の概要を確認してからの検討が可能です。
まとめ
財産分与は、原則として2分の1ルールが適用されます。夫婦の合意があれば、分配割合や財産の種類は自由に変更が可能です。
「財産分与請求権は放棄できる」「特有財産は財産分与の対象外になる」「2年間の除斥期間がある」などの決まりを適用したときは、財産分与をしないおよび財産分与額を減らせるといった対応ができる可能性があります。
そのため自分の手元に財産を多く残すには、「財産分与請求権をお互いに放棄するよう話し合う」「自分の特有財産を主張する」「除斥期間を主張する」などの方法が有効です。財産分与について話し合いや法的な争いをするときは、財産分与に強い弁護士への相談がおすすめです。
離婚時の財産分与に関してよくある質問
財産分与について弁護士に依頼したときの費用はいくら?
財産分与について弁護士に依頼したときの費用は、おおよそ次の通りです。
| 弁護士費用 |
おおまかな金額 |
| 相談料 |
・30分あたり5,000円
・初回無料や何度でも無料のところもあり |
| 着手金 |
・示談:10~30万円程度
・調停:20~40万円程度
・審判や訴訟:30~50万円程度
・調停や訴訟に進んだ場合は着手金が加算されるケースがあり |
| 報酬金 |
・基本報酬金:10~60万円程度
・経済的利益の額(得られた額、減らせた額)に応じた金額の10~20%程度 |
| 日当やそのほかの費用 |
出張日当、交通費、郵便切手代(内容証明郵便含む)、公文書取得費用、収入印紙代など、事務所や事案によって異なる |
費用の詳細は、以下の記事をご覧ください。
財産分与で得たものに税金はかかる?
財産分与で得た財産に関しては原則として贈与税や所得税などの国税はかかりません。しかし、不動産を取得したときは地方税(不動産取得税など)、相場を大きく上回る財産を得たときは贈与税がかかる可能性があります。また財産を渡した側が不動産や株式など価値が増減するものを分配したときは。取得価額と譲渡時点の時価の差額に対して所得税がかかる可能性があります。
また離婚が贈与税・相続税を免れるためにおこなわれたと判断されたときは、財産分与によって取得した財産すべてが贈与税の対象です。