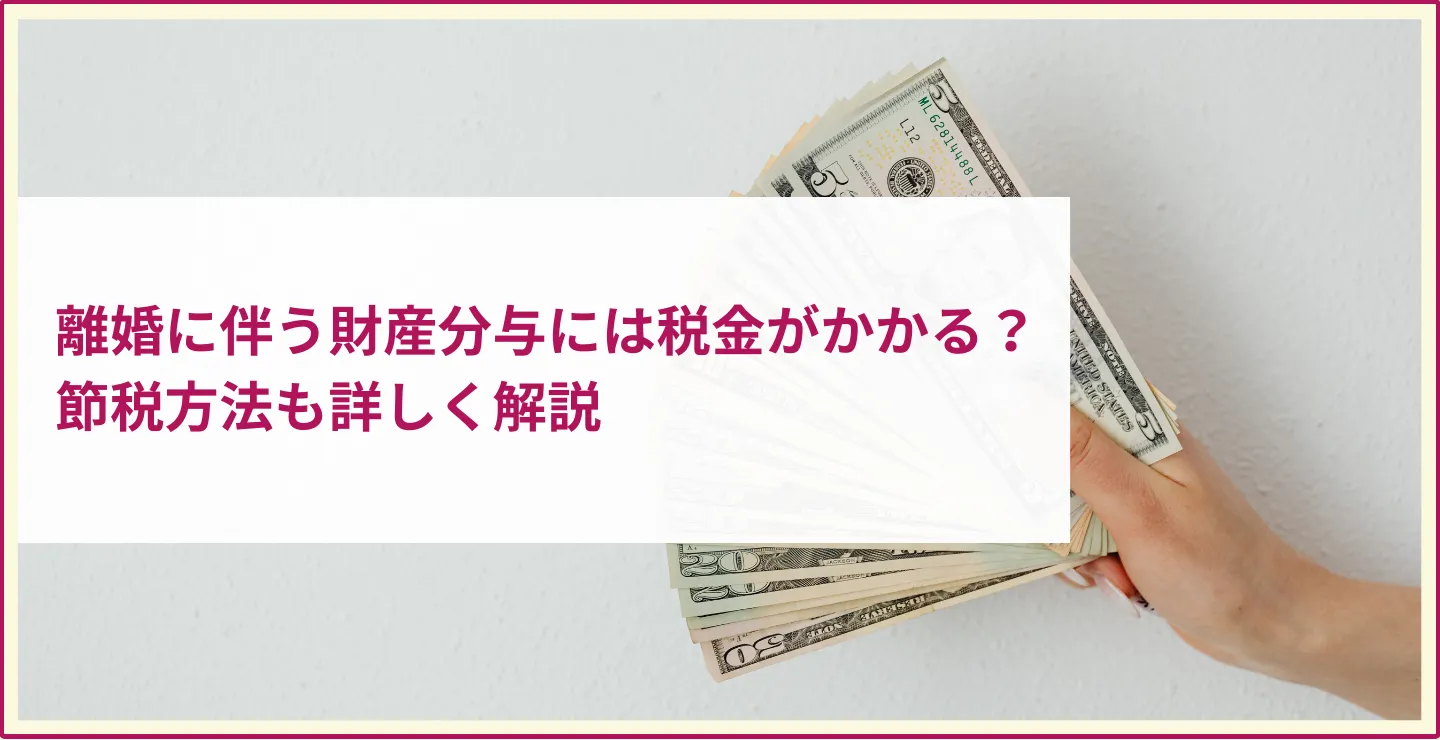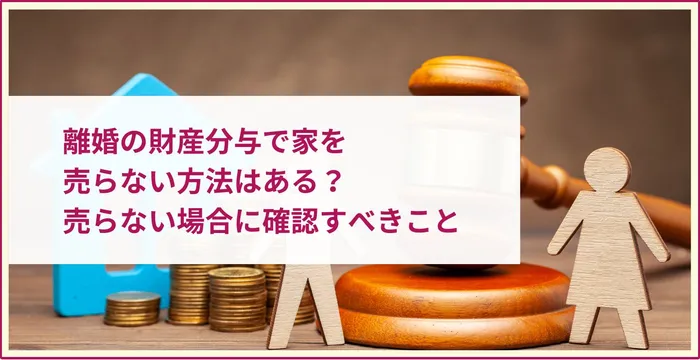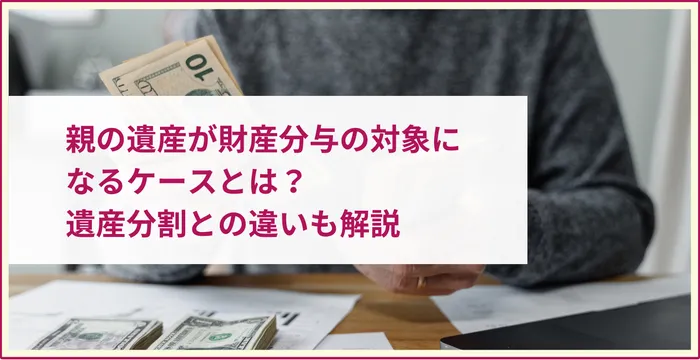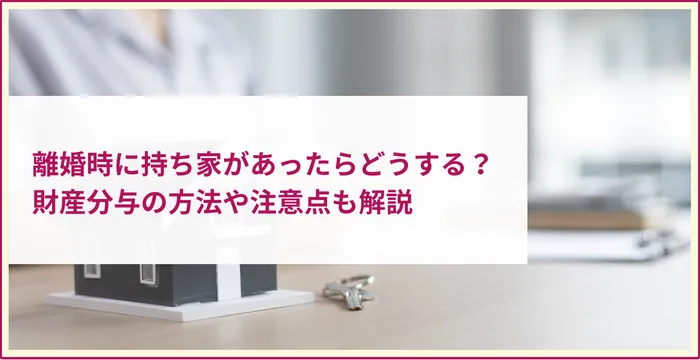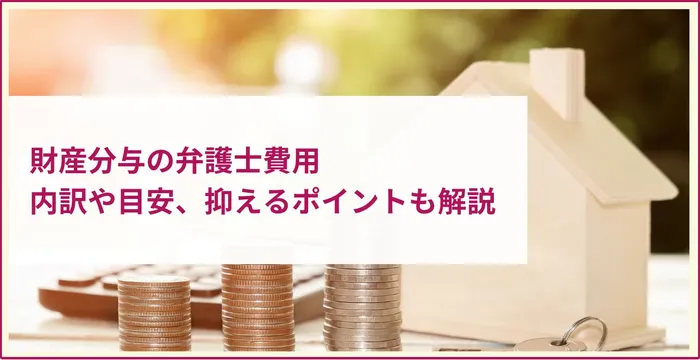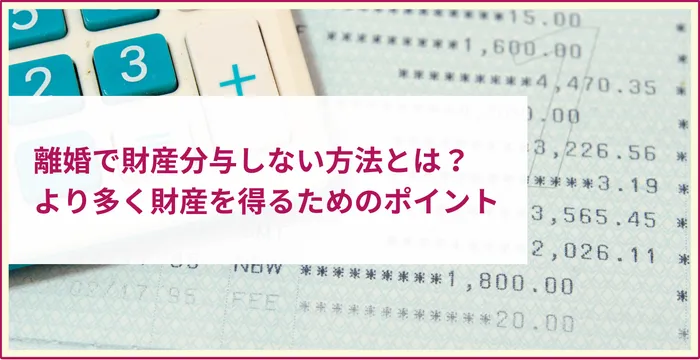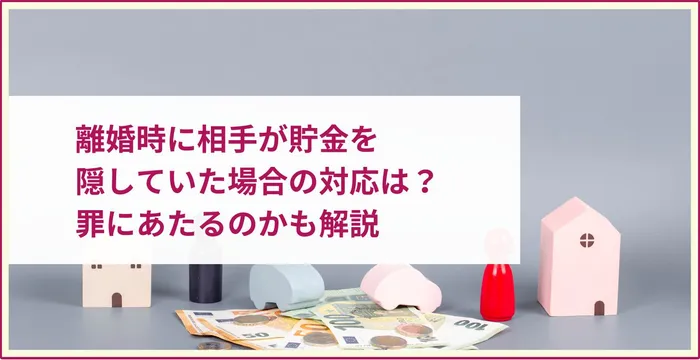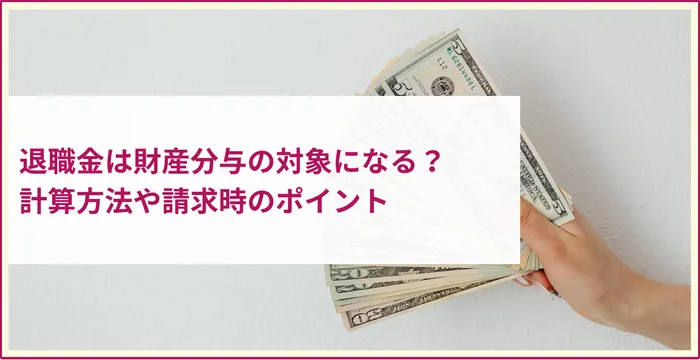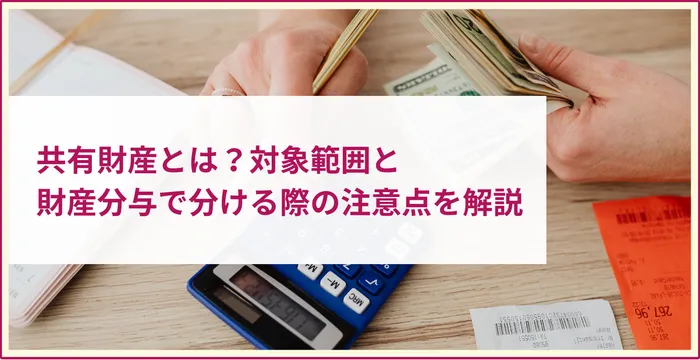財産分与には基本的に税金がかからない
財産分与で受け取った財産は、基本的に税金がかかりません。
財産分与とは、離婚の際、婚姻期間中に夫婦で築いた財産を分配することで、以下の3種類があります。
| 財産分与の種類 |
概要 |
| 清算的財産分与 |
・結婚中に夫婦で協力して築いた財産を貢献度に応じて公平に分配すること
・離婚の原因によって左右されないので、有責配偶者からの請求も認められる
・1/2ずつ分配するのが一般的
・現金・預貯金、不動産、有価証券、動産・債務などが含まれる
・結婚前から持っていた財産や結婚期間中に相続で取得した財産、別居後に取得した財産などは対象にならない |
| 扶養的財産分与 |
・離婚後、配偶者が生活に困窮してしまうことが明らかな場合、離婚した後も経済的に自立できるまで生活費を扶養すること
・病気や高齢で仕事に就けない場合や専業主婦(主夫)で仕事をしていなかった場合などに認められるケースが多い
・財産分与を請求される側の配偶者に、扶養するだけの能力が必要 |
| 慰謝料的財産分与 |
・慰謝料の支払い義務がある場合に、財産分与に慰謝料分も加味すること
・慰謝料の意味をこめて、財産分与を1/2以上支払ったり、現金での慰謝料支払が困難なため、自分の持分の不動産や車を渡して解決したりする |
財産分与は、受け取る権利として潜在していたものを受け取ります。
夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のために財産分与請求権に基づき給付を受けたもののため、基本的には非課税です。
財産分与に税金がかかる場合もある
財産分与は基本的に税金がかかりませんが、状況によってはかかる場合もあります。
金銭以外の財産分与を行った場合、譲渡所得税が発生する可能性があります。
課税対象になるものは、以下のとおりです。
- 土地などの不動産
- 株式などの有価証券
- 高価な美術品
- ゴルフなどの会員権
また不動産に関しては、譲渡所得税以外に不動産取得税や登録免許税、固定資産税などがかかります。
ここからは、財産分与を受ける側に課税されるケースと、財産分与する側が課税されるケースを解説します。
財産分与を受ける側に課税されるケース
財産分与を受ける側に課税されるケースは、以下のとおりです。
- 受け取った財産が不動産の場合
- 受け取る金額が極端に多い場合
- 偽装結婚とみなされた場合
それぞれ解説します。
不動産は不動産取得税と登記登録免許税、固定資産税がかかる
1つ目は、受け取った財産が不動産の場合です。
不動産を財産分与された場合は、以下の税金がかかります。
それぞれ詳しく解説します。
不動産取得税
不動産取得税とは、土地や家屋などの不動産を取得したときに、都道府県が課税する地方税です。
不動産を財産分与で受け取るときは、基本的に不動産取得税は課税されません。
なぜなら、不動産は夫婦の協力で取得された財産とみなされるためです。
ただし以下のような場合は、不動産取得税がかかる可能性があるため注意が必要です。
- 慰謝料代わりに不動産を譲渡した場合
- 共有名義だった不動産の一方の持分を財産分与した場合
- 不当に課税を免れるために離婚したと判断された場合
なお不動産取得税は、以下の計算式で算出します。
不動産の評価額(固定資産評価額)×税率(4%)=税額
参照:総務省|地方税制度|不動産取得税
ただし土地と住宅については、軽減税率として3%が適用されています。
たとえば、不動産の評価額が3,000万円の場合は、3,000万円×3%=90万円となります。
登記登録免許税
不動産を財産分与された場合は、それに伴い不動産の名義変更をする必要があります。
財産分与で名義変更の登記をする場合、登記登録免許税を納めなければなりません。
財産分与の場合の登記登録免許税は、以下の式で計算します。
登記登録免許税=不動産の固定資産税評価額×2%。
参照:登録免許税の税額表|国税庁
たとえば夫が妻に対して、自宅(評価額4,000万円)を財産分与した場合の登録免許税は、4,000万円×2%=80万円となります。
登録免許税法3条では、不動産を分与する側とされる側が共同して登記登録免許税を納付することになっていますが、不動産を取得した側が負担するのが一般的です。
ただし離婚協議書や調停調書で、登記手続き費用は分与する側が負担すると定めておけば、相手に全額負担させることもできます。
なお、不動産登記の所有者を自分名義に変更していない場合、正式に自分のものと認められません。
そのため、元の所有者に勝手に売却されてしまう可能性があります。
元の所有者が勝手に売却してしまった場合でも売られた相手からは取り戻せないため、不動産を財産分与される場合は、登記申請を忘れずに行いましょう。
固定資産税
財産分与で不動産を取得した場合、翌年以降から毎年、固定資産税を支払っていかなければなりません。
固定資産税とは、土地や家屋などの不動産や事業用の償却資産などに課される税金で市町村(東京23区は都)に納税します。
固定資産税は、毎年1月1日時点での不動産の所有者に課税され、以下の式で計算します。
固定資産税=固定資産税評価額×1.4%
※税率は自治体により異なる場合もあります。
参照:総務省|地方税制度|固定資産税
たとえば、固定資産評価額が2,000万円の場合は、固定資産税は2,000万円×1.4%=28万円となります。
また、不動産が市街化区域内にある場合は都市計画税も課税されます。
計算式は、以下のとおりです。
都市計画税=固定資産税評価額×0.3%
参照:総務省|地方税制度|都市計画税
なお財産分与の時期によっては、財産分与した側がすでに所有者ではないのに、固定資産税を課税される可能性があります。
年度途中に離婚して財産分与を行う場合は、その年の固定資産税をどのように清算するか決めておきましょう。
日割り計算するのが公平ですが、お互いが合意すれば一方が負担する形でも問題ありません。
トラブルを避けるためにも、話し合って決めた内容は、離婚協議書や公正証書などに残しておきましょう。
受け取る金額が極端に多い場合は贈与税がかかる
2つ目は、受け取る金額が極端に多い場合です。
受け取る金額が財産分与の相当額をはるかに上回っているとみなされる場合は、それ相応の贈与税がかかります。
なぜなら「財産分与は本来の自分の取り分を受け取るだけ」という前提条件から外れてしまうためです。
たとえば夫婦共有の財産が預貯金5,000万円だったとします。
財産分与は1/2ずつ分配するのが一般的なため、5,000万円の半分である2,500万円を夫婦がそれぞれ取得する場合は、贈与税はかかりません。
しかし5,000万円すべてを妻が受け取った場合は、妻の取り分が多すぎるとみなされ、本来受け取るべき金額を超えた分に対して贈与税がかかる可能性があります。
なお、贈与税が課税される金額に明確な基準はなく、婚姻中の夫婦間の事情を考慮して判断されます。
特殊な才能・能力によって財産を築いた場合や一方の浪費が激しかったケースなどは、夫婦双方の同意があれば、財産分与の割合を1/2以外にも変更が可能です。
どの程度の割合だと贈与税がかかるか判断できない場合、は弁護士に相談するのもよいでしょう。
偽装離婚とみなされた場合は贈与税がかかる
贈与税や相続税を免れることを目的とした離婚だと明らかに分かる場合は、偽装離婚とみなされます。
偽装離婚とは、実際には夫婦関係にあって別れるつもりがないのに、あえて離婚届を提出して体外的に離婚を装うことです。
たとえば、離婚後も一緒に暮らしていたり、婚姻期間が短いのに財産のほとんどを分与されたりする場合、偽装離婚とみなされる可能性があります。
偽装離婚の場合は、財産分与を受けた全額に贈与税がかかります。
税金逃れとみなされた場合は、延滞税や不申告加算税、重加算税などが課税され、支払う税金の総額が大幅に増加することもあるのです。
また偽装離婚は、公正証書原本不実記載等罪(刑法157条)に該当する可能性があります。
刑罰は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
なお夫(妻)の死亡後に偽装離婚が発覚した場合、妻(夫)への財産分与により相続財産が減っていても相続税はかかりません。
財産分与を装った偽装離婚による贈与税の脱税であるため、夫(妻)の死後であっても贈与税が課されます。
財産分与をする側には譲渡所得税がかかる場合がある
現金や預貯金以外で財産分与をする場合は、譲渡所得税がかかる場合があります。
譲渡所得税とは、取得費と譲渡費用を足した場合にプラスの利益が出た分にかかる税金です。
財産分与で課税対象になるものは、次のとおりです。
- 土地などの不動産
- 株式などの有価証券
- 高価な美術品
- ゴルフなどの会員権
譲渡所得は、次の式で計算します。
譲渡所得=譲渡評価額 -(取得費+譲渡費用)
取得費や譲渡費用の概要は、以下のとおりです。
|
概要 |
例 |
| 取得費 |
譲渡・売却する財産を取得した際にかかった購入代金や購入手数料などの費用 |
・売却した土地や建物の購入代金
・不動産会社に支払った仲介手数料
・購入時に納付した印紙税・登録免許税・不動産取得税などの税金
・司法書士に支払った登記手数料
・エアコンなどの設備費
・増改築費用など |
| 譲渡費用 |
譲渡・売却するために直接支出した費用 |
・土地や建物を売却するために支払った仲介手数料
・売買契約書の印紙代
・貸家を売却するため、借家人支払った立退料
・土地を売却するため建物を解体したときの取壊し費用
・借地権を売る際に、地主の承諾を得るために支払った名義書き換え料など |
参照: 譲渡費用となるもの|国税庁・ 取得費となるもの|国税庁
譲渡所得税は(譲渡評価額)-(取得費用+譲渡費用)の差額がゼロやマイナスだと課税されません。
たとえば、7年前に3,000万円で購入した不動産を夫が妻に財産分与する場合、分与時の価格が2,500万円であれば譲渡所得税はかかりません。
有価証券やゴルフの会員権なども、購入時から価値が下がっている場合は、譲渡所得税は非課税です。
また不動産の譲渡所得がゼロ以下の場合は、ほかの不動産譲渡所得と損益通算を行えば、その年の所得税を軽減できます。
なお、譲渡所得税は「所得税」「住民税」「復興特別所得税」の3つの税金を合計したものです。
財産の所有期間の長さにより、次の2つに分類され、それぞれ税率が異なります。
| 譲渡所得の種類 |
所有期間 |
税率(所得税+住民税+復興特別所得税) |
| 長期譲渡所得 |
分与した年の1月1日現在で所有期間が5年超 |
20.315%(15%+5%+0.315%) |
| 短期譲渡所得 |
分与した年の1月1日現在で所有期間が5年以下 |
39.63%(30%+9%+0.63%) |
譲渡所得税の具体的な計算例をあげてみましょう。
【例】
・結婚期間中に購入した夫名義の自宅を財産分与で妻に譲渡する場合
・購入時価格:3,000万円
・財産分与時の時価:3,800万円
・譲渡時にかかった費用:150万円
・不動産の所有期間:3年
譲渡所得=3,800万円-(3,000万円+150万円)=650万円
650万円の譲渡所得が発生しているため、譲渡所得税がかかります。
所有期間が5年以下のため短期譲渡所得となり、以下のように計算されます。
650万円×39.63%=257万5,950円
財産分与にかかる税金の節税方法
財産分与にかかる税金の節税方法は、以下のとおりです。
それぞれ解説します。
金銭で財産分与を行う
1つ目の節税方法は、金銭で財産分与を行うことです。
金銭で支払う場合は、譲渡所得税・不動産取得税・登録免許税・固定資産税などの税金はかかりません。
節税したいのであれば不動産や有価物などの現物ではなく、金銭での財産分与も検討しましょう。
ただし財産分与は夫婦で築き上げた財産を公平に分配することです。
必要以上の財産を受け取ると、贈与税が課税される恐れがあるため、客観的にみて適度な割合で分与するよう心がけましょう。
特例の制度を利用する
2つ目の節税方法は、特例の制度を利用することです。
利用できる特例は、以下のとおりです。
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 贈与税の配偶者控除
- 軽減税率特例
それぞれ解説します。
居住用財産の3,000万円特別控除を利用する
財産分与でマイホームを渡す際は「居住用財産3,000万円の特別控除」を利用できます。
「居住用財産3,000万円の特別控除」とは、一定の要件を満たして居住用財産を売却したとき、所有期間の長短にかかわらず、譲渡所得から最大3,000万円まで控除できる特例です。
特例を受けるためには、以下の要件に該当しなければなりません。
- 自分が居住している家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売却すること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地などの場合は、居住しなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
また、家屋を解体した場合は、次の2つの要件に該当すること
・家屋を解体した敷地の譲渡契約が、家屋解体から1年以内に結ばれ、かつ、居住しなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
・家屋を解体してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などに利用していないこと
- 売却した年の前年や前々年に3,000 万円特別控除の特例(「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」によりこの特例の適用を受けている場合を除く)またはマイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例を受けていないこと
- 売却した年、その前年や前々年にマイホームの買換えや交換の特例を受けていないこと
- 売却した家屋や敷地などが、収用等の場合の特別控除など、ほかの特例を受けていないこと
- 災害により滅失した家屋の場合は、その敷地に居住しなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
- 土地や建物の売主と買主が、親族や夫婦、内縁関係にある人や同族会社など特別な関係でないこと
また、次のような家屋を売却した場合は、3,000万円特別控除の特例は適用できません。
- 3,000万円特別控除の特例を受けるためだけに入居した家屋
- 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使用した家屋など、一時的な目的で入居した家屋
- 別荘などのような趣味・娯楽・保養のために所有している家屋
参照:マイホームを売ったときの特例|国税庁
この特例は、譲渡者が居住しなくなってから3年目の12月31日までに譲渡した場合に適用できます。
長期間別居状態で別宅に住んでいた場合は、認められない可能性があるため注意しましょう。
譲渡の相手が譲渡者の配偶者や親族などである場合は利用できないため、離婚後のタイミングで名義変更をする必要があります。
なお、この特例を受けるためには、確定申告が必要です。
確定申告書とあわせて提出する書類は次のとおりです。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
- マイホームを売却した人の住民票に記載されている住所と所在地が異なる場合は、戸籍の附票(今までの住所が記載されている)の写しなど
- 売買契約書コピー(取得時と譲渡時)
- 費用の領収書(取得費用、譲渡費用)
参照:マイホームを売ったときの特例|国税庁
(譲渡評価額)-(取得費用+譲渡費用)の差額がゼロやマイナスであれば確定申告は不要です。
ただし3,000万円特別控除を利用すると譲渡所得がゼロやマイナスになる場合は、確定申告が必要なため、忘れずに手続きをしましょう。
贈与税の配偶者控除を利用する
結婚20年以上の場合、贈与税の配偶者控除を利用すると、居住用不動産を対象とした最大2,110万円の節税が可能です。
贈与税の配偶者控除が2,000万円、その年の贈与税の基礎控除が110万円という内訳となります。
たとえば居住用不動産と購入資金の合計が4,500万円だった場合、2,000万円と110万円を贈与金額から控除できるため、2,390万円に贈与税が課税されます。
4,500万円-2,000万円-110万円=2,390万円
贈与税の配偶者控除の適用要件は、以下のとおりです。
- 夫婦の婚姻期間が贈与の時点で20年を過ぎていること
- 居住用不動産、または居住用不動産を取得するための贈与であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた者が居住しており、その後も引き続き住む見込みであること
- 同じ配偶者との間で、過去に贈与税の配偶者控除の特例を適用していないこと
参照:夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁
贈与税の配偶者控除は、婚姻届を提出していることが前提となるため、事実婚や内縁関係の場合は利用できません。
結婚生活期間のうち戸籍を抜いていた期間がある場合は、その期間を差し引いて20年以上の婚姻期間が必要です。
また、この特例の対象は「居住用不動産」のみのため、別荘として利用する予定の住宅やセカンドハウス、賃貸住宅(収益物件)は対象外となります。
日本国内にある不動産でなければならないため、他国の不動産を贈与したとしても贈与税の配偶者控除は適用されません。
土地や家屋の贈与後、すぐに売却してしまうと、土地や家屋の譲渡による所得税を不当に安くしたとみなされ税務署から指摘される場合があるため注意が必要です。
なお贈与税の配偶者控除を利用するためには、税額がゼロになるときでも贈与税の申告を行う必要があります。
贈与税を申告する場合は、贈与税の申告書に次の書類を添付して提出します。
- 財産の贈与を受けた日から10日以降に作成された戸籍の謄本または抄本
- 財産の贈与を受けた日から10日以降に作成された戸籍の附票の写し
- 居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得したと証明できるもの
金銭ではなく居住用不動産を贈与された場合は、上記書類のほかに、その居住用不動産を評価した評価明細書などの書類提出が必要です。
贈与税の申告をしないと、税務署では贈与税の配偶者控除を利用したのか申告漏れなのかが判断できず、適用が認められません。
適用が認められないと多額の贈与税を支払うだけでなく、延滞税や不申告加算税なども課税され負担が大きくなるため、忘れずに手続きしましょう。
軽減税率の特例を利用する
所有期間が10年を超える居住用不動産を財産分与する場合、一定の要件を満たすと譲渡所得税の税率が軽減されます(租税特別措置法31条の3)
特例を受けるための要件は、以下のとおりです。
- 日本国内にある自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともに敷地を売却すること
- 以前住んでいた家屋や敷地の場合は、住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
- 自分が住んでいた家屋が災害によって滅失した場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
- 売却した年の1月1日で、売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること
- 売却した年の前年および前々年に、軽減税率の特例を受けていないこと
- 売却した家屋や敷地について、マイホームの買換えや交換の特例など、ほかの特例を受けていないこと
- 親族や夫婦、内縁関係にある人や同族会社など、特別な関係がある人に売却したものではないこと
住んでいた家屋、または住まなくなった家屋を取り壊した場合は、以下の3つの要件に該当する必要があります。
- 取り壊された家屋およびその敷地は、家屋が解体された年の1月1日で所有期間が10年を超えていること
- その敷地の譲渡契約が家屋を解体してから1年以内に締結され、かつ、居住しなくなった日から3年目の12月31日までに売却すること
- 家屋を解体してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などに利用していないこと
参照:マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁
この特例は、3,000万円の特別控除と併用可能です。
ただし「売却した年の前年および前々年に、軽減税率の特例を受けていないこと」という条件があるため、適用できるのは3年に1回となります。
また、特定居住用財産の買換え特例や、住宅ローン控除などとは併用できません。
軽減税率の特例を利用した場合の税率は、以下のとおりです。
|
長期譲渡所得が6,000万円以下の部分 |
長期譲渡所得が6,000万円超えの部分 |
| 所得税 |
譲渡所得×10% |
譲渡所得×15% |
| 住民税 |
譲渡所得×4% |
譲渡所得×5% |
| 復興特別所得税 |
譲渡所得×0.21% |
譲渡所得×0.315% |
| 合計 |
譲渡所得×14.21% |
譲渡所得×20.315% |
参照:マイホームを売ったときの軽減税率の特例|国税庁
具体的な計算例をあげてみましょう。
【例】
・譲渡額:1億3,000万円
・取得費:7,000万円
・諸経費:500万円
まず譲渡所得を計算します。
・譲渡所得:1億3,000万円-(7,000万円+500万円)=5,500万円
譲渡所得のうち6,000万円以下の部分の税率は14.21%なので、5,500万円×14.21%=781万5,500円となります。
軽減税率の特例と3,000 万円特別控除を併用する場合は、譲渡所得から3,000万円を控除しておきます。
上記の例の場合、計算式は次のとおりです。
譲渡所得5,500万円-3,000万円=2,500万円
2,500万円×14.21%=355万2,500円となります。
なお、この特例を適用するためには、確定申告が必要です。
確定申告書に以下の書類を添えて提出します。
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
- 売却した居住用家屋やその敷地の登記事項証明書
- マイホームを売却した人の住民票に記載されている住所と所在地が異なる場合は、戸籍の附票(今までの住所が記載されている)の写しなど
- 譲渡した土地や建物の全部事項証明書
- 売却時の書類の写し(売買契約書など)
- 取得時の書類の写し(売買契約書・請負契約書等・領収書など)
- 住民票の写し、またはマイナンバー
万が一、確定申告をしなかった場合は、無申告加算税や延滞税がかかる場合があるため、忘れずに行いましょう。
財産分与をする側・される側で注意すべき点
財産分与をする側とされる側の注意すべき点は、以下のとおりです。
- 財産分与をする側は、確定申告を忘れずに行う
- 財産分与をされる側は、適正価格の調査を行う
それぞれ解説します。
【財産分与をする側】確定申告を忘れずに行う
財産分与が不動産や有価証券などで行われたとき、財産分与する側に、譲渡所得税がかかる場合があります。
譲渡所得税とは、不動産や株式、ゴルフ会員権などの資産の譲渡により譲渡所得が発生した場合にかかる税金です。
譲渡所得税がかかる場合は、自動的に納税通知書が届くわけではないため、自ら確定申告をしなければなりません。
財産が値下がりしており譲渡所得が発生しない場合は確定申告は不要ですが、特例を活用して税額がゼロになる場合は確定申告が必要です。
確定申告が必要な場合は、財産を譲渡した翌年の2月16日から3月15日までに忘れずに手続きを行いましょう。
なお、譲渡所得税の計算方法は複雑で難しいため、税務に強い弁護士に試算してもらうのも1つの方法です。
弁護士であれば、課税リスクを見とおした上で、財産の分与方法や特例の利用など、節税方法も提案してくれるでしょう。
また離婚した場合、配偶者や子どもがいたために受けられていた所得控除が受けられなくなることがあります。
離婚により受けられなくなる所得控除と、受けられるようになる所得控除は、以下のとおりです。
| 離婚により受けられなくなる所得控除 |
・配偶者控除:38万円控除
・配偶者特別控除:納税者と配偶者の所得金額に応じて1~38万円控除
・扶養控除:38万円控除(特定扶養親族の場合は63万円控除) |
| 離婚により受けられるようになる所得控除 |
・ひとり親控除:35万円控除
・寡婦控除:27万円控除 |
離婚により、子どもの親権を相手側が持った場合は、扶養控除を受けられません。
ただし、養育費を相手側に支払っており、常に生活費・学資金・療養費などの送金をおこなっている場合は「生計を一にする」ものとみなされ扶養控除を受けられます。
扶養控除はどちらか一方の親しか受けられないため、毎年どちらが扶養控除を受けるのか確認が必要です。
ひとり親控除と寡婦控除のどちらの要件も満たしている場合は、重複して適用することはできず、ひとり親控除が優先されます。
【財産分与をされる側】適正価格の調査を行うとよい
財産分与の金額が極端に多い場合、贈与税がかかるリスクがあるため、どの程度が財産分与の適正価格なのか調査しておくとよいでしょう。
適正な財産分与を行うためには、夫婦の共有財産が全部でいくらあるのか、何を持っているかを双方が把握しておかなければなりません。
ただし、財産を隠され、正確な共有財産を把握できない場合もあります。
また財産分与は、婚姻期間中に取得した財産を1/2に分配するのが一般的ですが、特殊な才能・能力によって財産を築いた場合や一方の浪費が激しかったケースなどは、割合を変更できます。
財産分与で贈与税が課税されるケースは極端な場合であり、基本的には贈与税はかかりません。
しかし、どの程度の財産分与なら課税対象になるのか、明確な基準がないため判断ができない場合も多いでしょう。
弁護士に相談すれば、個々の事情を考慮したうえで適正な割合をアドバイスしてもらえます。
財産隠しをされた場合でも、弁護士会照会制度を利用して相手の財産を調査できます。
調停や審判、裁判などの手続中の場合は、家庭裁判所の調査嘱託申し立てにより相手の財産を明らかにすることも可能です。
なお、財産分与を不動産で受け取る場合は、不動産取得税がかかる恐れがあります。
弁護士であれば、課税リスクを考慮したうえで、不動産や金銭で財産分与をした方がよいかアドバイスしてくれるでしょう。
まとめ
現金や預貯金で財産贈与した場合は、基本的に税金がかかりません。
ただし受け取った財産が不動産だったり、財産分与の金額が極端に多かったりした場合、偽装結婚とみなされるケースは贈与税がかかる可能性があります。
また、不動産や有価証券、ゴルフの会員権などを財産分与すると、譲渡所得税がかかります。
財産の額が大きい場合、税金の額も大きくなるため、心配な人は事前に弁護士に相談するとよいでしょう。
なお譲渡所得税が課税される場合は、一定の要件を満たすと居住用財産の3,000万円特別控除と軽減税率特例が利用できます。
控除を適用することにより譲渡所得がなくなる場合でも確定申告は必要です。
確定申告を行わないと無申告加算税や延滞税がかかる場合があるため、忘れずに行いましょう。
思わぬ税金が課税されてしまう事態を防ぐため、財産分与の税金について不安な場合は、税務に強い弁護士に相談されることをおすすめします。