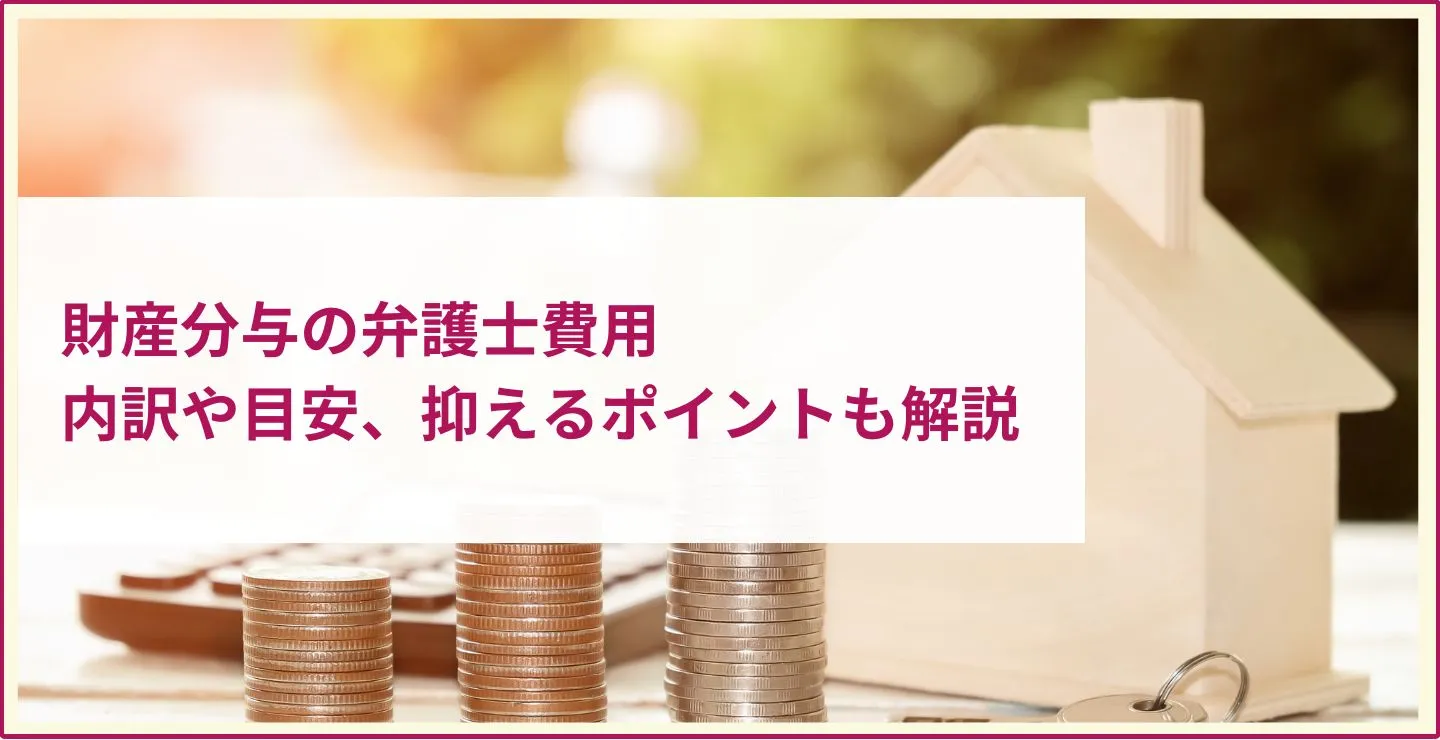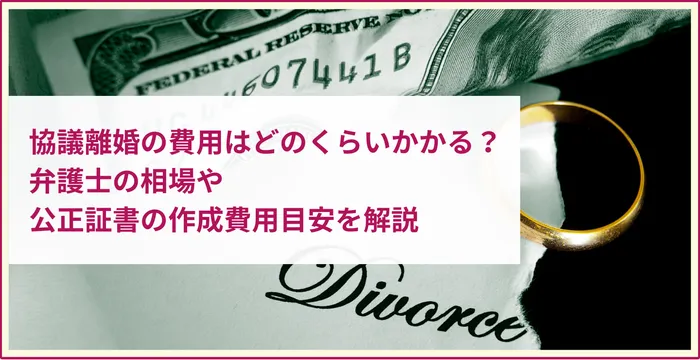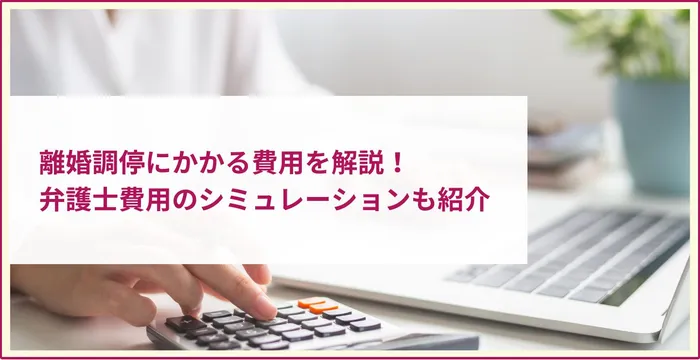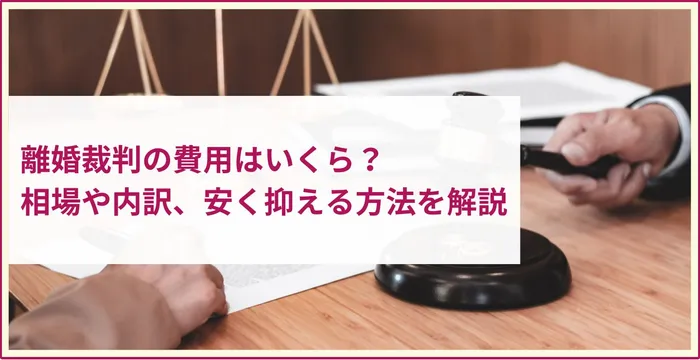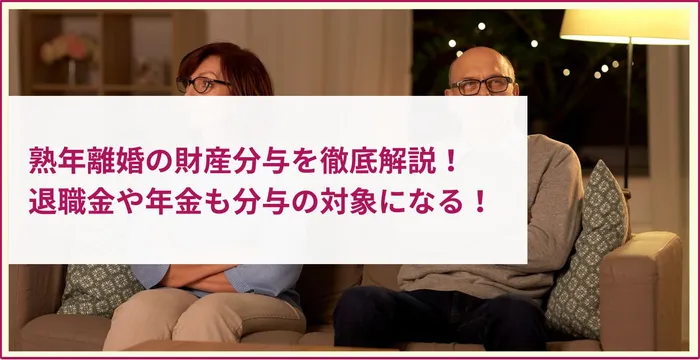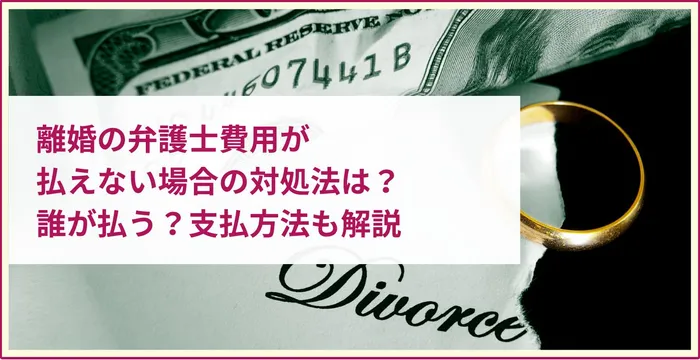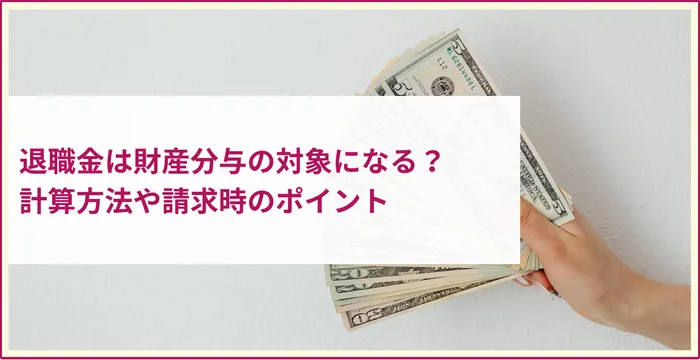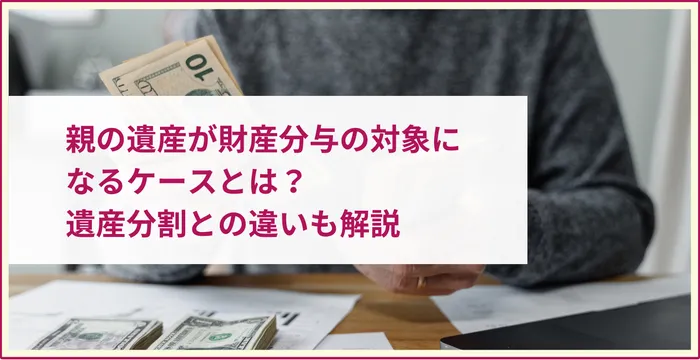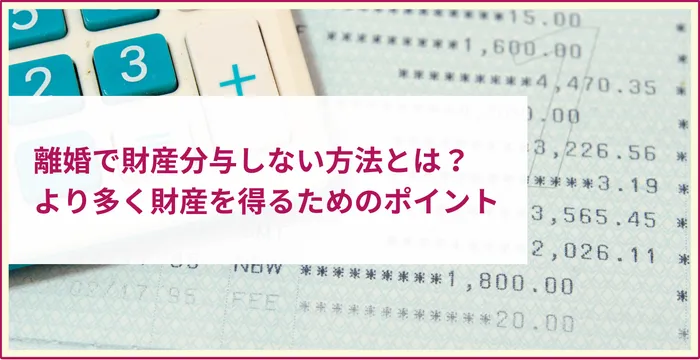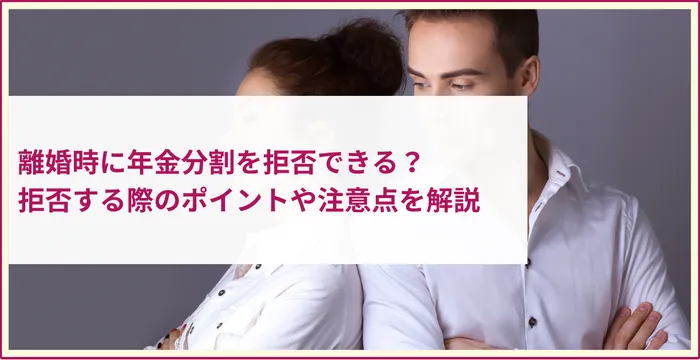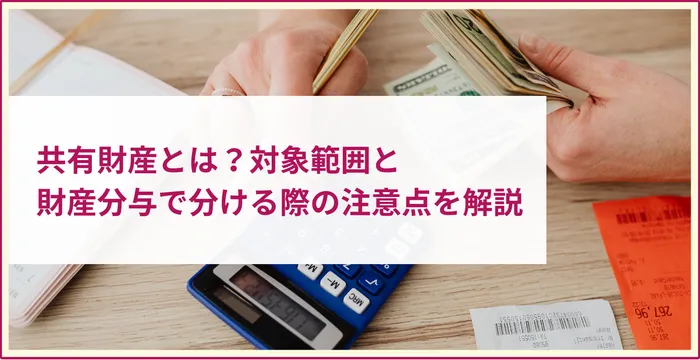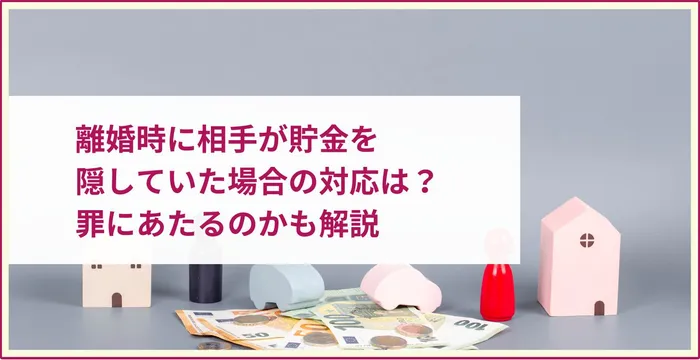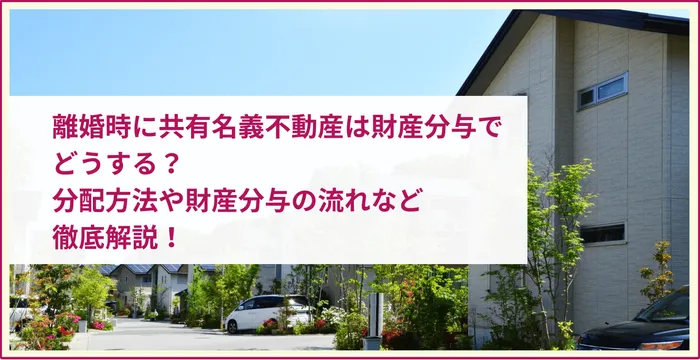離婚で財産分与を依頼する場合の弁護士費用の内訳
離婚時の重要な問題である財産分与について弁護士に対応を依頼する場合、かかる費用の内訳と相場は以下のとおりです。
弁護士費用の内訳・目安(財産分与)
| 内訳 |
相場 |
| 相談料 |
初回:無料
2回目以降:30分までごとに5,000円 |
| 着手金 |
示談:10~30万円
調停:20~40万円(示談からの移行はその分だけ加算)
審判・訴訟:30~50万円(調停からの移行はその分だけ加算) |
| 報酬金 |
基本報酬金:10~60万円
経済的利益の額(得られた額、減らせた額)に応じた金額:10~20% |
| 日当・その他実費 |
出張日当、交通費、郵便切手代(内容証明郵便含む)、公文書取得費用、収入印紙代など、事案によって異なる |
ただし、本記事で紹介しているのは、数ある離婚に関する問題のうち、財産分与だけを争った場合を想定した金額である点に注意してください。あわせて以下のような争いがある場合は、さらに費用がかかります。
- 離婚するかどうか
- 親権者を誰にするか
- 面会交流をどうするか
- 養育費の支払終期や金額はいくらか
- 慰謝料はどうするか
- 年金分割はどうするか
なお、日当や実費は事案によって大きく異なるため、相場として紹介するのには適していません。
仮に、初回相談の後に弁護士に対応を依頼し、示談で解決した場合は20万円以上、審判や訴訟で解決した場合は90万円以上かかるのが一般的です。
ただし、かかる費用は弁護士によって異なるのはもちろん、事案の複雑性や解決する段階(示談、調停、審判・訴訟)などによって異なります。
弁護士から見積もりを取得し、その金額に同意するかどうかは依頼者次第です。最終的には、弁護士と依頼者の双方が具体的な弁護士費用の額を決める点は把握しておきましょう。
とはいえ、弁護士費用には大まかな目安として相場が存在するため、弁護士と費用について話し合う際は相場を参考にすることも大切です。
弁護士費用の内訳である相談料や着手金、報酬金、日当・実費について、それぞれどのような費用なのか、財産分与ではいくらくらいが相場なのかを紹介します。
相談料│法律相談をした際にかかる
相談料とは、弁護士が相談者からの相談に応じるといったサービスの対価です。以下のような疑問や悩みに対応してもらえます。
- 財産分与を請求できるかどうか
- 財産分与の対象になる財産はどれか
- 不倫した側に支払う義務はないと言われたが、どうなのか
- オーバーローンの不動産は財産分与でどうするのか
- 財産分与を拒まれているが、どうすればよいか
- いくらぐらい請求できそうか
- どうやって請求すればよいか
- いつ財産の分与を受けられるのか
もちろん、上記以外の疑問や悩みでも、弁護士に相談することは可能です。
相談料は、財産分与の問題に限らず、初回の相談に限って無料としている弁護士は少なくありません。無料でない場合や2回目以降、無料の時間を超過した場合などは、30分までごとに5,000円(税抜)程度の相談料がするのが一般的です。
法律相談は、疑問を解消し、悩みの解決策を知ることができるのはもちろん、依頼する弁護士を見極めるための重要な機会でもあります。同じ内容を複数の弁護士に相談しても問題ありません。
財産分与で問題に直面しそうな場合、ぜひ早めに複数の弁護士に相談をしてみましょう。
着手金│正式に依頼したときに支払う
着手金とは、弁護士に依頼したときに発生する費用です。いわゆる初期費用であり、財産分与の請求が認められなかったり、1円も減額できなかったりした場合でも返還されません。
財産分与についての着手金の相場は、おおむね10~50万円程度です。ただし、以下のように段階に応じて設定している弁護士が少なくありません。
財産分与の着手金の相場
| 段階 |
着手金の相場 |
| 示談 |
10~30万円 |
| 調停 |
20~40万円
(示談からの移行でその分だけ加算) |
| 審判・訴訟 |
30~50万円
(調停からの移行でその分だけ加算) |
例えば、示談の段階で弁護士に依頼すると着手金は20万円です。しかし、示談が成立せず調停に移行すると10万円加算(合計30万円)、さらに審判や訴訟に移行すると10万円加算(合計40万円)といったように、段階に応じて加算される場合があります。
このような料金体系では、最終的に審判や訴訟まで移行することが想定される場合は着手金を高めに見積もっておくことが大切といえます。
なお、離婚自体に争いがある場合は10~20万円加算、親権について争いがある場合は10~30万円加算といったように、離婚に関する争いが多いほど高くなるケースがある点は把握しておいてください。
報酬金│事件が成功した場合に支払う成果報酬
報酬金とは、事件解決時に、事件の成功の度合いに応じて支払う費用です。
財産分与については、以下のように基本報酬と経済的利益に応じた金額の合計額を報酬金としている弁護士が多いといえます。
財産分与の報酬金
| 報酬金の算定要素 |
金額 |
| 基本報酬金 |
示談:20万円
調停:30万円
審判・訴訟:40万円 |
| 経済的利益に応じた金額 |
10~20% |
報酬金は、一般的に経済的利益を得なければ発生しません。ただし、財産分与の場合は、不利な内容で解決しても基本報酬金を請求される可能性がある点に注意してください。
例えば、相手から財産分与として100万円を請求されており、調停で100万円を支払う内容で解決したとします。この場合、経済的利益(減額分)に応じた金額が0円でも、報酬金は基本報酬の30万円となる場合があります。
請求された側の経済的利益は減額できた額であるところ、上記の例では当初の請求額100万円に対して解決額も100万円なので、減額できた額(経済的利益)は0円となります。
具体的な計算方法は弁護士によって異なる場合があるため、報酬金の計算方法は依頼前によく確認してください。
日当・その他実費│弁護士が遠方に出張したり、裁判所に出廷したりするときにかかる
日当とは、弁護士の時間を拘束した時に発生する費用です。財産分与については、調停や訴訟などで弁護士が裁判所に出頭する際に発生します。
日当の具体的な金額の計算方法は弁護士によって異なりますが、例えば往復2時間を超え4時間の範囲であれば3~5万円、往復4時間を超える場合は5~10万円程度が目安です。
日当は、特に裁判所と離れた弁護士に依頼すると高くなるため注意してください。
実費とは、以下のような実際に支出された費用のことです。
- 収入印紙代
- 郵便切手代(内容証明郵便含む)
- 公文書取得費用(戸籍全部事項証明書など)
- 交通費
ただし、弁護士の交通費を除いて、収入印紙代や郵便切手代などは、弁護士に依頼しなくてもかかる費用です。実費は、弁護士費用というより手続きに必要な費用と捉えたほうがよいでしょう。
財産分与の流れにおける弁護士の費用目安
ここまで、弁護士費用の内訳と相場を紹介してきました。
着手金や報酬金をみると、示談や調停、訴訟など財産分与の流れのうちどの段階で解決したかによって費用が大きく異なることがわかるはずです。
そこで本章では、協議・調停・裁判の場合について、あらためて弁護士費用の目安を紹介します。
参考として、2004年3月までに適用されていた日弁連の基準(旧弁護士報酬基準)は以下のとおりです。
旧弁護士報酬基準
(離婚・財産分与部分)
| 報酬の種類 |
金額 |
| 着手金 |
経済的利益の額が300万円以下:8%
300万円超え3000万円以下:5%+9万円
3000万円超え3億円以下:3%+69万円
3億円超え:2%+369万円
※着手金の最低額は10万円 |
| 報酬金 |
経済的利益の額が300万円以下:16%
300万円超え3000万円以下:10%+18万円
3000万円超え3億円以下:6%+138万円
3億円超え:4%+738万円 |
なお、着手金と報酬金は、それぞれ事件の内容に応じて30%の範囲内で増減でき、示談・調停ではそれぞれ3分の2に減額できるとされていました。
協議(示談)の場合の費用例
協議(示談)とは、裁判所の手続きである調停や訴訟ではなく、当事者である夫婦が話し合って結論を出すことです。裁判所の手続きを経ずに解決する協議(示談)は、弁護士費用も比較的安く抑えられます。
具体的には、着手金20万円、報酬金20万円の40万円以上が協議(示談)で解決する場合の弁護士費用の目安です。
財産分与を請求したのに話し合いがまとまらなかった場合は、弁護士費用として40万円を想定しておくとよいでしょう。
仮に財産分与として300万円の支払いを受けられることとなり、経済的利益の額に応じた金額の割合が15%の場合、45万円加算され合計額は85万円なる場合があります。
1,000万円の財産分与が成立した場合は、経済的利益の額に応じた金額が150万円となり、合計額は190万円と計算できます。
財産分与に限らない、協議離婚でかかる弁護士費用の相場については以下の記事で詳しく解説しています。
調停に進んだ場合の費用例
調停とは、夫婦の間に調停委員と呼ばれる職員が入り、夫婦が裁判所で話し合う手続きです。夫婦だけでは話し合いが難しい場合や、離婚訴訟を見越している場合などに利用します。
はじめは協議(示談)を想定して弁護士に依頼したものの、調停を利用することとなった場合、着手金や報酬金が増額するのが一般的です。
例えば、協議(示談)において着手金が20万円、基本報酬金が20万円だった場合、調停への移行でどちらも10万円加算される場合があります。
その結果着手金30万円、基本報酬金30万円となるため、調停に移行した場合の弁護士費用の目安は60万円以上です。
財産分与を請求したのに調停も成立しなかった場合は、弁護士費用として60万円を想定しておくとよいでしょう。
また、仮に財産分与として300万円の支払いを受けられることとなり、経済的利益の額に応じた金額の割合が15%の場合、45万円加算され合計額は105万円となります。
1,000万円の財産分与が成立した場合は、経済的利益の額に応じた金額が150万円となり、合計額は210万円と計算できます。
財産分与に限らない、離婚調停でかかる弁護士費用の相場については以下の記事で詳しく解説しています。
裁判に発展した場合の費用例
裁判とは、裁判官による判断(処分)です。
財産分与は訴訟の判決に含まれる場合もありますが、法律上は審判事項であり、裁判というと審判を指します(家事事件手続法別表第2の第4の項)。
裁判(審判)に発展した場合は、協議(示談)や調停と比べて最も弁護士費用が高くなりやすい点に注意してください。
具体的には、調停において着手金が30万円、基本報酬金が30万円だった場合、裁判(訴訟・審判)への移行でどちらも10万円加算される場合があります。
その結果着手金40万円、基本報酬金40万円となるため、裁判(審判・訴訟)に移行した場合の弁護士費用の目安は80万円以上です。
財産分与を請求したのに裁判でも認められなかった場合は、弁護士費用として80万円を想定しておくとよいでしょう。
また、仮に財産分与として300万円の支払いを受けられることとなり、経済的利益の額に応じた金額の割合が15%の場合、45万円加算され合計額は125万円となります。
1,000万円の財産分与が認められた場合は、経済的利益の額に応じた金額が150万円となり、合計額は290万円と計算できます。
ただし、離婚後に財産分与請求をすると、調停の後は自動的に審判に移行します。調停で提出していた書面などが審判に利用されるケースも少なくありません。
そこで、財産分与の調停から審判に移行した際は、着手金や基本報酬金の増額がない弁護士もいます。
財産分与に限らない、裁判離婚でかかる弁護士費用の相場については以下の記事で詳しく解説しています。
財産分与を行う場合の弁護士費用についての注意点
財産分与の弁護士費用では、以下の点に注意してください。
調停や裁判になると新たな着手金などが必要になる場合がある
当初は協議(示談)での解決を依頼した場合でも、その後、調停や裁判に発展することがあります。
引き続き弁護士に対応を依頼する場合は、調停や裁判に移行するごとに、10万円や20万円といった着手金が加算されることがあるため注意してください。
弁護士に依頼する際は、「裁判に移行しても着手金の金額は変わらないか」といった点を確認しておくとよいでしょう。
熟年離婚などで財産が高額な場合は弁護士費用も高額になりやすい
短期間で離婚するより、熟年離婚のほうが財産分与の対象額も高額になるケースが多いです。財産分与は婚姻中に取得・維持した財産が対象となるところ、婚姻期間が長いほどその対象となる財産も多くなると考えられます。
財産分与が高額になるほど、前述した経済的利益に応じた金額が高額になるため、弁護士費用が高額になりがちです。
財産分与を請求する立場において、経済的利益の額に応じた金額の割合が15%の場合、仮に請求額が100万円と500万円とでは弁護士費用は60万円異なります。
もっとも、対象となる財産が高額であるほど財産分与の結果が重要となるため、弁護士に依頼する価値も相対的に高いといえるでしょう。
熟年離婚の財産分与については、以下の記事で詳しく解説しています。
離婚の理由に関わらず、依頼した方が弁護士費用を支払う
相手のせいで弁護士費用の負担が必要になったと感じている場合、相手に弁護士費用を負担させられないかといった問題が生じます。
しかし、ご自身が依頼した弁護士にかかる費用について、相手に負担させることは原則できません。
ただし、慰謝料の請求などでは、弁護士費用の10%を相手に負担させた(損害賠償させた)事例があります。弁護士費用の全額を相手に負担させることは、ほとんど不可能です。
離婚の財産分与を依頼する際の弁護士費用を抑える4つのポイント
財産分与について弁護士に依頼する費用について、協議(示談)でも40万円以上が目安であることは前述したとおりです。40万円という額は、多くの方にとって軽くない負担となるはずです。
そこで本章では、弁護士費用の負担を抑えるポイントとして、以下の4点を紹介します。
弁護士費用を抑え、有利な解決を目指すためぜひ実践してください。
複数の弁護士に相談して比較する
弁護士費用は、おおむね同様の計算方法がみられるものの、具体的には弁護士によって異なります。そのため、複数の弁護士に相談して費用を比較することが大切です。
ただし、費用の安さだけで弁護士を選ばないようにしてください。弁護士によって費用が異なるように、弁護士によって実績や対応も異なるからです。
安くない弁護士費用を負担するからには、弁護士の力量や対応の丁寧さなども含めて総合的に検討しましょう。
離婚を検討し始めてからできるだけ早く弁護士に相談する
財産分与の流れにおける弁護士の費用相場で紹介したとおり、弁護士費用は、解決が早い段階ほど抑えられる傾向にあります。例えば、協議(示談)で解決すると40万円以上のところ、裁判(審判・訴訟)では80万円以上といった具合です。
そのため、離婚を考え始めた場合、できるだけ早く弁護士に相談することで弁護士費用を抑えられる可能性があります。
また、早めに弁護士に相談することは、費用だけでなくご自身にとって有利な解決につながる可能性がある点でも大切です。
財産分与の請求は難しいと考えていても、実際には請求が可能な場合もあります。また、裁判(審判・訴訟)ではご自身に不利な判断がされることが予測される場合でも、弁護士の交渉により有利な解決を実現できる場合もあります。
離婚を検討している方は、ぜひ早めに弁護士に相談してください。
所得が一定以下の場合は法テラスの利用も可能
弁護士費用を安くできる方法ではありませんが、所得が一定以下など条件を満たすと、法テラスの制度を利用して負担を軽減することもできます。
法テラスの制度とは、主に民事法律扶助(代理援助)と呼ばれる弁護士費用の立替制度です。法テラスが弁護士費用を立替えて支払うため、利用者は法テラスに立替えてもらった金額を分割で支払います。
要するに、法テラスの民事法律扶助(代理援助)とは、通常は一括払いが求められる弁護士費用を実質的に分割払いにできる制度です。
しかし、法テラスの民事法律扶助は誰でも利用できるわけではありません。以下のような利用条件があります。
- 収入(手取り月収)が一定以下であること
- 資産(資産の合計額)が一定以下であること
- 勝訴の見込みがないとは言えないこと
- 民事法律扶助の趣旨に適すること
特に収入・資産基準が主な条件で、具体的にはお住まいの地域や同居家族の人数などに応じた手取り月収と資産の合計額が一定以下である必要があります。
法テラスについての詳細は、ぜひ以下の記事でご確認ください。
どうしても支払いが難しい場合は分割払いを相談してみる
収入・資産が一定以下であるなど条件を満たすと、法テラスの制度で分割払いができることは前述のとおりです。
法テラスの利用条件を満たさない場合でも、直接、弁護士に分割払いを相談することはできます。
弁護士(事務所)によっては、弁護士費用について「分割払いにも柔軟に対応します」としているものや、報酬金の支払いを分割払いとする選択肢を提供しているものがあります。
分割払いに応じてくれるかどうかは弁護士(事務所)によって異なりますが、まずは担当弁護士に相談してみてください。
財産分与を依頼する弁護士の選び方
財産分与を依頼する弁護士は、どの弁護士でも良いわけではありません。弁護士費用の負担を抑えながらより有利な解決を図るには、以下の選び方を実践することが大切です。
ぜひ1つずつ確実に実践してください。
離婚や財産分与の実績が豊富な弁護士を選ぶ
実は、離婚や財産分与に関する対応をしたことがない弁護士もいます。例えば、相続に関する対応経験は豊富でも、離婚関係の対応経験はないといった弁護士です。
離婚や財産分与の経験がない弁護士より、実績が豊富な弁護士のほうが、多様な状況から適切な解決に導くノウハウは高いはずです。
弁護士を探す際は、ツナグ離婚弁護士のような弁護士検索ポータルサイトなどで、財産分与や養育費といった相談内容ごとに特化した弁護士を探すことをおすすめします。
実際に話して相性が良いと感じる弁護士を選ぶ
弁護士に依頼すると、弁護士があなたと二人三脚で、あるいは複数の弁護士がチームであなたを強力にサポートしてくれます。
弁護士とは1回きりや1日きりの関係ではなく、財産分与の問題が解決するまで同じ目標を歩むパートナーです。
そのため、いくら財産分与問題の解決実績が豊富な弁護士であっても、「話しにくい」や「信頼できない」といった相性面で問題を感じる弁護士への依頼はおすすめできません。
財産分与の問題解決を共に進めるパートナーとして、相性に問題がないかどうかも弁護士選びの基準として重要です。
費用の体系が明確で相場からかけ離れていない弁護士を選ぶ
弁護士は、報酬の算定方法など、報酬に関する基準を作成しなければなりません。(弁護士の報酬に関する規定第3条、日本弁護士連合会)
その算定方法が曖昧だと、実際に依頼した際に費用がいくらになるかの見通しがつきにくくなります。
また、算定方法が明確であっても、相場からかけ離れて高く設定している弁護士を選ぶことは、慎重な検討が必要です。費用が相場より高い弁護士を選ぶケースは、通常、他の弁護士よりも特に相性が良いと感じたり、対応実績が特に優れたりしている場合に限られるでしょう。
弁護士費用に関するトラブルを避けるためには、費用の体系・算定方法が明確で見通しがつきやすいことが大切です。また、意図せず割高な費用を支払わないためには、弁護士から提示された費用と相場を比較することも大切です。
リスクやデメリットについての説明もしてくれる
弁護士に依頼したからといって、必ずしもご自身が望む内容で解決するとは限りません。なぜなら、示談(協議)や調停では相手が、裁判(審判・訴訟)では裁判官が具体的な結果を決めるためです。
そのため、弁護士に依頼しても以下のように想定よりも不利な内容で解決する可能性はあります。
- 財産分与を請求したいのに請求できなかった
- 200万円の支払いを受けられると思っていたのに100万円になった
- 財産分与の対象となるはずだった財産を対象にできなかった
- 相手名義の不動産について分与を受けられなかった
上記のようなリスクやデメリットがあることなど、解決の見通しも丁寧に説明してくれる弁護士は、信頼できる弁護士といえるでしょう。
良いことばかりではなく、より現実的に問題に寄り添い、対応を案内してくれる誠実な弁護士を選ぶことも大切です。
まとめ
離婚時の財産分与について弁護士に依頼する際の費用は、離婚の流れのうちどの段階で依頼するかや、財産額により大きく異なります。解決までにかかる期間が長く、財産分与の額が高額であるほど高くなる傾向にあります。さらに、離婚そのものや親権など他に離婚関係の争いがある場合は加算されることがあるため注意してください。
具体的な費用は弁護士によって異なるため、法律相談のときなど、契約前に費用体系や算定方法について十分に確認しておくことが大切です。
弁護士費用の負担を少しでも抑えるために、複数の弁護士に相談して比較することや、できるだけ早く相談することを意識してください。調停や裁判(審判・訴訟)に至る前に早期に解決できると、弁護士費用は比較的安くなります。
もし弁護士費用の支払いが難しい場合は、弁護士に分割払いの相談をするか、法テラスの民事法律扶助(代理援助)の利用も検討してください。
離婚時の財産分与は金額が高額になるケースも少なくないため、離婚問題に特化した弁護士に依頼する重要性が高いといえます。
弁護士選びや弁護士費用で後悔しないよう、ぜひ本記事で紹介した内容を参考にしてください。できるだけ早めに弁護士選びをスタートすることが大切です。