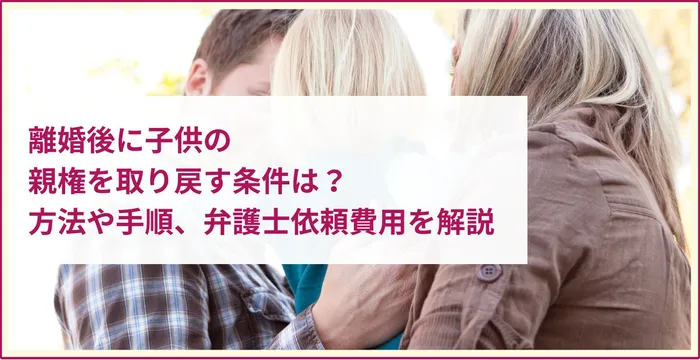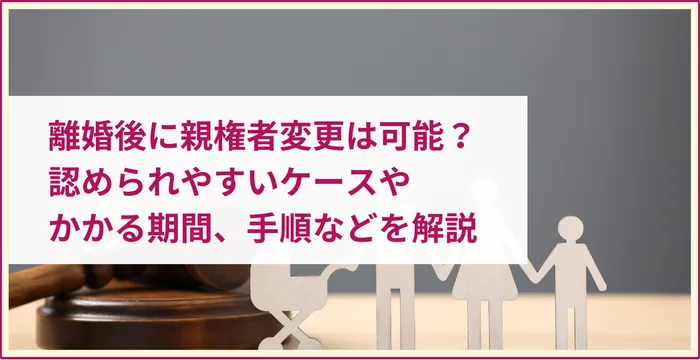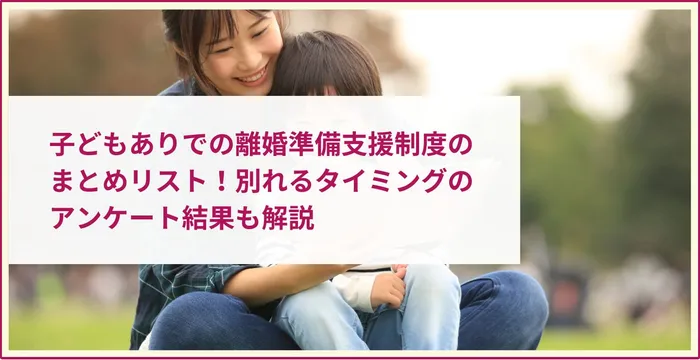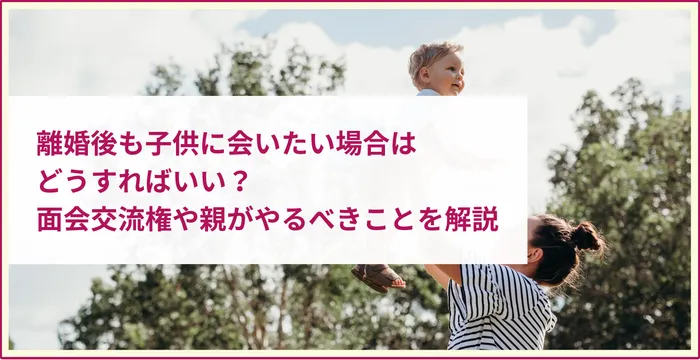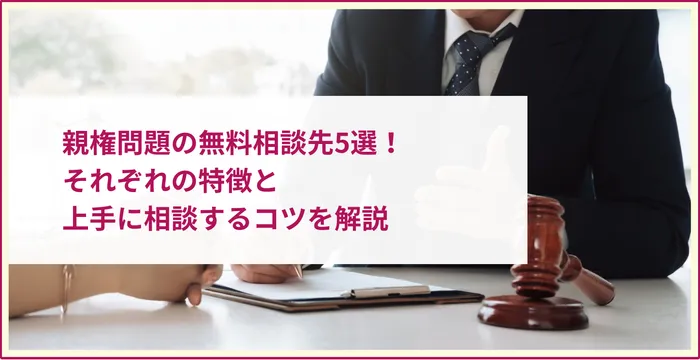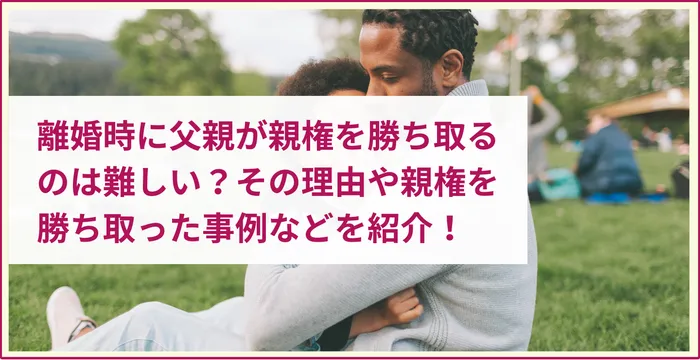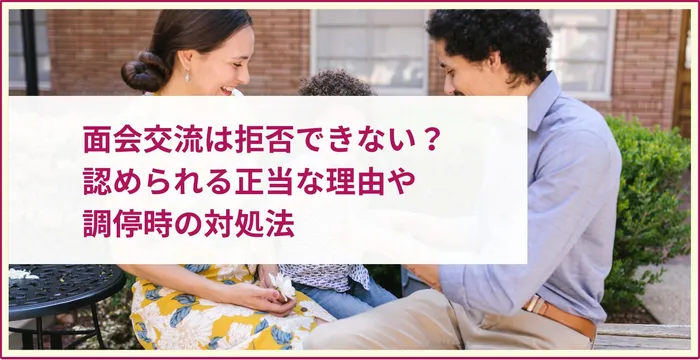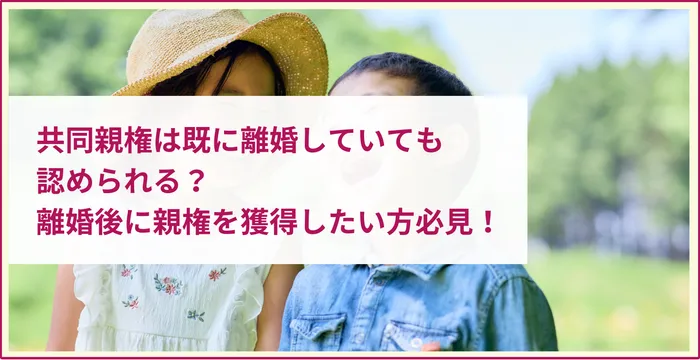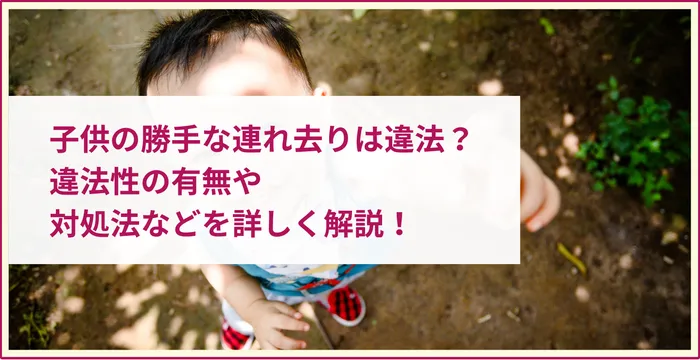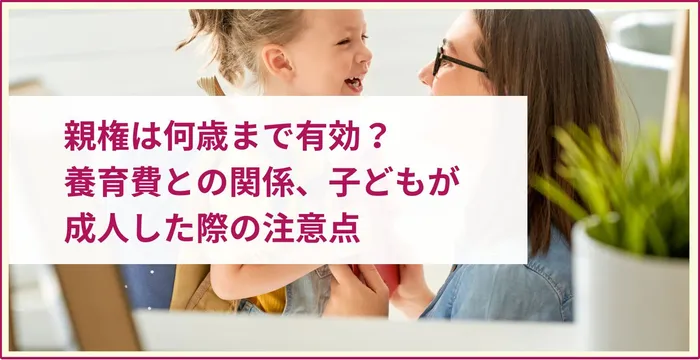親権の放棄は、原則として認められていません。しかし「離婚して単独親権者となったが経済的に余裕がない」「子どもと再婚相手の相性が悪い」など、親権で悩む人の事情はさまざまなものがあります。 家庭裁判所に申し立てを行い、やむを得ない理由があると認められれば親権を放棄することも可能です。親権の放棄が認められるのは以下のケースが挙げられます。
- 経済的に困窮しているため
- 重度の病気や怪我のため
- 服役するため
- 海外赴任するため
- 再婚するため
親権を放棄する方法は「親権の辞任」「親権者の変更」の2種類です。単独親権者が親権の辞任をするとき、子どもが未成年であれば未成年後見人選任の手続きをあわせて行う必要があります。親権を放棄したからといって、元配偶者などに親権が自動的に切り替わるわけではないため、忘れずに手続きを行いましょう。
しかし親権を手放すということは、この先子どもと深い繋がりを持てなくなるということです。子どもの心を傷つけたり、精神的な負担を与えたりする可能性も少なくありません。安易に親権の放棄を検討するのは避け、ほかの選択肢がないかをしっかりと考える必要があります。
本記事では、親権の放棄が認められる条件や手続きの流れ、必要書類、親権を放棄する際の注意点などを詳しく紹介します。離婚をきっかけに親権で悩んでいる人や、経済的な理由で子育てに不安を感じている人などは参考にしてください。
親権の放棄は原則として認められないが、適切な手続きにより放棄も可能
親権を放棄することは、原則として認められていません。親権とは子どもの監護や教育、財産の管理などをする権限のことです。一見すると「権利」のように思われますが、民法第820条では以下のような規定があり、親権は子どもが育つうえで欠かせない親の義務であることがわかります。
第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
引用元 民法 | e-Gov法令検索
しかし、やむを得ない理由があれば親権の放棄が認められるケースもあります。親権の放棄には、以下の2つの方法があります。
次の項目から、手続きの流れや必要書類などを詳しく紹介します。
親権者の辞任
民法第837条では、「親権又は管理権の辞任及び回復」として以下の規定があります。
第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
引用元 民法 | e-Gov法令検索
このように、やむを得ない理由があるときは家庭裁判所の許可を得たうえで、親権を放棄することもできます。親権者の辞任・変更が認められる条件の見出しで詳しく紹介しますが、「やむを得ない理由」に該当するのは再婚や怪我・病気など、親権の行使が難しいと客観的に判断できるケースです。「子育てをしたくない」「子どもとの相性が悪い」などの理由では、親権放棄が認められません。
また、民法第838条では以下の規定があります。
第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
引用元 民法 | e-Gov法令検索
このように、子どもが未成年で単独親権者の場合は後見人を選ぶ必要があります。未成年後見人の選任について、手続きの流れや必要書類などは後ほど詳しく紹介します。
親権者辞任の手続き・必要書類
親権者を辞任するには、まず家庭裁判所で親権辞任許可の審判を申し立てます。審判の流れは以下のとおりです。
- 子どもの住所を管轄する家庭裁判所で審判の申し立てをする
- 家庭裁判所で親権を放棄する理由・事情を説明する
- 子どもが15歳以上の場合は、子どもの意見を聴取する
- 親権辞任の審判が決定する
親権辞任許可の審判の必要書類は以下のとおりです。
- 親権者辞任許可の申立書
- 親権者と子どもの戸籍謄本
- 郵便切手
- 収入印紙(子ども1人あたり800円)
申立書は裁判所のホームページで書式をダウンロードできます。記載例や説明書などもあわせて確認し、記載内容に不備がないようにしましょう。
親権者の変更
民法第819条第6項では、「離婚又は認知の場合の親権者」として以下の規定があります。
第八百十九条
六 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
引用元 民法 | e-Gov法令検索
子どもがいる夫婦が協議離婚する場合、親権者をどちらにするか話し合いで決める必要があります。協議離婚であれば話し合いのみで親権者を決定でき、家庭裁判所での手続きは必要ありません。
しかし離婚後に親権者を変更する場合、家庭裁判所で親権者変更調停の申し立てをする必要があります。調停が成立し新たな親権者が決まったら、10日以内に市区町村役場まで親権者変更の届出を提出しましょう。
親権者変更の手続き・必要書類
親権者変更調停の手続きは以下のとおりです。
- 相手の住所を管轄する家庭裁判所に、親権者変更調停の申し立てをする
- 調停期日を調整し、面談する
- 必要に応じて複数回の調停期日を設ける
- 双方の合意が得られ、家庭裁判所が認めれば調停が成立する
親権者変更調停の申し立ての必要書類は以下のとおりです。
- 親権者変更申立書と写し
- 申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 相手方の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 郵便切手
- 収入印紙(子ども1人あたり1200円)
なお親権者変更申立書は、裁判所のホームページで書式をダウンロードできます。書式の記入例も公開されているので、参考にしながら準備を進めるとよいでしょう。
親権者の辞任・変更が認められる条件
先述したように親権者の辞任や変更が認められるのは、親権を行使することが難しい「やむを得ない理由」がある場合のみです。具体的な条件は下記のケースが挙げられます。
- 経済的に困窮しているため
- 重度の病気や怪我のため
- 服役するため
- 海外赴任するため
- 再婚するため
次の項目から、条件をより詳しく紹介します。
経済的に困窮しているため
「失業で生活苦におちいっている」「収入が減少し衣食住もままならない」など、経済的に困窮している場合は親権の放棄が認められる可能性があります。しかし、ただ経済的に不安があったり、収入が下がったりしただけではやむを得ない理由として認められません。家庭の状況やほかの改善策なども考慮され、子どもの生活を守ることが難しいと客観的に判断された場合のみ親権の放棄が認められます。
重度の病気や怪我のため
重大な病気や怪我で子育てができる身体状態ではないときは、親権の放棄が認められる可能性があります。たとえば「治療のために長期入院せざるを得ない」「大怪我の後遺症で障がいが残ってしまう」などのケースです。このような場合は子どもの養育・監護が難しく、親権を行使することが困難だと判断されます。
服役するため
親権者が犯罪を犯し、長期にわたって刑務所に入ることになった場合は親権の放棄が認められる可能性があります。懲役刑や禁固刑を言い渡されると刑事施設に収容され、物理的に子育てができない状況が続くからです。
海外赴任するため
勤務先の都合で長期の海外赴任が決まり、事情によって子どもを連れて行くのが難しい場合は親権の放棄が認められる可能性があります。
子どもを連れて行くのが難しい事情としては、「赴任先の情勢が悪く子どもの身に危険が及ぶ可能性がある」「子育てに適切な環境でない」などのケースが該当します。ただし認められるのは、環境の変化が子どもに悪影響を与える可能性がある場合のみです。単なる転勤や短期の海外出張などを理由に、親権を放棄するのは難しいでしょう。
再婚するため
子どもを連れて再婚するのが難しい場合は、親権の放棄が認められる可能性があります。たとえば「再婚相手から子どもが虐待を受けている」などのケースです。再婚するという理由だけでは認められず、親権を辞任・変更するほうが子どもにとって利益となる場合に限られる点に注意しましょう。
親権の辞任が認められた場合は未成年後見人が選任される
親権の辞任が認められた場合、親権者の代わりに子どもの養育・監護をする未成年後見人が選任されます。未成年後見人を選任する方法は、以下の2通りです。
- 親権者の遺言によって決定する
- 子ども本人や親族、利害関係人が家庭裁判所に申し立てる
次の項目から未成年後見人選任の手続きについて、詳しく紹介します。
未成年後見人とは
未成年後見人とは未成年の子どもに対して、親権者の代わりに養育・監護、財産の管理などを行う法定代理人です。家庭裁判所は親権者が亡くなったり、親権を放棄したりして親権者がいなくなった子どもに未成年後見人を選任します。未成年後見人になるには特別な資格や肩書きなどは必要ないものの、子どもの親族が選ばれるケースが一般的です。
しかし未成年後見人は、子どもとの関係や財産状況、経歴などさまざまな事情を考慮したうえで慎重に候補者が選出されます。状況によっては、親族ではなく弁護士や民間の社会福祉法人などが選ばれるケースも珍しくありません。選任には一定の制限が設けられており、以下の人は未成年後見人になることが禁止されています。
- 未成年者
- 行方不明者
- 家庭裁判所から法定代理人や保佐人などを解任された人
- 自己破産の復権をしていない人
- 未成年者に対して訴訟をする人(した人)やその配偶者、直系血族
未成年後見人選任の手続きの流れ
親権を放棄したら、親族や元配偶者などへ自動的に親権が移るわけではありません。必ず家庭裁判所で申し立てをする必要があり、手続きの流れは以下のとおりです。
- 必要書類の収集
- 子どもの住所地を管轄する家庭裁判所への申し立てをする
- 家庭裁判所が申立人・後見人候補者、未成年者本人と面接をする
- 未成年者の親族へ意向を確認する
- 審判書の送付
未成年後見人に選任された人は、未成年者の財産の調査をして1か月以内に財産目録を作成する必要があります。
未成年後見人選任に必要な書類
未成年後見人選任の手続きで必要な書類は以下のとおりです。
- 申立書
- 申立事情説明書
- 未成年者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 未成年者の住民票又は戸籍の附票
- 後見人候補者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 後見人候補者の住民票又は戸籍の附票
- 後見人候補者事情説明書
- 未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証明する資料
- 親族関係図
- 未成年者の財産、収支、負債に関する示す資料
- 法人登記簿謄本(後見人候補者が法人の場合)
- 親族関係を証明する戸籍謄本等(申立人が親族の場合)
- 利害関係を証明する資料(申立人が利害関係人の場合)
「未成年者に対して親権を行うものがないこと等を証明する資料」は、親権者が亡くなったことが記載されている戸籍謄本(全部事項証明書)、行方不明の事実を明らかにする書類などが挙げられます。
また「未成年者の財産に関する資料」は不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書通帳などが挙げられますが、不動産を所有していない場合は通帳の写しや残高証明書などでかまいません。
万が一入手できない書類がある場合、申請後に追加提出をすることもできます。家庭裁判所によって必要書類が異なるケースもあるため、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。
親権を放棄する際の注意点
このように、家庭裁判所がやむを得ない理由があると判断した場合に限り、親権を放棄することができます。しかし以下のような注意点もあるため、親権を手放すことが最善な選択なのかを慎重に考えることが大切です。
- 子どもに精神的なダメージを与えてしまう
- 子どもの大事な選択に関する決定権限を失う
- 子どもとは面会できない可能性がある
次の項目から、それぞれの内容を詳しく紹介します。
子どもに精神的なダメージを与えてしまう
親権を放棄することで、子どもは精神的に大きなダメージを負う可能性があります。「自分は捨てられてしまった」と深く傷つき、ショックから回復するまでに長い時間がかかるケースも珍しくありません。また家庭の状況を理解できない年齢だったり、話し合いが不十分だったりと、さまざまな状況から子どもが親を恨んでしまうケースもあります。親権放棄は最後の選択肢ととらえ、ほかの解決策を弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
子どもの大事な選択に関する決定権限を失う
親権を放棄するということは、子どもの人生を決める大事な選択に関与できなくなるということです。どの学校に進学するか、受験はするかなど、親権を手放したらそれらを自分の一存で決定する権限はありません。自分の方針と違っていたとしても、未成年後見人や新たな親権者に意見を言うことは難しいでしょう。
子どもとは面会できない可能性がある
親権を放棄した後、子どもとの面会ができない可能性もあります。子どもが親権を放棄したことを知って面会を拒否するケースや、新たな親権者が面会を嫌がるケースも多くあるからです。この先も子どもとの繋がりを持ちたいのであれば、親権放棄以外の選択肢を検討するのが現実的かもしれません。
親権の喪失・停止と親権の放棄の違いは?
「親権の喪失・停止」と「親権の放棄」は以下のような違いがあります。
- 親権の喪失・停止:裁判所により親権が剥奪、停止されること
- 親権の放棄:親権者本人の申出によるもの
次の項目から、それぞれの内容を詳しく紹介します。
親権の喪失・停止とは裁判所により親権が剥奪、停止されること
親権の喪失・停止とは、親権者が子どもの私益を侵害しているとき、家庭裁判所の審判によって親権を剥奪されたり一定期間の停止を命じられたりすることです。「親が子どもの面倒を見ていない」「子どもを虐待している」などが発覚した場合、子どもや子どもの親族、検察などは家庭裁判所に親権喪失や親権停止の申し立てを行えます。親権の喪失・停止につながる事情は、以下のものがあります。
親権停止の期間は最長で2年間とされており、家庭裁判所の審判によって期間が異なります。親権停止が終了した後、もし状況が改善していないようであれば、ふたたび親権停止の申し立てを行い期間を延長することも可能です。
一方、親権喪失は期限が設けられておらず、半永久的に親権を失うことになります。申し立てが認められるのは、以下のいずれかの条件を満たしている場合です。
- 親権者による虐待または悪意の遺棄があるとき
- 親権の行使が著しく困難または不適当であることにより、子の利益を”著しく”害するとき
ここで重要となるのが「子の利益を”著しく”害する」という点です。原因となった事情が2年以内に消滅する可能性がある場合や、状況が深刻でない場合などは申し立てが認められません。親権を奪うことが子どもにとって不利益とならないかを慎重に判断する必要があるため、親権喪失が認められた事例はあまり多くないのが現状です。
親権の放棄は「親権者本人の申出」によるもの
親権の放棄は、親権者本人の申し出によって親権を失うものです。先ほど紹介したように、親権の喪失・停止は子どもや子どもの親族、児童相談所の所長、未成年後見人、検察官などが家庭裁判所に申し立てを行います。一方、親権の放棄は親権者自らが家庭裁判所に申し立てを行い、親権を行使するのが難しい理由を説明します。
まとめ
「子育てに自信がない」「子どもに愛情が湧かない」など、主観的な理由で親権を放棄することはできません。しかし、親権を行使するのが難しいと客観的に判断できるやむを得ない理由がある場合のみ、親権の放棄が認められる可能性があります。それぞれの状況にもよりますが、親権の放棄が認められる可能性がある条件は以下のとおりです。
- 経済的に困窮しているため
- 重度の病気や怪我のため
- 服役するため
- 海外赴任するため
- 再婚するため
親権の放棄や親権者を変更するには、家庭裁判所で申し立てを行う必要があります。また子どもが未成年で親権者がいなくなってしまう場合、あわせて未成年後見人選任の手続きを行わなくてはなりません。親権を放棄したら、親族や元配偶者などへ自動的に親権が移るわけではない点に注意しましょう。
しかし親権の放棄は、子どもに精神的なダメージを与えたり、面会ができなくなったりする可能性も少なくありません。親権の放棄は最後の選択肢ととらえ、まずはほかの解決策がないか弁護士に相談することをおすすめします。
親権放棄に関するよくある質問
放棄した親権は回復できるのか?
親権放棄の原因となった「やむを得ない理由」が消滅したときは、家庭裁判所に申し立てをして親権をふたたび取り戻すこともできます。たとえば「仕事が見つかり収入が安定した」「重度の病気が回復し退院した」などのケースです。
家庭裁判所は親権回復の申し立てを受け、親権を回復することで子どもに悪影響を及ぼさないか、やむを得ない理由が本当に消滅したのかなどを調査します。無事に許可が降りたら、子どもの本籍地または元親権者の住所地を管轄する役所まで、忘れずに親権回復届を提出しましょう。