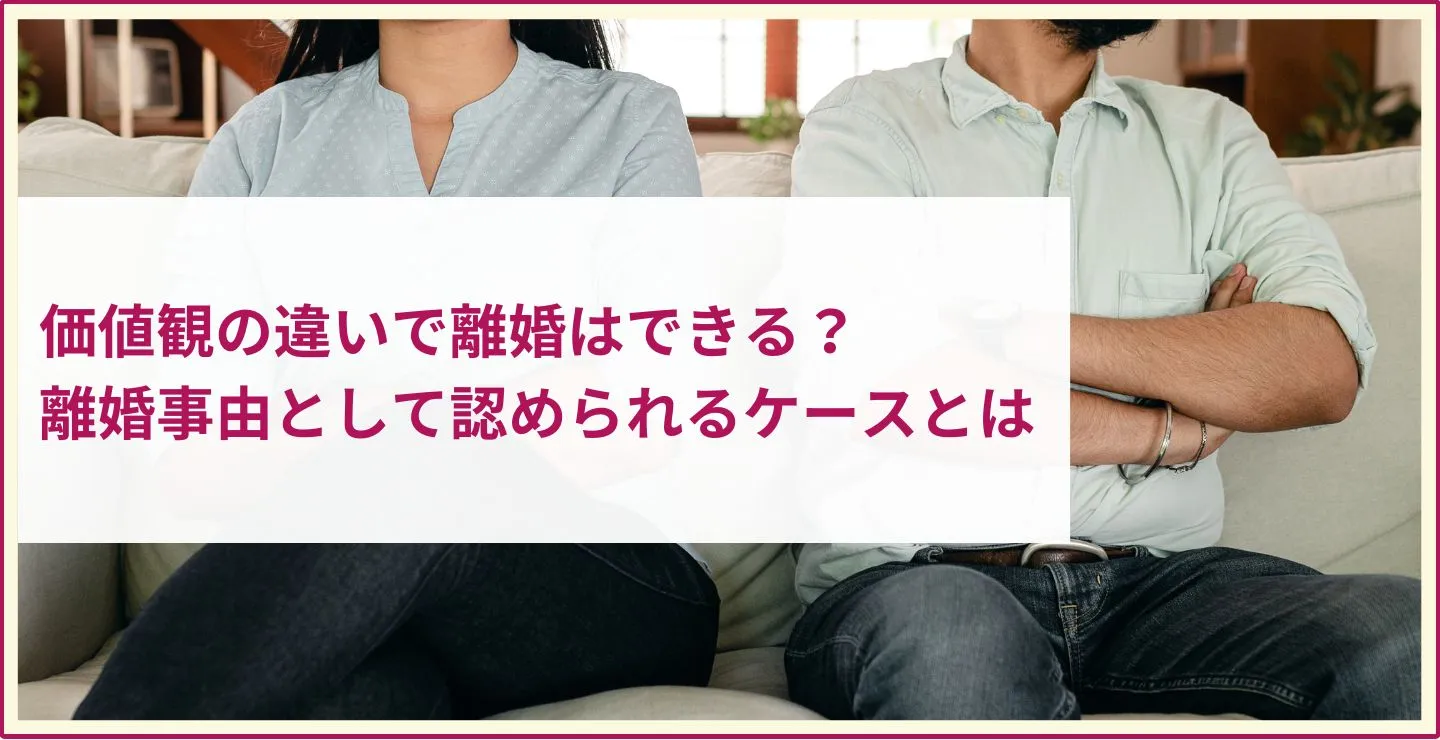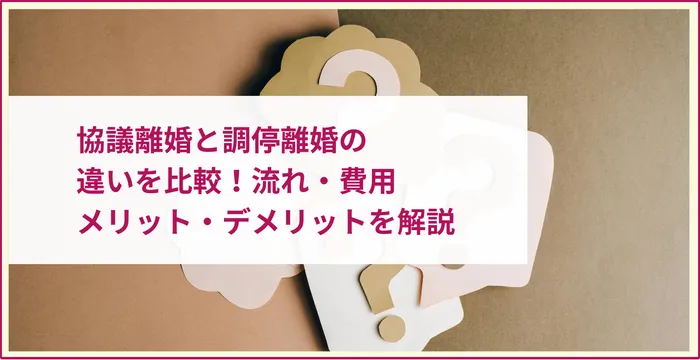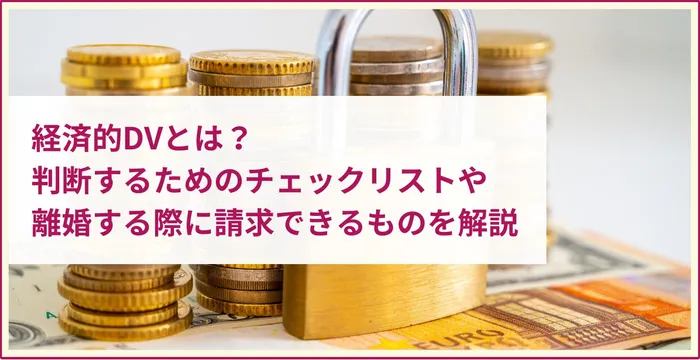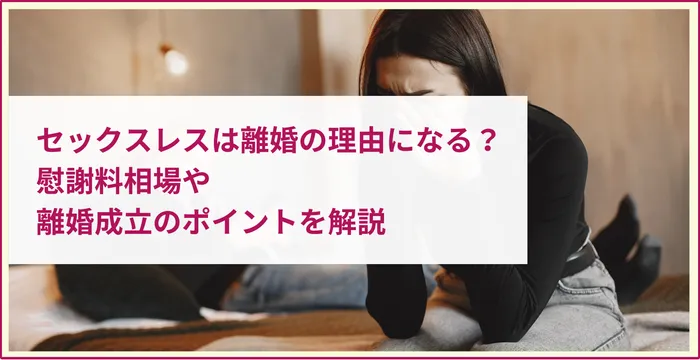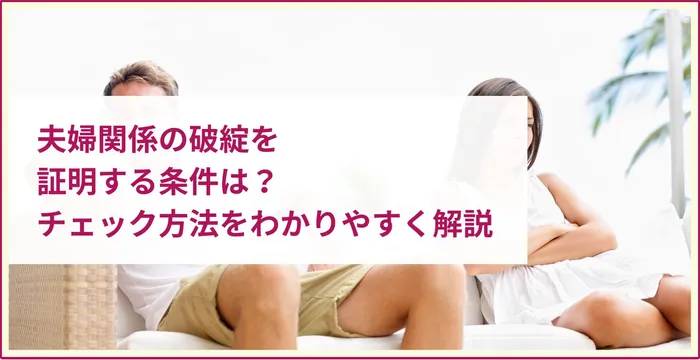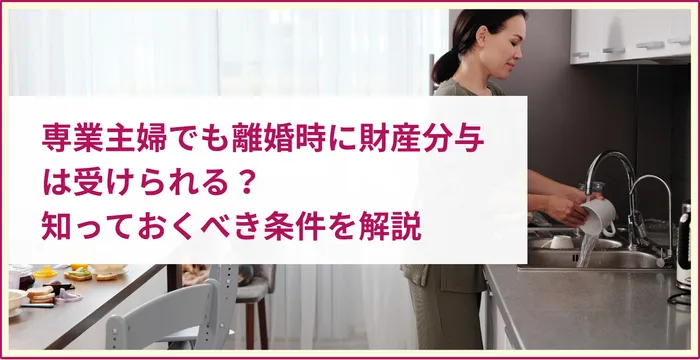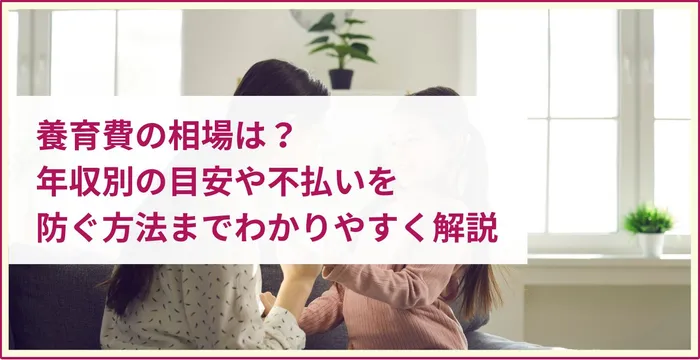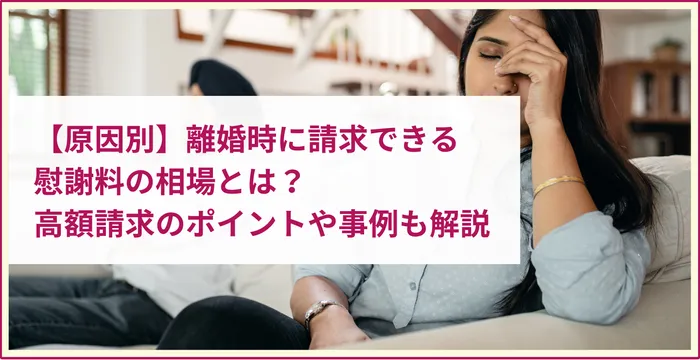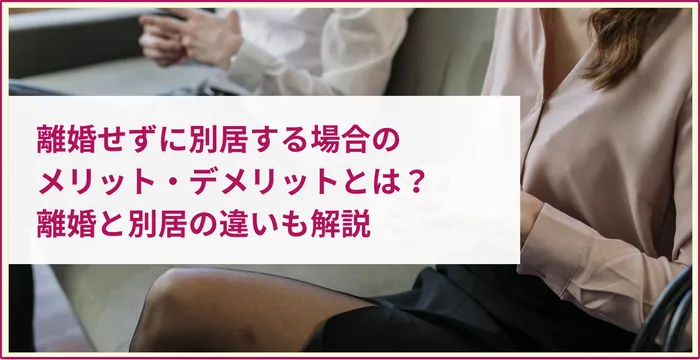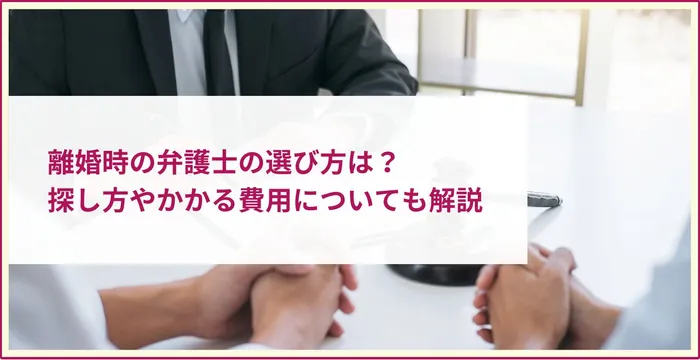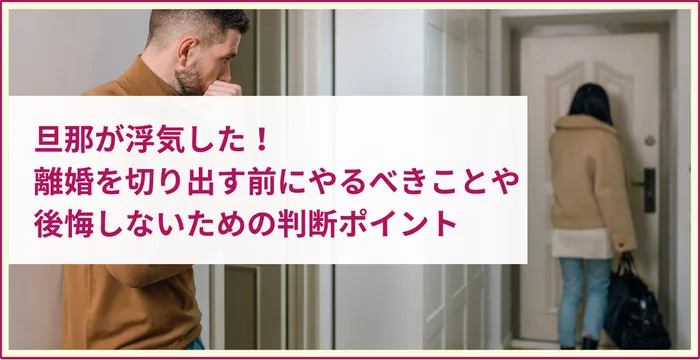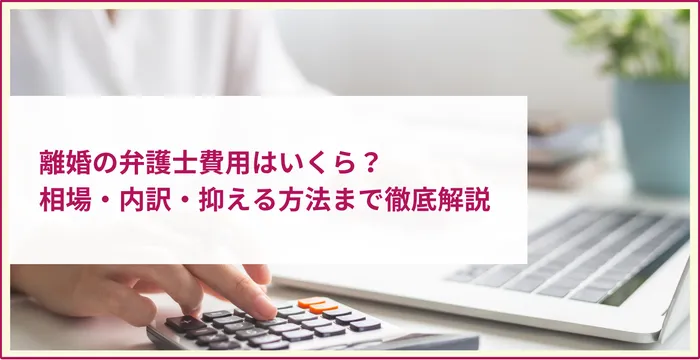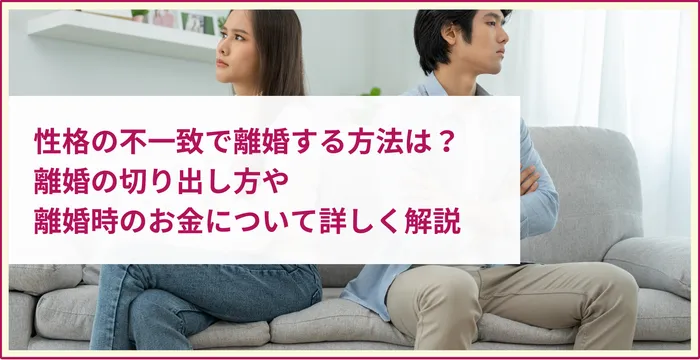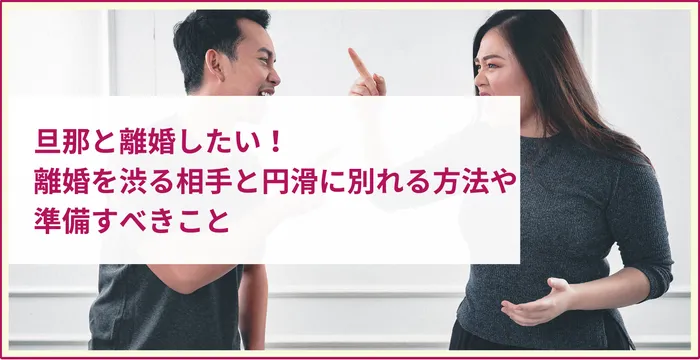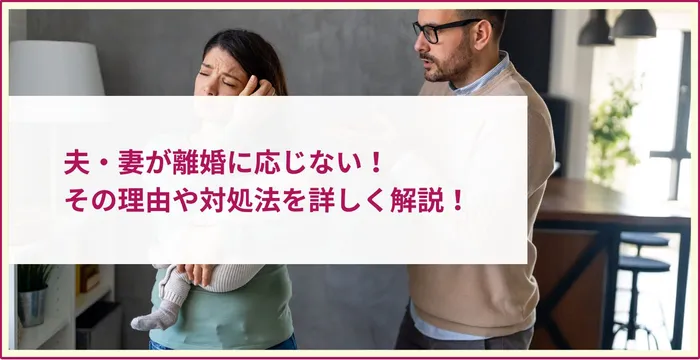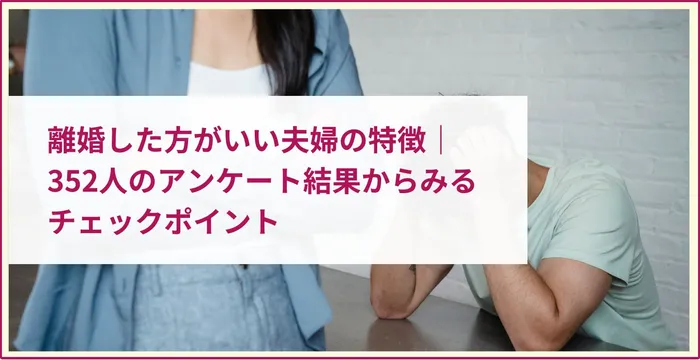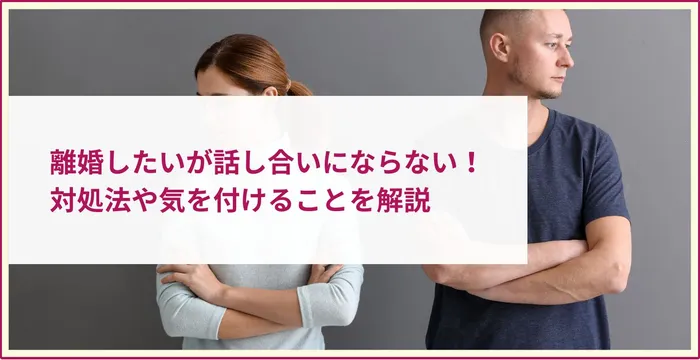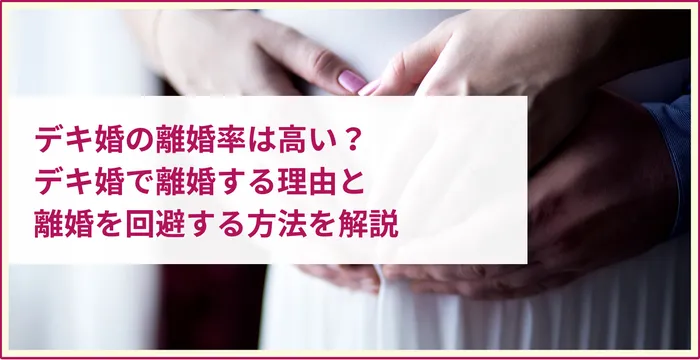価値観の違いを理由に離婚はできるのか?
価値観の違いを理由に離婚できるのか、不安に思う人も多いでしょう。
結論からいうと、協議離婚や調停離婚であれば、夫婦が合意すれば「価値観の違い」だけでも離婚は可能です。
一方で、裁判で離婚を求める場合は、価値観の違いそのものでは離婚理由として認められにくく、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するかどうかが判断のポイントになります。
ここでは、価値観の違いによる離婚が可能な場合と、裁判で認められるための条件について解説します。
協議離婚や離婚調停で双方が合意すれば「価値観の違い」で離婚できる
協議離婚や離婚調停では、夫婦が合意していれば「価値観の違い」だけでも離婚は可能です。
これらの手続きでは、合意さえあればどんな理由でも離婚できるため、裁判で求められる「法定離婚事由」も必要ありません。
協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚の条件を決め、離婚届を提出することで成立する方法です。「離婚したい」と思ったときは、まずこの協議離婚から進めるのが一般的です。
ただし「相手が話し合いに応じない」「感情的になってしまって話し合いが進まない」といった事情がある場合は、家庭裁判所での離婚調停を利用することになります。
離婚調停は、家庭裁判所で調停委員を介して行う話し合いの場です。中立的な立場の調停委員が双方の意見を聞きながら、離婚の可否や条件(財産分与・親権など)について合意できるようサポートします。
調停の場合も、離婚理由が「価値観の違い」であっても、双方の合意があれば離婚を成立させることができます。
離婚裁判の場合は法定離婚事由として認められる必要がある
話し合いによる離婚が難しい場合、訴訟を起こして裁判所の判断による離婚を目指すことになります。ただし、その前に離婚調停を行わなければ、裁判に進むことはできません(これを「調停前置主義」といいます)。
裁判で離婚を成立させるには、離婚するための客観的な理由が必要です。この理由は「法定離婚事由」と呼ばれ、民法第770条で次の5つが定められています。
| 法定離婚事由 |
内容 |
| 不貞行為 |
配偶者以外の人と性的な関係を持つこと |
| 悪意の遺棄 |
正当な理由なく、同居・扶助などの夫婦の義務を果たさない(例:生活費を渡さない、家出を繰り返すなど) |
| 3年以上の生死不明 |
配偶者の生死が3年以上わからない状態が続いている |
| 強度の精神病 |
配偶者が回復の見込みのない精神病にかかり、夫婦生活を継続するのが困難な場合 |
| その他婚姻を継続し難い重大な事由 |
上記以外の理由で、夫婦関係が回復困難なほど破綻している状態 |
価値観の違いは、これらの法定離婚事由には原則として該当しません。そのため、裁判で離婚が認められるには「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されるほど、夫婦関係の破綻が深刻である必要があります。
以下のようなケースは、この「重大な事由」に該当する可能性があります。
- DVやモラハラがある
- 単身赴任など正当な理由のない別居が3〜5年以上続いている
- 義両親との不和が原因で夫婦関係が悪化している
- 過度な宗教活動により家庭を顧みない
- 浪費やギャンブルを繰り返し、家庭が経済的に破綻している
- 性行為を強要する
- 正当な理由なく一方的に性行為を拒み続ける
- 家事や育児を放棄し、夫婦関係が破綻している
- 犯罪行為を繰り返す、または長期間服役している
一方で、「趣味や食事の好みが合わない」「子どもの教育方針にずれがある」といった価値観の違いでは、法定離婚事由として認められる可能性は低いでしょう。
離婚を考えるきっかけになりやすい価値観の違い
結婚生活を送るなかで、価値観の違いが離婚を考えるきっかけとなることも少なくありません。なかでも、以下のような価値観のズレは、関係に深刻な影響を及ぼしやすいとされています。
- 金銭的な価値観の違い
- 家族観や人生設計に関する価値観
- 性に関する価値観の違い
- 男女観や夫婦関係に関する価値観の違い
- 宗教的な価値観の違い
- 衛生面に対する価値観の違い
ここでは、それぞれの価値観の違いがどのように夫婦関係へ影響を及ぼし、離婚の原因となりうるのか解説します。
金銭的な価値観の違い
お金の使い方や考え方が合わないと、日々の生活で不満や不安が積み重なり、離婚を考えるきっかけになる可能性があります。
たとえば「貯金を重視したい人」と「今を楽しみたい人」では、生活の優先順位が異なるため、ストレスを感じてしまう場合もあるでしょう。
また、結婚前には気づかなかった浪費癖やギャンブル習慣が、生活費の不足や借金問題を引き起こすケースも考えられます。
よくある金銭的な価値観の違いの例は、次のようなものがあります。
- 将来に向けて貯金したいのに、パートナーが散財ばかりする
- 家計管理を一方的に握られて、自由に使えるお金がない
- ギャンブルや趣味に多額のお金を使われ、家計が圧迫されている
金銭的な価値観は生活の土台を支える重要な要素です。すれ違いが長引けば、経済的な不安から安心して暮らせなくなる可能性もあるでしょう。
「この先も一緒に生活していけるのか」と不安を感じるようになった場合は、離婚を検討するきっかけになるかもしれません。
家族観や人生設計に関する価値観の違い
家族観や人生設計に対する価値観の違いが、離婚を考えるきっかけになる場合があります。
たとえば、結婚後に「一方は子どもを望んでいるが、もう一方は望んでいない」「出産の時期について意見が食い違っている」といった価値観のズレが明らかになり、すれ違いが深刻化することもあります。
ほかにも、出産後の働き方や教育方針の違い、互いの家族との関わり方をめぐって衝突する夫婦も少なくありません。
家族や人生設計にまつわる価値観は、相手への信頼や将来設計に直結しやすいため、折り合いをつけるのが難しく、深刻な不和へとつながる場合があります。価値観の違いを乗り越えられない場合、離婚を検討する大きなきっかけになるでしょう。
性に関する価値観の違い
性に対する価値観の違いは、夫婦の間に見えない距離を生み、心のすれ違いを深めるきっかけになりがちです。
たとえば、性行為の頻度やスキンシップのあり方に対する認識の違いから、一方が「求めすぎ」「応じてくれない」と感じる場面は少なくありません。
また、性生活について話し合うことを避けがちな夫婦の場合、違和感や不満が蓄積しやすく、関係が冷え込んでしまうケースもあります。
よくある価値観の違いの例は以下のとおりです。
- 片方がスキンシップを重視する一方で、もう一方は接触を避けたがる
- 性行為の頻度についての希望が極端に異なる
- 妊娠や避妊に対する考え方がまったく合わない
性の価値観は個人的で繊細なテーマのため、話し合うきっかけをつかみにくく、不満が解消されないまま積み重なってしまう傾向にあります。
すれ違いが続くことで、相手への信頼や尊重の気持ちが揺らぎ「この人とは一緒に暮らしていけない」と感じるようになるかもしれません。
男女観や夫婦関係に関する価値観の違い
一方が古い男女観や夫婦関係に対する価値観を持っていることがわかり、離婚を考えるきっかけになるケースもあります。
- 女性が家事や育児をすべき
- 男性が働いて家族を養うべき
- 女性は男性を立てなくてはいけない
- 男性は自分を犠牲にして女性を守らなくてはいけない
このような考え方から、パートナーに特定の役割を強いたり、不当な扱いを受けたりすることで、不満やストレスが積み重なる場合があります。
本来は、話し合いを通じて平等でお互いを尊重し合う関係を築くことが望ましいですが、価値観の隔たりが大きいと、話し合いがうまくいかず、離婚に至るケースもあるでしょう。
宗教に関する価値観の違い
宗教に対する考え方が異なると、夫婦関係にすれ違いが生まれ、離婚を考えるきっかけになる場合があります。
信仰そのものは憲法で保障された自由ですが、その宗教的価値観が日常生活に強く影響し始めると、夫婦間でトラブルが生じやすくなります。
宗教に関する価値観の違いには、次のものがあげられます。
- 一方が宗教活動に熱中しすぎて、家庭生活が二の次になっている
- 宗教に多額のお金を使った結果、生活費が足りなくなっている
- 反対しているのに子どもに入信を勧めてくる
宗教をめぐるトラブルは、感情的な対立を深めやすく、家庭内の雰囲気が悪化する原因にもなります。
相手の信仰を尊重したい気持ちがあっても、自分や子どもにまで強要されるような状況が続けば、精神的に追い詰められてしまうでしょう。
信仰の違いによって会話や価値観の共有が難しくなったと感じたときは、一度冷静に関係を見つめ直してみることが大切です。
衛生面に対する価値観の違い
衛生面に対する価値観の違いは、お互いの心地良い暮らしに直結するため、トラブルや離婚の引き金になりやすいです。
衛生観念は人によって大きく異なり、生理的な感覚も関係するため、譲り合うことが難しい価値観のひとつです。以下のようなポイントで価値観が異なると、日常生活の中でストレスが積み重なっていきます。
- 掃除や洗濯の頻度、やり方
- 歯磨きやお風呂の頻度、タイミング
- トイレ・洗面台・台所・お風呂の使い方
たとえば「もう少しこまめに掃除してほしい」「お風呂に毎日入ってほしい」といった希望が一方にあるにもかかわらず、もう一方が応じない場合、相手に対する不満が蓄積していきます。
一度の出来事であれば我慢できても、日々の生活のなかで小さな不満が積み重なると、精神的な距離がどんどん広がっていくこともあるでしょう。
また、夫婦間だけでなく、義家族と衛生観念があわないことがストレスとなり、トラブルに発展するケースもみられます。とくに同居や頻繁な訪問がある場合は深刻化しやすい傾向にあります。
衛生面の価値観の違いは、一見些細なことに見えても、積み重なることで関係に大きな影響を及ぼします。互いに歩み寄れない場合は、早めに第三者に相談することも検討しましょう。
価値観の違いが離婚事由として認められやすいケース
夫婦間で価値観の違いが積み重なり、精神的な苦痛や関係の悪化につながっている場合、離婚が認められる可能性があります。
民法第770条が定める「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると判断されれば、裁判で離婚が成立する可能性が高まります。
とくに、次のような状況では「婚姻の継続が困難」とみなされやすく、離婚が認められやすいでしょう。
- 複数の価値観の違いによって精神的苦痛が生じている
- 価値観の違いが原因で長期間の別居が続いている
ここでは、それぞれの価値観の違いが、どのような場合に離婚事由として評価されやすいかを解説します。
複数の価値観の違いによって精神的苦痛が生じている
複数の価値観の違いにより、いずれか一方が強い精神的苦痛を受けている場合も、離婚事由として認められる可能性があります。
たとえば、性・金銭感覚・家族観・宗教など、いくつもの価値観の違いが重なり合い、夫婦間の溝が深まっているケースでは、婚姻を継続することが困難と判断される場合もあるでしょう。
これまで紹介したケースと同様に、精神的苦痛の程度や夫婦関係の破綻状況によっては、裁判で離婚が認められる可能性があります。
価値観の違いが原因で長期間の別居が続いている
価値観の違いが原因で長期間の別居が続いている場合、裁判で離婚が認められる可能性があります。
別居が数年にわたって継続し、夫婦関係が回復不能な状態にあると判断されれば、離婚理由が明確でなくても「婚姻を継続するのが困難」とみなされやすくなるでしょう。
不貞行為やDVといった明確な法定離婚事由がなくても、別居が3〜5年間程度続いていれば、離婚が成立する可能性は高くなります。
ただし、別居期間が比較的短くても、以下のような場合には離婚が認められやすくなります。
- 配偶者から法定離婚事由にあたる行為があった
- 婚姻期間が非常に短い
- 夫婦関係が完全に破綻しており、関係修復の見込みがない
法定離婚事由にあたる行為を行なった配偶者を「有責配偶者」と呼びます。有責配偶者へ離婚を請求する場合、別居期間に関わらず離婚が認められやすいです。
また、裁判所は「婚姻期間に対して別居期間がどれほど長いか」を重視します。たとえば婚姻期間が1年程度と短ければ、数ヵ月の別居でも「十分長い」と判断される可能性もあるでしょう。
さらに、明らかに夫婦関係が破綻しており、関係修復の見込みがないと裁判所が認めた場合にも、離婚が成立するケースがあります。
なお、相手の同意を得ずに自分の判断だけで一方的に別居を開始した場合は、有責配偶者とみなされるリスクがあります。有責配偶者からの離婚請求は、裁判で認められるまでに時間がかかりがちです。
これは「婚姻関係を破綻させた当事者が離婚を求めるのは信義に反する」とする裁判所の考え方があるためです。
そのため、別居を検討している場合は、できるだけ相手と事前に話し合い、同意を得てから始めることをおすすめします。
価値観の違いによる離婚で請求できる金銭や権利
価値観の違いを理由に離婚する場合でも、法律に基づいて請求できる金銭や権利があります。代表的なものは以下のとおりです。
| 項目 |
内容 |
| 財産分与 |
婚姻中に夫婦で築いた財産を公平に分け合う制度 |
| 年金分割 |
婚姻中に納めた厚生年金を離婚時に分け合う制度 |
| 養育費 |
離れて暮らす親が、子どもの生活費などを支払う義務 |
なお「親権」は財産分与や養育費のように請求できる権利とは異なり、子どもの利益を最優先に判断される重要な項目です。あわせて確認しておきましょう。
財産分与:婚姻中に夫婦で築いた財産を公平に分けあう制度
財産分与とは、夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚の際に分配することを指します。
財産分与の対象となる財産には、預貯金や不動産、保険、退職金などが含まれます。名義が一方のものでも、婚姻中に共同で築いた財産であれば対象になる可能性があります。
財産分与は、離婚の原因が価値観の違いであっても請求が可能です。
財産分与には、大きく3つの種類があります。
| 財産分与の種類 |
内容 |
| 清算的財産分与 |
夫婦が婚姻中に築いた財産の清算 |
| 扶養的財産分与 |
離婚により困窮する配偶者の扶養 |
| 慰謝料的財産分与 |
相手を傷つけたことに対する慰謝料の意味を含むもの |
扶養的財産分与は、離婚するときに一方が病気で働けなかったり、専業主婦(夫)が長く経済力が乏しかったりする場合、認められるケースがあります。
慰謝料的財産分与は、不法行為によって生じた精神的損害に対する補填を、財産分与の中に含めて対応するものです。この場合、慰謝料という名目では別途請求せず、財産分与の一部として処理されます。
以上のような特別な事情がない限りは、清算的財産分与の考え方に基づいて、財産は公平に2分の1ずつで分けるのが一般的です。
年金分割:婚姻中に納めた厚生年金を離婚時に分け合う制度
年金分割とは、婚姻中に夫婦が納めた厚生年金の年金保険料を離婚時に分け合う制度です。財産分与の一部とみなされ、将来受け取れる年金額に直接影響します。
対象となるのは、結婚から離婚までの婚姻期間中に納めた厚生年金保険料です。ただし、自営業者などが加入する国民年金は対象外となります。
また、年金分割は離婚すれば自動的に行われるわけではなく、離婚した翌日から2年以内に年金事務所で所定の手続きを行わなければなりません。この期限を過ぎると、原則として年金分割の権利を失ってしまうため、忘れずに対応しましょう。
なお別居中であっても、婚姻関係が継続していれば、その期間に納めた厚生年金保険料は原則として分割対象に含まれます。
年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があり、対象や手続き方法が異なります。詳細は年金事務所などで確認しておくとよいでしょう。
養育費の請求もできる
価値観の違いにより離婚した場合でも、養育費の請求は可能です。子どもと離れて暮らす親は、子どもが経済的に自立するまで養育費を支払う義務があります。
養育費の金額は、子どもの人数や年齢、それぞれの親の年収などをもとに、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考に算出されるのが一般的です。
実際の調停や裁判では、算定表を基準としつつ、住宅ローンや教育費など個別の事情に応じて増減されるケースもあります。
なお、離婚理由によって養育費の金額が変わることはありません。
また、生活保護や児童扶養手当といった公的扶助を受けている場合、養育費が収入とみなされ、支給額に影響する可能性があります。
子どもの親権は状況によって変わる
夫婦のどちらが子どもの親権者になるかは、話し合いによって決めることができます。協議や調停で合意できない場合は、家庭裁判所がどちらが親権者の適格性があるかを判断します。
親権者の判断基準は法律で明確に定められていませんが、一般的に以下のような要素が考慮されます。
- 監護への意欲と能力
- 健康状態
- 経済状況
- 居住・教育環境
- 子どもへの愛情
- 監護の援助の存在(親族や友人など)
つまり、子どもの親権がどちらに認められるかは、家庭の状況や子どもの利益に応じて判断されます。
基本的には子どもの福祉(利益)が最優先されるため、離婚の原因がたとえ不貞行為であっても、親権の判断に大きな影響がでるとは限りません。
また、子どもが既に10歳を超えている場合、本人の意思も尊重できるよう、家庭裁判所が子どもに意見を聞く機会を設けるケースもあります。
ちなみに、最高裁判所の司法統計によると、協議離婚や離婚調停も含めたケースでは約9割の親権を母親が獲得しています。これは「母性優先」という考え方ではなく、これまでの監護状況や家庭の実情をふまえたうえで判断されているためです。
父親でも親権を得ることは可能ですので、状況に応じて適切な準備や主張を行うことが重要です。
価値観の違いによる離婚で慰謝料は請求できる?
基本的に、価値観の違いによる離婚は、どちらか一方が悪かったり明確な過失があるケースではないため、慰謝料は発生しません。
慰謝料は、相手の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求できる損害賠償です。価値観の違いを理由に離婚した場合、慰謝料を請求するのは難しいとされています。
しかし、価値観の違いを発端として夫婦関係が悪化し、最終的に不貞行為や悪意の遺棄、DVやモラハラなどが発生した場合には、相手の不法行為が認められ、慰謝料を請求できる可能性があります。
相手に不法行為があれば50万~300万程度の慰謝料が発生する可能性がある
不貞行為や悪意の遺棄は、民法第770条に違反する不法行為に該当するため、慰謝料が発生する可能性があります。
DVやモラハラなども「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性が高く、慰謝料請求が認められる場合があります。
慰謝料の相場は、50万〜300万程度です。婚姻期間や被害の程度、精神的苦痛の内容などさまざまな事情をもとに金額が決まります。
{
「解決金」として支払われるケースもある
慰謝料ではなく「解決金」としてお金が支払われるケースもあります。
一方が離婚を拒んでいるときに、解決金の支払いを条件に交渉を進め、合意に至るケースもあります。
これは、法的な責任が問われるわけではないものの、離婚交渉を円滑に進めるために任意で支払われる金銭です。
たとえば、離婚後の生活が不安だとして離婚を拒む配偶者に対し、当面の生活費や引越し代などを「解決金」として支払うことで、離婚に同意してもらうといったケースがあります。
ただし、解決金は法律に定められていないため、金額や支払い義務についての法的なルールは存在しません。
そのため、支払いの有無や金額は夫婦間での合意によって決める必要があります。
価値観の違いで離婚を考える前にできること
価値観は人それぞれ異なります。離婚という選択をする前に、夫婦関係を見直すためにできることがないか、一度立ち止まって考えてみましょう。
夫婦関係を続けるために試してみたい行動としては、以下のようなものがあります。
- 相手の価値観について理解しようとしてみる
- 夫婦で話し合う時間をつくる
- 別居してお互いに考える時間をもつ
それぞれについて、以下で詳しく解説します。
相手の価値観について理解しようとしてみる
価値観の違いは、どんな夫婦にも起こり得るものです。だからこそ、自分と価値観が異なるからと頭ごなしに否定するのではなく、理解するよう努めることが大切です。
また、相手の価値観や考え方が、どのような経験や環境によって形成されたのかを知ると、受け入れやすくなるケースもあります。
たとえば、相手が倹約家であることに不満を感じていたとしても「幼少期に家庭が貧しかった経験がある」と知ったら理解できるようになるかもしれません。
相手が子どもの教育方針にこだわる場合も「自分自身が学力にコンプレックスを持っていた」と聞けば、理解したうえで話し合おうとする気持ちが芽生えるケースもあるでしょう。
価値観の違いを乗り越えるためには「なぜそう考えるのか?」という背景に目を向け、お互いの考え方を尊重しながら歩み寄ることが大切です。
夫婦で話し合う時間をつくる
お互いの価値観を知ったり、理解したりするには夫婦で話し合う時間が必要です。
遠慮や喧嘩を避けるあまり、自分の本音を押し殺してしまうと、不満が蓄積し、関係の悪化につながる場合もあります。
お互いの価値観や感じ方、考え方を伝え合ったうえで、どこまで譲り合えるか、何を大切にしたいかをすり合わせていくことが大切です。
価値観には、明確な「正解」や「間違い」があるわけではありません。相手にばかり譲歩や我慢を求めてしまう関係では、対等な信頼関係を築くのが難しくなる場合もあります。
別居してお互いに考える時間をもつ
夫婦関係を見つめ直すために、一度距離を置いて別居という選択をとるのもひとつの方法です。
どうしても距離が近いと精神的に甘えてしまったり、反対にいやなところばかりに目がついたりして、冷静な話し合いができない場合もあるでしょう。
別居してお互いに考える時間をもつことで、各々が冷静にどうしたいかを考えられる場合もあります。
結論を先延ばしにしたまま時間だけが過ぎてしまわないよう、別居するならあらかじめ期間を決めて、一定期間が経過した後に話し合う場を設けるのがおすすめです。
価値観の違いによる離婚に関する主な相談先
価値観の違いが原因で離婚を考えるようになったら、1人で抱え込まずに、専門家に相談することをおすすめします。
迷いがあるならカウンセラーに、離婚の意思が固まっているなら弁護士に相談するのがおすすめです。
カウンセラー
離婚したいのかどうかわからず、迷っている段階ならカウンセラーに相談するのも1つの方法です。
価値観の違いは、どの夫婦にも少なからずあるものです。歩み寄る方法がないか、冷静に考えるためにも、自分の気持ちを整理する時間を持ちましょう。
カウンセラーに相談することで、頭の中を整理できるだけでなく、第三者からの客観的なアドバイスを受けられるというメリットもあります。
その結果「自分は本当はどうしたいのか」「これからどう動くべきか」が明確になる場合もあるでしょう。
なお、カウンセラーへの相談は民間の心理相談所のほか、市区町村の相談窓口やNPO団体などでも受けられる場合があります。
費用は1回あたり5,000〜10,000円程度が相場ですが、自治体の無料相談を活用できるケースもあるため、事前に確認してみましょう。
弁護士
離婚の意思が固まっているなら、弁護士に相談するのがおすすめです。
弁護士に相談すれば、離婚手続きの流れや、自分の希望条件(財産分与・養育費・親権など)を法的にどう実現できるか、具体的なアドバイスを受けることが可能です。
また、相手が話し合いに応じない場合や、感情的な対立がある場合でも、弁護士が間に入ることで、冷静かつスムーズに協議を進めやすくなります。
必要に応じて、調停や裁判などの法的手続きも視野にいれて対応してもらえるため、複雑なケースにも安心して望むことができます。
離婚では財産や子どもに関する重要な決定が多く、判断を誤ると後悔につながることも少なくありません。
法律や手続きの知識が必要な場面では、弁護士のサポートによって、トラブルや不安を減らせるでしょう。
まとめ
協議離婚や調停離婚の場合、夫婦の合意があれば「価値観の違い」だけでも離婚は可能です。
一方、裁判で離婚を求める場合は「法定離婚事由」に該当している必要があり、価値観の違いが「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかが判断のポイントになります。
家族観や人生設計、男女観、衛生観念など、価値観の違いを感じる場面は多くありますが、価値観がすべて一致する夫婦は存在しません。
離婚を決断する前に「相手の価値観は本当に受け入れられないのか」「歩み寄るための話し合いは十分にできたか」一度立ち止まって考えてみることも大切です。
自分の気持ちが整理できないときは、カウンセラーに相談し、客観的な意見をもらうのもひとつの方法です。
なお、離婚の意思が固まっている場合は、よりよい条件で離婚を進めるためにも、弁護士への相談を検討しましょう。