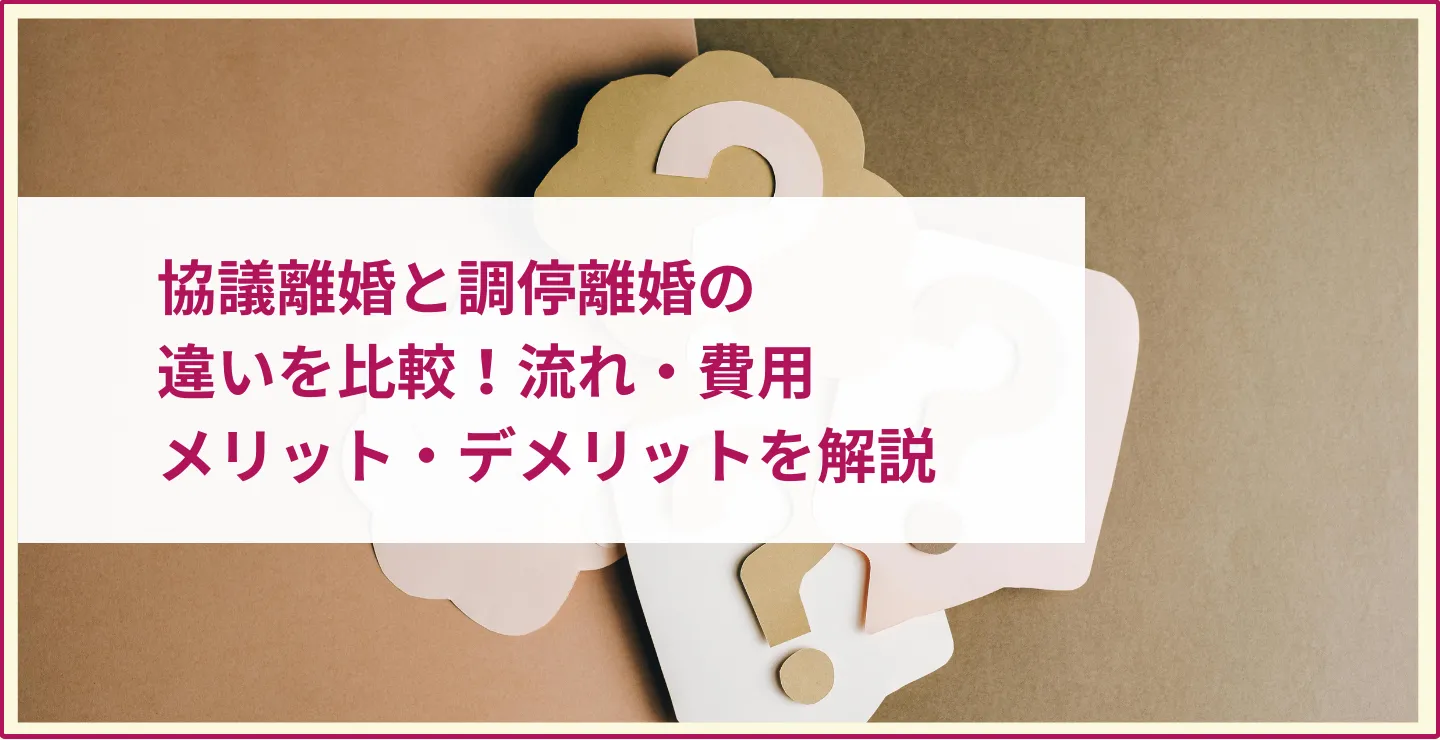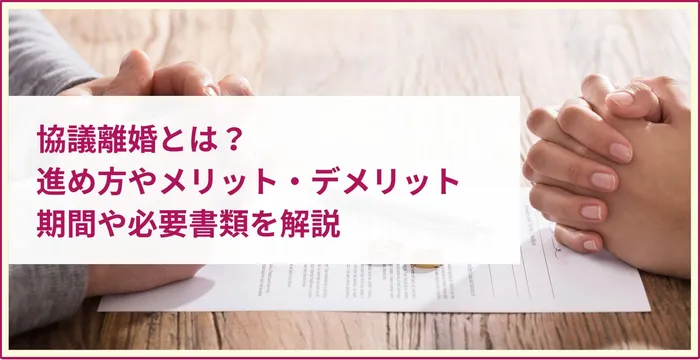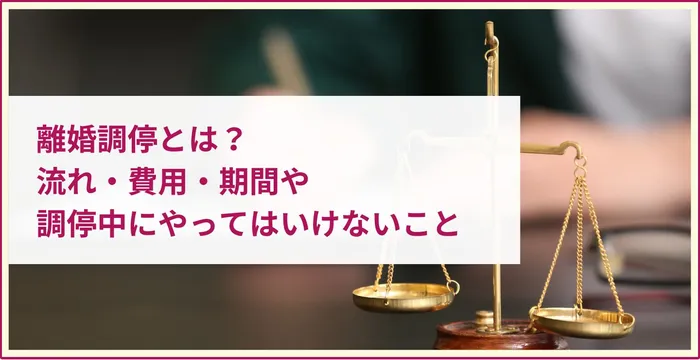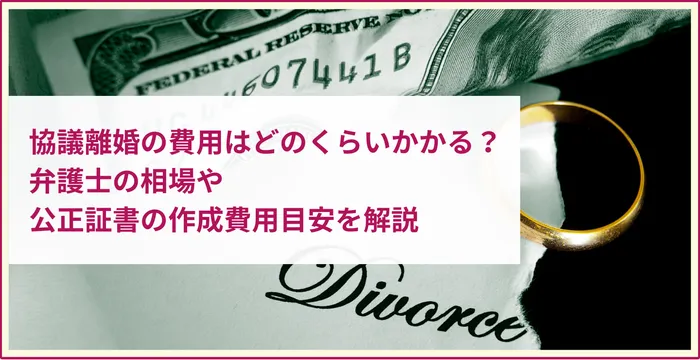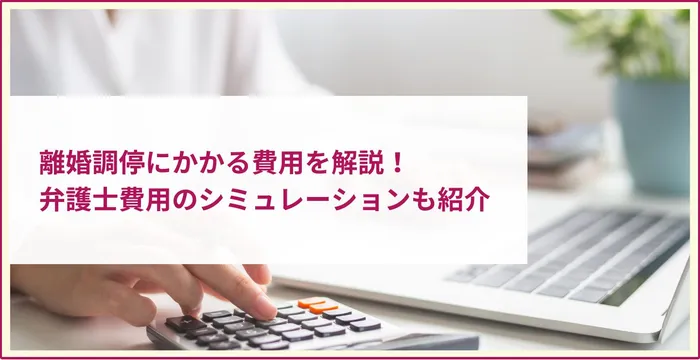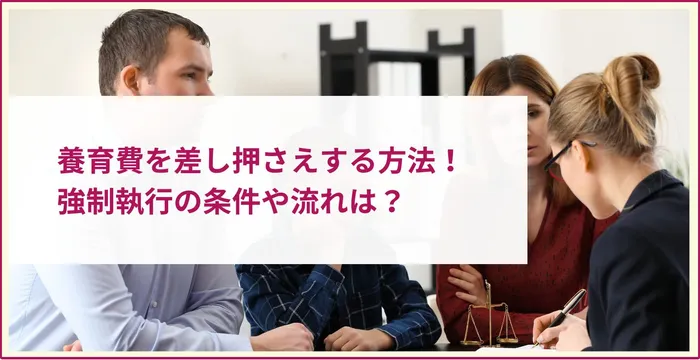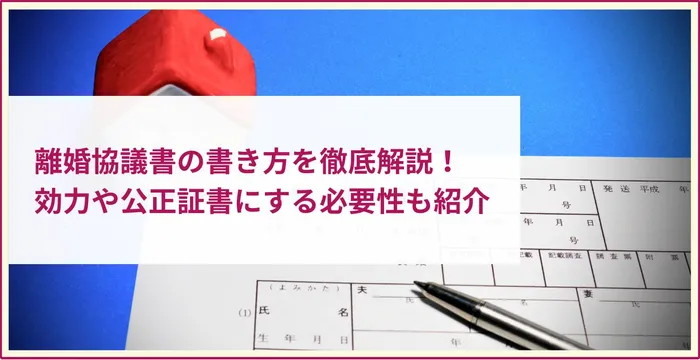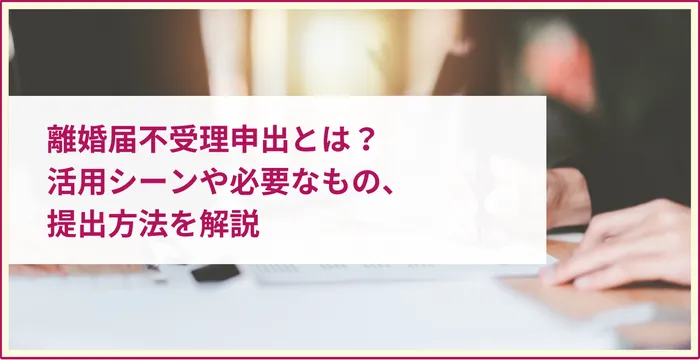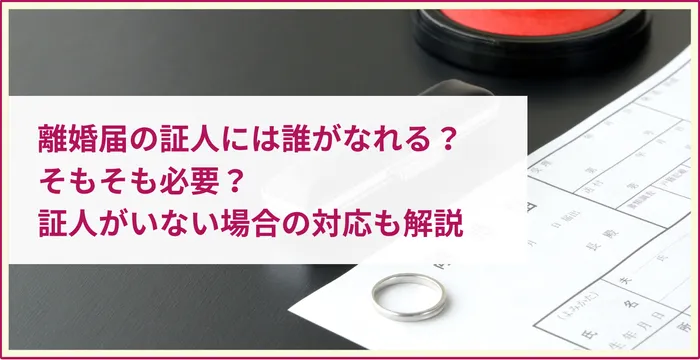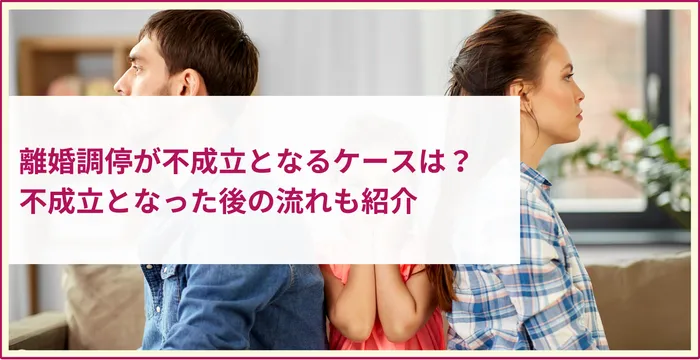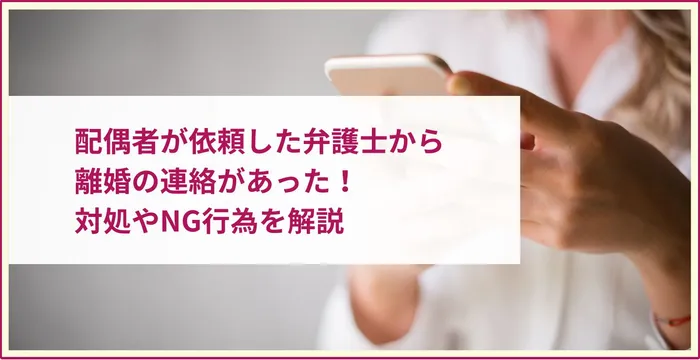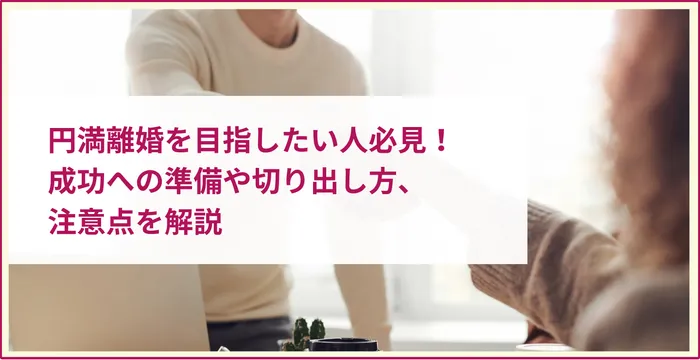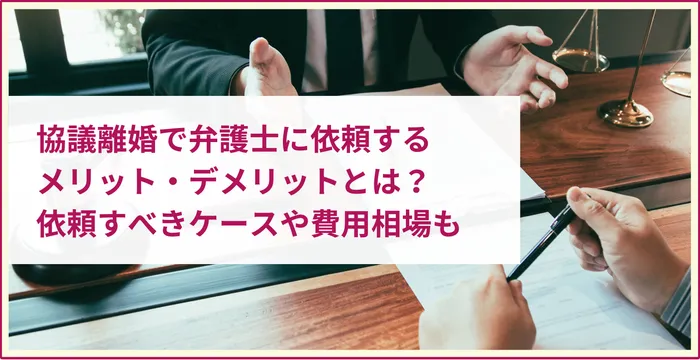協議離婚と調停離婚とは
協議離婚と調停離婚は、どちらも法律で認められた離婚方法ですが、手続きの進め方や関与する人、必要な費用などが異なります。
- 協議離婚:夫婦だけで話し合い、離婚を成立させる
- 調停離婚:家庭裁判所の調停委員が間に入り、話し合いを調整する
それぞれの特徴を詳しくみていきましょう。
協議離婚とは夫婦が話し合って離婚を成立させること
協議離婚は、夫婦だけの話し合いで離婚を成立させる方法です。夫婦双方が離婚の意思や条件に合意できれば、離婚届を提出するだけで成立します。
日本では離婚のうち約9割が協議離婚によって成立しており、もっとも一般的な離婚方法といえます。(※参照:厚生労働省「令和4年 離婚に関する統計の概況」)
協議離婚について詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。
調停離婚とは調停委員を介して離婚を成立させること
調停離婚は、夫婦間で話し合いがまとまらない場合に、いずれかが家庭裁判所へ調停を申し立て、調停委員を交えて合意を目指す方法です。
調停では、調停委員が双方の意見を個別に聞きながら、条件のすり合わせを行います。通常は夫婦が直接顔をあわせることはありません。
調停が成立すれば法的効力のある書面が作成される点が特徴です。
なお、調停委員の提案はあくまで助言のため、当事者が合意しなければ調停は不成立になります。その場合は審判や離婚裁判に進んでいくことになります。
調停離婚について詳しく知りたい人は、以下の記事を参考にしてください。
協議離婚と調停離婚における6つの違い
協議離婚と調停離婚は、話し合いの進め方だけでなく、関わる人や費用、必要な手続きなどにも違いがあります。
協議離婚と調停離婚における細かい違いは以下のとおりです。
| 比較項目 |
協議離婚 |
調停離婚 |
| 話し合いへの第三者の同席(立会人) |
不要(当事者同士で協議)
ただし、離婚届の証人欄に成人2名の署名が必要(民法第739条) |
必要(家庭裁判所の調停委員が関与) |
| 離婚成立までの期間 |
合意次第、即日成立も可能 |
申立てから数ヵ月〜1年程度かかるのが一般的 |
| 費用 |
基本的に不要(※弁護士費用・公正証書作成費を除く) |
3,000円程度(※弁護士費用は除く) |
| 戸籍の記載内容 |
離婚届の届出日を記載 |
調停成立日を記載 |
| 作成する書類 |
離婚協議書(任意) |
調停調書(裁判所が作成) |
| 強制執行の可否 |
原則不可(※強制執行認諾文言付きの公正証書にすれば可能) |
可能(調停調書に執行力がある) |
それぞれ詳しく解説します。
【立会人】協議離婚は不要・調停離婚は必要
協議離婚では、夫婦だけで話し合いを進めるため、立ち会う第三者(立会人)は必要ありません。
ただし、離婚届を提出する際には、成人2名の証人による署名が必要です(民法第739条)。
証人は、成人であれば親族・友人など、当事者以外であれば誰でもなることができます。証人の署名がない離婚届は受理されないため、提出前に記入漏れがないか確認しましょう。
一方、調停離婚では、家庭裁判所の調停委員が夫婦の間に入り、中立的な立場で話し合いをサポートします。調停委員は、当事者双方の意見を丁寧に聞き取り、合意に向けて調整を行います。
調停離婚では家庭裁判所が当事者の離婚意思を確認しているため、証人の署名は不要です。調停を申し立てた人が調停調書と自署した離婚届を役所に提出すれば離婚が成立します。(参考:
民法第739条2項・第763条・第764条・第765条)
なお、離婚協議を円滑に進めたい場合や、配偶者に不倫などの法定離婚事由があり、慰謝料や親権、養育費の条件を有利に進めたい場合は、弁護士に同席や代理交渉を依頼することも可能です。
法定離婚事由とは、法律上認められる離婚の理由です。不倫やモラハラ、生活費を渡さないなどが該当し、
民法第770条で定められています。
【離婚が成立するまでの期間】協議離婚は話がまとまるまで・調停離婚は数ヵ月~1年以上
協議離婚と調停離婚では、離婚が成立するまでの期間に差があります。
協議離婚は、夫婦間で合意さえできればすぐに離婚届を提出できるため、早ければ数日〜数週間で成立することもあります。
ただし、財産分与や親権などの条件で意見が対立すると、話し合いが長引き、離婚成立までに数ヵ月〜1年以上かかるケースもあります。
一方、調停離婚は、家庭裁判所への申し立てから離婚成立までに半年~1年程度かかるのが一般的です。また、調停前に行っていた協議にも時間がかかっていたケースも多く、全体としては2年近くかかる場合もあります。
【費用】協議離婚は基本的に不要・調停離婚は3,000円程度
協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚が成立する場合は、基本的に費用はかかりません。一方、調停離婚は家庭裁判所に申し立てを行う必要があるため、収入印紙代や切手代などの実費が必要です。
協議離婚と調停離婚の費用の違いは以下の通りです。
| ケース |
協議離婚 |
調停離婚 |
| 弁護士に依頼しない場合 |
0円 |
3,000円程度 |
| 弁護士に依頼する場合 |
20万円~60万円程度 |
50~100万円程度 |
| 公正証書を作成する場合 |
慰謝料や養育費などの金額による(5,000円~2万3,000円が相場) |
公正証書は作られない |
弁護士費用に幅がある理由は、親権や養育費、慰謝料や財産分与などといった争点の数に応じて「着手金」や「報酬金」が基本的に加算されるためです。
詳しくは以下の記事をご覧ください。
【戸籍の記載内容】協議離婚は離婚日・調停離婚は離婚の調停日
協議離婚の場合は、離婚した日と離婚届が受理された事実が戸籍に記載されます。
一方、調停離婚が成立した場合は、離婚日に加えて「離婚の調停成立日」という記載が入るため、戸籍をみれば調停をして離婚に至ったことが第三者にもわかります。
場合によっては、戸籍を確認した相手に「離婚時に揉めたのでは」と思われる可能性があるでしょう。
【作成する書類】協議離婚は離婚協議書・調停離婚は調停調書
協議離婚で離婚が成立する場合は、話し合いの結果を文書にまとめた「離婚協議書」を作成するのが一般的です。離婚協議書には、財産分与・慰謝料・養育費・親権といった離婚条件が明記され、後々のトラブルを防ぐ役割があります。
また、離婚協議書には法的拘束力はありませんが、強制執行認諾文言付きの公正証書にしておけば、支払いが滞った場合に給料や財産の差押えが可能になります。
※詳しくは【強制執行】協議離婚は原則不可・調停離婚は可能をご覧ください。
一方、調停離婚では、夫婦間で合意に至ると家庭裁判所の書記官が「調停調書」を作成します。 調停調書とは、調停で取り決めた内容を記録した文書で、裁判の確定判決と同じ法的効力をもちます。
そのため、調停調書に記載された内容に違反があった場合は、給与や預貯金などの財産を差し押さえることができます。
なお、調停調書は作成後に変更や不服申し立てができないため、内容に漏れや誤りがないか十分な確認が必要です。
調停が成立したあとは、調停調書の交付から10日以内に離婚届を市区町村役場に提出 しなければなりません。
【強制執行】協議離婚は原則不可・調停離婚は可能
離婚では、養育費や慰謝料、財産分与などの支払いについて話し合って取り決めるのが一般的です。
しかし、相手が約束どおりに支払わない場合には、財産や給料を差し押さえる「強制執行」という法的手続きで回収を図ることができます。
協議離婚では、基本的に強制執行はできません。 離婚協議書には法的拘束力がないため、たとえ相手が約束を守らなかったとしても、強制的に取り立てることはできないのです。
ただし、以下のいずれかの方法をとれば、協議離婚でも強制執行が可能になります。
- 離婚協議書をもとに訴訟を起こし、勝訴判決を得る
- 離婚協議書を「強制執行認諾文言付きの公正証書」にする
とくに後者は、裁判をしなくても強制執行を行えるため、金銭の回収にかかる手間や時間を軽減できます。
公正証書を作成する際には、公証人への手数料のほか、強制執行の申し立てに必要な費用(手数料:約4,000円、郵便代:約5,000円)も発生します。
一方、調停離婚では調停調書そのものが「確定判決」と同等の法的効力をもつため、別途裁判を起こしたり、公正証書を作成したりする必要はありません。
調停調書は「債務名義」として扱われ、その効力は家事事件手続法第268条1項にも明記されています。
協議離婚のメリット・デメリット
協議離婚には、スムーズに離婚できる反面、話し合いの内容を明確に書面に残さないと、後日トラブルになる可能性があります。
ここでは、協議離婚のメリットとデメリットについて解説します。
【メリット】早期解決しやすく費用がかからない
協議離婚は夫婦の話し合いだけで成立するため、早ければ数日〜数週間で離婚ができます。
離婚の理由は問われず、法定離婚事由がなくても合意さえあれば離婚が可能です。離婚届は役所で無料でもらえ、提出にも費用はかかりません。
また、家庭裁判所を通す必要がないため、調停や訴訟に比べて時間や手間も抑えられます。
弁護士に依頼しなければ費用も基本的にはかからないため、経済的な負担が少ないのもメリットといえるでしょう。
ただし、第三者の介入がないからこそ、当事者同士で冷静かつ公平に話し合えることが前提となります。
【デメリット】話し合いがまとまらず、後々トラブルになるリスクもある
協議離婚の最大のデメリットは、当事者間での合意が難しい場合、話し合いが平行線になってしまうことです。
たとえば、相手が離婚自体に応じなかったり、親権や金銭面の条件で対立したりしている場合は、話し合いがまとまらず、結局調停に進まなければならないケースもあります。
また、合意内容を文書に残さないまま離婚してしまうと、後日「そんな約束していない」とトラブルに発展する可能性もあります。
そのため、養育費・慰謝料・財産分与などについては、支払い金額や支払い方法、支払いが遅れた場合の対応などを明確に取り決め、強制執行認諾付きの公正証書にしておくとよいでしょう。
詳しくは【作成する書類】協議離婚は離婚協議書・調停離婚は調停調書をご覧ください。
ちなみに、協議離婚では離婚の合意さえできていればよいため、メールや電話、手紙、LINEなどのチャットツールで合意した場合でも離婚が成立します。
なお、相手からDVやモラハラなどを受ける危険がある場合は、弁護士に代理交渉を依頼すれば、安全に離婚を進めることができます。
調停離婚のメリット・デメリット
調停離婚には、冷静な話し合いを進めやすいというメリットがある一方で、時間や手間がかかるというデメリットもあります。
ここでは、調停離婚のメリットとデメリットを解説します。
【メリット】スムーズな話し合いができ、離婚後のトラブルも少ない
調停離婚では家庭裁判所の調停委員が中立的な立場で双方の意見を聞き、円滑に話し合いが進むよう調整してくれるため、感情的な衝突を避けやすいのがメリットです。
基本的に夫婦が直接顔をあわせることはなく、個別に意見を聞いてもらえるため、落ち着いて話ができます。
また、離婚調停では慰謝料や財産分与といった金銭面、親権の所在や面会交流の条件など、離婚条件を具体的に取り決めていきます。
合意内容は調停調書にまとめられ、確定判決と同じ効力をもつため、離婚後に約束が破られた場合でも、相手の給与や預貯金を差し押さえることが可能です。
【デメリット】平日の昼間に時間を作る必要があり、長期化しやすい
調停離婚のデメリットは、平日の日中に家庭裁判所へ出向く時間をつくらなければならない、調停が長期化し離婚成立までに時間がかかる点です。
離婚調停は家庭裁判所が開廷している時間に行われるため、平日の日中に時間をつくる必要があります。
また、調停が1回で成立するケースはほとんどないため、調停期日ごと(平均3~5回程度)に時間を調整しなければなりません。
提案内容に納得できない場合は、離婚に合意する必要はないため、当事者の双方、またはいずれかが納得しない場合、調停は長期化する可能性が高くなります。
合意に至らない場合、調停は不成立となり、審判や裁判へと移行することになります。この場合、さらに裁判にかかる費用の負担と時間が必要になります。
協議離婚と調停離婚の向いているケース
協議離婚と調停離婚は、進め方や必要な手続きが異なるため、それぞれ向いているケースも異なります。
協議離婚は、夫婦の間で冷静に話し合える関係が残っている場合に向いています。
一方、調停離婚は、話し合いがうまくいかない・一方が離婚に応じないといった状況の場合に適しているでしょう。
ここでは、それぞれの離婚方法がどのような状況に適しているのか解説します。
【協議離婚】お互いに歩み寄りがみられる場合
夫婦がお互いに歩み寄って離婚についての話し合いができる場合は、協議離婚が向いています。
話し合いがスムーズに進めば、時間や費用をかけずに、早期に離婚を成立させることが可能
です。
できるだけ簡単な手続きで済ませたい場合や、離婚成立に時間をかけたくない場合は、協議離婚を選ぶとよいでしょう。
ただし協議離婚を選択する場合は、条件を口頭だけで確認して済ませてしまうと、後から言った・言わないのトラブルになる恐れがあります。
トラブルを避けるためにも、離婚協議書を作成し、公正証書化しておくことをおすすめします。
【調停離婚】条件がまったく合わない場合
離婚条件について意見が食い違っていたり、一方が話し合いに応じなかったりする場合は、調停離婚が適しています。
このような状況において、当事者同士の話し合いのみで離婚問題を解決するのは、難しいでしょう。
離婚調停を申し立て、第三者である調停委員に間に入ってもらった方が離婚問題を解決しやすくなるはずです。
また、以下のようなケースも調停離婚が望ましいでしょう。
- 相手と直接会うと感情的になってしまう
- モラハラ・DVなどのリスクがある
- すでに話し合いが平行線になっている
ただし、調停は基本的に平日の日中に行われるため、仕事や子育てなどの合間に時間をつくる必要があります。
離婚成立までには、少なくとも数ヵ月〜1年程度かかることを念頭にいれておきましょう。
協議離婚と調停離婚の流れ
協議離婚と調停離婚がどのようなものか理解していても、それぞれがどのような流れで成立するのか知らない人もいるでしょう。
協議離婚の場合、当事者のいずれかが離婚の意思を伝え、離婚条件を話し合って合意した後に、離婚届が受理されれば離婚が成立します。
一方、調停離婚では当事者のいずれかが離婚調停を申し立て、調停が成立すれば離婚が成立、不成立の場合は離婚も不成立となります。
ここでは、協議離婚と調停離婚の大まかな流れについて解説します。
協議離婚の流れ
協議離婚の流れは以下の通りです。
- 配偶者に離婚の意思を伝える
- 離婚の是非や離婚条件を話し合う
- 離婚や条件に合意できたら離婚協議書を作成する
- 離婚届を作成して役所に提出し、受理されたら離婚が成立する
それぞれ説明します。
配偶者に離婚の意思を伝える
夫婦のいずれかが離婚を決意した場合、配偶者に離婚の意思を伝えます。口頭やメール、内容証明郵便などを用いて伝えるケースが多いでしょう。
離婚の意思を一方的に突きつけるとトラブルになる場合もあるため、できるだけ冷静に話し合いの姿勢をみせることが大切です。
離婚の是非や離婚条件を話し合う
次に、配偶者と離婚の可否や離婚条件について話し合います。とくに、離婚条件の取り決めは重要です。離婚条件に関する取り決めについて話し合うべき内容は次のとおりです。
- 財産分与
- 慰謝料(配偶者の不法行為があった場合や精神的苦痛を受けた場合)
- 年金分割
- 親権
- 養育費
- 面会交流の頻度や条件
財産分与や慰謝料、年金分割、養育費といった金銭的な取り決めや、子どもとの面会交流の頻度・条件は、その後の関わりや生活にも影響します。そのため支払い金額のほか、支払い方法や支払いを怠った場合の対応など、詳細に決める必要があります。
また、夫婦間に子どもがいる場合は、親権をどちらがもち、養育費をどちらが払うのかも明確に決めなければなりません。
未成年の子どもがいる場合、離婚届に親権者を記載する必要があるため、親権者を決めておかないと離婚が成立しないからです。
離婚や条件に合意できたら離婚協議書を作成する
離婚の可否や離婚条件に双方が合意した場合は、合意内容について記した離婚協議書を作成します。離婚後にトラブルに発展しないよう、離婚協議書は必ず作成しましょう。
なお、相手からの金銭面での支払いに不安がある場合は、離婚協議書を強制執行認諾文言付きの公正証書にすることをおすすめします。
「強制執行認諾文言」を付けておけば、支払いが滞った際に裁判を経ずに差し押さえが可能です。
ただし、夫婦間での話し合いでは離婚条件についても揉めるケースが多く、詳細を決めるまでに時間がかかる傾向があります。
そのため、条件交渉に嫌気がさして、条件が決まっていない状況で相手が離婚届を提出してしまう可能性があります。
そのような場合に備えて、事前に離婚届不受理申出をしておくとよいでしょう。
離婚届を作成して役所に提出→受理されたら離婚が成立する
離婚協議書の作成が完了し、内容に不備がないことをお互いが確認すれば、離婚協議は終了です。後は離婚届を提出して受理されれば、離婚は成立します。
離婚届は郵送で提出することも可能ですが、不備があれば差し戻されるため、書き漏れがないか十分に確認しましょう。
また、協議離婚の場合、離婚届には成人2名の証人による署名と押印が必要です。 証人は親族でも友人などの第三者でもかまいません。
離婚届の提出先は、夫婦の本籍地の役所もしくは夫婦のいずれかの住民登録地の役所となります。本籍地の役所に離婚届を提出する場合は、本人確認書類の提示が求められます。
一方、本籍地以外の役所に提出する場合は、離婚届に加えて夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)の提出が必要です。
なお、離婚届が受理された場合、届出日が法律上の離婚日となります。
調停離婚の流れ
調停離婚の流れは次のとおりです。
- 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
- 調停期日に家庭裁判所へ出頭する
- 調停が成立すれば離婚届を提出して離婚が成立する
それぞれ詳しく説明します。
家庭裁判所に離婚調停を申し立てる
離婚調停は、当事者のうち離婚を求めるほうが、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。申立て先は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
離婚調停の申立てには次の書類が必要です。
- 離婚調停の申立書
- 夫婦それぞれの戸籍謄本(離婚調停の申し立てに年金分割を含む場合)
- 年金分割のための情報通知書(該当する場合)
なお、調停の申立書は、裁判所の公式サイトからダウンロード可能です。また、申立てには収入印紙1,200円分と、裁判所ごとに指定された郵便切手代(1,000円前後)が必要になります。
申立書には以下のような内容を記載します(記載例)
- 【申立ての趣旨】:〇〇と離婚したい
- 【申立ての理由】:性格の不一致により夫婦関係が破綻している
- 【話し合いたい内容】:財産分与・養育費・親権など
実際の様式や書き方は、各家庭裁判所の書式例に従って作成してください。
※参照:調停申立書の記入例(東京家庭裁判所)
調停期日に調停に出頭する
申し立てが受理されると、第1回調停期日が記載された「呼出状」が裁判所から当事者双方に送られます。指定された日に家庭裁判所へ出頭し、調停に出席します。
調停は基本的に1回で終わることは少なく、数回にわたって実施されます。1回の調停は30分〜1時間程度で行われ、期日は1〜1.5ヵ月おきに設定されるのが一般的です。
争点の多さにもよりますが、全体では3〜6回程度、期間にして数ヵ月〜1年程度かかると考えておくとよいでしょう。
調停では、夫婦それぞれが別々の部屋で調停委員と面談し、主張を整理していきます。合意に至れば調停は成立となり、調停調書が作成されます。
調停が成立から10日以内に離婚届を提出すると離婚が成立する
当事者双方が離婚に合意し、条件が整えば調停は成立です。成立時には、裁判所が調停調書を作成・交付します。
調停調書には、親権や養育費、財産分与など、当事者間で合意した離婚条件がすべて記載されます。
この調停調書は、確定判決と同じ効力を持つため、支払いが滞った場合は強制執行が可能です。
調停成立から10日以内に、調停調書と離婚届を役所に提出すれば、離婚が成立します。
調停が不成立の場合の流れ
離婚の合意に至らない場合は、不成立として終了し、家庭裁判所から「不成立調書」が交付されます。その後、離婚を希望する側が離婚裁判を提起すれば、裁判手続きへと進みます。
調停離婚は、離婚を裁判で争う前に必ず通らなければならない「調停前置」の手続きです。調停での話し合いがまとまらなければ、離婚訴訟に移行することになります。
離婚問題は弁護士に相談するのがおすすめ
夫婦間で発生した離婚問題を迅速に解決したい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、相手のペースに巻き込まれることなく、自分の主張を法的根拠に基づいて交渉が可能です。
協議離婚では、相手が話し合いに応じてくれないケースもあります。そのような場合でも、弁護士が間に入ることで、離婚に対して真剣に向き合っているという意思を伝えられます。
また離婚条件についても、弁護士が代理人として交渉を行なえば、こちらの希望を法的観点から明確に伝えやすくなるでしょう。
配偶者からモラハラやDVを受けていて、当事者同士で交渉することに不安を抱えている場合も、弁護士に依頼すれば交渉の代行が可能です。
調停離婚においても、弁護士に調停への同席を依頼すれば、調停委員に対して論理的にこちらの考えを主張してもらえるほか、相手側の主張が適切なのか判断してもらえます。
その他、必要書類の準備も一任できるため、離婚調停に割くべき時間や手間を省けるでしょう。
弁護士費用が発生するというデメリットはあるものの「有利な条件での離婚」や「離婚問題の早期解決」など、メリットが得られる可能性もあります。
離婚の話し合いが進まない、条件で揉めている、相手に不安を感じているといった状況があれば、早めに弁護士への相談を検討してみてください。
まとめ
協議離婚と調停離婚は、手続きの進め方や関わる人、かかる費用、離婚成立までの期間などに大きな違いがあります。
夫婦だけで冷静に話し合える場合は、費用もかからず早期解決が可能な協議離婚が向いています。
一方、話し合いが難航している、相手と直接やりとりしたくないといった場合は、家庭裁判所を通じて進める調停離婚が適しているでしょう。
手続きに不安がある方や、相手との交渉に自信が持てない方は、いずれの場合も弁護士への相談を検討してみてください。